シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト
────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか
────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか
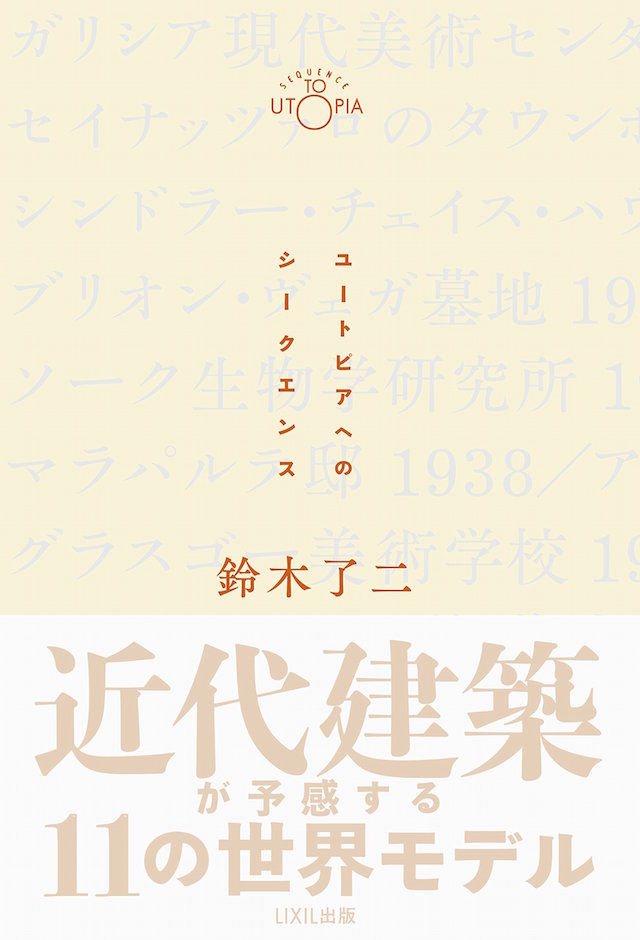
- 鈴木了二『ユートピアへのシークエンス
──近代建築が予感する11の世界モデル』
(LIXIL出版、2017)
建築空間を体験することは、テクストを読むことに似ている。それは個々の建築物の内部での経験に限られず、建築物にたどり着くまでの道程とランドスケープも含む。鈴木了二『ユートピアへのシークエンス──近代建築が予感する11の世界モデル』(LIXIL出版、2017)は、書籍そのものが物質とのシークエンシャルな邂逅の経験として、建築の内部を歩いていくような記述と構成となっている。11の建築を巡り、最後にユートピア的な場所に至るというナラティブ、書物の構造、そしてそれを読む経験そのものもまた、建築的なシークエンスをかたちづくる。
著者の鈴木了二は、11の20世紀建築を「世界モデル」として、講義形式で語る。最も古いのは1909年竣工のチャールズ・レニー・マッキントッシュによる《グラスゴー美術学校》であり、いちばん新しいのが1993年竣工のアルヴァロ・シザによる《ガリシア現代美術センター》である。テクストのあいだに建築ドローイングや図面が挿入され、章末に至ると、建築物の内外を写したカラー写真が現われている。いずれも光の成す陰影と、それによって際立つ建築物のマチエールが美しい。
書題には「ユートピア」とあるが、それはディストピアへの反転可能性を潜在させた、管理と規律の徹底した隔絶空間の謂いではない。それはむしろ、一定の道程を経た先に到達する、ある種の至高の場として語られる。あるいは、ハンス・シャロウンの《ベルリン・フィルハーモニー・コンサートホール》を取り上げた章の表現を借りるならば「鳥の巣」のような、私たちを柔らかく包みこむ空間のイメージである。著者は、このようなシークエンスにおいてこそ「建築の快楽」(本書7ページ、序文「近代建築・取扱い説明書」より)がもたらされるというのだ。
この書にはほかにも、「世界モデル」や「(ルイス・カーンがいう意味での)廃墟」、「瓦礫」、「物質」などの鍵語がちりばめられているが、その詳細については2017年4月に行なわれた鈴木氏と筆者の対談「歴史のイマジナリーラインズ」(『建築雑誌』2017年7月号「特集=建築は記念する」に収録)をご参照いただきたい。
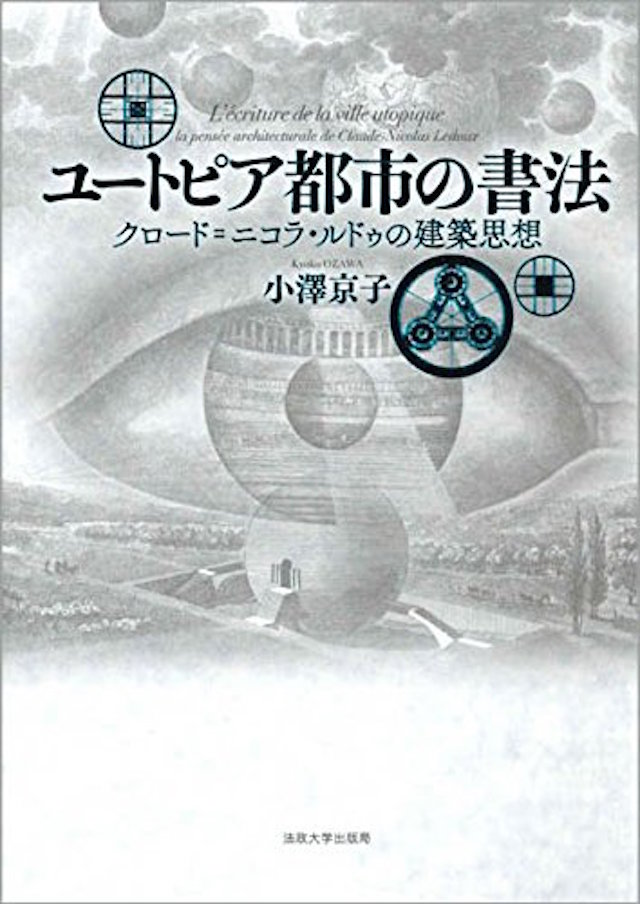
- 小澤京子『ユートピア都市の書法
──クロード=ニコラ・ルドゥの建築思想』
(法政大学出版局、2017)
テクストがもつ空間的な特性は、私自身が探究してきたテーマでもある。2017年7月に上梓した拙著『ユートピア都市の書法──クロード=ニコラ・ルドゥの建築思想』(法政大学出版局、2017)の第2部と第3部は、建築家ルドゥの畢生の書『芸術、習慣、法制との関係性の下で考察された建築』(1804、以下『建築論』と略記)と、その同時代人マルキ・ド・サドのテクストがともに有する、語りそのものが空間移動のシークエンスを成すという性質の分析に充てた。
ルドゥの『建築論』は、ひとりの旅人がショーの理想都市を旅しながら、さまざまな建築物に出会う構成となっている(建築を巡る旅としてのテクスト、という点では、フランチェスコ・コロンナの『ポリフィルスの狂恋夢』と共通するだろう)。サドの『ソドム百二十日』や『ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え』のようなリベルタン小説の場合は、俗世を隔てる山々や水辺を越えて、放蕩と倒錯的快楽の場──まさに18世紀ユートピア的な、隔絶され管理と規律の徹底された場所──に到着し、そこからさらに地下の墓へ、つまり死の場所へ至るという道行きである。
18世紀人ルドゥとサドにおける「建築空間のシークエンシャルな経験」は、フリーメイソン的な宇宙観の反映であると同時に、建築空間の配置と構造を通して人間の身体を管理していくという傾向の表われでもあり、さらには「旅」というもうひとつの18世紀的なモチーフの変奏でもある。同時に彼らは、テクストを、あるいは物質としての書物を、建築として読むことも可能であることを自覚させてくれるのだ(テクストやナラティブと建築空間のダイナミックな相互関係、という点からは、桑木野幸司『叡智の建築家──記憶のロクスとしての16−17世紀の庭園、劇場、都市』[中央公論美術出版、2014]を礎石となる一冊として挙げておきたい)。

- 柴崎友香『千の扉』(中央公論新社、2017)
現代日本で「建築的」なテクストを書く作家として注目しているのが、柴崎友香である。2017年に単行本として刊行された『千の扉』(中央公論新社)もまた、建築と場の記憶、そしてナラティブがつくりだす仮構的な空間性が、読む者に愉楽をもたらしてくれる1冊であった。舞台となるのは戦後に開発された、いくつかの団地である。義祖父からの頼みを受けた主人公が、おぼろげな手がかりに基づき、掴みどころのない人探しを続ける。ほぼ70年分の、複数の個人の生きた記憶が特定の場に積み重なり、それが物語の展開につれて、網の目状に繋がったり、あるいは場を共有するだけで繋がらないままであったりするさまが、視点人物を変えつつ描きだされてゆく。
同じ著者による『パノララ』(講談社、2015)もまた、空間的シークエンスを独特なやり方で体現した「建築的文学」であった。空間の連続性や空間経験の継起(当然ここには、「時間」という要素も絡んでくる)とその断絶、飛躍、反復という要素が、特徴的なブリコラージュ住宅や、パノラマモード写真(「別の角度から見た世界をつなぎ合わせた」★1、「少しずつずれて、欠けたり、重なったりしている風景」★2)、映画編集という主要モチーフと絡み合いながら展開する。本作では「映画」という、ともすればありふれたモチーフ以上に、アマチュア向けデジタルカメラやスマートフォンのカメラに付属している「パノラマモード」──個人的な経験では、撮影者の身体動作にも依存するため、むしろ「機械的な正確さ」では撮影することができず、連続するはずの空間が妙に間延びしたり圧縮されたりと、たいていの場合は「失敗」に終わる──と空間経験とのアナロジーが、新鮮なものに感じられた。
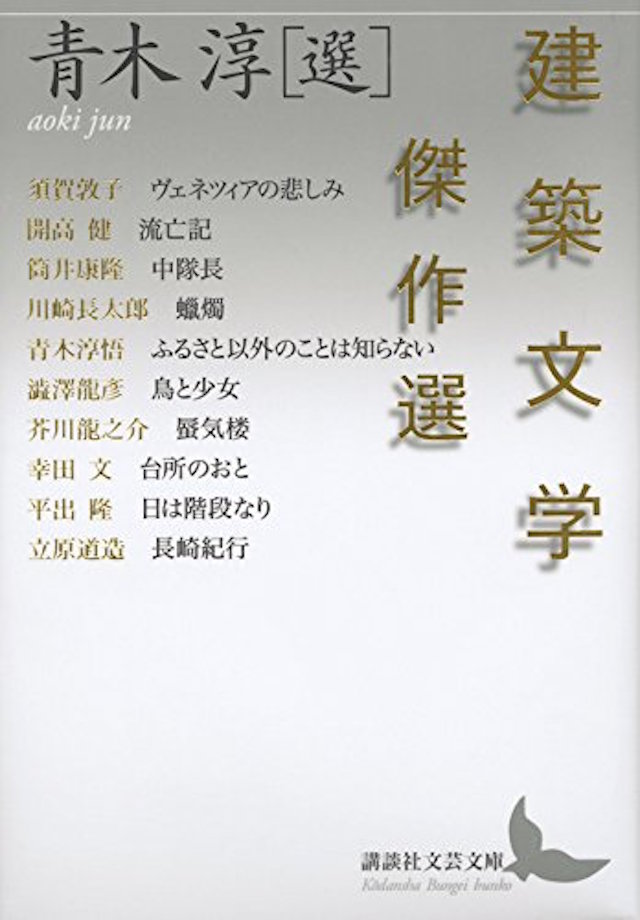
- 『建築文学傑作選』
(青木淳選・解説、講談社文芸文庫、2017)
建築的文学、という言葉を用いたからには、現代日本の建築家による短篇小説アンソロジー『建築文学傑作選』(青木淳選・解説、講談社文芸文庫、2017)にも言及しておきたい。なんらかの点で建築空間的(もしくは都市空間的)な構造をもつテクストというテマティスムに基づいて、さまざまな時代と地域の文学作品を取り集めてみたら面白いだろう、というのが私の数年来のささやかな野望であり、先述の『ポリフィルスの狂恋夢』やサドのいくつかの小説群のほか、ダンテ『神曲』(実際、ジュゼッペ・テラーニの「ダンテウム」構想はこのテクストを建築に「翻訳」する試みだった)、ブルトン『ナジャ』、カフカ『城』、ビュトール『時間割』や『心変わり』、ロブ=グリエ『迷路のなかで』、ボルヘス『バベルの図書館』、日本であれば内田百閒の『東京日記』などがまずは典型的なものとして思い浮かんでいたが、この『建築文学傑作選』の「搦め手」の選択眼には唸らされた。単に「建築描写が特徴的な文学」、「建築が主要なテーマとなる文学」というわかりやすい次元ではなく、テクストにおけるさまざまなレベルでの「建築的構造」が、建築家ならではの炯眼によって看取されているといえようか。
2017年は、建築をめぐるテクストやミュージアム、アーカイヴズでの展示という点でも、いくつかの目立つ出来事のあった年だった。建築史の優れた研究として、例えば加藤耕一『時がつくる建築──リノベーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017、第39回サントリー学芸賞受賞)が刊行され、また入場者が長蛇の列をなした「安藤忠雄展─挑戦─」(国立新美術館)や、国際巡回を経て東京国立近代美術館で開催された「日本の家──1945年以降の建築と暮らし」展、また戦後日本の建築家たちによるショー・ドローイングに対象を絞った(この点で1960年代以降しばしば開かれてきた「紙上建築」がテーマの展覧会とはまた別の、新しい視点を提示しているだろう)「紙の上の建築──日本の建築ドローイング1970s−1990s」展(国立近現代建築資料館)など、建築(ないし建築家や建築のイメージ)がテーマの展覧会も続いている(これは偶然のもたらした結果であって、「建築」を反省的に思考させるような決定的要因があるというわけではないと思うが)。ここに、同年に刊行された建築のシークエンシャルな経験についてのテクスト、あるいは建築的なシークエンス経験をもたらしてくれるテクストの一群を付け加えてみると、また新たな共時的布置が浮かび上がってくるのではないだろうか。
この文章自体が、書物をめぐる散漫なぶらぶら歩きのようになってしまったが、その末尾に。瑣末な私事であるが、夏の終わりに自覚症状のないまま潜んでいた病が発覚し、この年末まで連綿と続く治療に拘束され続けた。失意でも不安でも怒りでもなく、自分が自分自身から決定的にずれてしまったような離人感を覚えつつ、大学での仕事と通院に時間を分断される日々に押し流されるようだった。そのようななかで数カ月ぶりに手に取った『ユートピアへのシークエンス』は、テクスチュアルな愉楽をもたらし、そして建築を巡る旅へとふんわりと誘ってくれる1冊であった。
註
★1──柴崎友香『パノララ』(講談社、2015)、76頁。
★2──同書、421頁。
小澤京子(おざわ・きょうこ)
1976年生まれ。表象文化論研究。和洋女子大学准教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。著書=『ストローブ=ユイレ──シネマの絶対に向けて』(分担執筆、森話社、近刊)、『ユートピア都市の書法』(法政大学出版局、2017)、『破壊のあとの都市空間』(分担執筆、青弓社、2017)、『都市の解剖学』(ありな書房、2011)ほか。
201801
特集 ブック・レビュー 2018
歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか
オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか
中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか
器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか
21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか
ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか
「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか
シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか
歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか
中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか
建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか


