「拡張現実の時代」におけるプロシューマー論の射程──宇野常寛+濱野智史『希望論──2010年代の文化と社会』
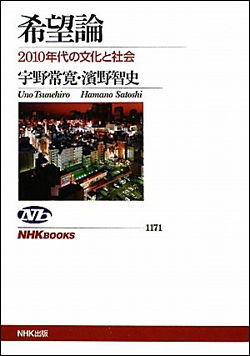
- ◉宇野常寛+濱野智史
『希望論──2010年代の文化と社会』
(NHKブックス、2012)
宇野常寛氏と濱野智史氏は東日本大震災を、ポスト戦後日本社会におけるダメ押し的な「でかい一発」と捉える。震災によって初めてもたらされた諸現象よりも、むしろ震災によって露呈され、浮き彫りになってきた事柄に目を向けることで、緩効的な「希望」の処方箋を提示しようというのが本書の企図である★1。
そこで、本書の随所で参照されているのが、先立って宇野氏の単著『リトル・ピープルの時代』で提起された「拡張現実の時代」というテーゼである★2。これは社会学者の見田宗介=大澤真幸によって区分された、戦後日本の精神史の枠組みを踏まえたものだ。広く知られているように、見田氏は90年代初頭、「現実」という概念の反対語に着目し、日本社会の現実を意味づける「反現実」として中心的に機能する概念が、戦後半世紀のあいだに段階的に移り変わってきたことを明快に論じた。すなわち、アメリカン・デモクラシーやソヴィエト・コミュニズムが未だない理想として立ち現われた戦後復興期=「理想の時代」、日本の近代化が促進されるとともに、その限界を熱い夢とともに(=政治の季節)乗り越えようとした高度成長期=「夢の時代」、消費社会の到来によって、商品が記号的な差異として意味づけられるとともに、リアリティの脱臭に向かう虚構の言説によって特徴づけられるポスト高度成長期=「虚構の時代」、という整理である★3。大澤氏はこの分析を継承し、オウム真理教事件が発覚した1995年を臨界点として、「虚構の時代」が終焉に向かったという議論を展開している★4。「拡張現実の時代」とは、いわゆる「虚構の時代の果て」を、つまり90年代後半以降の日本社会の相貌を、宇野氏の視座から言い表わしたものだ。
本書で繰り返し強調されているのは、ソーシャルメディアが普及して以降のインターネットにおいては、純粋に仮想空間に閉じた人間関係は成り立ちにくく、ネットは現実のコミュニケーションを拡張する方向に「しか」作用していないということである。たとえば、近年におけるソーシャルゲームの隆盛をとってみても、そこでは虚構(ゲーム)と現実(社会関係)が不可分に絡まり合っている。いまやリアル/ネット、現実/虚構、日常/非日常といった二項対立は成り立たない。これらは相互に重なりあい、複雑に混在しあうようになってきた。かつての「虚構」が「仮想現実」に近似できるとすれば、現代社会はまるで「拡張現実」のようだ。
さらに震災以後、「終わりなき日常」(宮台真司)に突然「非日常」が挿入され、いまや不気味に共在するようになったという点で、「拡張現実の時代」とは、ネットをめぐる技術動向を示すテーゼであるだけでなく、この1年の時代認識を言い表わす暗喩にもなっているという。
両氏がインターネットの可能性を(僕には若干、楽観的すぎると思えるほど)強調するのは、こうした分析を踏まえてのことだ。地震と津波、そして原発事故によって地域社会が徹底的に破壊され、共同体の存続自体が危ぶまれる集落も少なくない。長い目で見た場合、デジタルディバイド(情報格差)という古くて新しい問題を乗り越え、共同体の再生にソーシャルメディアを活用すべきという主張には、全面的に同意したい。緊急事態期や応急復旧期におけるソーシャルメディアの成果や課題についてはすでに、社会心理学や災害情報学などの観点から多く論じられているが、これから先、復興政策をめぐる合意形成、風評被害の予防や解消、そして原発事故をめぐる政治的論議など、地理的範囲を越えた広域的な議論や連帯が求められるなかで、ネットを通じて被災地の声を広く媒介していくことも欠かせないはずだ★5。
もっとも本書では、濱野氏がこれまでのアーキテクチャ論で展開した議論を踏まえて★6、日本のインターネット文化における「ガラパゴス」的な特性こそに「希望」が見出される。アメリカに比べて、匿名的、非人格的、集団主義的な日本のネット利用。2ちゃんねる/ニコニコ動画に代表されるように、ユーザーの無意識的な消費活動が集合的な創作として編みあがっていくような、日本特有のアーキテクチャの創造性。インターネット上の集合的無意識を政治的な回路に接続していくというヴィジョンは、言うまでもなく、東浩紀氏の『一般意志2.0』と通底する★7。また、近年では「ゲーミフィケーション」や「ゲーム型社会運動」といった営みに注目が集まっているが、それは人間のなかにある動物的な快楽、他者への利他的感情を生み出しやすいアーキテクチャに支えられているという。そこで両氏は、近代的市民として成熟した主体の形成に向けて人々を啓蒙するのでも、その反対に、未熟で欲望に忠実な動物として捉えて制度設計を施すのでもない、中間的な主体という人間観にもとづく運動を支持している。
さらに濱野氏は、「インターネットの匿名性こそが力を帯びつつあるのだとすれば、ゼロ年代に2ちゃんねる/ニコニコ動画的なインターネットの匿名性が吹き荒れた日本社会の経験とリテラシーというのは、むしろ世界に先んじている」のではないかと言い、「内発的に作動し続けるシステムを一部分だけちょっとイジって、じょじょに慣らし運転をしながら、だましだまし社会を別の方向に持っていくしかない。比喩的にいえば、日本社会のバグを突いて、裏技のようにハックする。それしか社会を『変える』という方法はないんじゃないか」と続ける(p.132, 134)。
こうした発想は、伊藤昌亮氏の『フラッシュモブズ』における分析を彷彿させる★8。「一瞬の群集」あるいは「閃光の暴徒」と直訳できるフラッシュモブ(flash mob)とは、インターネットやケータイを介して呼びかけられた、互いに見知らぬ人々が公共の場に集い、わけのわからないことをしてからすぐに解散するという集合的表現である。フラッシュモブはゼロ年代、世界各地の都市で同時多発的に立ち現われ、グローバルな現象として拡大していったが、そのなかでも「2ちゃんねるオフ」(2ちゃんねる上で企画されるオフ会)は、そのバカバカしさ、わけのわからなさ、くだらなさなどの点で、おそらく最高の水準でその精神と思想に合致していたという。伊藤氏が詳細に考察するのは、「吉野家祭り」と「24時間マラソン監視オフ」である。しかしそれらは、いわゆる「ガラパゴス」的なネット文化のなかで、その早すぎた成熟と爛熟の果てにほぼ絶滅してしまったという。あらゆる「外部」への可能性を包含するほどに強靭かつ柔軟な「システム」──すなわち「終わりなき日常」──のなかでなされるフラッシュモブは、したがって「システム」からその「外部」へと脱出することを目指すのではなく、むしろ「システム」の内側からみずからを取り巻く状況に働きかけ、ほんの一瞬でもそれを変容させることを目指して実践される。それは新たな市民運動とテロリズムの両極に連なっており、社会秩序に対して創造的に沸騰することもあれば、逆に破滅的に作用する危うさも兼ね備えている。『フラッシュモブズ』は震災の直前に出版された書物だが、今後、日本の「ガラパゴス」的な文化現象を介した新しい社会運動の可能性を、その限界も視野に入れて掘り下げていくうえで、重要な導き糸になるに違いない。
ところで、ネット上の創作活動をめぐる議論のなかで近年よく引き合いに出されるのが、アメリカの未来学者アルビン・トフラーが1980年代に提唱した「プロシューマー」(生産消費者)という概念である★9。非マス化(脱画一化)が促される脱産業社会の到来にともない、これまで市場のなかで乖離していた生産者(producer)と消費者(consumer)の役割が接近し、生産活動をおこなう消費者(prosumer = producer + consumer)の重要性が増していくというのがトフラーの主張だったが、ソーシャルメディアというプラットフォームの普及などによって、ようやくそれが現実化してきたというわけだ。
ただし、本書のなかでも示唆されているが、あるプラットフォームにおいて情報の生産者/消費者の境界線が消失するということと、そのアーキテクチャのデザイナー(設計者)/ユーザー(使用者)の関係のありようは区別されなければならない。加島卓氏が指摘するように、情報デザインのプラットフォームにおいては、ユーザーの主体性や能動性を先取りすることで、あらかじめユーザーの自由度もメタにデザインされなければならない。デザインの対象が拡張されたことで、「プロ」の居場所にズレが生じたとともに、ユーザー自身は想定の範囲内で(どこまでもほどほどに)表現に水路づけられていく★10。ここで詳述することは避けるが、ユーザーの安全性と引き換えに、メーカーによって利用環境が徹底的に管理される「紐付きアプライアンス」や、ユーザー各自の嗜好を踏まえて、知りたい情報だけが自動的にカスタマイズされる「フィルターバブル」など、インターネットの「箱庭化」といった傾向も見過ごせない★11。
結局のところ、インターネット上の集合的無意識に希望を託すにしても、「ユーザーはアーキテクチャのバグを突き、運営する側はそれに対応しながらアーキテクチャを修正していく」(p.201)というオープンスパイラルを理想的にまわしていくためには、濱野氏も認めているように、環境設計に対するリテラシーを社会的に高めていくしかない。その道筋を具体的に切り開いていくのは、今後の重要な(しかしきわめて困難な)課題であろう。
註
★1──もっとも、3年を要して制作されたという経緯もあり、両氏の精力的な仕事に馴染みがある読者にとっては、さほど目新しい知見を得ることができないかもしれない。
★2──宇野常寛『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎、2011)
★3──見田宗介『現代日本の感覚と思想』(講談社学術文庫、1996)、『社会学入門――人間と社会の未来』(岩波新書、2006)などを参照。
★4──大澤真幸『増補 虚構の時代の果て』(ちくま学芸文庫、2009)、『不可能性の時代』(岩波新書、2008)などを参照。
★5──拙論「震災後の地域メディアをITはエンパワーできるか──道具的文化から表現的文化へ」(コンピューターテクノロジー編集部編『IT時代の震災と核被害』インプレスジャパン、2011)
★6──濱野智史『アーキテクチャの生態系──情報環境はいかに設計されてきたか』(NTT出版、2008)
★7──東浩紀『一般意志2.0──ルソー、フロイト、グーグル』(講談社、2011)
★8──伊藤昌亮『フラッシュモブズ──儀礼と運動の交わるところ』(NTT出版、2011)
★9──アルビン・トフラー『第三の波』(徳山二郎監修、鈴木健次+櫻井元雄ほか訳、日本放送出版協会、1980)
★10──加島卓「ユーザーフレンドリーな情報デザイン──Design of What?」遠藤知巳編『フラット・カルチャー──現代日本の社会学』(せりか書房、2010)
★11──Jonathan Zittrain, The Future of the Internet: And How to Stop It, Yale University Press, 2008. 邦訳=『インターネットが死ぬ日──そして、それを避けるには』(井口耕二訳、早川書房、2009)。Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You, The Penguin Press HC, 2011. 邦訳=『閉じこもるインターネット──グーグル・パーソナライズ・民主主義』(井口耕二訳、早川書房、2012)。土橋臣吾+南田勝也+辻泉編著『デジタルメディアの社会学──問題を発見し、可能性を探る』(北樹出版、2011)などを参照。
201206
特集 書物のなかの震災と復興
木造仮設住宅から復興住宅へ──はりゅうウッドスタジオほか『木造仮設住宅群──3.11からはじまったある建築の記録』
線の思考──寸断とネットワーク──原武史『震災と鉄道』
混迷のなかで提示された技法としての倒錯──大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ──3・11後の哲学』
私たちの凄まじく具体的な暮らし──鞍田崇、中沢新一ほか『〈民藝〉のレッスン──つたなさの技法』
「今、音楽に何ができるか」という修辞に答える──震災時代の芸術作品
再び立てられた「問い」──露呈した近代─反近代の限界を超えて──日本建築学会編『3・11後の建築・まち──われわれは明日どこに住むか』
日本という〈身体〉の治癒はいかに可能か── 加藤典洋『3.11──死に神に突き飛ばされる』
逃げない「ヒト」を避難するようにするには── 片田敏孝『人が死なない防災』
政治としての建築──隈研吾『対談集 つなぐ建築』
社会がゲシュタルトクライシスにおちいるとき──篠原雅武『全─生活論──転形期の公共空間』
「拡張現実の時代」におけるプロシューマー論の射程──宇野常寛+濱野智史『希望論──2010年代の文化と社会』


