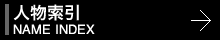ENQUETE
特集:201401 2013-2014年の都市・建築・言葉 アンケート<市川紘司
●A1今年読んだもののなかで一番面白かったのは槇文彦氏による『漂うモダニズム』(左右社)に所収された同名のテキストである。モダニズムという一艘の「船」が溶解して何でもありの「ポタージュスープ」と化した、というのが槇氏の現在の建築的状況に対する認識である。テキスト中では賛否どちらの結論も出していないのだが、筆者の読後感としては否定的なニュアンスのほうがつよく残った。おそらくそれは、この「船」というメタファーがフーコーによるヘテロトピア論を想起させたからである。フーコーによれば「船」とは「場所なき場所」であり、あらゆる現実的な事象を相対化させる「他者の場所」としてのヘテロトピアの最たる存在である。「船を持たない文明においては、夢は枯れ果て、スパイ活動が冒険に取って代わり、警察がならず者の船乗りたちに取って代わる」(「Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias」『Architecture, Mouvement, Continuité 5』1984)。かようなメタファーの同一性から、ヘテロトピア論を下敷きにしつつ「漂うモダニズム」を読むと、以下のような結論を想定せざるをえなかった。ポタージュスープのなかではあらゆる建築的実践が自由である、しかしそこで起きるのはせいぜい「小波」にすぎない、ゆえにむしろ一見不自由ではあってもさまざまな場所に発着可能である空間としての「船」に戻るべきではないか──。
現代という時代を「後期近代」と呼び、その特徴を旧来的な「規範」の液状化が進行した「リキッド・モダニティ」とまとめたのはジクムント・バウマンである。しかし、人は規範なしでは生きられないゆえ、自分自身で再帰的にみずからの規範を創造しなければならない。槇氏にとっての規範は(前期近代=「ソリッド・モダニティ」の産物である)「モダニズム」となるだろう。あるいはモダニズムが定着しなかった中国の建築においては、近年でも「伝統」に規範を求めることがしばしばである。しかしなによりも重要なのは、現在において、規範とはもっと小さく、細かく、多数あってよいということである(それが「規範」として各人に機能しさえすれば)。「規範」はいま一艘の船である必要はない。ポタージュに取り込まれた小波ではなく、自立した作家たちによる実践が独立した「小舟」として数多浮かぶような海景が、本来は望ましいのである。
筆者は2010年当時に絶版であった建築本だけを紹介する刊行物を制作したことがある(『ねもは01 絶版☆建築ブックガイド』)。現在の若い人間にも読まれるべき多くの本が入手困難であるように思われたからだった。今年、当時われわれが取り上げた『環境としての建築』(レイナー・バンハム)と『形の合成に関するノート』(クリストファー・アレグザンダー)が、鹿島出版会から再刊された。どちらもきわめて「理論」的な建築の書籍である。また、今年は、建築理論書を読みなおす研究会(「10+1 建築理論研究会」https://www.10plus1.jp/monthly/serial/riron/)が南泰裕氏らによって発足され、槇氏とともに20世紀後半の日本建築を理論的側面でリードしてきた磯崎新氏と原広司氏による「これからの建築理論」なるシンポジウムが開かれた(12月1日)。2013年は「建築理論」を再評価しようという動きがあった一年であったように思う。
「建築理論」というものの基礎的な役割は、旧来的な規範が溶解(または解体)をはじめた近代以降において、「建築」という枠組みそのものをあらためて策定することにあると筆者は考える。既存の規範を飲み込み、それをこねくり回しながら新しい規範をつくりだす、という「反芻」の行為が理論である。おそらく、ポタージュの小波を独立した小舟とするためには(つまりリキッドな世界のなかで再帰的にみずからのルールを規定するためには)、かつての「建築理論」は十分補助線となりうる。機能しなくなった古いものを反芻しながらみずからの新しい規範をつくらなければならない、という点では、20世紀も21世紀も変わらないからである。その意味で建築理論はいまこそ考えられるべきもののひとつであろう。どのように考えるのか。もちろん、経典を読んだり、巨匠のレクチャーを聞いたりすれば即済むわけではなく、ましてや展覧会から勇気だけもらって帰っていては達成され得ない。求められているのはあくまで反芻。インプットを別のかたちで創造的にアウトプットすることである。
-




- 槇文彦『漂うモダニズム』/『ねもは01 絶版☆建築ブックガイド』/レイナー・バンハム『環境としての建築』/クリストファー・アレグザンダー『形の合成に関するノート』
●A2
自分の仕事としては2014年前半に2冊刊行物が出せそうである。どちらも近年の中国建築に関するもので、オリンピックや万博の準備でイケイケだったゼロ年代とは異なる、2010年代における中国建築の状況を取り上げている。ゼロ年代と2010年代の中国建築のちがいは、端的にいえば、独立独歩のアトリエ建築家の充実である。王澍やMADアーキテクツやNeri&Huなど、ウェブメディアで作品が何度も掲載されるような建築家がずいぶん増えてきた。「外国人建築家の実験場」でしかなかった中国において、個人の作家としての建築家はどのようにして実践を進めているのか。そもそも中国において建築と都市はどのような制度のもと、どのようなプロセスを経てつくられているのか。そして日本はそれをどのように理解して、関わっていくべきなのか。日本でもとくにゼロ年代には中国に注目するメディアや特集が比較的多くあったが、彼の国のバブリーな荒波に目を奪われるかたちでじつはこういった根幹的な部分の分析があまりされていないように思える。ゼロ年代というひとつの大波が終わったあとだからこそ可能な、冷静な(嫌中でも親中でもない)目線での評論をしたいと思っている。
●A3
北京オリンピックのために建設された《中国国家体育場》(鳥の巣)のことを思い出した。2002年に行なわれた国際コンペによってヘルツォーク&ド・ムーロンによる案が決定され、その後コストカットのため規模の縮小や開閉屋根の設置中止などの対策が取られたのだが、これに対して張永和や劉家琨といった中国の建築家たちが連名で意見書を提出した。いわく、こうした処置は建築の全体性や、開放・成長する中国のアイコンとしてあったこの建築のイメージを損なう。東京オリンピックメインスタジアムのザハ・ハディド案を受けての動きとはまったく対照的なのだが、とはいえもちろん、これによってどちらかを褒めどちらかを貶めるつもりはなく、両国のオリンピック開催の背景にある状況のちがいだけをあらためて感じた。そもそも、《鳥の巣》は中心部から遠く離れた広大なオリンピックパークのなかに建設されるものであり、いくら大きくても大き過ぎることはなかった。オリンピック開発の少し前に建設がはじまったポール・アンドリューによる《国家大劇院》では、その敷地が天安門広場にほど近い歴史的空間にあったため、《鳥の巣》とは逆に、コストの高さ、劇場機能の不合理、周辺環境への悪影響といった批判をふくむ意見書が建築家の組織した委員会から提出されている。