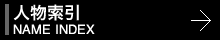ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<柴原聡子
●A1
震災を忘れてはならないと感じていた直後とは異なり、現在は、福島のこと、東北の復興のこと、ふたつの性質は違えど、いずれも途方もなく長い時間がかかる問題であることを改めて思う。忘れるどころか、いまも続いているという感覚。一時的な危機としてとらえていた時間が延々と続く現状では、今後の展望をゆったりと見渡すこともできない。だからか、震災を経て自分のDIYへのこだわりがますます強くなった。現在までも、音楽も自分でつくるし、企画も自分で考え、建物を一から建てたことはないが、工夫程度ならば自分でやってきたし、なんであれDIY精神に基づいて実践してきた。震災以降も、自分の手でできることに関してその姿勢は変わらないが、一方で、できないことはなにかについても考えている。自分が「できない」ことへの想像力が欠落していないか。自分でできることまで(おもにお金にかえて)「できないこと」として交換しすぎているのではないか。専門性を追求した結果、専門外になった途端無関心になっているのではないか。そのような問いが生まれた。かつて先端技術であった工業製品が、むしろ建設の技術を持たない人たちにとってのオープンソースとなったように、専門という枠を外して考えることで、自分たちの生活を積極的につくっていくことができたらと思う。そこにはきっとネットワークも有効になってくる。自分でやってみたけど(やってみたいけれど)できないことが生じたとき、専門という「枠」や「商品」に丸投げするのではなく、必要となる専門性を携えた「人」に声を掛けてみることに可能性を感じる。2011年のあいだに関わった人やプロジェクトを通して、このような感触を得るに至った。一つひとつは局所的な事例ではあるが、そこから得るヒントは多い。
気仙沼尾形家再建プロジェクト
2010年から2年間、日本建築学会『建築雑誌』の編集委員でご一緒した工学院大学の後藤治先生に紹介してもらい、ボランティアとして訪ねた先が気仙沼小々汐の尾形家である。200年以上の歴史を持つ民家で、国の指定はされていないが、家屋も、保管されてきた文書も、家で続いてきた行事も、あらゆる点において、重要な地元の歴史を伝える文化財である。海に面する大きな民家は、津波によって根こそぎ流されたが、海沿いの電信柱にひっかかり、その場で倒壊した。家型を保ったまま残ったため、震災以前から家主と交流を持ってきた人たちが再建を見込んで立ち上げたのがこのプロジェクトである。広大な敷地に散らばってしまった家屋の部材や細々とした文化財を、半年間かけて手作業で回収、建物は残った部材を使っての再建を目指し、儀礼に使っていた小物や、日用品などの文化財は国立歴史民俗博物館での再現展示に活用される予定である。
誰が中心というわけでもなく、自ずと集まったメンバーは、茅葺き施工業者、民俗学の研究者、国立の博物館のスタッフ、建築を学んだ若者、建築史家など、じつに多様だ。このプロジェクトを知り、ひとつの「家」を起点に人々が集まり、地域の文化が継がれていくことに感銘を受けた。今回の震災によって沿岸部の文化財は多く失われてしまったが、一口に地域の文化や文化財と言ってもそれらは複雑で、システマティックに拾い上げていくことはとても難しい。しかし、まだまだトップダウンのシステムがベースとなる救援方法しか適用されないために、津波の被害からかろうじて残った文化財も放置されたままとなり、日々失われていっているのが現状だ。そんななか、震災以前からのネットワークはすぐに起動し、インディペンデントに成果をあげている。今後、一人ひとりが災害時に対処をしていくためには、地域の文化が教育のツールとなって、その心得を伝えていかなくてはならない。そのためにも、このような震災以前からのネットワークを生かして地域文化を継承し、日々の生活に根付かせていくことは重要だと思う。
気仙沼尾形家再建プロジェクトについては、『建築雑誌』2011年11月号に記事を掲載した。

- 震災直後の尾形家。茅葺き屋根が水に浮いたことにより、かたちを保ったまま流された
撮影=田揚裕子

- 尾形家から発掘された古文書

- 発掘され、洗浄された尾形家の文化財
以上二点、筆者撮影
破滅村
オンライン同人文芸誌『破滅派』の高橋氏が山梨の山奥の土地約300坪を購入し、2010年より、開墾および自力建設をしているのが破滅村である。鬱蒼とした竹林だったところを1年程かけて開墾、建築の知識がないまま整地をし、C・アレグザンダーを参照しながら小屋を建て、いまも開拓と増築を進めている。いわゆるセルフビルドであるが、開墾から自分たちで行なっていること(整地されていないからか、土地はパソコン一台分程度の価格で購入できたという)、家主がウェブの仕事を生業とするため、オンラインであればどこでも仕事が可能であること、その場を開拓していく経過や、村での活動を外に向けて発信していることなど、同世代が実践できるDIYとして多くの刺激を受ける。発信する内容は、一人でバーベキューを効率よく行なう方法や、限られた電気のなか、キャンプファイヤーを照明に私一人しか演奏しなかった第1回破滅フェス(いずれもUSTREAMで放映)など、ささやかな出来事ばかりだが、単純に「やってみたらできた」というあっけらかんとしたモチベーションは、自分が考えるDIYの在り方にとても近い。
開墾から建設までの経過は、破滅派7号および、高橋氏のブログで読む事ができる。8号目となる最新号の破滅派では、四国にあるセルフビルドマンション「沢田マンション」で行なわれたSAWASONICのレポートなどもあり興味深い。

- 破滅派8号(2011)
●A2
古川日出男『馬たちよ、それでも光は無垢で』
福島出身の小説家である古川日出男氏が、自身の震災直後からの経過を、震災から一カ月後に福島浜通りを訪れたことを軸にして、綴ったテキスト。古川氏の目線で書かれたルポタージュを読み進めるうち、古川氏の著作である『聖家族』の主人公が登場する。そこからドキュメントとも小説とも言えない、不思議な文章に変貌していく。震災直後の動揺、感情が整理されない様子が見事に言語化されており、震災直後から夏くらいまでの自分では言葉にできなかった感情が、この本を読み返すと生々しく思い出される。文学のかたちをとって震災直後が記録されたという意味で、とても良い本だと思う。

- 古川日出男『馬たちよ、それでも光は無垢で』(新潮社、2011)
山口弥一郎『津浪と村』
民俗学者の山口弥一郎が、年月をかけて津浪の被害を受けた東北の村々を自分の足で歩き訪ね、津浪の被害を受けた村の存続の歴史、移動の歴史などを緻密に記録した本である。数値的な記録だけからは見えてこない、移転や移民の背景にある人々の思いや日々の生活の重みが、淡々とした文章から伝わってくる。この本は震災後の7月に復刊されたが、現代語訳にあたって、気仙沼尾形家再建プロジェクトでお会いしたリアス・アーク美術館の川島秀一氏が編纂された(石井正己氏との共編纂)。川島氏にお聞きした、津波が来る度に移動を繰り返してきた地域の歴史についてのお考えはたいへん示唆的であった。それらがベースになるであろう、今後のリアス・アーク美術館の活動にも注目したい。

- 山口弥一郎『津浪と村』(三弥井書店、2011)
フェスティバル/トーキョーで観た、村川拓也による演劇『ツァイトゲーバー』も興味深かった。ハンディキャップを持った人と、それを介護する人の身体のふるまいを再現する作品だが、特殊な事例を参照しているにもかかわらず、住居の中での普遍的な人のふるまいというのがよく表われていて、考えさせられた。この作品に限ったものではないのだろうが、平面図のように床に光の線が出るのみで住居の間取りが表現されたのも面白かった。ベランダでの出来事を演じるときだけ住居の輪郭線が浮き出て、室内でのシーンになると輪郭が消えるという仕組みは、通常私たちが家で認識する内と外の感覚が巧妙に視覚化されていたように思う。
ほかに、資生堂ギャラリーで開催された「あるべきようわ──三嶋りつ惠展」の青木淳氏による空間構成、東京国立近代美術館で開催された「パウル・クレー──おわらないアトリエ」展の西澤徹夫氏による空間構成は、いずれも平面や立体といった、決まったフォーマットの作品を展示する空間として、とても興味深かった。インスタレーションのような空間そのものを作品とする展示ではなく、これらの展覧会のような、平面や立体など物体として独立した作品を鑑賞する展示空間の可能性はもっと開拓されるべきだろう。
●A3
今後の東北でますます増える復興プロジェクトに、どのように建築家が関わるのか、またプロジェクトの生まれる段階やプログラムそのものに、どの程度建築家が主体的に関わることができるのか(もしくは立ち上げられるのか)に興味がある。また、大友良英氏が中心となってやっているプロジェクトFUKUSHIMA!は、DIYやネットワーク作りの実践として今後も注目したい。そして、第13回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館の展示。阪神大震災後の磯崎新コミッショナーによる日本館は鮮烈であったので、災害後の日本建築界のひとつの回答としてみられるであろう2012年の日本館はどのように展開されるのか、注目している。