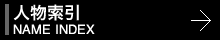ENQUETE
特集:201101 2010-2011年の都市・建築・言葉 アンケート<大山エンリコイサム
[1]──2010年はとても多くの刺激をもらった年だったので、個人的な回想を軸に考えてみたい。あいちトリエンナーレ2010/松戸アートラインプロジェクト2010
-


-

-

-

-

- アップロードされた「World's first graffiti on polar icebergs」の写真
-

- 「World's first graffiti on polar icebergs」の画像がアップロードされた掲示板
-

- グーグル・ストリートビューから見る都市空間
夏から秋にかけて参加した「あいちトリエンナーレ2010」は、「瀬戸内国際芸術祭2010」と並んで、昨年もっとも多くの人が訪れたアート・イベントのひとつだろう。その後、秋から冬にかけて参加した「松戸アートラインプロジェクト2010」は、中規模な地域型アート・プロジェクトとして充実したものになっていたと思う。これら大小のアート・プロジェクトは、どれも2010年に第一回目を行なった。横浜トリエンナーレと越後妻有トリエンナーレを筆頭に、ゼロ年代をつうじて蓄積された日本独自のアート・プロジェクトの遺産を、2010年に生まれたこれらのプロジェクトはどう活かし、そして、どう乗りこえていくのだろうか。今年は「横浜トリエンナーレ2011」が行なわれる。また、越後妻有トリエンナーレは2012年に第5回目が行なわれるはずだ。このふたつのプロジェクトも、今までと同じまま回だけを重ねていくわけではないだろう。2010年が新しく生まれたアート・プロジェクトの年だとしたら、2011年はその先達がどうでるのか、それに注目する年にしてみたい。
『アーキテクチャとクラウド──情報による空間の変容』
また、印象に残った書籍として『アーキテクチャとクラウド──情報による空間の変容』(millegraph、2010)があげられる。アマゾンやツイッターなど今日の情報環境を駆使して作られ、いくつかの対談やインタビューが収録されている本書には、南後由和とのメール対談というかたちで、主にストリート・アートに関して寄稿した。2005年に水戸芸術館で行なわれたグラフィティの展覧会「X-Color/グラフィティ in Japan」展を最後に、国内においてはアートや評論の立場からのストリート・アートに対する言及は久しく途絶えていたようにすら思えるが、ここ1、2年、建築・都市論の分野でふたたび増えはじめており、本書では比較的まとまった形をとることができた。今年は、荏開津広がストリート・アートに関する単著を準備しているという。こちらにもぜひ注目していきたい。
「SPECULA──21世紀芸術論」
建築・都市というお題からはやや逸れるが、昨年6月から今年1月まで続いた東京芸術大学先端芸術表現科と大学院映像研究科のパラレル・プログラム「SPECULA」は、約半年間にわたって全8回を行い、21世紀芸術論という副題のとおり、さまざまな議題を通じて今後の芸術のありかたを提示していて興味深かった。川俣正も登場した第7回では、これまでの、そして今後の地域型アート・プロジェクトの意義と問題についても議論が行なわれ、すでに述べた一連のトリエンナーレやアート・プロジェクトの動向に対する意識が変化してきていることを改めて確認することができた。「SPECULA」のように広く深い射程で議論が行なわれる機会はやはり貴重である。2011年のアート・シーンにさらなる可能性を期待したい。
[2]──2010年はまだゼロ年代の縁という感じがしなくもない。2011年こそ、次の10年の初年と考えてみたいところだが、とはいえ、まだ始まったばかりでどうにもヴィジョンが描きづらい。このアンケートの依頼を受けたあとも、しばらくどうしようかと考えていたが、そんな矢先、ある写真についてツイッター上で議論する機会があった。議論といっても、ちょっとした口ゲンカのようなものである。ところが、ひと晩寝て起きてみたら、そこに案外これからの都市空間を考える上で示唆的な部分があったのではないかと思えてきた。この機会にいちおう書いておきたい。
情報環境とストリート・アートの変化
件の写真はこれである。「World's first graffiti on polar icebergs (極地の氷山にかかれた世界で最初のグラフィティ)」という見出しで、2010年11月30日にインターネット上にアップロードされたこの写真は、これが本当にかかれたものかどうか、その真偽をめぐってささやかな議論を呼びおこした。結論から言えば、これはほぼ間違えなくフォトショップなどを使ったデジタル・コラージュであり、それは少し考えればすぐにわかるはずだ。にも関わらず、私自身もふくめ、多くの人は一瞬これが本当に描かれたものだと信じてしまった。それには理由がある。
周知のように、情報環境の飛躍的発展は私たちの生活を大きく変え、かつて手にとっていた多くのものはインターネット上でたやすく消費できるようになった。ストリート・アートも例外ではない。少なくても受容の仕方に限れば、実際に街で目にするのと同程度にネット上でストリート・アートを見るようになってきている。ここでは、その是非は問わないでおこう。しかしこの事実は、単に受容の仕方にとどまるものではない。ネット上での流通が加速すればするほど、作り手もそれを意識する。ネット上で公開することを前提につくられる、それどころか、その性質上、ネット上でしか正しく鑑賞できないようなストリート・アートが一部で現われてきているというのも、昨今の傾向だと言えるだろう(例えば、イタリアのストリート・アーティストBLUのアニメーション作品「MUTO」など)。そうでなくても、例えばグーグル・ストリートビューやセカイカメラの登場により、現実の都市空間とネット空間がヴァーチャルに──しかし、ある現実味を帯びつつ──重なるような感覚は、一般的にも浸透しつつある。これらのことは、先述の『アーキテクチャとクラウド』でも述べておいた。このように、現実世界を代替しかねないような情報環境の拡張が、そもそも現実の都市空間で行なわれているはずのストリート・アートに対する私たちの感覚を、部分的に麻痺させてしまったということは、やはり認めざるをえないだろう。インターネットで見ただけで、それを「見た気に」なってしまう錯覚は、多かれ少なかれ蔓延しているのである。
だとすれば、件の写真がフォトショップでつくってあること、いやむしろ、おそらくフォトショップでつくってあるだろうと「推測するしかない」ということは、それなりにひとつの問いかけである。もし私たちが、それを街で目にするならば、あるいは知人友人から聞いたのであれば、それが「本物」かどうかは即座に、または間接的に確認できる。だが、それが「極地の氷山にかかれたグラフィティの画像」である以上、現場に行って確認することは不可能に近いし、それが「ネットの掲示板にアップロードされた身元不明の画像」である以上、やはりその真偽は確認しがたい。多くの人がそれを一瞬信じてしまい、すぐに怪しいと気づくのだが、それを確認する手だてはない。このあいまいさ自体が、インターネット上で見るという受容の仕方に密接に結びついているわけだ。そのやりくちを通じてこの写真が示すのは、「インターネットにおけるストリート・アート受容の過多」という現状の盲点をついた批判であり、「みんなネットを通じて見ていないものを見た気になっているなら、なぜこれがグラフィティだと言えないのか?」というアイロニカルな態度であると考えてみたい。真偽をめぐる「本物性」は、そこでは宙づりのまま、不問に付されてしまうのである。
「遠方へのグラフィティ的想像力」
さて、この「本物性」のあいまいさは、インターネットというヴァーチャルなメディアにおいては、この写真に限らずとも多くのものに当てはまる問題だろう。だが、ストリート・アートがそもそも都市空間に直接かかれ、また見られるものであるということをふたたび思い出しておきたい。興味深いのは、ここではその真偽を不問に付すためのアリバイが二重になっているということである。すでに述べたように、それは単にネット上の「身元不明」の画像であるばかりでなく、「極地」でかかれたグラフィティの画像でもあり、直接その場に行って確認することができないということを含意している。従って、この写真では「現場にたどり着けない=地理的空間における距離」と「身元が不明である=情報空間における距離」の共犯関係が「本物性」のあいまいさを二重決定しているのだ。そこに、この写真独特のアクロバティックな魅力がある。なぜなら「地理的空間における距離」は、「本物性」のあいまいさにおける共犯関係をすぐに断ち切り、想像力を駆使して問題をななめに投げ返すからだ。
ストリート・アートには、建物の高いところや侵入しづらいところなど、なかなか手の届かない「距離」を越えていこうとするハードコアな傾向があるが、その時「あそこにかいてあったらみんな驚くだろう」というある種の想像力が働いている。ハードルの高さが、想像力を喚起するのだと言ってもよい。これを、さしあたり「遠方へのグラフィティ的想像力」と呼んでおこう。そして、地球上でもっとも手の届きづらい場所にかいてあるという意味で、件の写真はこの想像力を完璧に満たしている。いったい誰が、極地の氷山にグラフィティをかこうとするだろうか。この極端に即物的な「手の届かなさ=遠方への想像力」は、この写真から新たな批評性を引き出している。グーグル・ストリートビューやセカイカメラをはじめとする情報アーキテクチャがストリート・アート受容のあり方にも一定の影響を与えたこと、そして、この写真がその現状に対するアイロニーとして機能していることはすでに確認した。だが他方、ストリートビューがいくら世界中の都市を網羅しても、セカイカメラがいくら現実の都市にヴァーチャルにタグを書きこめても、地球上にはこれら情報アーキテクチャの手が届かない、地理的・空間的な「遠方」がある。グーグルやiPhoneは、極地へと実際に赴かなければ、それを代替することはできないのだから。だが、件の写真は、「遠方へのグラフィティ的想像力」を駆動させることで極地への距離をあっという間に飛び越えてみせる、というよりも、それをチープなデジタル・コラージュでばからしく演じてみせることで、ストリートビュー的ネット空間の彼方へと、アイロニカルに距離をとる。「本物性」を宙づりにし、情報環境に麻痺させられたストリート・アートを皮肉った「距離」は、ここではそのアイロニーの矛先を転じつつ、ストリートビュー的ネット空間からさらに遠方へと逃れるために、グラフィティの想像力をフル活用しているのだと考えてみたい。
技術的水準においても、感覚的水準においても、情報空間と現実の都市空間がますますその近接性を高めてきているという事実は否めない。だが、安易にその相同性を確認するのでもなく、逆にその相違を強調するのでもないかたちで、両者がもつれつつ織りなす編み目を読みほどいていくような作業が、今後ますます増えていくのではないだろうか。この文章でラフ・スケッチしたことにも、少なからずそのような意図がこめてある。だが「World's first graffiti on polar icebergs」がアイロニーにすぎず、それ以上でもそれ以下でもないのだとしたら、より具体的な思考─実践はこれから徐々に模索されるはずだ。2011年は、そのような意味での「初年」としても考えてみたい。