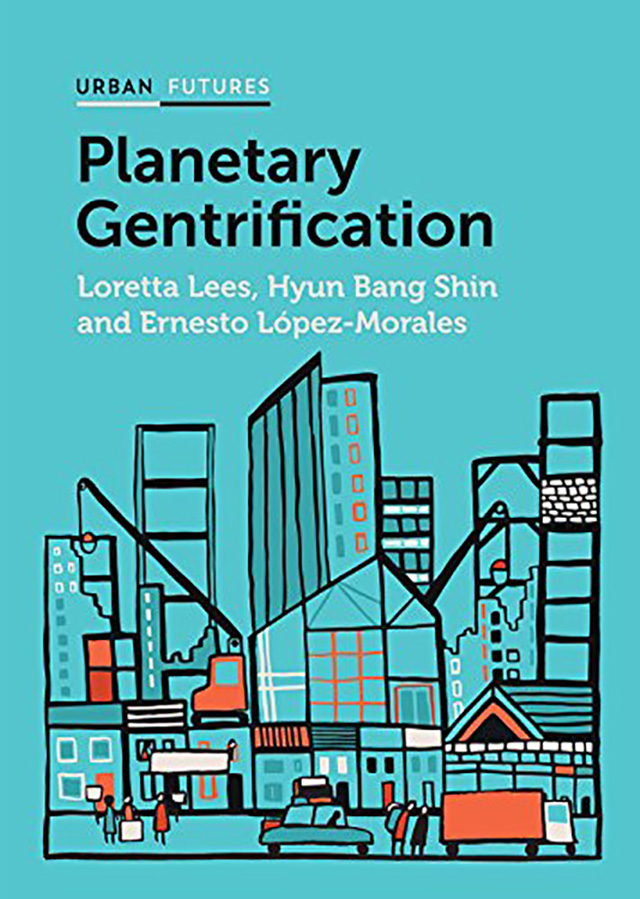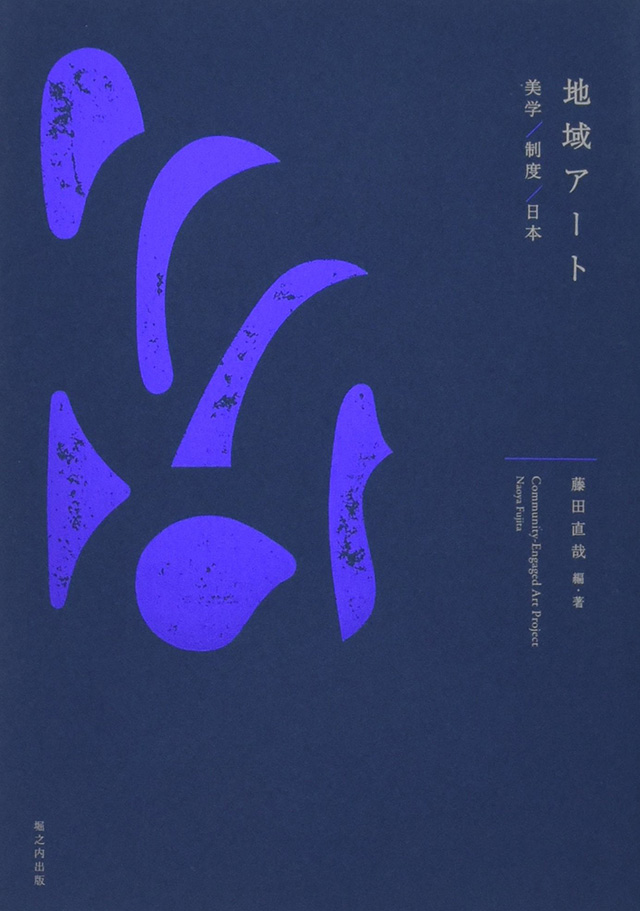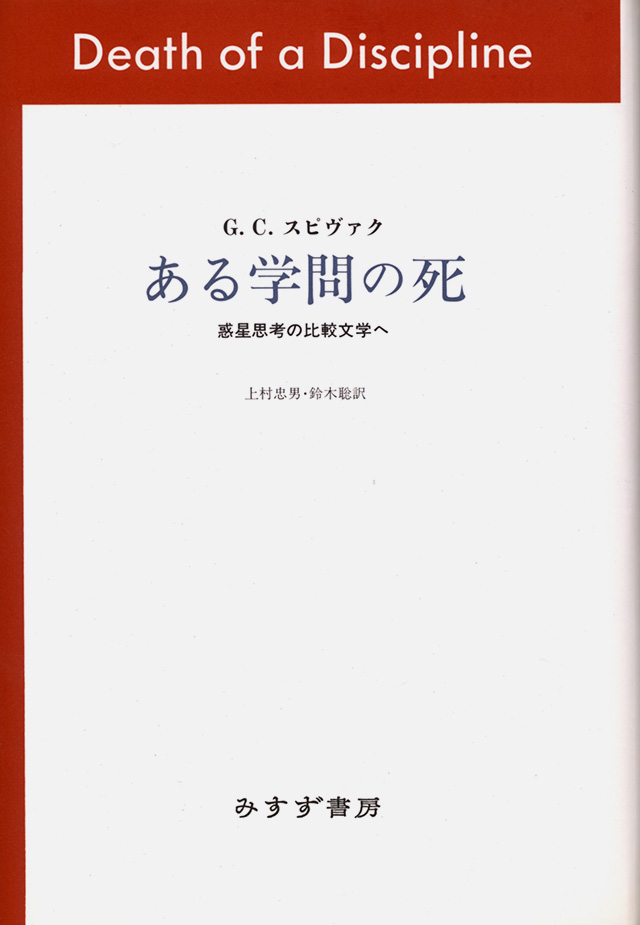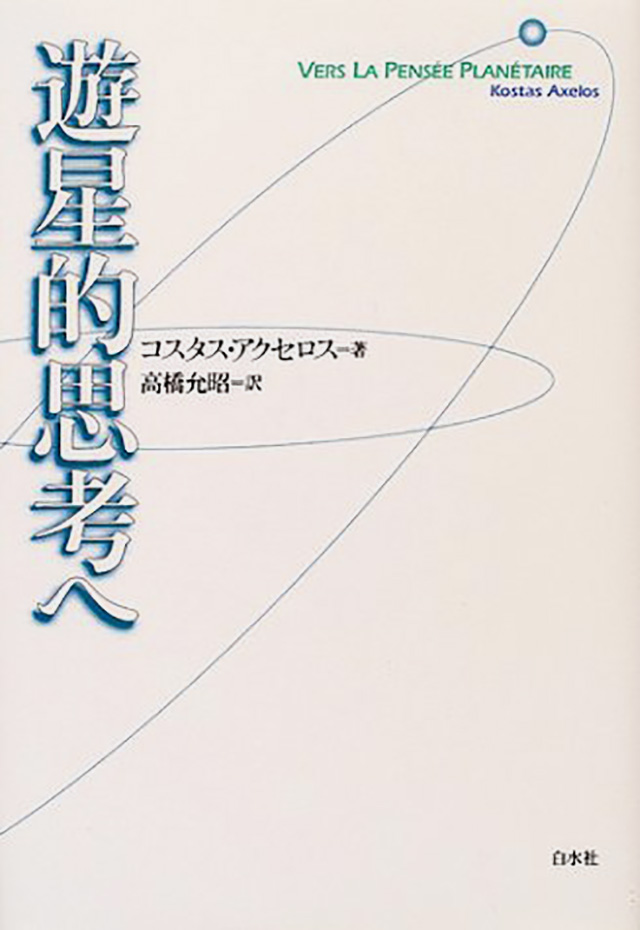進行形の都市研究を立ち上げる──プラネタリー・アーバニゼーションは遷移、侵犯する
ジェントリフィケーションが示唆するもの
平田──重要なケーススタディは増えてきているけれど、それだけでは必ずしも現代の都市のステータスや都市化の動きを理解するうえで十分ではないのではないか、そのためには個別研究をつなぎ、並べることで布置を描き出すような理論が求められるのではないか、そこに現代や過去の理論を突き合わせたり、それによって理論そのものを更新したりする余地があるのではないかということですね。
仙波──そのとおりだと思います。例えば、ジェントリフィケーションの議論自体、2000年代以降に本格化しますよね。おそらく94年の藤塚吉浩先生の仕事(「ジェントリフィケーション──海外諸国の研究動向と日本における研究の可能性」[『人文地理 』46(5)、1994])あたりがジェントリフィケーションについて体系的に書かれた最初期の論文だと思いますが、しかしニール・スミスを読めばわかるように、その起源には1950年代や60年代の都市開発があるわけです。そういう意味では、現在発生するジェントリフィケーションを調べることも重要なのだけれど、もう一方で、同時代のことを知るために過去のことを知ることは絶対に欠かせない、かつて存在した/いまに続く「広島」で何が起こったのかを問うことは、いまでも重要な意味がある。
以前、音楽評論家の東琢磨さんや写真家の笹岡啓子さんとシンポジウム(「ノー・モア・ヒロシマズ、だが、ヒロシマはいたるところに」2017年12月17日)に登壇させていただいたとき、出席されたとある高名な社会学者の方に、「僕たちの世代は広島のことを考えていかねばならないとつねづね思っていたけれど、その思考に対する何か見えない制約があった。でも君たちはそこから解き放たれている。もっと前へ進めていってほしい」とすごく背中を押される言葉をかけていただきました。もしかすると研究上の礼儀がなってないことのご指摘だったのかもしれませんが(笑)、かつての研究環境に課されていた社会的・政治的拘束のコードが変わってしまったのかもしれない。いずれにせよ、明確にディシプリンを設定しないことで見えてくることもたくさんある。その意味でも、都市にまつわる「理論」というものはきわめて重要で、それがないと現在地や取るべき進路を見失ってしまう、灯台のようなものかなと思っています。
平田──いい喩えですね。
仙波──別の例を出せば、北川さんが訳されているサンドロ・メッツァードラというボローニャ大学で教鞭を執る地理学者などは、まさにボーダーズ・メソッドと呼ばれる境界の問題について扱っています。例えば検問所の問題、入国管理局における移民収容の問題などはプラネタリー・アーバニゼーションにダイレクトにつながってくる。
そこからロジスティクスの話に移すと、去年、広島で豪雨災害があり、依然としてその傷が癒えたとは言いがたいのですが、当時の広島ではすぐにコンビニやスーパーからモノが消えました。われわれが自明だと考えるロジスティクスの存在は、想定以上に脆弱な側面がある。それは先ほどのコンテナの話とつながるところで、原口さんの議論では、そこには場所性というものが本来あったはずだと。わかりやすい例を挙げれば、マーロン・ブランドが主演した『波止場』(1954)で描かれたあの波止場のような、ある種の闘争の場としての港ですね。それがいまや港は完全に管理された、コンテナが移動するだけの係留点と見なされている。まさに非場所的なるものとしての港です(原口さんは「非場所」という言い方はしませんが)。そこにはどういう変化があるのか。コンビニなどへと至るロジスティクスの末端まで含めて考えると、自分たちの生活にとっての身近な問題とプラネタリー・アーバニゼーションの議論というのは、じつはすごく近しい関係にあるのだと気づく。それは意識しづらいことですが、意識した(してしまった)瞬間に見えることでもあります。
このことをプラネタリー・ジェントリフィケーションの話で言うとどうなるか。『Planetary Gentrification』(シン・ヒュンバン、ロレッタ・リーズ、エルネスト・ロペス=モラレス、Polity、2016)には「ジェントリフィケーション・ブループリント」という章があります。彼らは、ジェントリフィケーションのモデルは必ずしも単一のものでないと、この本のなかで繰り返しています。しかしそのやり方自体が模倣されることがある。例えばゼロ・トレランス(不寛容)方式などはジュリアーニがニューヨーク市長だった頃に同地で「奏功」し、それを見たメキシコシティの役人がジュリアーニのコンサルティング会社にフィーを支払うかたちで「転用」して、露店の排除政策につなげるわけですね。彼らによればリオデジャネイロの軽犯罪取締政策の背後にも、ジュリアーニのアイデアがあるとされる。つまり、ジェントリフィケーションを引き起こす、ないしは誘導する「青写真(ブループリント)」が惑星規模で伝播する現状がある。
また先ほど平田さんからシルヴィ・ティソの名前が出ました。彼女が言うにはボストンのサウスエンドはもともとスキッド・ロウ("ドヤ街")だったエリアですが、ジェントリフィケーションの結果、公園に住んでいた人たちが追い出されて高級犬が走り回るドッグランが整備されている。そうした場所が「ダイバーシティの街」であると自称し、またそう見られているわけです。日本の渋谷にしても、例えばLGBTの条例制定、そして宮下公園をめぐる一連の問題やきわめてドラスティックな都市再開発を見ればわかるように、明らかに「クリエイティブ・シティ」化していきたいという思惑を感じざるをえません。けれども、本当に人が住める街となっているのか。人がいる権利を排除する現在進行形の都市空間としての渋谷を、木村正人先生は「〈共〉(コモンズ)の私有化と抵抗──渋谷におけるジェントリフィケーション過程と野宿者運動」(『空間・社会・地理思想』第22号、2019)で描かれていました。そうした各地の事例を見るにつけ、きれいにしたい、かっこよくありたいという都市的欲望が、それぞれの場所において世界のスマート・シティ・ランキングを駆け上りたいという意思として現われ、結果として世界規模での人間の排除という動きにつながっている部分があるのではないでしょうか。
「プライベート化」の進展
平田──再びクリスティン・ロスの本について話すと、『もっと速く、もっときれいに』で繰り返し分析の対象になっているのが、ジャック・タチの『ぼくの伯父さん』(1958)や『プレイタイム』(1967)です。『ぼくの伯父さん』が撮られた1958年の頃はまだ「第2のオスマン化」といわれるパリ改造が完了していない時期で、一方にはタチ演じるユロ伯父さんの妹夫婦が住んでいるル・コルビュジエ風のデザイナーズ・ハウスがあり、もう一方にはユロ伯父さんが住む地域があって、そこでは昔ながらの共同体的な関係が息づいている。妹夫婦の家はまさにいま仙波さんが語られた「きれいにする」という規範が課される場となります。子どもが外で遊んで汚れて帰ってくるとシャワーでゴシゴシと洗われ──このシーンは影絵的に表現されていてちょっと怖い演出ですが──、汚いものや外部のものを排除するような閉じられた空間として表象されています。全体として映画はスラップスティック・コメディで、チャップリンが工場の機械としたことをタチは家電によってするのですが、映画は工事の騒音のシーンから始まり、最後にユロ伯父さんが住んでいた地域から人がいなくなりガランとした状態が映し出されます。鑑賞者に暗示されるのは、その地域の建物が壊されて、最終的になくなっていくということです。次の1967年の『プレイタイム』になると、高層建築物や空港などのスーパー・モダンな空間しか出てこなくなります。ロスはこれらのタチの映画を分析しながら、フランスの消費社会の隆盛において「プライベート化」が進んだことを指摘しています。『ぼくの伯父さん』でユロ伯父さんが住んでいたような相互扶助的なコミュニティ空間がどんどんなくなっていく一方で、閉じられた核家族的生活モデルが前景化するという状況があるわけです。
乱暴に言えばこういうプライベート化の話というのは、インターネット活動家であるイーライ・パリサーの2011年のフィルターバブルの話などにもつながってくると思います。要するに、インターネットにおける過剰な情報の流れをユーザーが管理しやすくすることを意図して、グーグルがすべてのユーザーの検索エンジンをパーソナライズ化して、自分が見たいものしか見られないようなアルゴリズムを実装していく。その結果、自分と同じような趣味や価値観をもっている人とのネットワークしかつくられない。パリサーの本ではすでに、後にGAFAと呼ばれるような巨大IT企業がユーザーの個人情報を収集することに対して懸念が表明されていましたが、2013年の6月にエドワード・スノーデンによる国家安全保障局(NSA)の国際的監視網に対する勇気ある告発──スノーデン自身が告発に至った動機としてオバマ大統領(当時)によるドローンの使用を挙げていました──によって、これらのIT企業がNSAに協力していたことが明らかにされました。パーソナライズ化による管理が有する負の影響は確実に大きくなります。後はご存知の通り、2016年には、ブレグジットやドナルド・トランプの大統領当選で、ポスト・トゥルースやフェイク・ニュースが世界的に語られ、自分の趣味や価値観に合わないのであれば真実などどうでもよいものとされ、社会の分断が言論空間にも浸透していることがいよいよ明らかになった。誰もが同じ情報=真実にアクセスできるはずだと想像していたインターネットの未来像が崩れ、誰もが外部の情報を選別・排除するフィルターに覆われてプライベートに閉じていくという現状が生まれたわけです。社会で共有されるべき価値はもはやない、とでも言わんばかりのように。
ジェントリフィケーションとクリエイティブ・シティ
仙波──いまのお話をプラネタリー・アーバニゼーションやプラネタリー・ジェントリフィケーションに絡めて言うと、ひとつはクリエイティブ・シティとかスマート・シティを推進する施策がはらんでいる問題で、そこに付随する問題系のひとつは「地域アート」の存在だと思います。文芸評論家の藤田直哉さんによる『地域アート──美学/制度/日本』(堀之内出版、2016)など、地域アートの問題を扱った本はあり、「10+1 website」での対談(星野太+藤田直哉「まちづくりと『地域アート』──『関係性の美学』の日本的文脈」)も再録されている。ここで藤田さんをはじめ掲げられている課題は、都市研究においても共有可能なものです。端的にアートが排除の道具に活用されるなかで、自治体や財団などが奨励するアートが「社会的課題」の解決策に位置づけられる。そもそもそれがアートなのか、と問うたのが上記の著作であるとすれば、都市研究の側からは、まさに「クリエイティブ・シティ化」の道具としてアートが文字通り「活用」されている現状を指摘できるでしょう。もちろんすべての事例がそうでないにせよ、地域アートをはじめとするなんらかの活動は、住民と軋轢を生む可能性をはらんでいる。極論を言えば、その地域の「ために」アートをやっているのに、地域の人々との断絶のうえに立ってクリエイティブ・シティやスマート・シティといった「排除」をともなう都市像の完成に寄与しようとしている。シンガポールの街を歩けば、POPS(Privately Owned Public Space)のうえに、有名無名を問わないアーティストの多くの作品を見ることができる。作品がそこにあり、そこに人がいることは許されないわけです。
実際に日本で、課題解決の道具として自身の「スキル」を位置づけるアーティストのプレゼンテーションを聞いたこともあります。往々にして、コミュニティとの関係構築をひとつの命題とする都市研究の領野で、こうした地域アートの機能、そして逆機能を考える喫緊の必要性がある。デヴィッド・グレーバーの官僚制の話のように、地域にどう貢献したかを書類に書いて、文化庁に紐づいたアート振興組織に提出するためのマニュアル本が書店の「美術」棚の一角を占めている。
繰り返しますが、こうした状況がすべてであるとはまったく思いません。先にも登場してもらったChim↑Pomの水野さんとは、普段どうしようもない話しかしていませんが、彼が基町ショッピングセンターで営む「オルタナティブ スペースコア」は名前の示す通り、地域とアートの異なる関係性を見出そうとしている。この前「いらっしゃいませ」の声が聞こえないと近所のスナックのママに怒られていましたが(笑)。しかし、都市の「非場所性」を促進する顔をもつ「道具」としての「地域アート」という問題系は、中央──地方を超えて、果ては惑星規模で見られる現象だと思います。都市研究はこうした事態と、どのように対峙することができるのか。
編集──リチャード・フロリダなどによる「クリエイティブ」な地域戦略モデルが20世紀末から10年くらいのあいだに一気に内面化されたわけですね。
仙波──需要側から見るとそうなのですが、じつはフロリダ自身『The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It』(Basic Book、2017)という比較的新しい本のなかで、自分がかつて提唱したクリエイティブ・クラスの集中による都市成長が、翻って社会的不平等とセグリゲーションを促進している事実を認めています。邦訳が去年出たネイトー・トンプソン『文化戦争──やわらかいプロパガンダがあなたを支配する』(大沢章子訳、春秋社、2018)という本でも、フロリダの提言に対する批判が書かれていました。また、例えばその名の通り『City Branding』(Routledge、2018)という著作で有名な政治経済地理学者アルベルト・ヴァノーロも、ニューキャッスル大学の社会学教授、ロバート・オランズの議論を引き継ぎながら、やはりフロリダ以降の戦略モデルである「スマート・シティ」政策を批判しています。他方、日本ではジェントリフィケーションに関する議論は比較的盛況な一方で、こうした政策に対する批判的検討は必ずしも多くない。この点はわれわれもさらに議論を重ねていきたいポイントです。
「プラネタリー」という形容が意味するもの
仙波──少なくとも著作としての『Planetary Gentrification』に限って言えば、ここでの「Planetary」は、G・C・スピヴァクの『ある学問の死──惑星思考の比較文学へ』(上村忠男+鈴木聡訳、みすず書房、2004)から採られていると結論部で記されていますね。「わたしは惑星(planet)という言葉を地球(globe)という言葉への重ね書きとして提案する」。この文章が引用されています。
平田──プラネタリー・アーバニゼーションのほうは、ルフェーヴルを参照していますが、より細かく言えば、独裁政権時代のギリシャからフランスに亡命して後、フランスでのハイデガー受容に貢献し、『遊星的思考へ』(高橋允昭訳、白水社、2002/原著=1964)の著者でもあるコスタ・アクセロスがルフェーヴルに着想を与えているのだと思います。
仙波──ただ、先述のアナンヤ・ロイなどはディペッシュ・チャクラバルティなどとともにかなりスピヴァクに依拠していて、そのあたりはつながっている感じがします。そして「惑星思考」のもと、彼女が繰り返し述べているのは、いまわれわれが自明視しているような境界をいかに逸脱するのか、いかに侵犯する(transgress)のかということです。これは先に述べたマッシーの議論に通ずるものがありますし、同様にボーダー・スタディーズの姿勢とも近い。くわえて、「私/あなた」あるいは「私たち/あなたたち/彼ら」というボーダーとして考えるなら、フィルターバブルの問題、それが提起する「プライベート/パブリック」の分割線を問うことともつながってきます。僕がいままで考えてきた「平和都市」をここに並べてもいい。「平和都市」というのはひとつの境界である。境界線が引かれる。そこには「周辺」という一言では片づけられないようなボーダーがある。カナダの人文地理学者の重鎮であるロブ・シールズも、チャールズ・ライト・ミルズの『社会学的想像力』(伊奈正人+中村好孝訳、ちくま学芸文庫、2017/原著=1959)をトポロジカルに読み替える試みのなかで、空間的差異と社会的不平等を示す事例としての「境界」を、姿勢のみならず知覚も変容してきたその過程を明るみに出すものであると位置づけています(「Expanding the Borders of The Sociological Imagination」2017)。
他方、スピヴァク自身がこの議論をその後うまく展開できたかというと微妙で、シールズのようにより空間の議論として捉え返すとするならば、引かれた線をいかに多面的に読み直すことができるのか、といった試みとしてプラネタリー・アーバニゼーションは位置づけられるのではないでしょうか。なぜならそれはプロセスであり、関係論的なものとして構成されているのだから。過去や歴史をどのようにすれば水平的な問題──遷移するもの、侵犯するもの──として捉え返すことができるのか。プラネタリー・アーバニゼーションはその有効な視点を提供するものとして考えられるのではないか。
その問題系自体は空間的なフィールドだけではなくて、まさにディシプリンの問題としてもあるのではないかというのが、私たちが行なっているプロジェクトの暫定的な結論のひとつです。つまり、地理学という境界を、より自由に「侵犯」してもいいのではないか。地理学を建築学や都市計画学として考えてもいいのではないか。さまざまな学知の知見を持ち寄る学際的・複合的(interdisciplinary)なやり方とは異なった、より開けっ広げに「遷移」「侵犯」していくような都市の見方が必要なのではないか。そのうちのひとつの試みが、私たちの考えるプラネタリー・アーバニゼーションのあり方なのではないかと思います。
平田──すでにきれいにオチがついたと思いますが、あえてここまでしてきた話をまとめれば、そもそもなぜ2回にわたって「10+1 website」でプラネタリー・アーバニゼーションを特集したのか、またそれがどういった議論を呼び込み、考えさせるのかということをめぐるものでもあったと思います。暴力的に要約すれば、プラネタリー・アーバニゼーション研究は、これまでの都市研究の限界を指摘し、日常生活のスケールやグローバルなスケールを含めマルチスケールに都市化を分析しようとするものです。このようなスケール横断的な分析は、都市というものがそれだけで成立せず、その外部にある関係性によってもかたちづくられたものであることを示します。こうしたスケール横断的な観点から2回の特集の内容を3つのポイントに集約できると思います。
第1に、仙波さんが広島研究のなかで直面したように、ある都市はどれだけその対象を知っていても、そこだけでは理解できない部分があるということです。そこから、仙波さんが参照されたロイを代表とするポストコロニアル都市研究で問われる、都市や場所と呼ばれるものの固有性と一般性・普遍性が切り結ばれる場面が現われます。この問いかけこそまさしく都市研究総体に関わる理論的な問題でしょう。その問いに賭けられているのは広島というひとつの都市を通して、既存の総称としての都市の理解を刷新するような広い地平に接続することなのだと思います。
第2に、ジェントリフィケーションやクリエイティブ・シティ化というローカルなレベルでの都市開発がグローバルなスケールでの都市間競争の圧力と切っても切り離せないものであることを理解させてくれます。この点は、「10+1 website」2018年11月号に寄せられたプラネタリー・ジェントリフィケーションに関する荒又美陽さんの論考(「ジェントリフィケーションをめぐるプラネタリーな想像力」)が明快に論じています。荒又さんは冒頭でジェントリフィケーションという言葉のポジティブな使用を一蹴したうえで、この言葉が、安全・多様性・創造性にそれぞれ関わるゼロ・トレランス、ミックス・コミュニティ、クリエイティブ・シティといったポジティブなフレーズによって日常生活に浸透し、低所得者層やホームレスを排除するものだと論じます。そしてこのようなジェントリフィケーションは単に世界の各地で起きているというだけでなく、まさに地球規模のひとつの過程として生じているということを強調します。
第3に、地球全体にフローの連続性を確立するロジスティックスの論理とその物質的基盤であるインフラストラクチャーが重要な考察対象となります。それは、ジェントリファイされた都市やスマート・シティの生活を物質的に支えながらも、その外にある後背地です。この点については、すでにこの対談でも触れた「10+1 website」2018年11月号の北川論考と本号の原口論考が濃密かつ有益な論点を与えてくれます。前者の論考では、ミラノの後背地であるローを事例として、交通インフラにアクセスできず、「軌道の保有者」としてのモビリティを失うことで、見捨てられ、その地に閉じ込められる町が論じられています。ルフェーヴルは『空間の生産』の第4版に付されたテクスト(1984)のなかで、空間の生産過程を単線的なものではなく、3つの相反する過程──均質化、断片化、階層化──が絡み合ったものとして論じていますが、北川さんが書かれるように、広範囲の都市化は、「一様な過程」ではなく、「地理的にきわめて不均等な発展過程」なのであって、それによって「無数の高速回廊、無数の飛び地、無数のゾーン、無数の境界」が生み出されるのです。
インフラストラクチャーとロジスティックスはこのような地理的分断線を走らせているだけではありません。原口論文が示すように、ロジスティクスの論理が都市空間に適用されることで、労働者の集合的な身体は破砕され、個々の身体はバラバラのままシームレスなフローの連続性に徹底的に服従させられるのです。それゆえ、「ロジスティクスは、失業と低賃金を押し広げただけでなく、かつてないほど世界を不透明なものにした」と原口さんは書くわけですが、この話は「プライベート化」の進展とどこか通じるところがあります。
ということで、これまで話してきたように、必ずしも専門的対象や政治的立場を同じくするわけではない複数の論者が「プラネタリー・アーバニゼーション」から複数の線を描き出すことができたということ、それ自体に2回の特集の1つの意味があるのではないかと思います。その意味は、読者のそれぞれの観点から付け加えたり膨らませたりすることができるものです。一紹介者としての願いを言えば、使えるところは使うもよし、けなすもよし、思いもよらない生産的なかたちで好き勝手に使ってもらえればと思います。ブレナーらもそう願っていると思いますし、一般的に理論的道具の紹介者が必ずしもその道具の使い方を知っているとは限らないですからね。
最後に個人的なことをお話しさせていただくと、私は思想史を専門として、アームチェア学者と罵られようともテキストを前にしていかに椅子に座っていられるかで勝負しているつもりですが、正直、フィールドを有し、そこから固有の知や経験を引き出すことを生業とする人に強い羨望の念を持っています。それゆえ今日は広島を事例として若くして優れた業績を出されている仙波さんからなぜ理論が必要なのかを聞けてよかったです。その話のなかで具体的な接点が与えられることで励まされたり、新たな課題を見つけられたりした気がします。仙波さん、そして、今回2回にわたって議論の場を与えてくださった「10+1 website」の編集者の方にも感謝の意を述べさせていただきたいと思います。
[2019年4月19日、東京にて]
平田周(ひらた・しゅう)
1981年生まれ。思想史。パリ第8大学博士課程修了。博士(哲学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、南山大学外国語学部フランス学科准教授。主な論文=「人間主義論争再訪──アルチュセールとルフェーヴルの理論と実践における人間の位置」(『相関社会科学』第21号、2012)、「ニコス・プーランザスとアンリ・ルフェーヴル──1970年代フランスの国家論の回顧と展望」(『社会思想史研究』第37号、2013)など。共訳=クロード・ルフォール『民主主義の発明』(勁草書房、2017)など。
仙波希望(せんば・のぞむ)
1987年生まれ。都市研究、カルチュラル・スタディーズ。博士(学術)。広島文教大学人間科学部専任講師。主な著書=『忘却の記憶』(共著、月曜社、2018)など。主な論文=「『平和都市』の『原爆スラム』──戦後広島復興期における相生通りの生成と消滅に着目して」(『日本都市社会学会年報』第34号、2016)、「日々の喪失、平和の喧伝──相生通りと動員される『平和都市』」(『現代思想』2016年8月号、青土社)など。
- ルフェーヴルから辿れるもの、切り開かれるもの/進行形の都市研究を立ち上げる
- 現代の地理学的な問題系/「広範囲の都市化」とロジスティックス──なぜ広島研究で理論が必要なのか
- ジェントリフィケーションが示唆するもの/「プライベート化」の進展/ジェントリフィケーションとクリエイティブ・シティ/「プラネタリー」という形容が意味するもの