堕落に抗する力
──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか
──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか
2018年は、1968年から50年という区切りの年だった(また明治150年という年でもあり、反体制の嵐が吹き荒れた1968年が明治100年だったという事実は、改めて興味深い)。千葉市立美術館では展覧会「1968年 激動の時代の芸術」が開催され、400点におよぶ当時の作品や資料が展示されていた★1。作品のみならず、チラシや印刷物などエフェメラ資料も多く展示されており、当時の問題意識が現在に続くものとして感じられた。筆者は、千円札裁判と「反戦と解放展」をめぐる展示に特に興味を惹かれた。「反戦と解放展」は、ベトナム反戦を掲げて針生一郎が呼びかけたもので、作品販売の収益を医療品購入費としてベトナムに送った。これに対して赤瀬川原平や石子順造らは、「戦後市民民主主義者の自慰運動」などとこの「固型した芸術」によるチャリティー展の批判を行った。展覧会ではこれを千円札裁判をめぐる議論の延長に位置づけている。この芸術と政治をめぐる問いは、3.11に対する態度をめぐって多くの芸術家や建築家が直面し、考えなくてはならなかった問題ではなかったか。展示においては直接に現在と展示内容を結びつけることはされていないが、50年を経て当時の資料の整理と研究が行われるようになり、現在の視点から現代史における意味を問い直すことが可能になってきているように思う。
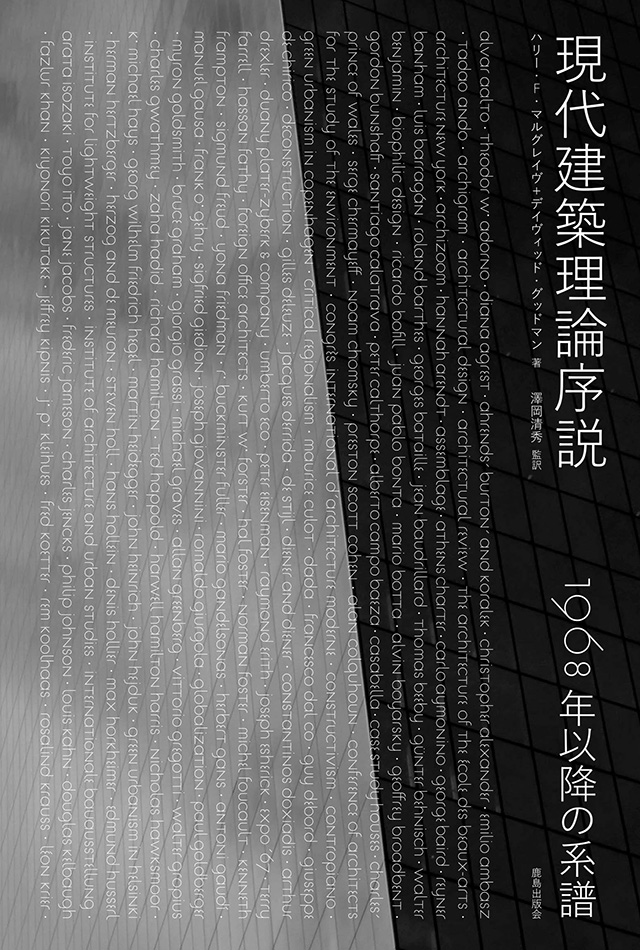
- ハリー・マルグレイヴ
+デイヴィッド・グッドマン
『現代建築理論序説──1968年以降の系譜』
(澤岡清秀監訳、鹿島出版会、2018)
この節目の年に翻訳が刊行されたハリー・フランシス・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説──1968年以降の系譜』(澤岡清秀監訳、鹿島出版会)も、1968年を境にしてそれ以降の建築理論史を概観している。マルグレイヴはこの前著にあたる『近代建築理論全史 1673-1968』(加藤耕一監訳、丸善出版、2016)において、この年を建築理論が揺さぶりをかけられた年だと位置づけて区切っている。マルグレイヴによれば1960年代後半は、50年代から60年代初頭にかけて炸裂した建築理論領域のエネルギーが雲散霧消してしまった時期であり、1968年は感情、精神、知を消耗した年だという。磯崎新は『建築の解体』において、60年代に頭角を現した建築家たちの紹介と分析を行っている★2。そして不確定なものとしながらも、彼らの特徴を「《建築の解体》症候群」と名付けて整理しており、その最初には「アパシィ」が挙げられていた。そしてクリストファー・アレグザンダーから「革命はとっくに終わっている」という言葉が引かれる。この認識は、大きくはマルグレイヴと一致している。
本書でマルグレイヴとグッドマンは、そのような60年代を起点に、ポストモダニズム、批判的地域主義、ポスト構造主義、デコンストラクションから90年代以降のミニマリズム的傾向、生物学や神経学からの影響といったところまで、現代思想や社会状況との関わりにも触れながら、主にアメリカにおける視点から建築理論史を整理している。ときには演繹的に具体的な建築家とその作品にも言及されている。示されている引用元にあたればより深くその時代や思想を学ぶこともできるだろうから、帯が謳うように格好の「入門書」だろう。
建築史や理論史の詳細について述べることはできないが、筆者の職務上の関心から本書を読んで改めて認識したのが、ここで解説されている建築理論史上、展覧会が重要な役割を果たしていることである。ピーター・アイゼンマンが指揮した「ファイヴ・アーキテクツ」展(MoMA、1969)やアーサー・ドレクスラー企画の「エコール・デ・ボザールの建築」展(MoMA、1975)は、ホワイト派とグレイ派の対抗の文脈で語られる。アルド・ロッシがキュレーターを務めた第15回ミラノ・トリエンナーレ(1973)は新しい合理主義運動の始まり、パオロ・ポルトゲージがキュレーターを務めたヴェネツィア・ビエンナーレ(1980)はポストモダンの輝かしい到達点とされ、フィリップ・ジョンソンがキュレーターとして復帰した「デコンストラクティヴィスト建築」展(MoMA、1988)は、「知的な承認欲求」が露わとなったアメリカの建築理論の象徴として取りあげられている。
これは日本における建築展が新しい言説を生み出したり議論の契機とはなりにくいのとは、対照的である。日本における展覧会が概して啓蒙的・解説的な傾向があるのに対して、これらの展覧会は非常に戦略的で、企画者の理論補強の手段となっているようにさえ見える。もちろん明確なビジョンを示すのがキュレーターの仕事だから、理論補強というよりは、理論そのものを提示する場として展覧会があるのだろう。これに対する日本の状況についてはしかし、単にキュレーションの不在や日本人特有の議論を厭う傾向といった説明だけで整理できるものではないだろう。2018年11月に行われた公開討論「批評の在り処」において、藤原徹平は日本の展覧会におけるキュレーションの難しさの原因として「座標がないこと」を挙げている★3。
同じく11月に行われたパネル・ディスカッション「拡張する現代美術と変わる美術館」において、MoMA館長であるグレン・ラウリィが「政治色のない美術館はない」と述べ、「自分たちのモラルに基づき行動しなければならない」と語っていたのは示唆に富む★4。もちろん政治的なメッセージを出せばよいというものではないし、MoMAは私立財団だから自由なことができるのだという意見もあるだろう。しかし、同ディスカッションでは国立機関であるテート・モダンがアイ・ウェイウェイ釈放のためのメッセージを発信したことも紹介されており、いずれにしても芸術文化の自律性が強く意識された発言だと思われる。日本とは美術館の機構が違うため同じように扱うことはできないだろうが、展覧会を開く組織自体が座標を持ち得るかということも問題となる。
筆者が職務で整理を行っている建築アーカイブズ自体は「座標」にはなり得ないが、アーカイブズを用いて座標を示すことは可能なはずである。日本において批評の土台となるべき座標を持つためにアーカイブズに関わる者ができることは、まずは知られざる資料をとにかく探し出し、なるべく多く公の場に引っ張り出すことから始まるのだろう。
『現代建築理論序説』に戻ると、前著が「全史」であるのに対してこれは「序説」であり、これから現代建築理論史を検討するための座標を用意してくれたといえる。
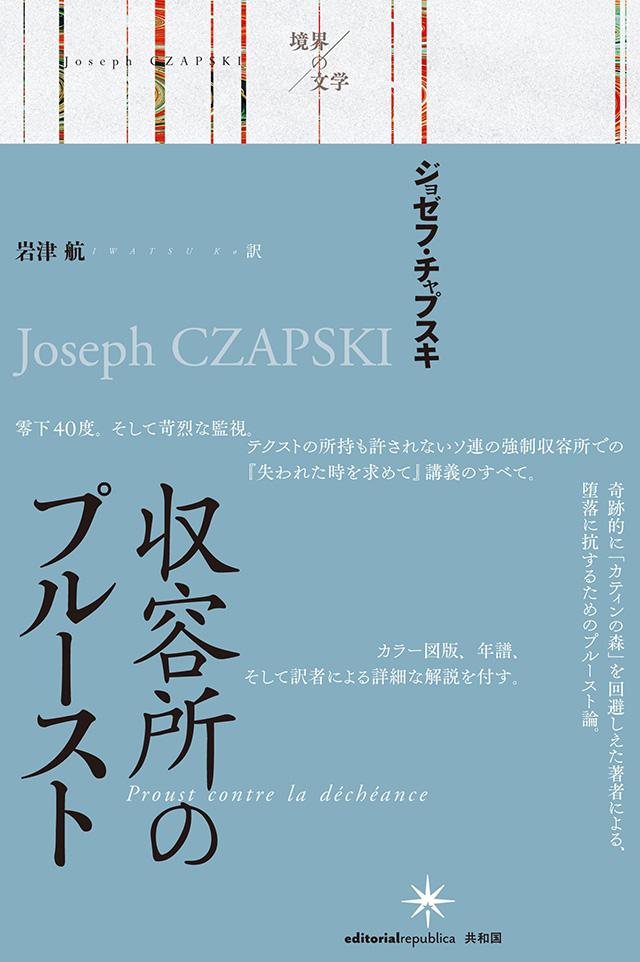
- ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』
(岩津航訳、共和国、2018)
歴史上の特異な状況下における、芸術の力を感じる感動的な一冊が、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』(岩津航訳、共和国、2018)だ。これは、ポーランド軍将校であったチャプスキ(1896-1993)が1939年にソ連軍に捕らえられ、グリャーゾヴェッツ捕虜収容所に収容されていた間に行った、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』についての講義を元に書かれた本である。講義が行われたのは1940年から41年の冬のあいだで、零下45度に達する極寒のなかでの労働のあとだったという。グリャーゾヴェッツの前に収容されていたスタロビエルスク収容所の同房者たち4千人は、ほぼ全員が「カティンの森事件」(ソ連による、指導的立場にあるポーランド将校ら2万5千人の虐殺事件)の犠牲者となった。著者は奇跡的な生き残りである。
本書にはグリャーゾヴェッツ収容所内で記されたと思しき手書きのノートから21の図版が収録されており、そのうち6葉分は日本語訳も付されている。ノートの表紙に描かれた四つ葉のクローバーと思しき図像は、あらゆる物理的・精神的苦境から精神を護ってくれる幸運のお守りとして、チャプスキがこのノートを抱えていたというしるしだろうか。プルーストは、忘れられ手つかずで閉じ込められていたがゆえに、当時のまま鮮やかに蘇る記憶について、誰にも開かれないまま図書館に保管されている本を比喩に描写している(アーカイブのことのようでもある)。時空間の制約を超えて記憶を呼び起こすこと、そのなかに生のきらめきを見出すこと、本に耽溺していた経験を過酷な状況下の自分のなかにそのままの形で見出したことは、どれだけ彼を勇気づけただろうか。講義のために記憶のなかにある言葉をノートに書きつけていくことは、具体的な救いであり、ぎりぎりの境界で自我を保つための創造行為であったと想像できる。
グリャーゾヴェッツ収容所では、建築の講義も行われていたという。現代において私たちが必要としている芸術、「生き延びさせてくれる芸術」とはどのようなものなのだろう。極限状態に置かれたときに、支えとなる芸術文化を持っているだろうか。チャプスキの置かれたような状況は、現在のわれわれにとっては考え難いかもしれないが、どのような社会状況であっても生き延びさせてくれる芸術は可能だと、考えられるだろうか。
この本の原題を直訳すると『堕落に抗するプルースト』だという。この「堕落」とはどういう意味だろう。訳者の岩津航は、チャプスキのパスカル的解釈をもって解説しているが、筆者には精神の衰弱と絶望に抗する、ということではないかと思われる。そう考えたときに、現代に生きる私たちにもこの言葉が切実さをもって迫ってこないだろうか。

- プルースト『失われた時を求めて』13巻
(吉川一義訳、岩波文庫、2018)
日本でも数多くの翻訳と研究が行われてきた『失われた時を求めて』だが、現在岩波書店より新訳が刊行中である。2018年12月に13巻が出版され、残すはあと1巻となった。
新訳の翻訳者、吉川一義はプルーストにおける絵画・草稿研究を行っており、注釈と図版が丁寧で充実している。図版は、できる限りプルースト自身が目にしていた当時の刊行物から取られているという。プルーストの教養とその背後にある広大な文化の一端を知る補助になってくれる。
プルーストのテキストを読むと、虚弱で花粉アレルギーを持ち、少食だった人とは思えないほど、植物や食べものの表現は豊かで官能的である。特に1巻はさまざまな植物の香りにあふれており、部屋の雰囲気まるごとをパイ「ショーソン」に、鐘楼を焼き上がったブリオッシュに例えるなどの比喩の多彩さを見ると、どれだけ食いしん坊なのかと思いそうになる。しかしこれらは物理的な物に対する嗅覚・味覚というより、観念上の官能だろう。『草枕』で夏目漱石が書いた、「玉と蝋石の雑種のようで、青磁から生まれたような、撫でてみたくなるつやつやした羊羹」に感じる、実際の羊羹を口にした時にはとても覚えることのできない甘美さと同様である(そういえば、漱石は1867年生まれ、1871年生まれのプルーストと同世代だ)。
プルーストはジョン・ラスキンに大きな影響を受け、その翻訳に詳しい注解をつけて出版している。文中で教会建築や装飾に触れることも多いが、その描写の主眼は、建物を経験することそのものにあるようである。主人公の空間経験に関する描写はこの小説の随所に見られ、どれも興味深い。友人のサン=ルーを訪ねたドンシエールで滞在することになるホテルでは、廊下が行ったり来たりしたかと思えば、玄関がお伴を申し出て、小さな部屋が大きなサロンに駆け寄ったり、驚いて散りぢりに庭のほうに逃げ出したりする。寝室の壁は部屋を抱きしめるようにとり囲み、身をひいて書棚の場所を空けたり、ベッドを置くへこみを確保したりする★5。空間は自在に伸縮し、時間は緊結されたかと思えば分断する。
1922年に亡くなったプルーストが、近代建築についてどのような見解を持ったであろうかは知る由もないが、おもしろい描写がある。主人公が滞在する避暑地バルベックの高級ホテルのメインダイニングルームは大きなガラス張りで、海岸に向かって開かれている。ちょうど最新技術として電気が導入された頃で、夜になるとダイニングルームは光で溢れ、「巨大な魔法の水槽」となる。そのすぐ外の闇には工場労働者や漁師が集まって、ガラスの内側の贅沢な暮らしをのぞき見ている。このガラスの仕切りがいつまで内側の生活を守ることができるのか、外の連中が中の人々を自分たちの水槽に移して食べてしまうのではないか、とプルーストは書く★6。モダニズム建築の均質空間を予感しているようだ。『失われた時を求めて』には、時に文明批評のような鋭い考察も混じっている。
『失われた時を求めて』はきわめて批評的な作品である。音楽に始まり演劇、絵画等のあらゆる芸術とともに、社交界を描くことを通じて人間そのものをも対象としている。プルーストは、繊細かつ執拗な感覚と同時に異様なほど醒めた分析力でもって、ありとあらゆるものを批評する。そしてその奥にある何かに迫ろうとしている。
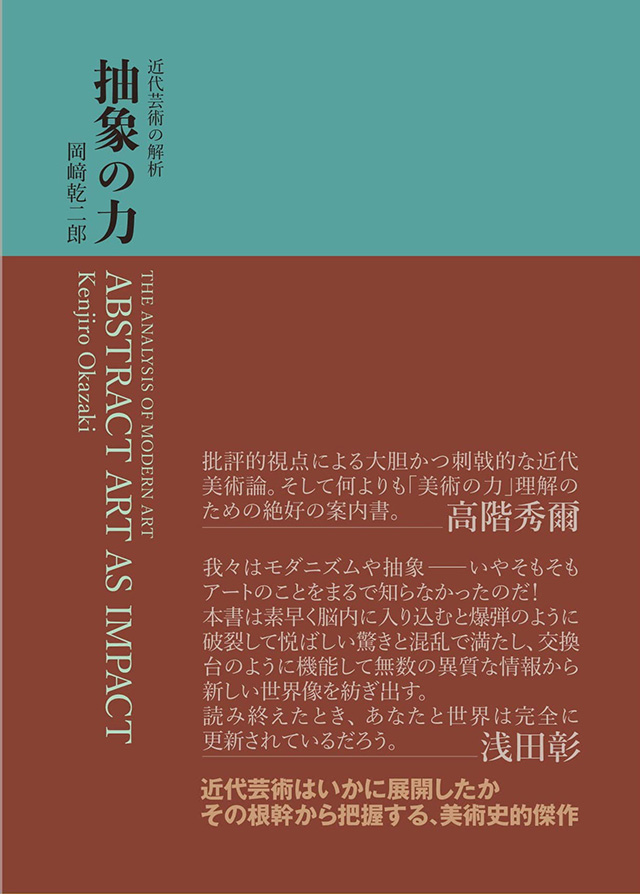
- 岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』
(亜紀書房、2018)
岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』(亜紀書房、2018)は、2017年に豊田市美術館で行われた同名の展覧会の図録に掲載された論考(大幅に加筆修正)を中心に構成されている。本書を開き、展覧会を観た際の高揚を改めて感じた。「抽象の力」において岡﨑は、漱石の「f+F」の理論を基点に、日本の芸術家たちの仕事を世界の同時代の作家と並行させながら、抽象芸術の系譜を縦横無尽に描き出す。時代で考えれば、プルーストもチャプスキもこの系譜に伴走していることになる。抽象芸術の核心として一貫して論じられているのが、「見える姿としては代表し表現することのできない」「潜在的な領域」を把握する力である。そうした芸術家たちの仕事の例として、岡﨑は生涯海外に出たことのない熊谷守一を挙げ、アンリ・マティスやミルトン・エイヴリー、ヴァネッサ・ベルといった同時代の作家との共時性を論じている。距離を持ちながら共振し合い、同期し、同じ場所を形成する共時性こそが世界性だという。これは、芸術作品の潜在的構造、可能性が場所に限定されず開かれたものであったことを示すのだと。
チャプスキは、モーリス・バレスの「芸術家たる者はなによりも祖国の栄光のために奉仕すべき」という主張に対する「芸術家は(中略)科学上の法則や実験や発見と同じように(中略)目の前にある真実以外のことは──たとえ祖国のことであれ──考えないという条件でしか、祖国に奉仕できない」という反論に、プルーストの芸術に対する姿勢を見ている★7。芸術における真実は、国家の枠組みに先んじる。チャプスキは講義において、トルストイやドストエフスキーなどの、自分たちを捕らえているいわば敵国の作家も積極的に取りあげている。それは彼らにプルーストと共通する思考を見出しているからにほかならない。
プルーストとチャプスキは同時代人ではないし、画家でもあったチャプスキの仕事は岡﨑の抽象の系譜には入っていない。しかし、プルーストの探求は漱石の問題意識と通じているように感じられてならないし、チャプスキもその核心を捉えていた。時代を超えて共有され引き継がれる彼らの思考もまた、「堕落に抗する」「抽象の力」と言えないか。
★1──「1968年──激動の時代の芸術」(千葉市美術館=2018.9.19-11.11、北九州市立美術館=2018.12.1-2019.1.27、静岡県立美術館=2019.2.10-3.24)
★2──「建築の解体」は1969年12月から1971年10月、「《建築の解体》症候群」は1973年8月から11月に『美術手帖』誌上に連載、1975年に美術出版社より出版された。
★3──「公開討論1『建築の論点』──批評に必要な座標とリスペクト」(『建築ジャーナル』2018年12月号)p.6
★4──パネル・ディスカッション「拡張する現代美術と変わる美術館」(開催=アカデミーヒルズ、2018年11月4日)参照=https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/18836
★5──『失われた時を求めて 5 ゲルマントのほうⅠ』(吉川一義訳、岩波文庫、2013)pp.175-178
★6──『失われた時を求めて 4 花咲く乙女たちのかげにⅡ』(吉川一義訳、岩波文庫、2012)p.104
★7──『失われた時を求めて 13 見出された時Ⅰ』(吉川一義訳、岩波文庫、2018)p.475
藤本貴子(ふじもと・たかこ)
1981年生まれ。国立近現代建築資料館建築資料調査官。慶應義塾大学総合政策学部卒業。磯崎新アトリエ勤務のち、文化庁新進芸術家海外研修員として建築アーカイブの研修・調査を行う。2014年10月より国立近現代建築資料館勤務。
201901
特集 ブック・レビュー 2019
1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見 ──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか
谺(こだま)するかたち ──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』
現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか
ゲノム編集・AI・ドローン ──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか
「建築の問題」を(再び)考えるために──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか
あいだの世界──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか
モノ=作品はいま、どこにあるのか──『デュシャン』、ジョージ・クブラー『時のかたち』ほか
堕落に抗する力──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか
オブジェクトと建築 ──千葉雅也『意味がない無意味』、Graham Harman『Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything』


