「建築の問題」を(再び)考えるために
──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか
──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか
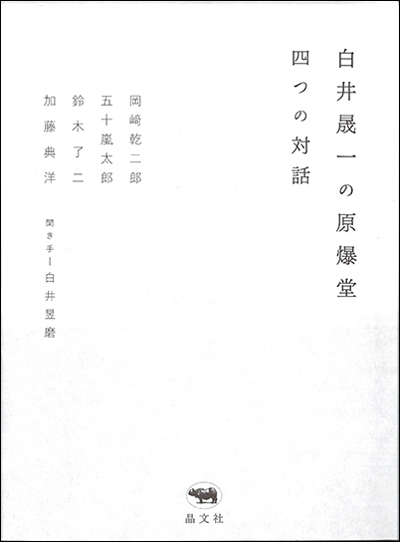
- 五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂
──四つの対話』(晶文社、2018)
白井晟一《原爆堂》は、戦後の日本建築史のアイコンとなっている。「メタボリズムの未来都市」展(2011-12)でも、「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」展(2014-15)でも、さながら戦後建築史のパースペクティブを描くための消失点のひとつであるかのように展示されていた。けれども、白井の論じられ方は相対的なものにとどまってきたようにも思われる。弥生に対する縄文。広島平和記念公園に対する《原爆堂》。正統に対する異端等々。戦後建築史の風景のなかに白井の《原爆堂》が置かれるとき、戦後復興・高度経済成長という光のなかに留まる陰というような、光をあてる側からの、どこか言い訳めいたニュアンスが感じられはしなかっただろうか。《原爆堂》の問いとははたしてなになのか。わたしが近年関心をもっている建築の記念性(記憶、記録)の問題からも、白井は当然気になる存在だ★1。
「白井晟一の『原爆堂』展 新たな対話にむけて」(Gallery 5610、2018)に合わせて出版された『白井晟一の原爆堂──四つの対話』(晶文社、2018)は、白井昱磨氏によるテキストに続いて、岡﨑乾二郎、五十嵐太郎、鈴木了二、加藤典洋の四氏に話を聞く。
岡﨑乾二郎「建築の覚悟」は、これも今年出版された『抽象の力──近代芸術の解析』のなかで氏が展開した白井論を、改めて岡﨑氏自身の個人史も織り交ぜながら語り下ろしていく。これについては後で戻ろう。
五十嵐太郎「社会と建築家の関係」は、白井の属した時代と社会の構図を的確に整理し、現在の問題へ接続していく。個人的には、近代建築史の記述からこぼれ落ちる宗教建築の話からはじまり、原発のモニュメント化計画である自身の卒業設計を経て、さまざまなメモリアルの具体的なデザイン分析に及ぶ断章に刺激を受けた★2。
鈴木了二「建築が批評であるとき」は、近年の「物質試行」であるDUB HOUSE、とくに東日本大震災・福島第一原発事故後に発表した「フィガロ計画」と、随伴するテキスト「『建屋』と瓦礫と」★3のなかに、白井晟一の共鳴を聞く。鈴木は、白井においては創造すなわち破壊であり、反対物が表裏一体となって背中合わせになっていると指摘する。鈴木はこれを、1982年のテキスト「一冊の白いパンフレット」★4のなかで──《原爆堂計画》透視図の天地をひっくりかえして!──「原爆的対称性」と呼んだ。このような白井建築のもつ複合性あるいは両義性は、次の加藤の論とも繋がっていく。
加藤典洋「未来と始原の同時探求」もまた、白井の建築とその論の本質を指摘して、異なるふたつのもののいずれかにではなく、両者の同時並立にあるとする。弥生と縄文、理念と現実といった二層構造のなかでのふたつのせめぎあいとしての建築。加藤はここで、東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』(2017)のなかに、現代人の生の基本的な条件としての二層性が指摘されているというのだが、近年多領域で研究が展開されている慰霊や記憶というテーマにおいても、持続的に批評の場を守ってきたのが東浩紀である。チェルノブイリや福島など、記念と記憶の場を巡る移動と思索を通じて『ゲンロン2』(特集「慰霊の空間」、2016)や『ゲンロン0 観光客の哲学』が世に出された。2018年の最後にも、東は6ページの短いテキスト「悪と記念碑の問題」(『新潮』2019年1月号)のなかで、自らの原点にまで立ち返って、記憶の装置であるとともに忘却の装置でもある記念碑の逆説について記している。
東のいう記録と記憶を巡る記念碑の逆説とは、物質と精神を巡る逆説であろう。東の短いテキストに触れ、改めて岡﨑乾二郎「建築の覚悟」に戻るとき、「人がふと集まって祈り始めるならば」(p.66)そこが教会であり、「カタストロフを外在化して記念碑として留めることではなく、内在化させることと『原爆堂計画』、親和銀行の思想とは繋がっています」(p.80)という言葉に胸を衝かれる。
共同体のなかでなされる記念に対して、祈りは個人のなかにあり続けるものだ。記念の共同性と祈念の個別性がどのようにしてひとつの空間において可能なのかという問いがそこにはあるのではないだろうか。
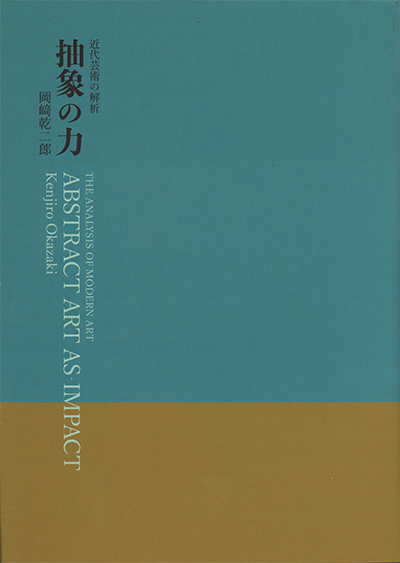
- 岡﨑乾二郎『抽象の力
──近代芸術の解析』(亜紀書房、2018)
原爆的対称性、現代の生の条件としての二層性、あるいは記念碑の逆説。このような問題群のなかにある白井晟一を本格的に論じたのが岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』(亜紀書房、2018)所収の白井論「白井晟一という問題群」3編だ。
岡﨑は、白井晟一を人的ネットワークと世界的な同時代性のなかに位置づけていく。たとえば中谷治宇二郎の縄文研究と同時代のパリにいたイサム・ノグチ、岡本太郎。「豆腐」のようなテキストも、戸坂潤、武谷三男らの科学技術論を下敷きに分析され、続くテキスト「めし」には賀川豊彦のキリスト教社会思想との共鳴が聞き取られる。テキストの読解だけでなく、岡﨑の真骨頂は具体的な作品分析においてあらわれる。《原爆堂》から《親和銀行本店》、《懐霄館》、《ノアビル》へと、玄関から内部空間の構成、構造形式から細部のモチーフに至るまで執拗に追求していく。18-19世紀フランスの建築家ジャン=ジャック・ルクー★5を引きながら、建築はさまざまな機関、器官として解釈される。
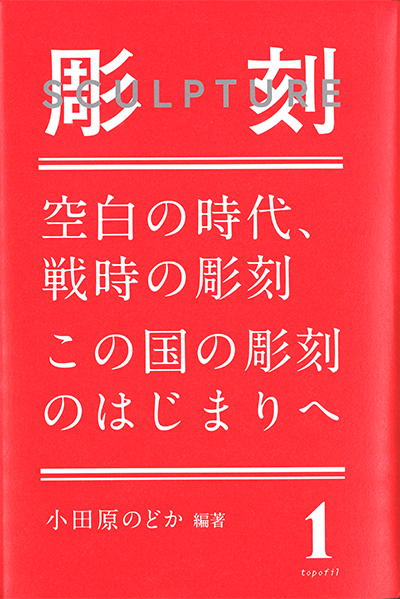
- 小田原のどか編著『彫刻1』
(トポフィル、2018)
その仔細は読書を通じて発見してもらいたい。『白井晟一の原爆堂』のなかの岡﨑の対話では、「白井晟一の問題群」を中心とした『抽象の力』第Ⅲ部「メタボリズム−自然弁証法」だけでなく、第Ⅰ部「抽象の力 本論」で展開されるキュビズム以降の近代芸術史も背景としている。注目したいのは、絵画−平面芸術を中心に展開する第Ⅰ部「抽象の力 本論」に対して、建築をテーマとした第Ⅲ部では彫刻−造形芸術が重要な位置を占めているということだ。そもそも、白井論の前にはイサム・ノグチ論「名を葬る場所」が置かれ、ノグチとジャコメッティの共有した問題群が示される。また『抽象の力』第Ⅲ部に直接の言及はないものの、白井昱磨との対話のなかでは、20世紀の彫刻家として他にヘンリー・ムア、バーバラ・ヘップワース、ジェルメーヌ・リシェらを引き「外側に現れる形への疑いと内臓的なもの、内側に流れる力」(p.64)を捕捉するという課題が20世紀以降の彫刻、なかんずくノグチ、そして白井のあいだにもあったと指摘する。器官的な建築という問題は、「抽象の力 本論」では村山知義、MAVOを通じて、石本喜久治において語られている。ドメスティックな文脈、あるいは建築ジャーナリズムのなかだけでは論じきれない、20世紀芸術の展開のなかに建築が位置づけられる(逆にそのような位置を占めうる建築にしか岡﨑は関心がない)。
補足すれば、彫刻と建築にまたがる問題群としては、たとえば1940年代にギーディオンが、さらに上の世代になるがピカソやレジェの絵画、あるいはブランクーシ、ペヴスナーの彫刻を参照しつつ建築の公共的な記念性について問題化している。彫刻は、建築にとってつねに予言的な先行者であった。彫刻と建築の問題群とは、芸術の問題であるとともに、また公共空間の設計、つまりは共同体の問題でもあったのだ。
彫刻と建築の問題を考えるうえで小田原のどか編著『彫刻1』(トポフィル、2018)も、この年、逸することのできない書物だ。彫刻家であり、長崎をフィールドに研究もする小田原の問題意識は『彫刻の問題』(トポフィル、2017)によく示されている。それを受けて叢書として発刊された『彫刻1』は「空白の時代、戦時の彫刻」と「この国の彫刻のはじまりへ」のふたつの特集からなるいわば歴史編だ。『彫刻2』では、アルトゥーロ・マルティーニ、クレメント・グリンバーグの1940年代後半の彫刻論が掲載されるとのことで、少しずつ20世紀も時代を下っていくようだ。『彫刻1』の特集テーマにかかわる範囲では近代建築史研究が先行していた側面もあり、またそれらを巡る批評もあったはずだが──対話のなかで五十嵐太郎も嘆いているように──今日、それらの歴史から汲み取るべきアクチュアリティへの関心は建築界とそれを取り巻く環境において後退している。様々な問いは建築界の外部においておこる(あるいはすでにおこっている)だろうし、そのときようやく「建築の問題」がはじまるのではないだろうか。★6
註
★1──建築の記念性については下記を参照。
10+1 website 2018年8月号特集「記念空間を考える──長崎、広島、ベルリンから」
10+1 website 2016年3月号特集「建築史の中の戦争」
日本建築学会『建築雑誌』2017年7月号通巻1700号特集「建築は記念する」
★2──小田原氏との対談でも述べたが、建築における記念性の表現は、いくつかの類型においてあらわれる。典型的なのが軸線と塔で、後者は近代主義の建築においてはアーチやシェルによる構造表現に変わった。このような類型化した表現に頼った造形上の記念性ではなく(これをわたしは「記念碑性」と限定したい)、記念性そのものとでもいうようなものを空間や建築の中に触知できないだろうか。
★3──はじめ『みすず』2011年6月号のち『寝そべる建築』(筑摩書房、2014)に収録。
★4──はじめ『白井晟一研究Ⅳ』(南洋堂出版、1982)のち『非建築的考察』(筑摩書房、1988)に収録。
★5──現在パリのプチ・パレで大回顧展が開催中である。「Jean Jacques Lequeu (1757-1826) Bâtisseur de fantasmes」展
★6──2018年は白井晟一について改めて考える年になったが、白井論ばかりを読んでいくと、今度は逆に、そのなかで語られる丹下健三の像が固定化していくようでもある。近年の近代建築史研究として豊川斎赫の充実した成果が続いているが、今年は新たな丹下論が出た。近本洋一「意味の在処──丹下健三と日本近代」(『すばる』2018年9月号)は、大東亜建設記念造営計画、広島、東京カテドラルを順に分析して、最終的に丹下とキリスト教の関係を論じて東京カテドラル聖マリア大聖堂に起こった軸線の「奇跡」へと論を結んでゆく。丹下−カトリックと白井−正教会という構図もさることながら、建築に生ずる意味を論じる二人の著者の方法を分析してみるべきだろう。
戸田穣(とだ・じょう)
1976年生まれ。建築史。博士(工学)。金沢工業大学建築学部建築学科准教授。おもな活動=「紙の上の建築 日本の建築ドローイング1970-1995」展ゲスト・キュレーター(文化庁国立近現代建築資料館、2017-18)ほか。共編著=『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』(鹿島出版会、2017)ほか。
201901
特集 ブック・レビュー 2019
1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見 ──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか
谺(こだま)するかたち ──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』
現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか
ゲノム編集・AI・ドローン ──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか
「建築の問題」を(再び)考えるために──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか
あいだの世界──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか
モノ=作品はいま、どこにあるのか──『デュシャン』、ジョージ・クブラー『時のかたち』ほか
堕落に抗する力──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか
オブジェクトと建築 ──千葉雅也『意味がない無意味』、Graham Harman『Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything』


