ゲノム編集・AI・ドローン
──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか
──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか
2018年11月25日から26日にかけて、中国の研究者が世界で初めてゲノムを編集した赤ちゃんを誕生させたと主張していることが明らかになった。その行為の正当性については、中国の科学者数百人による声明をはじめとして、すぐに多数の疑問と批判が提出されたが、この「臨床研究」の内実に関する詳細な情報はいまだ公表されておらず、関係者をやきもきさせる状態が続いている(件の研究者は論文を発表する予定だという)。
研究者によれば、生まれたのは双子の女児で、HIVに感染しないよう受精卵のDNAを編集したのだという。HIVに感染した男性の精子と、そのパートナーの女性の卵子を体外受精させてできた受精卵の遺伝子の一部を、CRISPR/Cas9(クリスパー/キャスナイン)で編集したとのことだ。CRISPR/Cas9とは、2012年に開発され、すでに各方面で愛用されているゲノム編集の定番ツールである。
この事件の要点は、ジャーナリストの粥川準二が指摘しているように、今回の研究が、社会におけるコンセンサス(中国を含め多くの国では生殖補助手段としての受精卵ゲノム編集は法律で禁止されている)を飛び越えて「遺伝子エンハンスメント人間(デザイナーベビー)」を誕生させてしまったということである。あらかじめHIVに耐性をもつ人間をつくることは、「治療」というより「エンハンスメント(能力強化)」と呼ぶべきものであろう。
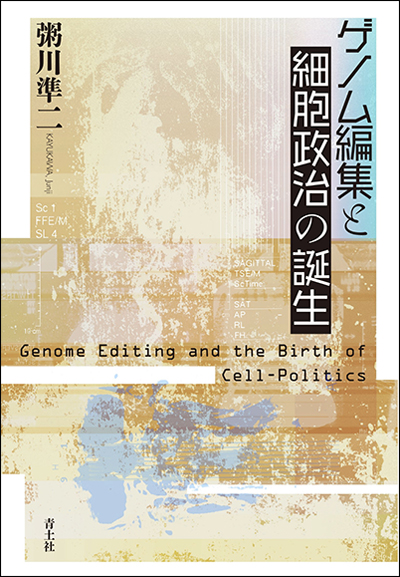
- 粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』
(青土社、2018)
先の粥川が2018年の春に刊行した著作『ゲノム編集と細胞政治の誕生』(青土社)は、この事件の意味をより深く理解し、今後の方針を考えるための材料が詰まった論文集である。遺伝子改変による治療やエンハンスメントという論題には、生命倫理学においてすでに半世紀近くの蓄積があるが、実のある議論をするためには、つねにその時々の技術的・社会的諸条件を踏まえておかなければならない。有用な最新版の議論の土俵を提出してくれるのが本書である。
ゲノム編集(バイオテクノロジー)と並ぶ、もうひとつのキラーテクノロジーである人工知能関連技術はどうだろうか。今年、第3次AIブームは去った、という意味の言葉を複数の関係者から聞いた。そうなのかもしれない。だが、メディアや新しもの好きが担ったブームが去っただけで、人工知能関連技術の実装そのものは、オートメーション化という大きな流れのもとで今後も進んでいくに違いない。

- ユヴァル・ノア・ハラリ
『ホモ・デウス
──テクノロジーとサピエンスの未来』
(上・下、柴田裕之訳、
河出書房新社、2018)
そのAIブームの掉尾を飾るにふさわしい大作が、ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス──テクノロジーとサピエンスの未来』(上・下、柴田裕之訳、河出書房新社、2018)である。ベストセラーとなった前作『サピエンス全史──文明の構造と人類の幸福』(上下、柴田裕之訳、河出書房新社、2016)の結びでハラリは、「私たちはなにを望みたいのか?(What do we want to want ?)」という問いをわれわれに向けて発した。周囲の環境だけでなく自分自身をも改変する力を手にしつつある現在、われわれはなにを望むのかではなく──なんでも望みどおりのものになれるのだからそれは問題ではない──、なにを望むことを望むのか? という2階の問いの前に立たされているのだ、という意味である。
この問いに対して、ハラリが自分で「こんなところではないか?」と答えてみたのが本書である。ハラリによれば、人間はテクノロジーの助けを借りて神のごとき存在(ホモ・デウス)になろうとするが、かえってそのせいで墓穴を掘ることになる。人間が欲望を実現するための手段であったテクノロジーが、逆に人間の存在理由を無化し、人間そのものを用済みにしてしまうからである。人間は自律化したテクノロジーが要求するデータの流れのマイナーな一支流にすぎなくなり、最後には消滅してしまうかもしれない。
こうした未来像自体はそれほど目新しいものではない。SFの世界ではおなじみのパターンとさえいえるだろう。だが、おそらくハラリの意図は、目新しい未来像を提示することではないし、自らの主張や願望を表明することでもない。人間社会における技術利用の歴史を踏まえたうえで、「このままいったらこうなるのではないですか?」という、ありうべきひとつのシナリオを提出したということなのだろう。実際にどうなるかは誰にもわからないとはいえ、ハラリのシナリオは私にとっても説得的であった。

- グレゴワール・シャマユー
『ドローンの哲学
──遠隔テクノロジーと〈無人化〉する戦争』
(渡名喜庸哲訳、明石書店、2018)
最後にもう一冊、重要な書物を紹介したい。グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学──遠隔テクノロジーと〈無人化〉する戦争』(渡名喜庸哲訳、明石書店)である。
先端テクノロジーがもたらしうる「いまここにある危機」のひとつに、無人兵器、ロボット兵器の問題がある。なかでもドローン兵器──遠隔的ないし自動的に制御される陸上、海上ないし航空の乗り物★1──を用いた攻撃は、すでに米軍によって「対テロ戦争」における重要な戦力となっている。本書は、軍用ドローンがどのように開発・運用されているか、そしてそれがどのような軍事的、政治的、さらには倫理的なインパクトをもたらすかを分析するものである。
軍用ドローンの登場によって、戦争はもはや戦争ではなくなる。それは殺すか殺されるかという戦いではなく、一方的な「狩り」による死刑執行であるからだ。軍事行動そのものの意味も変わるだろう。ドローンの行為は軍事的というより警察的であるからだ。そのような殺人行為はいかにして正当化されるのだろうか? 殺人ドローンの巡回する土地で暮らすとはどのようなことだろうか? そして、殺人ドローンを他国に展開することで自らの安全を保障する国家の国民であるとは、あるいはそのような国家の同盟国の国民であるとは、どのようなことだろうか?
このようなテクノロジーの発達と普及を目の当たりにして、「まるでSFの世界だ」と慨嘆することはもはや紋切り型に属するが、その際、私たちの多くは知らず知らず自身をSF作家の立場に置いているように見える。むしろ作品の登場人物の立場に近いはずであるにもかかわらず。私たちはウィンストン・スミス(『一九八四年』)として、バーナード・マルクス(『すばらしい新世界』)として、「私たちはなにを望みたいのか?(What do we want to want ?)」と問われているのである。
註
★1──グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学──遠隔テクノロジーと〈無人化〉する戦争』(渡名喜庸哲訳、明石書店)21頁。米軍の公式定義。Department of Defence, Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1-02, August 2011, 109.
吉川浩満(よしかわ・ひろみつ)
1972年生。文筆業。慶應義塾大学総合政策学部卒業。国書刊行会、ヤフーを経て、現職。山本貴光と「哲学の劇場」を主宰。主な著書=『人間の解剖はサルの解剖のための鍵である』(河出書房新社、2018)、『理不尽な進化──遺伝子と運のあいだ』(朝日出版社、2014)、『問題がモンダイなのだ』(山本との共著、ちくまプリマー新書、2006)、『心脳問題──「脳の世紀」を生き抜く』(山本との共著、朝日出版社、2004/増補改訂版『脳がわかれば心がわかるか──脳科学リテラシー養成講座』太田出版、2016)ほか。主な訳書=ジョン・R・サール『MiND──心の哲学』(山本との共訳、ちくま学芸文庫、2018)、メアリー・セットガスト『先史学者プラトン──紀元前1万年-5000年の神話と考古学』(山本との共訳、朝日出版社、2018)ほか。http://clnmn.net/
201901
特集 ブック・レビュー 2019
1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見 ──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか
谺(こだま)するかたち ──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』
現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか
ゲノム編集・AI・ドローン ──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか
「建築の問題」を(再び)考えるために──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか
あいだの世界──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか
モノ=作品はいま、どこにあるのか──『デュシャン』、ジョージ・クブラー『時のかたち』ほか
堕落に抗する力──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか
オブジェクトと建築 ──千葉雅也『意味がない無意味』、Graham Harman『Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything』


