復興からの創造はいかに可能か
震災遺構と記憶の継承
林──いま大槌町では旧庁舎[fig.3]の保存で揺れていますが、旧庁舎を巡る議論は、社会の分断を強める方向に進んでいるようにも見えました。人だけでなく、モノの存在も復興を大きく左右しますね。

- fig.3──大槌町の旧庁舎[撮影=岡村健太郎]
福嶋──いわゆる「震災遺構」をどうするかは喫緊の問題ですね。大槌町で旧庁舎を保存するという決断がなされたら、他の自治体にも波及していく可能性があるので、非常に重要な意味があります。震災の記憶を後世につなぐというとき、インターネットに情報があればいいというのは幻想に過ぎない。むしろ情報過多の状況だからこそ、モノとして形を残しておかないと記憶し続けることができません。
鞍田──この旧庁舎(震災遺構)保存の問題は、次の災害に備えてなにかを考える際のスパンが焦点になっていると思います。つまり、どれくらいの将来を見据えながら記憶を継承していくかという議論においてすごく重要なことだと思った。それは空間的な視点からもいえることで、これを大槌町だけの問題に狭めてしまうと、この街の人たちの分断やいがみあいにつながってしまうかもしれないので、そういう方向に落とし込まずに、もう少し広域的に共有できる方向にもっていったほうが、街にとって有益だと思う。分断の象徴ではなくて、今回の震災そのものの次への継承のステップとして、この震災遺構保存の問題を扱えばいいのではないかと。
林──いままでの成長型社会のなかでは、新しい空間をつくることができるという希望感のなかでモノがつくられてきました。しかし、モノは一度つくられてしまうと人より長生きできる性質を抱えている。建築のもつこうした「残る」という性質をうまく価値に変えていくことが、いまは大事だと思います。ただ、そうは言っても、残ったものを力強く価値に変えて、街をつくることはとても難しいのが現実です。大規模な盛土は、敷地に残っているものをすべて消し去ってしまっていて、新しくつくる論理が勝ってしまっています。
福嶋──素人の雑駁な印象論だけど、建築家は建てて終わりという人が多いんじゃないですか。しかし、本当に大事なのは事後的なモニタリングです。その建物が本当に自分の狙い通りに機能しているのかをちゃんとチェックしないといけない。被災地でそれがどれほどなされているのか、ちょっと疑問です。
鞍田──きのう宮司さんが、もっと街路樹を植えたいという話をしていたけれど、ああしたささやかな日常的な景観に対する視点は意外と大事でしょう。いまはまだ開発途中の段階だから更地の上に新築が立っていていかにも寒々しいので、ここにある種の潤いをどう与えていくのかという議論をする必要があるかもしれません。ここに盛土しなければよかったのにというような議論をいまさらしても仕方ないので、盛土をした後の街をどのようにいきいきさせるかを考えるべきですね。街路樹で人を街に呼び出すなどの、そういった小さな装置は大事だと思いました。それは、すごく自然的ないい街になる条件のひとつだと思う。土木とは少し違うけれど、景観形成の要素があってもいいし、それを街として投資してもいいかもしれないですね。
岡村──町方地区に、庁舎以外にも過去の記憶をとどめようとしてデザインされたものがいくつかあり、そのうちのひとつが御社地公園[fig.4]です。街の中心地に位置し、神社や池があって、雰囲気がよかった場所なので、そこは残しましょうと合意形成が取れたんだけれど、街全体は約2mかさ上げすることになったので、そこだけ窪地みたいになっています。かなり苦労して頑張って残したようなので、記憶の継承に繋がる場所になってほしいですね。

- fig.4──御社地公園[撮影=林憲吾]
鞍田──僕は個人的に庁舎保存における記憶の継承の問題と「生きた証プロジェクト」[fig.5]における「言葉」の問題が、すごく印象に残りました。
ハンナ・アーレントが『人間の条件』のなかで、3つの条件を出しています。ざっくり言えば、自然、社会、個人という3条件です。そして、これら3つの条件に応じたふるまい方があるというのをあの本で分析している。そのなかの「社会」というステージは、古代ギリシャにおいて永遠なるものと考えられた自然に匹敵する人間にとっての永遠性・永続性のことを言っているのです。そして、永遠性・永続性を構築していくひとつの典型が「建築」です。建築というのは、おのずから一世代だけの問題ではなくて、人間社会にとっての永続性や地域にとっての継続性の証になるもの。庁舎保存の問題はまさにここが問われているんだと思います。
3つ目の「個人」という条件への応答のひとつは、アーレント曰く、そこにその人がいた、あそこにあの英雄がいたというような「物語」のことなんです。「生きた証プロジェクト」の試みはまさにこうした物語の一例だと思う。実感として、粗野だけどたしかな営みだと感じます。建築と物語、旧庁舎と「生きた証プロジェクト」。いままさに大槌では、自分たちがなにを伝え、なにを残し、自分たちの条件をどう設定していくのかということがもう一回ゼロから行なわれているような感じがしました。それは大槌だけの話ではなくて、現代社会にとって普遍的な課題で、僕らはコミュニティのなにを残し、なにを伝えていくかということにつながっていくと思います。
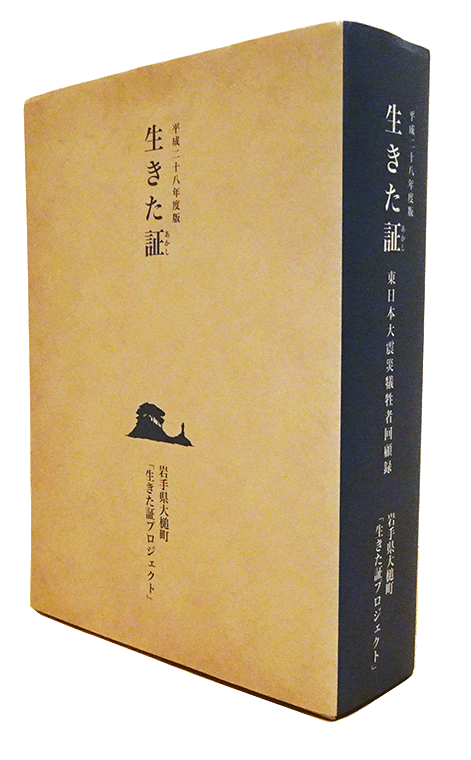
- fig.5──生きた証プロジェクトの書籍[撮影=岡村健太郎]
新たな言葉を創る
福嶋──文学研究のイロハを言えば、人間は言葉やイメージを現実と取り違えてしまう危うい生き物です。だからこそ、フィクションをつくることができるし、プロパガンダにも簡単に騙されてしまう。研究者や批評家は、日々現実のふりをした表象の分析を一生懸命やっているわけです(笑)。震災にしても、現実の問題であるとともに「言葉」の問題という側面もあります。
その意味でも、井上ひさしの『吉里吉里人』を再読するのは面白いのではないでしょうか。これは東北の村の「独立」をテーマとした大作ですが、思えば「独立」と「復興」は似ています。どちらもインフラをつくり、お金の流れ方を変え、新しい言語体系をつくらなければならない。『吉里吉里人』の特徴は、まさに言葉がとても豊かで、しかも独特の「おかしさ」があることです。それは震災後の世界と似ているかもしれない。復興にあたっては、それまで使わなかったような言葉を使わざるをえない。それは震災前の常識からすると、すごく変でおかしな言葉に見えるはずです。逆に言えば、『吉里吉里人』も「復興」を描いた文学として読み直せるかもしれません。
鞍田──具体的に変な言葉というのは、単語として聞き慣れない言葉とか?
福嶋──そうですね。言語体系そのものが変わらなければ、そもそも復興はできない。それは独立と似ているわけです。
鞍田──そう思います。例えば、それを井上ひさしみたいなある種のパーソナリティをもった人がドカッとひとつの作品にしていくのか、あるいは、「生きた証プロジェクト」に見られるような一個一個の言葉は極めて平易な日常語だけど、それの集積が変な言葉の素地をつくりだすような可能性はないのか。
ところで、福嶋さんが「生きた証プロジェクト」をどう感じたのか改めて聞いてみたいと思ったのですが。
福嶋──他の自治体ではほとんど試みられていないということで、挑戦的なプロジェクトだと思います。遺族から話を聞くことによって、孤立しがちな被災者をもう一度社会の側に包摂するような機能もあるわけですね。公共的な試みだと思いました。
鞍田──その試みが井上ひさしのような変な言葉を生み出すことにつながるということですか。
福嶋──そうですね。震災で孤独になると、話し相手がいなくなり、言葉の次元で孤立してしまうことがある。だから、官の立場からというよりは、ゲリラ的に話す・聞くというネットワークをつくっている人がいるのはとても素晴らしいことだと思います。それに、そもそも仏教の指導者は言葉の発明者でもあるんですね。唐からマントラを持ち帰ってきた空海は、『三教指帰』のような一種の戯曲も書いている。親鸞や蓮如にしても、和讃のような讃歌をつくったり、御文のようなわかりやすい布教媒体を用いたりしている。仏教者はただ心に働きかけるだけではなくて、言葉にも働きかけてきたわけです。そういう意味でも、このプロジェクトは正しく仏教的なのかもしれません。
鞍田──僕自身は「生きた証プロジェクト」にとても刺激を受けました。類例として、民俗学や人類学におけるインタヴュー、それから災害時における傾聴ボランティアといったものがあげられると思いますが、「生きた証プロジェクト」はどちらとも異なる第3の試みではないかと。
岡村──ここからなにか文学が生まれてもおかしくないですけどね。
林──福嶋さんの復興文化論によれば、復興から次の新しい文学の芽が出てきます。今回の震災からも生まれてほしいという思いはあります。直接被災地を扱わないにしても、前とは違う枠組みのなかから出てくる作品があると信じたいですね。
鞍田──僕もその点はすごく同感します。いま思い出したのは、以前、総合地球環境学研究所で井上章一さんを交えて座談会をしたときのことです。そのなかで、最近の環境学の議論として、実際に社会変革するには、個々人が一歩を踏み出さなければならないわけだけれども、その一歩をどのように促すことができるかという話をしました。もしかしたら、それって制度的・政策的なアプローチではなく、人の気持ちにダイレクトに働きかける文学や芸術に可能性があるのではないかって話になったんです。それに対して、井上さんは、芸術が盛り上がるときはたいてい世の中が乱れている時で、例えば、日本の場合だったら、戦乱の果ての安土桃山期の芸術活動が一番創造性に満ちていたと言っていた。井上さんの趣旨はそう簡単に芸術に期待されては困るよというものだったのですが、今回こうして復興途上の大槌に来て、まんざら現代の状況に当てはまらなくもないようにも思えてきました。既存のものや言葉が機能しなくなると、藁にもすがる思いで新しい表現や新しい言語空間に身を託したくなるのかもしれません。
福嶋──そもそも、東北人は寡黙だというイメージがあるけれども、今回お会したのは際限なくしゃべり続ける人ばかり(笑)。ほとんど無限に言葉が出てくるような感じですね。東北は閉鎖的な世界に見られるけれども実際は広々としているし、おしゃべりな人も多い。井上ひさしや太宰治だって、そういう東北的な饒舌さから作品を生み出してきたわけでしょう。繰り返しますが、東北のイメージの書き換えが必要だと思います。
鞍田──終わりがないというか、エンドレスな語り口だよね。もともと土地に根差した言葉の語り口ってそうなるものなのかもしれないけど。それこそ一義的にまとめちゃうのが近代だとすると、それに対する土着性の言葉というのは際限がないと思う。早く『吉里吉里人』を読む会をつくらなければいけないですね(笑)。
[2018年1月28日、さんずろ家(大槌町)にて]
鞍田崇(くらた・たかし)
1970年生まれ。明治大学理工学部准教授。哲学、環境人文学。著書=『民藝のインティマシー──「いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会、2015)。主な共著書=『雰囲気の美学──新しい現象学の挑戦』(晃洋書房、2006)、『〈民藝〉のレッスン──つたなさの技法』(フィルムアート社、2012)、『人間科学としての地球環境学』(京都通信社、2013)。
福嶋亮大(ふくしま・りょうた)
1981年生まれ。立教大学文学部准教授。文芸批評。著書=『神話が考える──ネットワーク社会の文化論』(青土社、2010)、『復興文化論──日本的創造の系譜』(青土社、2013)、『厄介な遺産──日本近代文学と演劇的想像力』(青土社、2016)。
林憲吾(はやし・けんご)
1980年生まれ。東京大学生産技術研究所講師。アジア近現代都市史。主な共著書=『相関地域研究3 衝突と変奏のジャスティス』(青弓社、2016)『メガシティ5 スプロール化するメガシティ』『メガシティ6 高密度化するメガシティ』(東京大学出版会、2017)。主な論文=「アジア熱帯メガシティの居住環境特性──ジャカルタ大都市圏を対象として」(2013)ほか。
岡村健太郎(おかむら・けんたろう)
1981年生まれ。東京大学生産技術研究所助教。建築史、都市史、災害史。博士(工学)。著書=『「三陸津波」と集落再編──ポスト近代復興に向けて』(鹿島出版会、2017)。主な共著書=『災害に学ぶ──文化資源の保存と再生』(勉誠出版、2015)ほか。主な論文=「『様式』としてのモダニズム──模型からみた近代建築史」(2007)、「昭和三陸津波後の岩手県大槌町吉里吉里集落の復興に関する研究──農山漁村経済再生運動と復興計画の関連」(2016)ほか。
- 被災地域の現在/中間領域を担う人材/アソシエーションの伏流
- 東北の開放性とインテリジェンス/アチェの復興と創造
- 震災遺構と記憶の継承/新たな言葉を創る


