「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか
環境が複層化・複雑化する時代の建築(家)
「環境」そのものの様態が急速に複雑化する現代社会のなかで、建築(家)の状況を冷静に考察することは難しい。物理環境、社会環境、情報環境など、さまざまなレイヤーにおいて急激的かつ構造的な変化が起きており、私たちを包囲する環境の全体像を把握することはもはや不可能である。ここ2、3年、AI、ビットコイン、シンギュラリティなどの言葉が飛び交い、想像もしなかった事象が当たり前のように実現している。2017年はそうしたことを強く感じた1年だった。そんな時代にどのように建築の現在を描くことができるだろうか。今年出版された3冊の本を通して考えてみたい。
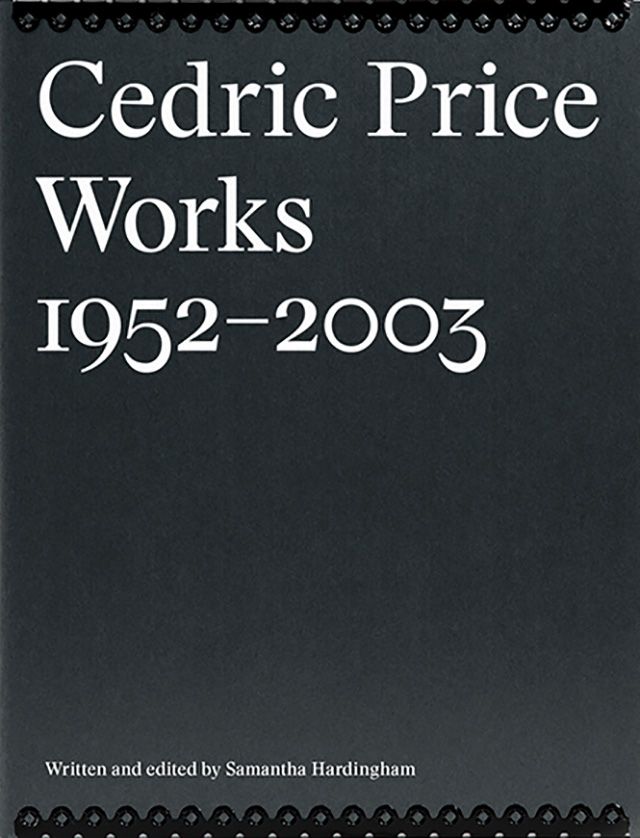
- Samantha Hardingham,
Cedric Price Works 1952-2003
A Forward-Minded Retrospective.
Architectural Association &
Canadian Centre for Architecture, 2017
20世紀後半のテクノロジーの発展によって「環境」が複層化・複雑化することに対していちはやく反応し、思考を巡らせた建築家がいた。セドリック・プライスである。今年、Samantha Hardinghamによって出版された『Cedric Price Works 1952-2003: A Forward-Minded Retrospective』と名づけられたこの本は、プロジェクト編と論考編の2冊によって構成され、厚さ11cmという圧巻の大きさを誇る超大型本である。それもそのはず、ここにはプライスの全プロジェクトが収められており、テキストも雑誌で書かれたもの、講演の文字起こし、個人のメモなど多岐にわたっている。特徴的なドローイング、文字、スタンプなどのグラフィックは眺めているだけでも楽しい。これまでも『Cedric Price -The Square Book』や『Re: CP』などの本があったが、本書はセドリック・プライスという人物像に対して包括的に迫ることのできる貴重なアーカイブになっている。さて、プライスの思索から建築の現在について考えてみたいのだが、その前に少し迂回をして、別の2冊からプライスの読み直しを図りたい。
インターフェイスの存在が自覚化された時代に

- 久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン
───久保田晃弘の思索と実装』
(ビー・エヌ・エヌ新社、2017)
デジタル化社会の到来によって人間と環境の関係の変化を捉えようと奮闘する久保田晃弘による『遥かなる他者のためのデザイン───久保田晃弘の思索と実装』(ビー・エヌ・エヌ新社)に触れたい。本書は、広義のデジタルデザインを探求してきたアーティストであり工学者である久保田が、ひとりの実践者として、デジタル化社会によって変容する創作と、その先にある人間のあり方について考察した1997年から現在までのテキストを時系列にまとめたものである。
デジタルデザインの定義のひとつとして久保田は「さまざまな方法で、数と知覚という2つの相異なる世界のインターフェイスを実験、探求、考察し、そこから新たな表現や概念を生み出していくこと」としている。本書を通読してみえてくるのは、2つの領域の関係を取り結ぶ「インターフェイス」という概念が、デジタル社会における人間のあり方を考察するうえで重要な位置づけにあるということだ。久保田は、インターフェイスはコンピュータの出現によってはじめて現われた概念であるとしながらも、昔から人間はあらゆるインターフェイスを通して文明や文化を築いてきたことを指摘している。「マウス」や「ディスプレイ」が発明されたことによってその存在を自覚するようになったのであり、インターフェイス自体は有史以来、人間にまとわりつく根本的かつ本質的な概念のひとつなのだ。身の回りの「家具」や「道具」をはじめ、「建築」も環境との間のインターフェイスであり、「身体」は私たちにとって最も馴染み深く、そしてほとんど意識することのない究極のインターフェイスである。本書の意図は、デジタル環境が敷衍した現代社会のなかで、さまざまなインターフェイスのリ・デザインを通して(当然GUIなどのことではない)変容する私たちの身体に着目し、そこから新たな人間観を構築することにある。久保田はそうした認知や身体の変化を敏感に感じ取り、言語化できる稀有な存在だ。感覚と論理の間を自由に横断できるしなやかな感性によって、本書のテキスト群は支えられている。
身体的インターフェイスと社会的インターフェイス
さて、「コンピュータ音楽とユーザーインターフェイス」という短いテキストのなかで、久保田は「身体的」と「社会的」という2つのインターフェイスの違いを挙げている。音楽を例にとると、シンセサイザーは直接私たちが操作するものであるため「身体的」だが、一方でサウンドファイルのウェブ上の流通や販売、あるいはサンプリングやリミックス文化を可能にするデジタルインフラは複数の他者で共有されるものであり「社会的」なインターフェイスであるとしている。あるリソースの獲得に対して直接的に身体を介在させるか、あるいは複数の他者との連携によって実現されるかの違いだ。当然、この2つの定義の切り分けは見通しをよくするための便宜的なものにすぎないが、こうした視座を得ることによって、触れる/触れない、サービス/プロダクト、デジタル/アナログという違いに関係なく、あらゆるものを「インターフェイス」として読み替える知性を獲得することができる。そして、あらゆるものがインターフェイスとして認識されるときに問われるのは、どのようにして自覚的にその一つひとつをデザインしていくかということである。本書のタイトルにある「他者」とはコンピュータのことだ。デジタル化した「ポスト人間中心主義の時代」あるいは「ポストインターフェイスの時代」において、コンピュータは「道具」ではなく「他者」なのである。こうした根本的な他者が現われたとき、建築というドメインはどのような変化の波を受けるのだろうか。
「プロトコル」というインターフェイス
インターフェイスの様態によって私たちのできること・できないこと、その可能性はあらかじめ定義づけられていると言える。身体というインターフェイスによって、私たちは空を飛ぶことはできないが、その制限ゆえに豊かな文化を生み出してきた。つまり、インターフェイスのデザインとは、私たちの可能性と制限を規定するインフラを設計することと同義である。そんなことを考えさせられるのが、情報化社会における新たな権力(マネージメント)のあり方を示した『プロトコル──脱中心化以後のコントロールはいかに作動するのか』(人文書院)である。原著は2004年にアレクサンダー・ギャロウェイによって執筆され出版されたが、13年経って、今年ようやく日本語訳が出版された。
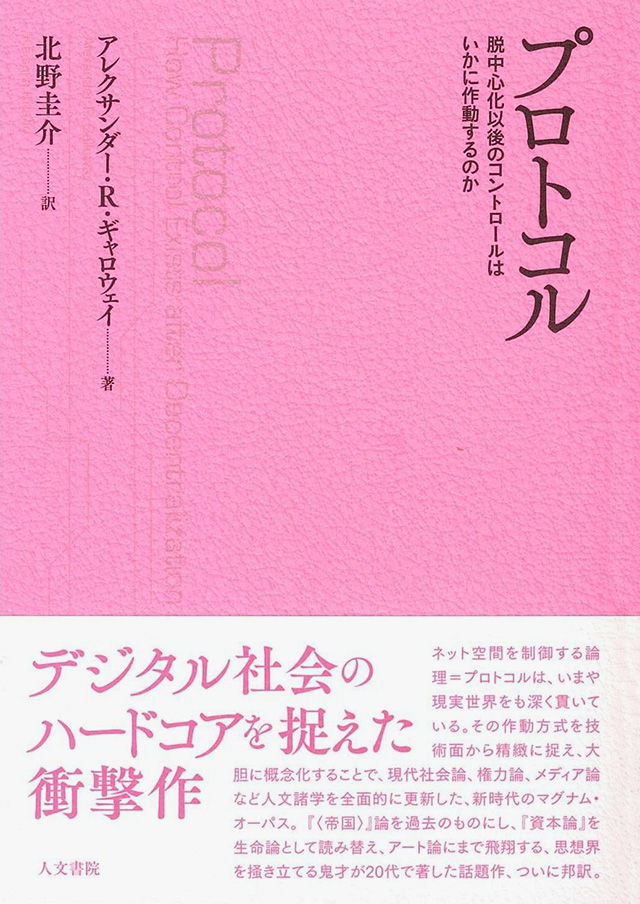
- アレクサンダー・R・ギャロウェイ
『プロトコル──脱中心化以後の
コントロールはいかに作動するのか』
(北野圭介訳、人文書院、2017)
本書は、フーコーやドゥルーズを経由しながら、現代社会における管理やマネジメントの形式を考えるために、時代区分を君主=主権型社会、規律=訓練型社会、そして制御=管理型社会の3つに区分している。プロトコルは、この制御=管理型社会の権力の発動のあり方を捉えるための鍵概念だ。プロトコルとは、広義の意味では儀礼や手続きという意味を持つが、インターネットの世界では例えばTCP/IPやDNSなどのように、ネットワーク上での情報のやりとりに関する通信の規約や規格のことである。通信する際には、複数のプロトコルが階層的に組み合わされて情報のやりとりが実現している。強調されているのは、プロトコルがメタファーではなく、物質化したメディアであり、ある2つの事象をつなぐ物理的論理であるということである。一般的にインターネットにおいて、ネットワークの「水平性」、つまり接続していくことの自由さ、そしてそのことによって実現される参加、集合、公開が強調される。他方、こうした時代のなかで、プロトコルというものをその形式性に着目し、切断や排泄が同時に内包されており、私たちのコミュニケーションがその形式によって高度にコントロールされるという「垂直性」を指摘している点に本書の価値はある。序言でユージン・サッカーが指摘しているように、インターネットは「開放」でも「閉鎖」でもなく調整された「形式」なのである。リソースとしてアクセスできるもの/できないものがあらかじめ規定された形式、それがインターネットの本質である、とギャロウェイは主張する。
このことが示す問題系の射程は計り知れない。テクノロジーがラップトップに留まらず、あらゆる環境のなかに溶けていく現代社会のなかで、プロトコルという形式はインターネットのなかだけにとどまらず、あらゆる場面に浸透しているのだ。例えば、スピードを出す車をどのように禁止するかという課題に対して、法律や警察に頼るという手もあるが、スピード抑止体を設置するという方法がある。これは物理的にスピードを出せない状況をシステムとして構築するという方法だ。プロトコルはこうした類の形式的な装置なのである。著者の言葉を借りれば「回路なのであって文ではない」のだ。この例にも表われているように、プロトコルの議論は、ローレンス・レッシグが2000年代初めに4つの権力機構のひとつとして挙げたアーキテクチャや、国内においては東浩紀を中心に環境管理型権力として議論されてきたことと多くの点で類似する。
不可視、そして無自覚なシステムが私たちの環境を形成している、その比率が加速度的に増えている。本書は、前半でプロトコルの性質を説明したうえで、後半では、プロトコルに対して、古典的な権力のかたちとして対抗・抵抗するのではなく、形式を戦術的に使いこなし肥大化させていくことの重要性を主張し、その具体的な事例のいくつかを紹介している。誰がどのように「プロトコル」を設計していくのか、それが本書の問いだとも言える。
インターフェイスとしての「建築」
さて、以上の2冊の本を経由して、プライス本について考えてみたい。いまの私たちには「インターフェイス」という新たな想像力が備わっている。「ケンチク」として考えると奇抜で不可解で謎に満ちたプロジェクトのいくつかをまずは簡単におさらいしてみよう。
「ファンパレス」は、可動式設備を備えた構造体を提案することにより、演者と鑑賞者との間にあるヒエラルキーを解体し、さらには「舞台」が建築として制限してしまうありとあらゆる意思決定や身体上の制約を開放しようとしたプロジェクトだ。こうした複雑なプログラムを実現するためにサイバネティクス学者のゴードン・パスクと協働していたというエピソードも興味深い。建築そのものは背景として後退し、存在するのは複雑に張り巡らされた環境メカニズムである。ゆえに利用者はもはや建築を意識しない。
「ポタリーズ・シンクベルト」や「マグネット」では、単体の建築ではなく、離散的に組織された環境が提案されている。前者であれば、衰退しつつある窯業地域のインフラ、後者であればロンドン市内に点在するオープンスペースをハックし、そうした空間に対して構築物が分散配置される。一つひとつの建築物に対する美的関心は希薄であり、代わりに構築物が配置されネットワーク化されることで生まれる環境の総体そのものに関心が向けられていることが特徴だ。ネットワークが形成されることによって、未来の「大学」や「公共施設」が環境として立ち現われることが企図されている。
どのプロジェクトもかたちの問題に帰結しない。プロジェクトもバージョンの改変が延々とあるのみで、ひとつのかたちへと収斂しない。それは古典的な建築的価値観で考えた場合に物足りなく不自然に感じるかもしれない。しかし、これら一連のプロジェクトを環境との間のインターフェイスとして捉えることでその印象が一変する。どのプロジェクトもある特定のリソースに対して新たな関係を「建築」によって取り結びアクセスできるようにすることがプライスの狙いだったと理解できるようになるからである。
too much "architecture", more interface.
「マグネット」のドローイングのなかに日本人スタッフのひとりが書いた1枚のドローイングが掲載されている。その右端にプライスの直筆で小さくコメントが書かれている。
lovely sketch - but too much "architecture"!
プライスの作品には、インパクトのある写真やパースが見当たらない。ひたすら技術仕様書、ダイヤグラム、問いかけリストがあるのみだ。なぜ、ここまでして「建築」を背後に後退させようとするのだろうか。
産業革命における技術革新は主に物理的水準における変化をもたらした。それと地続きにモダニズムは新たな素材や工法の発明によって生まれた美学であり運動だと言える。実体を伴った物理的な環境を相手にすることが20世紀までの建築家の仕事の大半を占めていた。しかし、現在起きているテクノロジーの変化はいままで私たちが想像していた古典的な環境とは違うレイヤーで起こっている変化だ。テクノロジー自体が新たな環境を創出してもいる。久保田やギャロウェイの著作はそうした変化を教えてくれる。こうした予感があったからこそ、プライスは物理的実体としての建築ではなく、インターフェイスとしての建築を志向する必要があったのではないだろうか。
既存の「作品」や「作家」という単位では正当に評価することが難しいプライスの一連のプロジェクトは、すでに過去のものになってしまい、古めかしく見えるものもあるが、ここに「インターフェイスとしての建築」のための新たな作品論や作家論が生まれるヒントが隠れている。そして、そうした新たな言説が、いま待望されているようにも思われる。
改めて、人間について考えてみる
最後に、改めて久保田の言葉を思い出してみたい。「ポスト人間中心時代のインターフェイス」という短いテキストのなかでインターフェイスは「環境」であるとし、「他者としての環境」とのインタラクションを通して、人間の認識や身体が変化していく動的世界観が示されている。インターフェイスを考えることは人間を考えることでもあるのだ。多くの人がリスペクトするファンパレスのプロジェクトをはじめ、プライスの作品にはこうした人間と環境とのインタラクションを実現することが目指されている。環境、そしてインターフェイスを問い直す作業それ自体が、人間そのものを問い直すことでもあるのだ。プライスは"Technology is the Answer, but what was the Question?"と題されたトークの最後に、最も重要なリソースは人間そのものであるということを「ジェネレイター」というプロジェクトを通して主張している。何を環境と捉え、そこにどのような人間像を描くのか、現代の建築家全員が問われている。最後に同じ講演のなかからプライスの言葉を再び引用して締めくくろう。「環境」の全体がますます見えにくくなる現代社会のなかで闘うすべての建築家へ送られる力強いメッセージだ。
I feel that the real definition of architecture is that which, through a natural distortion of time, place and interval, creates beneficial social conditions that hitherto were considered impossible.
P.S.
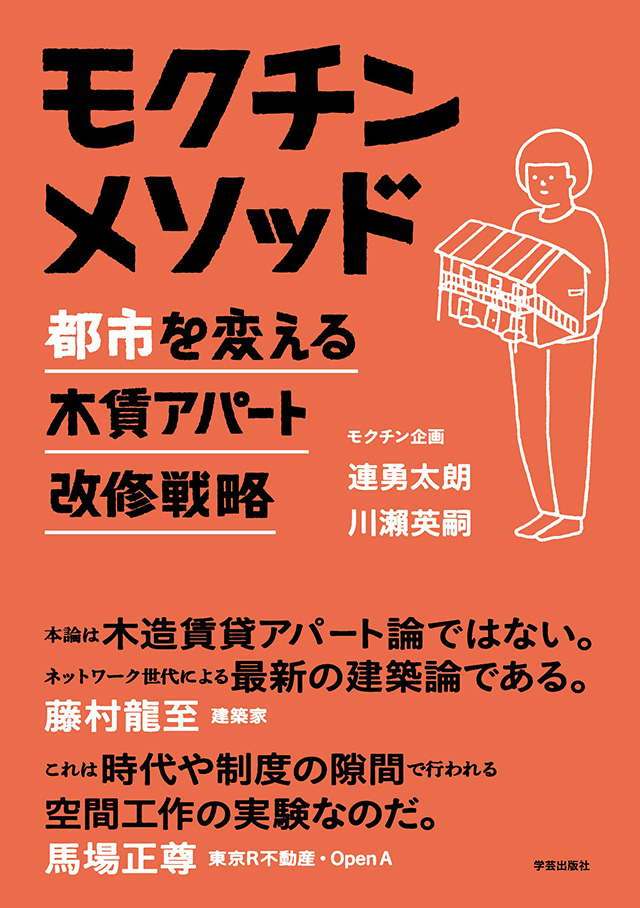
- 連勇太朗+川瀬英嗣『モクチンメソッド
──都市を変える木賃アパート改修戦略』
(学芸出版社、2017)
モクチン企画の活動をまとめた本を『モクチンメソッド──都市を変える木賃アパート改修戦略』(学芸出版社)と題して出版した。この書評を書いていて、モクチン企画/モクチンレシピも同様にインターフェイスのデザインと捉えるとわかりやすいのではないかと気づいた。モクチン企画は、いわば戦後日本社会の旧式OSで動く都市計画や建設産業の枠組みのなかで、木賃アパートやウェブなどの、ある特定の環境レイヤーにかかるインターフェイスを更新することで活動を展開しようとしているからだ。レシピのシステムそのものは「社会的」インターフェイスであり、レシピのアイデアそのものは「身体的」インターフェイスと言える。私たちの活動は、一般的な基準からすると、建築(家)としてみなされないし、作品をつくっているとは思われないかもしれない。しかし「インターフェイス」というキーワードを通して、私たちの活動を概観すると、少しはその意図が明確になるのではないだろうか。それはいままで積み上げられてきた建築的知性を捨てることを意味しない、むしろその逆である。だがしかし、私たちは「建物」を設計している場合ではないのだ。
連勇太朗(むらじ・ゆうたろう)
1987年生まれ。建築家。現在、特定非営利活動法人モクチン企画代表理事、慶應義塾大学大学院特任助教、横浜国立大学客員助教。共著=『モクチンメソッド──都市を変える木賃アパート改修戦略』(学芸出版社、2017)ほか。
201801
特集 ブック・レビュー 2018
歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか
オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか
中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか
器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか
21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか
ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか
「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか
シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか
歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか
中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか
建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか


