建築情報学とは何だろうか
契機
豊田啓介──「建築情報学」とは、建築をデジタル技術による広がりの先に再定義するための理解や技術の体系だと考えています。この漠然とした必要性は認識されつつあるものの、いまだはっきりと体系づけることができていません。まさにこれから多くの方と議論しながら、かたちに落とし込んでいく作業が必要なタイミングだと感じています。
僕自身はそうした体系化の試みを、教育と実務の両面から推し進めることが不可欠だと強く感じています。2010年に東京大学建築学科で、コロンビア大学建築学部(GSAPP)と共催し、コンピュテーショナル・デザインとデジタルファブリケーションを一体的に扱うワークショップを行ないました。「Digital Teahouse」というテーマで、単にパヴィリオンを設計・施工するだけではなく、「Rhinoceros+Grasshopper」を制作ツールとし、デジタルファブリケーションも前提とすることで、その使い方だけではなく考え方や背景も教えて、最終的に形として制作するまでの実践的なプログラムでした[figs.1,2]。大学の建築教育のなかでの正式なカリキュラムとしては先駆的だったと思います。


- figs.1,2──「Digital Teahouse」ワークショップ(2010)とその成果[撮影=豊田啓介]
豊田──こうした動きは当時ちょうど東大の教授に就任された隈研吾さんに働きかけて始まったのですが、体系的にそうした教育を始めるため、AA SchoolのDRL(Design Research Laboratory)ディレクターだった小渕祐介さんをお招きして常設の拠点をつくり、1年ごとに大手ゼネコンなど民間企業との協働リサーチや実践プロジェクトを始めたりと、この頃から日本でのさまざまな動きが徐々に繋がり始めたように思います。当時から問題に感じていたのは、既存の建築学のカリキュラムが、あまりに明治時代の工部大学校由来の、ジョサイア・コンドルの頃からの、意匠・構造・環境・材料といった領域に分割された体系を引きずり過ぎていることです。現実はもうインターネットやCAD、BIMはもちろん、デジタルスキャニングやファブリケーション、アーカイビングやシミュレーションなど、なんらかのかたちで情報技術を活用しない分野など考えられない状態になっているのに、建築という学問や実務に関わる情報技術という体系を、その重要性と広範な方向性に合致するように独立して扱おうという事例が、まだあまりに少ないということです。デリダやソシュールなどは頻繁に触れられるのに、コンピュータの概念を初めて理論化したアラン・チューリング(1912-57)や現代のコンピュータの父と言われるジョン・フォン・ノイマン(1903-57)、情報通信理論を確立したクロード・シャノン(1916-2001)など、少なくとも同等以上に現在の建築の情報環境に大きな影響を与えた人物や理論、発展の過程などは、ほとんど話題にのぼらないことに違和感を覚えていました。
また、ちょうどその頃、『Rhinoceros+Grasshopper 建築デザイン実践ハンドブック』(彰国社、2011[第2版=2014])という本をつくっていて、建築と情報技術の関わりについての年表を載せようとしたのですが、意外なくらいに参考資料がどこにもまとめられていないことに気づきました。おそらくいまだにCADの歴史のような体系をまとめられた書籍はないはずです。そうした資料がないということは、知識として共有することができず、ひいてはこれまでの歴史と現状、これからありうる価値や体系とを相対化して評価できないということを意味します。すなわちこれは学問としての不可能性であり、実務でもより大きな社会実装を考えるうえで決定的な手がかりの不足を感じていました。それらを解決するためには、「建築情報学」という明快な学問体系をつくり、各大学に建築情報学系研究室とその指導ができる教官がいるべきだと考えるようになりました。
同じ頃、池田靖史先生は論考「建築の生産と情報技術の結合がデザインを進化させる デジタル・ファブリケーション/BIM/アルゴリズミック・デザイン」(『新建築』2010年6月号)を発表されていて、当時の国際的な動向や課題などがよくまとめられていました。池田先生は、建築領域のなかでも情報技術を扱った論文の査読や会議のオーガナイズをされていましたので、こうした領域の体系化や実践についてアドバイスをいただけるのではないかと考えご相談したのが初めてお会いした時だったと思います。

- 豊田啓介氏
池田靖史──豊田さんから「建築情報学」の必要性についての熱い思いを聞き、まずすごく意義があると思いましたし、この30年くらいのあいだ、私自身が何をしていたのだろう、と申し訳なくも思いました。そうした議論のルーツを辿ると、そのひとつに僕が学生時代に最も刺激を受けた磯崎新『建築の解体』(美術出版社、1975[鹿島出版会、1997])があります。各章のサブタイトルを見ても「建築を情報に還元する」「伝達メディアとしてのポップ建築」「システムのなかに建築を消去する」といった言葉はまるで最近書かれたかのようであり、建築が情報化という波のなかで存在を変えていくという予測が非常にクリアにまとめられています。当時の磯崎さんのテクストには未来へ向けたアジテーションのようなニュアンスがありましたが、私が言いたいのは、いまやむしろ現実のほうが先に進んでしまっているのに、それを建設業界や建築アカデミズムがどれだけ明快に認識できているのかということです。
1960年代以降、建築と情報技術の関わりが決定的な問題にならざるをえないということはずっと指摘され、50年以上前からそうした議論があり、いまさら建築情報学の必要性を言うのも不思議なくらいですが、これまでは何か新奇性や未来性が強すぎて、過去を振り返りながら体系化する努力が足らなかったのだと思います。同時に、「建築の解体」という言葉通り、既存の建築概念や建築学体系を乗り越えるようなものにならざるをえないので、アジテーションを超えた動きにするには相当な時間と労力が必要なのだとも思いますが、いまだからこそ、既存の建築学の枠に収まることなく体系を考えなくてはいけないと思うようになりました。

- 池田靖史氏
豊田──磯崎さんは先見の明があり、それを言語化する天才ですよね。でも、そこから先の実践や広がりにつなげるためには、具体的な研究・実験や論文といったかたちでの知の積み重ねをし、解像度を上げ、共有・展開が可能な学問体系にしていかない限り、実効的な社会実装にまで至ることは困難です。そうしなければ、ひとりの天才が語るという特殊解に留まってしまいますし、つながるべきほかの分野との連携の機会を逃すということは、これだけ領域融合的な新しいシステムが社会を急速に変えている時代にあって、建築全体にとって不幸どころの話ではありません。特に、昨今新しいテックやビジネスの視点から、建築や都市への興味が急速に高まっているなかで、建築側が外と共有できる体系の構築は急務です。
池田──そう、つまり「情報学」としての横の連携こそが大事だと思うのです。日本建築学会でもそうした建築と情報技術の問題を扱った委員会がありますが、あくまで建築学の体系があり、そのなかの分野のひとつ、建築をサポートするための道具のひとつだと捉えられています。しかし建築情報学は、ほかの学問領域や産業とも連携し、建築分野自体を書き換え、既存の建築学を脅かすくらいの可能性があると思います。僕のいまの職場は慶應義塾大学のSFCですが、そこにはまさに建築だけではなく、いろんな分野で同じような思いを持った人が集まっています。生物学や経済学といった学問も、情報技術から新しく捉え直すことができる、再定義できると考えられています。だから、建築情報学もこれまでの領域を横断した論文や学生を拡大再生産的に輩出し、実務でもアカデミアでも縦割の専門家の傾向を助長するのではなく、既存の建築学内はもとより、建築以外の領域、情報工学や生物学、社会学、経済学などあらゆる分野とも横方向に連携できるプラットフォームとして機能するべきだと思います。
人材の育成は大きなテーマで、自分の学生時代を振り返って、個人史として思い出すことがあります。アルバイトに行っていた槇文彦さんの事務所では、コンペで勝った《幕張メッセ》の基本設計をしていました。巨大な円弧状の立体トラス屋根があり、当時は手書き図面で、商用のCADすら存在しない時代でしたが、立体トラスの各座標位置が単純なアルゴリズムで再帰的に導き出せるのだから、座標入力しなくてもコンピュータでパースの下書きが描けるということを閃きました。2週間もかかっていたのを「ひと晩で作図できますよ」と言ってしまいました。もちろんその言葉だけでは誰にも信じてもらえず、まだ自分のパソコンも持っていなかったので大学へ戻り、大学のパソコンを使って「Basic」でプログラムをつくって図面を描き、プリントアウトして持って行ったのです[fig.3]。既存の建築学とは別の方法論によって、ほかの人にはできない問題解決を提示できたというひとつの成功体験でしたが、自分のキャリアがあの時から始まっているような気がしています。
当時はCADが設計の中心になるとは信じられていなかった頃ですし、それに対して僕自身も強く反論できたわけではありませんでしたが、いまは当然のように誰もがCADを使っています。情報技術は黎明期にあった抵抗感よりも意外とスムーズに浸透してきているのです。デザイナーへの情報技術の教育がもっと新しい可能性を学生に与えられると思います。
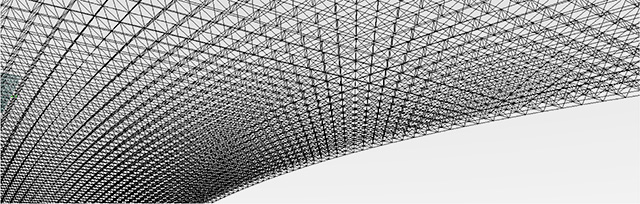
- fig.3──《幕張メッセ》のトラスのパース(再現)[提供=池田靖史]
豊田──僕が修士課程で在籍していた2000年前後のコロンビア大学は、バーナード・チュミによる「ペーパーレス・スタジオ」などの実験的なデジタル教育が一定の成果を出しつつあった時期で、そうしたプログラミングによる形態やジオメトリの生成などの実践がまさに自然発生的に始まっていました。その結果、既存の建築という概念にとらわれない多様な人材を、映画や広告、ビジネスなど他分野にどんどん輩出し始めていました。
池田──豊田さんがいた頃のコロンビア大学は、デザインへの情報技術の導入についてまさに先端的な試行がされていた時代だったと思います。ほかにもいろんな実践をされてきた方がたくさんいますが、デザイナーの思考という意味で、われわれ2人はある種の共通体験から建築情報学の立ち上げを考えているのかもしれません。
豊田──2000年前後は特に海外で新しく実践的な動きが広がった時期でもあります。フランク・O・ゲーリーが3D CADの「CATIA」をカスタマイズして《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》(1997)[fig.4]を実現させたことはよく知られていますが、その後、2002年に「ゲーリー・テクノロジーズ」が独立しています。

- fig.4──フランク・O・ゲーリー《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》[撮影=池田靖史]
豊田──僕自身の経験で言えば、コロンビア大で修士課程を修了し、ニューヨークのSHoP Architectsで働いていた時、ちょうどRhinocerosのVersion 2が出てきた頃で、「新しいソフトだからとりあえず使ってみよう」という事務所内での実験的な試みとして使っていました。まずはやってみて、ダメだったらほかを試そう、というような気軽な感覚です。例えば、JFK空港にヴァージンアトランティック航空のラウンジ《Virgin Atlantic Clubhouse》(2004)[fig.5]を設計したのですが、何万ピースもの異なる形の部材を扱っています★1。当時アルゴリズムエディタなどはありませんでしたから、デジタル空間上で生成した立体を何千もの断面で切断し、つなぎ合わせ、ナンバリングをしたうえでCNC切削のために各部材を平面的に並べ込むという作業をすべて手作業でしていました。まだヒストリー機能すらなく、途中で設計変更があればまた数週間かけてやり直したり、とにかく非常に手間のかかる作業でした。そうした経緯を経ていたからこそ、2007年に「Grasshopper」というプラグインが出てきた時には、「これだ!」と感動したものです。なぜこれがいままでできなかったのかと。いまではより多くの、必ずしも建築用ではないソフトウエアやプログラミング言語を横断しながら、その都度組み合わせてカスタマイズをしていくことも当然になっていますが、まだ十分な機能や互換性がなかった時期からそうしたソフトウエアを工夫しながら多領域と接続し、使い込んできたことで、逆に未来の方向が読めるような感覚があります。

- fig.5──SHoP Architects《Virgin Atlantic Clubhouse》[撮影=豊田啓介]
豊田──また、2000年頃から現在にかけての面白い傾向として、デジタル技術を基礎としてデザインと施工、理論を繋ぐ新しい職能が生まれてきたという流れがあります。例えば「Front」というファサードエンジニアリングの会社は、《シアトル中央図書館》(設計=OMA、2004)[fig.6]などの複雑なカーテンウォール部分の実装を担当していました。ファサードは性能的にもクリティカルですし、いわゆるメーカーとして受け身になるのではなく、デザイン側と施工側どちらの勘所も押さえながら、デジタル技術とジオメトリの理論的理解をベースに、新しい実装のかたちを与えていくような職能がより求められるようになります。例えばARUPなどにもファサードエンジニアリング専門の部署がありますが、Frontはファサードのジオメトリ解析と実装に特化した会社です。ETHチューリッヒからスピンオフしてSANAAの《ROLEX ラーニング センター》(2010)[fig.7]などのジオメトリエンジニアリングをしている「Design-to-Production」なども、同じような分野のパイオニアですし、台湾や中国などにも、こうしたジオメトリと施工をつなぐ新しい立ち位置の事務所が生まれています。SHoPは、当時すでに先進的な事務所としてそこそこ名は通っていましたが、同じ界隈ではむしろFrontで働いていることがよりクールであるような、ちょっとギークな価値の転換みたいなものがあったように思います。SHoPもその後、こうしたデジタル技術によるデザインや施工、コスト管理の技術的サポートに特化した「SHoP Construction」を分社化してほかの設計事務所のテクニカルな実装部分のみを請け負ったり(その後SHoPに再度吸収)、SHoPから独立したBIMコンサルティング事務所の「Case」が「WeWork」に買収され、テック企業としてのWeWorkの核になったり、こうした分野でも相当活発な動きが始まっています。

- fig.6──OMA《シアトル中央図書館》[撮影=豊田啓介]

- fig.7──SANAA《ROLEX ラーニング センター》[撮影=富井雄太郎]
池田──情報技術によってデザインと職人のものづくりとの新しい接続が生まれていますね。
改めて最近思うのは、ロンドンのAA Schoolがこの30年で果たした役割はものすごく大きいということです。一つひとつのプロジェクトは、なんの役に立つのだろうかと言いたくなるようなものかもしれませんが、延々とチャレンジを続け、事後的に結果を見ると、歴史的成果になっています。いま目の前の仕事で不足している人材のためにカリキュラムや必要科目を決めて......、という考えとは違う教育システムですね。
豊田──ETHチューリヒやシュツットガルト大学ICDなども同様で、さまざまな興味深いスピンオフを輩出していますよね。こうした変化の急な時代には、一見無駄や失敗にも見える活動の蓄積こそが既存の領域を乗り越えて、長い目で見ると単なる足し算ではない指数関数的な爆発を生み出します。コロンビア大学での教育を見ていても、SHoPや周辺の活発に動いている事務所を見ていてもそれは強く感じます。
池田──構造家のセシル・バルモンドが現われたことも象徴的で、彼には建築家と構造家のどちらが、どのような協力関係でデザインをしているのだろうかと改めて考えさせられるような力がありました。構法技術的には完成してしまった近代建築を、情報技術によって見直し、もう一度開発力やつくり方そのものを考え直すことを重視する時代に戻ってきています。
註
★1──『a+u』2005年5月号に詳細が掲載されている


