「オブジェクト」はわれわれが思う以上に面白い

- 左から、エリー・デューリング氏、清水高志氏、柄沢祐輔氏(《s-house》にて)
オブジェクトの中のプロジェクト
──反プロセスとしてのプロトタイプ論

-
fig.1──ブルーノ・ラトゥール
『虚構の近代
──科学人類学は警告する』
(川村久美子訳、新評論、2008)
fig.2──Elie During,
"Prototypes (pour en finir avec
le romantisme)" in
Esthétique et Société,
C. Tron dir.,
Paris, Éditions de L'Harmattan,
2009.(「プロトタイプ論
──芸術作品の新たな分身(1)」
『現代思想』
「特集=現代思想の新展開 2015
──思弁的実在論と新しい唯物論」
青土社、2015年1月号)
さて、今日私たちは清水高志さんの自邸《s-house》(設計:柄沢祐輔建築設計事務所、2013)を訪れたわけですが、「プロトタイプ論」の観点から《s-house》をどうご覧になりましたか?
エリー・デューリング──まず、あなたの最初のご質問について言うと、諸々の解釈の理論には今日、次のような傾向があると思います。たとえばラトゥールの理論や、もっと一般的に、オブジェクトの関係的な性格を強調する理論、ロマン主義の流れをくむ、古い美学の枠組みに立つものなどです。これらの理論の根幹にある直観はこうしたものです──アートや建築は、有限の限られた形態のなかで無限性をなんとか表現するのですが、それらの形態には、それ自体をはるかに超えることが強いられることになる。こうした弁証法が到達する極限は、〔美を超えるものとしてカントが語った〕
その極端な例として、なにも建てない、見せない、展示しないアーティストたちがいます。彼らのプロジェクトそのものが、進行中のプロセスを根気強く見届ける証人に十分なっているというわけです。コンセプチュアル・アートの根強い伝統においては、オブジェクトを見せる必要はありません。ある意味で自らを持続するプロジェクトやアイデアそのものに主眼が置かれるのです。しかし私はこれは間違っていると思います。彼らにとって重要なのはそんなプロセスではないはずだからです。諸々の関係が示唆するのは、新しい存在論──オブジェクトの真の性質をめぐる問いを喚起するような、新しい存在論なのです。

- fig.3──Graham Harman,
The Quadruple Object,
John Hunt Publishing, 2011.
有限と無限──同時存在するパースペクティヴ

- fig.4──ホルヘ・ルイス ボルヘス
『エル・アレフ』(木村榮一訳、
平凡社ライブラリー、2005)
こういう圧縮された濃密さは、日本では黄金の仏像がひしめいている昔の京都の仏教建築のうちにもありますね。しかし鎌倉時代に近づくと、禅の文化とともに、むしろ閉ざされた内部と外部に通路をつくるような思考が展開され、建築にも変化が現われるように思います。密集したなかに、「風」が吹いてくる......。
柄沢──外部/内部が非常に特殊な方法で現われるわけですね。その現われ方は例えば京都の古い町屋や街並みなどの至るところにおいても見出すことができます。外部と内部が縫合されているようなかたちで関係性が現われます。清水さんはそれらが仏教思想から立ち上がっているとお考えなのですね。
デューリング──ボルヘスの『エル・アレフ』には、私もとても興味をそそられますね。日本庭園の茶室においても同じようなことを感じとることができます。茶室は自然に開かれているけれど、その自然は枠づけられた自然であって、まるで内側に自然が現われたかのようです。同じように《s-house》[fig.5]においても、つねに外部/内部の曖昧さが作用しているんです。なぜなら空間の内部にリアルな境界がないからです。壁も間仕切りもなく、面が自由に浮かんでいる。しかもなお、なにかある種の空間の区分があるわけです。通常の意味では「部屋」とは呼べないのですが、だがしかしはっきりした領域、あるいはテリトリーがあるんです。しかしそれは、「間をとる」プロセスのなかで生じてくる。私たちはそれを、境界から始めるわけではありません。むしろ、開かれた空間としてそれは創造されるのです。《s-house》について考えていて、「これは壁がない家なんだ」と自分に言いきかせていました。もちろん技術的には壁や、壁として働く支持構造はあるのですが、これらの壁はそれじたい、なにかもっとベーシックなものが立ちあがるという性質のものだと思うんです。それはもちろん、多種多様な身体のヴァーチュアルな動きを暗示しながら、あらゆる面の内/外の曖昧さの導入にむけて開かれている、二重の階段の構造的な機能にも関わっているのですが。
あなたは部屋の内にいても、壁の仕切りがないために、外部にいるのです。こうした知覚(あるいはパースペクティヴ)の同時性こそが、有限と無限の問題として考えられている、ロマン主義的な内と外の弁証法にとって替わるべきものです。私にとって、このパラダイムは建築の製図で用いられる等角投影法や軸測投影法の構造ですね。あるいは有名な「ネッカーキューブ」のような、曖昧な形態をもとにしたヨゼフ・アルバースの驚くべき複雑な幾何学構造かもしれません。お望みならそれを、静止状態にある

- fig.5──《s-house》外観(撮影:鳥村鋼一)
柄沢──先ほどデューリングさんは、無限性が有限なもの、プロトタイプになりうると仰っていましたが、それは《s-house》においても見出すことができると思います。
デューリング──そう思います。ボルヘスの『エル・アレフ』について幾つか言うと、オブジェクト(アレフ)は階段の2つの段のあいだで無限性を内包しているものとして現われています。これは無限というのが超越ではなく、なにかあいだにあるものだ──実際には2つの段のあいだですが──、という考えをうまく描き出しています。無限に関する個々の表現が、なにか超越したものを残しているとロマン主義は考えます。もし無限が表現されたとしても、それは必然的に有限な形態を通じてなされねばならないというのがロマン主義の考えです。そうした有限な形態は、不十分で、脆弱で、壊れてしまう。というのも、そこから溢れだすものが現われるからです。しかしながら、プロトタイプにおいては、あなたが見たものをあなたは得ることになる。そして無限はヴァーチュアルなものであり、オブジェクトに包摂されているのです。
柄沢──ヴァーチュアルな無限性を有限のもののなかに見出す。非常に重要な点ですね。
デューリング──これは、ライプニッツによって展開された、非常に強靭な直観ですね。実際のところ、無限というのは有限なものの錯綜なのです。
柄沢──《s-house》においても見出すことができますね。
デューリング──そうですね。《s-house》に対する私のアプローチは、同時的で多方向的な諸々のパースペクティヴの相互作用という見地に立つものです。
柄沢──無限性としての同時性を有限な《s-house》に見出すことができる。
デューリング──ええ、そう捉えることもできるでしょう。
プロトタイプ・オブジェクトがつくる多極的な世界観
デューリング──私は修士の学生のときにはライプニッツに取り組んでいたんですよ。その後はベルグソンとアインシュタインに転じました。しかしライプニッツには今でも強い関心を持っています。私の考えでは、相対性理論は現代のモナドロジーですね。というのも、それは究極のところ、空間-時間のパースペクティヴの理論で、物理的な意味で異なる視点(〈参照フレーム〉、もしくは〈参照システム〉)がどのようにして同じ宇宙の表現として捉えられうるのか、お互いのなかでどのように変容するのか(数学的には、それは諸々のパースペクティヴの対称性を確立する対称群です)ということを私たちに語っているのです。特定の変換群のうちでの不変項が、オブジェクトだとよく言われますね。プロトタイプ・オブジェクトに関して言うと、それらはそれら自身のうちに変換群を含んでいます。そうした変換群は、(スケールモデルから完全な構造までの)さまざまなフォーマットでそれらのうちに投影されるのです。プロトタイプ・オブジェクトは、それ自身の変換(変容)から、すなわち、場所から場所へと描かれるこうした変換(変容)の軌道から切り離すことができないのです。柄沢──清水さんもライプニッツについて相対的・関係的なネットワークの哲学という視点から思考していらっしゃる。
清水──僕は昔から、クリスティアーヌ・フレモンがやったような、相対主義や関係主義にもとづいたライプニッツ解釈を、ミシェル・セールに読み込もうと試みてきました。彼女は、〈実体間紐帯〉というライプニッツの晩年の思想に着目し、彼の思想を実体論的なものというよりはネットワーク的なものとして捉えようとしました。『存在と関係』というその著作には、セールも序文を寄せていますね。
いっぽうで、日本には日本のライプニッツ研究の伝統があって、それは西田幾多郎の弟子(下村寅太郎)から始まっています。西田のライプニッツ解釈も、いくつかの論文から窺われるところでは、非常に関係主義的なものです。これらを踏まえて、西田とライプニッツとセールをミックスして、その理論を全部発展させることを僕は考えていました。
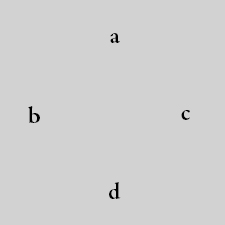
- fig.6
しかし一方で、個別なものが、複数のものの媒体になる関係もまた考えられるのです。これが、近傍の関係です。順序の関係はどうしても不可逆的なものになりますが、近傍の関係まで絡むと、そこには並存性や、可逆性がでてきます。順序が垂直に積み上げるものを、それは再び並存性のうちに繰り込んでしまうのですから。現代の哲学や美学も、デューリングさんのプロトタイプ論もそうですが、モノやオブジェクトをめぐる一種のアナクロニックな共存関係に着目しているように思われます。そうした思考のヒントが、若いライプニッツが語った、こうした〈近傍的な共存〉にすでにあるように私は思うのです。
ミシェル・セールは、まずなんらかの学問の
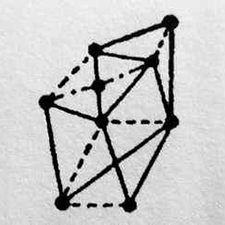
- fig.7
ところで、僕が昔から頭を悩ませているのは、今の例でいえば、一つの結節点に複数のものが合流してくる「一と多」という問題と、「主体と対象」という問題なのです。とはいえ、これらの対の両極は、じつのところ役割を交換しうるものなのではないだろうか? 各々のオブジェクト=結節点は、複数のアプローチの合流点ですが、それ自体別の結節点へと合流していく、〈複数のアプローチ〉の一部、その出発点の一つにもなりえます。このときオブジェクト(対象)であったものが、別のオブジェクトに向かう主体へと役割を替えるというふうにも考えられるでしょう──こうした対は、可換的なものとして一緒に、相関的に考えざるをえない。しかしそうした対そのものもまた複数あり、しかもそれらがどうやら重なりあっているようなのです。
セールは準-客体論というかたちで、こうした関係をモデル化しました★1。近年人類学と哲学の双方で影響力を増しつつある哲学者ブルーノ・ラトゥールはこうした問題意識をふまえ、主体と対象が実際には厳密には分離できない、ハイブリッドなものだということを指摘しています。そうして彼が産み出した理論がアクター・ネットワーク論ですね。
デューリング──ラトゥールの概念でいう、中心的な「アクタント」と周縁的な「エージェンシー」(行為体)が可換的であることを踏まえるなら、アクター・ネットワーク理論は主体-客体の構造よりももっと根本的なものだと思います。
清水──デューリングさんのプロトタイプ論で、とりわけ僕が面白いと思ったのは、アラン・バディウの批判を継承しつつ、ロマン主義について議論をしているあたりです。デューリングさんはここで、有限性と無限性の話をしていますよね。有限と無限は、もちろん二項対立的なものですが、ロマン主義はこれらを二項対立的なまま繋いでしまう。有限の表象が繰り返し限定されていく操作が、そのまま外部へ、無限への〈開かれ〉でもあるというふうに、両者を短絡させてしまうのです★2。ロマン主義は、提示されるものの有限性を自覚的に強調してみせることで、無限性が表現されるという発想にもとづいている。芸術はそこでは、そうした限定や断絶、異なる文脈のもとでの読み替えといった身振りを伴いつつ、徐々に外部へ開かれていくという、たんなるパフォーマンスになります。芸術がただのプラクシス(実践)になってしまっているという、あなたの指摘はもっともだと思います。
デューリング──ロマン主義もプラクシス中心主義である、とおっしゃりたいんですね。
- オブジェクトの中のプロジェクト──反プロセスとしてのプロトタイプ論/有限と無限──同時存在するパースペクティヴ/プロトタイプ・オブジェクトがつくる多極的な世界観
- プロトタイプ、オブジェクト指向哲学、幹-形而上学──ロマン主義批判としての/準-客体、アクター・ネットワーク、離接的綜合/動く身体の生態系としての建築──視覚のスピードと身体的なマテリアルの合流
- 新しいパースペクティヴィズムへ──連動と断絶のトポロジー的探求/個に内在する複数の存在論/「関係」のイデオロギーとハイブリッドの「切断」──アーキテクチャーのプロトタイプ
- メタ・スタビリティと結晶化の萌芽/21世紀のアート、建築、哲学が向かっている方向


