en[縁]:アート・オブ・ネクサス──「質感」と「リズム」の建築
人の生活や物語性がモノに刻まれていく
篠原(雅)──ラトゥールは、人間と自然という区別は成り立たないとする立場です。彼は、人間の生活というのは自然との連関のなかで営まれているという話をしていて、そのときにモノがもつ「手触り」──「質感」や「リズム」とも言えるかもしれませんが──が立ち現われてくると言っている。それは人間世界と無関係のところで生じているわけではなくて、人間がつくりだすことで出てくるものだと言える。先ほど篠原さんと今村さんがしてくれた里山の話ではありませんが、人の生活や物語性がモノに刻まれていき、それを介して継承されていく。簡単に整理すると、そういうことではないのでしょうか。
- 能作文徳氏
私はオブジェクト指向存在論をそれほど理解できているわけではないですが、人が認識できないモノの不思議さから思考を始めようというのが狙いではないかと思います。クァンタン・メイヤスーの提示した「祖先以前性」という概念があります。例えば、46億年前に地球が誕生して、27億年前に酸素が生成され、そこから海中の酸素濃度が高まり溶解していた鉄が固体化して堆積して鉄鉱石の原料ができ......というような現象は、人間が生存するはるか前に起こったことですね。そういう人間とは関係のないところで起こるモノの不思議さをどうやって受け止めるか、オブジェクトがもつ不思議さをどうやって考えるかということが、「オブジェクト指向存在論」では提示されていると思うんです。
私はラトゥールの「アクターネットワーク論」と「オブジェクト指向存在論」のオブジェクトの不思議さという話は、交差するところがあると考えています。どういうことかというと、モノにはそれぞれ性質や傾向があって、例えば石というのは重くて硬いものです。そうなると動かすにも切るにも大変な労力が要る。莫大な労働力が必要になると、それを組織する権力が必要です。そういう「重い」とか「硬い」というモノの性質が人に抵抗することを通して、人とモノのネットワークが生み出されていく。そのようなネットワークが積み重なって、例えばピラミッドのようなものまでつくってしまう。そういう意味で、人間の世界でつくり上げられた社会的なネットワークはモノの世界と切り離せない。
篠原(雅)──そうすると、やっぱりそれはモノそのものとは言えない気がするんですよね。モノが不思議さを帯びるのは、人間が関わるからじゃないのかな。
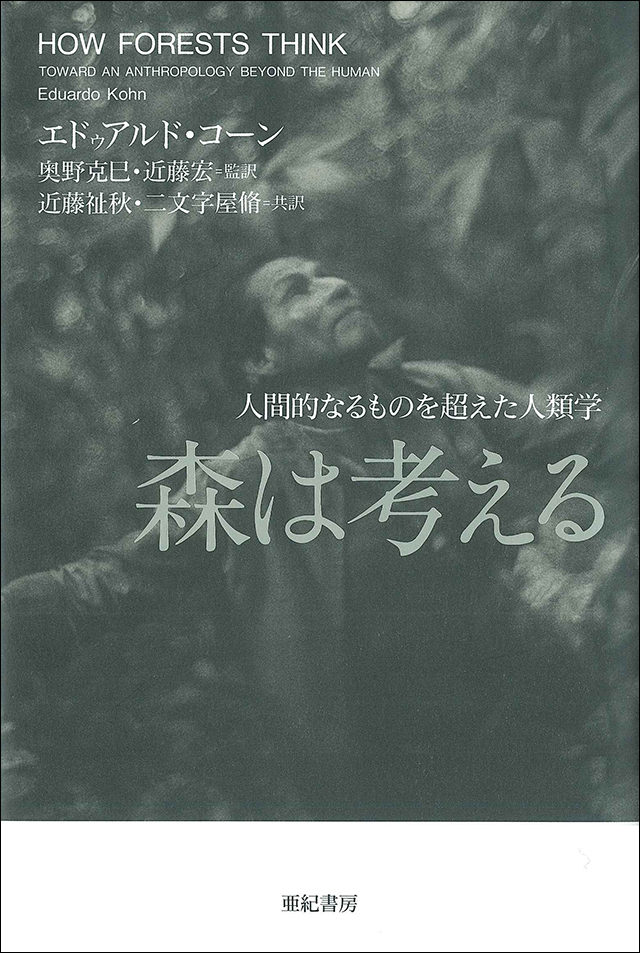
- fig.19──エドゥアルド・コーン
『森は考える──人間的なるものを
超えた人類学』(奥野克巳+近藤宏監訳、
近藤祉秋+二文字屋脩訳、
亜紀書房、2016)
それを踏まえて言うと、建築の場合は、必ず人とモノのセットで考える必要があるわけです。人なりの自然観やモノへの感受性を作動させることによってしか建築はできない。モノの「質感」というのも、そういうことだと思うんです。そこには、人なりの感じ方が含まれています。
質感と時間、具体性を伴った建築

- 金野千恵氏
伊藤──ちょっと個人的な話になりますが、以前、私はヨコミゾマコトさんの事務所にいて、《富弘美術館》(2005)という建物の仕事を担当していました。丸い部屋が連なっている建物で、壁の厚みを極力薄くして、シングルライン★1でプランがつくれるような、抽象の極致みたいな建築です。ただ、その抽象性を確保するために、どうやって鉄骨を組むか、どこに断熱を入れるか、具体的な検討をたくさんするわけです。図面上でダブルライン、トリプルライン★2の検討を重ねて、現場で職人さんたちと具体的な検討をしまくって、しかし最後はボードを張って塗装して、何ごともなかったかのようにツルッとしたシングルラインで表現できる建築にする。そのボードを張る前の状態が、結構かっこよかったんです。そのときに、これはこれでひとつの建築の価値なんじゃないかということをぼんやりと思っていたんです。現場の人には抽象性なんて関係ありませんから、「これにボードを張るの? もったいない」とみんな言う。それでいざボードを張ってみたら、背後にあるさまざまな要素が全部消えて、ものすごく抽象的な、それこそシングルラインの空間が登場して、それはそれで感動したのですが、一方で仕上げる前のあの姿も忘れられなくて。モノがどういうふうに成り立っているのかということがそのまま建築の価値になれば、ひょっとしたら職人や大工、クライアントやユーザーなど、抽象性への志向が高くない人たちにも何か訴えかけるものになるんじゃないかとそのときに思ったわけです。
多分、ものをつくっている人たちって、みんなそういう感性をもっているんじゃないでしょうか。これまではボードを張らなきゃいけないとか、建築に対してfinishedなものを求める傾向があったと思うのですが、もっと違った価値があるということが受け入れられてきた感じがします。
結局、シングルラインの建築を突き詰めていくと、家具は置けないしご飯も食べられない、建築と生活とが乖離した空間になってしまう。それが現在では、日々の生活や営みやふるまいが建築に力を及ぼすようになってきています。そのことを考えないと、説得力のある建築をつくれなくなってきているんじゃないかという感覚はすごくありますね。

- 篠原勲氏
私は、具体性はもちろんですが、やっぱり抽象性も大切だと考えています。私たちが手がけた《駒沢公園の家》は、中央の部屋がシナ合板を張ってできているんですね。この規模だとパテ処理の手間代が高いので、小口処理のいらないシナ合板を突きつけ★3とし、白く塗ってもつなぎ目が出るデザインとしています。シナ合板の幅は普通910mmなので3枚張ると2,730mmになります。ところが、部屋の幅は2,100mmしかない。そのため、つなぎ目が等間隔で出るように、1枚700mmに切ってもらっているんですね。それを見て2人とも「どうして等間隔にするのか」と驚いていて、そのことが逆に衝撃的でした(笑)。
伊藤──私も抽象性を信じてはいるのですが、シングルラインで抽象的な図面を描いてそれを建築にすると、どうしても抽象概念の劣化版になってしまう。それじゃあ面白くないなあと思っていて、最近は具体性の先にある抽象というか、具体的なものをとことん積み上げていくと、最終的には抽象的な領域に行けるんじゃないかというような感覚があります。
能作──私も自分のなかに抽象性がまったくないとは思わないし、むしろ抽象的に考えているほうだと思っています。モノに対する扱い方が以前とは違ってきているだけだと思っています。
伊藤──抽象性をどこに見出すかということもありますね。モノの形が抽象的であるのか、ネットワーク=縁のつくり方が抽象的であるのか。そういう違いはあると思います。
個別解からスタートし、人とモノの網の目につなげる

- ヴェネチア・ビエンナーレ日本館
能作──壁を白く塗るという操作も、そうすることの背後には、一般化したい、普遍化したいという意図があります。素材がそのまま現われるとモノ性が出すぎてしまうので、漂白したくなるということです。ただ、私は、すべて個別解でいいのだと思い始めています。個別解というと建築一般の問題として広がりがないと思われがちですが、そういうことはない。なぜかというと、出発点がどれだけ個別であっても、その個別の物事のネットワークを辿っていけば、必ず社会や産業や自然といった広い領域につながるからです。そう考えれば、モノそのものからスタートできるわけで、白く塗る必要もない。つまり一般化すること、普遍化することをあらかじめ建築に定着する必要はないと思っています。自分にとって、そこが今までの世界観や建築観とかなり変わってきた部分かなと思っています。
篠原(雅)──それがネットワークの話とどうつながるのか、もう少し詳しく説明していただけますか。
能作──私は人とモノの網の目というのがすでにあって、建築を通してそれをどう組み替えたり、形を与えたりするかというふうに考えています。ネットワークというのは際限なく張り巡らされています。その複雑なネットワークのなかで、何かを普遍化しようと努力してもあまり意味がない。そうではなく、ネットワークのある一点から遡ってつなげていくことで、人やモノが連関した社会の領域がおのずと見えてくるはずだと考えています。
伊藤──網の目が張り巡らされているなかで建築をつくろうとするときに、ちょっと前の時代だったら、無数にある網の目のなかから一本だけを選んでつくっていたのが、今はどれだけたくさんの関係の糸を引っ張ってこれるかという方向にシフトしているとも言えるのかな。
能作──今回ビエンナーレに参加している建築家は、ネットワークがあることを前提に、建築をつくっている。とはいえ、既存のネットワークのなかでつくってしまうと社会に従属したものにしかならない。いろいろ関係性を組み替えることによって、新しい空間像や社会像を切り拓こうとしている。それこそが作品であり「詩」であると言いたい。
伊藤──その辺の案配に作家性のようなものが出るのかもしれませんね。
今村──そうですね。先ほどの《駒沢公園の家》の例で言うと、天井の色は、当初は塗らないで素材現わしにするつもりだったのですが、下地の組み方や木目が具体的すぎて重たく感じてしまい、白く塗りました。そのあたりを一つひとつ調整していかないと、うまく全体がつくれない。
能作──おそらく今言われた「白さ」というのは、抽象化のための白さというよりも、どちらかといえば快適さにつながるような白さではないでしょうか。白い空間には軽やかさがあります。そのように白さを考えると、一般化や普遍化とはまた違ったふうな捉え方ができる。つまり、白=抽象というわけではなく、「白いペンキで塗る」という質感が強調されれば、そこには具体性が立ち現われてくる。
篠原(雅)──それは面白い指摘ですね。確かに「白さ」そのものと「白く塗る」ことは違う。「白く塗る」ということは、人とモノとの関わりのなかから出てくるものと言えるかもしれません。それはたんにネットワークに従属するということではない。建築家はそこでモノに促されながら能動性を発揮することになるわけで、いわば「他動詞的な能動性」とでも言うべき力を発揮する。建築家は今ではネットワークに組み込まれながら能動性を発揮する存在になっているということでしょうかね。それは今回皆さんの作品を見せてもらうなかで私も感じたことです。
しかし、強調しなければならないのは、それはたんにネットワークがあるというだけの話ではないということです。そこでどうリズムを調整したり物語を紡いでいくのか、そこに建築家の主体性、独自性があると言える。今回の展示では、そこが見せられたのはよかったなと思っています。
最後にまとめとして、ひと言ずついただけますか。
さまざまなモノと時間・空間的につながっている

- 伊藤暁氏
言ってみれば、私たちが活動している神山という場所も、日本の国土計画から言ったらバグのかたまりみたいな場所で、高齢化と過疎化が進み、将来的には消滅する可能性もある。しかし、そういうバグだらけの場所であっても、そこで活動している現地の人を見ると、みんなすごくいきいきしていて、自分たちの置かれた状況をポジティヴに読み替え、それこそハッキングしているように見える。プログラムを書く、バグを直すというと、どこかfinishすることが前提になっている気がするのですが、今後はある状況のなかでいかにネットワークを組み替え続けていくかということがますます求められるのではないかと思っています。
今村──今回のビエンナーレは「縁」というテーマでしたが、現在はさまざまなモノと空間的にも時間的にもすでにつながってしまっています。そのことを知り抜いたうえで、そこにある関係性を読み解いて新たな形に落としていくという、センシティヴなつくり方が建築家には求められているのかなと、今日のお話を聞いていて思いました。以前は、時間も空間も広大な領域につながっているんだという意識ってあまりなかったので、そのことにきちんと向き合いたいと思いました。そのつながりを変える責任について、いつも自覚していたいと思います。
篠原(勲)──建築というのは、人が使ったり手入れをすることで美しいと感じる状態になるのだと思います。「縁」というのは、人が手を加え続けること、そしてそれを丁寧に行なうことが重要なのではないかと思っています。
金野──私は今回出展作家という立場ではなくて、状況を読み解くという役回りでもあったのですが、皆さんの建築に向き合うスタンスには非常に共感し、学ぶところが多かったです。建築に、独立して建つ強さが求められていた時代もありましたが、今は時間を含んだ周縁のモノ・ことと建築とをどうつないでいくかが問われている。そのためのフレームをどうセッティングしていけるかに建築家は足を踏み入れ始めていると感じました。
一方で、その新しい建築の枠組みの表現は、もう一歩、開発不足だったと思う部分もあって、自立した建築に相当する、あるいは超えるくらい強さがあることを見せるには、何ができるのか。それは今後の機会を通した課題でもあり、また自分自身の建築のあり方を表明するうえでの課題だと思っています。
能作──今回のビエンナーレの展示を見ていて思ったのは、世界的に課題がある程度共有されているという点です。準備段階で皆さんのプロジェクトを見せてもらうなかで、日本の問題や状況を世界に提示する機会なんだという姿勢で臨んでいました。蓋を開けてみたら、世界で似たような現象が起こっている。
一方で、先月フィリピンのマニラに行ったのですが、生きることに必死にならざるをえない状況を目の当たりにして、とてもショックを受けたんです。世界的には環境配慮型の建築をつくりましょうと言われていますが、マニラでは断熱材なしのコンクリートそのままの室内環境で、みんなクーラーをガンガン付けっぱなしにしているわけです。また空調によって調整された室内環境にいられる人は中流以上の階級の人です。世界には多くの対立や格差があります。ビエンナーレで共有された問題系がある一方で、それとは別の問題系もまだたくさん残されているように感じます。私は、エコロジーとネットワークというのはすごく近い考え方だと思っています。地球環境問題に取り組む運動も、現在はヨーロッパをはじめとする先進国主導でやっているけれども、依然としてそこにはさまざまな問題点や限界がある。地球環境と経済格差、人間の権利と自然の権利がどう見積もられるべきかなど、複雑な対立です。それについては引き続き考えていきたいと思っています。
篠原(雅)──今日は非常に濃密な議論を聞けたと思っています。長い時間、ありがとうございました。
[6月10日、LIXIL:GINZAにて]
註
★1──壁の厚みを省いて描く抽象化された図面。縮尺の小さな図面で用いられる。
★2──ダブルラインは壁の厚みを示した図面。トリプルラインは壁の中の仕様を示す図面で、主に施工の際に用いられる縮尺の大きな図面で用いられる。
★3──二つの部材を直接接着剤や釘などで接合すること
篠原雅武(しのはら・まさたけ)
1975年、神奈川県生まれ。哲学、思想史、都市空間論。大阪大学公共政策研究科特任准教授。主な著書=『公共空間の政治理論』(人文書院、2007)、『空間のために:遍在化するスラム的世界のなかで』(以文社、2011)、『全-生活論:転形期の公共空間』(以文社、2012)、『生きられたニュータウン:未来空間の哲学』(青土社、2015)。編著=『en[縁]:アート・オブ・ネクサス』(TOTO出版、2016)。Website:http://masatakeshinohara.tumblr.com/
今村水紀(いまむら・みずき)
1975年、神奈川県生まれ。建築家、篠原勲とともにmiCo.共同主宰。女子美術大学、日本工業大学、明治大学、東京理科大学、日本大学非常勤講師。2001―08年、妹島和世建築設計事務所勤務。2011年、SDレビュー入選。主な作品=《駒沢公園の家》(2011)、《原宿のサロン》(2012)、《久我山の住宅》(2014)ほか。Website:http://micomico.co.jp/
篠原勲(しのはら・いさお)
1977年、愛知県生まれ。建築家、今村水紀とともにmiCo.共同主宰。女子美術大学、東京理科大学、昭和女子大学非常勤講師。2003―12年、SANAA勤務。2011年、SDレビュー入選。主な作品=《駒沢公園の家》(2011)、《原宿のサロン》(2012)、《久我山の住宅》(2014)ほか。Website:http://micomico.co.jp/
伊藤暁(いとう・さとる)
1976年、東京都生まれ。建築家、伊藤暁建築設計事務所主宰。首都大学東京、東洋大学非常勤講師。2002-06年aat+ヨコミゾマコト建築設計事務所勤務。須磨一清、坂東幸輔とともに建築ユニット・バスアーキテクツを結成。主な作品=《えんがわオフィス》(2013、バスアーキテクツ)、《横浜の住宅》(2014)、《WEEK神山》(2015、バスアーキテクツ)。Website:http://www.satoruito.com/
金野千恵(こんの・ちえ)
1981年、神奈川県生まれ。アリソン理恵とともにteco共同主宰。日本工業大学助教。2011年、東京工業大学院博士課程修了、博士(工学)取得。2011-12年神戸芸術工科大学大学院助手。2011年、クイーンズランド大学客員研究員。主な作品=《向陽ロッジアハウス》(2011)、《amu》(2015)、《KMK》(2016―)、「水戸新市民会館コンペ優秀賞」(能作建築設計事務所と協働、2016)Website:http://te-co.jp/
能作文徳(のうさく・ふみのり)
1982年、富山県生まれ。建築家、能作文徳建築設計事務所主宰。東京工業大学大学院建築学系助教。2008年、Njiric+Arhitekti勤務。2012年、東京工業大学院博士課程修了、博士(工学)取得。2013年、SDレビュー2013鹿島賞。主な作品=《ホールのある住宅》(2010)、《Steel House》(2012)、《高岡のゲストハウス》(能作淳平と協働、2016)、「水戸新市民会館コンペ優秀賞」(tecoと協働、2016)ほか。Website:http://nousaku.web.fc2.com/
- 前線からの報告
- コンパクトであることの詩性
- スペイン館の展示「Unfinished」
- en[縁]という言葉のとらえ方
- 人の生活や物語性がモノに刻まれていく


