en[縁]:アート・オブ・ネクサス──「質感」と「リズム」の建築
en[縁]という言葉のとらえ方

- ヴェネチア・ビエンナーレ日本館
能作──「縁」という言葉に対して、ある世代以上の人たちは警戒感をもっていると指摘されました。どういうことか私なりに整理すると、1960年代、経済成長時代の急激な都市化にともなって、都市では人どうしのつながり、つまり「縁」が喪失した状態になっていきました。都市が人間性の喪失を生み出すとさえ思われていました。そこで住宅や集合住宅を建てる際に、一部の建築家や計画学者はコミュニティを構築できる環境をあらかじめ計画しようとしました。けれども、他人どうしが住むということでさまざまな軋轢やすれ違いが生じて、そうした試みはことごとく失敗してきたと言われました。(並行して大きな都市計画を指向するメタボリズムがありましたが、そちらも成功とはいえないでしょう)。そのような状況では、建築家がコミュニティに軸足を置いて建築を構想することが難しくなっていったと思われます。そして70年代くらいになると建築の自律性ということが言われるようになった。そういう文脈があるなかで、コミュニティをつくることに対する不信感があるのだと思います。だから「縁」という言葉に警戒感をもつ人たちが多いのではないかと捉えています。
伊藤──私もそういう警戒感や後ろめたさは共有していますね。それが世代なのか個人的なものなのかはわかりませんが。ただ、ビエンナーレを経験して思ったのは、日本の、とくに建築界隈において「縁」という言葉は、いろいろな意味がこびり付いているので変に身構えてしまうのですが、そういう含意を共有していない外国人に日本館のプロジェクトを説明するときにはものすごく便利な言葉だということです。コミュニティや人とのつながりというのは、否定しようのない「よいもの」なわけですね。しかし、そうした否定できないものに無条件に寄り添ってしまうことは、80、90年代に経済に寄り添いすぎたポストモダンの失敗を知っている身としては、とても危うくも感じられる。そんなこともあって、警戒されている風潮がある気がします。
篠原雅武さんが書かれた文章「縁の空間論」(山名善之ほか編『en[縁]:アート・オブ・ネクサス』TOTO出版、2016)でも、「縁」には「へり」や「ふち」という意味もあって、つながることだけではなくて切れること、分割することも含意されていると書かれていましたが、そういう両義的な解釈ができる言葉ですよね。今の日本の状況では、「縁≒絆」という認識があるので警戒してしまうわけですが、「縁」という言葉からどういう意味を読み取るかは、じつは私たち次第というところがある。
篠原(雅)──2013年に塚本由晴さんと対談したことがあって(「対談:空間と個と全体──コモナリティのほうへ」)、そのときに塚本さんは、「個」へと切り離されていく住宅の状況への反発から建築を始めたけれど、だからといって、個と正反対の方向にいってしまうのも違うんじゃないかと話されていました。それだとたんに拡張された全体のなかに個が統合されていくというモデルになってしまうわけで、60年代にあったようなコミュニティ路線──メタボリズムもある意味そうなんじゃないかという気がしますが──と変わらなくなってしまう。
近代化を信じていた世代から見ると、「縁」的なものというのは封建制につながる否定すべきものです。ところが、われわれは近代を当たり前のものとして生きてしまっている感覚があって、だからこそ近代特有の歪みをも感じている。その歪みは、日本の近代特有の捻れといいますか、完全に近代化されずにイヤな封建的なメンタリティが残滓として残っているとか、形だけ近代化して精神性が伴わないとか、挙げだすときりがない。そのときに、封建的な意味での「縁」に立ち返ろうなんて一切思いませんが──そもそもそれがどういうものか感覚的にわからないわけですから──、近代主義的なロジックを解体するために「縁」という言葉を使ってみるのも、そこに若干なりともアイロニカルなニュアンスをこめることができればそれはそれで面白いんじゃないかと思います(素朴に縁などといってしまうと、すごくつまらないですね)。
能作──一般的に「縁」と言われるときには、人のつながり、「人の縁」というイメージが強いですよね。実際、「縁」という言葉から「インタラクティブ」アートのような展示を想起された方もいたようでした。「モノの縁」はまたそれとは違う部分だと思います。モノが起点となり、モノどうしやモノと人がつながっていくという「縁」です。また「アート・オブ・ネクサス」の「アート」は、芸術という意味合いだけではなく、技術や技能という意味で捉えています。モノと人をつないでいるのは、技能であり感受性です。私の建築観は、モノがあって、それに影響を受けて人のあり方が変わっていき、それでまた人がモノをつくっていくというモノと人とが相互に連関したものです。なので、私は最初「縁」というキーワードを聞いたときに、まさにそうしたモノと人との連関につなげたいと思いました。
今村──今回参加した人たちのインタビューを読むと、それぞれの「縁」の捉え方が少しずつ違いますよね。それから、篠原さんが『en[縁]:アート・オブ・ネクサス』中の「人の縁」の章で書いていた文章を読むと、人の縁をつくるものとしてモノの連関があるというように、モノにフォーカスして書かれています。そこが面白くて、「人の縁」や「地域の縁」というと、一瞬ベタな縁を思い浮かべてしまいがちだけれど、違う切り口が入り込んでいたように感じたんです。
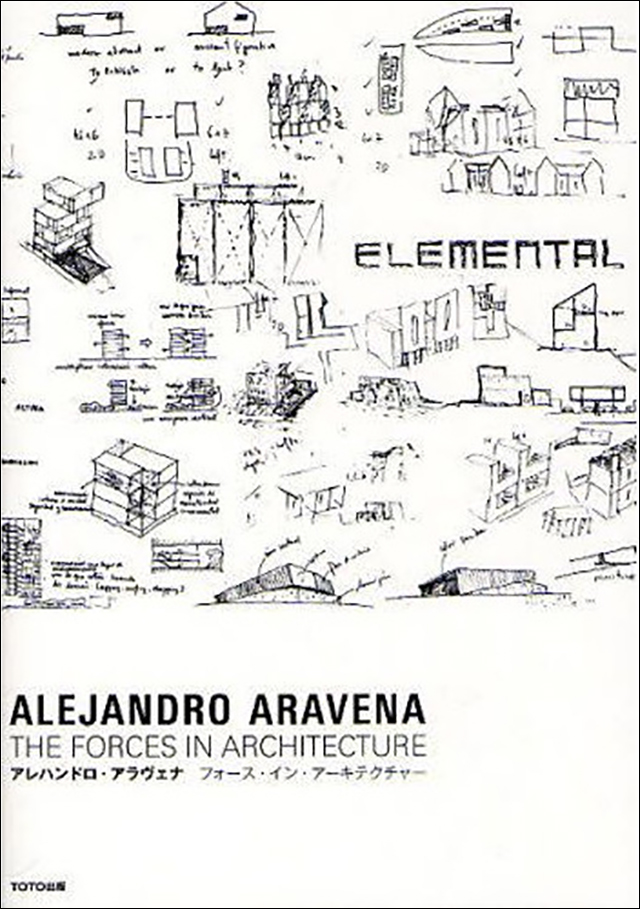
- fig.18──『アレハンドロ・アラヴェナ
──フォース・イン・アーキテクチャー』
(TOTO出版、2011)
アラヴェナは形(form)の話をしています(『アレハンドロ・アラヴェナ──フォース・イン・アーキテクチャー』TOTO出版、2011)[fig.18]。20世紀の建築のようにイメージをつくるための形として建築を扱うのか、マテリアルと人をつなげていく先に建築を考えていくのかに大きな違いがあります。それはすでにあるマテリアルから「質」を生み出すことと関係していると思います。形はマテリアルによって「質」を生み出す媒介でしかない。なので「こういう形をつくりたい」とか「こういうイメージにしたい」というよりも、どのような質、どのような連関を生み出していくかに私は着目しています。建築の形は連関のなかで湧き上がるようにできてほしい。
金野──今回、作品を実際に拝見させていただくなかで印象的だったのが、「神山町プロジェクト」と《馬木キャンプ》です。これらを続けて見学した2日間で、これまでの「建築」の捉えていた範疇を軽々と拡張していると感じました。作品を案内してもらうのに、まず寄り道ばかりして、なかなか辿り着かない(笑)。「ここから見る街の風景がいいんだ」、「この小屋がイチオシなんだ」、「ここのパンがおいしい」、そして地域のたくさんの方との立ち話、などなど。そこでの生活や営みを如何に紡いでいくかがとても重要なんです。ひとつの完結した建築作品をつくっているというよりも、モノや人や環境や風景といった、暮らしを紡ぐプレーヤーのひとつとして建築が位置づけられているという印象を受けました。逆に、どんなに小さな建築でも、取り組みの方法次第で、大きなストーリーに接続しうる可能性を提示している、とも感じられました。
モノの哲学──アクターネットワークとオブジェクト指向存在論

- 篠原雅武氏
それに関して最近気になったことを2点ほど挙げると、ひとつはブルーノ・ラトゥールとアルヴェナ・ヤネヴァの"Give me a Gun and I will Make All Buildings Move : An ANT's View of Architecture," という論文です。いまや建築においては現象学的な空間論(メルロー=ポンティなど)からの転換が起こっていて、それに代わって建築を「thingly nature(モノ性)」で捉える段階に入ったと彼は言うわけです。現象学では人間の内面性の反映として空間を捉えていって、それを多木浩二は「生きられた空間」と言っていましたが、これに対してラトゥールは、人間の内面性と接点をもっているのかもってないのかわからないところにモノを位置づけます。このモノ性において、今の建築が成り立っていると考えたほうがいいと、ラトゥールは言います。
もうひとつのエピソードとして、ラトゥールとペーター・スローターダイクというドイツの哲学者がハーバード大学GSD(デザイン大学院)に呼ばれて講演をしたことがあるんですね("Philosophers expand meaning of 'space'")。スローターダイクは人間の生きている「環世界(Umwelt)」について議論を展開するなど、ラトゥールと並んで欧米では注目されています。スローターダイクは例えば"Architecture As an Art of Immersion"という文章のなかで、今や建築の世界では、全体主義体制への嫌悪から多くの人がインテリア志向になり、私的空間の心地よさを求めている。それで、インテリアの生産が重要になった、と言っています。限定された領域内で心地よさを演出するということです。そしてスローターダイクは最後のほうで、建築は「浸透状態(immersion)」のデザインである、空間の生産の倫理の一部は、その雰囲気への責任にある、と言っています。雰囲気の生産ということですが、これも人間の内面性というより、建築が発する何ものかのことで、やはり「モノ」性に着目している。
また、モノの哲学ということでいうと、最近ではグレアム・ハーマンやティモシー・モートンなどによるオブジェクト指向存在論(object-oriented ontology)なども注目されています。自分なりに今日の議論に引きつけて解釈すると、思想の世界でも、モノの「手触り」への関心がどうしようもなく出てきてしまっているということなのではないでしょうか。モノの「手触り」に直面せざるをえないような現実をわれわれが生きていることに今更ながら気づいてしまったことへの自覚から、そのなかで生活する場をつくっていくことの条件をめぐる議論として私は受けとめています。
ただ、そのときモノの「手触り」と言うからには、そこで人間がなんらかのかたちで関わっているわけですね。モートンの議論では、人間が関わりつつも関わらないという絶妙なところにモノの世界が設定されています。例えば、「a weird entity withdrawn from access, yet somehow manifest」と、彼は"An Object-Oriented Defense of poetry"という文章のなかで言い表わしています。人が接近しようにもそこから逃れてしまうが、それでも、なんとなくではあれ存在感を出している。彼の議論を踏まえて言うなら、この奇妙さのなかで建築をどう展開していくかということが問われているのではないでしょうか。ちなみに建築に関するモートンの見解は次のインタビュー"Timothy Morton on haunted architecture, dark ecology, and other objects"で見ることができます。

- 今村水紀氏
- 前線からの報告
- コンパクトであることの詩性
- スペイン館の展示「Unfinished」
- en[縁]という言葉のとらえ方
- 人の生活や物語性がモノに刻まれていく


