ウォーフェアからウェルフェアへ──戦中と戦後、空間と言説
戦前から戦後の連続性
──昨年は戦後70年という節目の年でした。ジャーナリズムや言説の世界では数多くの言及や特集が組まれました。とりわけ、現代美術の世界では「戦後70年」にフォーカスした展覧会やイベントが多数ありました。たとえば「戦争画」が改めて注目されて、『戦争画とニッポン』(会田誠、椹木野衣著、講談社、2015)という本が出版されたり、『日本美術全集』(小学館)の18巻は1冊丸ごと「戦争と美術(戦前・戦中)」です。しかし、僕の見たかぎり、建築の領域はこの問題に対してほとんど無関心だったように思いました。
本日は、建築史--建築批評の第一線でお仕事をされている八束さん・青井さんにこの問題に関連して、戦時下の建築家は戦争に対してどういうスタンスだったのか、さらには、戦後、建築史--建築批評は「戦争」に対してどのような総括を行ったのか等々について討議いただきたいと思います。歴史修正主義的な言説に抗する、戦争と建築を考えるための序論、若い人たちに向けたきっかけになればと思います。
青井哲人──たしかに「戦争と建築」というような主題の立て方は建築ではほとんど見られないですね。「戦後史」なら、雑誌『建築ジャーナル』では1年間にわたり「戦後建築の70年」という連載があり、また金沢21世紀美術館では「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」展が行われました。戦後史の見直しは今後進むと思っていますが、時間がかかりそうです。いずれにせよ、今日は「戦争」ですね。
八束はじめ──いきなり建築の問題にしてしまうのではなく、「戦争」をキーにして時代そのものをどう考えるかを議論しないといけないでしょうね。僕は、日本に限って言えば、戦争が終わって時代がひっくり返ったのではなく、かなりの部分が「折り返し」として、反復されていると考えています。「戦後」をいつまでとするかと言えば、1965年あたりまでではないか。「戦後は終った」という『経済白書』は56年で、これはこれで戦災復興が一息ついたということでしょうけど、まだまだ朝鮮戦争の余波とかキューバ危機とかが残されていた。1965年には、僕は高校生でしたが、世代的にギリギリその空気に触れていた感じです。これは問題がある言い方かもしれませんが、戦後世代は一億総懺悔で、民主主義を問うてきた左翼文化がありますが、僕は、それはうまくいかなかったと考えています。
それともうひとつ、今も世界中で一向に戦争はなくなりませんが、それはネーションステート同士の戦争ではありません。65年をまたいでいるベトナム戦争は日本の高度成長と表裏一体関係にあったわけだけれども、既に先進国同士の戦争とは違う。イデオロギー的には東西間の戦争ではあるけれども、不均衡な戦いという意味では南北間の戦争でもある。テロを含めた今の戦争の様相ということになると、枠組が全く違うので、建築の問題にせよ立て方が変わってくる。ですから、たとえば、今改めて日本の建築界の戦争責任を考える、というようなことでは何も始まらない気がします。
歴史を見れば、第一次世界大戦に関してエーリヒ・ルーデンドルフが「総力戦」と言ったように、ネーションステート同士の戦いがあり、その中で、建築や都市計画、国土計画がつくられていきます。まさに「総力」なので、文化や経済もすべて含まれます。そのようなネーションステートの構造は大部分、日本の戦前・戦中・戦後にも受け継がれています。けれども、それは今まで引っぱって来れる構図ではない。
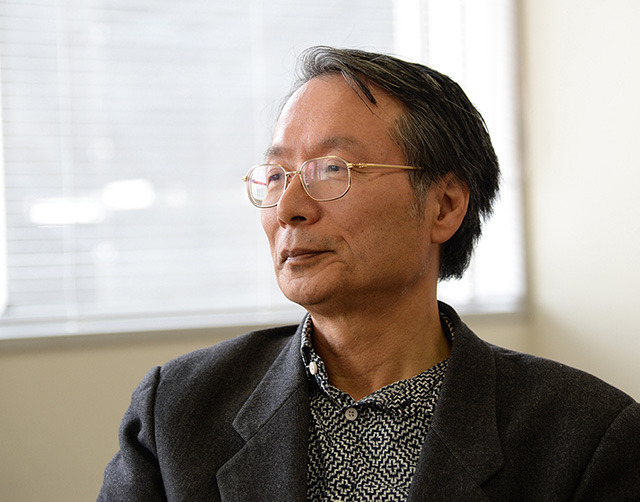
- 八束はじめ氏
──戦争責任と建築家ということで言えば、たとえばアルベルト・シュペーアは裁判にかけられ、徹底的に追求され、終身刑に処されています。
八束──でもシュペーアは建築家として裁かれたわけではなく、ヒトラー内閣の閣僚として裁判にかけられたわけです。ナチ党大会の会場デザインや首都ベルリンの大改造を手がけたことではなく、ヒトラー政権の軍需大臣として、兵站(Military Logistics)など、近代的なインフラ組織や物資の輸送を束ねたという問題だったのだと思います。ただ、それは実はもっと大きな意味で建築に関わると思う。こうした大きなメカニズムを動かしていくような仕事は、実は建築家に向いていて、丹下健三さんにもそういう面があったと思います。そういう意味では、戦争と建築的思考の関わりはすごく強い。
僕が書いた『メタボリズム・ネクサス』(オーム社、2011)の帯文を出版社が磯崎新さんに頼んだのですが、「建築=都市=国家・合体装置(メガストラクチュア)。20世紀の日本がただひとつ自慢できる発明ではあったが、どこの資本=ネーション=国家も、まだ使いこなせていない」と書いていました。あの時は何でこの文章がいきなり出てきたのか戸惑ったのですが、磯崎さんは東日本大震災直前あたりの頃から、「ヒトラーやスターリンは国家の建築家(アーキテクト)だった」と言い出しています。丹下研究室には、デザイナー系のグループ(磯崎さんもいた)と、プランナー系のグループがあり、丹下さんは両方をマスターしていたと思いますが、後者のロジックは国土計画などと密接に関わりますし、戦争と国家という大きな問題機制ともつながっている。戸惑ったというのは、磯崎さんはそちらの方ではなかったからですが、本当はこっちの方が大きな問題だと思います。
青井──そうですね。戦争責任という、それこそ戦後的な問題はいろいろあると思いますが、編集部から「若い人へ向けて」という話もありましたし、まずは大きく時代の構造をつかまえる地 図を描きたいですね。世界的にみても、19世紀的な自由主義体制が行き詰まり、30年前後から の世界的な恐慌の下で計画経済的な体制に転換し、それが戦後も装いを変えて維持されます。ウォーフェア(戦争)からウェルフェア(福祉)へ、ということですね。もっとも戦後日本の場合は欧米的な福祉国家体制よりも後進国的な開発独裁体制に近いと言われることも多いわけですが。先ほど八束さんは1965年頃までと言われましたが、おおむね30年代から60年代までの40年くらいをひとつの時代として括って考えることができますし、またそういう見方が重要だと思います。では、戦争を挟む40年間の計画主義の下で国土(帝国)から生活の隅々までがどう再編されようとしたのか、その大きな経済的・社会的な再編の枠組のなかで建築家やプランナーはどういう役割を担ったのか、そのなかで彼らはどんな表象や言説を組み立てたのか。面倒でもまずはこういう順序で考えてみる必要があると思います。

- 青井哲人氏
八束──表象論はわかりやすいですし、建築史はどうしても目に見えるものを対象にしがちなので、「戦争と建築」という問題の立て方をすると帝冠様式を容易に思い付きますが、実は核心というより末端の話だと思います。井上章一さんの議論では、それが軍部の意志だったかどうか、建築家たちの一人相撲ではなかったかが問われていますが、「戦争」の問題を「軍部」の横暴や暴走に限定してしまうのは問題の矮小化でしかない。逆に「一億総懺悔」みたいな議論も問題を曖昧にしてしまうと思うけれども、「戦争」の主体についてはもっと構造的な見方が必要なのではないか。
青井──逆に言うと、なぜこれまでの建築史がそうした構造的な問題を立て損ねてきたのか、言い換えると、戦後の言説空間がどう組み立てられ、どんなバイアスをつくってきたか、という問題をあぶり出す必要がありますね。そういう意味で、戦争を主題化することはこれまで書かれてきた歴史を批判することでもあります。
八束──僕は森美術館で行われた「メタボリズムの未来都市展──戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」(2011)に関わりました。磯崎さん以降、メタボリズムに対してはオプティミスティックで高度経済成長期の国家に乗った運動と批判されがちですが、メタボリストたちはそれぞれで違いますし、たとえば川添登さんの言説を見ていくと、1963年頃まではすごくペシミスティックです。メタボリズムの最初のパンフレットでも「地球の核戦争が起きて、宇宙人が来た時に残っているのは建築だけ」みたいなことを書いていますし、『建築の滅亡』(現代思潮社、1960)という著書もあります。朝鮮戦争(1950-1953)を経て、キューバ危機(1962)があり、冷戦下でいつ核戦争が起こるかわからない時代の実感があったのだと思います。高度経済成長は始まっていましたが、裏にはそうした影があったのです。1965年頃から国内的にはそうした暗い影が薄れていき、1970年大阪万博の祝祭へ向かっていきます。戦中の帝国主義的な空間再編と戦後復興はまさに同じコインの裏と表で、見過ごしてはいけないところです。わかりやすい肯定や否定、白黒の問題で見ようとすると捉え損なうと思います。
青井──1930年代から1945年までと、1945年から60年代とを比べると、後者は前者の連続と反転と反復を組み合せたような感じで、つまり大きくいえば構造が持続したということでしょうね。
八束──『小説岸信介常在戦場』(池田太郎著、社会評論社、2014)という小説がありますが、2007年の安倍首相の退陣から話が始まり、祖父の岸信介の戦中から戦後が描かれています。岸は、産業官僚として、関東軍を後ろ盾にして、満州を開発しようとします。その野心は終戦でダメになるのですが、岸はその後、日本を戦後の東西冷戦の前線に仕立てようとするCIAから金銭面でバックアップを受けます。関東軍がCIAにバックが替わり、政体は引っ繰り返っていても構造は同じです。それで高度経済成長への入口を実現していくという小説で、戦中と戦後がつながっていることがよくわかります。あくまで小説仕立てだし、岸が巣鴨拘置所から放免される前から既に満州の官僚たちが東京の中央に戻って活動しているので、もちろん厳密に史実に沿った分析というわけではないのですが、戦中と戦後が連続していることは岸信介という一人の政治家を見ても言えるという例ですね。「常在戦場」というのは、戦後も彼は戦場にいたということなのでしょう。岸が戦前同様戦後もファシストだったという評価は間違いではないでしょうが、そこからすぐに責任論(だけ)にもっていくと時代の構造を読み違える。
丹下健三についてもある意味で同じことが言えます。彼の建築を「真の帝冠様式」ということも、間違いではないけれども、それでことを済ませても何もならない。丹下さんは、造形家として卓越していただけではなく、もっと大きな文脈を構築していく関心と力があったのです。それが戦後社会が要請したものであったことは否定出来ない。


