戦術しかない/戦略しかない
──「問い」を開く黒い塊(ブラック・ブロック)
──「問い」を開く黒い塊(ブラック・ブロック)
この数年、アラブの春からオキュパイ運動の渦中にあった若い世代の活動家の話を聞いたり、かれらによるテキストを読んでいると、即座に気づくことになる顕著な現象がある。「戦術」に対する意識の高さと置かれた比重の大きさである。かれらはパソコンのディスプレイ上でたくみに都市のストラクチャーをレイヤリングしてみせ、どこでどのようなかたちの行動の可能性があるのかを論じ、旗やバナーについてどのような意味があるのか、どのようにしてヒエラルキー的組織を形成しないのか、などを、おどろくほどつきつめて考えている。もちろんわたしの触れたものが先鋭的な一部であるにしても、2011年の民衆叛乱前後から現在までの全体の傾向のある側面を具現しているのはまちがいないと思う(やや次元が違うが、2009年ごろソウルで大規模に展開された「ろうそくデモ」にたまたま居合せたことがあったが、若い活動家たちがラップトップのコンピュータで町中の監視カメラにアクセスして警察の動向を把握し、その配備のもっとも手薄なところをその都度ネットにアップすることで行動のための情報供与を行なっていたのも思いだす)。そしてその趨勢は、はっきりと戦略そのものをしりぞける部分をその極に持つに至っている。理念も戦略も不要である。われわれはただ行動の可能性を拡げることにしか関心がない、と。話を聞いてみると、それはアラブ諸国からヨーロッパ、ニューヨークに至るまで、じつに多様なかたちで権力とわたりあった末の冷徹な認識にもとづくものでもある。かれらは、もう運動はいらない、とさえ言うのである。運動は闘争ではない。運動は闘争を抑え込み、闘争を排除し、無効化する。わたしたちが一歩進むためには、運動から闘争を解放しなければならない、と。
わたしはいまこの含意を文脈の隅々までふまえたうえで明らかにする準備はないし、この趨勢についてじぶんなりの判断をすることもできないのだが、このような極は情勢の認識に照明を与えてくれる。すなわち、以上の趨勢を「戦術の過剰」というか「戦術がすべて」を極として持つものとすれば、他方の極には「戦略の過剰」あるいは「戦略がすべて」も想定できる。つまり戦略に戦術が完全に従属している状態である。たとえば、組織に指導された運動においては、戦略のためにもっとも効率的に奉仕すべく戦術がすべて統制される傾向にあるが、このとき戦術の独自性や自律性はほぼ無となる。あるいはマーケティングである。それは「戦略がすべて」の側にある発想であり、だれにどうアピールするか(買わせるか)のためにすべての戦術は動員され、目的にむかって奉仕するものでしかない。「見た目」に過剰な力点がかかるのは、戦術への拘泥ではなく、戦略がすべてであり戦術に自律性が存在しないことの徴候である。
戦術は行動の可能性であるわけだから、それが戦略に完全に統制されず相対的に自律するということは、行動の可能性そのものの領域が問題視されており、また、そのためのスペースが生まれているということである。谷川雁は1962年、三井三池闘争以後の炭鉱労働者による運動の後退局面にあって、次のように述べている。「だが状況がかくあるときこそ、固定観念をはらって見るならば、抑圧されつづけた大衆の戦術思想をよびがえらせる好機である。たとえば大正行動隊のとった戦術は、例外なく往昔の坑夫たち、現代の中小鉱の坑夫たちが私闘、公闘のなかでうみだした発想に根拠をもつといってよい。だが状況がかくあるときこそ、固定観念をはらって見るならば、抑圧されつづけた大衆の戦術思想をよびがえらせる好機である。たとえば大正行動隊のとった戦術は、例外なく往昔の坑夫たち、現代の中小鉱の坑夫たちが私闘、公闘のなかでうみだした発想に根拠をもつといってよい」(『影の越境をめぐって』現代思潮社、1963)。これまでの戦略戦術連関が袋小路に追いつめられたという状況認識のもとで、谷川雁は戦術の次元の独自のルーツや時間性に注目し、そこから戦略戦術連関総体を組み替えるよう提案している。つまり、デモ、ストライキ、ピケといった戦術が袋小路におちいったとき、ケンカまでふくむ坑夫たちの生活とその継承のうちに独特の厚みをもっているものとしてとらえ返され、さらに、そこに思想性の存在が示唆されているわけである。日本の近代史においても、しばしば逸脱的に突っ走る民衆の「土着」の戦術と近代的組織による戦略にもとづく統制の対立する場面がみられるが、谷川雁はこの「土着」の戦術のうちにそうした近代的組織を超えていく思想性すら見出さねばならないというのである。かように、ふつう戦略に従属して考えられている戦術、すなわち、目的と手段の関係において考えられている戦略と戦術だが、目的と手段の連関が機能不全におちいるような契機には、とりわけ戦術の次元の独自性が浮上してくるようだ。ただし、戦術そのものの自律的意味は、なんらかの抗争のあるところいつの時代にも伏在しているわけである。
たとえば、1960年安保闘争についてさまざまな資料を掘り返していると、この運動を「突破者」的に牽引した全学連主流派(ブント)について、かれら自身はどのように大仰な修辞によって世界革命の「戦略」を語っていたとしても、実践においては戦術に大きく傾斜していたことが感じとられる。かれらは膠着した状況をどう流動化させるかに全体重を傾け、実際にたびたび沈滞に襲われた1960年の安保闘争を1959年末の「国会突入」------ただしこれはブント単独の行動ではない------から羽田空港占拠、装甲車乗り越えなどでそのつど、流動化させ、闘争の終息とともに自己解体した。いまでは忘れられがちだが、国会突入によって事態が大きく流動化する直前までは、安保闘争は盛りあがらない(「安保は重い」)という諦念まじりの見方が反安保諸勢力のなかで拡がった観測であり、しかも一旦はずみがついても幾度かの沈滞を経ているのである。状況をつき動かす大きな動力でありながら、一貫して大メディアや革新側の大組織からは非難され罵倒されつづけた「不幸な主役」(清水幾太郎)としてのブントは、運動の終息とともに(というかそれを待たずして)たちまち解体した。実態としては、冷徹な認識にもとづく合意による決断というより、たんにズルズルの成り行きの産物だとは思うが、組織の存続が目的へと転倒し、しばしば事態の膠着に手を貸すヒエラルキー的組織に化してしまうことも往々にしてある日本社会においては、この「役割が終わったら解体する」こと自体意味があるように思われるし、そのような情勢に対して受動的に振りまわされ------しかもその弱みも曝けだしながら------場当たり的に突破口を開きながら消滅したこと自体もそれほど否定すべきことではないと思う。そしてまさにかれらは、そうした点を組織至上主義の観点からただただ弱点とのみ認識した党派からは「戦術左翼」と罵られていたわけである。
わたしたちはこの「戦術左翼」という特徴づけをニュートラルにとらえ返してみたいのだが、そうすると、この時期の全学連主流派が、現在「ブラック・ブロック」と呼ばれている潮流と類似している点をいくつか持っていることに気づく。それこそ世界中の占拠行動や抗議行動に黒づくめの匿名の集団として現われ、「過激」な行動で物議をかもすアナキスト「集団」とみなされているブラック・ブロックであるが、しかし、このようなプロフィールにはまずもって大きな誤解がある。そもそもそれは集団でも組織でもないからである。ブラック・ブロックとはたんに特定の戦術の名称であり、どのような組織に属していようがいまいが個人でこの戦術をとろうと考えるならブラック・ブロックを形成する一員となればよいのである。組織ではないからかれらを主体とした文書もあまり存在しない。ブラック・ブロックは抗争のあるところ、そのつど、趨勢の境界線を引き直し、膠着状態を突破し、可能性の領域を拡大し、そして消えていく。ある意味でいえば、ブラック・ブロックとはなんの戦略=目的にも従属せず、ただ戦術を通して「可能性」そのものを拡げるために存在するわけである。行動の空間の可能性、行動の多様な展開の可能性、そして究極的には、いまここにある実定的な世界以外の世界の可能性である。その世界がなにかを示すことはない。ただ可能性一般をひらく のみなのである。したがってそれは「革命組織」のようなものでもない。
「戦略の蒸発」というこのところの趨勢の文脈には、もちろん(より露骨となっている暴力の行使をともなう)管理技術の深化と同時に政治的無力化のいっそうの深化がある。そして、それにともなう、もはや可能性がすべて封じられたという憂鬱な感覚である。このような感覚は、たとえば「ISはアラブの春の灰燼からあらわれた」★1といわれるように、一挙に開花した可能性が一転して封じられ、希望のうちにかいまみられたビジョンとは真逆のものとなって返ってくることへの絶望的な空気である。あるいは今年のギリシャにおいてはより「先進的」制度においても明快に現われた。すなわち、どれほど路上が沸騰しよう------シリザ登場を準備したのはおどろくべき多様で創造的な直接行動の開花であった------が、それが既存の「デモクラシー」のシステムに回路を求めた瞬間にすべて無効化してしまうというものである。たとえ、その政策が国民投票で信任を得た、すなわちデモクラシー的な正当性を与えられたにしても、いっさいなにも変えることはできないどころか、事態は悪化するばかりであり、もはや「金融寡頭制」には手も足もでないといった感覚である。このような「現存デモクラシーの機能不全」の情勢は、世界でも共通のものであって日本に特有のものではない。
この数十年日本においても市民運動も学生運動も不在であったどころではないし、いまでも多様で微細な動き(それこそ「闘争」)があって、それが全体的なシーン(はずみ)を形成しているにもかかわらず、このところ、すくなくとも言説上では、あたかも「権力の局在した」と想定されている場所での特定の行動が「運動」として過剰に焦点化されていた。このような「焦点化」のあり方自体、権力論としてもメディア論としてもさらには原理的にも、そして重要なことだが実践的にも、それなりに長いあいだ問われてきた態度のはずであるが、それはここではおいておこう。しかし、このような形式的にも内容的にも「焦点化」の好まれる状況そのものが、現代日本における「戦略の過剰」の無意識への浸食度を端的に表現しているようにもみえる。それと関連しているが、それなりに運動が「可視化」され(たとされ)ればされるほど即座に「議会政治」が結びつくようになり、そうであればあるほどなにか言葉がフラットになっていくといった感じはしないだろうか。つまり言葉からカッコがとれていくといった印象である。もちろんそれだけではないにしても、わたしたちにとっても街頭に出ることはなによりもまず「離脱」の経験であった。それは世界を分節しなおす経験であり、この「現実」と距離をとる経験だったのである。「国民」「民衆」「治安」「民主主義」「自由」「動員」「暴力」「暴徒」「過激派」、それこそ「現実」など、そうした支配的語彙がことごとく宙づりされるような、それ以降はカッコに入れることなしには語れなくなるような経験である。いっさい語れなくなるのではない。それを語るには思考しなければならない、という命法が自分のなかで生まれるのである。だから、そこに出たからといって、なにか解答が見つかるわけでも、「成果」がすぐに上がるわけでもない。したがって、「多数のひとの同意を得ること」「多数のひとを変えること」といったこと、つまり、目標のための手段とはさしあたり直接には関係がないことが多い。むしろその場所は、自分に対しても他者に対しても「問い」をひらく空間であり、そこで経験されるのは可能性がひらかれることそのものである。しかし、このように可能性のひらかれる場所だからこそ、即効性はないように見えてもときに力を持つ──目標の達成に導くこともある──のであり、だから、このような空間がそのロケーションはどこであれ維持されているかぎり世界は崩壊の危機に瀕しても再生への潜在的力を持ちうるように思う。
ところがそのような可能性のひらかれは、大きな戦略に従属させられる度合いにしたがって圧縮されてしまうものである。圧縮不可能な「なにか」がかならず存在しているにしても。さまざまな戦後の体制の解体と再編、とりわけ平和主義に関するそれにあたって、さしせまった危機意識がこのような状況を促進していることは理解できる。ごく当然のことだが「焦点化」がときに必要なことも理解できる。ただそれは、さまざまな持続性をもつ経験や知見、積み上げられた作風などの相互作用や干渉、戦略家の眼にはただ「妨害」や「阻害要因」にしかみえないかもしれない「遠心力」によって力を与えられるものではあるまいか。奇妙なことに、これまではむしろそれを問い返す契機であったはずの場所も含め、すべての領域に繁殖をつづけている「リベラル」とその系列に属する語彙は、この可能性をひらく動きを促進させる以上に不可視化させるものであるようにみえる。そして、それに集約される可視的世界に現われないもの、そこからこぼれ落ちるものこそ、ひそやかに次の時代の土壌を耕しているのだと思う。
わたしはいまこの含意を文脈の隅々までふまえたうえで明らかにする準備はないし、この趨勢についてじぶんなりの判断をすることもできないのだが、このような極は情勢の認識に照明を与えてくれる。すなわち、以上の趨勢を「戦術の過剰」というか「戦術がすべて」を極として持つものとすれば、他方の極には「戦略の過剰」あるいは「戦略がすべて」も想定できる。つまり戦略に戦術が完全に従属している状態である。たとえば、組織に指導された運動においては、戦略のためにもっとも効率的に奉仕すべく戦術がすべて統制される傾向にあるが、このとき戦術の独自性や自律性はほぼ無となる。あるいはマーケティングである。それは「戦略がすべて」の側にある発想であり、だれにどうアピールするか(買わせるか)のためにすべての戦術は動員され、目的にむかって奉仕するものでしかない。「見た目」に過剰な力点がかかるのは、戦術への拘泥ではなく、戦略がすべてであり戦術に自律性が存在しないことの徴候である。
戦術は行動の可能性であるわけだから、それが戦略に完全に統制されず相対的に自律するということは、行動の可能性そのものの領域が問題視されており、また、そのためのスペースが生まれているということである。谷川雁は1962年、三井三池闘争以後の炭鉱労働者による運動の後退局面にあって、次のように述べている。「だが状況がかくあるときこそ、固定観念をはらって見るならば、抑圧されつづけた大衆の戦術思想をよびがえらせる好機である。たとえば大正行動隊のとった戦術は、例外なく往昔の坑夫たち、現代の中小鉱の坑夫たちが私闘、公闘のなかでうみだした発想に根拠をもつといってよい。だが状況がかくあるときこそ、固定観念をはらって見るならば、抑圧されつづけた大衆の戦術思想をよびがえらせる好機である。たとえば大正行動隊のとった戦術は、例外なく往昔の坑夫たち、現代の中小鉱の坑夫たちが私闘、公闘のなかでうみだした発想に根拠をもつといってよい」(『影の越境をめぐって』現代思潮社、1963)。これまでの戦略戦術連関が袋小路に追いつめられたという状況認識のもとで、谷川雁は戦術の次元の独自のルーツや時間性に注目し、そこから戦略戦術連関総体を組み替えるよう提案している。つまり、デモ、ストライキ、ピケといった戦術が袋小路におちいったとき、ケンカまでふくむ坑夫たちの生活とその継承のうちに独特の厚みをもっているものとしてとらえ返され、さらに、そこに思想性の存在が示唆されているわけである。日本の近代史においても、しばしば逸脱的に突っ走る民衆の「土着」の戦術と近代的組織による戦略にもとづく統制の対立する場面がみられるが、谷川雁はこの「土着」の戦術のうちにそうした近代的組織を超えていく思想性すら見出さねばならないというのである。かように、ふつう戦略に従属して考えられている戦術、すなわち、目的と手段の関係において考えられている戦略と戦術だが、目的と手段の連関が機能不全におちいるような契機には、とりわけ戦術の次元の独自性が浮上してくるようだ。ただし、戦術そのものの自律的意味は、なんらかの抗争のあるところいつの時代にも伏在しているわけである。
たとえば、1960年安保闘争についてさまざまな資料を掘り返していると、この運動を「突破者」的に牽引した全学連主流派(ブント)について、かれら自身はどのように大仰な修辞によって世界革命の「戦略」を語っていたとしても、実践においては戦術に大きく傾斜していたことが感じとられる。かれらは膠着した状況をどう流動化させるかに全体重を傾け、実際にたびたび沈滞に襲われた1960年の安保闘争を1959年末の「国会突入」------ただしこれはブント単独の行動ではない------から羽田空港占拠、装甲車乗り越えなどでそのつど、流動化させ、闘争の終息とともに自己解体した。いまでは忘れられがちだが、国会突入によって事態が大きく流動化する直前までは、安保闘争は盛りあがらない(「安保は重い」)という諦念まじりの見方が反安保諸勢力のなかで拡がった観測であり、しかも一旦はずみがついても幾度かの沈滞を経ているのである。状況をつき動かす大きな動力でありながら、一貫して大メディアや革新側の大組織からは非難され罵倒されつづけた「不幸な主役」(清水幾太郎)としてのブントは、運動の終息とともに(というかそれを待たずして)たちまち解体した。実態としては、冷徹な認識にもとづく合意による決断というより、たんにズルズルの成り行きの産物だとは思うが、組織の存続が目的へと転倒し、しばしば事態の膠着に手を貸すヒエラルキー的組織に化してしまうことも往々にしてある日本社会においては、この「役割が終わったら解体する」こと自体意味があるように思われるし、そのような情勢に対して受動的に振りまわされ------しかもその弱みも曝けだしながら------場当たり的に突破口を開きながら消滅したこと自体もそれほど否定すべきことではないと思う。そしてまさにかれらは、そうした点を組織至上主義の観点からただただ弱点とのみ認識した党派からは「戦術左翼」と罵られていたわけである。
わたしたちはこの「戦術左翼」という特徴づけをニュートラルにとらえ返してみたいのだが、そうすると、この時期の全学連主流派が、現在「ブラック・ブロック」と呼ばれている潮流と類似している点をいくつか持っていることに気づく。それこそ世界中の占拠行動や抗議行動に黒づくめの匿名の集団として現われ、「過激」な行動で物議をかもすアナキスト「集団」とみなされているブラック・ブロックであるが、しかし、このようなプロフィールにはまずもって大きな誤解がある。そもそもそれは集団でも組織でもないからである。ブラック・ブロックとはたんに特定の戦術の名称であり、どのような組織に属していようがいまいが個人でこの戦術をとろうと考えるならブラック・ブロックを形成する一員となればよいのである。組織ではないからかれらを主体とした文書もあまり存在しない。ブラック・ブロックは抗争のあるところ、そのつど、趨勢の境界線を引き直し、膠着状態を突破し、可能性の領域を拡大し、そして消えていく。ある意味でいえば、ブラック・ブロックとはなんの戦略=目的にも従属せず、ただ戦術を通して「可能性」そのものを拡げるために存在するわけである。行動の空間の可能性、行動の多様な展開の可能性、そして究極的には、いまここにある実定的な世界以外の世界の可能性である。その世界がなにかを示すことはない。ただ
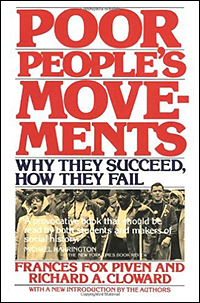
- Frances Fox Piven and Richard Cloward,
Poor People's Movements
Why They Succeed, How They Fail,
Pantheon Books, 1977.
「戦略の蒸発」というこのところの趨勢の文脈には、もちろん(より露骨となっている暴力の行使をともなう)管理技術の深化と同時に政治的無力化のいっそうの深化がある。そして、それにともなう、もはや可能性がすべて封じられたという憂鬱な感覚である。このような感覚は、たとえば「ISはアラブの春の灰燼からあらわれた」★1といわれるように、一挙に開花した可能性が一転して封じられ、希望のうちにかいまみられたビジョンとは真逆のものとなって返ってくることへの絶望的な空気である。あるいは今年のギリシャにおいてはより「先進的」制度においても明快に現われた。すなわち、どれほど路上が沸騰しよう------シリザ登場を準備したのはおどろくべき多様で創造的な直接行動の開花であった------が、それが既存の「デモクラシー」のシステムに回路を求めた瞬間にすべて無効化してしまうというものである。たとえ、その政策が国民投票で信任を得た、すなわちデモクラシー的な正当性を与えられたにしても、いっさいなにも変えることはできないどころか、事態は悪化するばかりであり、もはや「金融寡頭制」には手も足もでないといった感覚である。このような「現存デモクラシーの機能不全」の情勢は、世界でも共通のものであって日本に特有のものではない。
この数十年日本においても市民運動も学生運動も不在であったどころではないし、いまでも多様で微細な動き(それこそ「闘争」)があって、それが全体的なシーン(はずみ)を形成しているにもかかわらず、このところ、すくなくとも言説上では、あたかも「権力の局在した」と想定されている場所での特定の行動が「運動」として過剰に焦点化されていた。このような「焦点化」のあり方自体、権力論としてもメディア論としてもさらには原理的にも、そして重要なことだが実践的にも、それなりに長いあいだ問われてきた態度のはずであるが、それはここではおいておこう。しかし、このような形式的にも内容的にも「焦点化」の好まれる状況そのものが、現代日本における「戦略の過剰」の無意識への浸食度を端的に表現しているようにもみえる。それと関連しているが、それなりに運動が「可視化」され(たとされ)ればされるほど即座に「議会政治」が結びつくようになり、そうであればあるほどなにか言葉がフラットになっていくといった感じはしないだろうか。つまり言葉からカッコがとれていくといった印象である。もちろんそれだけではないにしても、わたしたちにとっても街頭に出ることはなによりもまず「離脱」の経験であった。それは世界を分節しなおす経験であり、この「現実」と距離をとる経験だったのである。「国民」「民衆」「治安」「民主主義」「自由」「動員」「暴力」「暴徒」「過激派」、それこそ「現実」など、そうした支配的語彙がことごとく宙づりされるような、それ以降はカッコに入れることなしには語れなくなるような経験である。いっさい語れなくなるのではない。それを語るには思考しなければならない、という命法が自分のなかで生まれるのである。だから、そこに出たからといって、なにか解答が見つかるわけでも、「成果」がすぐに上がるわけでもない。したがって、「多数のひとの同意を得ること」「多数のひとを変えること」といったこと、つまり、目標のための手段とはさしあたり直接には関係がないことが多い。むしろその場所は、自分に対しても他者に対しても「問い」をひらく空間であり、そこで経験されるのは可能性がひらかれることそのものである。しかし、このように可能性のひらかれる場所だからこそ、即効性はないように見えてもときに力を持つ──目標の達成に導くこともある──のであり、だから、このような空間がそのロケーションはどこであれ維持されているかぎり世界は崩壊の危機に瀕しても再生への潜在的力を持ちうるように思う。
ところがそのような可能性のひらかれは、大きな戦略に従属させられる度合いにしたがって圧縮されてしまうものである。圧縮不可能な「なにか」がかならず存在しているにしても。さまざまな戦後の体制の解体と再編、とりわけ平和主義に関するそれにあたって、さしせまった危機意識がこのような状況を促進していることは理解できる。ごく当然のことだが「焦点化」がときに必要なことも理解できる。ただそれは、さまざまな持続性をもつ経験や知見、積み上げられた作風などの相互作用や干渉、戦略家の眼にはただ「妨害」や「阻害要因」にしかみえないかもしれない「遠心力」によって力を与えられるものではあるまいか。奇妙なことに、これまではむしろそれを問い返す契機であったはずの場所も含め、すべての領域に繁殖をつづけている「リベラル」とその系列に属する語彙は、この可能性をひらく動きを促進させる以上に不可視化させるものであるようにみえる。そして、それに集約される可視的世界に現われないもの、そこからこぼれ落ちるものこそ、ひそやかに次の時代の土壌を耕しているのだと思う。
註
★1──"Violence Comes Home: Arun Kundnani interviewed by Open Democracy", 27 November 2015 (http://www.versobooks.com/blogs/2356-violence-comes-home-arun-kundnani-interviewed-by-open-democracy)
酒井隆史(さかい・たかし)
1965年生まれ。社会思想史、大阪府立大学准教授。著書=『自由論──現在性の系譜学』(2001)、『暴力の哲学』(2004)、『通天閣──新・日本資本主義発達史』(2012)。翻訳、共訳=スラヴォイ・ジジェク『否定的なもののもとへの滞留──カント、ヘーゲル、イデオロギー批判』(1998)、アントニオ・ネグリ+マイケル・ハート『〈帝国〉──グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』(2003)、アントニオ・ネグリ+マイケル・ハート『ディオニュソスの労働──国家形態批判』(2008)、マイク・デイヴィス『スラムの惑星──都市貧困のグローバル化』(2010)ほか。


