歴史を耕し、未来をつくるためにできること
長谷川豪『カンバセーションズ──ヨーロッパ建築家と考える現在と歴史』(LIXIL出版)の刊行記念講演会として、著者である長谷川豪と保坂健二朗(東京国立近代美術館キュレーター)によるトークイベント「歴史を耕し未来をつくるためにできること」が代官山 蔦屋書店で行なわれました。ヨーロッパ現代建築の魅力や、建築家の設計手法、彼らの作品に息づく歴史感覚の豊かさ、そして日本において歴史を耕し未来をつくるための方法について話していただきました。
最初に、この本を出すことになった経緯をお話します。僕は2012年の秋からスイスのメンドリシオ建築アカデミーで2年間スタジオを持ちました。それまで留学経験も海外プロジェクトの経験もなく、どちらかといえば日本でドメスティックに建築を学んで仕事をしてきた僕が、月に1、2回、スイスに通う生活がはじまりました。メンドリシオ建築アカデミーは1996年に開校したスイス南部のイタリア語圏にある建築学校です。学生はスイス人、イタリア人、その他の国からの留学生がそれぞれ3分の1ずつくらいで、スイスのなかでも特にインターナショナルな大学として有名です。開校当初はマリオ・ボッタやピーター・ズントーなどが教え、いまは教授や客員教授に、ヴァレリオ・オルジアティ(スイス)、アイレス・マテウス(ポルトガル)、ジョナサン・サージソン(イギリス)、ビジョイ・ジェイン(インド)、フランシス・ケレ(ブルキナファソ)などさまざまな国の建築家が教えています。とても雰囲気の良い学校です。
僕は日本の大学でも何度か非常勤講師として教えた経験があったので、ヨーロッパの学生と日本の学生がどう違うのか興味があったのですが、教えはじめて半年くらい経った頃に「歴史観」がとても違うことに気づきました。
メンドリシオはイタリア語圏だということもありイタリアの建築をレファレンスにすることが多いのですが、現代建築はほとんど参照しないんです。たとえばパッラーディオのヴィラの写真や平面図を参照元にプロジェクトを始める学生がいました。初めはそうした牧歌的なやり方をどうも保守的に感じていたのですが、進めるうちにうまくジャンプできた学生は建築の歴史と個人の感覚がハイブリッドしたプロジェクトになることがあり、それはなかなか新鮮でした。学生だけでなくヨーロッパの人には、建築は古くなくてはいけないという考えが基本にある。それが重くのしかかっていて学生たちが大胆なアイデアが出せなくなっているもどかしさもありましたが、別の見方をすれば建築の古さや長い時間に対する想像力でもあるんですよね。
それに対して日本の建築教育やメディアは基本的に、「いま」に敏感になれということがベースにあるように思います。いま社会状況がこうだから、建築業界はこうなっていくから、変化に乗り遅れるなと。学生もそうした「空気」を読むことが無意識のうちに要求されているところがあります。そして歴史については、「いま」がどういう時代なのかを位置づけるために俯瞰的に、現状分析的に語られがちです。「いま」が絶対化していて、ヨーロッパとは建築の根拠がかなり違う。それは学生だけではなくて、自分自身も含めて日本人が歴史を「身体化」していないからなのではないかと思うようになりました。
せっかくヨーロッパに定期的に通う機会を得たので、その経験をなんらかのかたちでアウトプットしたいと考えていた時に、2013年にポルト大学でのワークショップの講師をすることになりました。ポルト大学建築学部棟はアルヴァロ・シザの代表作のひとつですが、そのワークショップをコーディネートした建築家が僕に、シザと対話してみないかと提案してくれた。そのときに対話形式の書籍を思いついたのです。僕の最初の著作(『考えること、建築すること、生きること(現代建築家コンセプト・シリーズ)』LIXIL出版、2011)が刊行されたときに、担当編集者が「5年後にもう一度本を出そう」と言ってくれたので、とりあえずメールで相談してみました。彼は興味をもってくれて「とにかく対談を楽しんでくるように」と返事をくれた。だから、この本の企画はポルトで生まれたんです。
保坂健二朗──その違和感は具体的にいつ頃から持っていましたか。
長谷川──たとえば僕が独立していくつか住宅作品を発表しはじめたときに、東工大スクールの系譜として云々という反応をもらいました。年上の建築家でさえそういうことを言う人がいました。まあそれはいくらか予想していたことでもあったのですが、自分の名前で事務所をはじめたのに僕の出自から作品が読まれることにフラストレーションを感じた時期がありました。もちろん自分が学んだ環境からかなり影響を受けていることは自覚しているし、そうした反応もだんだんポジティヴに考えられるようになりましたが、どうして「スクール」のようなフレームなしに建築を評価できないんだろうと思っていました。でも海外へ行ったりしているうちに、師匠や世代の乗り越えを語りたがるのは、日本特有の島国的な考え方なのだと次第に理解していきました。
保坂──では、「歴史観」というこの本のコンセプトのひとつは、メンドリシオへ行ってはじめて意識したことというよりは、日本で実作をつくりながら考えたことの延長線上にあるということなんですね。
長谷川──そうですね。もとを辿れば学生の頃から少し意識していたかもしれません。日本では、近代を乗り超えるという物語が長らく建築をつくる拠り所になりましたが、それに対しては学生時代からなんとなく変だなと思っていましたね。わかりやすく言えばル・コルビュジエのドミノ・システムに「×」をつけて、それに対する21世紀の新たな形式を描いて「○」をつけるというふうに。もはや近代批判は「いま」を正当化するための道具としてかなり形骸化していますが、そもそも近代を丸ごと乗り超える対象としてしまっていいのか。否定や破壊をエネルギーにしないと新しい建築はつくれないのか。そもそも建築において「新しい」ってどういうことなのか。そういったことは学生の頃に悶々と考えていました。このような問題意識がメンドリシオでの経験を経て、肥大化したということかもしれません。
保坂──シザ以降の人選は数珠つなぎに決まったのでしょうか。
長谷川──そうですね。スイスに通っていたので、メンドリシオで教えているオルジャティ、それからチューリッヒのスイス連邦工科大学(ETH Zürich)で教えていたメルクリの2人は自然に決まりました。それから、大学院生時代に僕が数ヶ月インターンをしていたパリのラカトン&ヴァッサルには話を聞きたいと思っていました。
彼らから話を聞くうちに、どういう時代にキャリアをスタートさせたかがその建築家の活動に影響を与えていることに気づいたので、僕と同世代の70年代生まれのヨーロッパの建築家にも歴史の問題をどう考えているのか聞いてみたいと思いました。若手2組についてはまだ作品も少ないので悩みましたが、フラマーはオルジャティのアトリエ出身で、スイスの同世代ではいま一番注目されている人です。もう一組は、ケルステン・ゲールス&ダヴィッド・ファン・セーヴェレン。ケルステンとは2年前に客員教授として東京工業大学に来ていたときに会っていて、とてもスマートな人でプロジェクトも新鮮だったので、この機会に話を聞いてみたいと思いました。
保坂──長谷川さんの観点から6組の建築家を選ばれているので、最終的には長谷川さんの考える歴史観が浮かび上がってくるような気もするのですが、実際に6組の建築家と話された印象はどのようなものでしたか。
長谷川──まず対話を終えた感想は、歴史って自由なんだなということでした。6組ともまったく違う。それぞれ自分なりに建築の歴史を捉え、独自の物語を立ちあげている。でも現代に建築をつくることと歴史について考えることが表裏一体になっているという点で、結果的に6組の建築家の考えかたは一致していました。歴史への対峙の仕方がすでに創作の出発点になっていることが興味深かったのですが、それはそういう建築家たちを選んだ僕自身が目指したい方向性を示しているとも言えます。
日本だと、歴史は正しくなくてはいけないという意識がどこかにあるように思います。歴史小説などはとても人気があるのに、こと創作の世界においては、歴史は教義的なもので、そこから逸脱しないように語らなくてはいけないという雰囲気がある。だから歴史観が一元化して膠着してしまい、さきほどの形骸化した近代批判のようなベタな物語に陥りやすいのかもしれません。
6者6様の歴史観といえば、ゲールス&ファン・セーヴェレンの章は、ベルギーという国の特殊性が語られていて興味深かったです。大国に行きやすいという地の利や、一国のなかで文化の異なる南北の対立構造があり、つねに揺れ動いている場所で、若い世代がどう設計しているのか知ることができたのは参考になりました。長谷川さんは、ベルギーという、日本ではヨーロッパの他の国ほどはよく知られていない国の同世代の建築家と話してなにを感じましたか。
長谷川──僕と同世代ということもあって、やはりレム・コールハースは大きな存在だと語っていたのが印象的でした。「ラ・ヴィレット公園」や「フランス国立図書館」のコンペ案に加え、《ダラヴァ邸》、《コングレクスポ》、《ボルドーの住宅》と、初期OMAの代表作の多くはフランスのプロジェクトなのですが、その時コールハースは、ベルギーの腕のいい職人をたくさんフランスの現場に連れていったようです。スイスにはクラフトマンシップはあるがアーバニズムがない、逆にフランスにはアーバニズムはあるがクラフトマンシップがない、それに対してベルギーではクラフトマンシップとアーバニズムのふたつが両立できるという彼らの話は興味深かった。ベルギーはスイスのように一国のなかに複数の言語圏があって、さらにフランス、オランダ、ドイツ、イギリスという強いムーヴメントを起こす大国に囲まれているという状況がある。そこでベルギーは複数のアイデンティティを持ちあわせることになり、クラフトマンシップとアーバニズムのハイブリッドのようなことが可能になったということです。この複雑な時代において、そうしたハイブリッドなあり方は強みになるのかもしれない。これからベルギー建築がどういう展開を見せるのか楽しみですね。
長谷川──そうですね、自由になったように思います。たとえばメルクリの話はとても印象に残りました。彼は他人と違うことをやろうなんてまったく考えていないというか、まあ他の現代建築家に興味がないのだと思います。それよりも太古の昔から先人が考えてきたことをさらに掘り下げて、数千年前の建築の延長上に自分の創作を位置づけようとしています。
メルクリはギリシア建築から延々と続く、水平要素の重力を柱がどう受けるのかという問題に関心があると話してくれました。それはなぜかというととても単純で、どうしても納得できないから(笑)。いわば建築最古の問題であるにもかかわらず、自分はまだ納得できていないから考えたい、というシンプルな姿勢にはとても驚きました。まるで建築の問題は古いほうがいいと言っているかのようです。問題の新しさを競いがちな日本とは真逆ですよね。
保坂──2008年にメルクリと青木淳さんの展覧会「建築がうまれるとき──ペーター・メルクリと青木淳」を東京国立近代美術館で企画したときに、僕もチューリッヒにあるメルクリのアトリエに行きました。彼のアトリエは、建物に囲まれた中庭のなかにある、一棟建ての建物の2階にあります。その界隈は、現代美術館やギャラリーがたくさんある、チューリッヒでも最新のアートが集まる場所なんですが、このアトリエそのものが周囲から隔絶されているように、そのなかで行なわれていることも、最新の流行とはまったく違う。そこにはメルクリ独自の世界があります。たとえば彼のアトリエにある本棚はまるで古本屋のようで、最近の本がまったく見当たらないんです(笑)。
そこで見せてもらったのが膨大な数のドローイングでした。柱のリズムやプロポーションをどう変えるかということを、このラフさで違いがわかるのかというぐらいものすごくラフなドローイングを何百枚と描くことで検討している。ドローイングからも彼の建物からも、正直に言えば、「新しさ」という質はまったく感じられないのですが、でも、と同時に、師匠であるルドルフ・オルジャティの影響からの変遷を見ることはできる。そして、その変遷の仕方は非常に断続的にも見える。ジャンプがあるというか。メルクリ自身の作品では、初期の小さな住宅と最近の豪華な素材を使った大きなオフィスビルなどとは連続性が見えづらいのですが、かといってちがう人の作品とは思えず、ちゃんと1人の作品として見える。それはメルクリの関心のひとつである柱のリズムとプロポーションがどう建築に影響を与えているのかという、その一点において統一されているからでしょう。内部空間に関してはまた違ったロジックで動いているのかもしれませんが、とにかく他にはいないタイプの建築家だと感じました。
その後も展覧会や企画の準備などで半年に一回はチューリッヒに行っているのですが、そのたびに「今日もメルクリはあそこにいるのかな」「時代と関係なく今日もあのドローイングを描いているのかな」と、ギャラリーのあるエリアから思いを馳せてしまいます。メルクリみたいな人が世界にひとりはいて欲しいですね。
保坂──一方、ヴァレリオ・オルジャティも相当特殊な建築家だと感じていますが、長谷川さんは対談を通じて彼に対する見方に変化はあったのでしょうか。
長谷川──ヴァレリオとはメンドリシオで話す機会が多く、作品もほとんど見せてもらってよく知っていたので、それほど見方が変わったということはないですが、確固たる地位を築いた建築家である父親(ルドルフ・オルジャティ)から逃れるためにこうならざるを得なかったと、正直な語り方をしてくれたのが意外でした。ヨーロッパ文脈から離れた日本人建築家からの質問だったので、気負わずに答えてくれたのかもしれません。
保坂──お父さんの話はある意味タブーだと聞いていたので、驚きました。ルドルフ・オルジャティから、メルクリとヴァレリオという非常に対照的な建築家が出たというのは興味深いですね。
長谷川──たしかにメルクリとヴァレリオの建築は対照的ですが、結構近いところもあるように思います。時代に依存しないタイムレスな建築をつくろうとするところや、ヴァレリオが対話のなかで語っている「人々に思考させる建築」は、表現の仕方はまったく違うにせよメルクリの建築にも言えることだと思います。
ヴァレリオは、大学のスタジオでも事務所でも、スケッチは一切せずに言葉だけでスタディします。「感情を揺さぶる建築」や「現象的な建築」を痛烈に批判しながら、「建築的(Architectonically)に考えること」とはどういうことなのかを自問自答するように語っていたのが印象的でした。また僕は彼の建築に宿る神殿のような強い自律性についてわりとしつこく質問しました。それに対してヴァレリオは自分の建築に神殿という言葉を使いたくないと言う一方で、神殿がなにかほかの建築を参照しないで存在していること(non-referencial)への共感を語ってくれてそれがとても興味深かったですね。
保坂──「建築は言語で語れるほど抽象的な存在にならなきゃいけないんだ」「建築は抽象的に存在しうるんだ」という強い思い、あるいはそこになんとかして到達したいという意志をヴァレリオは持っているような気がしますね。それを本当にピュアに追い求めている人です。しかも、だからと言って、周囲の環境を完全に無視することはしない。
ヴァレリオとスイスからロンドンに一緒に行ったことがあります。その道中でピーター・ズントーと自分はどう違うのかという話をしてくれました。この本ではスイスの建築家としてヴァレリオとメルクリが取りあげられていますが、プリツカー賞を受賞しているズントーをあえて扱わなかった理由はありますか。あるいは、ズントーの建築について長谷川さんはどう思っていますか。
長谷川──ズントーの建築は学生の頃から好きでした。もともと家具職人だったということも関係しているのかもしれませんが、どこかプロダクト的な完成度を求めるところがありますよね。ズントーの関心はモノとしての建築、あるいは現象的なことに依っていて、建築の歴史性について議論する今回の本とは合わないかなと思いました。
建築をつくることは人間の場所について考えることですが、建築には2つの「場所」があると最近考えています。ローカル(Local)とローカス(Locus)です。まずローカルは、たとえば代官山やヒルサイドテラスといった地域や建物など、僕たちが普段慣れ親しんで使っている「具体的な場所」に対応する言葉です。もうひとつの「場所」であるローカスは、遺伝学の言葉でDNAのどこに位置しているかという意味で、人類学的な時間をもついわば「抽象的な場所」のことなのですが、建築の領域ではアルド・ロッシの『都市の建築』(大島哲蔵+福田晴虔訳、大龍堂書店、1991)のなかでたびたび出てくる用語で、ロッシはローカスを、ある特定の敷地とその場所に立地する構築物とのあいだに見られる特異で普遍的な関係のことだとしています。また「都市は集団的記憶の〈場(ローカス)〉なのだ」とも述べています。
僕は特異で普遍的な、個人的でありながら集団的記憶に触れる建築をつくりたいと考えてきました。あるいは建築としての自律性をもちながら、周りの普通の建物との繋がりをもつものであってほしい。つまり場所(ローカル)に応えるのと同時に、自分のつくった建築が歴史上どう位置づくかという、建築の遺伝子的な場所(ローカス)をいつも気にしながら設計してきました。そのどちらか一方では駄目で、現実の場所にも応答しながら、建築のタイポロジーやエレメントを通して、建築の歴史的で人類学的な時間との関わりをもちたい。そうしたローカルとローカスというふたつの「場所」が交わるところに建築をつくりたいと考えています。
保坂──DNA配列における位置づけという話はおもしろいですね。というのも、無限にも思える数の要素が並んでいるなかの、どこかのパーツ(一部)ということですから。しかもその並びは螺旋状になっている。モダニズムの歴史の考え方は基本的に線的で、その最先端にいることが新しさを保証しているという考え方でした。しかし、螺旋構造を思い描きながらいまの考え方を聞くと、過去、現在、未来すべてを含んだうえで、どこをとってもいいという歴史観をどこかで長谷川さんは持っているのではないかと感じました。僕なりのたとえをすると、歴史をモザイク状の面ととらえて、その欠けた部分にピースを埋めていく作業とでもいいますか。
長谷川──先ほどお話したようにもともと持っていた問題意識がモチベーションになっているので、この本を現在の状況に対するカウンター・パンチというよりも、もっと長い射程で考えたいと思っています。反応としては、いまのところ日本よりもヨーロッパからの反響のほうが圧倒的に大きいので、今日はどんな意見が聞けるか楽しみにして来ました。せっかく多くの方に集まってもらっているので、会場からの意見も聞いてみたいと思います。
会場1──僕自身設計の仕事をしていますが、この本でも触れられているように、僕よりも少し上の60年代後半から70年代初めに生まれた世代の人は、どこか新しさを追いかけているような印象があり、僕はそこに違和感を感じています。日本国内のポストモダンは、バブル崩壊とともに強制終了されたと思っているんですが、その頃を境に歴史を参照することからみんな撤退してしまって、もう一度ゼロベースから新しいものはなにか、ということをやりはじめていたように見えます。
そういう時期も過ぎて、改めてもう一度建築をつくることを考えたときに、歴史のことを考えるのは自然なことだし、この本を読んでいまの時代について考えながら、歴史に対して自由に構えていいんだと、楽になった気がします。僕から一つ質問をさせていただきたいのですが、6人と話して長谷川さんがもっとも共感した人はどなたでしたか。
長谷川──ありがとうございます。そうですね、共感する部分はそれぞれの人にありましたが、本になってから改めて全体を読み返してみたときに、シザとの対話のなかで出てきた「多重性」という言葉がしっくりきました。シザは敷地や自然、経済性や政治、ありとあらゆることに配慮して、でもそのどれかに依存しない建築をつくる意義を話していたのですが、これはとても示唆的な発言だと思います。いろんな文脈に配慮した結果としての建築の自律性。いろいろな文脈にただ応えているだけでは建築は応答の総和にしかならないんですよね。重要なのは、さまざまな文脈に一旦グッと近づいていって全体を理解したあとに、どれかに依存しないようにそれぞれから距離をとることで、結果として建築は自律性を獲得する。この感覚はとても共感します。ちなみにこの建築の状態を、対話のなかではMultiplicityと言っているのですが、これに「多様性」ではなく「多重性」という訳をつけました。あらゆる具体的な文脈に配慮してそのいずれにも依存しないというシザのMultiplicityは、関わる対象の種類が多いこと(多様性)よりも、建築の自律性にさまざまな関係性が主体的に束ねられていることに意味があるので、翻訳家の方に相談のうえで「多重性」としました。
意地悪な質問ですが、明治以降、日本人は西洋から学ぶ、識者が西洋の建築を紹介するという流れがあって、この本もその歴史的な流れのなかにあると思っていいのでしょうか。
長谷川──この本はヨーロッパ礼讃、あるいは海外から最新スタイルを輸入しようという内容ではないですよね。こと歴史において、彼らの姿勢に参考にできることはあるけれど、彼らがやっている実践の方法論を今の日本にそのまま輸入しても意味はないと思います。保坂さんからもこの対談がはじまる前に、なぜ日本人を入れなかったのかと聞かれました。じつは同じテーマで日本人の上の世代の建築家に話を聞くという案も最初はあったし、それもあり得たと思うんですが、今回はあえて日本の建築家を外して、歴史というものを客観視することを優先しました。
保坂──この本で取り上げられている建築家の作品は、日本では見られないですよね。海外の建築家でも日本で実作を見ることができるインターナショナルな建築家はいるにもかかわらず、そういう人はあえて外して相当ローカルな建築家たちが選ばれている。結果論だとしても、設計自体をインターナショナルに行なっていなくても、インターナショナルに評価されている建築家が掲載されていて、そこがおもしろいところだと思いました。
長谷川──たしかにそうですね。まず僕がメンドリシオで教えていた状況がおもしろいと思っていて、日本でほとんど住宅しかつくっていないような日本の若手建築家がヨーロッパの大学で教えるなんて20年前にはなかったですし、あるいは僕より年下の世代でも海外のローカルな場所でプロジェクトをもつことが普通のことになってきている。世界で認められた巨匠だけがインターナショナルに活動していたのが20世紀だったと思うのですが、いまは直接ローカルとローカルが出会って互いに影響を受け合うということが建築以外の領域でもいろいろな場面で起こっている。それは情報技術の発達でローカルな活動が世界に届きやすくなったとか、飛行機代が安くなったとか、いろいろな要因で可能になったのだと思いますが、僕はいまの時代のローカルとローカルに可能性を感じていて、それはかつてのインターナショナル経由の外国文化の輸入とはまるで違うものだと思います。
長谷川──いま台湾・台北で歴史的な保存建築の改修と増築のプロジェクトを進めています。いわゆる官民共同の公共的なプロジェクトで、来春に完成予定です。もちろんスケールなどの違いはありますが、歴史や時間への向き合い方を含め、設計の仕方ということでいうと実感としては住宅でこれまでやってきたこととほとんど変わりませんね。むしろそういう歴史的意味が大きなプロジェクトだからこそ、それを客観視する改修というか、ベタにその建物の歴史のみに入り込まずに複数の時間が並走する状態をつくろうとしています。
でも保坂さんにいま指摘いただいたように、日本の公共建築は人々にとってわかりやすい歴史観を、住宅は作家個人の歴史観を、という対立は一般的にはあるように思います。最近の公共建築のプロポーザル方式では「わかりやすいことが良し」ということがますますイデオロギー化していて、実践としてはかなりベタな方法論に陥っている。どうにかこの状況を変えていきたいのですが。
長谷川──つくりますよ(笑)
保坂──だとすると、それはやっぱり僕のキュレーターとしての能力の限界なんですけど、ごめんなさい、とても想像ができなかったんです。もしお願いしても「僕は人が住まない空間はつくりません」とか言われそうだと思って(笑)。でもそれは長谷川さんのいいところでもある。その時参加してくれた建築家が間違っているということではけっしてないんですが。
長谷川──いや、このあいだフランスで学生とやったワークショップでは「プリミティヴで最小限の建築とは何か」という問いから、草原の中に穴を掘るインスタレーションのようなものをやりました。寸法を綿密に定義して、メンバー6人のスケールの空間を自然のなかにつくりました。だからインスタレーションもできると思うんですけど......。でもたしかに、ギャラリー間の展覧会では中庭に建築(《石巻の鐘楼》2012)をつくりましたね(笑)。
保坂──そういう建築家はいてもいいだろうし、いるべきなんです。むしろ、僕ら美術館側はインスタレーションをつくらない建築家を、どう見せればいいのかを考えなければならない、いまはそう思っています。建築を学んだ人だけが観るなら図面や模型の展示でいいのかもしれませんが、美術館という枠組みではなかなかそうはいかない。ではどうすればよいか。そういう観点においても、『カンバセーションズ』からはヒントをもらったと思っています。ここで見えてくる歴史観の違いをうまく展覧会に組み合わせることができたならば、展示としておもしろいものになるだろうなと思いました。
じつはいま、海外で日本の住宅を紹介する展覧会に関わっているのですが、その展示では戦後から現代までの日本の住宅だけで構成します。なんの予備知識ももたない海外の人に日本の住宅のおもしろさをどう伝えていくのか、これは難問です。現段階では建築家と建築史家にスーパーバイザーになってもらって、スクールで見せるのは結局「人」で語ることになりかねないからなるべく避けて、住宅作品を単位とした系譜学の観点から見せていこうと話しています。安藤忠雄さんの《住吉の長屋》と何がつながるか、長谷川さんの《経堂の住宅》と何がつながるか、模造紙上で系譜をマッピングしているところです。なにか新しい展覧会ができそうな予感があります。美術館という、街や歴史と切れた、地面のない場所でどうやって建築を見せていくことができるのか、それが僕自身の課題であり続けています。
長谷川──「人」ではなく「住宅」を単位とした系譜学の展覧会というのはおもしろそうですね。美術館での建築展はたしかになかなか難しい課題です。「建築はどこにあるの?」展のなかでは、アトリエ・ワンの「まちあわせ」は上手いなと思いましたが、それでもあれは美術館の外でしたよね。僕だったらどうしただろう? 美術館や展示室の歴史やコンテクストをそれでも読み解こうとしたかもしれない。
保坂──さまざまなかたちで建築家と美術家は共同作業ができるはずです。特に日本の場合は、建築を恒常的に扱っているところがないので、美術館のキュレーターとして建築を見せていくことは責務だと思っています。よく「なぜアート界の人が建築展をやるんですか」と聞かれるんですが、いつかそういう質問が無くなるといいと思っています。
エリック・ホブズボームというイギリスの歴史家の『破断の時代──20世紀の文化と社会』(慶應義塾大学出版会、2015)を読んでいて、そこに衝撃的なことが書いてありました。絵画、彫刻、文学、音楽など、いろいろな芸術のジャンルがあるなかで、なくならないものは建築と文学くらいで、絵画や彫刻は余命いくばくもないというのです。彼に言わせるとメディウムがいろいろ変わっていってもフォーマットを合わせていけるジャンルは残るそうです。その点建築はつねに技術の側にあるからフォーマットは合わせていくのは得意だし、なにより人が住まなくなることはないだろうから、残る可能性が高い。それを読んでますます本腰を入れて、ある意味絵画以上にやらなきゃいけないなと思いました。
しかし日本だとなかなかそうはいきません。資料館もないところでスクラップアンドビルドばかりが進む国で歴史を問うていくことは相当難しい。そうした状況で、まだ若手と言える長谷川さんがこの本を出されたことがおもしろい。ひょっとしたら長谷川さんは戦略的にやったのかもしれませんが、日本人を対談相手に加えるときっと歴史を抽象化できなくなってしまっていたでしょうね。「建築を抽象的に考えることができるか」という命題があると同時に、「歴史を抽象的に考えることができるか」という命題もこの本にとってはとても重要だったのではないか。その距離感を大事にされていたように感じました。
僕は6本の対話の後にそれぞれ短い文章を書きました。対話から一歩引いてみて、遠い国から来て細かいコンテクストや裏事情を知らない僕と彼らとの距離感を定着させる試みでした。先日ヴァレリオが本の感想を送ってきてくれて、これらのテキストによって6組の建築的思考があらわになると同時に、僕自身の興味が逆照射されているのがとてもおもしろかったと言ってくれました。
保坂──長谷川さん自身の興味というのは、具体的にはどのあたりにあるのですか。
長谷川──読み返してみたときに、自分が6組の建築家に対してそれぞれ違うタームを使いながら、建築の自律性について繰り返し聞いていることに気づきました。シザが語っていた「多重性」の話に繋がりますが、社会状況に反応するリアクティブな建築が増えていくなかで、僕は現代建築の自律性がいかに可能かについて考えたかったのだと思います。この本をつくることでそれに気づくことができたことは大きな収穫でした。
[2015年5月10日、代官山 蔦屋書店にて]

- 保坂健二朗氏(左)、長谷川豪氏(右)
日本とヨーロッパとの往復──「歴史」と「いま」を行き来する

- 長谷川豪『カンバセーションズ──
ヨーロッパ建築家と考える現在と歴史』
(LIXIL出版、2015)
最初に、この本を出すことになった経緯をお話します。僕は2012年の秋からスイスのメンドリシオ建築アカデミーで2年間スタジオを持ちました。それまで留学経験も海外プロジェクトの経験もなく、どちらかといえば日本でドメスティックに建築を学んで仕事をしてきた僕が、月に1、2回、スイスに通う生活がはじまりました。メンドリシオ建築アカデミーは1996年に開校したスイス南部のイタリア語圏にある建築学校です。学生はスイス人、イタリア人、その他の国からの留学生がそれぞれ3分の1ずつくらいで、スイスのなかでも特にインターナショナルな大学として有名です。開校当初はマリオ・ボッタやピーター・ズントーなどが教え、いまは教授や客員教授に、ヴァレリオ・オルジアティ(スイス)、アイレス・マテウス(ポルトガル)、ジョナサン・サージソン(イギリス)、ビジョイ・ジェイン(インド)、フランシス・ケレ(ブルキナファソ)などさまざまな国の建築家が教えています。とても雰囲気の良い学校です。
僕は日本の大学でも何度か非常勤講師として教えた経験があったので、ヨーロッパの学生と日本の学生がどう違うのか興味があったのですが、教えはじめて半年くらい経った頃に「歴史観」がとても違うことに気づきました。
メンドリシオはイタリア語圏だということもありイタリアの建築をレファレンスにすることが多いのですが、現代建築はほとんど参照しないんです。たとえばパッラーディオのヴィラの写真や平面図を参照元にプロジェクトを始める学生がいました。初めはそうした牧歌的なやり方をどうも保守的に感じていたのですが、進めるうちにうまくジャンプできた学生は建築の歴史と個人の感覚がハイブリッドしたプロジェクトになることがあり、それはなかなか新鮮でした。学生だけでなくヨーロッパの人には、建築は古くなくてはいけないという考えが基本にある。それが重くのしかかっていて学生たちが大胆なアイデアが出せなくなっているもどかしさもありましたが、別の見方をすれば建築の古さや長い時間に対する想像力でもあるんですよね。
それに対して日本の建築教育やメディアは基本的に、「いま」に敏感になれということがベースにあるように思います。いま社会状況がこうだから、建築業界はこうなっていくから、変化に乗り遅れるなと。学生もそうした「空気」を読むことが無意識のうちに要求されているところがあります。そして歴史については、「いま」がどういう時代なのかを位置づけるために俯瞰的に、現状分析的に語られがちです。「いま」が絶対化していて、ヨーロッパとは建築の根拠がかなり違う。それは学生だけではなくて、自分自身も含めて日本人が歴史を「身体化」していないからなのではないかと思うようになりました。
せっかくヨーロッパに定期的に通う機会を得たので、その経験をなんらかのかたちでアウトプットしたいと考えていた時に、2013年にポルト大学でのワークショップの講師をすることになりました。ポルト大学建築学部棟はアルヴァロ・シザの代表作のひとつですが、そのワークショップをコーディネートした建築家が僕に、シザと対話してみないかと提案してくれた。そのときに対話形式の書籍を思いついたのです。僕の最初の著作(『考えること、建築すること、生きること(現代建築家コンセプト・シリーズ)』LIXIL出版、2011)が刊行されたときに、担当編集者が「5年後にもう一度本を出そう」と言ってくれたので、とりあえずメールで相談してみました。彼は興味をもってくれて「とにかく対談を楽しんでくるように」と返事をくれた。だから、この本の企画はポルトで生まれたんです。

- 長谷川豪氏
保坂健二朗──その違和感は具体的にいつ頃から持っていましたか。
長谷川──たとえば僕が独立していくつか住宅作品を発表しはじめたときに、東工大スクールの系譜として云々という反応をもらいました。年上の建築家でさえそういうことを言う人がいました。まあそれはいくらか予想していたことでもあったのですが、自分の名前で事務所をはじめたのに僕の出自から作品が読まれることにフラストレーションを感じた時期がありました。もちろん自分が学んだ環境からかなり影響を受けていることは自覚しているし、そうした反応もだんだんポジティヴに考えられるようになりましたが、どうして「スクール」のようなフレームなしに建築を評価できないんだろうと思っていました。でも海外へ行ったりしているうちに、師匠や世代の乗り越えを語りたがるのは、日本特有の島国的な考え方なのだと次第に理解していきました。
保坂──では、「歴史観」というこの本のコンセプトのひとつは、メンドリシオへ行ってはじめて意識したことというよりは、日本で実作をつくりながら考えたことの延長線上にあるということなんですね。
長谷川──そうですね。もとを辿れば学生の頃から少し意識していたかもしれません。日本では、近代を乗り超えるという物語が長らく建築をつくる拠り所になりましたが、それに対しては学生時代からなんとなく変だなと思っていましたね。わかりやすく言えばル・コルビュジエのドミノ・システムに「×」をつけて、それに対する21世紀の新たな形式を描いて「○」をつけるというふうに。もはや近代批判は「いま」を正当化するための道具としてかなり形骸化していますが、そもそも近代を丸ごと乗り超える対象としてしまっていいのか。否定や破壊をエネルギーにしないと新しい建築はつくれないのか。そもそも建築において「新しい」ってどういうことなのか。そういったことは学生の頃に悶々と考えていました。このような問題意識がメンドリシオでの経験を経て、肥大化したということかもしれません。
6組の建築家、創作の出発点としての歴史観
長谷川──この本の掲載順は収録した順なのですが、たまたま世代順にもなっています。アルヴァロ・シザが1930年代生まれで、ヴァレリオ・オルジャティ、ペーター・メルクリ、アンヌ・ラカトン&ジャン=フィリップ・ヴァッサルが50年代、パスカル・フラマー、ケルステン・ゲールス&ダヴィッド・ファン・セーヴェレンが70年代生まれで、20年ごとの3つの世代に分かれています。保坂──シザ以降の人選は数珠つなぎに決まったのでしょうか。
長谷川──そうですね。スイスに通っていたので、メンドリシオで教えているオルジャティ、それからチューリッヒのスイス連邦工科大学(ETH Zürich)で教えていたメルクリの2人は自然に決まりました。それから、大学院生時代に僕が数ヶ月インターンをしていたパリのラカトン&ヴァッサルには話を聞きたいと思っていました。
彼らから話を聞くうちに、どういう時代にキャリアをスタートさせたかがその建築家の活動に影響を与えていることに気づいたので、僕と同世代の70年代生まれのヨーロッパの建築家にも歴史の問題をどう考えているのか聞いてみたいと思いました。若手2組についてはまだ作品も少ないので悩みましたが、フラマーはオルジャティのアトリエ出身で、スイスの同世代ではいま一番注目されている人です。もう一組は、ケルステン・ゲールス&ダヴィッド・ファン・セーヴェレン。ケルステンとは2年前に客員教授として東京工業大学に来ていたときに会っていて、とてもスマートな人でプロジェクトも新鮮だったので、この機会に話を聞いてみたいと思いました。

- ラカトン&ヴァッサル《キャップ・フェレのD邸》撮影=長谷川豪
保坂──長谷川さんの観点から6組の建築家を選ばれているので、最終的には長谷川さんの考える歴史観が浮かび上がってくるような気もするのですが、実際に6組の建築家と話された印象はどのようなものでしたか。
長谷川──まず対話を終えた感想は、歴史って自由なんだなということでした。6組ともまったく違う。それぞれ自分なりに建築の歴史を捉え、独自の物語を立ちあげている。でも現代に建築をつくることと歴史について考えることが表裏一体になっているという点で、結果的に6組の建築家の考えかたは一致していました。歴史への対峙の仕方がすでに創作の出発点になっていることが興味深かったのですが、それはそういう建築家たちを選んだ僕自身が目指したい方向性を示しているとも言えます。
日本だと、歴史は正しくなくてはいけないという意識がどこかにあるように思います。歴史小説などはとても人気があるのに、こと創作の世界においては、歴史は教義的なもので、そこから逸脱しないように語らなくてはいけないという雰囲気がある。だから歴史観が一元化して膠着してしまい、さきほどの形骸化した近代批判のようなベタな物語に陥りやすいのかもしれません。

- パスカル・フラマー《バルシュタールの住宅》撮影=長谷川豪

- 保坂健二朗氏
6者6様の歴史観といえば、ゲールス&ファン・セーヴェレンの章は、ベルギーという国の特殊性が語られていて興味深かったです。大国に行きやすいという地の利や、一国のなかで文化の異なる南北の対立構造があり、つねに揺れ動いている場所で、若い世代がどう設計しているのか知ることができたのは参考になりました。長谷川さんは、ベルギーという、日本ではヨーロッパの他の国ほどはよく知られていない国の同世代の建築家と話してなにを感じましたか。
長谷川──僕と同世代ということもあって、やはりレム・コールハースは大きな存在だと語っていたのが印象的でした。「ラ・ヴィレット公園」や「フランス国立図書館」のコンペ案に加え、《ダラヴァ邸》、《コングレクスポ》、《ボルドーの住宅》と、初期OMAの代表作の多くはフランスのプロジェクトなのですが、その時コールハースは、ベルギーの腕のいい職人をたくさんフランスの現場に連れていったようです。スイスにはクラフトマンシップはあるがアーバニズムがない、逆にフランスにはアーバニズムはあるがクラフトマンシップがない、それに対してベルギーではクラフトマンシップとアーバニズムのふたつが両立できるという彼らの話は興味深かった。ベルギーはスイスのように一国のなかに複数の言語圏があって、さらにフランス、オランダ、ドイツ、イギリスという強いムーヴメントを起こす大国に囲まれているという状況がある。そこでベルギーは複数のアイデンティティを持ちあわせることになり、クラフトマンシップとアーバニズムのハイブリッドのようなことが可能になったということです。この複雑な時代において、そうしたハイブリッドなあり方は強みになるのかもしれない。これからベルギー建築がどういう展開を見せるのか楽しみですね。

- オフィス・ケルステン・ゲールス・ダヴィッド・ファン・セーヴェレン《OFFICE 39:バーゲンホフトのヴィラ》(2010)撮影=長谷川豪
ペーター・メルクリとヴァレリオ・オルジャティ
保坂──全然違う6つの歴史観を聞いて、長谷川さん自身の歴史観に変化はありましたか。長谷川──そうですね、自由になったように思います。たとえばメルクリの話はとても印象に残りました。彼は他人と違うことをやろうなんてまったく考えていないというか、まあ他の現代建築家に興味がないのだと思います。それよりも太古の昔から先人が考えてきたことをさらに掘り下げて、数千年前の建築の延長上に自分の創作を位置づけようとしています。
メルクリはギリシア建築から延々と続く、水平要素の重力を柱がどう受けるのかという問題に関心があると話してくれました。それはなぜかというととても単純で、どうしても納得できないから(笑)。いわば建築最古の問題であるにもかかわらず、自分はまだ納得できていないから考えたい、というシンプルな姿勢にはとても驚きました。まるで建築の問題は古いほうがいいと言っているかのようです。問題の新しさを競いがちな日本とは真逆ですよね。

- ペーター・メルクリ《シンセスの新施設》(2012)撮影=長谷川豪
保坂──2008年にメルクリと青木淳さんの展覧会「建築がうまれるとき──ペーター・メルクリと青木淳」を東京国立近代美術館で企画したときに、僕もチューリッヒにあるメルクリのアトリエに行きました。彼のアトリエは、建物に囲まれた中庭のなかにある、一棟建ての建物の2階にあります。その界隈は、現代美術館やギャラリーがたくさんある、チューリッヒでも最新のアートが集まる場所なんですが、このアトリエそのものが周囲から隔絶されているように、そのなかで行なわれていることも、最新の流行とはまったく違う。そこにはメルクリ独自の世界があります。たとえば彼のアトリエにある本棚はまるで古本屋のようで、最近の本がまったく見当たらないんです(笑)。
そこで見せてもらったのが膨大な数のドローイングでした。柱のリズムやプロポーションをどう変えるかということを、このラフさで違いがわかるのかというぐらいものすごくラフなドローイングを何百枚と描くことで検討している。ドローイングからも彼の建物からも、正直に言えば、「新しさ」という質はまったく感じられないのですが、でも、と同時に、師匠であるルドルフ・オルジャティの影響からの変遷を見ることはできる。そして、その変遷の仕方は非常に断続的にも見える。ジャンプがあるというか。メルクリ自身の作品では、初期の小さな住宅と最近の豪華な素材を使った大きなオフィスビルなどとは連続性が見えづらいのですが、かといってちがう人の作品とは思えず、ちゃんと1人の作品として見える。それはメルクリの関心のひとつである柱のリズムとプロポーションがどう建築に影響を与えているのかという、その一点において統一されているからでしょう。内部空間に関してはまた違ったロジックで動いているのかもしれませんが、とにかく他にはいないタイプの建築家だと感じました。
その後も展覧会や企画の準備などで半年に一回はチューリッヒに行っているのですが、そのたびに「今日もメルクリはあそこにいるのかな」「時代と関係なく今日もあのドローイングを描いているのかな」と、ギャラリーのあるエリアから思いを馳せてしまいます。メルクリみたいな人が世界にひとりはいて欲しいですね。
保坂──一方、ヴァレリオ・オルジャティも相当特殊な建築家だと感じていますが、長谷川さんは対談を通じて彼に対する見方に変化はあったのでしょうか。
長谷川──ヴァレリオとはメンドリシオで話す機会が多く、作品もほとんど見せてもらってよく知っていたので、それほど見方が変わったということはないですが、確固たる地位を築いた建築家である父親(ルドルフ・オルジャティ)から逃れるためにこうならざるを得なかったと、正直な語り方をしてくれたのが意外でした。ヨーロッパ文脈から離れた日本人建築家からの質問だったので、気負わずに答えてくれたのかもしれません。
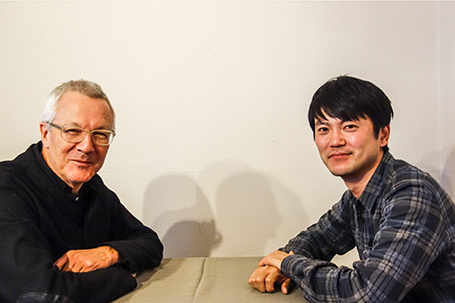
- 対談収録の様子。ヴァレリオ・オルジャティ(左)提供=長谷川豪
保坂──お父さんの話はある意味タブーだと聞いていたので、驚きました。ルドルフ・オルジャティから、メルクリとヴァレリオという非常に対照的な建築家が出たというのは興味深いですね。
長谷川──たしかにメルクリとヴァレリオの建築は対照的ですが、結構近いところもあるように思います。時代に依存しないタイムレスな建築をつくろうとするところや、ヴァレリオが対話のなかで語っている「人々に思考させる建築」は、表現の仕方はまったく違うにせよメルクリの建築にも言えることだと思います。
ヴァレリオは、大学のスタジオでも事務所でも、スケッチは一切せずに言葉だけでスタディします。「感情を揺さぶる建築」や「現象的な建築」を痛烈に批判しながら、「建築的(Architectonically)に考えること」とはどういうことなのかを自問自答するように語っていたのが印象的でした。また僕は彼の建築に宿る神殿のような強い自律性についてわりとしつこく質問しました。それに対してヴァレリオは自分の建築に神殿という言葉を使いたくないと言う一方で、神殿がなにかほかの建築を参照しないで存在していること(non-referencial)への共感を語ってくれてそれがとても興味深かったですね。

- ヴァレリオ・オルジャティ《パスペルスの小学校》(1998)撮影=長谷川豪
保坂──「建築は言語で語れるほど抽象的な存在にならなきゃいけないんだ」「建築は抽象的に存在しうるんだ」という強い思い、あるいはそこになんとかして到達したいという意志をヴァレリオは持っているような気がしますね。それを本当にピュアに追い求めている人です。しかも、だからと言って、周囲の環境を完全に無視することはしない。
ヴァレリオとスイスからロンドンに一緒に行ったことがあります。その道中でピーター・ズントーと自分はどう違うのかという話をしてくれました。この本ではスイスの建築家としてヴァレリオとメルクリが取りあげられていますが、プリツカー賞を受賞しているズントーをあえて扱わなかった理由はありますか。あるいは、ズントーの建築について長谷川さんはどう思っていますか。
長谷川──ズントーの建築は学生の頃から好きでした。もともと家具職人だったということも関係しているのかもしれませんが、どこかプロダクト的な完成度を求めるところがありますよね。ズントーの関心はモノとしての建築、あるいは現象的なことに依っていて、建築の歴史性について議論する今回の本とは合わないかなと思いました。
場所の持つ二つの意味──ローカルとローカス
保坂──この書籍で扱われている「歴史とどう向き合うか」と「建築を抽象的に考えることができるか」とは、おそらくつながっている問いなのだと思います。長谷川さん自身は、自分の建築をどのように自己分析されていますか。つまり、歴史との関わりあいのなかでどう位置づけているのでしょうか。
- アルド・ロッシ『都市の建築』
(大島哲蔵+福田晴虔訳、
大龍堂書店、1991)
建築をつくることは人間の場所について考えることですが、建築には2つの「場所」があると最近考えています。ローカル(Local)とローカス(Locus)です。まずローカルは、たとえば代官山やヒルサイドテラスといった地域や建物など、僕たちが普段慣れ親しんで使っている「具体的な場所」に対応する言葉です。もうひとつの「場所」であるローカスは、遺伝学の言葉でDNAのどこに位置しているかという意味で、人類学的な時間をもついわば「抽象的な場所」のことなのですが、建築の領域ではアルド・ロッシの『都市の建築』(大島哲蔵+福田晴虔訳、大龍堂書店、1991)のなかでたびたび出てくる用語で、ロッシはローカスを、ある特定の敷地とその場所に立地する構築物とのあいだに見られる特異で普遍的な関係のことだとしています。また「都市は集団的記憶の〈場(ローカス)〉なのだ」とも述べています。
僕は特異で普遍的な、個人的でありながら集団的記憶に触れる建築をつくりたいと考えてきました。あるいは建築としての自律性をもちながら、周りの普通の建物との繋がりをもつものであってほしい。つまり場所(ローカル)に応えるのと同時に、自分のつくった建築が歴史上どう位置づくかという、建築の遺伝子的な場所(ローカス)をいつも気にしながら設計してきました。そのどちらか一方では駄目で、現実の場所にも応答しながら、建築のタイポロジーやエレメントを通して、建築の歴史的で人類学的な時間との関わりをもちたい。そうしたローカルとローカスというふたつの「場所」が交わるところに建築をつくりたいと考えています。
保坂──DNA配列における位置づけという話はおもしろいですね。というのも、無限にも思える数の要素が並んでいるなかの、どこかのパーツ(一部)ということですから。しかもその並びは螺旋状になっている。モダニズムの歴史の考え方は基本的に線的で、その最先端にいることが新しさを保証しているという考え方でした。しかし、螺旋構造を思い描きながらいまの考え方を聞くと、過去、現在、未来すべてを含んだうえで、どこをとってもいいという歴史観をどこかで長谷川さんは持っているのではないかと感じました。僕なりのたとえをすると、歴史をモザイク状の面ととらえて、その欠けた部分にピースを埋めていく作業とでもいいますか。
建築の自律性──あらゆるものに配慮して、でもそのいずれにも依存しない
保坂──ところで、「建てない建築家」が最近注目されていますよね。『カンバセーションズ』は、そうした動きへのカウンター・パンチのようにも見えるんですが、建築界からの反応はどのようなものなのでしょうか。長谷川──先ほどお話したようにもともと持っていた問題意識がモチベーションになっているので、この本を現在の状況に対するカウンター・パンチというよりも、もっと長い射程で考えたいと思っています。反応としては、いまのところ日本よりもヨーロッパからの反響のほうが圧倒的に大きいので、今日はどんな意見が聞けるか楽しみにして来ました。せっかく多くの方に集まってもらっているので、会場からの意見も聞いてみたいと思います。
会場1──僕自身設計の仕事をしていますが、この本でも触れられているように、僕よりも少し上の60年代後半から70年代初めに生まれた世代の人は、どこか新しさを追いかけているような印象があり、僕はそこに違和感を感じています。日本国内のポストモダンは、バブル崩壊とともに強制終了されたと思っているんですが、その頃を境に歴史を参照することからみんな撤退してしまって、もう一度ゼロベースから新しいものはなにか、ということをやりはじめていたように見えます。
そういう時期も過ぎて、改めてもう一度建築をつくることを考えたときに、歴史のことを考えるのは自然なことだし、この本を読んでいまの時代について考えながら、歴史に対して自由に構えていいんだと、楽になった気がします。僕から一つ質問をさせていただきたいのですが、6人と話して長谷川さんがもっとも共感した人はどなたでしたか。
長谷川──ありがとうございます。そうですね、共感する部分はそれぞれの人にありましたが、本になってから改めて全体を読み返してみたときに、シザとの対話のなかで出てきた「多重性」という言葉がしっくりきました。シザは敷地や自然、経済性や政治、ありとあらゆることに配慮して、でもそのどれかに依存しない建築をつくる意義を話していたのですが、これはとても示唆的な発言だと思います。いろんな文脈に配慮した結果としての建築の自律性。いろいろな文脈にただ応えているだけでは建築は応答の総和にしかならないんですよね。重要なのは、さまざまな文脈に一旦グッと近づいていって全体を理解したあとに、どれかに依存しないようにそれぞれから距離をとることで、結果として建築は自律性を獲得する。この感覚はとても共感します。ちなみにこの建築の状態を、対話のなかではMultiplicityと言っているのですが、これに「多様性」ではなく「多重性」という訳をつけました。あらゆる具体的な文脈に配慮してそのいずれにも依存しないというシザのMultiplicityは、関わる対象の種類が多いこと(多様性)よりも、建築の自律性にさまざまな関係性が主体的に束ねられていることに意味があるので、翻訳家の方に相談のうえで「多重性」としました。

- アルヴァロ・シザ《レサのスイミング・プール》(1966)撮影=長谷川豪
公共建築の歴史観、住宅建築の歴史観──ローカルとローカルがつながる
会場2──『建築と日常』という雑誌を個人で出版している長島明夫と申します。たまたま『カンバセーションズ』と同時期に「現在する歴史」というテーマで最新号を出したのですが、長谷川さんのほうと違って、こちらでは日本人の建築家3人にインタビューをしています。意地悪な質問ですが、明治以降、日本人は西洋から学ぶ、識者が西洋の建築を紹介するという流れがあって、この本もその歴史的な流れのなかにあると思っていいのでしょうか。
長谷川──この本はヨーロッパ礼讃、あるいは海外から最新スタイルを輸入しようという内容ではないですよね。こと歴史において、彼らの姿勢に参考にできることはあるけれど、彼らがやっている実践の方法論を今の日本にそのまま輸入しても意味はないと思います。保坂さんからもこの対談がはじまる前に、なぜ日本人を入れなかったのかと聞かれました。じつは同じテーマで日本人の上の世代の建築家に話を聞くという案も最初はあったし、それもあり得たと思うんですが、今回はあえて日本の建築家を外して、歴史というものを客観視することを優先しました。
保坂──この本で取り上げられている建築家の作品は、日本では見られないですよね。海外の建築家でも日本で実作を見ることができるインターナショナルな建築家はいるにもかかわらず、そういう人はあえて外して相当ローカルな建築家たちが選ばれている。結果論だとしても、設計自体をインターナショナルに行なっていなくても、インターナショナルに評価されている建築家が掲載されていて、そこがおもしろいところだと思いました。
長谷川──たしかにそうですね。まず僕がメンドリシオで教えていた状況がおもしろいと思っていて、日本でほとんど住宅しかつくっていないような日本の若手建築家がヨーロッパの大学で教えるなんて20年前にはなかったですし、あるいは僕より年下の世代でも海外のローカルな場所でプロジェクトをもつことが普通のことになってきている。世界で認められた巨匠だけがインターナショナルに活動していたのが20世紀だったと思うのですが、いまは直接ローカルとローカルが出会って互いに影響を受け合うということが建築以外の領域でもいろいろな場面で起こっている。それは情報技術の発達でローカルな活動が世界に届きやすくなったとか、飛行機代が安くなったとか、いろいろな要因で可能になったのだと思いますが、僕はいまの時代のローカルとローカルに可能性を感じていて、それはかつてのインターナショナル経由の外国文化の輸入とはまるで違うものだと思います。
長谷川──いま台湾・台北で歴史的な保存建築の改修と増築のプロジェクトを進めています。いわゆる官民共同の公共的なプロジェクトで、来春に完成予定です。もちろんスケールなどの違いはありますが、歴史や時間への向き合い方を含め、設計の仕方ということでいうと実感としては住宅でこれまでやってきたこととほとんど変わりませんね。むしろそういう歴史的意味が大きなプロジェクトだからこそ、それを客観視する改修というか、ベタにその建物の歴史のみに入り込まずに複数の時間が並走する状態をつくろうとしています。
でも保坂さんにいま指摘いただいたように、日本の公共建築は人々にとってわかりやすい歴史観を、住宅は作家個人の歴史観を、という対立は一般的にはあるように思います。最近の公共建築のプロポーザル方式では「わかりやすいことが良し」ということがますますイデオロギー化していて、実践としてはかなりベタな方法論に陥っている。どうにかこの状況を変えていきたいのですが。
歴史観を含みこんだ建築展示は可能か
保坂──以前僕が企画した「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」展(国立近代美術館、2010)では、建築家には、実作の紹介ではなくインスタレーション作品をつくって欲しいと依頼しました。というのも、通常美術館は「作品」を展示する場所なので、それ以外のものを持ち込むのは難しいからです。と同時に、美術界では、インスタレーション作品ばかりが制作されて、規模が大きくなると、それだけで時には建築的な作品だと言われたりする、そんな状況に対する不満もあったので、建築家もインスタレーションをつくれるんだから、アーティストは他のことをやった方がいいんじゃないか、なんて気持ちもどこかにありました。もちろん建築家がつくるインスタレーションは、アーティストとは違うスタンスでつくることになるだろうし、実際そういう作品が集まったと思っています。そんな展覧会を企画する際、いろんな世代を入れようと考えるなかで、長谷川さんは真っ先に落選しました(笑)。それはなぜかというと、この人はインスタレーションをつくらないだろうな、と思ったんですね。長谷川──つくりますよ(笑)
保坂──だとすると、それはやっぱり僕のキュレーターとしての能力の限界なんですけど、ごめんなさい、とても想像ができなかったんです。もしお願いしても「僕は人が住まない空間はつくりません」とか言われそうだと思って(笑)。でもそれは長谷川さんのいいところでもある。その時参加してくれた建築家が間違っているということではけっしてないんですが。
長谷川──いや、このあいだフランスで学生とやったワークショップでは「プリミティヴで最小限の建築とは何か」という問いから、草原の中に穴を掘るインスタレーションのようなものをやりました。寸法を綿密に定義して、メンバー6人のスケールの空間を自然のなかにつくりました。だからインスタレーションもできると思うんですけど......。でもたしかに、ギャラリー間の展覧会では中庭に建築(《石巻の鐘楼》2012)をつくりましたね(笑)。

- 長谷川豪《ブアブシェのホール》(2014)撮影=長谷川豪
保坂──そういう建築家はいてもいいだろうし、いるべきなんです。むしろ、僕ら美術館側はインスタレーションをつくらない建築家を、どう見せればいいのかを考えなければならない、いまはそう思っています。建築を学んだ人だけが観るなら図面や模型の展示でいいのかもしれませんが、美術館という枠組みではなかなかそうはいかない。ではどうすればよいか。そういう観点においても、『カンバセーションズ』からはヒントをもらったと思っています。ここで見えてくる歴史観の違いをうまく展覧会に組み合わせることができたならば、展示としておもしろいものになるだろうなと思いました。
じつはいま、海外で日本の住宅を紹介する展覧会に関わっているのですが、その展示では戦後から現代までの日本の住宅だけで構成します。なんの予備知識ももたない海外の人に日本の住宅のおもしろさをどう伝えていくのか、これは難問です。現段階では建築家と建築史家にスーパーバイザーになってもらって、スクールで見せるのは結局「人」で語ることになりかねないからなるべく避けて、住宅作品を単位とした系譜学の観点から見せていこうと話しています。安藤忠雄さんの《住吉の長屋》と何がつながるか、長谷川さんの《経堂の住宅》と何がつながるか、模造紙上で系譜をマッピングしているところです。なにか新しい展覧会ができそうな予感があります。美術館という、街や歴史と切れた、地面のない場所でどうやって建築を見せていくことができるのか、それが僕自身の課題であり続けています。
長谷川──「人」ではなく「住宅」を単位とした系譜学の展覧会というのはおもしろそうですね。美術館での建築展はたしかになかなか難しい課題です。「建築はどこにあるの?」展のなかでは、アトリエ・ワンの「まちあわせ」は上手いなと思いましたが、それでもあれは美術館の外でしたよね。僕だったらどうしただろう? 美術館や展示室の歴史やコンテクストをそれでも読み解こうとしたかもしれない。
保坂──さまざまなかたちで建築家と美術家は共同作業ができるはずです。特に日本の場合は、建築を恒常的に扱っているところがないので、美術館のキュレーターとして建築を見せていくことは責務だと思っています。よく「なぜアート界の人が建築展をやるんですか」と聞かれるんですが、いつかそういう質問が無くなるといいと思っています。
エリック・ホブズボームというイギリスの歴史家の『破断の時代──20世紀の文化と社会』(慶應義塾大学出版会、2015)を読んでいて、そこに衝撃的なことが書いてありました。絵画、彫刻、文学、音楽など、いろいろな芸術のジャンルがあるなかで、なくならないものは建築と文学くらいで、絵画や彫刻は余命いくばくもないというのです。彼に言わせるとメディウムがいろいろ変わっていってもフォーマットを合わせていけるジャンルは残るそうです。その点建築はつねに技術の側にあるからフォーマットは合わせていくのは得意だし、なにより人が住まなくなることはないだろうから、残る可能性が高い。それを読んでますます本腰を入れて、ある意味絵画以上にやらなきゃいけないなと思いました。
建築の抽象性、歴史の抽象性
保坂──わかりやすいかたちで建築の歴史を学べる場所としての建築の資料館(アーカイヴ)や博物館(ミュージアム)があまりに少ない。NAi(オランダ建築博物館)もカルチャーを含む施設へと組織替えし、その名はなくなってしまった。組織替えしてから行ってないので現状はよくわからないのですが、少なくとも変わる前のNAiは、レム・コールハースが監修にかかわるかたちで、オランダの建築の歴史をおもしろく伝えていました。それを見て20世紀以降の建築の歴史をコンパクトにフォローできる場所が身近にあることはいいなと、あらためて思っていたんですが。そういう場所があれば、つねに歴史観をブラッシュアップできるし、実際に町なかに行けば、20世紀の以前の建築も残っているので、つねに立ち返ることができる。歴史を身体化することができるわけです。しかし日本だとなかなかそうはいきません。資料館もないところでスクラップアンドビルドばかりが進む国で歴史を問うていくことは相当難しい。そうした状況で、まだ若手と言える長谷川さんがこの本を出されたことがおもしろい。ひょっとしたら長谷川さんは戦略的にやったのかもしれませんが、日本人を対談相手に加えるときっと歴史を抽象化できなくなってしまっていたでしょうね。「建築を抽象的に考えることができるか」という命題があると同時に、「歴史を抽象的に考えることができるか」という命題もこの本にとってはとても重要だったのではないか。その距離感を大事にされていたように感じました。
僕は6本の対話の後にそれぞれ短い文章を書きました。対話から一歩引いてみて、遠い国から来て細かいコンテクストや裏事情を知らない僕と彼らとの距離感を定着させる試みでした。先日ヴァレリオが本の感想を送ってきてくれて、これらのテキストによって6組の建築的思考があらわになると同時に、僕自身の興味が逆照射されているのがとてもおもしろかったと言ってくれました。
保坂──長谷川さん自身の興味というのは、具体的にはどのあたりにあるのですか。
長谷川──読み返してみたときに、自分が6組の建築家に対してそれぞれ違うタームを使いながら、建築の自律性について繰り返し聞いていることに気づきました。シザが語っていた「多重性」の話に繋がりますが、社会状況に反応するリアクティブな建築が増えていくなかで、僕は現代建築の自律性がいかに可能かについて考えたかったのだと思います。この本をつくることでそれに気づくことができたことは大きな収穫でした。
[2015年5月10日、代官山 蔦屋書店にて]
長谷川豪(はせがわ・ごう)
1977年生まれ。建築家。2005年長谷川豪建築設計事務所設立。2009−11年東京工業大学ほか非常勤講師、2012−14年メンドリシオ建築アカデミー客員教授、2014年オスロ建築大学客員教授。主な作品=《森のなかの住宅》(2005)、《駒沢の住宅》(2011)、《石巻の鐘楼》(2012)、《御徒町のアパートメント》(2014)ほか。主な著作=『考えること、建築すること、生きること』(LIXIL出版、2011)、『カンバセーションズ──ヨーロッパ建築家と考える現在と歴史』(LIXIL出版、2015)ほか。
保坂健二朗(ほさか・けんじろう)
1976年生まれ。東京国立近代美術館主任研究員。著作=(共著)『JUN AOKI COMPLETE WORKS 1 1991-2006』(INAX出版、2006)、(編著)『キュレーターになりたい! アートを世に出す表現者』(フィルムアート社、2009)、(監修)『アール・ブリュット アート 日本』(平凡社、2013)など。企画した主な展覧会=「建築がうまれるとき ペーター・メルクリと青木淳」(2008)、「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」(2010)、「ヴァレリオ・オルジャティ」(2011)「高松次郎ミステリーズ」(2013)など。





