生の形式としての建築展示
建築概念と展示形式の変遷

- 『インターナショナル・スタイル』
(鹿島出版会、1978、原著=1932)
一方、1980年にパオロ・ポルトゲージがディレクションした第1回のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展は、近代建築の合理的画一性や生産主義的アプローチへの批判として、「過去の現前(Presence of the Past)」をテーマに開催された。ポストモダニズムが指し示すコンセプトを現実の空間として提示したことが、のちの世界的なポストモダニズム建築の流行に強い影響を与えた。ここでは参加した20組の建築家によってさまざまな時代・地域の様式を記号的に操作しデザインされた建物のファサードが、インスタレーション形式で元造船所の空間に実物大で制作され、都市の街路のような空間がつくり出された。この書き割り的な舞台装置は、会場そのものを固有の場(サイト・スペシフィック)へと変換し、観客は身体的にその空間を体験する。このように空間を場所の固有性と身体性へと還元する傾向は、以後のポストモダン、さらには一見すると相反するさまざまな建築潮流のなかで重視されてきた。そしてインスタレーションは、これらをわかりやすく体験として受け取ることのできる手法として、現在も美術館の内外で用いられている。
関係性なるものへの転回

- 『表象05』(月曜社、2011)
社会的諸関係そのものを対象とする潮流は、アートの領域においても90年代後半から00年代にかけて議論されてきた。キュレーターのニコラ・ブリオーが「関係」の創出という観点から同時代の作家たちを論じたエッセイ『関係性の美学』が1998年に出版され、リレーショナル・アートという言葉が普及する。美術史家・美術批評家のクレア・ビショップは、『関係性の美学』の枠組みを評価しつつも、ブリオーの考える関係性の中核をなす「現在の隣人たちとのありうべき」ミクロトピアへの志向性を批評し、むしろ対立関係が解消されるのではなく維持されるような社会の「敵対」に目を向けることの重要性を指摘している★2。
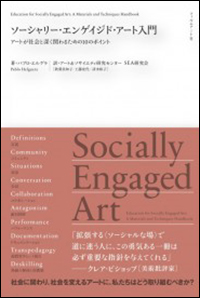
- 『ソーシャリー・エンゲイジド・
アート入門』(フィルムアート社、2015)

- ハル・フォスター『アート建築複合態』
(瀧本雅志訳、鹿島出版会、
2011、邦訳=2014)
このような建築を狭小住宅から都市再開発まで種々のスケールで現われてくる社会的諸力を媒介し相互介入を含みこんだ実践として捉えるプロジェクトは、ポスト震災というべき社会的状況のなかで注目を集めてきた。金沢21世紀美術館で昨秋から今春にかけて開催された「3.11以後の建築」展は、そのような流れをうけて開催された国内初の公立美術館における展覧会だった。新しい建築の動向をひとくくりに示す展覧会がパブリックな場で開かれるという意義は大きい。しかしながら、個別にはさまざまな工夫がされているものの、パネルや模型によってこれまでの経緯を紹介しているものが多く、ひたすらメディアを介した情報を読み込むという展示方法には課題も感じられた。パブロ・エルゲラも、社会的相互介入そのものを目的としたアートプロジェクトは、展覧会で提示される場合、何かしらのメディアによる記録となってしまい、それは現実の代理体験の役割をはたすものではないために、観客にフラストレーションを引き起こすと指摘している。
建築展が示す内容が様式・造形原理から身体性・場所性へと移行するなかで、展示方法も模型と図版からインスタレーション(空間体験)へと変化したように、ポスト震災における諸実践における展示内容とその方法とはいかなるものとして考えることができるだろうか。
「生」そのものとしての建築実践
美術批評家のボリス・グロイスは「生政治〔バイオポリティクス〕時代における芸術──芸術作品〔アートワーク〕からアート・ドキュメンテーションへ」において、生政治(主要な統治対象が生に持続したものとなる政治的統治形式)の時代においては、芸術も何かしらの現実や原理の記号=イメージとしてではなく、生(もしくは現実的状況)そのものとなると述べる★6。先に示したポスト震災の時代における建築家の諸実践も、その結果として生み出された建築作品というよりは、プロセスとそのなかで生まれる関係性こそが重要なものとして理解されている。この「生」そのものの実践は、それがプロセスそのものであるために、展示においては諸所のメディアによる記録、つまり(アート)ドキュメンテーションによって表象される。グロイスは、それが何かしらの方法で空間に展開するという意味で、ドキュメンテーションの展示は一種のインスタレーションとして把握されるとし、以下のように述べている。インスタレーションというものは、画像や文章、その場に設置されるそれ以外のオブジェだけでなく、インスタレーションの空間そのものが決定的な役割を果たす芸術形式である。つまり、この空間は抽象的あるいはニュートラルなものではなく、それ自体が一つの生の形式をなしている。かくしてある特定の空間へ自らを書き込む行為としてドキュメンテーションをひとつのインスタレーションに形づくることは、ニュートラルな展示の行為ではなく、物語が時間の次元で果たすことを空間の次元で果たす行為と言える。いわばそれは生の書き込みという行為なのだ。★7
このように、生そのものとしての実践は何かしらの記録=ドキュメントとして提示されざるをえないが、それが設置される空間にその生の形式を書き込む行為=ドキュメンテーションとしての展示は可能である。つまり、諸所の建築(的)実践の展示においては、その出来事自体を一方的に記録し語るのではなく、実践において形成される社会的相互作用、関係性の形式を展示空間のなかにいかに書き込むかということが重要となる。展示は単に出来事を指し示す記録を見る、理解するという行為から、その空間に書き込まれた生の形式を辿り、解釈するための場として開かれる。では、この生の形式の空間への書き込み=ドキュメンテーションはいかにして行なわれるのか。そのヒントになるであろう建築の展示(アートプロジェクト含む)について、以下に簡単なコメントを記してみたい。
浜松を中心に活動する403architecture[dajiba]が、浜松の小さなイベントで行なった展示・インスタレーション★8は、彼らが浜松での日々の実践を通じて知り合った人々(クライアント含む)がインタビューイーとなり建築家について語る映像を、インタビューイーが使っている愛用のイスに座って見るというものであった。この映像は、語りを分解し、共通の話題によって再構成することで、同じ話題のなかで建築家に対する複数の印象が示される。その複数化されたイメージが徐々に網目状に展開していくことで、彼らの築いている関係性はクライアントと建築家という単一のものではなく、さまざまな役割やパーソナリティが流動しながら形成されており、建築家と街との関係性であることが示されている。さらにイスに座るというとても強い接触性をもつ行為は、座るイスによって異なる持ち主との擬似的なつながりを生み出し、建築家がつくり出している関係性の渦へと身をゆだねているような感覚を得ることができる。このように映像の編集形式に、またそれを鑑賞する空間として、日々の実践が生み出す関係性の形式がドキュメンテーションされていた。

- 画像提供=403architecture[dajiba]
また2014年の第14回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館の展示「In the Real World 現実のはなし──日本建築の倉から」★9は、70年代を基準点とした日本の建築100年のリサーチと、その結果集められた大量のモノが展示され、会場構成を担当した小林恵吾によってさまざまな文脈が重なり合う場として巧みに配置されていた。そこでは一定の見通しが暫定的に提示されてはいるものの、圧倒的な物量はそうした主催者側の整理を意図的に無効にし、モノは単一の証言=ドキュメントであることをやめ、観客はその場において、複数のモノを関連づけながら、文脈を自らつくり出すことになる。タイトルにもある「現実のはなし」とはけっして誰かが特権的に語るものではなく、一人ひとりが無数に散らばる過去の痕跡のなかから、何かしら意味のある星座をつくりだし、書き込んでいく場として展示空間は作用していたのではないだろうか。展示自体はまさに記録=ドキュメントの集積ではあるが、そうしたモノを現在性のなかにひらくことで★10、観客は固有の解釈と経験を空間のなかに見出す。

- Photo=Takeshi Yamagishi、画像提供=国際交流基金
「あいちトリエンナーレ2013」での藤村龍至の「あいちプロジェクト」は、名古屋市内の具体的な都市デザインの提案を会期中に作成し、毎週観客による投票を実施しながら、最終的な提案にまとめていくというものであった。生み出された案と投票の結果が日々記録されるが、生み出された案(それ自体は記録として示されている)そのものよりも、実際のプロジェクトで用いられている「投票」という行為が一種のパフォーマンスとして空間のなかに組み込まれることで、異なる主体間の意見を統合する建築の力場そのものがドキュメンテーションされていると考えることもできる。

- 撮影=菊山義浩、提供=藤村龍至建築設計事務所
同じく芸術祭における作品として建設された、dot architectsが小豆島で取り組んだ《Umaki camp》は、会期終了後の現在も小さな社会実験の場として活用されているソーシャリー・エンゲージド型の建築プロジェクトとして位置づけることができる。彼らは住人参加のワークショップや、共同作業に対して批判的な立場をとっている。彼らが選択した自力建設という手段は住人の参加を可能にするためにではなく、むしろ一種のパフォーマンスとして地域住人に彼らが建設している姿を提示するためのものだ。完成後は、それまで観客であったはずの地域住人が《Umaki camp》という舞台でさまざまなパフォーマンスを繰り広げ、芸術祭の会期中に訪問した観客はそうした現場を目撃する。また建築は、どのようにつくられたかを読み取ることが極力可能なようにデザインされているという。建築がその使用も含めた時間軸のなかで形成されるものとして理解するならば、日々の地域住人による振る舞いは、建築家が刻んだつくりかたのドキュメントに、実践を通じた建築プロセスの続きをドキュメンテーションする行為として捉えることもできないだろうか。

- photo=Yoshiro Masuda
以上、4組の建築家の実践とその展示におけるドキュメンテーションのあり方を探った。先に述べた、空間のなかに「生」そのものの形式を書き込むドキュメンテーションは、まずもって諸実践のなかで産出される関係性の質や構造そのものを、展示空間のなかで実現させることなのかもしれない。「生」そのものが建築(芸術)であるポスト震災における展示は、単にその「生」を指し示す記録、一方的な出来事の証言を語る場ではなく、その空間に書き込まれた「生」の形式を読み取り解釈し、評価することによって成立する。この時、展覧会は、まさにひとつの「生」として、それ自体が相互的なプロセスの場へと拡張していく。
註
★1──ヘンリー=ラッセル・ヒッチコックJr.、フィリップ・ジョンソン『インターナショナル・スタイル』(武澤秀一訳、鹿島出版会、1978、原著=1932)
★2──クレア・ビショップ「敵対と関係性の美学」(星野太訳、『表象』05、月曜社、2004、邦訳=2011)
★3──パブロ・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門──アートが社会と深く関わるための10のポイント』(アート&ソサイエティ研究センターSEA研究会訳、フィルムアート社、2015)
★4──クレア・ビショップ、前掲書
★5──ハル・フォスター『アート建築複合態』(瀧本雅志訳、鹿島出版会、2011、邦訳=2014)
★6──ボリス・グロイス「生政治〔バイオポリティクス〕時代における芸術──芸術作品〔アートワーク〕からアート・ドキュメンテーションへ」(三本松倫代訳、『表象05』、月曜社、2003、邦訳=2011)
★7──同前
★8──『はままっくすデザイン会議2013』という1日限りのイベント内で実施されたインスタレーション
★9──コミッショナーの太田佳代子氏が関わったOMAの展覧会「CONTENT」(2004)においても同じようなコンセプトの見せ方が試みられている。
★10──70年代のモノ派を代表する作家・菅木志雄は、最近のインタビューで、モノそのものはつねに現在性を持っていると述べている。(『美術手帖』2015年3月号239ページ)
川勝真一(かわかつ・しんいち)
1983年生まれ。2008年、京都工芸繊維大学大学院建築設計学専攻修了。現在、京都工芸繊維大学大学院博士後期課程在席、京都造形芸術大学および京都精華大学非常勤講師。2008年に建築的領域の可能性をリサーチするインディペンデントプロジェクト RAD(Research for Architectural Domain)を設立し、建築の展覧会キュレーション、市民参加型の改修ワークショップの企画運営、レクチャーイベントの実施、行政への都市利用提案などの実践を通じた建築と社会の関わり方、そして建築家の役割についてのリサーチを行なっている。


