空間の静謐/静謐の空間
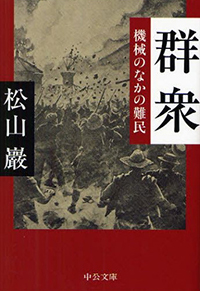
- 松山巌『群集──機械のなかの難民』
(中公文庫、2009)
坂部恵は、生活の営みの根拠が相互人格的な場であると述べつつ、この場が、彼の生きていた時代の動向において、保たれることがむずかしくなっているとも考えていた。
「人間のすべての〈ふるまい〉が、「せぬひま」、「静慮」、vita contemplativaへのひそかな、しかし何よりもたしかな根づきとつながりを失うとき、人間の〈ふるまい〉はおそらく、本来人間の〈ふるまい〉とは呼べないグロテスクな何ものかに変じてしまい、悠久の時このかたひとびとの暮らしをひそやかに支えつづけてきた〈正気〉は、それと気づかれることもないままに生活の舞台をそっと立ち去るであろう。」(坂部恵『〈ふるまい〉の詩学』21頁)

- 坂部恵『〈ふるまい〉の詩学』
(岩波書店、1997)
正気が去るとはどういうことか。それを非理性的な状態と捉えるならば、ニュータウンという空間は、いっそうの理性化を要するということになろうが、となると、合理化、効率化をさらに推し進めていくことで、正気の欠如の克服が可能ということになる。問題は、情報伝達の経路、住民間の意思疎通の不全にあった。とするならば、インターネットの拡充などが進行した今は、正気は回復されているはずである。
だが坂部なら、そうは考えないだろう。正気の消滅は、非理性的で非合理な情念への囚われの帰結ではなく、生活の営みとしての〈ふるまい〉が、「せぬひま」や「静慮」とのつながりを失うことの帰結である。「せぬひま」や「静慮」は、字義通りとらえるならば静かな状態ということだが、坂部が独自なのは、「せぬひま」や「静慮」を、ふるまいの場という、人間の内面性とは独立の領域との接点で考えているところにある。静けさは、生活という営みの条件である場において、場として、生じてくる。ところが坂部は、この静けさの場が、現実生活では、失われていると考えている。
*
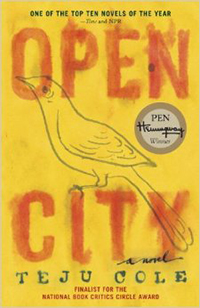
- Teju Cole, Open City,
Random House, 2012.
そこで重要な主題となるのが、静けさである。静けさは、音がない状態を意味しない。最初の部分で、語り手がおそらくは自室で、カナダかドイツかオランダのインターネットラジオを好んで聴取している様子が語られている。なぜかといえば、第一にそれは、アメリカのラジオから流れる宣伝が趣味にあわないからである。ベートーヴェンのあとにスキージャケットの宣伝が流れ、ワーグナーのあとに高級チーズの宣伝が流れるというのが嫌なのだ。語り手は、異国のラジオに耳をかたむける。アナウンサーの言っている言葉の意味はわからない。それでも、彼がそれを聴くのは、それらの声の調子と、語り手自身の心とが、波長をあわせ、共鳴するのを感じるからだ。その同調、共鳴を、快適なものと感じる。これは、音を聴くという営みと、それをとりまく音の環境とが、摩擦なく共鳴し、穏やかでいられる状態である。
この穏やかさがマンハッタンの日常世界で普通に保たれているかといえば、そのようなことはない。朝に目を覚ました語り手が部屋の外に出て街路と出会うとき、そこを「たえまのない喧騒」と捉える。「街の忙しない場所を歩くのは、一日をつうじて見ることのできる許容量をこえた多くの人に、何百人も何千人もの多くの人に目を向けていくことを意味する。だが、こういった数えきれない顔という顔の印象は、私の孤独の感覚を鎮めることはない。どちらかといえば、それはこの感覚を強めるのだ」(Cole, Open City, p.6)。孤独とは、波長をあわせることのできない刺激にみちた都市の街路の只中で感じる緊張感であり、疲弊し苛まれている状態であるが、それがなにゆえに辛いかといえば、静けさの空間が奪われているからだ。語り手は、タワーレコードについてこう述べる。「私はいつも、音楽の店のスピーカーで流されているものはなんであれ、嫌いだった。それは他の音楽のことを考えるという愉楽を台無しにした。レコード店は静かな空間であるべきだ、と私は思った。そこでは、ほかのどのようなところにもまして、心が清澄である必要がある」(Cole, Open City, p.16)。

- John Brewster Jr., One Shoe Off, 1807
静謐が、大切である。静謐のなかに身を浸すことではじめて、私たちは、己が何を考えているか、どのように感じているか、何に共感しているのかを、じっくりと落ち着いて確認し、内省することができるようになる。内省は、一人であってもいいし、親しい人との会話においてでもいい。
*
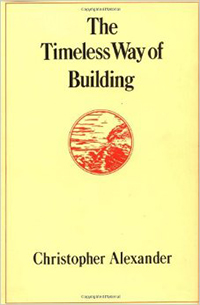
- Christopher Alexander,
The Timeless Way of Building,
Oxford University Press, 1979.
邦訳=平田翰那訳『時を超えた建設の道』
(鹿島出版会、1993)
亀岡市にあるみずのき美術館は、乾久美子の作品である。もともとは町家であった建物の改装だが、たしかに、柱や壁をよくみると、かつて使われていた家の分解過程で産出された木材がそのまま転用されていることがわかる。だがそれも、よくみないとわからない。むしろ、乾の建築作品を経験するときまず思うのは、とても静かな空間である、ということである。簡潔で、静かで、落ち着いていられる。緊張を強いる無音とは違う。そこは、美術館という、作品の展示と鑑賞のための空間である。だから、静けさを空間において生じさせるということが、第一に求められたのだろう。建築の経験においては、形態的な美や意味、都市の意味論的な文脈との照応といったことはじつはもう第一義的ではなく、重要なのは静謐で、しかもこの静謐が空間の質として実在するかどうかが重要な価値となっていることが、作品において、示されている。空間の静謐が、人がいて、作品を展示し、鑑賞し、かかわりあうという営みの条件として、つくりだされている。
坂部が述べていたように、私たちの生きている世界では、正気は去りつつあって、ふるまいは醜悪になり、人心の荒廃もすすんでいると考えることはできる。この醜悪、荒廃を、耐え難いと思う人もいる。ではいったい、それは新しい事態なのか。私には、そうとは思えない。坂部が述べていたのは、1990年代である。正気は、すでに20年前に去りつつあったといえるだろうし、トイレットペーパー騒動が起こったのは40年前のことである。現在は、ここ40年来進行していた事態が、さらに徹底化した状況にあると考えることもできる。40年のあいだにも、何が問題であるかを考えている人はいた。今できるのは、彼らの思考を継承し現代的な展開を試みることである。
空間の静謐が重要である。そしてこの静謐は、空間の質という、アレグザンダーが提示した問題にかかわる。乾久美子の作品に共感したのは、この質をめぐる思考と実践の模索の痕跡を感じたからである。
篠原雅武(しのはら・まさたけ)
1975年生まれ。社会哲学・思想史、大阪大学特任准教授。京都大学人間・環境学研究科博士課程修了。主な著書=『公共空間の政治理論』(人文書院、2007)、『空間のために──遍在化するスラム的世界のなかで』(以文社、2011)、『全-生活論──転形期の公共空間』(以文社、2012)。主な訳書=シャンタル・ムフ『政治的なものについて──ラディカル・デモクラシー』(共訳、明石書店、2008)、マイク・デイヴィス『スラムの惑星─都市貧困のグローバル化』(共訳、2010)、ジョン・ホロウェイ『革命─資本主義に亀裂をいれる』(共訳、河出書房新社、2011)、ロビン・D・G・ケリー『フリーダム・ドリームス─アメリカ黒人文化運動の歴史的想像力』(共訳、人文書院、2011)ほか。


