都市を考察するロジック、建築をつくる方法
60年代末と90年代末という時代
藤村龍至──この度11年間勤められた芝浦工業大学を退職されるということで、これまでの八束さんのキャリアからお伺いしたいと思います。
八束はじめ──僕が大学に入ったのは1967年で、丹下健三研究室に進んだのが1971年です。当時は学園紛争の只中でしたから、丹下研究室は事実上ないようなものでした。丹下先生はURTEC(丹下健三・都市・建築設計研究所)に活動の比重を移していて、研究室に来るのは年に3回ほどでした。僕は弟子といっても、多分顔も名前も覚えてもらっていない程度のものです。学園紛争が落ち着き、修士1年の時に丹下先生は退官されました。
丹下さんというとル・コルビュジエを連想しがちですが、それは個人としての作家に対してであって、最初の渡欧の際にヨーロッパが遅れていることにがっかりしたこともあって、将来的な指針としてはむしろアメリカの影響が大きかったと思います。槇文彦さんが1952年に渡米してハーバード大学に行きましたが、槇さんを通じてアメリカの情報を入手していました。それが後の丹下研究室のアプローチの原型をつくったのではないかと思います。また、丹下研究室はオーバードクターで多くの人が長く所属していました。磯崎新さんのように辞めてからも丹下さんと仕事をするケースもありますし、その蓄積やネットワークはすごいと思います。
そういった伝統は僕が研究室に入ったときはもうありませんでした。丹下さんが退官される時も、きちんと整理をしていたら貴重な資料も出てきたと思いますが、かなり失われたのではないでしょうか。
その後、大谷幸夫研究室に4年間所属しました。大谷研究室は当時、川越について地域保存に取り組んでいましたが、自分は「壊してもいい」ということを言わない保存は違うと考えていて、あまり加わりませんでした(笑)。ただ、先生からの別の面での影響は結構あったと思います。僕は最近「悪の都市計画」とか悪ぶっている(笑)ので、聖人君子で知られた大谷先生とは正反対のように見られると思いますが、基底にはモラルを残している積もりでいますので。じゃないと社会とか都市とか語れない訳で。
なので、僕は特殊で、研究室のテーマに沿って研究を始めたわけでもなく、とにかく何もないところからキャリアを組み立て始めました。その時に勉強しようと思ったのが歴史です。都市は歴史的に形成されていくものですから、それを知らなければ話にならないと思い、都市史を英語文献で勉強し始めました。当時だと日本語では殆どなかったので。
後からわかったことですが、丹下さんや丹下さんのライバルであった内田祥文さんも戦争直後はやはりそうやって何もないところから勉強を始めています。その意味では戦争直後と大学紛争直後は似ていたかもしれません。

- 八束はじめ氏
藤村──都市史の研究から建築批評を始められたのはどのような流れだったのでしょうか。
八束──大学紛争の世代なので当時は左翼文献を読むのが一般教養という時代でした。マルクスやレーニンを読み、建築や自分たちの仕事を通して社会を変えることに対する憧れ、野心があった時代です。
都市史は自分にとって教養を身につけるためのものでしたが、その勉強を通してフランス革命やロシア革命に興味を持ちました。
博士課程の頃に磯崎新さんが指導されていた建築学科の読書会に参加していて、そこではピーター・アイゼンマンたちがやっていた『OPPOSITIONS』を読んでいました。そこが初めてではなかったけれども、磯崎さんと関係が出来ていくきっかけですね。建築批評への関心も自分で選んでそうなったというよりは成り行きです。
藤村さんの場合は社会工学科から建築学科に移られましたが、どんな経緯だったのですか。
藤村──都市計画や都市設計に興味があり、当時はそれほど建築と社会工学の区別をしていませんでした。学部4年生の時には、東京工業大学社会工学科の土肥真人研究室に所属していました。土肥先生はカルフォルニアに留学されていて、参加型オープンスペースデザインの中で、特に「方法」について主張していたランディ・ヘスターと恊働されていた経緯もあり、住民参加の方法論を研究テーマのひとつにしていました。
その頃は都市計画の時代が終わったとされ、いわゆるひらがな「まちづくり」の時代に入っており、地方分権が叫ばれ始めた頃でした。いろいろな都市コンサルタントがノウハウとマンパワーを求め、大学の研究室にアプローチしていました。その流れで土肥研究室も市役所や地域に乗り込み、模造紙を広げ、付箋を貼るようなワークショップをしていました。
私はファシリテーターをしている先輩の手伝いで、付箋とマジックを持って議論の内容を記録するような役割でした。議論に集まったおじいさんやおばあさんたちは、最初は黙って座っているのですが、ファシリテーション・グラフィックスという手法を使うと、10分後には堰を切ったように活発に議論し始めます。それが模造紙に組み上がっていく様子を見た時は衝撃でした。ただ、議論をしていろいろな人が考えていることが模造紙に描かれていくこと自体はおもしろかったのですが、具体的な計画案にする時に、その議論から飛躍してしまうことに次第に不満を抱くようになり、文句を言っていたところ「いいからお前は建築に行け」と言われました。
そこで、大学院は建築を受け、塚本由晴研究室に入りました。塚本さんは「この長い空間は気持ちいいよね」という感じで住宅を設計されていて衝撃でした(笑)。その空間を施主が「良い」と思うならわかりますが、建築家がそう思うからと言ってそれを根拠に案を決めていくとはどういうことなのか最初は理解できなかったのですね。後に、建築設計とは決定の主体を代理し、いろいろな人の合意を形成していく職業であると理解しましたが、最初はただ驚きでした。
やがてその建築設計の構築性と、住民参加の開放性が自分の中で統合され、プロセスの設計を主張するに至りました。段階的に発展させていくことで、少しずつ人のニーズを形にしていく方法を考えるようになりました。

- 藤村龍至氏
八束──僕とは違って藤村さんは順風満帆ですね(笑)。紛争がなかったからでしょうね。研究室に入る前に塚本さんをどう知ったのですか。
藤村──当時から塚本さんは世代のオピニオンリーダー的存在で、『10+1』などを読み、活発に発言をする人だというイメージを持っていました。また、塚本さんと貝島桃代さんは、オランダ建築やスイス建築の窓口のような役割を果たしていて、塚本研究室はヨーロッパのいろいろな情報が入ってくる場所というイメージがありました。今と少し違うのは、そういった海外の「震源地」があったことで、その頃はオランダ、スイスへ留学した人が、いろいろな情報を持ち帰って来ていました。
私もオランダのベルラーへ・インスティテュ−トに留学し、ヴィニー・マースのスタジオを取りました。MVRDVが一番ノっている時期でした。数字で説得したり、線形で進めるという手法です。オランダは合意形成の国で、少しずつ説明をしてある種のコンセンサスをつくっていきますので、その意味ではそれまでの自分の関心とも連続していました。
設計における方法の重要性
八束──そのような経験が今の藤村研究室に活かされているのですね。
藤村──そうですね。東洋大学に着任して4年が経ちましたが、まず市民の前で模型を並べて、投票によって反応を見て、その結果を周囲の人と一緒に分析していくという方法を教育の現場で試みています。議論する前に、成果物をいきなり市民という他者の前に並べるというやり方です。ウェブデザインの分野では「A/Bテスト」と呼ばれる方法があり、社内でディスカッションせずに、とにかく複数の案をリリースして、アクセス数で評価し、良い方を選んで進化させていくそうですが、それに近い方法で設計の授業を進めています。
八束──今の日本の学生はロジカルに説明できない人が多いですね。コンセプトやロジックなしに、フィーリングで物事を捉えています。藤村さんのように明確な方法論だと学生から「こういう形がやりたい」「こういう雰囲気が好き」という反発が出そうですが、そのあたりはどうですか。
藤村──最初はこの方法から逃れようとする学生もいましたが、定着し始めたので、スムーズになってきました。何年か続けていると少しずつ「この案はあの案と比べてここが違う」という感覚が客観的に位置付けられてきます。3年くらい付き合えば新しい方法も馴染んでくるのかなと思います。

- 八束はじめ『ル・コルビュジエ──
生政治としてのユルバニスム』
(青土社、2013)

- 八束はじめ『メタボリズム・ネクサス』
(オーム社、2011)
八束──その位置づけの根拠という点で、少し角度を変えますが、藝大で教えているトム・ヘネガンと話していたら、日本には知識としての建築史はあるけれど、それが自分たちのプラクティスと関係するような教え方をまったくしていないというのですね。彼は、歴史が仮説や方法、コンセプトを組み立てていく重要なレファレンスであるという見方がされていないことを非常に嘆いていました。アメリカの大学でもAAでもそうではありません。
僕の研究室では「ハイパー・デン・シティ」という超高密度都市など、極端な仮説によってデザイン・モデルを考えていきます。この方向にシフトしたのは5〜6年前です。方法的にはアルゴリズミックな手法や、交通や経済などの指標によって都市構造を調べたり、いろいろなものがありますが、基本的には今の「小さな空間」「コミュニティ」などを志向するまちづくりとはまったく違うものです。現在の趨勢とは真逆のことをやっているので、抵抗がありそうな気もしたのですが、学生は意外と素直に取り組んでくれています。その反応はおもしろいと思いますね。
3.11の後、首都機能を分散させるという議論が新聞やテレビで賑わいを見せていた時ですら、研究室では超高密な都市をつくる計画を考えていたりするわけです。あまりにも逆方向だったので、その時はさすがに私も考えて、学生を、自分の意見は脇に置いて分散型都市派と集中型都市派というふたつのグループに分け、議論してもらいました。また、グループのメンバーを入れ替えて、逆の立場も考えてもらいました。でも基本方向はぶれなかった。
研究室の外では理解されなかったと思いますが、そこでの議論は学生にとっても役に立つものだったと思います。自分の研究室を持てて、そういったリサーチができたことは良かった。ただ、大学と社会にはギャップがありますから、極端な事をやっていたのに対して最後にリバウンドが来ることもあります。OBの反応には研究室でのことがすごく役に立ったという人と、あえて語らない人と両方います(笑)。
藤村さんは「ソーシャルアーキテクト」という肩書きですが、普通に見れば新進作家なわけで、いわゆるアトリエ系の設計事務所を志向する学生が入ってきそうですがどうですか。
藤村──もともと東洋大のカラーとして、設計でアトリエ系に進むという人はあまりいませんね。
八束──僕の研究室は藤井博巳先生の後でしたので、初期はアトリエ志向が多かったのですが、次第にそうではなくなりました。アトリエ事務所では大きな仕事ができないので、組織事務所やゼネコン、ディベロッパー、不動産関係に就職するようになり、傾向ははっきり変わりました。設計の研究室なのですが、実際は都市の研究室になっています。研究室を引き継ぐ西沢大良さんもそれを意識されていると思います。
今、若い学生はアトリエ事務所に就職しなくなりましたね。アルバイトはしても就職はしない。夢がなくなってきたとも言えるのかもしれませんが、アトリエ派がすべてではないと思っているのも確かですね。僕は結構健全な感覚のような気もしますが。
藤村──ちょうど私が卒業する頃は就職氷河期で、ゼネコンや組織設計事務所が人をとらなかった時期なので、同級生は広告代理店やディベロッパーなど、いろいろな分野に散らばりました。対して今の東工大の意匠系研究室を出た人たちのほとんどはゼネコン設計部か組織設計事務所に就職しています。
八束──この傾向は今後の建築教育や実践に影響が出るでしょうね。藤村さんの研究室では設計の方法論などは教えられているのですか。

- 柄沢祐輔+田中浩也+藤村龍至+
ドミニク・チェン+松川昌平『設計の設計』
(LIXIL出版、2011)
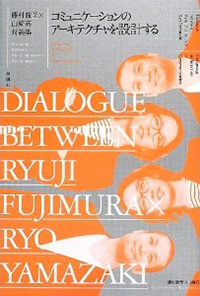
- 藤村龍至×山崎亮『コミュニケーションの
アーキテクチャを設計する』
(彰国社、2012)
藤村──私の担当は2年生と4年生です。東工大でも塚本さんが2年生の担当で、そのTAをやりながら、まっさらな状態の学生がどう建築を学んでいくのかを観察してきました。
自分が社会工学科から建築学科に移った時は、間取り図と平面図の違いがよくわかりませんでした。間取り図は描けるのですが平面図が描けなかったのです。博士課程に入り、塚本さんの仕事を手伝うようになり、ようやく寸法というものを覚えました。「寸法」と「形式」を覚え、ようやく建築の「平面図」を描けるようになりました。
その経験から、つまずいている学生には、まず寸法と形式を教えるようにしています。そうすると一気に建築が組み立てられるようになっていきます。それをそのままオープンな場所でやると市民参加の方法論になるのです。やはり建築の組み立てや成立の「可視化」に関心を持っています。
難しいのは、私の場合は全体を底上げしていく教育方法なので、全員が平均的にスキルアップしていきますが、突出した人があまり出てこない傾向があるようです。これまでの建築教育で一般的にイメージされるのは、ひたすら競争させるスター教育です。今の設計教育の現場は、スター教育と私のようなボトムアップ型の教育が併存しているような気がします。
八束──藤村流のやり方は新しいと思います。設計課題で学生が最初に苦痛なのは、「なぜ、自分の評価がCであいつの評価がAなのか」という評価基準がわからないことです。教える方も「自分でわからないとしょうがないよ」と突き離してしまいます。だと学生は納得できずに脱落していってしまう。
丹下先生は極端でした。生意気な学生がいて丹下さんのレビューに反論すると丹下さんはもう説明しないわけです。「そんなことをおっしゃるなら、あなたは建築家になるのをやめたほうがいいです」と。ことばは丁寧なんだけどあれは本当に怖かった。「世界のタンゲ」にそんなことを言われたら、死ねと言われているようなものですからね。あの時代で丹下さんだからこそ許される発言だと思いますが(笑)。
藤村──「建築をやめろ」というようなセリフは以前よく聞きましたが、最近聞かなくなりましたね。確かにCとAの評価の違いは、教える側もロジックなしに付けているところがあると思います。先生とウマが合えばどんどん伸び、合わないと悶々とするというのは、自分が学生の時もありました。
今は、卒業設計など公開で講評がされていますね。東洋大でもふだんの課題から公開講評を行うようになりました。約200人の学生からスタジオごとに三つずつ、計30作品を選び、場合によってはプロセス模型まで含めて30×4個ほどを並べて、その中からオープンに選んでいきます。製図室は狭いので、模型を並べられるように学食を借りています(笑)。そうすると学生もなぜこれが選ばれたのか議論の経緯がわかるようになる。オープンディスカッションをやるようになって、少し雰囲気が変わったような気がしますね。それは、先生同士の価値観の相対化にも役立っていると思います。
八束──アメリカのスタジオ・レビューでは学生そっちのけで先生が議論というかバトルしたりするものね。学生はナマモノであるというのが僕の持論で、育て方によって本当に化けますし、化けてほしい。今の日本の教育システムでは、それが起きるのは3年生か4年生で、大学院まで行くと化けることはあまりないですね、少なくともデザインでは。
藤村さんは模型を沢山つくりますが、設計の方法としては模型が最初ですか。
藤村──図面が先にあり、模型で全体像を共有するという順番です。修正点の指摘等は図面で行います。
八束──藤村流の方法論で模型が重要だということはよくわかるので、異議はないのですが、一般的な話として、卒業設計などであまりにも模型に力を入れる傾向があるのが気になりますね。大きな模型をつくって満足して、図面が描けない。模型の雰囲気でごまかしているのは今の建築教育の大きな問題かもしれません。
藤村──私が塚本研究室に入った頃、ちょうど妹島和世さんが活躍し始めた頃でした。『妹島和世読本--1998』(エーディーエー・エディタ・トーキョー、1998)という本が出ますが、その中で妹島和世さんは、住宅1軒の設計に対し模型を100個つくるとか、自分は比較でしか選べないということを言っていて、メタファーを使わないのです。敷地にボリュームを置いてみて、合っていればOK、間違っていれば直すという方法です。最近まで、自分も設計とはそういうものだと思っていたのですが、世代によってイメージが違ってくると思います。
八束──そうですね。ただ妹島さんのそういうやり方だとディテールに向かいません。全体はいろいろなスタディをしますが、基本一種類のディテールなので、多様な空間があるように見えますが、実はひとつの空間で成り立っていて、古典的な空間の質という意味では問題を残している気はします。
藤村──確かにそうですね。もちろん実務になれば詳細を詰めますが、学生は図面を描いてから空間をイメージするという手順がなくなっている傾向はあると思います。建築のプレゼンテーションもウェブ画像やYouTubeのようになってきている気がします。画像的な建築というか。
八束──図面を描く際のスケールの感覚がなくなりましたよね。手描きで図面を描いていた頃は、1/30、1/50、1/100ではまったく違うものを描いているという意識がありましたが、CADではその違いがなくなりました。プリントアウトする時の指定でしかないから、たとえば1/30のスケールで図面を描く時のスケール感覚がなくなります。大学院生の頃、丹下さんの建物をいろいろ見に行きましたが、実際に見に行くと大抵想像していたものより大きいのです。反対に菊竹さんの建物は想像していたものより小さい。自分で設計した建物の現場を見に行く時も、デザインしたものが実際にどのくらいの大きさなのかが一番気になります。手描きの図面を描かなくなると、そういうセンスが育たなくなるような気がします。
少し前の世代では、アルヴァ・アアルトのディテールには驚かされました。ヘルシンキに行くと駅の近くにスティーヴン・ホールの《ヘルシンキ現代美術館(キアズマ)》があります。そのすぐ奥にアアルトの《フィンランディアホール》があります。ふたつを比べると、スティーヴン・ホールが考え終えた段階くらいからアアルトはデザインを練っているというぐらいの差があります。アアルトの方が4倍も5倍も労力をかけているのではないかと。アアルトのやり方だけが建築だとは思いませんが、その違いがわからない学生を育てているのではないかという危惧があります。
藤村──篠原一男さんの建築は、「虚構を美しく演出したまえ」という言葉を遺されているように、竣工写真の虚構性にこだわっていらしたので写真で見るとすごく感動するのですが、坂本一成さんの建築は反対に、写真では見えにくいけれど、実際見に行くと非常に細かい寸法の処理がされていて、自分で設計して寸法を設定したことがある人にとってはすごく感動するものだと思います。
八束──坂本さんの寸法って、きめきめでこれしかない、みたいな取り方を敢えてしないところがありますね。そのくせものすごく気を遣って決めている。先日、藤村さんが芝浦工大の卒業設計の講評会にゲストで来られて、原田真宏さんの研究室の学生たちのプロジェクトは形があり、八束研究室の学生たちのは形がないという話をされていたのをおもしろく聞いていました。以前レム・コールハースは磯崎新さんとの対談で「槇文彦さんは形がない人だけど、あなたは形がある人だ。自分も形が好きな方だが、どうなんだろう」という話をしていました。僕はレムはそうなのかなと思いましたが。
僕は建築家としてアトリエ事務所を主宰していた頃は形が非常に好きでした。それが大学で教えるようになってから、もっと広い範囲のシステムで物事を考えるようになり、次第に形がなくなっていったような気がします。建築より都市だからというのもあるでしょうけど。藤村さんは最初は形から入らなかったのですか。
藤村──そうですね。東工大の坂本一成さんも塚本由晴さんも形をつくらない人でしたから、その影響は大きいと思います。また、東工大の先生には「アンチ篠原一男」という思いがあると思います。
八束──篠原さんが強力すぎたということですね。形をつくらないとすれば、よりロジックが必要になりますよね。そのロジックは坂本、塚本、藤村ではどういう関係ですか。
藤村──塚本さんの博士論文は坂本研究室での構成論をベースとしたものです。ところが、2003年頃からアンリ・ルフェーブルを読みだして、「実践」や「ジョイ(快楽)」、最近は「振る舞い(ビヘイビア)」という言葉を軸にされています。アントニン・レーモンド夫妻が藤棚の下で食事するシーンをフォーカスしたり、一言で言うと「外で飯を食べるとうまい」というような(笑)。初期の構成論的な作品への興味から入った私としては距離を感じるようになりました。
なので、隔世遺伝のように坂本さんの影響も受けている気がします。大学院に在籍していた頃、坂本さんがギャラリー・間で展覧会をされ、『住宅--日常の詩学』(TOTO出版、2001)という本を出されました。坂本研究室のゼミに参加したこともなく、直接教えられたこともなかったのですが、本によって坂本さんの仕事が体系化されて学びやすくなり、間接的に坂本さんの作品や言説をよく勉強しました。「構成」というロジックで見れば形がなくても建築は組み立てられるということを学びました。
八束──そこでの「構成」はコンポジションという意味ではありませんね。
藤村──どちらかと言えば「コンストラクション」に近いものです。後に市民参加型のシティマネジメントやプロジェクトに関わるようになりましたが、そこでも、出てきた話を構成要素のひとつとして設計言語に翻訳し、配置していくという考え方です。その方法を用いれば、参加する市民が増えるほど材料が増えるという感じになっていきます。
八束──形を持ち出してしまうとイエスかノーしかなくなりますからね。
藤村──そうですね。形を持ち出すとあまりいろいろなことに対応できなくなります。そういうことも含めて、形がないということには、ある種の現代性があるのではないかと思います。
建築や都市を観察・分析すること
八束──最近の学生は建築を見に行かなくなったと聞きますが、藤村さんのところの学生はどうですか。
藤村──その傾向には日々衝撃を受けています。先日も安藤忠雄さんが好きで建築を始めたという学生と話していたら、実はまだ一度も実物を見たことがないと言うのです(笑)。昔は大阪まで行かなくてはいけませんでしたが、今は東京にたくさんあるのにもかかわらずです。
ただ、その学生らとも話をしていて思ったのですが、最近、旅を語る建築家がいなくなりましたよね。まさに安藤さんはよく旅について書かれていましたし、私たちの年代にとってはバイブルでした。
八束──僕らの世代は外国に憧れがありましたからね。フランスに行って、ル・コルビュジエの建築を見てその経験を心に染み込ませることが貴重な体験になったわけです。僕が初めてヨーロッパへ行ったのは1976年で修士の頃でした。2カ月半の旅行でしたが、毎日できるだけたくさんの建築を見て回りました。あの時の経験がいまだに自分の引き出しになっています。
先日大学の海外建築研修で10日間程、2年生を60〜80人くらい連れてヨーロッパに行きました。ウィーンに行った時は、フリーな時間に久しぶりにアドルフ・ロースやオットー・ワーグナーの建築を見に行きました。しばらく建築離れしていたとはいえ、やはり自分は建築が好きなのだなと思いました。行ってみないと分からない所があるし。そういう感覚が今の学生にはあまりないですね。まさに写真と実物の違いという感覚があまりないのかもしれませんね。
──フィールドワークについてお聞きしたいと思います。1994年に八束さんに『10+1』の編集協力をお願いし、創刊号は「ノン・カテゴリーシティ 都市的なるもの、あるいはペリフェリーの変容」で、多摩ニュータウンを扱っています。そして、最終号が「Tokyo Metabolism 2010/50 Years After 1960」で湾岸を扱い、どちらも八束さんによる都市に関する特集でした。
八束──とりわけフィールドワークを意識してきたということはありませんが、研究室のゼミ旅行では、ほとんど毎年中国や台湾に行きます。去年はシンガポールでした。最初は香港でしたが、香港は超過密都市ですよね。学生は「ハイパー・デン・シティ」のスタディをしているにも関わらず香港に行くと、あまりにも高密度なので気持ち悪くなるのです。でもそういった経験を経ると、日本の都市の平坦さが意識できるようになります。基本的な感覚を持たせるためにフィールドワークは大事だと思います。いわゆるショック療法です(笑)。建築ではあまりショック療法にならないかもしれませんが、都市は圧倒的に違いますから、初めての経験では大きな衝撃を受けると思います。藤村さんは塚本研究室でかなりフィールドワークをされていましたね。
藤村──そうですね。ただ、塚本研究室の場合は、たとえば「ペット・アーキテクチャー」など、採るべき獲物のターゲットが決まっており、それを探すためのフィールドワークでした。
自分で教えるようになってからは、どちらかと言えばツアーのような感じになりました。あるテーマのもとで場所を選び、学生と一緒に行って、体験を共有する。たとえば、成田空港を一周するだけで、政治や権力のことがよくわかります。
八束──それは面白いね。僕はステーション・シティなんかのウォッチャーとしての藤村龍至を買っているから。現地で藤村さんがガイドをするのですね。
藤村──そうですね。たとえば沖縄なら辺野古の埋め立て予定地などに行って説明します。そうすると学生も状況が理解でき、より自分のこととして興味を持つようになります。その体験の共有がその後の議論にフィードバックされるわけです。最近はそういうツアーをして、実際の都市を一緒に歩きながら物語を組み立てていくやり方をやるようになっています。
──『日本の都市空間』(彰国社、1968)をどのように見ていましたか? あれもフィールドワークですよね。
八束──ものすごくよくできた本で、あの後はちょっとできないですよね。学生さんには必見だと言って勧めています。やはり、伊藤ていじさんがいたことが大きいと思います。伊藤さんは民家の調査から始めており、フィールドワークのプロですから。磯崎さんや川上秀光さんは必ずしもそうではありません。伝統的なものを見直そうとして、現地を見に行く学生達を伊藤さんがガイダンスをして、それをジャーナリスティックにフレームアップしたのが磯崎さんだという感じがします。ただ、あの話を今の都市に使えるかというとさすがに難しい。
藤村──今はいわゆるサーベイが減ってきて、ワークショップが多くなった気がします。特に3.11の後はその傾向が顕著です。いろいろな大学のプロフェッサー・アーキテクトが被災地に行ってワークショップをすることが、以前のフィールドワークの代わりになり、学生の主な活動になっています。そこではコミュニケーションそのものがテーマとなり、テーマそのものの設定が失われているような気がします。
八束──確かにそうですね。大きな問題だと思います。『日本の都市空間』だって、まずコンセプトがあったはずで、フィールドから実感的、帰納的に出てきたとは思えない。今の学生にはロジックとかロング・ヴィジョンがないから、一般的に言って発想がすごくベタです。被災地に行くことも結局同じようにベタです。最初は学生がボランティア活動に行くことに対して、意外に社会性があるなぁと思っていたのですが、段々とあれは違うのではないかと考えるようになりました。むしろ、社会性がない裏返しのまま行っているだけなのではないかと。もちろん被災地で炊き出しをすること自体は良いことだと思います。しかし、建築家ないし建築学生として関わるのであれば、もうひとつ何かロジックや方法が絡んでいないとまずいのではないか。それは今日の対談につながりますね。今後の日本の建築教育にとってすごく重要な問題です。
[2014年3月19日、藤村龍至建築設計事務所にて]
やつか・はじめ
1948年生。建築家、建築評論家。東京大学大学院修了後、磯崎アトリエを経て、1985年、株式会社UPM(Urban Project Machine)設立。建築作品=美里町文化交流センター「ひびき」ほか。著作=『テクノロジカルなシーン 20世紀建築とテクノロジー』『ロシア・アヴァンギャルド建築』『ミースという神話ユニヴァーサル・スペースの起源』『思想としての日本近代建築』『メタボリズム・ネクサス』『ル・コルビュジエ──生政治としてのユルバニスム』ほか。
ふじむら・りゅうじ
1976年東京生まれ。建築家。東洋大学理工学部建築学科専任講師。藤村龍至建築設計事務所代表。作品=《BUILDING K》《東京郊外の家》《倉庫の家》《小屋の家》ほか。編著書=『1995年以後』『アーキテクト2.0』『3・11後の建築と社会デザイン』『コミュニケーションのアーキテクチャを設計する』ほか。


