2013-2014年の都市・建築・言葉 アンケート
- 饗庭伸
- 天内大樹
- 有山宙
- 五十嵐太郎
- 市川紘司
- 井上雅人
- 今村創平
- 岩元真明
- 木村浩之
- 吉良森子
- 暮沢剛巳
- 榑沼範久
- 小原真史
- 坂牛卓
- 佐々木啓
- 篠原雅武
- 田川欣哉
- 田中浩也
- 戸田穣
- ドミニク・チェン
- 中島直人
- 中谷礼仁
- 保坂健二朗
- 水野祐
- 南泰裕
- 山崎亮
- [New!→]
- 青井哲人
- 蘆田裕史
- 足立元
- 荏開津広
- 江渡浩一郎
- 太下義之
- 大向一輝
- 大山エンリコイサム
- 岡本源太
- 笠置秀紀
- 門林岳史
- 門脇耕三
- 菊地宏
- 小林恵吾
- 後藤治
- 佐藤信
- 沢山遼
- 城一裕
- 須之内元洋
- 津田和俊
- 土屋誠一
- 永井幸輔
- 成相肇
- 成實弘至
- 西澤徹夫
- 服部浩之
- 平瀬有人
- 藤村龍至
- 牧紀男
- 松田達
- 松原慈
- 光岡寿郎
- 山内真理
- 山岸剛
1──2013年中に印象に残った、都市や建築を語るうえでの人・建築作品・言葉・発言・書物・映像・メデイア・出来事などを挙げ、それについてコメントしてください。
2──2014年の[ご自身の関与するものも含めて]関心のあるプロジェクト──作品・計画・展覧会・書物・シンポジウム・イベントなどをお答えください。
3──2020年に開催が決定した「東京オリンピック」について、考えたこと、考えていることについて、お聞かせください。
饗庭伸(首都大学東京都市環境学部准教授/都市計画・まちづくり)
●A14月に開催された「ニコニコ超会議2」というものに行ってきました。たぶん日本中の趣味を集めたメタなコミケみたいなもんだと思います。「ニコニコ動画のすべて(だいたい)を地上に再現する」というコンセプトで開かれたこの会議、広大な幕張メッセが小さなブースに区切られ、ブースごとにめくるめく趣味の世界を覗くことができました。一つひとつのブースは熱気があるけれど、意外と小規模であり、出入りをする人の流れを見ていると、お互いに関心がない、という、インターネットがそのまま現前したような空間で面白かったです。日本中がもっと暇になったら、こういう面白い都市空間が出来るのになあ、と思いますが、みなさんオリンピックで忙しいんでしょうか。そもそもオリンピックだって趣味の集まりなんですがね。
-

- 「ニコニコ超会議2」会場
●A2
個別的ではないのですが、そろそろ震災復興が空間の形をとって建ち上がり始めるのではないかと思います。コンペで設計者が決められたいくつかの建物、高台移転の住宅地、復興公営住宅、防潮堤、浜小屋といった恒久的なものに加え、たくさんの仮設住宅や仮設商店の次の姿、福島の中長期型の仮設住宅、「仮の町」への取り組みの進捗などが気になります。区画整理や再開発の取り組みも変わらず続くと思いますが、順調にいったものでも2014年に建ち上がり始めるものはないでしょうね。
●A3
64年のオリンピックが国家のオリンピックだったとしたら、20年のオリンピックは民のオリンピックなのだと思います。2002年にスタートした都市再生からのここ10年間、東京はひたすら「民が都市をつくる」ための力、制度、組織、方法を蓄えてきました。都市計画道路だって民がつくるくらいですから、この10年間で東京の都市計画のOSは完全に入れ替わってしまったわけですね。公共の判断や価値観というものは、基本的にはブレません。国土交通省の官僚も、小さな町の都市計画課の職員も、同じ判断を下し、同じように都市計画を進めるというのが公共による都市づくりですが、民とは本質的に多数で、すべて異なる判断を下します。その民が都市をつくる仕組みがこの10年間の東京でジャングルのように発達し、それはおそらくこれまでのオリンピック都市では一番のジャングルのはずです。そのジャングルを使って、総意や工夫をこらして、どのようにオリンピックを迎える都市をつくるのか、注視したいと思っています。
私なりに「こうなればよいな」ということを一言でいうと、「多様な値段の観客席を7年かけて東京の中にどうつくるか」、ということです。空間のスピードの多様さです。民によって、ゼロ円の観客席から1億円の観客席まで、さまざまなスピードを持つ観客席を都市の中に混在させてつくることができれば、東京は素晴らしい都市になると思います。例えば超高層の建物のオーナーが、屋上の空間をオリンピックの観客席に解放して世界中から人を集める、世田谷の商店街が路面を封鎖してデザインされたパイプ椅子を並べ、振る舞い酒をしながらイスラムの人たちとオリンピックを見る、空いている建築ストックをリノベーションし、世界の貧しい人たちがオリンピックを楽しめる空間にする......など、民が所有する多様な空間の可能性を試す機会にオリンピックがなればよいと思いますし、7年後をゴールにして、そこから逆算的に現在の建物の使い方を考えていくこともあってよいと思います。「民」とは多義な言葉で、そこには大規模なデベロッパーも、空き家活用を仕掛けるNPOも、土地をたくさん持っている市民も、たいしてお金を持っていない市民も、ホームレスのおじさんも含まれます。ほぼすべての私たちが自分のもつ空間を使ってどうオリンピックを迎えるのか、ということです。スタジアムや選手村といった派手な空間ばかりが話題になりますが、オリンピックを迎えるのは施設ではなく都市ですから、どういう種類の都市の空間がオリンピックに向けてあるべきか、なんてことをきちんと考えたいですね。
あいば・しん
1971年生(兵庫)早稲田大学卒業。共著に『住民主体の都市計画』『Insurgent Public Space』ほか。
Twitter @shinaiba
WEB http://www.comp.tmu.ac.jp/shinaiba/frame2.htm
天内大樹(美学芸術学、建築思想史)
●A1東京理科大学、明治大学など建築学科創設50周年を記念する大学がいくつかあり、明治大学では私もその集いに立たせていただいた。明治大学での堀口捨己と神代雄一郎、法政大学での大江宏(こちらは1950年創設で、今年は大江生誕のセンテニアルだったが)のように、各学科の基礎を築き、カラーを彩った人々が回顧されたことには、戦後建築史研究の端緒を切り拓く意義があった。これらは国立近現代建築資料館の開館と同館での丹下・坂倉展、国立西洋美術館でのル・コルビュジエ展とともに記したい。
明治・法政大学の集いでは、双方とも会場からの質問の最初が、当時からの校舎の解体と現在のタワー型校舎の建設とについて問う卒業生のものだった。東京理科大学の集いには私は参加していないが、記念行事がまさに2013年開設の葛飾キャンパスで行なわれており、しかも同キャンパスの設計に理科大建築学科はファカルティとしてはほぼ関わらなかったと聞く。法政や明治と同種の指摘が、少なくとも潜在的にはあっただろう(もっとも法政や明治では旧校舎「解体」が惜しまれ、理科大ではおそらく新校舎「建設」が大学理事会と組織設計事務所のみで進行したことが惜しまれる違いはあるだろう──旧住宅・都市整備公団本部=旧理科大九段校舎も味わい深い建物だと思ったが)。国立競技場改築をめぐる/にふれたシンポジウム群でも、従来型の建築家像では建築の立場から都市や国家の意思決定に参与できない点が繰り返し指摘された。その構図が各大学の50年間にもそれぞれのかたちで反復されていたともいえる。
出版は2012年だが、中川大地『東京スカイツリー論』(光文社、2012)は建築物の量的ではなく質的な側面を問うものとして、着実な議論を示してくれた。何より、私には隅田川の対岸のお祭り騒ぎとしか映らなかった出来事が多面的・立体的に像を結んでいくさまは、読書体験そのものとしても面白かった。円堂都司昭『ディズニーの隣の風景──オンステージ化する日本』(原書房、2013)も同種の切り口に分類できようか。押上も浦安も従来像どおりに建築家が関与したものではない。しかしスカイツリーやシンデレラ城(またはミッキーマウス)に動態としての共同体が象徴されるならば、それらをある種のモニュメントとして光を当てるのは、従来型の建築家像が引き受けてきた役割のひとつだろう(照明計画をせよとか記念碑を建設せよなどと主張しているのではない)。あいちトリエンナーレが仮初めのイヴェントを通じて目指したもの、あるいはもしかしたら東浩紀編『福島第一原発観光地化計画』(ゲンロン、2013)で目指されているものも、これではないか(後者については現地の自発性を損ねる懸念から、「計画」として実定的に進める点には判断を保留したい)。
-


- 円堂都司昭『ディズニーの隣の風景──オンステージ化する日本』/
東浩紀編『福島第一原発観光地化計画』
●A2
自身のプロジェクトはどれも遅滞気味か中断してしまっており大変申し訳ない。個人的には初めて東京以外の街に住むことになりそうで、こちらは楽しみである。
●A3
最近は「少なくとも2020年まで東京には戻りません」と冗談を言っているが、いずれにせよ建設ラッシュで東京は騒がしい7年を過ごすことになる(直接のオリンピック施設だけでなく、ホテル建設や交通整備も伴うからだ)。建設の是非については、霞ヶ丘競技場より葛西臨海公園のほうに懸念がある。この数十年のものとはいえ生態系維持の観点から、中央防波堤にカヌー・スラローム会場を移す余裕はないだろうか。また晴海の選手村は、閉幕後中古住宅を一度に大量に供給することになるが、健全な住宅地として維持できるのだろうか。民間に任せれば解決できるというものでもない。
霞ヶ丘はコンペ勝者が「設計者」ではなく「デザイン監修者」に就任するという、もとより心許ない条件だった。北京国家体育場と同様に設計縮小になるだろうが、それが当初から発注者の視野に入っていたらしい点は東京人として恥ずかしい。政府施設とはいえこのコンペの前提を糺せず、選出過程に関与した実感も持てなかったことに対する、東京の人間としての悔いはいくら強調してもしすぎることはない。ただ、何もなければ結果的にザハ・ハディド氏のデザインの出涸らしのような縮小再生産が、つつがなく進行するだろう。
越沢明『東京都市計画物語』(筑摩書房、2001)で、神宮外苑は歴史的景観を保った貴重な地域というよりも、当初計画の戦後復興に対する挫折として描かれている。絵画館前の緑地は草野球場と化し、両脇の学習院と陸軍大学校の跡地はラグビー場と都営アパート(2000年頃改築)や中学校になった。今回はラグビーW杯のための新競技場建設なのだから、秩父宮ラグビー場は解体して跡地に他スポーツ施設を移し、せめて絵画館前は使用申請不要のオープンスペースとして開放できないだろうか。また逆に、オープンスペースを諦めてスポーツ施設を「ラウンド・ワン」のように過密に集約する可能性もあるだろう。外苑全体は高々100年前に死去した人物を記念したにすぎないのだから、当時の市民有志の所産でこそあれ、神域として過剰に崇める必要はない。また明治神宮内苑と代々木公園の鬱蒼たる人工林に比べれば、我々はここをすでにズタズタにしてしまっているのだ。
-
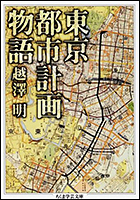
- 越沢明『東京都市計画物語』
大切なのは、新競技場の「デザインが奇抜」だから反対というような、建築家の創意を束縛しかねない議論には与しないことだろう。「奇抜」なデザインを行う建築家に、われわれはすでに霞ヶ丘を委ねたのだ。
あまない・だいき
1980年生。美学芸術学、建築思想史。東京理科大学工学部第二部建築学科ポストドクトラル研究員。共著=『ディスポジション』、『建築・都市ブックガイド21世紀』など。
有山宙(建築家/assistant)
●A1
コロガルパビリオンと異常な天候
2013年7月28日未明、激しい雷の音で目を覚ます。
数日前から、常時何種類もの天気予報をチェックしていたから、大雨に対する心の準備はできていた。1分もかからず着替えをすませると、2階で寝ていたはずなのに、いつの間にか同じく準備ができている会田大也氏★1とともに家をでる。車で中央公園へと向かう途中、大粒の雨が落ちてくる。数分で、中央公園に到着し、26日にオープニングを迎えたばかりのコロガルパビリオンへ向かう。
すでに、公園の芝の上にはうっすらと水がはり始めていた。その日の大雨を予想し、前日の夜までに取り付けた雨水の排水システムは、問題なく機能しているようだ。ひとまずは安心。「排水システムの実証実験にはちょうど良い」。そのときはまだ、そんな軽口をたたく余裕もあった。
外の雨はますます強くなる。公園の芝の上の水位も瞬く間に上昇し、コロガルパビリオンの床に水があがってくる。突風が吹き、テント屋根は大きく浮かびあがり、二つあるコロガルパビリオンのもう一方から、山岡大地氏★2の叫び声が聞こえた。慌ててそちらに向かうと、屋根のテントがもっこりと垂れ下がり、テントの上に風呂桶ほどの水が溜まっていた。テントの上にたまってしまった水は、その重さでますますテントを引っぱり、屋根全体の雨を集めるようになる。そのまま、雨が溜まり続ければ、コロガルパビリオンの構造はもたないだろう。会田氏の活躍によりテントにたまった水を排出することはできたが、そうこうしているうちに、もう一方のコロガルパビリオンの排水システムが倒壊していた。
雨は止む気配がない。身の安全を優先するために、コロガルパビリオンの責任者である会田氏の判断で、コロガルパビリオンを放棄することを決めた。コロガルパビリオンから全館停電中のYCAM館内に避難して、ほどなくして雨は止んだ。公園全体に膝まであがった水位も、瞬く間に下がっていった。
山口島根豪雨と名付けられたこの雨は、山口市で1時間に143ミリという観測史上最大の雨を記録したという。
コロガルパビリオンとは、山口情報芸術センター(YCAM)の10周年祭にあわせて、隣接する中央公園に建てられたパビリオンだ。
高さ4メートル、直径25メートルと直径20メートルの二つのシリンダー状の建築の内部に、音響、照明、ネットワークなどのメディアテクノロジーが埋め込まれたスケートボードランプのような不定形な床面がひろがる。
建物の設計をassistantが担当した。10周年祭終了後には取り壊すことが決まっていたため★3、仮設建築物の建築基準法の緩和を適用し、また、組み立ておよび解体が簡易になるように考えたため、基礎を鉄骨で組み、屋根をテント膜とした。
今回、山口島根豪雨でのコロガルパビリオンの被害は、一部のデバイスの交換だけで済み、1週間の補修工事のあと無事に再開することができたが、コロガルパビリオンを通して、日本の気候、風土の変化をしみじみと肌で感じることとなった。ゲリラ豪雨を察知するアプリケーションをインストールした会田氏の携帯は、夏中、不気味なアラームを鳴り響かせ、9月の桂川の氾濫や、10月の大島の土砂災害、夏から秋にかけて、何度も「観測史上最大」という言葉を聞いた。
気候、風土にあわせて、長い年月をかけ最適化されてきたであろう建築が、急激な気候の変化ついていくのは難しい。


- コロガルパビリオン
提供=山口情報芸術センター [YCAM]
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
撮影=丸尾隆一(YCAM)
Photo: Ryuichi Maruo (YCAM)
★1──YCAMの教育普及担当、コロガルパビリオンの責任者
★2──コロガルパビリオンのプレーリーダー
★3──会期終了が近づくにつれ、自然発生的に子どもたちから、コロガルパビリオンを存続させるための運動がはじまった。子どもたち自らポスターをつくり、存続のための署名運動をはじめ、最終的には1,000を超える署名が集まった。現在は山口市で対応を協議中。
●A2
ヴェネチア・ビエンナーレ建築展のナショナルパビリオン展示
●A3
2020年の前に、まずは2014年ブラジル・ワールドカップの様子が怪しい。どうやら、大きな問題を抱えているらしい。とくにおもしろいのは、サッカー界の悪童、ロマーリオが猛烈に2014ブラジル・ワールドカップを批判しているということ。日本でも有名な、1994年ワールドカップMVPのブラジル人FWは、2010年から政治家に転身している。国民的スポーツ・スターが政治家になるのはどこの国でもよくあることだが、その政治家が、自身のバックグラウンドの国家イベントを批判するのは、あまり聞いたことはない。ロマーリオは、病院や学校が資金不足に苦しむなか、多額の公的資金がスタジアム建設に費やされることを懸念している。とてもまっとうな意見だ。FIFAはイベントの収益ばかり気にして、イベント後のブラジルのことなど何も考えていないと。国立競技場に問題提起する建築家という図式を含め、2020年の東京とよく似ている。
そして、2020年の東京を飛び越えて、さらに深刻に見えるのは、開催自体が危ぶまれている2022年カタール・ワールドカップ。こちらは、真夏の砂漠で、サッカーをすること、観戦すること自体に疑問が投げかけられている。スタジアムに冷房を完備したとしても、スタジアムの移動を含めて、観客への影響が大きすぎるというのだ。さらには、スタジアム建設の出稼ぎ労働者たちの労働環境の悪さも指摘されており、建設が滞りなく進むのかも怪しくなってきた。そして、最近発表された、カタール・ワールドカップのスタジアムのひとつも、ザハ・ハディドの設計だった。
ありやま・ひろい
1978年奈良県生まれ。建築家。2003年東京大学大学院建築学科修了。2004-05年Alsop Architects, Ushida Findlay architects(ポーラ芸術財団の助成)。assistant共同主宰。 www.withassistant.net
五十嵐太郎(建築史、建築批評/東北大学教授)
●A1全体として建築は、新築物件よりも、国立近現代建築資料館の開館が印象に残りました。いまはささやかな施設ですが、建築の未来を考えると、重要な出来事だったと思います。あいちトリエンナーレ2013の芸術監督をつとめ、大変な一年でしたが、終了直後に『中日新聞』の酷評座談会に対して、Twitterで連投反論を行なったことは、個人的にメディアと批評について考えさせられる機会となりました。Togetterのまとめが、5万5千ビューもあったことは、全体来場者数の62万人に対しても少なくない数字です。
12月に中国を訪れ、天津、北京、重慶でレクチャーを行なったのですが、雑誌や本などの紙メディアが元気なのが、うらやましく思いました。また自分の本でもっともハードコアの『建築と音楽』(NTT出版、2008)が中国語訳されているのですが、何人もの学生がこの本をもってきていたのに対し、日本の学生で、この本を買って読んでくれている人にほとんど会ったことがないことは心配になりました。旅行の最後は、四川大地震の被災地を訪れ、そこで廃墟になった街をまるごと保存し、いまは観光地になっている震災遺構、少数民族の現地再建や移転による幾つかのニュータウン、それに隣接する壊れた学校の震災遺構、震災博物館などをまわりました。善し悪しはともかく、ほとんどが震災後2年くらいで完成しており、そのスピードにただただ驚きました。一方、東日本大震災の震災遺構は、もうほとんど残っていません。
-

- 五十嵐太郎+菅野裕子『建築と音楽』(NTT出版、2008)
●A2
横浜トリエンナーレが、どのようにコンセプチュアルなテーマを国際展としてまとめていくかに大変、興味があります。またヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展が例年よりも早く始まり、レム・コールハースのディレクションによって全体がどのように変わるのか、また日本館における太田佳代子さん、中谷礼仁さんがどのような展示を魅せるかにも期待しています。自分の関わるものでは、埼玉県立近代美術館を皮切りに各地を巡回する日本の戦後住宅展が夏からスタートするので、鋭意準備中です。
●A3
ザハ・ハディドの新国立競技場案が、多くの人が公共施設をめぐって、あれこれ意見を言える機会をもったのは、新しいランドマークとして重要なことだと思う(パリのエッフェル塔やポンピドゥ・センターにはそれがあったが、東京スカイツリーにはなかった)。ともあれ、東京オリンピックは、東北の復興に貢献するどころか、新しい施設やインフラの工事がかぶると、ただでさえ人手不足と建設費高騰が起きているわけだから、今後はむしろブレーキになる可能性があるのが心配だ。ちなみに、本当は2016年招致のときの国内で出されていた磯崎新らが関わった福岡の案が、いまでもよかったと思っている。仮に世界の招致競争に勝てなかったとしても。
いがらし・たろう
1967年生。東北大学教授。建築史、建築批評。著書=『終わりの建築/始まりの建築』『新宗教と巨大建築』『戦争と建築』『過防備都市』『現代建築のパースペクティブ』『建築と音楽』『建築と植物』など。
http://www.cybermetric.org/50/50_twisted_column.html
市川紘司(中国近現代建築史/『ねもは』編集長)
●A1今年読んだもののなかで一番面白かったのは槇文彦氏による『漂うモダニズム』(左右社)に所収された同名のテキストである。モダニズムという一艘の「船」が溶解して何でもありの「ポタージュスープ」と化した、というのが槇氏の現在の建築的状況に対する認識である。テキスト中では賛否どちらの結論も出していないのだが、筆者の読後感としては否定的なニュアンスのほうがつよく残った。おそらくそれは、この「船」というメタファーがフーコーによるヘテロトピア論を想起させたからである。フーコーによれば「船」とは「場所なき場所」であり、あらゆる現実的な事象を相対化させる「他者の場所」としてのヘテロトピアの最たる存在である。「船を持たない文明においては、夢は枯れ果て、スパイ活動が冒険に取って代わり、警察がならず者の船乗りたちに取って代わる」(「Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias」『Architecture, Mouvement, Continuité 5』1984)。かようなメタファーの同一性から、ヘテロトピア論を下敷きにしつつ「漂うモダニズム」を読むと、以下のような結論を想定せざるをえなかった。ポタージュスープのなかではあらゆる建築的実践が自由である、しかしそこで起きるのはせいぜい「小波」にすぎない、ゆえにむしろ一見不自由ではあってもさまざまな場所に発着可能である空間としての「船」に戻るべきではないか──。
現代という時代を「後期近代」と呼び、その特徴を旧来的な「規範」の液状化が進行した「リキッド・モダニティ」とまとめたのはジクムント・バウマンである。しかし、人は規範なしでは生きられないゆえ、自分自身で再帰的にみずからの規範を創造しなければならない。槇氏にとっての規範は(前期近代=「ソリッド・モダニティ」の産物である)「モダニズム」となるだろう。あるいはモダニズムが定着しなかった中国の建築においては、近年でも「伝統」に規範を求めることがしばしばである。しかしなによりも重要なのは、現在において、規範とはもっと小さく、細かく、多数あってよいということである(それが「規範」として各人に機能しさえすれば)。「規範」はいま一艘の船である必要はない。ポタージュに取り込まれた小波ではなく、自立した作家たちによる実践が独立した「小舟」として数多浮かぶような海景が、本来は望ましいのである。
筆者は2010年当時に絶版であった建築本だけを紹介する刊行物を制作したことがある(『ねもは01 絶版☆建築ブックガイド』)。現在の若い人間にも読まれるべき多くの本が入手困難であるように思われたからだった。今年、当時われわれが取り上げた『環境としての建築』(レイナー・バンハム)と『形の合成に関するノート』(クリストファー・アレグザンダー)が、鹿島出版会から再刊された。どちらもきわめて「理論」的な建築の書籍である。また、今年は、建築理論書を読みなおす研究会(「10+1 建築理論研究会」https://www.10plus1.jp/monthly/serial/riron/)が南泰裕氏らによって発足され、槇氏とともに20世紀後半の日本建築を理論的側面でリードしてきた磯崎新氏と原広司氏による「これからの建築理論」なるシンポジウムが開かれた(12月1日)。2013年は「建築理論」を再評価しようという動きがあった一年であったように思う。
「建築理論」というものの基礎的な役割は、旧来的な規範が溶解(または解体)をはじめた近代以降において、「建築」という枠組みそのものをあらためて策定することにあると筆者は考える。既存の規範を飲み込み、それをこねくり回しながら新しい規範をつくりだす、という「反芻」の行為が理論である。おそらく、ポタージュの小波を独立した小舟とするためには(つまりリキッドな世界のなかで再帰的にみずからのルールを規定するためには)、かつての「建築理論」は十分補助線となりうる。機能しなくなった古いものを反芻しながらみずからの新しい規範をつくらなければならない、という点では、20世紀も21世紀も変わらないからである。その意味で建築理論はいまこそ考えられるべきもののひとつであろう。どのように考えるのか。もちろん、経典を読んだり、巨匠のレクチャーを聞いたりすれば即済むわけではなく、ましてや展覧会から勇気だけもらって帰っていては達成され得ない。求められているのはあくまで反芻。インプットを別のかたちで創造的にアウトプットすることである。
-




- 槇文彦『漂うモダニズム』/『ねもは01 絶版☆建築ブックガイド』/レイナー・バンハム『環境としての建築』/クリストファー・アレグザンダー『形の合成に関するノート』
●A2
自分の仕事としては2014年前半に2冊刊行物が出せそうである。どちらも近年の中国建築に関するもので、オリンピックや万博の準備でイケイケだったゼロ年代とは異なる、2010年代における中国建築の状況を取り上げている。ゼロ年代と2010年代の中国建築のちがいは、端的にいえば、独立独歩のアトリエ建築家の充実である。王澍やMADアーキテクツやNeri&Huなど、ウェブメディアで作品が何度も掲載されるような建築家がずいぶん増えてきた。「外国人建築家の実験場」でしかなかった中国において、個人の作家としての建築家はどのようにして実践を進めているのか。そもそも中国において建築と都市はどのような制度のもと、どのようなプロセスを経てつくられているのか。そして日本はそれをどのように理解して、関わっていくべきなのか。日本でもとくにゼロ年代には中国に注目するメディアや特集が比較的多くあったが、彼の国のバブリーな荒波に目を奪われるかたちでじつはこういった根幹的な部分の分析があまりされていないように思える。ゼロ年代というひとつの大波が終わったあとだからこそ可能な、冷静な(嫌中でも親中でもない)目線での評論をしたいと思っている。
●A3
北京オリンピックのために建設された《中国国家体育場》(鳥の巣)のことを思い出した。2002年に行なわれた国際コンペによってヘルツォーク&ド・ムーロンによる案が決定され、その後コストカットのため規模の縮小や開閉屋根の設置中止などの対策が取られたのだが、これに対して張永和や劉家琨といった中国の建築家たちが連名で意見書を提出した。いわく、こうした処置は建築の全体性や、開放・成長する中国のアイコンとしてあったこの建築のイメージを損なう。東京オリンピックメインスタジアムのザハ・ハディド案を受けての動きとはまったく対照的なのだが、とはいえもちろん、これによってどちらかを褒めどちらかを貶めるつもりはなく、両国のオリンピック開催の背景にある状況のちがいだけをあらためて感じた。そもそも、《鳥の巣》は中心部から遠く離れた広大なオリンピックパークのなかに建設されるものであり、いくら大きくても大き過ぎることはなかった。オリンピック開発の少し前に建設がはじまったポール・アンドリューによる《国家大劇院》では、その敷地が天安門広場にほど近い歴史的空間にあったため、《鳥の巣》とは逆に、コストの高さ、劇場機能の不合理、周辺環境への悪影響といった批判をふくむ意見書が建築家の組織した委員会から提出されている。
いちかわ・こうじ
1985年生。東北大学大学院工学研究科都市建築学専攻博士後期課程。2013年から中国政府留学生(高級進修生)として清華大学に留学。専門は中国近現代建築史。建築雑誌『ねもは』編集長。
井上雅人(デザイン史、ファッション史/武庫川女子大学講師)
●A1姫路城の天守閣修理を見学できる施設「天空の白鷺」が、2014年の1月で閉鎖されることになった。閉鎖されるという言い方はおかしいが、つまり修理が終ったので、むしろ姫路城そのものは公開されることになった。夏ごろには、天守閣が全部お目見えするそうだ。
建物全体を大屋根で覆って修復作業を行なう手法は、これまでも随分とされてきたわけで、さほど珍しいことでもないが、そこに八階建ての見学施設をつけて、通常なら鳥や昆虫でなければ見ることの出来ない距離から姫路城を見下ろす体験をもたらしてくれたことの意義は大きい。普通では得られない視点を与えてくれたのみならず、保存修復に携わる人びとにスポットライトを与えてくれたりもした。とはいえ、そういった意義の大きさ以前に、修理を見学することの楽しさを提供してくれたことには感謝であろう。
-

- 姫路城[撮影:Reggaeman]
http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Himeji_Castle_The_Keep_Towers.jpg
-

- 復元された東京駅[撮影:馬場三士]
その、姫路城の修復を手がけた「鹿島」は、2012年の秋には東京駅の復元も完成させていた。東京ステーションギャラリーでは、空襲で炭化した木レンガまで見ることができる。今、自分がいる建築が、どのような歴史を経ているのかストレートに教えてくれるような貴重な証言者と、親しく交わることができるわけだ。わざわざ町中を探してまわらなくとも、きちんと整備した形で歴史の積み重ねを見せてくれる施設が増えていることは大変喜ばしい。歴史は文字で知るものであっても、やはり実物の説得力には叶わない。それゆえ、単に何ごとも無かったかのように奇麗に修復されたり、復元されたりするよりは、人間の創造や、逆に災害の痕跡を生々しく見せてくれる方がいい。姫路城や東京駅といった誰でも知っているような歴史的な建造物に限らず、もっといろいろな建築が、多様な関わりを人びとと持ってもいいのかもしれない。単純に、解体される直前のビルが、内装を全部はずした形で公開されたら、それはそれで面白い。9月には、解体に入った小学館ビルに漫画家たちが別れを惜しんで壁やガラスにラクガキをしたことも、話題を呼んだ。それに多くの人びとが関心を示し、見たいと思ったということは、建築と人の関係の意外な幅の広げ方があることを示唆している。
ところで、ここにきて、東京オリンピックの興奮のなか、江戸城天守閣を復元しようという話が出てきている。興味深いのは、木造で修復しようとしているところである。昭和において再建された大阪城も、名古屋城もコンクリートで建てられている。今となっては、天守をコンクリートで建てたことの方が不思議でならないが、それはつまり、この50年ほどで人びとの歴史的建造物への考え方が大きく変わったということでもある。本物そっくりに再建されたものとして代表的なのは、三島由紀夫の小説で有名な鹿苑寺こと、いわゆる金閣寺であるが、いくら元の場所に同じ方法で建てられたとしても、それはレプリカのはずである。そのことを忘れて、国粋主義的な風潮を生みだす道具立てになるくらいなら、まだ果てしなく偽物臭い大阪城の方がましであろう。
江戸城の再建は、もちろん政府が主導しての話ではないが、景気が良くなるならと、安易に飛びついてしまう人の多い世の中である。江戸城天守は、幕府が成立して50年ほどで燃えてしまったが、財政の逼迫や、再度の延焼を危惧して、敢えて再建しなかったというのも、また歴史である。立て直すことには興味をそそられるが、自己顕示の代替物としては建ててもらいたくはないと思う。同じ幕府の建築であれば、なかなか募金の集まらない二条城の修復にも支援をして欲しい。
●A2
2013年、私と蘆田裕史と藤井美代子は、京都に「コトバトフク」というセレクトショップを開いた。隣接された「gallery110」とともに、デザイナーの活動を支援し、関西に紹介するためである。主に衣服、アクセサリー、それとファッションやデザインに関わる書籍を扱っている。
若手デザイナーの支援、という話は、ここのところよく聞くようになった。ほとんどがファッション・デザイナーへの支援ではあるのだが、2013年も、ルミネやパルコといった商業施設や、LVMHやアルマーニといったブランドが、次々とプロジェクトを発表した。こういった動きが効を奏しているという話はまだ聞かないが、2014年には、さらに増え、ファッションに限らず、より多くの分野にまで普及していってほしい。
ファッション・デザインの分野は、個人が個人の名前で商品を販売することをグローバル市場においても成立させてきた。もちろん、その後ろにはたくさんの業者や技術者やサポートする人びとがおり、個人の名前で物が売られていたとしても個人が作っているわけではない、という矛盾も抱えてきた。しかし、そうすることによって、個人が個人の考えを商品にして世界中に訴えるルートを、まがりなりにも確保してきた。
今、若手デザイナーに支援が行なわれているということは、そういったあり方が難しくなっているということでもある。この20年あまり、ファッション産業では、デザイナー・ブランドのグループ化が進んだ。一部の巨大企業が、個人の経営するブランドを傘下に収め、あるいは老舗ブランドを買い取り、ちょうど野球やサッカーの監督を配するようにして、デザイナーを雇った。売上が伸びれば契約を更新し、結果を出せなければ契約を打ち切るという関係性を、企業とデザイナーは結ぶようになった。ファッション・デザイナーが、個人の力で商品を世界に問うということが、難しくなっているのだ。
一方で、広く見渡してみれば、Bsizeのような個人が経営する家電メーカーなども出現している。食への不安は、生産者が誰であるかということに人びとの目を導いた。東北の復興も、小さくて良いものを作る企業を応援しようという風潮を生んだ。生産者の顔が見えることは、むしろ歓迎される傾向にある。
「コトバトフク」では、「作り手たちの顔が見える商品」をならべることを心がけている。「作り手」個人の主張ではなく、そこに関わる「作り手たち」同士の幸福な関係性までが伝わってきて、買う側もその関係性のなかに巻き込んでしまうような物を選んでいる。先に、個人の考えを、商品を通して伝えることの重要性をあげたこととは矛盾するようだが、やはり、個人が個人の考えを世界に直に訴えるようなことは、どうしようもなく難しくなっている。であるのならば、闇雲に個人が巨大企業と戦うよりは、お互いに顔の見える少数の集団をいくつも作っていく方が現実的であろうし、強力なリーダーに率いられる集団よりは協調的な集団の方が、現在の日本の社会に合っているだろうと考えたからである。
「コトバトフク」という小さな店に、どこまでのことが出来るかは分からない。いやしくも学問を生業とする人間が、商売に手を染めるのもどうかと言う向きもあろう。しかし、少しでも余力のある素人が下手な鉄砲を撃っていかないと、残らない果実もあれば、出ない芽もある。
-


- コトバトフク
●A3
東京でオリンピックの開催が決まったのは、3度目である。一度目の1940年のオリンピックは返上したうえに、その代わりの64年のオリンピックであるし、開催まで漕ぎ着けたのも64年だけなので、2020年のオリンピックを2度目とカウントするのに異論は無い。だが、それにしても決定したのは3度目である。
20世紀の前半までは、近代オリンピックは欧米のなかで巡回していたので、40年に東京で開催を決定したのは、実に大きな変化であった。結局開催されなかったとはいえ、これ以降、20世紀の後半は開催地域と参加国をひたすら広げていくことになった。これまでに夏のオリンピックを3度開催したのは前回の開催地のロンドンだけであるが、第1回のアテネも、非公式の1906年大会を含めると3度となる。そのほかにも、2度開催した地としてはパリ、ロサンジェルスがある。いずれも欧米の街である。20世紀の後半は植民地が解放され、人種や国境を超えて、人類であれば誰でも平等である日が来ることが祈られた時代である。いずれ、発展途上国でもオリンピックが開かれることになるであろうと、誰もが思い描いた。
ところが、21世紀に入るあたりから、どうも、そんな簡単なことでもなさそうだということになってきた。オリンピックを行なうような街では戦争はもう起こらないという思い込みは、サラエヴォが戦地になることで、あっけなく裏切られた。ひょっとしたらサラエヴォは、東京同様中止になっていた可能性だってあった。さらには、アテネは開催後、大きな不況に飲み込まれた。こちらも返上する可能性が無かったとは言い切れない。すると、こういったことを踏まえて、今後はオリンピックの開催される街が、限られてくる可能性だってある。戦争の危機が無く、不況のリスクを乗り越えられるような街など、世界中にそれほどあるわけではない。
そんなことになってしまったのは、オリンピックをグローバル経済における、4年に1度の起爆剤にしようとするからである。循環する景気を人工的にコントロールするために、オリンピック産業が利用されようとしているのは、誰の目にも明らかである。起爆剤は、頻度が多すぎても、火薬の量が少なすぎても効果が無い。4年に1度という絶妙な間隔で、できるだけ大きな花火を確実に打ち上げなくてはいけない。
しかし、そうなると「オリンピック」は、かつて人類学者たちが発見した「クラ」や「ポトラッチ」といった、南洋や北米の部族のあいだで行なわれていた儀式とそっくりなものになっていく。日本は「先進国」と呼ばれるメンバーに所属しているかぎり、この文化人類学的な贈与や交換のシステムから逃れることはできず、これから先も何十年かに一度、儀式を執り行なうことになるだろう。近代の行きついたところが、部族社会と同じなのは興味深いが、せめて、この手の儀式でよく見られる、わざと宝物を破壊したり、過度の贅沢を行なったりすることで、代わりに将来の危険を回避しようとするような、どうしようもなく呪術的な儀式にはならないでほしいものだ。
いのうえ・まさひと
1974年東京生まれ。東京大学大学院博士課程退学。文化服装学院卒。単著に『洋服と日本人』、共著に『生活の美学を探る』『相対性コムデギャルソン論』など。作品に《stilllife》シリーズ(CENTER EAST+井上雅人)、《竹林》。
今村創平(建築家/アトリエ・イマム/千葉工業大学准教授)
●A1まずは、昨年同様、2013年に鑑賞した展覧会で、これはよかった!と思うものを挙げてみます。
「Japanese Junction 2012」(HAGISO)
「アーネスト・サトウ展 light and shadow」(gallery 916)
「フランシス・ベーコン展」(国立近代美術館)
「ス・ドホ展」(金沢21世紀美術館)
「日本の民家一九五五年 二川幸夫・建築写真の原点」(パナソニック 汐留ミュージアム)
「マテリアライズ展」(東京藝術大学陳列館)
「和洋の書」(国立博物館)
「スミルハン・ラディック展」(メゾン・エルメス)
「Ninety Nine Failure」(東京大学工学部前庭)
「Japanese Junction 2012」は、留学している日本人の建築の学生が、世界各地の建築学校で製作したプロジェクトを持ち寄るという企画。実は、2012年末に見たものだが、前回のアンケートには間に合わなかったものの、一年で一番面白かったといえるくらい良かったので入れている。きわめてユニークで濃厚なプロジェクト群が、古い木造家屋の中に配され、建築を生み出す熱気に満ちていた。
「アーネスト・サトウ展」は、この写真家の魅力を教えてくれた。この写真専門のギャラリーでは、ほかにも上田義彦、森山大道の優れた展覧会を観たが、古い倉庫をリノベーションしたスペースそのものが、日本のギャラリーでは稀有な質を有していて、訪問するたびに感心した。
「フランシス・ベーコン展」「ス・ドホ展」、どちらも2度足を運んだ。現代美術展ははずれが多いが、本当に優れたものから受ける刺激は、クラッシックなアートから受けるのとはまったく別の質で、それは現在の私たちの感受性と響きあうものだから現代美術は面白い。 今年一番記憶に残るのは、「マテリアライズ展」と「Ninety Nine Failure」だ。ともに、こうした領域のプロジェクトが、日本でこのレベルに達したのかと、ある種の感慨を覚えた。もちろん、アルゴリズムやデジタルファブリケーションは今に始まったことではなく、foa《横浜港大さん橋国際客船ターミナル》の完成は2002年とすでに10年以上前のことであるし、『10+1』誌で「アルゴリズム的思考と建築」特集が組まれたのも2007年のことだ。だが、今年は、田中浩也さんが以前から主唱してきた3Dプリンターやファブラボが広く社会的に認知されるようになり、これまで完成した建築のみを対象としてきた『GA』が『GA JAPAN』誌でコンピュテーションの特集を組んだ(7月刊行、No.123)。これまでは、先端的ではあるものの、ある一部の人が熱狂していたものが、だんだんと広がりを見せている。「マテリアライズ展」と「Ninety Nine Failure」でのプロジェクトも、きわめてレベルの高い試みであり、またそれが限られた趣味者のものではない展開を見せていた。おそらく、次の数年で、格段に進化したプロジェクトが登場するのではないかとの予感がある。
●A2
2013年は、マンフレッド・タフーリと近代/現代建築との関わりについての書、Marco Biraghi著『Project of Crisis』が出版され(タフーリについては、以前Andrew Leach という人が評伝『Manfredo Tafuri: Choosing History』を書いている)、またヴェンチューリとスコット・ブラウンのラスヴェガスのリサーチについての書、Martino Stierli著『Las Vegas in the Rearview Mirror.』も出版された(彼らのラスヴェガス論については、Aron Vinegarによる『I am Monument』という本もある)。『Log』の2013年夏号では、レイナー・バンハムの論考「ストックテイキング」を今日試みようと、ここしばらくの建築理論を総ざらいする特集を組んでいた。ついでながら、レイナー・バンハムの評伝 Nigel Whiteley著『Reyner Banham: Historian of the Immediate Future』も最近入手した。
何を書いているかというと、1960年以降の建築理論を再考する本が次々と出ており(近年、アーキグラム、セドリック・プライス、シチュアシオニストに関する本も出ている)、それらを入手はしているものの、積読状態なので、2014年はまとめて読みたいと思っているということです(蛇足ながら、2013年『現代都市理論講義』という拙著を上梓し、そこで扱った1960−70年代の都市に関する理論について、より理解と考察を深めたいと考えている)。
また、2013年は、ジェフリー・キプニスによる現代建築についての評論を集めた『A Question of Qualities』が出版され、すでに一昨年だが、アレハンドロ・ザエロ・ポロの論考を集めた『The Sniper's Log』も出ており、ここしばらく言われ続けている、建築批評の不在というのは、どこの話?といった感じであり、また建築批評が不在なのは、もしかして日本だけなのかという気もしてくる。建築批評の不在を嘆いているのは、私も含めて単なる怠慢のためであって、建築批評が成立する土壌が消えてしまったためではなくて、建築批評を書いたり建築理論を組み上げようという努力の不在のためではないかという気がしている年末である(次の設問の、国立競技場を巡る状況からしても、批評は不要どころか、求められているのではないか)。
-






- Marco Biraghi『Project of Crisis』/Martino Stierli『Las Vegas in the Rearview Mirror.』/『Log』(2013年夏号)/Nigel Whiteley『Reyner Banham: Historian of the Immediate Future』/今村創平『現代都市理論講義』/Jeffrey Kipnis『A Question of Qualities』
●A3
日々情報が足され、新しい意見が出される現状のなかで、計画の内容等について「感想」のようなものをここで書いても、あまり意味がないと思いますので、それは控えます。twitterやfacebookであれば、その瞬間に反応して書くことがそのメディアの特性でしょうが、こうした年度区切りのアンケートには、もう少し耐久性のある見解が求められているように思われます。すみませんが、今の私にはその用意がありません。
一方で、今回広範な関心と議論とが生み出されたことは、とても良かったと思います。いくぶんコレクトな言い方ですが、まずはさまざまな知見により理解が深まりましたし、また当初想定していなかった、いわば反対の意見からも、学ぶところがありました。優等生的な意見で、コレクトなのですが、これは実感です。一方で、自分と異なる考えを否定したり、取るに足りないものとするのは、理論の場においても起こりますが、今回のような具体的なケースでは、それらを簡単に片付けられないようです。議論をすべきだというのは正論ですが、議論をすることの難しさ、さまざまな意見をと言いながらも、無意識のうちに好ましくない議論は切り捨ててしまうこと、「正しさ」が厄介さを抱え込んでいること(「正しさ」が人を追い込んでしまうこと)に思い至りました。
また、そもそものきっかけである槇文彦氏の論考は多くの人が共有していると思いますが、その後の議論というのは世代などの違いにより異なっており、ほとんど共有できていないのではないかと思います。ですので、こうした大きな問いについて、世代や領域を超えた議論をしようとしても、難しい状態があります。新聞を読んでいる学生は1割もいなく、新聞は60歳以上の高齢者向けメディアになっているという調査が先日ありました。今回の問題が、新聞でも繰り返し伝えられているとしても、若い人たちはほとんどそれを読んでいません。一方では、このサイトなどは、20代と30代の読者が過半でしょう。例えば、facebookをやっている人は世代を超えて多数いるといっても、facebookでの情報は自分に近い世代や立場の人からが大半でしょうから、結局はその外からの情報というのは、ほとんど入って来ない、そういう使い方をしている人が多いでしょう。新聞やTVが、メディアのインフラであった時代は終わり、近しい人とのコミュニケーションが主流となっています。建築が建築家の創造性の産物であることよりも、より社会と関わり組み上げられていくべきだという最近の傾向は是とした場合、ではいかに広範に意見を集め、共通の議論の場を作れるのでしょうか。
今回、さまざまな意見を読んだと冒頭で書きましたが、とはいえ、私も積極的に情報を集めているわけでもなく、自然に目の前に流れてきたものを、時間に余裕があるときには拾い読みした程度です。私がたまたま目にした以外に、多くの情報や意見があり、また私が目にしたものに、どの程度偏りがあるかもわかりません。小さなメディアが無数にあるような時代に、どのように今回のような問題を考えればいいのか、模索は続きます。
いまむら・そうへい
1966年生。建築家、アトリエ・イマム主宰、千葉工業大学准教授。作品=《神宮前の住宅》《富士ふたば幼稚園新園舎》《オーストラリア・ハウス》《Corridor》など。著書=『現代建築家99』(共著)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(共著)、『現代都市理論講義』など。
岩元真明(建築家/Vo Trong Nghia Architects)
●A1
OMA《インターレース》
シンガポール出張中に訪れたOMA設計の《インターレース》が印象に残っている。2014年に竣工予定の1,000戸以上を収める巨大集合住宅である★1。
インターレースは6層分の高さを持つ直方体のヴォリュームを蜂の巣状に積み重ねることで構成されている。単純な操作だが、結果として生まれた外部空間と外観はきわめて複雑であった。とにかくスケールが大きい。視界に全貌を収めることができない。単純なシステムでも、人間の目では一部しかとらえることができない。積み木のように直方体を積み重ねる「スタッキング」の操作は、昨今の現代建築の常套手段である。しかし、紋切り型の手法でも超巨大なスケールで展開することで、既視感のない構築物が生まれていた。
蜂の巣状の配置からは、1960〜70年代にオランダで建設された巨大開発プロジェクト、《ベルマミーア団地》が想起される。一辺約100メートルの高層団地を六角形状に配置したベルマミーアは、中産階級を想定して建てられたものの、低所得者層によって占められてスラム化したという負の歴史を持つ。無論OMAは、ベルマミーア団地を知らずにインターレースを設計した訳ではないだろう。実際、OMAは1980年代にベルマミーアの再開発計画を提案したことがあり★2、また、コールハースは近年のインタビューにおいても、ベルマミーアについて言及している★3。
インターレースはベルマミーアを批判的に応用したものと考えるのが妥当だろう。両者の配置図は似通っているが、インターレースはブロックを積み木のように重ねた建築なので全体の約半分はヴォイドである。高層団地が板状に視線を遮り、目の届かない危険な中庭が生まれたベルマミーアと異なり、インターレースの中庭は閉鎖されていない。ベルマミーアは、結局は減築を行なうことで、すなわち密度を減らすことで再開発された。一方、インターレースは高密度を維持しつつ、あらかじめヴォイドを計画することで開放性を生み出すことに成功している。
超巨大スケール、高密度、ヴォイドの操作、近代建築の批判的適用。インターレースはこれらすべてを備えた、きわめてOMA的な建築と言える。ただ、コールハースの原点であるシュルレアルな神秘性は、そこにはない。インターレースの主任建築家は、現在OMAを独立したオレ・シェーレンである。インターレースはOMAがコールハースの手を離れ、彼個人の作家性を押し殺し、「ジェネリック」な運動を始めた記念碑と言えるかもしれない。


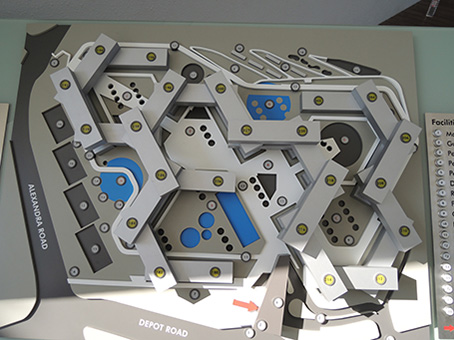
- OMA《インターレース》
筆者撮影
★1──インターレースについては以下ウェブサイトを参照した。
URL=http://www.dezeen.com/2013/10/14/the-interlace-by-oma-and-ole-scheeren-nears-completion/
★2──OMAのベルマミーア再開発案は1986年に計画された。
URL=http://www.oma.eu/projects/1986/bijlmermeer-redevelopment
★3──コールハースは近作《デ・ロッテルダム》を説明する際に、ベルマミーア団地について言及している。
URL=http://www.dezeen.com/2013/11/27/de-rotterdam-rem-koolhaas-transcript/
●A2
OMA/コールハースが続いてしまうが、「ファンダメンタルズ」と題されたコールハースが総合ディレクターを務めるヴェネツィア・ビエンナーレに注目している★4。ファンダメンタルズとは「基礎的事項」と訳される経済用語であり、国際社会における一国の経済状態を表現する指標のことである。たとえば、経済成長率や物価上昇率、失業率などはファンダメンタルズである。ビエンナーレという国際的な舞台において、コールハースは各国を相対化する彼らしいテーマを掲げたと言えるだろう。ステートメントから一節を引用する。
──1914年の段階では「中国の」建築、「スイスの」建築、「インドの」建築などについて語ることに意味があった。その100年後、(...中略...)かつては固有性を持ちローカルなものであった建築は、交換可能でグローバルなものとなった。国家のアイデンティティは近代性の生贄として捧げられたのだ★5。
「近代化の進展とともに、都市のアイデンティティが失われる」というのは、1994年に発表されたエッセイ「ジェネリック・シティ」のテーゼであった。そして、「ファンダメンタルズ」では、「都市(シティ)」が「国家(ネーション)」のスケールへと拡張される。すなわち、コールハースは近代化とグローバリゼーションが不可避的に「ジェネリック・ネーション」を招いた、と考えているのだ。各国の参加者には、この流れに抗って、あるいは身をまかせて、提案を行なうことが期待されている。もちろん、ファンダメンタルズには「基本」「原理」といった意味合いも含まれるはずである。各国がどのようなファンダメンタルズを示すか、注目したいと思う。
★4──ヴェネチア・ビエンナーレ 第14回国際建築展(会期=2014年6月7日〜11月23日)
URL=http://www.labiennale.org/en/architecture/
★5──拙訳。原文は以下。
URL=http://www.labiennale.org/en/architecture/news/25-01.html
●A3
オリンピックに関する一連の報道を聞きながら、いつかはベトナムでオリンピックをすることもあるのだろうかと考えていた。しかし、調べてみると熱帯でオリンピックが開催されたことは過去に一度もない。暑くて記録が伸びないからかもしれないが、いずれにせよ、オリンピックやスポーツという枠組み自体に近代という時代が深く刻印されていることを感じる。
JIAの機関誌に掲載された槇文彦の「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」★6は真に批評的な文章であった。
大多数の建築家は、プリツカー賞受賞者云々という法外な参加資格によってコンペの蚊帳の外に置かれた。そして、オリンピック選手の活躍をTVで見る視聴者のようにプロジェクトの行く末を傍観していた。新国立競技場に関わる回路など、一切ないように思えた。しかし、槇の批評は国家的プロジェクトに対して、各自が当事者意識を持つことを訴え、また、主体的に行動する可能性をも示すものであった。
★6──『JIA MAGAZINE』Vol. 295、2013年8月号。以下よりPDFで閲覧可能。
URL=http://www.jia.or.jp/service/newsletter_jia/detail.html?id=34
いわもと・まさあき
1982年生まれ。建築家。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修士課程修了後、難波和彦+界工作舎勤務。2011年よりVo Trong Nghia Architectsパートナー。ベトナム内外のプロジェクトに携わっている。URL=https://sites.google.com/site/masaakiiwamoto/
木村浩之(建築家/Diener & Diener Architekten[スイス・バーゼル])
●A1エドワード・スノーデンによるアメリカ国家安全保障局(NSA)による個人情報収集の暴露事件。インターネット依存社会には、もはやプライバシーなど完全に存在しない、いや、どんなプライバシーだって侵害できる、そんな現実が明らかになった。壁や仕切りや空間は、あるようで、ない。信じていたものが、崩れていく。ハードとしての建築だって、スマートグリッドの導入によって完全にオンライン化されるのだ。一般人の毎日の生活がなんら変わるわけではないが、僕以外にも居心地の悪さをもって自分を取り囲む空間を再度見回した人はいるだろう。
●A2
震災からもう2年半以上もたってメディア的に「飽き」がきてしまったのか、震災復興の話題をあまり聞かなくなった。オリンピック決定などの華やかなニュースにおされてしまっているということもあるだろう。そもそも飽きのくるのが早い社会だ。単体の建築だって、ある程度の規模になれば数年かかるものだ。復興は長丁場になる。必ずしも大衆の注目を常時必要とすることではないが、長期にわたっても、ある程度の関心を風化させない方法が必要だと思う。この場を借りて、復興プロジェクトに関わっている方々へ、そしてこれから関わる方々へ、エールを送りたいと思う。
●A3
2度目の開催地でもあり、成熟した社会としてのホストであってほしいと思う。会期中のみならず、開会に至るまでのすべてのプロセスで、今後のオリンピックだけでなく、国・都市・社会としての模範となれるような態度を取れればいいと願う。そして、超高齢化・共生社会への構造変化を遂げるきっかけになればいいと願う。
建築分野においてすでに、新国立競技場の国際建築設計競技において、日本(の行政)はいまだ文化的後進国であることを晒してしまった。建築の社会面においても、日本人が不得意としてきた外国人建設労働者への対応──それも大勢が予想されている──において改善が望まれる。建設関係者だけでなく、一般市民も街中で、外国人建設労働者に出くわすだろう。共生できる準備が整っているだろうか。
お家芸だという「おもてなし」以外にも、望まれていること、なさねばならぬことは多い。成熟、模範への遠い道のりは7年で達成できるわけではないかもしれないが、確実に大きな変化が求められている。
きむら・ひろゆき
1971年生(北海道)。1997-98年スイス連邦工科大学留学。1999年東京大学大学院修了。1999年よりDiener & Diener Architekten(スイス・バーゼル)勤務。
吉良森子(建築家/moriko kira architect b.v.主宰、神戸芸術工科大学客員教授)
●A1やはり新国立競技場についてのムーブメントが一番印象に残った。
この出来事が「固有性と自立性ありき」という自縛から日本の建築を解放するきっかけとなるのではないかと夢見ている。
日本において、過去、ここまで進んだプロジェクトに対して建築家や専門家が問題を提議したことはなかったのではないだろうか。日本の建築家にとって都市や景観は現象であって、景観における一要素として、そして景観を総体としてよりよくすることを目的として、自分の作品を設計しようとする人は希有だ。今回の問題提議のきっかけをつくった槇文彦さんは、生涯、町並みと建築について、考え、発言し、実行してきた数少ない建築家のひとりだが、結果的にこれまで建築と景観、歴史との関係に対して無関心だった建築家たちがこぞって名を連ねたことを私はポジティブに捉えたい。Better too late than neverだ。
新国立競技場に対するムーブメントが話題を呼び、専門家、市民の関心を獲得したことと震災は無縁ではないように思える。震災後、多くの建築家や若者や市民が試行錯誤しながら被災地の復興にさまざまなかたちで関わってきている。建築がさまざまな意味でコミュニティや周辺に開かれることによって、市民も、建築がコミュニティにとってかけがいのない価値をもつ可能性があるということを意識し始めたのではないだろうか。「固有で自立した」建築だけが建築の価値ではない、ということを、人々とのコミュニケーションを通して、また、身体的な体験を通して実感することで、新しい日本の建築の歴史が生み出されようとしているのではないだろうか。そのことと新国立競技場への関心とは無関係ではないと思うのだが。
果たしてこのことが何かを変えるのか。それは一つひとつのプロジェクトに対峙する一人ひとりの建築家にかかっていると思う。
●A2
真鶴の町づくり条例「美の基準」が来年20年を迎える。民間のプロジェクトの第一号となった「真鶴共生舎」の設計に関わり、そのおかげでこの10年間の真鶴の歩みを近くから見ることができた。
何が変わったのか? というと、多分「変わらなかった」ことが一番の成果なのだと思う。もともと戦後の経済発展に乗り遅れ、バブル期の別荘ブームの時にも条例によって大きなマンションが建たなかったので、真鶴の景観は、大多数の近郊の町のように以前の面影もない、ということはなく、昔からの景観を維持しながら展開してきた。近年は真鶴での時間を愛おしむような、いい感じの別荘で自由な時間を過ごす東京や横浜の住民や真鶴に移り住んで東京で仕事をしたり、という人がますます増えているようだ。
20年を経て、ここでこれまでを振り返り、高齢化、縮小化時代において、この条例が、真鶴のこれからにどのような意味をもつのか、立ち止まって考え、町民をはじめ、町づくり条例に関心のある人々とビジョンを共有することが重要なのではないかと思う。
●A3
東京でのオリンピック開催が決定されて、これまでは対岸の火事だった、オリンピック産業自体が他の国際スポーツイベントと同じように各国の大企業の利権とつながりながら、税金を吸い上げ、借金をつくって世界中を席巻するという構図に東京が直面することとなり、正直暗澹としている。借金をかかえ、これから劇的に縮小する日本は、これまでとはまったく違ったビジョンを提案しなければいけない瀬戸際にいるのに、オリンピックによって避けがたくこの問題が先延ばしにされる。これからの7年間の人工的な経済活動で利益を得る人とその後の責任をとらされる人のメンツが違うというあまりにも明らかな社会的不公平。どうしたらよいものか。正直、7年後に神風でも吹かないかと思う。日本には歴史の節目節目でそういう状況がやってくるのか、と思ったり。
きら・もりこ
1965年生。早稲田大学卒業。同大学大学院修了。デルフト工科大学留学。1995年ローマ賞基本賞受賞。1996年アムステルダムに建築事務所を設立。2004-2010年アムステルダム市美観委員会委員。神戸芸術工科大学客員教授。著書=『これまで と これから──建築をさがして』
暮沢剛巳(現代美術研究/東京工科大学デザイン学部准教授)
●A1生誕100周年という節目を迎えたこともあり、丹下健三関連の展覧会や出版企画が随分と充実していた印象がある。
特に『丹下健三とKENZO TANGE』は資料的な価値が高く、編者の労を多としたい。
また現在刊行中の『磯崎新建築論集』は、収録テキストそのものは大半が既出だが、若い世代の編集協力者が新たな読み変えを試みている点が新鮮で興味深い。
-


- 豊川斎赫『丹下健三とKENZO TANGE』(オーム社)/『磯崎新建築論集』(岩波書店)
●A2
[3]とも関連するが、来春ソウルでオープン予定のザハ・ハディド設計の《東大門デザインプラザ&パーク》が大いに気になっている。
日本でも本格的なデザインミュージアムの設立を求める声が高まりつつあり、どのような影響を及ぼすかにも注目したい。
●A3
現在の日本にはオリンピック招致より優先すべき課題が山積しているばかりか、できればイスタンブールでのオリンピックを見てみたかったこともあり個人的にはあまり歓迎していない。もちろん開催する以上は(いろいろな意味で)成功してもらいたいと思うが、現在の都政の混乱を見る限りは期待薄か。
昨今話題になっている国立スタジアムの件は、実現可能性よりも話題を優先したコンペの弊害がさまざまなかたちで露呈してきているように見受けられる。
ただ昨年もこの欄で指摘したように、デザイン自体は興味深いものでもあり、選んだ/選ばれた責任を全うするという意味でも、可能な限り原案に近い状態で実現し、また新たな問題を提起してほしいと思っている。
くれさわ・たけみ
1966年生。美術批評、文化批評。
榑沼範久(思想・芸術論/横浜国立大学都市イノベーション研究院・教育人間科学部人間文化課程)
消滅・距離・出生雑誌『nobody』39(Summer 2013)「特集=梅本洋一の仕事と時代」掲載の対談(北山恒×榑沼範久)が終わったあと、梅本洋一(1953.1.9 - 2013.3.12)の著書『建築を読む──アーバン・ランドスケープ Tokyo-Yokohama』(青土社、2006)を再び読み返した。「かつてあったもの──それを懐かしく思おうが、嫌悪しようがどちらでも同じことだが──がきっぱりと、そして明瞭に『消滅』してしまうこと」(82頁)。これは「東京」を見つめる小林信彦を論じた章の核になる文だが、消滅という違和、現在への距離が、『建築を読む』全体を突き動かしている。この違和や距離のないところで建築・都市を語る言葉を自分は信頼できないし、場所でも人間でも、消滅の衝撃を自分は見透すことができない。
-


- 梅本洋一『建築を読む』/小林信彦『昭和の東京、平成の東京』
映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』(アリソン・クレイマン監督、2012)が東京・大阪・福岡で2013年の暮れから公開されている。これから2014年にかけて、横浜・名古屋・神戸・京都・那覇・札幌でも『アイ・ウェイウェイは謝らない』は順次公開されていく。われわれの《遠近法の研究》は、何との距離を測りながら、どの場所で、何を消失点に狙っていくか。
暗い時代や薄暗い時代を生き抜くなかで、おそらく初めて完全に回帰してくる言葉がある。例えばそれは、ハンナ・アレントの言葉だ。「人間事象の領域である世界は、そのまま放置すれば『自然に』破滅する。それを救う奇蹟というのは、究極的には、人間の出生という事実であり、活動の能力も存在論的にはこの出生にもとづいている。いいかえれば、それは、新しい人びとの誕生であり、新しい始まりであり、人びとが誕生したことによって行ないうる活動である。この能力が完全に経験されて初めて、人間事象に信仰と希望が与えられる。(...中略...)福音書が『福音』を告げたとき、そのわずかな言葉の中で、最も光栄ある、最も簡潔な表現で語られたのは、世界にたいするこの信仰と希望である。そのわずかな言葉とはこうである。『わたしたちのもとに子供が生まれた』」(ハンナ・アレント『人間の条件』志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994、385-386頁)。映画『ハンナ・アーレント』(マルガレーテ・フォン・トロッタ監督、2012)も2013年の暮れから2014年にかけて、飛び火するように日本で上映館を増やしている。
-

- ハンナ・アレント『人間の条件』
くれぬま・のりひさ
1968年生。思想・芸術論。横浜国立大学都市イノベーション研究院・教育人間科学部人間文化課程准教授。論文=「自滅するヴィジョン」「音響による人体の爆撃」「フライト・シミュレーターのヴィジョン」「知覚と生」(1-4)「ダーウィン、フロイト」「問題の真偽と実在の区分」「生態学的建築をめざして」など。翻訳=ハル・フォスター編『視覚論』、マーティン・コーエン『倫理問題101問』。
小原真史(写真批評/IZU PHOTO MUSEUMキュレーター)
小原真史 ●A1北村優季著『平城京成立史論』(吉川弘文館、2013)
日本の古代史は畿内史とニアイコールとなっていることは言うまでもないが、北村優季の『平城京成立史論』はその畿内に出現した古代都市がいかに成立し、展開していったのかを史料を駆使しながら辿る労作となっている。唐の都との比較の中で畿内の豪族たちが天皇のもとに再編されていく過程やさまざまな生業を営む住人たちの姿などが生き生きと描き出され、政治と文化の結節点としての古代都市の実像に迫っている。
-

- 北村優季著『平城京成立史論』
●A2
「増山たづ子 すべて写真になる日まで」展(IZU PHOTO MUSEUM、静岡)
毎年のように紹介してきた気がするが、ようやく開催することができた。ダムに沈みゆく故郷の村を撮影し続けたカメラばあちゃん・増山たづ子の展覧会だ。IZU PHOTO MUSEUMの開館以来ずっと開催したいと思っていた。手前味噌になってしまうが震災以降、最も重要な展覧会のひとつになったと思う。国による公共事業の問題だけでなく、過疎地と都市部の関係、戦争の記憶、故郷や共同体についてなど観者によってさまざまな読み取り方ができるはずだ。ぜひ観にきてほしい。1月19日と2月9日にトークイベントも予定している。
増山たづ子「すべて写真になる日まで」
会場:IZU PHOTO MUSEUM[http://www.izuphoto-museum.jp/index.html]
会期:2013年10月6日(日)〜 2014年3月2日(日)
-

- 大西暢夫《徳山小学校校門跡の増山たづ子》(1996)
-

- 増山たづ子《櫨原分校》(1983)
●A3
紀元2600(1940)年記念のオリンピックと万博は関東大震災からの復興する帝都東京のアピールと経済振興を掲げて1930年代から招致活動が行なわれたが、日中戦争の激化と国際的な孤立、財政難などによって日本は開催権を返上し、明治以来の宿願だった万博とオリンピックの開催は戦後にまで持ち越されることになる。東日本大震災後に招致活動のアクセルが踏まれた2020年のオリンピックは、まるで1940年に開催されるはずだった「幻の東京オリンピック」の亡霊が現在に甦ったようにも思える。安倍政権は戦争のできる国へと急激に舵を切っているから、歴史が繰り返される可能性もゼロではない。
こはら・まさし
1978年生。映像作家、批評家。2005年、「中平卓馬試論」で第10回重森弘淹写真評論賞受賞。『カメラになった男──写真家 中平卓馬』監督、IZU PHOTO MUSEUMキュレーター。
坂牛卓(建築家/O.F.D.A./東京理科大学教授)
●A1ちょっと古い本なのだが、鷲田清一『「聴く」ことの力──臨床哲学詩論』(阪急コミュニケーションズ、1999)は、今年読んだ本でとても印象的だった。哲学はそもそも対話から始まったものなのに、ある時から自らを深く「反省」して物事を「基礎づける」学問となり、現在その方法ではにっちもさっちもいかない危機を迎えているという。アドルノも同様の批判を行ない、そこからの脱却の方法として彼は「エッセイ」という方法を挙げた(「形式としてのエッセー」[『文学ノート』みすず書房、2009])。僕ら理工系大学人はよく「君の論文はエッセイのようだ」とこの言葉を否定的に使う。それは論文というものが今でも「基礎づける」ことで成り立っていることの裏返しである。ということは、アドルノに言わせれば、論文という方法に基づく大学での知の生成には限界があるということでもある。
「反省」「基礎づけ」という自己閉塞的な方法論の否定は、「自己が語ること」から「他人を聴くこと」を必然的に招来する。この「聴く」という動作は「触れる」という動作と密接に関連し、「触れる」は「さわる」と異なり自─他、内─外、能動─受動の差異を超えた動作なのだと言う。ここまで来ると「聴く」とは新たな哲学の位相であり、「聴く」力とは単に音を聴くということを超え、身体が何かを「享ける」力と言い換えてもよい。
この力はとても示唆的である。おそらくこれから建築を作っていくうえで重要な要素のひとつなのだと思う。われわれ建築家が「享ける」べきものはさまざまある。建築を使う人であり、場所であり、材料であり、作る人である。そうしたさまざまな作用をトータルに「享ける」ことをベースとして、極度に基礎づけられていないエッセイのような建築があるのでは?と感じている。原理(アルゴリズム)に縛られ過ぎず、「享けた」ことに柔軟に対応する少々気まぐれなやり方が建築をもっと楽しくしていくのかもしれない。
-
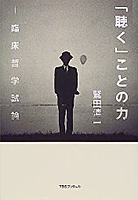

- 鷲田清一『「聴く」ことの力──臨床哲学詩論』/テオドール・アドルノ『文学ノート』
●A2
2013年の秋ブエノスアイレス国際建築ビエンナーレに招待された。このイヴェントは今年が13回目。日本からは私が参加し、3週間の展覧会と1週間のレクチャー・シリーズが行なわれた。レクチャー・シリーズには世界各国から50名近くの建築家が招待され、連日一人50分のレクチャーが連続して行なわれた(ちなみに私の前に話したのは、元モルフォシス主宰者マイケル・ロトンディだった)。展覧会はブエノスアイレスの中心にあるレコレタ文化センターで大々的に行なわれ、模型、パネルなどが所狭しと展示された。場所がらアジアからの参加は少なく、南北アメリカ、ヨーロッパが大部分を占めていた。
これだけ多くの建築家の作品を一遍に見てその語りを一時に聞くと言う機会はめったにない。久しぶりに建築のさまざまな側面、そしてそれに基づく多くの主張に触れ、日本で語られている建築はその一部でしかないということを再認した。
建築は今後さらにグローバルな流れを加速するだろう。一方でその流れに抵抗するローカルな価値が再評価されていくこともまた事実である。グローバルな視野のなかでローカルな価値を語ること、すなわち背景の異なる世界の人々のなかで自分の考えを理解してもらうことが今後ますます重要になるであろうと感じるイヴェントであった。
-

- ビエンナーレ・レクチャー・シリーズでの著者講演風景
9月24日、ブエノスアイレス、レコレタ文化センター・オーディトリアム
-

- ビエンナーレ展覧会、著者模型パネル展示風景
9月19日─10月15日、レコレタ文化センター、ブエノス・アイレス
●A3
秋にブラジルに行って多くの学生たちと話をしたところ、彼らは必ずしもオリンピックを歓迎していないことを知った。なぜかと言えばオリンピックが貧富の差こそ助長するものの生活を豊かにすることに寄与しないと見ているからである。その理由として施設への過剰投資を挙げていた。経済が上り調子の国においてすらこうなのだから経済が横這いの国でのオリンピックはそれなりの工夫が必要である。今回の計画は、レガシーの活用、コンパクト化などがコンセプトで謳われ、予算も低く抑えられ、そうした配慮を感じさせる。しかし最終支出は予算の数倍になるのがつねである。それらを考えあわせると、レガシーゾーンの中心を建て替えるというこの計画のへそにやや違和感を覚えてしまう。それは、景観の問題もさることながらコンセプトに反するし、コスト増にもつながるからである。せっかくいいコンセプトをつくっているのだからそれを徹底したらいいのではないか。企画倒れにならないことを祈っている。
さかうし・たく
1959年生。建築家、O.F.D.A.、東京理科大学教授。作品=《クローバー学園》《神田明神脇のオフィス》《アリスとテレス》《内の家》など。著書=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築』(共訳)、『建築の規則──現代建築を創り・読み解く可能性』、『αスペース──塚本由晴・坂牛卓のエスキスチェック』(共書)など。
佐々木啓(建築家/東京工業大学・補佐員)
●A1新建築『住宅特集』12月号・住宅白書
2013年を総括するにはいささか大袈裟だが、新建築『住宅特集』誌が過去に掲載された住宅作品の今を伝えた12月の特集には示唆を受けた。住宅建築のその後を取り上げること自体は他に例がないわけではないだろうが、新しく建てられた住宅建築のレビューがその役割として定着した媒体の決断にはそれなりのインパクトと批評性があるように思う。もしくは普段は建築家の意図が表現される場であることに筆者も含めて読者は慣れているので、それとの違いがより浮かび上がりやすかった、ということなのかもしれない。誌面では新築当時と現在の写真などを織り交ぜながら、住み始めてからの変化が詳細に掲載されていて設計者として勉強になることも多いし、なにより建主の言葉がとても面白い。住み始めてからの印象や気づきに加えて、状況の変化に応じて与えられた空間を解釈し、新しい使い方を開発しているように読めるところが特に良い。家族は歳を取るし、周辺環境も変わる。子供室の使い方を考え直したり、時には家族以外の人が入り込んでシェアハウスになったりと、建主の日々にはいろいろな変化があり、変化の数だけ建物と建主の対話がある。そして当然のことながら建物は簡単に建替えられたりしないので、つまり建築が生きる時間尺度は人々が引き受ける変化の時間尺度より随分と長いので、人々は与えられた空間のなかで変化を理解し、新たな生活の秩序を見出すべく模索し折り合いをつけていく。このとき建築は、人々にとって各自の立ち位置を理解することを可能にするような、ある種の基盤として現れてくる。このことに気が付くと、誌面で紹介されている住宅建築は、竣工時をその創造性のピークとするような過去のものとしてではなく、日々の生活に秩序を与え、変化に応じて新たな均衡をもたらす現在進行形の創造性を見出すことができる。誌面を眺めていると、建築が人より長い時間を生きるという単純な事実は、これだけ人々と空間の間に豊かな対話を与えるものなのだな、ということを実感でき、とても考えさせられる内容だった。
2013年は震災から2年が過ぎ、震災の経験が表現として具体的に定着しはじめた1年だったように思う。アーキエイドの活動や、みんなの家、あるいは東北各地で行なわれたプロポーザルなど、直接的に復興に関わるものもあるが、建築表現を巡る認識のなかでは、こうした建築と時間の関係に対する言葉が更新されつつあるように感じるし、また筆者自身もこのことに取り組みたいと思っている。それは建物を長く使うことの美徳というよりも、建物が人間より長い時間を生きることが人間の日々を再帰的に条件づけるということへの期待として現われる。この変わらないことに価値を見出す建築表現の探求は、新しさを巡る建築表現の探求と同じくらいエネルギーが掛けられても良いのではないかという気がしている。
-

- 『新建築『住宅特集』12月号・住宅白書
●A2
コモナリティデザイン
2014年は筆者の所属する東京工業大学塚本研究室にて「コモナリティ」(共同性)について論じた書物が出版される予定である。コミュニティやシェアといった概念は近年関心の高い言葉であるが、これらが人々の間に関係として見出されるものなのに対して、「コモナリティ」は個々に共通して内蔵されるものを捉えようとする言葉だ。私たちはコモナリティという言葉を考えることで、良いパブリックスペースとは何かを考えられるようになるのではないかと考えている。例えば花見。花見シーズンの公園は日本が誇る素晴らしいパブリックスペースのひとつだが、これは桜があれば世界各地どこでも起こる代物ではない。そこには人間の側に桜の下でお酒を飲んだり食事をしたりして楽しむ、その仕方が体感的に理解されている必要がある。私たちは現にそれを心得ているから、見ず知らずの人たちの真横にシートを敷いて花見を楽しむことができる。この人々に内蔵された性質を「コモナリティ」と呼びたい。そしてこの性質が公共空間の設計の組み立てにとっていかに寄与しうるかを捉えることを目指している。
ささき・けい
建築家/東京工業大学・補佐員
篠原雅武(社会哲学・思想史/大阪大学特任准教授)
●A1今年の夏はとても暑かったが、そのさなか、「エコロジー思考への転回」という文章(『現代思想』10月号に掲載)を書いていた。それでティモシー・モートンの『Ecology without Nature』(Harvard University Press、2007)をあらためて読み返した。この本は、「人間は環境を生きている」ということをめぐってただひたすら考察を進めていくというものだが、重要なのは、モートンが環境を、いわゆる自然環境、人間に対して客体として存在する自然環境ではなく、人間がそこにおいて生きている、「とりまくもの」として捉えようとしている、ということだ。モートンは、「とりまくもの」としての環境を、人工か自然かという図式でとらえるのは適切でないと考えている。現代においては、むしろ人工的な風景が当たり前で、『攻殻機動隊』や『ニューロマンサー』や伊藤計劃の小説や黒沢清の映画といった作品が描き出す、人工化が徹底化された果てに一種の荒廃感をも感じさせるものと化しつつあるというのが実情ではないか。人工化の果てに現われてきた荒みつつある「とりまくもの」をどう考えるかが、現代の課題であると思う。そのためにも、環境といえば自然環境であるという通念を逃れた思考としてエコロジー思考を提示するというモートンの思想の研究は必要だろう。また鈴木了二の『マテリアル・サスペンス』(LIXIL出版、2013)もそうしたことを主題にしているように思われる。
ところでモートンの思想は、object-oriented-ontologyおよび思弁的実在論という思潮の成立と無関係ではない(http://speculations.squarespace.com/storage/Morton_Response%20to%20Peter%20Gratton_v1.pdf)。それは、グレアム・ハーマンやメイヤスーらが中心となって現在進行形で進展している思潮である。その最新の動向については、ハーマンの論考を参照のこと(http://www.speculations-journal.org/storage/Harman_Current%20State%20of%20SR_Speculations_IV.pdf)。これとハーマンのメイヤスー論などを読んでいると、思弁的実在論はそれ自体決して一枚岩ではないこともわかってくるが、なぜこの思潮が現代において重要なのかを考えておく必要はあるだろうし、日本の知的状況に導入をはかるにしても、なんらかの工夫は必要だろう。その点、千葉雅也の『動きすぎてはいけない』(河出書房新社、2013)は、ドゥルーズ論ではありながら、モートンやメイヤスーの思想を射程に入れつつドゥルーズを読むというスタイルで書かれている。思弁的実在論を日本の知的コンテクストにおいてどう導入するかを考えることはこれからの思想研究の課題のひとつになるだろうが、おそらく、建築・都市を考えるうえでも、こうした思潮は大きな示唆を与えるだろうと思われる。それらは、いわゆるポスト・モダン以後の思想であるからだ。千葉さんが『現代思想』で行なっていた連載は、ハーマンとメイヤスーをもっと直接に論じているので、これがどのような形で単行本化されるかが楽しみである。
高嶺格の「ジャパンシンドローム」(関西編、山口編、水戸編)を京都芸術センターで観ることができたが、これも印象的だった。この作品は、2011年3月11日以後の日本社会の雰囲気を捉えたものとなっている。いずれの作品も、演劇仕立てのビデオ作品なのだが、そこで演じられるのが、たとえば喫茶店で店員に、「この食品はどこ産ですか? 放射能対策は大丈夫ですか?」と質問してみたときの実際の反応を再現する、というものだ。あるいは、関西のとある魚市場で、「この鯨、どこを回遊してきたかとか、わかりますか?」と質問したときの反応を再現するとか、和歌山の海辺で魚釣りをしている人に、「海の汚染とか、気になりませんか?」と質問したときの反応を再現するとか、そういうことである。私たちにとって、この問題は、けっこうデリケートだろう。食品に気をつけていることを誰かに対して話すにしても、共感を得られるとはかぎらない。そんなこと、もう大丈夫だろうとか、本気で信じている人も多いと思う。高嶺氏の作品は、そういうことの通じなさを、アートとして捉えようとしている。とくに水戸編に顕著だが、なんとなく放射能のことは気になるが、それでも、日々の暮らしのなかで、それを気にしないでやり過ごそうとしている人の逡巡を、丁寧に再現しようとしている。
宇野重規の『民主主義のつくり方』(筑摩書房、2013年)は、C・S・パース、ウィリアム・ジェームズらのプラグマティズムの現代的意義を問い直そうとする本であるが、藤田省三の「経験論」を再考しようとしていることには、共感を覚えた。というのも、私もここ数年、藤田の論文を熟読していたからで、特に「新品文化」はいろいろとヒントにしてきた。また、『民主主義のつくり方』では、個でもなく共同性でもない紐帯をどう構想するかが重要な課題と述べられているが、それとよく似たことを、塚本由晴さんが私との対談で、「コモナリティ(commonality)」という概念の重要性を説きつつ述べている(「10+1 website」2013年10月号、「空間と個と全体──政治的意図を凌駕する公共空間は可能か──コモナリティのほうへ」(https://www.10plus1.jp/monthly/2013/10/post-85.php))。なお、宇野さんには大阪で公開セミナーをしていただいたが、そこではジェイン・ジェイコブスの重要性を指摘されていた。政治思想と建築というように分野の異なるお二人が関心を共有しているようだが、そのあたりに、現代の重要な思想的・実践的課題があるのではないかと思う。
また、塚本さんとの対談の準備のため、あらためて建築と思想との交錯ということを考えてみたのだが、やはり、多木浩二の業績は重要だと思った。そのとき役に立ったのが『建築と日常』の別冊『多木浩二と建築』であった。これを機に多木浩二再評価が進むことを期待したい。
The Third Gallary Aya(大阪市西区)では、牛腸茂雄の写真展が開催されていたが、これも印象的だった。名前は知っていたが、じっくりと写真をみたことはなかった。配布されていた堀江敏幸の文章もよかった。
あとひとつ、2013年に心に残ったのは、アートエリアB1で12月18日に行なった、岸井大輔とのトークイベント(「『戯曲「東京の条件」』発行記念 劇作家・岸井大輔と考える「都市の公共性」」であった。岸井さんは「東京の条件」というプロジェクト(http://tokyocondition.com)にかかわって、その成果を今年戯曲として発表した。じつは、私はこのイベントに誘われるまで、岸井さんのことを知らなかったのだが、この戯曲を読み、考えているうちに、かなり私と関心の重なることがあるように思った。トークイベントでは、そもそもこの戯曲は何を狙いとしているのかなどと核心にふれる疑問を提起したのだが、岸井さんは一つひとつ丁寧に答えてくれた。劇作家として、都市のなかに人の集まれるおもしろい場(それこそが公共空間であると私は思う)をつくりだそうという試みの紆余曲折をいろいろと伺ったが、彼のやっていることは、建築に関係する人にも多くの示唆をあたえてくれると思われる。
ところで、自宅にはテレビがないために、「あまちゃん」はまったく観なかった。テレビがあったとしても多分観なかっただろう。ただ、なんでこういうドラマがこの年に流行ったかということは、考えてみる価値のあるテーマだとは思う。『ミュージック・マガジン』の特集「ベスト・アルバム2013」の「ロック(日本)」部門では「あまちゃん」のサウンドトラックが一位だったが、私個人の意見では、それよりはむしろ三位にランクインした青葉市子のアルバム(『0』)のほうが、文化の未来を考えるうえでインスピレーションを与えてくれるものだと思う。
-
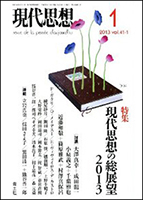
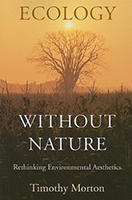




- 『現代思想』2013年10月号/ティモシー・モートン『Ecology without Nature』/鈴木了二『マテリアル・サスペンス』/千葉雅也『動きすぎてはいけない』/宇野重規『民主主義のつくり方』/『多木浩二と建築』
●A2
アトリエ・ワンの広島市現代美術館における展示。塚本由晴さんとの対談が機縁となって、この展示のためのカタログを書くことになった。実際書いてみて思ったのは、アトリエ・ワンは篠原一男から一貫する何かをちゃんと継承しているということであり、また、篠原の対話者であった多木浩二からも何かを継承している、ということだった。その何かが何であるのかをさらに考えてみたいと思ったので、この展示は個人的にも楽しみである。
●A3
2001年9月11日のテロがあったからか、いつしか私は、未来はかならずしも現在の延長上にはなく、唐突に崩壊するということもあると、考えるようになっている。この唐突な崩壊という感覚が、このとき以来ずっと、体のどこかにつきまとうようになって、だから、震災のときも、驚いたといえば驚いたが、9.11のときに呼び覚まされた感覚がまた蘇ったようにも感じた。
2020年に東京でオリンピックが開催されるというのも、確定したこととしては感じられない。つまり、実現されるべき目標として、現在の延長上に確実に行なわれる事業として、実感できない。2020年まで、あと6年。だが、この6年後を、何の破局的事態も起こらぬままに迎えることができると、現在において、確言できるだろうか。ところで磯崎新は、「建築=都市=国家・合体装置」という論考で、日本列島は、25年周期で大変動に見舞われてきたと述べている(『思想』2011年第5号)。1945年、1970年、1995年、というように。そうであるならば、次の区切りは2020年である。ということはつまり、2020年がどのようになっているかは、95年に始まった時代がどのようなものであるかを考えることで想像可能になる、ということだ。2020年にオリンピックが本当に開催されるのだとしたら、そのとき、95年に始まる過程が何であったかがあらわになるかもしれず、そのかぎりでは、興味深い。ただし、本当に開催されるかどうかわからないという、この非現実的な感覚が何であるかを問うことも、必要だろうと思う。さらに、2020年にひとつの過程が終わるとすれば、なにか新しい過程がそこで始まるということでもある。とするなら、私たちは、2020年以後がどのようになるかを想像しなくてはならないだろう。
しのはら・まさたけ
1975年生。大阪大学特任准教授、社会哲学・思想史。著書=『公共空間の政治理論』、『空間のために──遍在化するスラム的世界のなかで』、『全−生活論──転形期の公共空間』。
田川欣哉(デザインエンジニア/takram design engineering)
2009年にサンフランシスコで生まれたリムジン・タクシー配車サービスの「UBER」(https://www.uber.com)。その完成度の高いユーザーエクスペリエンスとビジネスモデルを武器に、この数年でアメリカを中心に爆発的な勢いで成長を遂げている。ユーザーはスマートフォンのアプリからこのサービスを利用する。アプリをダウンロードし、そこにクレジットカードを登録することで準備は完了。アプリを起動すると、地図画面が立ち上がり、自分の周囲にいる呼び出し可能な車が表示される。一台選んで、実際に呼び出してみると、数分でその車が目の前に現れる。ドライバーの質も担保されているから、運転は安全で正確。しかも、運賃の支払いはアプリにより自動で行なわれるため、目的地について下車する際に財布を出す必要がない。私も実際に使ってみて、下車の際に支払をする必要がないその快適さに驚いた。これはもはや魔法的な体験である。このように、呼び出しから乗車を経て下車まで一貫してスムーズでクオリティの高い体験を味うことができる。私は仕事柄、さまざまなサービスを利用し研究しているのだが、「UBER」が私のなかでは2013年のベストサービスであった。
私自身、このサービスを使い始めて、サンフランシスコという都市に帯するイメージが一変してしまった。ビジネスで各都市に短期滞在する私はタクシーを頻繁に利用する。サンフランシスコでの「タクシーが拾えない」「運転手の質が悪い」「車が古い」といったタクシー環境への不満は、そのまま都市への不満へと繋がっていた。それがこのサービスを利用することで、うそのように解消されてしまった。私のなかでサンフランシスコは、もはや「移動が快適な都市」になったのだ。
「UBER」は、道路やタクシーといった都市の既存インフラを最新のITを駆使することにより再編集することに成功している。ハードウェアにはひとつも手を付けずにである。オリンピックを控えた東京を考えるとき「UBER」の成功例は示唆に富んでいる。都市計画を考えるとき、ハードウェア・ソフトウェア・サービスの高度な編集作業を視野に置くことができるか。新しい頭で考えたいものだ。
たがわ・きんや
1976年生。東京大学工学部卒業。2001年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了。帰国後、リーディング・エッジ・デザインに参加。デザインとエンジニアリングの2つの視点を活かした多角的なアプローチで、インタラクティブなアート作品からソフトウェア、ハードウェアまで幅広い製品を手掛ける。主な作品=親指入力機器「tagtype Garage Kit」、レーザードローイングツール「Afterglow」、NTTドコモ「iコンシェル」「iウィジェット」のユーザインタフェースデザインなど。
田中浩也(人工物設計学/慶應義塾大学環境情報学部准教授、COI-T慶應大学ディジタルファブリケーション国際研究拠点長)
2013年、私は「第9回世界ファブラボ代表者会議(横浜)/Personal Fabrication as the Dawn of New Renaissance 2013」の大会委員長を務めた(1週間にわたる会議の全貌は、http://www.fab9jp.com/に映像や写真などでアーカイブされている)。「ファブラボ」という新しいものづくりの運動★1を現在進行形で進めている各国の代表者が、30カ国以上から200人も集まり、1週間をかけて密度の濃い議論とプロジェクトが行なわれた。この代表者には、デザイナー、エンジニア、アーティスト、建築家、市民、社会活動家、教育関係者などさまざまなプロフェッションが含まれる。また、総務省、経済産業省、国際協力機構(JICA)の代表者を招いてのシンポジウムも開催し★2、政策への展開についても意見交換を行なった。さらに、このシンポジウムに合わせるように、3冊の書籍が準備された★3。今年の前半期、私は持てる時間のすべてをこの準備のためだけに費やした。世界ファブラボ会議を日本で開催するのはおそらくこれが最初で最後になるだろう。
この準備のなか、私は約50年前に開催された「世界デザイン会議」との不思議な類似に気がついた。世界デザイン会議は、1960年の5月11日から16日まで日本初の国際デザイン会議として、世界24カ国から227名のデザイナー、建築家が参加して東京で開催されたとされる。この期間と規模が、「世界ファブラボ会議」とたいへん似ている。そして、この「世界デザイン会議」を契機に、メタボリズム・グループが誕生し、会議によって実現された異分野のデザイナーどうしの交流が、東京オリンピック(1964)や大阪万博(1970)に繋がっていったことは、よく知られた史実である。
実際に会議を経験してみて、200名という参加人数と1週間という期間の「設定」が、「すべての参加者が他のすべての参加者と1対1の密度の高い対話をする」のに必要十分な規模になっているということが良くわかった。完全に顔の見えるN対N(「1対1」×「N」)のコミュニケーションが発生し、結果として会期中に強力なコミュニティが形成される設定になっているのだ。この濃度は、次の新しい何かを生み出す孵化器としてふさわしい。このコミュニケーション形態は、メールともSNSともTwitterともFacebookともAKB48ともニコニコ学会とも異なる。村のコミュニケーションのようなものだから、原始的といえば原始的だが、原始的なコミュニケーションがもっとも強度を帯びる逆説的な状況がIT登場以後続いている(そして、このファブラボ「村」は、1週間で爽やかに解散し世界中に離散した)。


- 第9回 世界ファブラボ会議 国際シンポジウム(神奈川芸術劇場、2013年8月26日)
引用出典=http://www.flickr.com/photos/100633064@N02/
次回、第10回の世界ファブラボ会議は、来年スペインのバルセロナで、「From Fab Labs to Fab City」をテーマに開催されることになった。バルセロナ市では、FabLab Barcelona★4がシティ・アーキテクトに選ばれ、現在市中に6〜7箇所のファブラボの設立を予定している。これに歩調を合わせるように、国内でも、そして他の国々でも自治体ベースでのFabLabの設立が鋭意進められている。FabLabとは単なる地域の市民工房ではなく、「工房の世界的なネットワーク」であることがその本質である。いまから約20年前、ルーターでサーバーをつないでインターネットを構成したところから、現在の情報化社会は始まった。いま、工房と工房をつないで「デジタルファブリケーション施設」のネットワーク、すなわち自律・分散・協調的な「ネットワーク型」として、「工場」を解体・再編成しようとしているのがファブラボである。はたして、これが情報インフラの次の「インフラ」になりうるか。また米国ではファブラボは「21世紀の図書館」とも称されている。図書館はすでに各自治体に整備され、情報ネットワーク(図書館情報システム)でも接続されている、「ネットワーク型公共施設」の先駆例である。ファブラボは図書館に続く、新しい公共施設のモデルになりうるか。
さて、世界ファブラボ会議を開催した8月末の時点ではまだ予想もしていなかったのだが、その後、オリンピックが東京で開催されることが決定した。私の周辺でも(建築や都市スケールの話ではないが)おぼろげながらオリンピックに向けたプロジェクトが立ち上がりつつある。メディアやテクノロジーの側からも、このイベントに向けてさまざまな試みが発ちあげられそうだ。私はこの機会を、「ITが前提となった、その次に来るフィジカルな(物質的な)世界を描く」ための好機ととらえたいと考えている。3Dプリンタやデジタルファブリケーション技術は「ものづくり革命」という言葉と関連付けて説明されているが、その実態は「ものづくり」なのではなく、むしろ「ものをソフトウェアのように扱う」「ものをデジタルな存在として扱う」ことにある。つまり、情報と物質を完全に等価に扱おうというのがこの技術の核心である。では、情報と物質とが完全に等価になった世界とはどんなものだろうか。
それを考えるためのヒントのひとつとして、60年代〜70年代の想像力や物語がじつは参照点になるのではないかと考えている。たとえば、漫画『ドラえもん』に描かれた物語の多くは、「もの(物質)」をいかに操作可能にするかという問いから発せれている。もの(物質)を拡大縮小するためのスモールライ」、もの(物質)を複製量産するためのフエルミラー。音声を物質化するためのコエカタマリン。この時代の想像力のなかに、IT(情報コミュニケーション技術)の発想はまだない。むしろ、身のまわりの物質(フィジカル)な世界への操作可能性を高め、ハードウェアをソフトウェア化すること、可塑性を高めることの試論が描かれているのだ。すなわち、「環境技術」。
「世界デザイン会議」から半世紀が経って、私たちはデジタルな思考と認識をすでに当たり前のものとし、さらに現在の3Dプリンタと3Dスキャナを組み合わせれば、初期的ではあるがフエルミラーもスモールライトもコエカタマリンもすでにSFではなく実際に制作可能な状況に到達した。私は、そうしたものたち、つまり未来生活のアイテムを、アニメや漫画ではなく、実際にひとつずつこれから具体的につくっていこうと思っている。電子工作やプロダクトデザインの技術を組み合わせれば、従来の制約を遥かに超える、(ほぼ)あらゆるものが制作可能だ。つまり、SF(Science Fiction)をSF(Speculative Fabrication=思索的・推論的・批評的ものづくり)へと転換させ、それを経たうえで、SF的想像力について再び吟味するのである。空想が空想ではなく、現実に実現可能になったときはじめて、わたしたちは、空想の裏にあった本当の思いや欲望というものに別のかたちで触れていくことができるのではないか。そこに批評性があるのではないか。それを「自ら自身が」経験することが大切ではないか。
生活のなかで「(ほぼ)あらゆるものをつくることができる」技術(=How)を徹底的に実践した先に、「なぜ、なにをつくるのか」(=What, Why)という問いがおのずと浮上してくる。ここに新しい議論の場を立ち上げたいのだ。1月より始まる総務省「ファブ社会についての検討委員会」の場ではこの準備を行なうつもりである。
★1──「10+1 website」2011年5月号(特集=パーソナル・ファブリケーション──(ほぼ)なんでもつくる)を参照。
URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2011/05/
★2──第9回 世界ファブラボ会議 国際シンポジウム「進化するメイカームーブメント──グローカルものづくりの未来」
URL=http://www.fab9jp.com/expo
★3──以下の3冊。
3-1:『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(オライリー・ジャパン、2013)
3-2:『FABに何が可能か──「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』(フィルムアート社、2013)
*書評=山形浩生「モノ作りムーヴメント:その現状と新たな可能性──田中浩也編著『FABに何が可能か「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』」(「10+1 website」2013年11月号、LIXIL出版)
URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2013/11/yamagata.php
3-3:『実践FAB・プロジェクトノート』(グラフィック社、2013)
★4──FabLab Barcelona URL=http://www.fablabbcn.org/



- 『オープンデザイン』/『FABに何が可能か』/『実践FAB・プロジェクトノート』
たなか・ひろや
1975年生まれ。博士(工学)。慶應義塾大学環境情報学部准教授、FabLab Kamakura、Fab Association アジア地区代表、How To Make Almost Anything 2010修了者(http://fab.sfc.keio.ac.jp/howto2010/)。著書=『FabLife──デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』。監修=『Fab──パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ』。共著=『設計の設計』『いきるためのメディア』ほか。共訳=『アルゴリズミック・アーキテクチュア』ほか。
戸田穣(建築史/金沢工業大学講師)
秋に山口を訪れた。山口情報芸術センター(YCAM)の教育普及チームが制作した《コロガルパビリオン》★1がめあてだが、昨年の本アンケートで、服部浩之さんが《コロガル公園》を紹介されていて★2、その続編。屋内に設けられた人工地形だった《コロガル公園》が今年は外にとびだし、YCAMを背景に芝生の庭に現われたのが《コロガルパビリオン》だ。設計に際して協働したのが松原慈さんと有山宙さんのユニットassistant。
山口という町での、このような営みについては、山口をよく知る服部さんの昨年の文章を読んでいただきたく、以下、恐縮だが私記である。
★1──山口情報芸術センター《コロガルパビリオン》
URL=http://10th.ycam.jp/term1/488/
★2──服部浩之「山口という都市の半公共空間(セミパブリックスペース)」
URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2013/01/enq-2013.php#2192
金沢から陸路6時間かけて、山口に赴くことになったのは、今年度の札幌での学会の際に、久しぶりに再会した須之内元洋さんに、ずいぶん前にわたくしが訳したクロード・パランの『斜めにのびる建築』(青土社、2008)が、《コロガル公園》のリファレンスのひとつになっていることを教えられたからで、それは行かねばということで、二度目の山口訪問となった。最初の山口訪問は2002年の夏で、YCAMはまだ建設中だった。
エデュケーターの会田大也さんと菅沼聖さんの案内で見学した《コロガルパビリオン》は「子どもたちが創造する屋外メディア公園」と銘打たれ、2棟からなるひとつは円形の建物に四角い中庭が設けられ、もうひとつは円形の囲いのなかに方形の建物が納められて、内外が反転している。前者では、外壁をぐるっと上って下りるスロープが設えられ、その側面は、斜度30度と60度を組み合わせた斜面で床と繋がれる。後者では、上にいくほど小さくなっていく台形状のジャングルジムや、地元の人には馴染みの山のミニチュアなどが置かれていた。円形パビリオンで子どもたちはかけまわり、かけあがり、方形パビリオンではさまざまな遊具に子どもたちがもぐり込み、這い上がり、ジャンプしている様子を眺めるのが楽しく、また彼ら/彼女らをやさしくみつめる親御さんたちの佇まいも絵になっていた。
二つのパビリオンは、仕込まれたさまざまなメディアで繋がれ、「media > mediate(媒介する)」の言葉の意味は、子どもたちにはまだぴんと来てなかったとしても、身体で感じていたに違いない。そうした仕掛けも「子供あそびばミーティング」で子どもたちが発案したアイデアを元にしているそうだ。



- コロガルパビリオン(2013)
筆者撮影
1970年の『斜めにのびる建築』は、同年のヴェネチア・ビエンナーレでの斜めのワークショップにあわせて書かれたものだが、その後もパランは、斜めのワークショップを幾度か開催している。そこでも子どもたちは時に楽しげな、時に神妙な顔つきで斜めを感じている。
ある時期に寄り添った、40年以上前に書かれたテキストが誰かの目に止まり、また何かにつながるという出来事にまみえたのがうれしく、このパビリオンにかかわり、遊んだ子どもたち大人たちに感謝しつつ、自分も時と場所を超えてなにかを媒介できたとしたらよかったと、ここ数年のうちでもさわやかな一事だった。


- 斜めのワークショップ(1971-73)
引用出典=Claude Parent, Entrelacs de l'oblique, Édition du Moniteur, 1981, pp. 96, 99.
*
一方、金沢では、21世紀美術館で「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」の第6弾として企画されたワークショップ《Aloha Amigo!》が今年の3月大団円を迎えた★3。むしろ昨年のアンケートで挙げたほうがよかったかもしれないが、2012年4月から2013年の3月まで、フェデリコ・エレロさんの制作した《トロピカル・ランドスケープ》を舞台に、ウクレリアンとしても有名なサザン・オールスターズの関口和之さんのプロデュースをうけて実現した「常設展示」であって、なにが常設されているのかというと、毎日毎日ボランティア・スタッフが《トロピカル・ランドスケープ》がかわいらしく鎮座する展示室13に集合して、その日たまたま21美を訪れ、なんとなく展示室に足を踏み入れた来場者に、三つくらいのコードをその場で教えて、最後にみんなで合奏・合唱するという企画である。じつは、わたくしもそのボランティアの一員であったわけで、なんか楽器したいなあとぼやいていたら、それならウクレレやりませんかと本展示のキュレーター村田大輔さんに誘われたのがきっかけで、試しに1回行なってみたら、ウクレレのかわいらしさにたちまちやられて次の日には楽器店に購入に走ったという次第。そしてほどなく幽霊部員にもなってしまったわけでたいしたことは言えないのだが、確実に金沢、石川、北陸のハワイアン文化は盛り上がりをみせたし、今年も夏には、ウクレレ・パイナ2013 in 金沢と題したイベントが行なわれて(わたくしは遠くから眺めていただけなんですけど)★4、いま、雷、霰、そして雪に覆われる冬空の下でもウクレレが奏でられている様子が、TwitterやFacebookを通じて伝えられている。
★3──「Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之」(金沢21世紀美術館、2012-2013)
URL=http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=19&d=1395
★4──Ukulele Paina 2013 in 金沢(しいのき迎賓館、2013年8月24日)
URL=http://ukulelepaina.com/
わたくしはすぐに一人の楽しみにまた戻ってしまったけれど、続いていくというのはたいへんなことで、金沢では今年、湯涌ぼんぼり祭りが3年目を迎えた★5。3年目の祭りというのも、2008年の浅野川の氾濫からの復興3周年イベントとして2011年からはじまったものだからなのだが、なぜここまでの祭りになったかといえば、『花咲くいろは』というアニメの舞台となった「湯乃鷺温泉」のモデルが金沢の奥座敷湯涌温泉という、いわばご当地アニメで(制作のP.A.WORKSも隣県富山である)、学生に薦められて鑑賞したのだが、聖地巡礼も見込んだタイアップ事業であるわけだ。聖地巡礼も長い伝統だが、祭りを生んだ例がすでにあるのか、詳らかにしないけれど、テレビ放映は2011年で、今年は劇場版も公開され、毎年恒例の声優イベントや、主題歌を歌ったnano.RIPEの小学校ライブが開催され、昨年、一昨年以上の参加者を迎えたようだ。
アニメの記憶が今は昔となった頃にも続いていくよう、地元の祭りとしての定着を目指していくそうだ。続いていけと、nano.RIPEの来月発売の新譜を楽しみにしている。
- nano.RIPE「ハナノイロ」PV Full size(TVアニメ『花咲くいろは』OP主題歌)
- nano.RIPE『面影ワープ』Music Video(Full Ver.)
★5──第3回湯涌ぼんぼり祭り(石川県金沢市湯涌温泉街、2013年10月12日)
URL=http://yuwaku.gr.jp/bonbori/
ところで、毎年のアンケートには、その年に「印象に残った、都市や建築を語るうえで重要と思われる」と(いま考えると)さらっと書いてあって、今回まで気に留めなかったが、今年山口という地方都市のことを書こうとして、「2013年」という時間的なまとまりのなかでの事の軽重を共有しうる感覚というのは、「国内」でも「国際社会」でも「建築界」でも構わないが、ある空間的な、あるいは社会的な圏域を前提としているのだというあたりまえのことに、あらためて思い至る。重要さを推し量るというのは──逆説的に、でもないだろう──結局はある範囲内での、ものごとの一般化である。一般化に堪えるからこそ重要なのだが、一般化を逃れる体験の固有性・単独性が、その場所に立ったものにとっては大切なこととして残る。そして、新川和江がうたったように、わたしは束ねられたくないのだから、大切なことというのは単独性そのものである固有名で記すしかなく(「あの人はわたしにとって彼でも彼女でもない。あの人は自分自身の名前しかもっていない、その固有名しか。」ロラン・バルト★6)、あるいは固有名を冠した私記としてしか綴ることができず、束ねられることから逃れるように、言葉を費やしていくしかないのだろう。
★6──Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Édition du Seuil, 1977.
*
最後に、とくにきっかけがあったわけではないが、夏の終わりにTwitterもFacebookも退会した。去年のログを見ても夏は呟きが低調であったらしいので、そういうタイミングであったのだろう。多くの思いや言葉との出会いがあった。最後に心に留まったのは、花田佳明さんの7月4日の言葉で、翻って建築史も大改造を免れえないと、たまに書き留めたカードを見返しその言葉の重さを薄い紙片に感じている。「近(現)代建築をどう評価するかという問題を解くには、建築史学の近傍領域、特に建築設計理論や建築計画学といった分野の論理的で批評的な分析手法を投入する必要がある。逆に言えば、そういう作業に役立たない建築設計理論や建築計画学は大改造が必要である。価値観の理論化という目標に向かって。」★7
★7──URL=https://twitter.com/yoshiakihanada/statuses/352799450328080386
とだ・じょう
1976年生まれ。建築史。博士(工学)、金沢工業大学講師。共著=Le Public et la politique des arts au siècle des Lumières, Bibliotheques d'architectureほか。翻訳=クロード・パラン『斜めにのびる建築──クロード・パランの建築原理』。共訳=ル・コルビュジエ『マルセイユのユニテ・ダビタシオン』(山名善之と共訳)ほか。
ドミニク・チェン
2013年は計算機と人間のアーキテクチャにどっぷり漬かる年でした。 2013年7月に青土社より『インターネットを生命化する──プロクロニズムの思想と実践』を上梓しました。この本の第一部は『10+1』での連載がベースとなっており、第二部は2013年3月に東京大学に提出した博士論文がベースとなっています。今回一冊の本にまとめるうえで、生命論とネットワーク・コンピュテーションの接続を改めて再考するきっかけとなりました。-

- ドミニク・チェン
『インターネットを生命化する──プロクロニズムの思想と実践』
(青土社、2013)
IT業界においては、GoogleAppEngineやParseのようなBaaS(Backend as a Service)の発展が著しく、スマートフォンやタブレットのクライアントアプリケーションの開発が一層進化してきたと感じています。また、iBeaconのような物理デバイスが市販されたり、Kickstarter上で新しいデバイスが続々と開発されたり、2014年のGoogle Glassやスマートウォッチ等のウェラブルデバイスの登場を控えて、昨今のPCからスマホへの移行に見られるような身体とネットワーク・コンピュテーションの距離の短縮が一層進むことが予想されますが、建築や空間の設計においてもこうした状況と呼応する動きが出てくるのではないでしょうか。
計算デバイスと身体がますます密接することによって、アプリケーションの設計においても純粋な計算機科学的な議論だけではなく、ユーザーの身体性に基づく議論も同等に重要になってきていますが、「モノのインターネット」(Internet of Things)の敷衍もそろそろ本格化しそうな気配を感じています。
この度、「ファブ社会」について考える集いに建築家、法律家、大学人のメンバーと共に参加することになったので、2014年前半を通して、2020年頃までに実現されるべき情報ファブ社会について考えを深めることになると思います。
2020年といえばちょうど東京オリンピックが予定される時期ですが、オリンピックそのものについては、被災地の復興、原発の再稼働問題、農産物の風評被害の払拭、そして次の大地震のリスクに向けた耐震改修など、日本国内に閉じていた諸々の問題が国際的に注目され、より透明なかたちで検証され、対応が生み出される契機となればいいと思います。日本のファブ社会は大文字の「復興」と切り離して考えることはできないのではないでしょうか。
どみにく・ちぇん
1981年生。博士(学際情報学、東京大学)。国際大学GLOCOMフェロー(2013─)、NPO法人コモンスフィア(旧クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)理事(2007─)。主な著書=『インターネットを生命化する──プロクロニズムの思想と実践』。
中島直人(慶應義塾大学環境情報学部准教授/博士(工学))
●A1「今からでも復興計画の更新の必要性を強く感じています」
ちょうど一年前になる。企画・編集を担当した『建築雑誌』の2013年3月号のための座談会で、当時、内閣府大臣官房審議官兼災害対策法制企画室長であった佐々木晶二氏が語った言葉である。2011年3月11日から2年近くが経とうとしていて、各自治体の復興計画の大要が決まり、事業に向けて動き出しつつあった。編集側の私たちは、結局、中央政府・官僚がフレームをつくり、従来とおりの開発主義のもと基盤整備を最優先する復興計画を、近代固有の成長社会を前提とした復興体制を引きずっているとしてあえて「近代復興」と名付けて、批判的に検証しようとしていた。口では何と言ったか、あるいは編集意図にどう書いたかは別として、正直、すでに方向性が決まり、動き出しつつあった復興計画に対して、不埒にも高みからただ評論するような気持ちがどこかにあったのかも知れない。佐々木氏の「復興計画は今からでも変更できる」「いや、更新しなくてはならない」という言葉に、はっとさせられた。たとえ、各自治体の復興計画の立案に携わっていなくても、被災地で支援する現場を持っていなくても、都市計画に関わる者は誰もが「当事者」としての気持ちを持ち続けなくてはならない、そう、思った。
-

- 『建築雑誌』2013年3月号
その後、2013年8月に日本建築学会大会で開催された研究協議会「復興のプランニングⅠ 「復興計画」から「まちの再建・再生」へ」の企画を担当する機会があり、ここで佐々木氏や、自治体の復興のプランニングを支援している都市計画研究者にもご登壇頂き、被災した各自治体の復興計画の全体像を俯瞰し、一体どこを変更、更新しないといけないのか、そのための方法はどのようなものが考えられるのかを議論した。要点だけを紹介すると、今後も続く人口減少を見据えた際に明らかに過大な基盤整備事業をどのように適正な規模に縮小していくのか、が最もクリティカルな現場の課題であることが確認されたということであった。そして、まちの再建との関係づけが整理しきれないまま先に進んでいる防潮堤建設の問題も改めて提起された。いずれも震災直後から指摘されていた話である。都市計画の関係者の多くは、3.11は20世紀後半型の都市計画の惰性を断ち切る不連続点となる(べきだ)と思ったが、震災から3年目の現在において、実はひとつの正念場を迎えている。
なお、佐々木氏は、ご自身のブログで下記のような文章をまとめている。参考までに紹介しておきたい。
● 広めにかけた土地区画整理事業を縮小する方法について(第二稿) http://shoji1217.blog52.fc2.com/blog-entry-1563.html
● 海岸保全施設の高さと復興まちづくりについて(法的視点から、私案) http://shoji1217.blog52.fc2.com/blog-entry-1570.html
●A2
昨年のアンケートで、ニューヨークの都市デザインに着目すべきだと書いた。2013年11月に行われたニューヨーク市長選挙では、三期12年間務めたマイケル・ブルームバーグ市長に代わる新たな市長として、民主党のビル・デブラシオ氏が当選し、2014年1月1日に市長に就任する。20年ぶりの民主党政権となり、格差解消をはじめとして、さまざまな政策が大きく転換していくものと思われる。ブルームバーグ市政下で積極的に取り組まれた都市デザイン戦略の多くが、この後、どうなっていくのか。都市デザインと政治との関係を、引き続きウォッチしていきたい。
●A3
東京という都市のこれからについて、あるいは東京を出発点として、日本の国土のありようについて、多くの人が関心を持つきっかけとなるのではないかと思っている(久しく人々の関心の中心から外れていた「都市」が、また舞台に戻ってくるという思いもある)。特に2020年までという、ある「時間」の長さが共有されることが、議論の土台としては大きいと思う。7年先という近未来はすぐそこであろうが、少なくともこれからの方向性を見定めるには十分な時間である。しかし、「東京オリンピック」を「さまざまなアーバニズムのアリーナ」を生み出す契機として活かすためには、現在の単なる「施設配置計画」としてしか表現されていない構想の背景やその先の展望について、やはりここでも「当事者」のひとりという思いで探求を重ねていかなくてはならないと考えている。
なかじま・なおと
1976年生。東京大学工学部都市工学科卒、同大学院修士課程修了。博士(工学)。東京大学大学院助手、助教、慶應義塾大学専任講師を経て、2013年より現職。専門は都市計画。著書= 『都市美運動』、『都市計画家石川栄耀』(共著)など。
中谷礼仁(歴史工学家)
●A1・坂口恭平、治郎丸恵子両氏の吉阪隆正賞受賞(生活学会)
・2013年1月2日から9月11日まで断続的に行なったユーラシアプレート境界の旅
揺れるのは東北だけではないと、震災コンプレックス、石造コンプレックス、コスモロジーコンプレックスなど、当方が抱えていたインフェリオリティ・コンプレックスを根こそぎ治療してくれたグラウンドツアーだった。インド、ネパール、イラン、トルコ、ギリシャ諸島、マルタ、シシリア、チュニジア、モロッコ、ジブラルタル海峡、インドネシア諸島と旅した。たくさんノートを取り、たくさん写真を写して、何のためらいもなく私費で同行してくれた深見奈緒子(イスラム建築)、佐藤浩司(インドネシア・建築人類学)ら諸先達、そして現地の人々から多くの生き継ぐべきことを教えていただいた。ブログとピカサ・アルバムで旅行記を鬼のようにアップした。紀元前5000年につくられたとされるマルタのハイポジウム地下神殿がクライマックスだった。シシリア島のベリーチェ地震後の廃村を、地元の家族と散歩した時の話も思い出に強く残っている。
http://rhenin.wordpress.com/category/on-the-edge-tour-2013/
https://picasaweb.google.com/108551454693342851793
・川合健二マニュアル再版
ご遺族のご協力により再版可能となった著作。必要な人にぜひ行き渡ってほしいと思う。よかれと思ったのに結果的に入手困難にしてしまうのはよくないから。
http://www.acetate-ed.net/bookdata/008/008.html
-

- 『川合健二マニュアル』(編集出版組織体アセテート、2007)
・11月に熊本に行った時に偶然立ち寄った熊本県立農業大学校学生寮(2001)が、夢のような建築だった。
・11月に伊豆大島緊急災害調査を千年村関東班で行なった時の被災住民の方々の強さ。まだ再建可能であるという確信があるとないとでは大違いだと思った。また訪れたいと思います。
・書籍では後藤治ほか『食と土木建築』、西沢立衛『けんちくワークブック』、Josef Koudelka『WALL』
-



- 後藤治ほか『食と建築土木 たべものをつくる建築土木』(LIXIL出版)/西沢立衛『けんちくワークブック』(平凡社)/Josef Koudelka『WALL』(Prestel Verlag)
●A2
ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館展示はこれまででおそらく最もハードコアなものになると思います。
●A3
賛成も反対も何も、スポーツ自体に興味がない層がいることを知ってほしい。便乗再開発はしないでほしい。ポスターぐらいは1964年ぐらいビシっとしたデザインをお願いしたい。
なかたに・のりひと
1965年生まれ。歴史工学家。早稲田大学創造理工学部教授、編集出版組織体アセテート主宰。http://www.nakatani-seminar.org/
保坂健二朗(東京国立近代美術館主任研究員)
4月、「武雄市図書館」が改修工事を終えて再開館、また「佐世保の実験住宅 ハウステンボススマートハウス」(設計:東京大学生産技術研究所川添善行研究室)が竣工。ともに九州で偶然に同月。前者はCCC、後者はHISに関係するプロジェクト。ある世代以降の経営者の、「建築」に対する意識の変化を象徴するかのような出来事ではなかろうか。5月、国立近現代建築資料館が開館。業界にとっては悲願であったと思われるが、「一般」に、あるいは「国外」に周知しようという努力がほとんど見られない点には、美術(館)の立場から関心を持ち続けてきた者として、あえて苦言を呈したい。8月、ハンス=ウルリッヒ・オブリストの『キュレーション──「現代アート」をつくったキュレーターたち』(フィルムアート社)の翻訳が刊行される。「現代アート」の展覧会の黎明期においては、建築が相当に重要な位置を占めていたことが改めてわかる好著。しかし、となると今日に見られるひどい「分化」はなぜ生じたのか......。おそらくはキュレーターの「自称専門家化」ゆえであろう。その点、8─10月の「あいちトリエンナーレ」が、客人(まれびと)的な五十嵐太郎氏のディレクションの下、都市とアートと建築とに真っ向から取り組んだことは、現代アートのあるべき姿への回帰だったとすら言える。11─12月の「F/T13」では、Port B(高山明)の「東京ヘテロトピア」が、大都市東京に存在しているはずの「ヘテロ」を、聴覚という身体的な感覚を通して、訪れた者の肉体に、あるいは記憶に、柔らかく刻み込んだ。12月、ソウル市内に韓国国立現代美術館がオープン。同館の3つめとなる施設で巨大。6月には香港のM+の建築コンペも終わっており、それらのアグレッシブさに比べると日本の文化行政の停滞を強く感じざるをえない一年であった。-

- ハンス=ウルリッヒ・オブリスト
『キュレーション──「現代アート」をつくったキュレーターたち』
ほさか・けんじろう
1976年生。東京国立近代美術館主任研究員。近現代美術。主な展覧会企画=「建築がうまれるとき──ペーター・メルクリと青木淳」、「現代美術への視点6 エモーショナル・ドローイング」、「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」、「イケムラレイコ うつりゆくもの」、「ヴァレリオ・オルジャティ」など。『すばる』『朝日新聞』にて連載。
水野祐(弁護士/Arts and Law代表理事、Creative Commons Japan、FabLab Japan)
●A1
私は、弁護士としての本業の傍ら、これまでクリエイティブ・コモンズやファブラボという団体で活動をしてきましたが、これらの情報コンテンツやプロダクツの分野に広がってきたオープン化やリソースの利活用といった視点が、建築・不動産の分野まで広がりつつあること、そしてそのような視点がこの分野においても有効であるということを確信した年でした。
人口減少や予算縮小というなかで「減築」というテーマが叫ばれるなかで、既存のリソースをいかに有効に利活用していくか、そのためには建物、土地という不動産の所有権や、賃貸借契約によって生じる賃借権、そして建築基準法や都市計画法等により規制される諸権利をいったん柔らかく解きほぐし、流動化できる状態にし、そこで生まれるリソースを利活用するという思考が大切になります。
具体的には、トビムシが行なっているような、森林や土地を循環し有効活用していくためのダイナミックな法的スキームや、《Nowhere resort》や《メゾン青樹》に見られるようなリノベーションにおける大家と賃借人とのあいだの柔軟な賃貸借契約、そして吉村靖孝さんの『超合法建築図鑑』(彰国社、2006)において提唱され、Open Aの馬場正尊さんなどが実践しているような建築基準法や関連規定の規制や運用をいかに戦略的にクリアし、どのようにクリエイティヴに「読み替えて」いくかという思考と実践等、さまざまなトライがなされ、そこでのアイデアが問われています。
法律を変えるためには想像以上に時間と労力を要しますが、契約やライセンスは意外に制限がなく、柔軟に当事者の実現したい状態を作り出すことができます。また、法律の適用においても、その解釈には「幅」があり、その規制の「越え方」もさまざまな工夫の余地があると感じるところです。
クリエイティブ・コモンズというライセンスは、まさにこのような視点から情報コンテンツの分野で活用されています。アメリカの憲法学者ローレンス・レッシグがクリエイティブ・コモンズを提唱してから10年強が経過しましたが、つい先日、そのver.4.0が発表されました(日本語訳の発表にはまだ時間がかかりそうです)★1。特徴としては、著作者人格権の明示的な放棄やデータベース権の明記、そしてさらに国際的な標準化を推し進められたかたちとなっていることですが、このように10年以上前に生まれた法的なスキームですら、まるで生き物のように耐えず変化しています。
建築・不動産の分野においても、旧来的な契約やライセンスのスキームだけではなく、クリエイティブ・コモンズのようなフレッシュなアイデアが不断に求められており、私もそのお手伝いができればと考えています。
創造性を加速させる法律や契約の視点については、今年共同で翻訳・執筆を担当させていただいた『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(オライリー・ジャパン、2013)という本でも紹介させていただきましたので、ご興味をお持ちいただいた方はご一読いただければ幸甚です。
★1──CC's Next Generation Licenses -- Welcome Version 4.0!
URL=http://creativecommons.org/weblog/entry/40768?utm_campaign=2013fund&utm_source=email2j&utm_medium=html

- 『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(オライリー・ジャパン、2013)
●A2
自分以外の2014年の予定がわからないので、どうしても手前味噌になってしまうのですが、個人的に楽しみにしているプロジェクトを挙げてみます。
総務省「ファブ社会の展望に関する検討会」★2
メンバーとして参加する予定のこの会は、昨今「ファブ」と呼ばれている3Dプリンターやレーザーカッター等の「物質への出力」を特徴とした機器の登場が、国際的な情報通信政策の観点から、どのような変化を生み出すのかを検討する会です。デザイン学、建築学、工学、法律、文化芸術、教育学、経済学と幅広い視点から「ファブ社会」の可能性を議論します。議論は公開で行なわれる予定なので、ご興味があればぜひご参加ください。
★2──「『ファブ社会』の展望に関する検討会」の開催
URL=http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000013.html
意匠制度の改正
特許庁の意匠制度改正の委員会にも関わらせていただいております。現行法では保護されづらいウェブ等の画面デザインを保護するための意匠制度の拡充と国際化について議論しており、今年は意匠法について熟考する機会が多くなりそうです。
国際芸術祭の開催
来年行なわれる横浜トリエンナーレ2014★3、札幌国際芸術祭2014★4という二つの国際展をお手伝いさせていただいている関係で、アート分野における国際的なプラクティスを拡充できそうなので楽しみにしています。
★3──横浜トリエンナーレ2014
URL=http://www.yokohamatriennale.jp/2014/index.html
★4──札幌国際芸術祭2014
URL=http://www.sapporo-internationalartfestival.jp/
そのほか、個人的にも、co-labさんとともに、サロン形式の定期イベントを行なう予定です。
●A3
2020年までに、「オープン」や「ファブ」という思想をいかに社会制度として潜在的に実装できるか、それを法律や契約といった法的側面からどれだけ加速・促進できるか、その結果として日本人がオリンピックというものをどれだけ「わがこと」としてとらえることができるのかということを考えています。
みずの・たすく
弁護士。シティライツ法律事務所代表。Creative Commons Japan 、FabCommons(FabLab Japan Network)、LiFETONES などにも所属。NPO法人ドリフターズ・インターナショナル、一般社団法人マザーアーキテクチャア監事。アート、クリエイティブ、IT、建築不動産など分野の法務に従事しつつ、カルチャーの新しいプラットフォームを模索する活動をしている。共著=『クリエイターの渡世術』。共同翻訳・執筆=『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』。
南泰裕(建築家/アトリエ・アンプレックス)
●A1槇文彦の20年にわたる活動をまとめた『漂うモダニズム』が、2013年に読んだ書物のなかで、強く印象に残った。建築に関わる一人ひとりが、指針のないままに大海原を漂っている現在の状態を、静かに含蓄のある態度で語っている槇の言葉には、しばし黙考を誘われる。20世紀初頭の、福音書としてのあるいは神託としてのモダニズム。その展開の先に、さまざまなねじれがあらわになってきて以降もなお、「モダニズムとは何か」という問いがかたちを変えてい生き続け、ほぼ1世紀近くを迎えている。
言語のアナロジーによってモダン・アーキテクチャーを考察する視点は、モダニズムの建築自体の出自を再確認しており、わかりやすい。徹底的に微分された文化的志向と、世界を隈なく覆い尽くすグローバリズム。この対極的なものの同時存在様態をなす現在の状況に対して、私たちはどのような態度を取るのか。〈モダニズム〉とは、そうした状況を測定し、新しい思考を紡ぐための、ねじれた概念装置であり続けていることを、再確認させられる。
-

- 槇文彦『漂うモダニズム』(左右社)
●A2
2013年に、私の研究室において「New Plat 2013」というプロジェクトをまとめ、発表した。これは、現在の東京の築地市場が、近い将来に豊洲へと移転することから、築地に残されることになる約23ヘクタールあまりの膨大な跡地に、これからのありうるべき都市空間を想定した計画案である。築地という、東京都心の広大な更地をどう再編成するか、ということが、2014年以降、いよいよ具体的な都市的課題となることは確かで、こうした試みが、そのための試金石をなすのでは、と考えたからである。
-

-
「New Plat 2013」のイメージモデル。2013年6月に、南洋堂書店にて同プロジェクト展を開催
[製作:国士舘大学南研究室、2013]
-
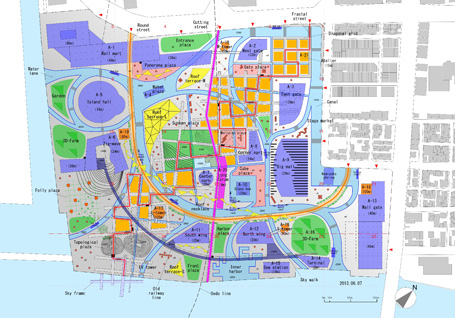
- 全体配置図。敷地に運河のネットワークを張り巡らせ、多様体のように全体を織り上げた計画案
●A3
2020年の「東京オリンピック」について思うのは、「それ以前/それ以降」ということである。祝祭は一瞬で通り過ぎる。なので、オリンピックそれ自体よりも、2020年までの準備・再編成期間と、2020年以降の将来を、どのように突き合わせて考えてみるか、ということが肝要なのではないかと思う。
20世紀以降の東京は、関東大震災と第二次大戦というカタストロフィからの復興により、構造的にも社会資本の数々も、大きく変化した。旧赤坂プリンスホテルのような超高層も、近年、あっさりと解体されてしまったので、関東大震災からほぼ100年を迎える2020年頃を境として、20世紀半ばにつくられた東京の超高層の数々が、解体されていくのではないか。もはや東京には開発のための未踏の地は次第になくなってきている。なので、都市の欲望は今度は、過密化した超高層群の自己抹殺へと向かう可能性がある。そのときに、21世紀型の新しい東京の再編が、行なわれることになるだろうか。
みなみ・やすひろ
1967年生。建築家。アトリエ・アンプレックス主宰、国士舘大学理工学部教授。作品=《PARK HOUSE》《南洋堂ルーフラウンジ》《spin-off》など。著書=『住居はいかに可能か』『ブリコラージュの伝言』『トラヴァース』など。
http://www.atelierimplexe.com/
http://bricoleurs.exblog.jp/
山崎亮(コミュニティデザイナー/studio-L、京都造形芸術大学教授)
●A1各地で土砂災害が多発したこと。これまでに増して大きな災害が頻発したことは印象的でした。もちろん、大型の台風が多く日本に上陸したり接近したりしたことなどが直接的な要因だと思いますが、これまで懸念されてきたように山や森林の脆弱化もまた原因のひとつなのではないかと考えています。日本の山や森が管理されない状態が続いて久しいですが、照葉樹林帯に位置する日本では極相林に近づくまで不安定な時期が続きますので、今後はますます各地で多くの災害が起きるのではないかと懸念しています。さらに、こうした出来事が都市近郊でも起きるようになる危険性が高まっていますので、コンクリートとアスファルトで固めれば自然をコントロールできるという考え方から脱して、人が介在することによって動的な均衡を保ってきた近自然との付き合い方を現代的にデザインする必要があると感じています。
●A2
手前味噌で恐縮ですが、2014年4月から東北芸術工科大学にコミュニティデザイン学科が誕生し、そこでコミュニティデザイナーを育てることになっています。毎年30人ずつの学生を受け入れ、4年間かけてコミュニティデザイナーとして自立するように育てたいと考えています。東北の被災地復興のお手伝いをはじめ、中山間離島地域や商店街のまちづくりに直接関わることによって、現場でコミュニティデザインの具体的な方法を体得してもらおうと思っています。そのために、大学内にstudio-Lの山形事務所をつくる予定です。現在、学科の講師陣やカリキュラムを検討しているところですが、この段階ですでに新しい学科がスタートしたら起きるであろうさまざまな出来事を想像しながら興奮している自分に気付いています。
●A3
行政や専門家がおもてなしするだけでなく、市民もまたおもてなしするようなオリンピックになるといいですね。ボランティアとして関わることをはじめ、市民事業として関わったり、地縁型コミュニティやテーマ型コミュニティがさまざまな方法で関わることができるようなスキームになることを願います。これによって、オリンピックを単なる大規模イベントとして終わらせてしまうのではなく、オリンピック後に残ったさまざまなコミュニティが東京のまちづくりに関わり続けるようなきっかけをつくり出せると理想的だと思います。
やまざき・りょう
1973年生まれ。著書=『コミュニティデザインの時代』ほか
青井哲人(建築史・都市史、明治大学准教授)
●A1〜A3デヴィッド・ハーヴェイ(森田成也・大屋定晴・中村好孝・新井大輔訳)
『反乱する都市』(作品社、2013.2/David Harvey, Rebel Cities, 2012)
経済地理学におけるいわゆる空間編成論のおさらいおよび現状分析と、資本主義的空間編成に対する世界各地の「反乱」を支持する議論の構築を試みた書。研究室の学生たちと読んだ。「空間編成論」は、都市形成の理論的アリーナを想定するうえで強力かつ有効(建築分野の都市形成史はいくぶんナイーブにすぎる)。一方の「反乱」の可能性についてはなかなか日本の状況に即して実感するのは難しい面があり、『建築雑誌』2013年12月号「特集:ストラグリング・アーキテクチャー」の座談会で、ハーヴェイの別書の訳者であり日本での空間編成論の主唱者のひとりである水岡不二雄先生にその点たずねたところ、やはり「反乱」のリアリティを失ってきた日本社会の軌跡を反芻しておられた。
年末にたずねたプノンペン(カンボジア)では、反政府デモのため低所得層の人々が連日泊まり込む夜のフリーダムパークを縫うように歩いた。彼らの主張そのものは「都市反乱」的なものではなく、むしろ労働運動の色が濃い。ただ、私たちが日本に帰国した直後に治安部隊との衝突で死者が出ており、このデモ鎮圧の背景に、海外資本進出とそれを失いたくない政府という構図がちらつく。プノンペン(首都)やシエムリアップ(アンコール遺跡観光拠点)の都市開発も加速している。私たちが歩いた公園の横でも、外資による超高層ビル建設のクレーンが立っていた。
2020東京オリンピックについても、少なくともハーヴェイはじめ今日読めるいくつかの都市論の水準はおさえて、グローバル都市東京の問題として議論すべきだろう。本書と併せて読みたい最近の本として、シャロン・ズーキン(内田奈芳美・真野洋介訳)『都市はなぜ魂を失ったか ジェイコブズ後のニューヨーク論』(講談社、2013)、エドワード・グレイザー(山形浩生訳)『都市は人類最高の発明である』(NTT出版、2012)、ハーバート・ガンズ(松本康訳)『都市の村人たち イタリア系アメリカ人の階級文化と都市再開発』(ハーベスト社、2006)をさしあたりあげておく。
-


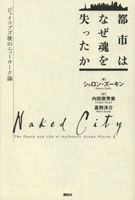


- デヴィッド・ハーヴェイ『反乱する都市』(作品社、2013.12)/『建築雑誌』2013年12月号「特集:ストラグリング・アーキテクチャー」/『都市はなぜ魂を失ったか ジェイコブズ後のニューヨーク論』(講談社、2013)/エドワード・グレイザー『都市は人類最高の発明である』(NTT出版、2012)/ハーバート・ガンズ『都市の村人たち イタリア系アメリカ人の階級文化と都市再開発』(ハーベスト社、2006)
*
『郊外のサステナビリティ:東急電鉄にみる地域開発とその運営』(新建築別冊、2013年11月)
都市開発は、資本を動かせる者にイニシアチブがある以上、階級闘争の場にほかならないとハーヴェイは主張するが、たとえば東急の都市開発を主題とした猪瀬直樹『土地の神話』(小学館、1988)は日本的イニシアチブの特質を知るのにすぐれた歴史的ルポだ。ただし猪瀬が、この仕事を通して日本の都市形成をめぐる権力関係を知りえたことが自らの都市行政に大いに役立っているのだと自ら振り返ったときには、正直なところ驚き、次の瞬間ナルホドと思った(『建築雑誌』2012年11月号「特集:トーキョー・アーバニズム」でのインタビュー)。
一方、東急のような開発資本も、不動産の建設・売却に収益を依存する段階から、建設した広義のインフラとそこに生まれ動いている社会のマネジメントに向き合う段階へと、自らの仕事を変質させてきたのだと教えてくれるのが、本書『郊外のサステナビリティ』である。もちろん、それも資本による空間編成のフェーズの遷移と捉えることはできるのだが──。
郊外論のこれまでの傾向を振り返れば、近代的あるいは戦後日本的な政治経済過程のなかで創出された均質な社会=空間としての「郊外」の異様さを言挙げするのがアカデミックな、あるいはジャーナリスティックな言説のクリシェにすらなってきた(『建築雑誌』2010年4月号「特集:〈郊外〉でくくるな」も参照)。それに対して本書がどのような郊外論を示唆するのかを読者は考えるべきだろう。他方で、郊外住宅地形成の歴史研究という線での建築分野からの貢献としては、山口廣『郊外住宅地の系譜 東京の田園ユートピア』(鹿島出版会、1987)などがあり、本書をこれと併せて読むことも有益だろう。だが、もっとアノニマスなスプロールの具体的ドキュメントもどんどん掘り起こしたい。東京の郊外形成、ひいては都市形成の全体像にそれなりの見通しをつけるための戦略が必要だ。
-

- 『郊外のサステナビリティ:東急電鉄にみる地域開発とその運営』(新建築社、2013.11)
*
新国立競技場問題については、今回のコンペの特質について本誌(10+1 website 2013年11月号)に記事を寄せた。コンペ自体のセッティングに、やはりグローバル都市の空間編成とそれに動員される建築設計・生産体制の今日的ありようが前提的に組み込まれていたのではないかと指摘した。大学で習う都市計画に至っては、コンペでは無視されていて、(事後的に)文字どおり空間編成の力学に沿って気づかぬうちに改変されうるようなものになってしまっている。
ところで、筆者が歴史分野から発言できるもうひとつの視角は、明治神宮外苑をどう見るか、である。直ちにオリンピックと東京の将来について示唆できるという類いのものではないが、日本あるいは東京の特異な公共空間の形成にかかる歴史的知見が共有されることには意義があろう。筆者は、東京に越してきた翌年(2009年)、機会があり歴史学や神道学など異分野の研究者の皆さんに提案して明治神宮史研究会という有志の研究グループをつくったが、とくに国学院大学の皆さんの尽力によりこの研究はそれなりに大きな運動になってきた。ここでは明治神宮をひとつの焦点として、空間と公共性の問題に、どのような論理と歴史過程が絡まっているのかを解きほぐそうとしている。『明治神宮:「伝統」を創った大プロジェクト』(新潮社、2013年2月)の著者今泉宜子もこのグループの中心的メンバーのひとりで、同書は私たちの研究成果を盛り込んでもいるのだが、槇文彦氏や陣内秀信氏が、新国立競技場問題の議論においてこの文脈で依拠しているのも同書である。今後、さらに研究を深めつつ成果を社会化していきたいと思っている。
-

- 今泉宜子『明治神宮:「伝統」を創った大プロジェクト』(新潮社、2013.2)
*
4月の堀口捨己・神代雄一郎展(明治大学)、11月の大江宏展(法政大学)
前者は筆者が企画責任者で、大江宏シンポにも出席している磯崎新氏らを招いた記念シンポジウムの成果は本誌(10+1 website 2013年6月号)に掲載されている。丹下健三およびメタボリストたちの回顧が進むが、一方では多様な立場が緊張を孕みつつ織り成す歴史的脈絡の複数性を蘇生させ続ける努力が伴わなければいけない。これもまた、近代、そして近代日本の技術・経済および空間編成の歴史的特質と、そのなかでの建築設計者(建築家)の職能像との、複雑にして抜き差しならぬ関係への問いになっていかざるをえない。
あおい・あきひと
1970年生まれ。建築史・都市史。明治大学准教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』『植民地神社と帝国日本』ほか。
http://d.hatena.ne.jp/a_aoi/
蘆田裕史(ファッション批評/京都精華大学教員)
●A12013年5月26日に東京都小平市で住民投票が行なわれた。これは小平市都道328号線計画の是非を問うものである。雑木林をつぶして道路を建設するというこの計画(しかも策定は50年も前とのこと)に疑問を抱いた住民の運動によって住民投票が行なわれることになったが、議会は後から「投票率50%を超えなければ開票しない」という条件をつけることになる。結果、投票率が50%を超えることなく、開票は行なわれなかった(この経緯については國分功一郎『来るべき民主主義』を参照)。
この顛末は、「都市は誰のものか?」というきわめてありふれた、だが根源的な問いを私たちに投げかける。都市の寿命は人間のそれよりも長い。であれば、私たちは一体誰のために都市計画を行なうのがよいのだろうか。もちろんいまここに暮らす住民のためを考えることは重要だが、小平市の事例からは数十年先の未来を見据えた計画を行なうことの必要性を改めて感じさせられる。2013年は新国立競技場のデザインの是非が話題となっていたが、歴史と建築、環境と建築、政治と建築といった点において両者の問題は通じるものがあるだろう。
-

- 國分功一郎『来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎、2013)
●A2
自分が関わったプロジェクトの話になるが、2013年7月にファッション専門のギャラリー「gallery 110」を京都に開設した。運営メンバーは私のほか、関西在住の研究者、キュレーター、デザイナーなどである。
これまで日本にはファッションに特化したギャラリーというものはなかった。もちろん、多目的利用が可能なスペースを借りてファッションの展覧会やショーを行なうことは珍しくない。だが、ほかのジャンルに目を向けて見ると、写真、テキスタイル、建築、グラフィックデザインなど、ひとつのジャンルに特化したギャラリーが多少なりとも存在する。このようなギャラリーの活動を追いかけていくと、ジャンルの歴史がおぼろげながらも見えてくるだろう。
インディペンデントの組織である「gallery 110」に、今後どれだけのことができるかはわからない。だが、10年後、30年後にふりかえったとき、少しでも2010年代のファッションが見えてくるような場にできればと思っている。
●A3
オリンピック会場となる新国立競技場のデザインの是非についてさまざまな建築家や批評家が論じていたが、門外漢としてはそこで交わされている議論に少なからぬ違和感も覚えた。
ザハ・ハディドのプランは確かに環境や歴史を踏まえたものではないかもしれない。だが、現在日本で評価されている建築家のなかには同様に、実際にその建築を使う人々、周りに住む人々のことを考えているようには見えない建築家も少なからずいるように思われる。そうした建築のことは無視しておきながら、新国立競技場にだけ集中砲火するというのはいささか不公平だという印象を受ける。建築家のエゴの塊のような派手な建築ばかりではなく、地味であっても使い手や環境のことがきちんと考えられた建築をきちんと評価していくことが、今回の件と同じことを繰り返さないために必要なのではないだろうか。
あしだ・ひろし
1978年京都生。批評家/キュレーター。ファッションの批評誌『vanitas』編集委員。共著=『現代芸術の交通論』(丸善、2005)、『ファッションは語りはじめた──現代日本のファッション批評』(フィルムアート社、2011)ほか。
足立元(美術史、美術評論)
●A1昨年、「東京」という日本の中で最も巨大かつ有名な都市の名が、展覧会タイトルとして用いられたのを見た。ニューヨーク近代美術館の「TOKYO: 1955-1970 A NEW AVANT-GARDE」展である(2012年11月〜13年2月)。これは、日本の戦後美術史の見取り図を示そうとしたものとして重要だが、同時に、アメリカ人の視点でそれがどのように見えるかを提示したものとして興味深かった。
多彩な戦後美術史を要約するのは困難なことだが、この展覧会では、主に、丹下健三の「東京計画1960」のような過激な都市計画、中村宏の絵に見られる歪んだ人間像、そして東松照明らの鮮烈なモノクローム写真、という三つの側面を強調していたように思う。 ちなみに、同時期に隣の数倍の広さの会場で開催されていた「Inventing Abstraction, 1910-1925」展は、20世紀前半の西洋における造形の進化を重要な作品・資料で鮮やかに示していた。それに比べると、「TOKYO」展はインパクトばかりが空回りするような(もちろんそんなことはないはずだが)、原始的・未開の印象を与えるものだったことに、小さなショックを覚えた。オリエンタリズムは終わっていない。
-
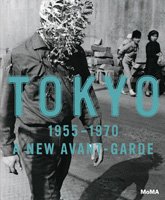

- 「TOKYO: 1955-1970 A NEW AVANT-GARDE」カタログ/「Inventing Abstraction 1910-1925」カタログ
同時期のニューヨークでは、グッゲンハイム美術館で、関西にあった前衛グループ・具体に関する「Gutai: Splendid Playground」展を開催中だった(2013年2月〜5月)。前年に国立新美術館で開催された具体展がクロノロジカルに結成から終焉までを折っていたのに対し、グッゲンハイムの展覧会は膨大な調査に基づきながらもあくまで華やかな祝祭として演出していた。後者の方がはるかに楽しめるものであったことは間違いない。だが、これらの展覧会のように、日本の美術が英語圏の中で拾ってもらうことを、果たして国際的な評価として素直に喜ぶべきか、あるいはグローバリゼーションにおける文化資本の収奪として懸念するべきか。
その頃、デューク大学准教授ジェニファー・ワイゼンフェルドの『IMAGING DISASTER: TOKYO AND THE VISUAL CULTURE OF JAPAN'S GREAT EATHQUAKE OF 1923』(University of California Press, 2013)の出版があった。絵画、漫画、写真、建築、統計など関東大震災にまつわる多様な視覚表象から1945年のヒロシマまでを論じた本である。直接の言及はないが、東日本大震災とその復興のことも著者の念頭にはあっただろう。アメリカの中には、日本の美術情報を単に英語化してアメリカを中心とする歴史の中に組み込む、という以上の、知的でアクチュアルな取り組みも確かに存在する。
-


- 「Gutai: Splendid Playground」カタログ/『Imaging Disaster: Tokyo and the Visual Culture of Japan's Great Earthquake of 1923』
再び昨年の海外出張からの話題だが、6月に訪れたロンドンで、印象に残った展覧会の二つを紹介したい。ウェルカム・コレクションという変わった施設で、「SOUZOU: Outsider Art from Japan」という展覧会を見た(2013年3月〜6月)。タイトルは「創造」と「想像」をかけたもので、日本の知的障害者たちによる美術作品を紹介するものだ。「エイブル・アート」とも称されてよく見た作品に再会し、それらがヨーロッパの人々をも楽しませる力があることを確認した。また、ロンドンのヘイワード・ギャラリーでは「ALTERNATIVE GUIDE TO THE UNIVERSE」展を見た(2013年6月〜3月)。これは西洋と中国における同様の美術を紹介するもので、初めて見る刺激的な作品も多かった。こちらでは「self-taught artists」(独学の美術家)といういい方をする。ともあれ、ロンドンで東西のアウトサイダーを合わせて見る幸運に恵まれたわけだ。
この二つを見て、意外なことに気づいた。個人の内面を深く、深く、掘り下げるアウトサイダー・アートには、個人を超えた都市や建築に関する要素が、少なからずある。例えば、「SOUZOU」展に出品された勝部翔太の作品は、ビニール袋などの口をくくるためのカラフルな針金で作った、高さ数センチの小さな戦士の人形を300体ほど並べたものだ。それはまるで少年が夢見る戦士の都市をつくっていて、子どもも大人も見ていて飽きない。他方、「ALTERNATIVE GUIDE」展に出品されたフランスのマルセル・ストー(Marcel Storr)は、紙に色鉛筆で夢の大聖堂を描く。ただそればかり、延々と、繰り返す。その建物はサイケデリックな色彩で、遠近法にも重力にも縛られず、増殖し、結合し、あたかも現代建築の過激な都市計画のような姿へと展開する。アウトサイダーの建築は、精神の災害の後に続く、夢の復興といえるかもしれない。
●A2
今年1月に、かつて『日本近現代美術全史』と呼ばれていた本が、企画から10数年を経て、ついに刊行される。最終的に『美術の日本近現代史─制度・言説・造型』(東京美術)というタイトルになった。北澤憲昭、佐藤道信、森仁史が編集委員となり、「全史」すなわち、歴史の全てではなく、歴史の全体をまとめるものとして、日本の近現代美術史を総括するという試みを行なった。千頁近くの分量で、価格も相当なものだが、美術に関心がある者であれば資料として手元に置いておくべき本であろう。
また、4月には小学館『日本美術全集』の17巻「前衛とモダン」、年明けには同18巻「戦争と美術」が刊行される。紙の美術全集としてはおそらく最後となるものであり、2010年代の美術史家たちがスタンダードとして認める作品を、大きな図版で収録している。
今年は、そのほかの共著にも関わらせていただいている。しかし、これからは自身の研究を深めることにも注力したい。今後の数年間には、拙著『前衛の遺伝子』(ブリュッケ、2012年)のサイド・ストーリー、続編、そしてスピン・オフの番外編、といった本を、書いていくつもりである。もっと大きな視点で、もっと面白いネタを取りあげてみたい。
-

- 『美術の日本近現代史──制度・言説・造型』
あだち・げん
1977年生。美術史家。著書に『前衛の遺伝子 アナキズムから戦後美術へ』(ブリュッケ、2012)。
荏開津広(著述/翻訳)
●A12013年には、僕は3月に高須咲恵、松下徹などと共に展覧会「サイドコア 身体/媒体/グラフィティ」を、また6月にアントナン・ゴルチエ、碓井千鶴などと共に映像フェスティヴァル「オール・ピスト東京」を行いました。前者はグラフィティが内包している問題を現代美術の分野に探る試みで、後者はポンピドゥー・センター発の制約のない映像フェスティヴァルです。これらのプロジェクトと関連して、幾つか印象に残ることをここに記すことで許していただきたいです。
2013年は、アヴァンギャルド映像作家、飯村隆彦の渋谷UPLINKで4月に行われたパフォーマンス[http://www.uplink.co.jp/event/2013/13026/]、空間全体を、映像が生まれる瞬間に人々を立ち会わせる経験に転じた"Circle and Square"で始まり、やはり渋谷のUPLINK で12月の終わりに上映された、パリ郊外にあるル・コルビュジエのサヴォワ邸で撮影された、ヴィデオ・アーティスト河合政之の"IN/OUT"[http://www.uplink.co.jp/event/2013/18778]の、黒人のモデルたちの姿態を驚きながら見つめるまで、映像やグラフィティの展覧会を通して建築や都市、空間について感じることが多い時間でした。
-


- 河合政之 "IN/OUT" (2009, 8min. HDV)
前年、自分が海外のジャーナリストと慌ただしく出かけていった福島県いわき市という場所の森美術館で、竹内公太の見る姿勢を問いただすような、より誠実であろうとする「影を食う光」[http://kota-takeuchi.net/sight_consuming_shadow.html]という個展を見たのもその印象を強めたでしょう。
品川のスタジオ1-8-5 で11月に見たフロリアン・ゴールドマンの「モデリング・カタストロフィ」[http://studio1-8-5.com/2013/11/15/115/]は、大災害を模型化する行為をTVで目撃した彫刻家のリサーチ/作品とも言うべき展示で、同じ作者が著したアテネのグラフィティについての調査に基づいた書籍「Flexible Signposts to Coded Territories」[http://florianichibangoldmann.wordpress.com/2013/07/20/flexible-signposts-to-coded-territories/]と共に刺激を受け勇気づけられました。グラフィティを背景に持つこの作家が、グラフィティを真摯に捉える他の全ての共犯者ともいうべき、作家や批評家、オーガナイザーたちと同様にメディアのストリート・アートを巡る喧伝と離れても仕事を積み上げていこうとしていたからです。その意味で、大山エンリコイサムの自ら描いた壁画をバフしたというNYでのショウを目撃できなかったのは残念でした。
グラフィティと関連したショウで優れて印象に残ったもののなかで「サイドコア 身体/媒体/グラフィティ」にも参加してもらったQPの"個813/9展"(セキルバーグ・カフェ、12月)は圧倒的な体験でしたが、それが美術ではないとしたら、ストリート・スラング以外のどのような言葉がこの作品を記録し、批評!していくのか、と自問せずにはいられず、また同時に勝手な責任感も感じました。
ここまでは作品と言葉について書いたのですが、2013年の始まりから、ここへの寄稿者でもある、建築家/アーティストの松原慈という人物が東京にいない、彼女が主にモロッコの空の下にいることを選んだという事実も大きな出来事でした。
-


- 「個813/9展」チラシ
●A2
ジャーナリスト、キャメロン・マキーンと手がけているグラフィティについての本は今年こそ出したいと思っています。また、サイドコアのメンバーと、もしくはサイドコアから離れて、グラフィティと現代美術が交差する領域での展覧会を手がけたいと考えています。2014年は、目の前の現実と前衛芸術と言葉がフィードバックしていく、その端緒のバグを自ら蒔く──おこがましいですが、そんな年になればと思っています。
●A3
考えていることで、特にここで記すようなことはありません。感慨にもなりようがありませんが、ザハ・ハディッドの卒業制作のカタログがこれを書いているデスクのすぐ横の本棚に置いてあります。意味もなく手に入れたものですが、そのときも、2011年に広州でオペラ・ハウスを見物したときも、彼女がこれほど自分の未来にのしかかってくるとは、まったく思ってもいませんでした。
えがいつ・ひろし
東京在住。ライター/DJ/東京藝術大学、多摩美術大学非常勤講師。著書=『人々の音楽のために』(単著)、翻訳=『サウンド・アート』(共訳)など。エッセイ=「Words Are Pictures」「Art As Punk」「Attempt To Reconfigure Post Graffiti」など。
江渡浩一郎
●A1まず、自分が関わった仕事について紹介する。
磯崎新「都市ソラリス」展
現在、NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で磯崎新「都市ソラリス」展(http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2013/ISOZAKI_Arata_SOLARIS/index_j.html)が開催されている。これは、磯崎新のこれまでの建築や都市計画に関わる資料が展示される展覧会であり、同時にメディア・アーティストとの共同制作による新作も展示されている。
この展覧会に先立つ2月24日(日)の「〈都市〉はアーキテクチャか?」(http://www.ntticc.or.jp/Archive/2013/ICC15/index_j.html)と題するシンポジウムで、私は、磯崎新氏、高山明氏、浅田彰氏、羽藤英二氏とともにパネル登壇した。
建築を意味する「アーキテクチャ」という言葉は、現代ではコンピュータ上のシステムの基本設計を表わす言葉として使われるようになった。この現状を踏まえて、逆に建築におけるアーキテクチャ、さらには建築の集積である都市をアーキテクチャとして捉えることができるのか、というテーマのシンポジウムである。
私は「ニコニコ建築の可能性」と題する発表を行なった。これまで「ニコニコ学会β」というユーザー参加型イヴェントを開催してきたが、それが定常状態として発展し、さらには都市レベルにまで拡大する可能性について検討した。アレグザンダーが指摘するように、都市は長い年月を経て多数の住民が参加することによって、ツリー構造ではなくセミラティス構造を備えるに至る。そのような住民参加、すなわち「ユーザー参加」をより積極的に都市設計に取り込んだ計画として、コンスタント・ニーヴェンホイスによる「ニューバビロン」(1957)が考えられる。しかし、実際にはニューバビロンは都市計画として実現されることはなかった。
では、そのような「ユーザー参加型都市」を現代に実現している事例はあるだろうか。私は「バーニングマン・フェスティバル」がその実例だと思う。バーニングマンは、アメリカ・ネバダ州の砂漠に毎年1週間だけ「ブラックロック・シティ」という架空の都市を作り、そこに約5万人の人が集まるイヴェントである。
「No spectator」(傍観者になるな)がスローガンであり、貨幣経済は禁止され、贈与経済が共同体を成立させている。自己表現が貨幣の代わりとなり、人々は自分自身の創造性をその対価として支払う。絵を描く、彫刻を作る、踊る、唄う、何をやってもいい。そのような自己表現が対価となる世界である。
このような個人の創造的な行為を基盤とした都市が成立する可能性、さらには独立した国家へと発展していく可能性について妄想し、そのような国家の理想像を仮に「ニコニ国家」と名付け、未来の可能性として提示した。
結果として、議論はあまり噛み合わなかった。磯崎氏はまさしく現実の都市計画を主導する都市計画家である。都市計画の基本は治水であり、どこに川や道を引くのかのグランドデザインが起点となる。そのような基本的な都市計画の考え方と、私自身の考えをどのように接続するか、その点を私自身があまり考えていなかったことが原因である。とはいえ、磯崎新氏、浅田彰氏と直接議論させていただいたのは、私としては貴重な経験だった。
この「ニコニコ建築」については、東北大学大学院有志で制作している建築雑誌『ねもは』に関連した『ニコちく──「ニコニコ建築」の幻像学』(http://nicochiku.wordpress.com)という同人誌にインタヴューに答えるかたちで語っている。
そのような磯崎氏の展覧会が、3月2日(日)までの会期でNTT ICCで開催されている。これまでの建築設計の資料とともに、メディア・アーティストとの共同制作による新作を展示しているが、ユーザー参加やインターネットからの情報収集を元に意味のあるランダム性を導入する仕組みであり、《孵化過程》(1962)の続編のようにも思える。理念をそのままストレートに都市計画へと広げたグランドデザインに対して、いかにして実りのある偶然性を導入するかという実験を継続しているように思えて、興味深い。
YCAM10周年記念祭
2013年は、山口情報芸術センター(YCAM)の開館10周年にあたる。この10周年を記念した展覧会「アートと環境の未来・ 山口 YCAM10周年記念祭」(http://10th.ycam.jp)が開催された。私は、国際グループ展「art and collective intelligence」(http://10th.ycam.jp/term1/453/)にて、「collective intelligence・リサーチ・プロジェクト」と題する調査プロジェクトを行なった。
これは、集合知の歴史を概観し、代表的な事例をアイコンとして構成して窓ガラス上にパネル展示するものである。集合知がテーマといっても、いわゆるインターネット上の集合知だけを対象としているわけではない。ヴァネヴァー・ブッシュによる「As We May Think」(1945)を起点とし、コンピュータを知能を拡大するための道具として扱う活動を含んでいる。また、「E.A.T」のようなアーティストと科学者による集団制作も扱っている。多数の人が参加する知的活動総体に関するパースペクティヴを一望しようという「集合知年表」となっている。そのなかでも特に重要なイヴェントを取り上げ、カッティングシートによるアイコンをガラス窓に展示した。同時にiPadによるインタラクティブな仕掛けにより、そのアイコンが表す内容を見られるようにした。私のこれまでの集合知研究を年表という形で振り返ることができ、自分の思考を整理する良い機会となった。
また「LIFE BY MEDIA」(http://10th.ycam.jp/term2/966/)という生活空間をメディアを使って変えるという国際コンペティションの審査員も担当した。6名の審査員(坂本龍一、青木淳、江渡浩一郎、津村耕佑、山崎亮、兼松佳宏)で審査し、最終的に3作品を選んだ。
▷犬飼博士+ 安藤僚子《スポーツタイムマシン》
▷西尾美也《PUBROBE(パブローブ)》
▷深澤孝史《とくいの銀行 山口》
いずれも生活空間をメディアで変容させるというテーマを高いレベルで実現した作品だったが、そのなかでも特に《スポーツタイムマシン》が印象に残った。これは「映像データベースに保存されたさまざまな人々とかけっこで競走できる装置をつくる」というプロジェクトであり、しかもそのデータを保存することによって時空間を越えてさまざまな存在と一緒にかけっこできるようにしている。犬飼氏は「100年後まで残す」という前提で発想しており、その構想自体がすばらしい。犬飼氏はこれまでも日本科学未来館の常設展示物《アナグラのうた──消えた博士と残された装置》(2011)(http://www.miraikan.jp/anagura/)を発表しているが、それと比較しても《スポーツタイムマシン》の完成度は高い。大胆な発想を制約条件の多いなかで実現しており、犬飼氏の実力の高さを感じた。本作品は2013年度文化庁メディア芸術祭の優秀賞(http://j-mediaarts.jp/awards/excellence_award?locale=ja§ion_id=2)に選ばれており、2014年2月に行なわれる文化庁メディア芸術祭で展示されることになっている。
パターンランゲージ関連
2013年はパターンランゲージ関連の書籍に大きな動きがあった。
まず、井庭崇氏による『パターンランゲージ──未来を創る創造的言語』(http://www.amazon.co.jp/dp/4766419871)が出版された。中埜博、竹中平蔵、江渡浩一郎、中西泰人、羽生田栄一らとの対談や鼎談が収められている。私は、井庭氏、中西氏との鼎談に参加している。2011年に行なった鼎談なので、約2年前の私の考えであり、『パターン、Wiki、XP』を出版した2年後の考えでもある。このように自分の考えが少しずつ整理され、発展する様子を自分で辿れるのはありがたい。また、本書は井庭氏による前書きや注釈が充実している。また、中埜博氏による『ネイチャー・オブ・オーダー』の解説が載っており、簡単に全体を掴むためにも有意義である。
アレグザンダーが現在取り組んでいる『生命の現象 (ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質)』(http://www.amazon.co.jp/dp/4306045935)の日本語訳第1巻が出版された。翻訳にあたった中埜博氏の努力の賜物と思う。この本に関してはいろいろな事前情報があったが、実際にざっと読んでみての感想は、思ったよりも理路整然とわかりやすく書いているということ。アレグザンダーの意見に同意するかどうかは別として、『形の合成に関するノート』から連なるデザイン(設計)に関する思想の集大成として有意義だと思う。
そして、その『形の合成に関するノート/都市はツリーではない 』(SD選書)(http://www.amazon.co.jp/dp/430605263X)や、『オレゴン大学の実験』(http://www.amazon.co.jp/dp/4306051285)は長らく絶版になっていたが、2013年に復刊した。拙著『パターン、Wiki、XP』がきっかけとなってアレグザンダー再評価のブームが起こり、それがきっかけとなって再販が進んだと聞いたことがあるが、事実だとしたらこれに勝る喜びはない。また、再販に向けて動いた鹿島出版会をはじめとする関係者の皆様に敬意を表したい。
考えてみれば、2013年はパターンランゲージを日本に紹介した磯崎新氏と議論する機会もあり、パターンランゲージについての思考を深めることができた年だった。
グッドデザイン賞
2013年より、グッドデザイン賞の審査員となった。私の担当領域は生活レベルのインタラクションデザインである。近年は審査対象が多様化し、建築においても、ユーザーを巻き込んだデザイン手法が多数試みられており、そういった分野も含まれている。つまり、意外なことに建築についても多数評価することになった。
審査員になって思ったことは、想像以上に面白いということだ。応募総数が約3000件で受賞が約1000件ということは、受賞しなかった約2000点は表に出ないわけである。審査員はその全体を見ながら審査するわけなので、自ずと結果に対する見方も変わっていった。
ニコニコ学会β
ニコニコ学会βの活動も展開している。2013年4月には「第4回ニコニコ学会β」(http://niconicogakkai.jp/nng4/)を、12月には「第5回ニコニコ学会β」(http://niconicogakkai.jp/nng5/)を開催した。8月には「ニコニコ学会βサマーキャンプ2013」(http://peatix.com/event/15759/view)と、「ニコニコ学会β夏の自由研究」(http://niconicogakkai.jp/info/nng_summer)を実施した。5月には、ニコニコ学会βはアルス・エレクトロニカ賞を受賞し(http://kai-you.net/article/453)、9月には授賞式に出席するためにアルス・エレクトロニカ・フェスティバルに行ってきた。12月には、「月刊ニコニコ学会β」を創刊し、これまでにすでに3号出版している。「月刊ニコニコ学会β 創刊準備号」(http://www.amazon.co.jp/dp/B00GJFDACU)、「月刊ニコニコ学会β 第1号」(http://www.amazon.co.jp/dp/B00HCZJVCO)、「月刊ニコニコ学会β第2号」(http://www.amazon.co.jp/dp/B00I0LKVI2)。その中でも特に第1号ではアルス・エレクトロニカ・フェスティバルの体験記を載せているので、ぜひ読んでみてほしい。
以下、自分が関係していないが、2013年の興味深い作品である。
Port B『東京ヘテロトピア』(構成・演出:高山明)
Port Bによる『東京ヘテロトピア』(http://www.festival-tokyo.jp/program/13/tokyo_heterotopia/)は、劇作家の高山明氏による都市を使った演劇である。アジア各地から東京への留学生がテーマとなっており、留学生の活動とその足跡を辿る旅となっている。舞台装置としては、2012年の『光のないII』(http://www.festival-tokyo.jp/program/12/kein_licht_2/)と同じように、地図とラジオの組み合わせである。受け取ったパンフレットに書かれている地図が示す場所に行ってラジオの周波数を合わせると、物語が聞こえてくるというものである。
私は東京のなかに、これほどアジアからの留学生の足跡が残っているとは知らなかった。たとえば、アウンサンスーチーの父親アウンサン将軍は日本の支援を受けていて、「面田紋次」という日本名を名乗っていた。クーデターを起こしたネウィン将軍は、日本名が「高杉晋」だった。ミャンマー、かつてのビルマと日本の間のつながりがこれほどまでに深いとは、私は知らなかった。
また、カンボジアにポルポト政権があって、そこで大虐殺が起こったことは知っていたが、そのようなカンボジアから難民として日本に移ってきて、東京で「アンコールワット」という店を構えている人がいるとは知らなかった。
また、私は以前文京グリーンコートに勤務していて、そのすぐ横の「アジア文化会館」の食堂「ABK食堂」で、毎日のように地元仕様のランチを食べていた。このアジア文化会館の前身として「新星学寮」があり、今もその建物が残っている。このような深い歴史があるとは知らなかった。
これまでの高山明作品と同じなのは、東京という街を異化して違う風景を見せるところだろう。まさしく「現実の中の異郷=ヘテロトピア」をテーマとしている。今回特に強調されているのは、それが歴史的に作られてきた経緯に着目している点である。アジアでは、上海が魔界都市と言われているが、規模は違うが東京にも同じような意味がある。そのような、アジアの歴史と交差する東京という歴史のなかの位置づけを深く体感することができる演劇作品だった。
また、今回は「フェスティバル/トーキョー」における最後の高山明作品でもある。これまでフェスティバル/トーキョーを支えていたディレクター相馬千秋氏は、2013年度で退任することとなった(http://www.festival-tokyo.jp/news/2013/12/ft-1218.html)。この異動に伴い、2014年度のフェスティバル/トーキョーでは高山明作品は公開されないことになった。相馬氏の退任理由は明らかにされていない。
この6年間フェスティバル/トーキョーを続け、東京の演劇シーンを面白くしてきた相馬氏の努力に敬意を表し、心から感謝したい。相馬さん、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。
ティノ・セーガルが金獅子賞受賞
第55回ヴェネチア・ビエンナーレにて、ティノ・セーガル氏が金獅子賞を受賞した(http://www.tomosha.com/asia/0-1531)。一切の物を残さずに、パフォーマーによって状況を作り上げることで作品とする。このような空間を変容させる作品は今後さらに発展していくことだろう。
Fethno
「Fethno」(http://fethno.jp)は、民族音楽学者 小泉文夫氏の没後30年に際し、彼が現代の音楽界に与えた影響を「再発見」するためのライブ・イヴェントである。アフガニスタン、アイリッシュ、北インド、アイヌなどのさまざまな民族の音楽をその道の第一人者が演奏する。また同時に小泉文夫が辿ってきた足跡を関係者のインタヴューによって振り返る。全ての演奏がすばらしかったが、特にアイリッシュの音楽は胸に響いた。このプロジェクトで特筆すべき点は、全て東京藝大の現役の学部生によって進められた点だ。小泉文夫が撒いた種が、きちんと受け継がれている点がすばらしい。
●A2
私の活動としては、まず2014年4月26日(土)~27日(日)の「ニコニコ超会議3」(http://www.chokaigi.jp)における「第6回ニコニコ学会β」にむけて準備を進めている。私としては、第5回ニコニコ学会βでシンポジウム形式での開催については十分模索できたと考えている。そのため、第6回では、よりユーザーの関与を強める形でシンポジウムやワークショップを構成したいと考えている。
また、パターンランゲージに関わる学会「AsianPLoP2014」(http://patterns- wg.fuka.info.waseda.ac.jp/asianplop/)では、プログラム委員を担当している。このようなパターンランゲージに関する活動を続けることで、少しずつ自分のなかでの知見が深まっていく。大変ありがたい。
ほか、「札幌国際芸術祭2014」(http://www.sapporo-internationalartfestival.jp)は、YCAM10周年記念事業に続き、坂本龍一氏がゲストディレクターをつとめている。文化都市札幌でどのような芸術祭が展開するのか、期待している。「道後オンセナート2014」(http://www.dogoonsenart.com)は、地域振興型の芸術祭として、旅館を巻き込む形で展開しており、興味深い。
●A3
喜ばしいことと考えている。特にデジタル技術の発達という点で、6年後に向けて発展させるための目標が誕生したと考えられる。
えと・こういちろう
1971年生。ニコニコ学会β実行委員長/独立行政法人産業技術総合研究所主任研究員/メディアアーティスト。東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了。博士(情報理工学)。ニコニコ学会βは、グッドデザイン賞、アルス・エレクトロニカ賞を受賞。著書=『パターン、Wiki、XP』『ニコニコ学会βを研究してみた』『進化するアカデミア』など。
太下義之(文化政策/三菱UFJリサーチ&コンサルティング 芸術・文化政策センター 主席研究員)
●A1
2013年で印象に残ったものに関しては、「文学」「演劇」「映画」「漫画」「美術」「音楽」「その他」の七つの分野に分けて回答したい。
[1]文学
東日本大震災以降、柳田国男『遠野物語』があらためて脚光を浴びているようである。『遠野物語』は、赤坂憲雄『3.11から考える「この国のかたち」──東北学を再建する』においても引用されているし、畑中章宏『柳田国男と今和次郎──災害に向き合う民俗学』においては主要なテーマとしてとりあげられている。ちなみに、『遠野物語』が発表されたのは明治43(1910)年6月のことであったので、それから100年と9カ月後に東日本大震災が発生したことになる。
そして昨年(2013年)、小説家の京極夏彦が『遠野物語remix』を発表した。同書は京極の新作小説というわけではなく、オリジナルの『遠野物語』に収録されていた119話のエピソードの順序を並び替えて、新しい『遠野物語』をつくりあげたものである。そして、同書を読むと、「改変」および「語り」という二つの創作手法の重要性にあらためて気づかされる。
上述した通り、『遠野物語remix』は物語の順序を並び替えただけで、テキスト自体にはほとんど手を入れていないのだが、本書全体としてはオリジナルとは異なる魅力を有しているように感じられる。ポピュラー音楽の世界でいえば、プロデューサーが収録曲の順番を入れ替えることで、あるCDがまったく別の作品に再創造されることに相通じるものがある。
そして、この京極による「改変」は、オリジナルとされる柳田国男『遠野物語』自体も、もしかしたらこうした「改変」の産物なのではないか、と読者に気付かせる効果も有している。
たとえば、やはり『遠野物語』をオリジナルとする、井上ひさし『新釈遠野物語』(1976)を読んでみよう。こちらは全篇にわたって、いかにも井上ひさし(または東北)らしい艶笑談で構成されているのだが、オリジナルの『遠野物語』にはじつは艶笑談がほとんど収録されていないことに、ふと気づかされる。
柳田国男は当時の農水省の高級官僚であったので(この事実はあまり知られていないようであるが)、独特のセンサーシップをはたらかせ、あえて艶笑談を削除したのではいなか、などと邪推してみたくなってしまう。そして、井上ひさしは、そのように中央政府的な感性で「改変」された『遠野物語』に対するアンチテーゼの意味を込めて、本来の遠野の物語としてこの『新釈遠野物語』を執筆したのではないだろうか。
さて、もうひとつの重要なポイントは「語り」である。「語り」の魅力の素晴らしさ故に、『遠野物語』は100年たっても色褪せることがない。そして、「語り」と言えば、ノーベル文学賞に一番近い作家・村上春樹の新作『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013)も「語り」の魅力に支えられた物語であった。思い返してみると、村上春樹の作品には印象的な「語り」の場面が多々あり、同じ作家の『ねじまき鳥クロニクル』に登場する間宮徳太郎中尉の「語り」も素晴らしかったし、『ノルウェイの森』にも同書の魅力の根幹をなすかのような「語り」の場面があった。さらにいえば、村上春樹をかつてリスペクトしていた小説家・古川日出男の『聖家族』(2008)も「語り」の文学であり、かつ今から振り返ると、3.11を予感させるかのような物語であった。
そして、「語り」は「騙り」でもある。もしも「騙り」の文学を堪能したいのであれば、宗教学者として世界的に有名なミルチャ・エリアーデの小説『ムントゥリャサ通りで』(1968)が一番のおすすめである。
なお、「文学」に関連するテーマとして、2013年は電子書籍の普及がより加速した年でもあった。電子書籍(e-book)に関しては、JapanTimesの記事に私のコメントが掲載されているので、興味のある方はご参照いただきたい。
「Japan's readers slower to make e-book leap」(JapanTimes、2013年11月18日)
URL=http://www.japantimes.co.jp/news/2013/11/18/reference/japans-readers-slower-to-make-e-book-leap/

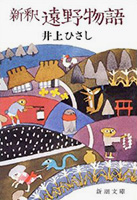
- 『遠野物語remix』/『新釈遠野物語』
[2]演劇
演劇分野に関しては、2013年に上演された舞台をそれなりの本数見ているので、個人的なベスト5(と番外)をあげさせていただきたい。
マームとジプシー『cocoon』(東京芸術劇場シアターイースト)
漫画家・今日マチ子による、沖縄のひめゆり学徒隊をモチーフとした戦争漫画を原作とした作品。特定のセリフを執拗に反復し、さらにそれらをコラージュしていくという手法はこの劇団の最大の特徴であるが、本作に関してはその手法がたんに表現上の前衛的な手法ということではなく、たとえば前半部分における女子高生たちの会話を通じて立ち上がる、戦時下の女子高生たちの日常生活に象徴されるように、まさにこの舞台のために開発された手法であるかのように、物語にピタリとはまっていたように思う。また、昨今の流行となっている映像と舞台のミクスチャーについても、物語とリンクした極めてインパクトのある映像の投影によって、意味のある形で見事にシンクロしていたと思う。そしてなによりも戦争を題材としながらも"敵"を一人も登場させずに、ただひたすらに死んでいくクラスメイトたちの姿を描くことで、戦争の理不尽さと無意味さを描いている点が素晴らしかった。このような新しい感性に、2020年・東京オリンピックの開幕式の演出を委ねてみたい。そんなことを思わせる舞台であった。
テアトル・ド・コンプリシテ『春琴 Shun-kin』(世田谷パブリックシアター)
2008年に初演された舞台で、今回が四演とのことである。そして、初演時と今回では、役者もスタッフも演出もほとんど変化がないとのことであるが、今回の舞台のほうが初演(これも素晴らしい舞台であった)よりも、作品としてさらに進化してよくなっているように感じられた。たとえば、演出家サイモン・マクバーニーお得意の、シンプルな道具を利用した瞬間的な舞台転換であるとか、主演女優と人形とのエロティックな絡みであるとか、物語の朗読の場面と(物語上の)現実の浮気話との交錯であるとか、初演時にも観ていたはずの仕掛けであるが、今回の舞台はあらためて初見のように感動的であった(もっとも、具体的に何がどう違うのかはうまく説明できないのであるが)。こういう不思議な邂逅がたまにあるから、芝居通いが止められない、そんな作品。
勅使川原三郎『春、一夜にして』(シアターⅩ(カイ))
ポーランドのユダヤ人作家・ブルーノ・シュルツのテキスト「春」をモチーフとした作品。勅使川原三郎とシュルツの組み合わせとなると、これは見逃すわけにはいかない。そして本作は、①シュルツのテキストのナレーション入り、②音楽はなし、③照明による演出効果もなし、④とてもスローな振り付け、⑤群舞もなし、と通常の勅使川原三郎の作品とはまったく異なる作品に仕上げられていた。勅使川原三郎の作品というと、スピード感がある独特の振り付けを期待してしまうが、むしろ本作のように音楽がないなかで異形の踊りを鑑賞するほうが、勅使川原三郎に独特の動きをじっくりと理解することができる。ラストで顔に巻きつけていたテープのようなものをはぎ取っていくという演劇的な演出がとても印象的な作品であった。
クロード・レジ『室内』(静岡県舞台芸術センター)
演出のクロード・レジは御年90歳を超えるフランス演劇界の巨匠。もっとも、来日したご本人の外見はとても若々しく、せいぜい60歳代にしか見えない。そして、本作を見て、いまから30年以上も前、1982年に開催された 第1回世界演劇祭「利賀フェスティバル」のことを思い出した。この演劇祭(特に寺山修司が参加した第1回)は日本と世界から当時の演劇の最前衛が終結した素晴らしいフェスティバルであったが、このなかに、ロバート・ウィルソンの『つんぼの視線』と太田省吾の『小町風伝』があった。そして、『室内』も、そして『つんぼの視線』と『小町風伝』にもみな共通しているのは、超スローな動きが続いていき、そしてある瞬間で突然に動作が早まるという転換が出現する点である。また、本作において、違和感をそのまま観客に投げつけるかのような演者の独特なセリフ術は、かつての転位21を想起させた。とても静謐で緊張感あふれる、素晴らしい舞台。
リミニ・プロトコル『100%トーキョー』(東京芸術劇場)
フェスティバル/トーキョーの常連、リミニ・プロトコルの日本での第四弾。日本初紹介の『ムネモ・パーク』では鉄道模型を舞台とし、続く『資本論』ではあの有名な書籍をテーマに、さらに『Cargo Tokyo-Yokohama』においては東京から横浜に移動する特製トラックでの上演という、常に意外性を追求してきたプロジェクトの新作。本作では、東京23区に住む約900万人の属性(性別、年齢、住所、外国人)の比率を元に抽出された100人の出演者が、次々と繰り出される質問にYesかNoで回答していくという構成となっている。そして、こうした展開が繰り返されていく過程で、われわれ観客はいつしかこの舞台上の100人がわれわれの代表サンプルであるかのように錯覚していくことになる。そして、穏当な質問のなかに、たとえば「憲法九条」「天皇制」「家族を守るために人を殺すことができるか」といった極めてセンシティブな質問が紛れて出されるのである。そして、それらの質問に対する回答のなかには、意外な回答のバランスもあり、そうした回答状況に反応(反発)することによって、観客は自分自身の思想や信条の偏りを再確認することになるのである。一種の社会実験としてじつに興味深い舞台であった。
番外:寺山修司
昨年(2013年)は、寺山修司没後30年という節目の年でもあった。そして、なかでも印象的な舞台であったのが、維新派の松本雄吉が演出した『レミング』(パルコ劇場)と、天井桟敷の遺児・J・A・シーザーが演出した『邪宗門』(座・高円寺)の2件であった。
『レミング』は、一言でいえば維新派の新作のような舞台であり、ヂャンヂャンオペラ風の台詞の繰り返しにより、寺山修司のテキストが(天井桟敷の舞台よりも)リリカルに響いていたことが新鮮な発見であった。もっとも、この『レミング』を寺山演劇を継承する作品として受容できた観客は少なかったのではないだろうか。
もう一方の『邪宗門』は、マッチの炎が燃えている間の一気呵成のセリフ術や、痙攣のように飛び跳ねる演技、シーザー自身による秘教的なロックなど、上述した『レミング』とは対照的に、かつての天井桟敷の演出が伝統芸能のように継承されている点が印象的な舞台であった。
どちらの作品とも見応えがある舞台であったが、見終わっての感想は何かしら不完全燃焼のような気分が残ったことも確かである。そもそも寺山修司の作品とは、そのアウトプット自体に価値があるのではなく、それを体験した観客がまるで疫病にでも感染してしまうかのように、その後の行動や思想を変質させてしまうという、そのような派生的な構造にこそ本質があるのではなかったか。そんなことを考えた寺山没後30年の舞台であった。
-





- マームとジプシー『cocoon』/テアトル・ド・コンプリシテ『春琴 Shun-kin』/勅使川原三郎『春、一夜にして』/『レミング』/『邪宗門』
[3]映画
2013年は映画館で多くの映画を鑑賞したのだが、そのほとんどが旧作であったので、じつは新作はあまり鑑賞していない。そんな数少ないなかではあるが、海外出張のフライト中に鑑賞した怪獣映画『パシフィック・リム』はとても面白かった。本作はメキシコ出身のギレルモ・デル・トロ監督によるものであるが、このデル・トロは、スペイン・カタルーニャ地方を舞台としたダーク・ファンタジーの名作『パンズ・ラビリンス』の監督である。そして、怪獣と怪獣映画を愛するデル・トロ監督は、『パシフィック・リム』において、英語のmonsterではなく、kaiju(怪獣)という日本語をそのまま使用している。さらに、デル・トロ監督は、怪獣を巡る三つの謎に対して自分なりの答えを本作のなかで用意している。その「三つの謎」とは、「怪獣が生物であるとすると、なぜ個体でしか登場とないのか?(同じ形態の生物が多数登場しても良いのではないか?)」「(宇宙または地中から登場するものを除いて)なぜ多くの怪獣は海から出現するのか?」、そして「なぜ怪獣は都市と人間を襲うのか?」である。その謎解きの合理性(および好き嫌い)はともかく、怪獣の骨や臓器の売買でしこたま儲けている怪しいブローカーとその拠点が存在する怪獣の骨で構成された街や、怪獣オタクの研究者が怪獣の脳とシンクロする様子など、怪獣を愛してやまないデル・トロ監督ならではのストーリー展開とキャラクター設定が楽しめる一作である。
なお、その他の映画としては、東京フィルメックスで上映された『ハーモニーレッスン』が素晴らしかった。なお、本作は日本国内ではあまり上映される機会のないカザフスタンの映画であった。
- Pacific Rim - HD Trailer - Official Warner Bros. UK
[4]漫画
本とコミックの情報誌『ダ・ヴィンチ』の2013年「コミックランキング部門」にて№1に見事輝いたのが、諌山創の『進撃の巨人』である。本作については、ヤフー・ニュースにコメントしているので、そちらをご参照いただきたい。
「大人気の『進撃の巨人』 その魅力とは?」(THE PAGE、2013年8月12日)
URL=http://thepage.jp/detail/20130812-00010002-wordleaf
なお、都市と漫画の関係について付言すると、新潟市において「マンガ・アニメを活用したまちづくり構想 検討委員会」(私が委員長を務めました)での提言に基づいて、「新潟市マンガ・アニメ情報館」が2013年5月に開館しており、その入館者数が年間目標(7万人)を超える勢いとなっている。
[5]美術
美術(展覧会)分野に関しても、2013年に開催された展覧会のうち、個人的なベスト5(と番外)をあげさせていただきたい。
瀬戸内国際芸術祭2013
「瀬戸内国際芸術祭2013」においてもっとも主要なサイトのひとつである直島は、《ベネッセハウス・ミュージアム棟》(1992)に始まり、《ベネッセハウス・オーバル》(1995)、《家プロジェクト・南寺》(1999)、《地中美術館》(2004)、《ベネッセハウス・パーク》(2006)、《ベネッセハウス・ピーチ》(2006)、《李禹煥美術館》(2010)、そして極め付きに安藤忠雄自身のミュージアム《ANDO MUSEUM》(2013)と、安藤建築の聖地として進化し続けている姿がじつに印象的であった。
また、アーティスト・内藤礼と建築家・西沢立衛による《豊島美術館》は、前回「瀬戸内国際芸術祭」の閉幕間際に開館したため、タイミングが合わず見逃していたものを今回ようやく初体験できた。美術館と一体となった作品「母型」は、まるで卵の内部のように乳白色に包まれた空間の中で、床の小さな孔から水が湧き出ており、それが緩やかな傾斜に沿って徐々に合流していくという、ただそれだけのアートであるが、これらの動きを見つめていると、これらが生命の営みそのもののように感じられてくる。アーティスト・内藤礼は本物の天才だと実感。この作品と空間を体験するというそのためだけでも、瀬戸内海の豊島に行く価値がある。
十和田奥入瀬芸術祭
この芸術祭で特筆すべきは、《水産保養所》という作品である。廃墟となっていた元宿泊施設「湯治の宿おいらせ」を、梅田哲也、志賀理江子、コンタクトゴンゾという3組のアーティストが、廃墟そのものをひとつの作品として生まれ変わらせた。
ある場所や空間が、そこにアーティストやクリエーターが参加して手を加えることにより、元々とはまったく別の意味を持ちうるのだということをこの「作品」は立証したのだと思う。
「極限芸術──死刑囚の表現」(鞆の浦ミュージアム)
『崖の上のポニョ』(2008)で、宮崎駿監督が構想を練った地として有名な鞆の浦に立地する、アール・ブリュット(障がい者や専門的な美術教育を受けていない人による表現)を紹介するミュージアムで、築150年の蔵をコンバージョンした施設。
この鞆の浦ミュージアムで開催されていたのは、死刑囚たちの作品。たとえば、和歌山毒物カレー事件で死刑が確定した林眞須美死刑囚の作品「国家と殺人」や「四面楚歌」は単純な抽象画であるが、作者の置かれている状況を勘案すると大へん意味深長である。また、埼玉愛犬家連続殺人事件の風間博子死刑囚の作品《無実という希望 潔白の罪》を見ると、この人は本当のところ無実なのではないかと思わせる迫力がある。さらに、大牟田一家4人殺害事件の北村孝紘死刑囚の《自画生首図》は自分が死刑執行される場面を描いているが、ひたすらリアルで不気味である。その他、音音(ねおん、筆名)の《左眼の愁い》は、美術館に展示されているシュールレアリズムの作品と比較しても遜色がない出来栄えである。この大胆な企画に賛辞を送りたい。
ソフィ・カル「最後のとき/最初のとき」(原美術館)
イスタンブールの失明した人々を取材した写真(とテキスト)《最後に見たもの》(2010)と、初めて海を見る人々の表情をとらえた映像作品《海を見る》(2011)の2部構成による展覧会。
このうち《最後に見たもの》は、タイトル通り、失明した人々が最後に見たものや眼が見えていた頃の記憶について語る言葉を、彼らの写真とともに展示するという作品。特に印象的なものは、マフィアの一員に両目を銃で撃たれたタクシー運転手の語る《盲目の人とリボルバー》や、医療ミスによって視力を失ってしまった《盲目の人とマイクロバス》、そして自分の夫がいつまでも(最後に見た)39歳のままのイメージとして残るという《盲目の人と夫》などの作品である。2014年は、記憶とその表現としてのアートについて考えてみるつもりであるが、私にとってその契機となった展覧会。
「つくることが生きること」東日本大震災復興支援プロジェクト展(3331)
2012年に開催された同名の展覧会は、「アートでもとにかく何かをやらないと」という意気込みとそれゆえの表現としての未完成さが同居していたが、震災から2年が経ち、アートによる復興プロジェクトも全体として成熟さと落ち着きを見せ始めているように感じた。
畠山直哉《気仙川》および《陸前高田》にて、写真家によって切り取られた被災地の風景にはもはや震災の生々しさや悲惨さが直接投影されているわけではないのだが、なにか特別な聖痕(スティグマ)の付けられた土地ように感じられ、観客は目を逸らすことができない。
その他、震災のガレキを使って子どもたちとオブジェをつくるという《ワタノハスマイル》や、漁船に企業のロゴを貼り付けるスポンサーシップによって漁業の復興を目指そうという《ADBOAT PROJECT》などが印象的であった。
番外:欧州文化首都。コシツェ(スロバキア)とマルセイユ(フランス)
2013年は、「欧州文化首都」という文化イベントを開催していた、コシツェ(スロバキア)、マルセイユ(フランス)の2都市を自主研究のために訪問した。この「欧州文化首都(European Capital of Culture)」とは、EU加盟国の2都市が協力しつつ(当初は1都市)、一年間を通じてさまざまな芸術文化に関する行事を開催する、という制度である。詳しくは、以下の小文をご参照いただきたい。
太下義之「『東アジア文化都市』と『欧州文化首都』」(2013)
URL=http://www.murc.jp/thinktank/rc/column/search_now/sn130528
「欧州文化首都」は単なる文化イベントではなく、「都市が変化するための触媒」「都市の長期的文化発展戦略」などとも言われている。たとえば、マルセイユの場合、2013年の欧州文化首都に合わせて建設あるいは改修した文化施設は60以上もあり、その投資総額は6億8,100万ユーロにものぼっている。なかでも、フランスの建築家ルディ・リッチオッティ(Rudy Ricciotti)の設計による《欧州地中海文明博物館(MuCEM: Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée)》や隈研吾の設計による《PACA地域圏現代美術基金センター(FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur》は、その代表事例であろう。2014年は前半のうちに、この欧州文化首都についてのレポートをまとめたいと考えている。
-




- 瀬戸内国際芸術祭2013/十和田奥入瀬芸術祭/極限芸術──死刑囚の表現/つくることが生きること
[6]音楽
2013年は、3月には初音ミクの人気曲「千本桜」がミュージカル化、4月には美術展「LOVE展」でミクが展示され、8月にはライブフェス「サマーソニック」にも出演。11月にはミクが主演するオペラ『THE END』が仏パリで遠征公演されるなど、「初音ミク」のメディアミックスが加速した1年だったといえる。
この「初音ミク」については、ヤフー・ニュースにコメントしているので、関心のある方はご参照いただきたい。
「初音ミクの人気の理由と未来」(THE PAGE、2014年1月5日)
URL=http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140105-00000005-wordleaf-cul
[7]その他
その他、2013年で印象に残ったものとして、文化芸術の分野ではないが、異次元的なクリエイティビティという点で、Googleをあげておきたい。Googleの活動は近年さまざまな分野にわたってきているが、そのなかでも特に自動運転車のプロジェクトは、もしかしたら都市や建築というものを根源から再構築する起爆剤となるのかもしれないと考えている。もしも、このようなテーマに関心があるのであれば、私がGoogleについて書いた長めのエッセイをぜひご参照いただきたい。
太下義之「Googleのゴールは何か?──"異次元イノベーション"に関する考察」(『季刊 政策・経営研究』vol.3、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2013)
URL=http://www.murc.jp/thinktank/rc/quarterly/quarterly_detail/201303_01
●A2
2014年で関心のあるアート関連のプロジェクトについては、二つのアート・イベントとひとつの法律の計3点をあげたい。ちなみに「二つのイベント」とは、「ヨコハマトリエンナーレ2014」と「札幌国際芸術祭2014」のことであり、また、「ひとつの法律」とは、「デジタルアーカイブ振興法」(仮称)のことである。
これらの点についても、ヤフー・ニュースの取材にコメントしているので、関心のある方はご参照いただきたい。
「2014年は『東アジア文化』元年? デジタルアーカイブ推進の法整備も」(THE PAGE、2014年1月4日)
URL=http://thepage.jp/detail/20140104-00000003-wordleaf
●A3
2020年の東京オリンピックに関して、じつのところ私は、結果としてリオ・デ・ジャネイロの開催に決定した2016年のオリンピックの招致の時点(概ね2007年ころ)から今回の2020年の招致まで、文化プログラムの面で関わっていた。そこで、このオリンピックに関しては、自分の専門分野である文化政策の視点から、日本ではまだほとんど語られていない三つの点を指摘しておきたい。
第一は、オリンピックはたんにスポーツの祭典だけではなく、文化の祭典でもあるという点である。じつは、オリンピックの提唱者であるクーベルタン男爵の理念(オリンピズム)にのっとって、文化とスポーツ、その両方がオリンピックにおいては非常に大事であるとされている。そこで、国際オリンピック委員会はオリンピックの開催にあたって、オリンピック精神の普及を目指す観点から、スポーツ競技と同時に文化や芸術を通じた国際交流「文化プログラム」を重要なテーマとして開催国に義務付けているのである。
第二点目は、2020年のオリンピックは東京の話だと思っている方が多いかもしれないが、オリンピックの文化プログラムは東京だけではなく、全国で開催されるという点である。実際に2012年に開催されたロンドン・オリンピックでは、全英を12のブロックに分けて、各ブロックのイニシアチブで、イギリス全土でオリンピックムーブメントを盛り上げる文化プログラムが行われた。しかもそれは基本的には公募で、アーティストが主導するアイデアを実現するという「Artist taking the Lead」という、アーティストに主導権を委ねるのだというコンセプトで行なわれた非常に大規模な文化プログラムであった。
もちろん、東京オリンピックはロンドンのまねをする必要はないのであるが、2020年の東京オリンピックの開催にあたっては、東京だけでなく全国で文化的なプログラムが行なわれるということが期待される。
それから三点目が、「そうは言っても,2020年はいまから7年後でずいぶん先の話ですね」というふうに思われるかもしれないが、オリンピックの文化プログラムは2020年だけではなく、2016年から開始されるという点である。オリンピックの文化プログラムは、開催に向けて4年間ずっと続けるものであり、具体的に言うと、2016年に開催されるリオ・デ・ジャネイロのオリンピックの閉幕式Hand over Ceremonyが行なわれた瞬間から、2020年に向けての文化プログラムが開始されるのである。別の言い方をすると、いわゆるスポーツの祭典としてのオリンピックは、4年に1回、世界のどこかで開かれるという性質のものであるが、文化プログラムに関しては、つねに世界のどこかで実施されているのである。
いまから2年後の2016年、リオ・デ・ジャネイロ五輪が終わって直ちに文化プログラムを始めるために、準備期間はじつは余りない。すぐにでも動き出す必要がある。その意味では、2014年は、2020年へ向けての文化政策が本格的に検討され始める元年になるであろう。
おおした・よしゆき
1962年生まれ。三菱UFJリサーチ&コンサルティング 芸術・文化政策センター主席研究員/センター長。文化経済学会〈日本〉理事。文化政策学会理事。文化審議会文化政策部会委員、東京芸術文化評議会専門委員。大阪府・大阪市特別参与、沖縄文化活性化・創造発信支援事業評議員、鶴岡市食文化創造都市アドバイザー、企業メセナ協議会監事。文化情報の整備と活用100人委員会委員。著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム発起人。
大向一輝(情報学/国立情報学研究所准教授)
●A1
ウェブ上で再利用性の高いデータを公開する「オープンデータ」の動きは、政府・自治体などの公共機関から企業、そして芸術・文化領域まで広がりつつある。この分野のオープンデータも、目録や所蔵品のメタデータのレベルから、EUの文化遺産ポータルEuropeanaのようにデジタル化された書籍・絵画・写真データそのものを利用できるようにしたり★1、スミソニアン博物館による所蔵品の3Dデータ公開など★2、1次情報に及んでいる。
国内では昨年末に東京藝大で行なわれたイベント★3で、芸術・文化情報におけるデータのオープン化が研究・教育やビジネス、そして制作者個人の感情に至るまでどのような影響を及ぼすのかについて濃密な議論が行なわれた。多くの識者が指摘するように、ナイーブかつ全面的なオープン化を行なうだけでは長期的なエコシステムが構築できない。しかしながら、アテンション・エコノミーのなかで可視化されない情報はアーカイブの対象にもならないという現実のなかで、守られるべき情報の価値を見定め、そのためのアーキテクチャの設計が必要であることが再認識された。一方で、制作者や所蔵者自らが情報を開いていくことも重要である。OpenGLAM★4など、技術コミュニティとの連携によるオープン化の活動は今後も注目していきたい。

- 「芸術・文化情報とオープンデータ」(2013)
★1──Linked Open Data - data.europeana.eu
URL=http://pro.europeana.eu/web/guest/linked-open-data
★2──Smithsonian X 3D
URL=http://3d.si.edu
★3──シンポジウム「芸術・文化情報とオープンデータ」(東京藝術大学、2013年11月28日)
URL=http://arcir.geidai.ac.jp/62
★4──OpenGLAM
URL=http://openglam.org
●A2
2014年はティム・バーナーズ=リーがウェブを提案して25年目にあたる★5。1人の設計者によって生み出されたものがこれほどの短期間に世界を変えた例は他にないだろう。ウェブのトレンドは日々変わっていくものだが、節目の年にあらためてウェブとは何であったのかについて考えたい。幸いにしてティム・バーナーズ=リー本人がウェブの初期の歴史を綴った『Webの創成』★6が発刊されているものの、残念ながら日本語訳は絶版状態にある。これを何らかのかたちで再び読むことができるよう、有志で活動しているところである。

- 『Webの創成』(2001)
★5──Tim Berners-Lee's proposal
URL=http://info.cern.ch/Proposal.html
★6──ティム・バーナーズ=リー『Webの創成──World Wide Webはいかにして生まれどこに向かうのか』(高橋徹 訳、毎日コミュニケーションズ、2001)
URL=http://www.amazon.co.jp/dp/4839902879
●A3
流行語にもなってしまった「おもてなし」を、どのように実装するかについて考えている。国力の低下が叫ばれるなかにあっても、個々のサービスやファシリティの品質は依然として高く、それを磨き上げていきさえすれば自然と達成されるという見方もあるだろう。一方で、単体としてのクオリティが高ければ高いほど、それらのつながりの悪さが目につくようになってきてもいる。Uber★7やAirbnb★8といった海外の優良サービスはおしなべてユーザエクスペリエンスを競争力の源泉としているが、それらを仔細に見れば一連の動作と動作のあいだにあるつながりにこそ気が配られていることがわかる。都市レベルでつながりをデザインするためにはサービス・ファシリティを作り出す人々のあいだ、いわば他者同士の対話が必須である。コミュニティの創出や教育など課題は多いものの、2020年にはなめらかな都市として選手や観客を歓待したい。
★5──Uber
URL=https://www.uber.com
★6──Airbnb
URL=https://www.airbnb.jp
おおむかい・いっき
1977年京都生まれ。国立情報学研究所准教授、グルコース取締役。博士(情報学)。著書=『ウェブがわかる本』。
大山エンリコイサム(美術家)
表現の空間のために──アブデスメッドからクロックタワーまで
●A1
レーニンの肖像を描いて破壊されたディエゴ・リベラの壁画《十字路の人物(Man at the Crossroads)》(ニューヨーク・ロックフェラーセンター、1933)や、89年に自主撤去を余儀なくされたリチャード・セラの《傾いた弧(Tilted Arc)》(ニューヨーク・フェデラルプラザ、1981)など、美術史上でパブリックアート撤去の先例は散見されるが、2013年はとくに公共彫刻にとっての厄年だったようだ。まずはこれについてざっくばらんに振り返りたい。
サッカー選手・ジダンの有名な頭突きをモチーフにしたアデル・アブデスメッドの《頭突き(Coup de tête)》(ドーハ、10月)、カエルに対する少年の好奇心や恐れを表現したというチャールズ・レイの《蛙を持つ少年(Boy with Frog)》(ヴェネツィア、5月)、サッカーチーム、フラムの本拠地クレイヴン・コテージにサポーターの不満を無視して置かれたマイケル・ジャクソン像(ロンドン、9月)、ルネッサンスの傑作に「下着をはかせてほしい」という苦情で海外からも注目されたミケランジェロのダビデ像レプリカ(島根県奥出雲町、2月)、そして、政府への怒りから市民に引きずり倒されたウラジミール・レーニン像(キエフ、12月)......など、撤去や破壊の憂き目にあった公共彫刻は去年だけでざっとこれだけある。一見それほど共通点がない各事例だが、通して眺めてみると意外に興味深い。
- アデル・アブデスメッドの撤去されるジダン像
引用出典=HUFFINGTONPOST LIVE
たとえば、《Boy with Frog》と奥出雲町のダビデ像は、前者が着色された鉄製の少年、後者が大理石製の屈強な青年と異なるものの、男性の白く古典的な裸体像であるという点で、外見として遠い印象はさほどない。だが、撤去理由はある意味で対称的だ。イタリアの歴史的芸術に囲まれたヴェネツィア住人は裸体像など見慣れているはずだが「(現代アートは)伝統的景観を損なう」ため(観光客には人気があった)《Boy with Frog》の撤去を要求し、そのイタリアが伝統的に誇るルネッサンスの代名詞・ダビデ像は「裸体が不謹慎」と奥出雲町民からクレームを受ける(撤去されたかは不明)★1。
なにが伝統に属し、なにが景観として適切かをめぐる判断は当事者とその慣習に依拠するということだが、その際に当のオブジェクトが与える実際の視覚的印象はさほど問題ではないのかもしれない。なお「裸体に下着を」という発想は、1897(明治30)年の第二回白馬会展に出品された黒田清輝の裸体画《智・感・情》が、当時公開にあたり特別室を設けられ、また下半身を布で覆って展示されたという逸話を想起させる。

- チャールズ・レイ《Boy With Frog》
引用出典=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles-Ray-Boy-with-frog.jpg
★1──島根県奥出雲町のダビデ像については下記を参照のこと。
「Japan town demands pants for Michelangelo's David」(The Straits Times, Asia Report、2013年2月6日)
URL=http://www.stasiareport.com/the-big-story/asia-report/japan/story/japan-town-demands-pants-michelangelos-david-20130206
他方で、ダビデ像と同じ5メートルの背丈となるアブデスメッドのジダン像撤去は当初、ジダン本人の圧力が働いた可能性についてアブデスメッド側が抗議をしていると報じられていた(カタールは2022年のサッカー・ワールド杯のホスト国であるため、国側の政治的配慮があったという指摘もある)。だが本稿執筆にあたり調べ直したところ、現在は「偶像崇拝禁止の教えに背く」という保守派ムスリム教徒たちの反対によって撤去されたという報道に変わっている。
その真偽は置くにしても、たしかにジダンの頭突きは、世界の現状を象徴するモチーフのひとつかもしれない。しばしばスポーツは「ルールを知らないと見方がわからない」ということから現代アートの難解さを説明するメタファとなるが、ワールド杯決勝の大舞台で、その「ルール」を突きやぶって生起してしまったこのスキャンダラスな「逸脱」は、アルジェリア系フランス人のジダンに対する相手選手の差別発言が原因であるという説も示すように、グローバル化する世界において前景化するミクロ/マクロなエスニシティ間の摩擦が、それを制御しようとする国際政治のシステムに抗って噴出する瞬間に準えることもできなくはない。
さらにその決定的瞬間を、同じアルジェリア出身でフランスを拠点にするアブデスメッドが彫刻にし、その作品をアルジェリアと同じイスラム文化圏であるカタールの文化政策事業(Qatar Museum Authority)が購入したという経緯を考えれば、一連の出来事から、複雑化するエスニシティやネーションの問題とそこに並走する今日の文化戦争(スポーツもアートも文化戦争だ)の生々しい姿が透けて見えてくる。
これら重層的なコンテクストをひとつの彫刻に宿したアブデスメッドの手腕は評価すべきだが、完成度の高さも、偶像的な力を危険視された一因ということだろうか。
さて、2011年にオーナーの個人的趣味で設置されたというクレイヴン・コテージのマイケル・ジャクソン像は、同じサッカー関連というよりも、むしろその偶像性でドーハのジダン像に似たところがある。ただし、それはキッチュな偶像だ。パブリックアートではないが、ジェフ・クーンズがかつてマイケルをモチーフにした彫刻作品《マイケル・ジャクソンとバブルス(Michael Jackson and Bubbles)》(1988)を制作したことを思い出そう。消費社会のポップネスとマス・メディアのイメージ再生産によって形成された、時代のアイドル(=偶像)としてのマイケル・ジャクソンである。
だがそのキッチュなアメリカ的偶像は、ロンドンのサッカー・ファンにとって(危険なのではなく)たんに不快なのである。そして不快なものを、彼らにとって神聖な空間であるスタジアムに一方的に設置されれば、怒りを買うのは自然なことである。この心性は、ヴェネツィアや奥出雲町の住人にも重なるが、異なるのは、その過激な熱狂性で知られるブリティッシュ・フーリガンを特徴づけるのは、ときに宗教性を帯びるようなチームへの「信仰心」であり、必ずしも単純に景観や風紀の問題ではないということだ。その意味ではむしろ、規模こそ違うものの、2010年に村上隆がベルサイユ宮殿で展覧会を開催したおり、地元の右翼系団体が抗議のデモをしたケースに近いと言えるかもしれない。

- クレイヴン・コテージのマイケル・ジャクソン像
©Abi Skipp

- ジェフ・クーンズ《Michael Jackson and Bubbles》(1988)
引用出典=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Jackson_et_Bubbles_de_Jeff_Koons_%28Versailles%29_%282973994306%29.jpg
ただ、偶像に対する熱狂がもっとも過激に表出したのは、言うまでもなくキエフでのレーニン像倒壊だろう。もちろん、それは「怒り」の感情が生む熱狂だ。ウクライナがソ連の構成共和国だった1946年に建立されたこの像は、91年の独立時にもその撤去を免れ、清算し切れない過去の遺物であるかのように残存しつづけた。その倒壊はまさに歴史的なインパクトをもっており、ほかの事例とは一線を画す。
一方で印象に残ったのは、この事件については多くのメディア報道が映像をともなっていたことだ。それは本件が、公共彫刻という「静物(の撤去)」についてではなく(それならば静止画で間に合う)、その倒壊、つまり「静物」が「倒れる=動く」瞬間に関するものであるからだと考えたい。ジダン像と比較するならば、アブデスメッドは時間軸のなかに生じた頭突きの一瞬を彫刻へと封じ込め静物化したのに対し、レーニン像は、それが台座から倒れ落ちる数秒をもって映像という時間軸のなかへ放出され、そのイメージは未来派的な運動のつらなりとして残像化していく。ここで公共彫刻は、破壊と同時に映像という別のメディアへと再登録されているのかもしれない。
- 破壊されるキエフのレーニン像
引用出典=「Icon-o-clash: Ukrainian protesters topple statue of Lenin in Kiev」(World News on NBC NEWS.com、2013年12月8日)
この話題についてもうひとつ記しておきたいのは、「撤去」は別の視点からすると「動産化」でもあるということだ。
クレイヴン・コテージから撤去されたマイケル・ジャクソン像はスタジアムの前オーナーに返却され、10月時点の報道によれば、オークションにかけられ売り上げは慈善事業に寄付される予定という。このエピソードは、2013年2月と7月に、ロンドンにあったバンクシーのストリートアートが何者かに壁ごと持ち去られ、その後オークションにて高額で落札されたというニュースを直ちに連想させる。
このバンクシー現象はそれ自体、これからのストリートアートのあり方について示唆に富むものだが、それ以上に、より広いコンテクストにおいてアート全般が直面している市場主義のリスクがそこにあるかもしれない。周知の通り、美術品の動産化は歴史的にもマーケットの論理と密接に結びついている。不動産であるはずのパブリックアートをも飲み込む資本の欲望は、どこに向かおうというのか。
- 持ち去られたあと、オークションに登場したバンクシーのストリートアート
引用出典=Banksy Mural Ripped Off(NowThis News、2013年2月19日)
URL=http://www.nowthisnews.com/news/banksy-mural-ripped-off
●A2
しかしどうやら、資本の欲望に襲われているのは、公共彫刻だけではなさそうだ。つぎに、ストリートアートの話題から広げて触れておきたいのは、ニューヨークで合法グラフィティのメッカとして知られるクイーンズ区ロング・アイランド・シティのファイブ・ポインツ・エアロゾル・アートセンターが、11月19日の早朝、見るも無残に白く塗り潰された件だ。ファイブ・ポインツの取り壊しは以前から噂されていたが、ロング・アイランド・シティでも近年顕著であった地価高騰とジェントリフィケーションの波を受け、建物のオーナーであったジェリー・ウォルコフはいよいよ正式に新しいコンドミニアム(高級分譲マンション)の建設を決めた。ウォルコフ曰く、グラフィティのかいてある壁面をそのまま壊すのは「心が痛む」ので、事前に一度白く塗りつぶしたという。
ここには、公共彫刻の撤去とはまた異なるかたちで、都市空間における芸術のあり方をめぐるクリティカルな状況を見て取ることができる。つまり、ユニークでオルタナティヴな芸術のための自律的な場が、それもとくに貴重なもののうちのいくつかが、2013年に閉鎖に追い込まれたか、あるいは現在その危機に直面しているのだ。
- ファイブ・ポインツ・エアロゾル・アートセンター
筆者撮影
ニューヨークではさらに、歴史的なオルタナティヴ・アートスペースであるクロックタワー・ギャラリーの移転騒動があった。クロックタワーは、ファイブ・ポインツの斜め前にあるMoMA PS1の前身P.S.1 コンテンポラリー・アートセンターの創立者としても著名なアラナ・ハイスによって、1972年にマンハッタン南部トライベッカに開設された世界最初のオルタナティヴ・アートスペースのひとつだが、2013年の11月を最後に、40年以上の歴史を紡いだビルを離れ、ブルックリンのレッドフック地区へ本拠地を移動した。ニューヨーク市の所有物であったビルが、デベロッパーに売却されたためだ。
筆者自身、13年5〜7月に約6週間、クロックタワーのレジデンシープログラムに参加した経験から、この場所が生んださまざまな伝統、人的ネットワーク、そして歴史的手触りとしか言いようのないものを肌身に受け取っていただけに、なにか大きなものの喪失を感じる。やはり「場」に蓄積された膨大な時間は、代替の効かないものだ。ただ、組織としてのクロックタワーは今後も継続され、先述のようにレッドフックの新拠点を中心に新たな展開を目論んでいるとのことなので、いまはその続報を待ちたい。
日本でも、2001年より造形作家の岡崎乾二郎がディレクターを務める四谷アート・ステュディウムの閉校問題が注視されている(本稿執筆時現在)。現場でアクチュアルに活動するアーティストや批評家を多数輩出した本校は、近畿大学国際人文科学研究所というインスティテューショナルな別称にもかかわらず、きわめて個性的で先進的なカリキュラムをもつオルタナティヴな教育施設として、多くの美術関係者がリスペクトしてきた。それを反映するかのように、近畿大学側からの一方的な閉校通知に対し抗議するさまざまなアクションがすでに起こっている(そのひとつが、在学生有志が運営する「四谷アート・ステュディウム存続へ向けて」というウェブサイトだ)。いまだ決着を見ない本件については、引き続き状況を見守っていきたい。
最後に、より個人的な思いからつけ加えたいのは、筆者の学生時代の恩師である東京藝術大学先端芸術表現科教授・木幡和枝氏の退職と、それにともなう木幡研究室の解散である。木幡研究室は、筆者個人にとって重要な成長の場であったのみならず、大学の一研究室でありながら、所属学生に留まらない学内外からの有象無象の表現者・思索者が数多く出入りし、関わり、つねに多くのプロジェクトが活発に行なわれた空間であった。木幡氏が長年にわたり旧P.S.1の客員キュレーターを務め、アラナ・ハイスとともにオルタナタィヴなアートスペースの運動に初期から関わってきたことを踏まえれば、その研究室のアクティヴィティの多産ぶりは驚くに値しないだろう。クロックタワー同様に、大学制度としての研究室がなくなったとしても、そこから生まれたダイナミズムが今後も持続的に発展することを期待している。
ここに挙げたいくつかの「危機」の舞台は、どれも背景や文脈が異なる、それぞれ固有で多様な「場-たち」である。それらを閉鎖や撤退に追いやるのは、しかし、売り上げ重視の大学や、営利目的でデベロッパーと結託するビルオーナーやシティ・ガバメントなど、一元的な経済合理主義と言える。ネグリ+ハートの有名な図式を借りるならば、その関係を「マルチチュード」と「〈帝国〉」と呼んでもよいかもしれない。ふと、以前どこかで聞いた岡崎乾二郎の言葉が頭をよぎる──「絵をかくことには、社会的な力がない。だからこそ、それは抵抗の拠点にもなる」★2。表現者の存在論というものがあるのだとすれば、それはなによりもまず、そのための自律的な時空をみずから生成・確保するということにほかならない。
★2──「絵画TV」(出演=岡崎乾二郎、粟田大輔、田中功起、保坂健次朗、2013年1月27日)における発言。
おおやま・えんりこいさむ
1983年、イタリア人の父と日本人の母のもと、東京に生まれる。 美術家。グラフィティの視覚言語から抽出された「クイックターン・ストラクチャー(Quick Turn Structure)」というモチーフを軸に、ペインティングやインスタレーション、壁画などの作品を発表する。また現代美術とストリートアートを横断する視点から、批評活動やシンポジウムへの参加も並行して行なう。2011年秋のパリ・コレクションではCOMME des GARÇONSにアートワークを提供するなど積極的に活動の幅を広げている。2012年よりニューヨーク在住。
岡本源太(美学/岡山大学准教授)
●A1実験工房展──戦後芸術を切り拓く(2013年1月12日から2014年1月26日にかけて、神奈川県立近代美術館・鎌倉、いわき市立美術館、富山県立近代美術館、北九州市立美術館分館、世田谷美術館を巡回)。
戦後日本の前衛芸術運動の先陣を切った「実験工房」は、1951年から1957年頃にかけての活動期間中には建築家とのコラボレーションこそなかったものの、その後の「空間から環境へ」展(1966年)や大阪万国博覧会(1970年)などの動きへと直接的につながっていったという点で、空間や環境の問題系においても看過できない足跡を残しただろう。昨年、大規模な回顧展が国内5ヶ所の美術館を巡回して、実験工房の全貌に触れる機会に恵まれた。 工房メンバーだった湯浅譲二や武満徹の電子音響音楽にはかねてから親しんでいたけれども、このたび実験工房の作品と記録にまとめて触れてみると、戦後復興期にアートとテクノロジーの先端を切り拓いていった前衛芸術家集団、というイメージからはいくぶん逸脱する側面のほうが強く印象に残る。彼らの作品は、いわばブリコラージュ的な発想に支えられていて、むしろ「進歩」に反旗を翻すかのような想像力のありようも見せる。第五福竜丸事件の1年前に、原子力発電のために壊滅する惑星を物語った作品を上演してすらいる(《見知らぬ世界の話》[1953年])。
現代フランスの哲学者エリー・デューリングは、論考「実験のいくつかの体制」(2009)のなかで、戦後に各地で展開された「実験芸術」には複数の体制があったことを指摘した。けれども、デューリングの分析する「人間行動学的体制」(E.A.T.やジャン・ティンゲリーなど)、「認識論的体制」(アスガー・ヨルンやシチュアシオニストなど)、「宇宙論的体制」(ジョン・ケージやフルクサスなど)のいずれにも、実験工房の「実験」はすっきりと収まらない。テクノロジーを利用し開拓するにしても、新たな媒体や素材自体に興味があるわけではない。既存の芸術制度や社会状況に対するオルタナティヴな場を切り拓きはするが、芸術を直接的な政治活動にはしない。いちはやくケージと交流をもったけれど、日常生活への着目や自己表現の放棄をおこなうわけでもなく、ワーク・イン・プログレスという発想もない。
実験工房の「実験」は、いまだいかなる文化や因習にも取り込まれていない真新しいテクノロジーを介して、あらゆる文明以前の全人類的な「起源」にさかのぼろうというものだ。「進歩」ではなく「回帰」──それを、瀧口修造から受け継がれたシュルレアリスム的な実験の精神の一展開と見るべきかもしれないと思いつつ、戦後の成長と発展のイデオロギーとは異なる「場」の姿を仄見る機会となった。
-


- 「実験工房展──戦後芸術を切り拓く」チラシ/Élie During et al. (dir.), In actu. De l'expérimental dans l'art, Dijon, Les Presses du réel, 2009
●A2
ジョルジョ・ヴァザーリ『美術家列伝』(中央公論美術出版)
ジョルジョ・ヴァザーリの著した『美術家列伝』、すなわち『いとも卓越せる画家、彫刻家、建築家の生涯』(初版1550年、第二版1568年)の日本語全訳刊行が、今年から6年がかりで予定されている。この書物は言うまでもなく、「建築」が実際の建造物としてだけでなく理論的言説としても存在しはじめたルネサンス期イタリアのもっとも貴重で重要な証言のひとつだ。すでに抄訳されてはいたものの、全容が日本語で読めるようになるのはなによりも喜ばしい。
ヴァザーリの「ディセーニョ〔disegno〕」の理論が──ほとんど暗黙裏のうちに──建築のみならず空間に関する僕らの思考をどれほど涵養し、また束縛してもいるのか。さらに展開させるにせよ、あるいは棄却するにせよ、それはこの古典の再読を通してしか可能ではないように思う。
おかもと・げんた
1981年生。美学。岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授。著書=『ジョルダーノ・ブルーノの哲学』(新プラトン主義協会賞)など。訳書=ジョルジョ・アガンベン『事物のしるし』(岡田温司との共訳)など。http://passing.nobody.jp/
笠置秀紀(建築家/mi-ri meter共同代表)
●A1「あいちトリエンナーレ」★1と「アーツ前橋」とその周辺★2。
地域アートプロジェクトを全て見ているわけではないので、これが現在の日本標準なのか、それとも最先端なのかは不明だが、ひとつの断面であることは確かだ。具体的な共通点としては、良い意味での「地味さ」だ。メディア的、観光的にものすごく地味なのだ。これまで地方のアートフェスティバルや現代アートを扱う地方美術館に行くきっかけとして、有名な海外アーティストが出展していたり、スペクタクル志向の派手なアート作品の存在があった。個人的に言うならば、足を延ばすのはそれらに客寄せパンダ的に引き寄せられ、その副産物として地域の魅力に触れるだけにとどまっていた。これらの試みは継続を通じて確かに地域に浸透した部分はあるものの、「あいち」と「前橋」はより地に足の着いた、成熟したものに感じられたのだ。それは観光から日常へのシフトと言ってもよいだろう。
「あいちトリエンナーレ」では、NAKAYOSHIのVISITOR CENTER AND STAND CAFE★3が特徴的だった。主要会場の長者町に、使われていない商店をカフェバーに改装した拠点である。特筆すべきは、このVISITOR CENTERが公式プログラムではないことだ。アーティストが商店街に乗り込み、ゲリラのように始めた期間限定の施設である。聞くところによると商店街から無償でさまざまな家具や、厨房機器まで集まってきて、営業ができるようになったのだという。地元のこのような社会関係資本が自然につながる背景には、アーティストの力もあるが、「あいちトリエンナーレ」が地域に根づいた証拠に違いない。
秋にオープンした公立美術館、「アーツ前橋」にも同じような状況がある。デパートを美術館にコンバージョンした施設も特筆すべきだが、それにともなって同時多発的に近くの商店街に生まれた、空き商店を利用したアートスペースの数々である。そう、1つや2つではないのだ。いくつかは市営のスペースもあるのだが、そのうちの一つである閉店した銭湯を利用したスペースも、前橋市民の部活動からつながった関係から見つけた場所なのだそうだ。前橋の文化的蓄積は大きくあるものの、公共のプロジェクトが起点となってさまざまなスペースが生まれているのである。
これまでは「箱モノ」「役所仕事」などと揶揄されたプロジェクトも、市民一人ひとりがそれをチャンスとして捉え、行政から与えられることに依存せず、DIYで自分たちのスペースを作っていく。もはやその状況は官か民かという対立を超えている。「行政とDIY」これが最強な組み合わせなのかもしれない。市民の社会的な脚本に「行政のやることに反対ありき」から「行政をうまく利用しながらDIY」のような選択肢が着実に広がり移行し始めている。
一方でそこに展示される美術作品の質は必ず担保されなければ、このような効果は生まれないのかもしれない。美術が"まちづくり"や"コミュニティ"という名のもとに、うまいように利用されるのではなく、そこに美術の本質を伝える作家とキュレーションが存在しなければならない。この2つのアートプロジェクトでは、優れた作品がその場所を開く力を持っていると改めて思わされた体験ができた。
例えばアーツ前橋の開館記念展「カゼイロノハナ」★4は、地元の作家の作品を中心とした企画展であった。立体や現代美術、絵画、地誌的資料などが相対的に組み合わされ、其々が際立っていたとともに、一見「地味な」絵画がひときわ輝きを放っていた。赤城山など地元の風景を描いた作品は、「ご当地」で見ることによっていきいきと迫ってきた。かつて上野などで見ていた、遠い地方の風景画は、どこか観光的な視点に捉えられて空々しく思え、いつしか見過ごすようになっていたのだ。これがキュレーションのテクニックなのか、絵画の力なのかは、判断できる力を持ち合わせていない。しかし絵画の「ご当地」性は周りに広がる地元の日常風景を際立たせる効果があることは確かなようだ。
「あいちトリエンナーレ」では、岡崎会場の志賀理江子「螺旋海岸」★5が秀逸であった。デパート上階の空きスペースを利用した会場は、現在の地方都市がおかれている状況がうまく表出していた。「螺旋海岸」は夜な夜な繰り広げられる老人たちの宴をとらえたような写真群を、螺旋状に配置したインスタレーションのような作品。見ている間にリアルなのか演劇なのか虚実皮膜の間で彷徨う感覚に陥る写真作品だ。ふと順路を外れた時に、会場の端にある真っ暗なエスカレータホールに迷い込んでしまった。営業を続ける下の階の淡々とした館内放送が聞こえてきた瞬間に、日常に戻され、同時に被写体の妖しい宴がリアルさを増した。被写体たちの宴はまさにこの打ち捨てられたデパートの空間で繰り広げられているのではと、錯覚してしまったことが印象的であった。
「カゼイロノハナ」と「螺旋海岸」に共通するのは、「いまここにいること」の感覚が開くことだったように思える。現在、本当に地域に必要なのは、場所の奥深い本質に迫るための方法論なのではないだろうか。その素養の上に立つことで、地味な日常はものすごく魅力的に見えてくるはずだ。
-


- 「あいちトリエンナーレ」「アーツ前橋開館記念展 カゼイロノハナ 未来への対話」ポスター
●A2
プロジェクトではないのだが、わたしの地元である吉祥寺の行方はますます気になっている。昨年に本サイトで特集記事として掲載いただいた「東京で一番住みたい街、吉祥寺──街の魅力とジェントリフィケーションをめぐって」★6の後、ドンキホーテの駅前出店や、75年続いた老舗家具店のMIYAKEの閉店、焼き鳥屋の「いせや」新装オープン等、吉祥寺の変容は加速し続けている。つい先日もネットニュースの吉祥寺を揶揄するニュース★7が目に入ってきたりと、街のイメージが簡単に乱高下する状況は注視するとともに、今までにないアクションを起こさなければならない。これも日常と観光化の問題なのかもしれない。
●A3
建築家というのはそれほど強くない。なにかが建設されるとなると、とたんに建築家が矢面に立たされて批判を浴びるが、世の中が思うほど建築家のコントロールできることは大きくない。むしろ社会システムの翻訳者でしかないのかもしれないとも思わされる。それでも、仕事を依頼されたなら、コンペを勝ち取ったなら、少しでもシステムの隙間から社会を変える戦いを行なうのが建築家なのではないだろうか。やると決まったらやるしか無い。2020年の東京オリンピックはまさにそんな状況だ。
一方でザハ・ハディドの新国立競技場ばかりに目を向けていることは大きな問題である。むしろ目を向けるべきは建築のシンボリズムではなく、東京の都市全体である。オリンピックをきっかけに、テロ対策や安全性を理由にして、東京の公共空間が余計に抑圧されることは避けてほしい。昨年末の宮下公園におけるホームレス排除★8などは、どうしてもこのオリンピックに関連した序章なのではと邪推せざるえない。またこれらが、日常の生活空間や、名も無き建築が織りなす風景にまで及び、破壊されないことを願うばかりである。
註
★1──あいちトリエンナーレ:http://aichitriennale.jp/
★2──アーツ前橋:http://artsmaebashi.jp/
★3──Facebookページ:https://www.facebook.com/pages/NAKAYOSI-VISITOR-CENTER-AND-STAND-CAFE-ビジターセンターアンドスタンドカフェ/1399486116930487
★4──アーツ前橋開館記念展 カゼイロノハナ 未来への対話:http://www.artsmaebashi.jp/?p=2112
★5──志賀理江子「螺旋海岸」:http://aichitriennale.jp/artist/shiga_lieko.html
★6──東京で一番住みたい街、吉祥寺──街の魅力とジェントリフィケーションをめぐって((Website10+1」):https://www.10plus1.jp/monthly/2013/07/issue01.php
★7──住みたい街人気NO1「吉祥寺」これまで評価が高すぎで、実際はたいしたことない?(「J-CASTニュース」):http://www.j-cast.com/2014/01/25194797.html
★8──渋谷区と警察、公園から野宿者を強制排除(「BLOGOS」):http://blogos.com/article/76930/
かさぎ・ひでのり
1975年東京生まれ。建築家。ミリメーター共同代表。日本大学芸術学部美術学科住空間デザインコース修了。2000年、宮口明子とミリメーター設立。公共空間に関わるプロダクトやフィールドワークを多数発表。プロジェクト=「アーバンピクニックシリーズ」「アーツ前橋 交流スペース」ほか。
門林岳史(関西大学准教授/表象文化論、メディア論)
●A1近頃は毎年のことであるが、2013年も日本各地でさまざまな芸術祭のたぐいが開催されており、私も比較的多くを見てまわった。部分的に参加したものも含めて訪れた順に列挙すると以下となる。「第5回恵比寿映像祭」「堂島リバービエンナーレ2013」「YCAM 10th Anniversary」「あいちトリエンナーレ2013」「おおがきビエンナーレ2013」「十和田奥入瀬芸術祭」「KYOTO EXPERIMENT 2013」「神戸ビエンナーレ2013」「FESTIVAL/TOKYO 13」。すべての芸術祭についてここで適切にコメントすることはできないので、全体を通して印象に残った点として、アートにおける拡張現実性なるものについて書き記しておきたい。
直接的に拡張現実(AR: Augmented Reality)のテクノロジーを利用している作品として、「KYOTO EXPERIMENT 2013」のフリンジ企画「使えるプログラム」に出展していたni_kaによるAR詩劇《キャラクターズ・リブ》と、「FESTIVAL/TOKYO 13」のPort B(高山明)《東京ヘテロトピア》の2作がある。
AR詩劇《キャラクターズ・リブ》は、つい先日サービスを終了したARアプリケーション「セカイカメラ」を利用して、街を歩きながらセカイカメラの画面上に浮かび上がってくる「詩」を鑑賞する、というものである。ni_kaは、2011年2〜3月に開催された「floating view "郊外"からうまれるアート」展(トーキョーワンダーサイト本郷)において、同様の作品を初めて発表しており、今回、京都の出町商店街を舞台に展開した作品はAR詩としては2度目の作品となる。事前に指示されたルートにしたがって商店街付近を歩いていると、セカイカメラの画面上にni_kaが設置した大量の「キティちゃん」のイメージが浮かび上がってくる。それらのキティちゃんのなかにはクリックするとテクストが表示されるものがあり、そのテクストをたどりながら街を歩くことでAR詩を鑑賞できるという作品である。
他方、《東京ヘテロトピア》は、より古いテクノロジーであるラジオを利用した作品である。受付で小型ラジオとガイドマップを手渡され、ガイドマップに従って移動し、指定の場所でラジオの周波数を合わせると、その場所にまつわるテクストの朗読を聞くことができる。東京都内に10カ所あまり散らばっている指定の場所は、記念碑やエスニックレストランなど、それぞれに移民の記憶を携えたトポスであり、鑑賞者はその付近にしばらくたたずんで、ラジオから聞こえてくる移民の声に耳を傾けることになる。ミシェル・フーコーの概念を借用した「ヘテロトピア(異在郷)」というタイトルの通り、都市に偏在している異質な記憶の層を浮かび上がらせる、ある種の観光の提案としては興味深い。ただし、そのからくりがわかってしまうと、一つひとつの朗読を聴く経験はそれほど鮮烈なものではない。
ここにはおそらく、芸術鑑賞の経験における集中と散漫の2つの極が関わっている。ヴァルター・ベンヤミンの有名なテーゼを思い起こすまでもなく、都市を歩く経験は本来的に散漫な経験である。にもかかわらず、ラジオから聞こえてくる朗読は、テクストへのそれなりの集中を要求する。記念碑やエスニックレストランでたたずむ身体は、周りの風景や行き会う人々に気をとられ、この集中への要請に応えることができない。とりわけ、私のように強引に一日で鑑賞を終えようとしている者にとっては、エスニックレストランに立ち寄っても、次の予定を考えるとそこで食事をとるわけにもいかず、なにやら中途半端に一つひとつのミッションをこなしていくことだけに満足感を求め始めてしまう結果となる。それならいっそ、この作品全体の経験がより根底的に散漫なものとして構想されていてもよかったのではないか、という感想を抱いた。
同じことはni_kaのAR詩についても言える。今回京都で展開されていた作品は、少女が父親に宛てた手紙という体裁の12本のテクストを順番に読み進めていくというかたちを取っており、ni_kaが作り出した作品世界に没入し、手紙をすべて拾い集めるというミッションを完了することによってしか、作品の経験に満足感を得ることは許されていない。しかしながら、そうであればこの作品のために拡張現実のテクノロジーを利用する意味はあっただろうか。現実の都市空間と作品世界の境界が曖昧になっていくような経験を与えてこそ、拡張現実のテクノロジーを利用する意義があるはずだが、実際の作品経験は必ずしもそのようなものではない。むしろ、鑑賞者はテクストを探し求めることに必死でセカイカメラの画面に没入し、結果として都市空間はないがしろになってしまった(端的に道を歩いていて危ない)ように思われるのである。
実は、京都でのni_kaの作品を鑑賞したあとになにやらもやもやしたものを感じたので、その後東京に立ち寄ったおりに、上に言及した「floating view」展の際のAR詩の痕跡を体験してきた。結論としては、こちらのほうがはるかに興味深い鑑賞経験であった。まず、京都の作品の場合、ni_kaが設置したものとは関係のない情報をフィルタリングするために、セカイカメラのタグ表示を最近数カ月のものに制限することが求められていた。他方で、東京での作品の場合、2年以上前の作品を追体験することになるので、フィルタリングを無制限にしなければni_kaが設置したタグを追うことはできない。結果として、御茶ノ水駅から会場のトーキョーワンダーサイト本郷まで歩く道程で、セカイカメラの画面には、ni_kaのAR詩に混じって無数の匿名のタグが表示され続けることになる(例えばお茶の水橋上からある方向にセカイカメラを向けると、画面には「肉 肉 肉」というタグが表示される。おそらくその向こうに焼き肉屋があるのだろう)。しかしながら、真に拡張現実的な作品を構想するのであれば、こうした作品外のタグを作品経験にとってのノイズとして排除するのではなく、むしろ、作品に不可欠の構成要素として(パレルゴンとして?)取り込むことこそが望ましいのではないか。
「floating view」展は、その会期中に東日本大震災が起こり、そのことでni_kaの作品も大きく性質を変えることになった。ni_kaは会場付近に設置したAR詩に加えて、会期中に東京各地で被災者を追悼する趣旨のAR詩を展開していったのである。これらのAR詩の記録画像はいまでもni_kaのブログ上で観ることができる。というよりは、ブログ上にはこれらのAR詩が設置されている場所は公開されていないので、東京タワーや六本木ヒルズ展望台のように明らかに場所を特定できるものをのぞいて、これらのAR詩はブログ上でのみ閲覧することが想定されて製作されていると考えてよいだろう。その結果、作品経験はふたたび都市空間から隔離されるのである。
さて、上記2作は明示的に拡張現実のテクノロジーを応用した作品であるが、思い返してみると各芸術祭にはそれ以外にも拡張現実的と呼ぶのがふさわしい作品がいくつかあった。例えば「YCAM 10th Anniversary」で展示されていた瀬田なつきの映像インスタレーション《5 windows》。横浜・黄金町の川辺の風景をスケッチしたオムニバス風の4本の短編と、それらの映像を統合した物語作品の計5本の映画からなる作品である。これまでに横浜、吉祥寺、渋谷などで上映されてきたが、今回のYCAM(山口情報芸術センター)での上映/展示に際しては、山口市内の一の坂川付近が会場に選ばれた。一の坂川に沿って4本の短編をリピート再生するディスプレイが設置され、そこから少し離れたところに位置する山口ふるさと伝承総合センター内の一室で5本目の作品が上映されるという趣向である。その結果得られるのは、横浜の川辺で展開される虚構の物語と、山口の川辺の現実の風景が、映像に媒介されて溶け合うような心地よい経験である。
あるいは「十和田奥入瀬芸術祭」では、芸術祭の一環として『十和田、奥入瀬──水と土地をめぐる旅』(管啓次郎編、青幻舎)という書籍が刊行されていた。芸術祭のカタログに相当する書籍であり、芸術祭出品作に関連するテクストも収録されているが、それだけにはとどまらない。それに加えて短編小説3篇と畠山直哉による撮り下ろしの写真も収録されており、この書籍自体が芸術祭のもうひとつの(ヴァーチュアルな)会場という趣向になっているのである。この書籍のために、小林エリカ、石田千、小野正嗣の3名の作家はそれぞれ、芸術祭の3つの会場である十和田湖、奥入瀬渓流、十和田市街にまつわる物語を書き下ろした。例えば芸術祭を訪れた帰路、記憶も新しいままにこの本のページをめくってみる。そうすると、まだ自分の体に染みついている土地の風景やにおいが、その土地の歴史に根ざして紡がれる虚構の物語と混じりあう不思議な経験をすることになる。その意味ではこの本全体が、書籍という古いメディアを舞台にして現実と虚構、記憶と歴史を折りあわせるある種の拡張現実的な作品である。
そして最後にもうひとつ、「あいちトリエンナーレ2013」で展示されていた宮本住明《福島第一さかえ原発》を挙げておきたい。(あいちトリエンナーレではインヴィジブル・プレイグラウンド《ささいな出来事の美術館》という明示的に拡張現実的な作品も出品されていたのだが、4人一組で参加する作品のため体験することができなかった)。この作品は、トリエンナーレのメイン会場である愛知芸術文化センター全体を、同じくらいの規模の建造物である福島第一原子力発電所の建屋に見立て、会場の床や壁、天井に原子炉の断面線をテープ状のカッティングシートでなぞったものである。テープがかたちづくるなにやらモダニズムめいた抽象的なフォルムは、トリエンナーレ会場を縁どるお洒落な演出のように見え、会場に入ってしばらくの間は、これが作品であるとは気づかない。しばらく会場内を巡ったあとになって、いままで会場内のいたるところで眼にしてきたテープのラインが、実は原子炉をかたどったものであり、自分は拡張現実的な空間において原子炉とそれを取り囲む建屋の内部を移動し続けていたことを知る。それはある種のコペルニクス的転回と言うにふさわしい経験であり、この作品の存在を知った瞬間に、展示会場全体の見え方が変わってしまうのである。
以上、後半では現実の空間と虚構の空間や経験を溶け合わせることを作品経験の核としている3つの作品を概観してきた。そのいずれもが、いわゆる拡張現実のテクノロジーを応用したメディアアートというわけではないが、優れて拡張現実的な経験を作品の内部に折り込んでいる。それに加えて共通しているのは、芸術祭の会場を歩き回るという本質的に散漫な経験が、作品の成立にとって不可欠な構成要素になっている点である。もちろん極論すれば、あらゆる優れた芸術作品は拡張現実的な虚構の経験を与えるものであると言いうるだろう。しかしながら、これらの集中を要求しない作品が与えている散漫な拡張現実的なるものは、各地に芸術祭が乱立する現在のアートシーンになにかふさわしいものなのかもしれない。
かどばやし・たけし
1974年生。関西大学准教授。表象文化論、メディア論。著書=『ホワッチャドゥーイン、マーシャル・マクルーハン?──感性論的メディア論』、翻訳=リピット水田堯『原子の光(影の光学)』など。
門脇耕三
●A12013年は、建築家が歴史を認識することの重要性が、繰り返し指摘された年だった。『GA JAPAN』No.124には、「歴史観なき現代建築に未来はない」という直截なタイトルの特集が掲載されたし、日本建築学会の学会誌『建築雑誌』でも、「『建築家』が問われるとき」と題して、建築家という職能を歴史的に位置付ける特集が組まれた(2013年11月号)。年末に発行された『SD2013』でも、第2特集「日本現代建築における歴史認識をめぐって」において、SDレビュー入選者の歴史的位置付けが、入選者自身によって披瀝された。
また、2013年は、いくつかの媒体において、建築批評の場が増えた年でもあった。『新建築 住宅特集』では、2013年7月号より、掲載作品に対する「批評」欄が設けられ、2013年最後の号となる2014年1月号では、ほとんどすべての掲載作品に対して、第三者による批評が掲載された。日本建築学会には、「建築討論委員会」が新設され、Webを媒体とした建築批評の場が準備されつつある。
この2つの動きは、おそらく同じ地平の上に展開していると考えてよいだろう。すなわち、建築における言説空間の重要性の再確認が、進んでいるのである。
こうした動き自体は、歓迎すべきことだと筆者は考えている。建築作品そればかりではなく、個別の建築作品を成り立たせている文化的・技術的・制度的な共通基盤(これこそArchitecture=建築にほかならない)を如何に豊かなものへと育て上げていけるかが、建築に携わる者の最重要の責務であると筆者は信じているし、建築における言説空間が、この基盤の一端を担っていることに間違いはないからだ。
一方で、2000年代に通底していた、建築創造にまつわる一種の楽観主義的な気分も、ここ1、2年で、一気に雲散霧消してしまったようにも感じている。これが建築創造の可能性を狭めるものではなく、むしろ拡張するものであってほしいと筆者は願っているが、この動きの向かう先は、おそらく2014年中には、おぼろげながらに見えてくることだろうと感じている。
-



- 『GA JAPAN』No.124/『SD2013』/『新建築 住宅特集』2013年7月号
●A2, A3
東京オリンピックに関する企画が、建築系のメディアでも動き出しつつあり、2014年の最大の関心事のひとつになることは間違いなさそうである。2013年は、槇文彦の論考に端を発する《新国立競技場》に関する議論が話題を集めたが、筆者も大いに関心を持って議論の行く末を見守っており、多くの識者からの意見や提案を新聞・雑誌・Webなどで拝読した。ただし、これらの意見や提案は多様である反面、玉石混交である感は否めない、というのが正直な感想である。陸上競技場の国際規格やトレンド、国内の建築関連法令にそぐわない意見や提案も散見された。筆者は競技施設計画の専門家ではないが、多くの設計者や技術者や研究者とこの問題について直接議論するなかで、勉強させていただいた観点が多数あった。これだけの規模の競技場なのだから、エラーやバグのない意見を個人に求めること自体が、おそらく困難なのだろう。
だとするならば、多様な意見をピアチェックを経て集約し、専門家集団の見解としてオーソライズする方法は考えられないだろうか。今後、オリンピックについて語られるべき事柄は、単体施設の是非の域を出て、地域全体、東京全体、ひいては日本全体の問題へと遷移していくはずである。2020年には、「震災後」という状況にも、ひとまずの区切りをつけねばならないだろう。つまり建築や都市に携わるあらゆる専門家は、オリンピックの問題に関して、部外者ではあり得ない。したがって、専門家による集合知の形成が、重要な課題として浮上してくるわけであるが、Webがこれだけ発達した現在、情報がきちんと開示され、適切な専門家団体が舵をとれば、これは決して不可能なことではあるまい。
かどわき・こうぞう
1977年生。明治大学専任講師。建築構法、構法計画、建築設計、設計方法論。
共著=『シェアをデザインする──変わるコミュニティ、ビジネス、クリエイションの現場』など。
菊地宏(建築家/菊地宏建築設計事務所)
●A1東京では、3/16に東横線の渋谷駅が地下化され、3/23には小田急線下北沢の地下化された。
どちらも、営業を継続した状態で、地下に鉄道を移設するという非常に複雑な工事を難なくやって見せた。
それとともに都市の様相は一変し、今まで使われていた空間が突如閉鎖され、利用者は混乱する中、多少の不満をもらしつつも新しい状況に適応していく。渋谷では、これを機に大規模な再開発が駅を中心に行なわれるが、地形に精通している人であれば、渋谷川との関係も気になるところだろう。
下北沢駅は、今まで小田急線と井の頭線によって四つに分断されていたが、これを機に町の構図も変わり、踏み切りで電車の通過待ちをしていた風景も消えた。不便であった町も今振り返ると何か寂しい。
ところで個人的な大きな出来事といえば、初めての単著『菊地宏 │ バッソコンティヌオ──空間を支配する旋律』がLIXIL出版より出版されたことだ。長い時間校正を重ね、撮りためた写真の選定など、自分にとっては新しい試みも多かった。内容は、ぜひ手に取ってみていただきたいが、自然観察を通じて見えてくる建築の空間や光そして色について書かれている。今まで漠然と感じていたことをひとつにまとめたことは、自分にとっても大きなことであった。
-

- 菊地宏『バッソコンティヌオ──空間を支配する旋律』
(現代建築家コンセプ・トシリーズ15、LIXIL出版)
●A2
今年も引き続き、都市の構造は大きく変わっていくだろう。特に立川駅周辺の開発、圏央道や首都高中央環状線の開通で東京の縦方向の交通網もかなり改善され、都市構造に大きなインパクトを与えるだろう。この二つが開通することによって都市内部でも首都高などの改造が急速に進む環境が整うことを考えると、これからの都市内部の大きな改変も気になるところだ。
●A3
外国人が今まで以上に東京を訪れるようになるだろう。ふと、街角や駅構内を見わたすと、サインのほかにお手製の注意書きや補助的なサインが目に付く。過密都市東京は、どうも計画されたサインだけでは
追いつかないのか、そういった親切心からくるサインなどが効果的であると同時に景観として醜いものにしていることも強く感じる。もっとサイン計画というものが洗練され都市景観として積極的に美しさに寄与していけば、国際都市としてより品の良い洗練されたものとして成長してゆくだろう。
きくち・ひろし
1972年生。1996年東京理科大学工学部第一部建築学科卒業。1998年同大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了。1998-1999年妹島和世建築設計事務所勤務。2000-2004年ヘルツォーク&ド・ムーロン建築事務所勤務。2004年菊地宏建築設計事務所設立。作品に《南洋堂書店改修》《LUZ STORE》ほか。著書=『バッソコンティヌオ──空間を支配する旋律』。
http://www.hiroshikikuchi.com/
小林恵吾(建築家/早稲田大学建築学科助教)
●A1
ロッテルダムという長年住んでいた小さな町から、突如東京という巨大都市に移り住むことになってまもなく迎えた2013年は、膨大な情報の渦や忙しない社会の流れといったなかで、個々の出来事の重要性をあまり振り返る暇もなく、あっという間に過ぎ去ってしまったという印象がとても強い。
そんななかでも印象に残っている出来事といえば、やはり東京オリンピックの決定が大きいが、エドワード・スノーデンがモスクワのシェレメチェボ空港のトランジットターミナル内に1カ月以上滞在していたことは、非常に興味深かった。映画『ターミナル』のトム・ハンクスではないが、現実としてどの国にも属さない領域において、長期間にわたって住まうという行為や、彼自身がバーチャル内の機密データを持ち出し流出させたという事実によって引き起こされたということもまた映画のシナリオのようで、われわれを取り巻く世界が一昔前のフィクションをなぞっているような感覚を覚えた。その後、ちょうどスノーデンがロシア亡命をはたし空港を出たころ、ベトナムの密林の中から今度は40年間ものあいだ、国家や社会と一切の関係を持たずに生活していた親子二人が発見された。全部ひっくるめて、まるでB級SF映画が現実化したような世の中だと思った。
●A2
個人的にも関わっているが、第14回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展。レム・コールハースのディレクションのもと行なわれる今回のビエンナーレは、「建築家ではなく、建築のためのビエンナーレ」と彼が言うように、全体として例年のものとは性質の違ったものになると期待している。
●A3
東京オリンピックについては多方面でいろいろと議論がなされたり、教育の場でも課題テーマとして扱われたりと、それなりに世間を騒がしてはいるが、正直なところ自分とは遠いところでことが進んでいる印象が強く、あまり関心が持てていない。ゼネコン各社のJVや、大手広告業と行政、都と国といったプレーヤーによって、知らないうちにあらゆることが進められているという印象を持っている。6年先という時間を長いとみるか、短いとみるかは人それぞれかもしれないが、7年後に決定直前の昨年途中で保留となった多くの課題にまた向き合うことになると思うと、その現実から逃避するには6年という時間はあまりにも短く、問題に立ち向かうためのモチベーションを持続するにはあまりにも長過ぎると個人的には感じている。
こばやし・けいご
1978年生まれ。2002年早稲田大学理工学部建築学科卒業、2005年ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程卒業、2005年-2012年OMA/AMO勤務、現在早稲田大学建築学科助教。
後藤治(建築史・保存修復、工学院大学建築学部教授)
●A1槇文彦「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」
発表された槇先生に敬意を表したいのと同時に、歴史を研究している者のひとりとして、研究者がこのことを先に指摘できなかったことに恥じ入るばかりです。
●A2
つだゆみ(マンガ・文)『夢の超特急ひかり号が走った』(西日本出版社)
自ら企画に関与しているものの参考になったので。出版に協力した愛媛県西条市からいただきました。市町村が協力してできた本としても秀逸だと思います。
-

- つだゆみ『夢の超特急ひかり号が走った』(西日本出版社)
●A3
人の手当(特に職方)が大変だと思うのと、同時に、ワールドカップは国単位で受け入れるのに、オリンピックはなぜ自治体単位なのかと考えてしまいます。それが、コンパクト化ではなく、かえって、大規模開発型を後押ししてしまっているように思います。
ごとう・おさむ
1960年生。工学院大学建築学部教授。著書=『建築学の基礎6日本建築史』『四国の住まい』。共著=『食と建築土木』『それでも、「木密」に住み続けたい!』『都市の記憶を失う前に』ほか
佐藤信
●A12013年いっぱい『週刊読書人』という雑誌で論壇時評を担当させてもらった。総合雑誌が中心なので建築や都市に関する記事を直接に扱うことはなかったのだが、地方がこれまでと違ったかたちで注目され、これから問題になってゆくであろうことは強く感じた。郊外のショッピングモールに関する論考が多く出版され、若者の就農(農ギャル)などが注目されていることはみなさんご存知の通りである。だが、こうした潮流は持続的社会を目指すロハス的生活とは流れを異にしているように見える。大雑把にまとめるなら、その潮流は、都市と地方という二極性(と止まらない都市への人口流出)を前提にしながら、自分の生活を組み立ててゆくという生活態度なのだと思う。両極の半ばに居心地のよさを見出したり、両極を自分の生活のなかでバランスよく組み合わせたりといった具合にである。
これまでならば、はいそうですか、で終わりだったのだが、現代の日本社会における問題はこの都市―地方の議論と(環境の持続性はさておいて)日本社会そのものの持続性との議論がリンクしてくることである。その突端とも呼べるのが増田寛也・人口減少問題研究会が『中央公論』12月号に発表した「2040年、地方消滅。『極点社会』が到来する」。
タイトルが魅力的じゃなかったからか知らないが、このレポートに対する一般社会における反応はあまりない。そのうえ、ネット上の反応をさらっと見てみたら、地方の復権を理想的に語っている人たちがまるで我が意を得たりといったように賛意を示していたが、これは我田引水も甚だしい解釈だと思う。確かにこのレポートは、大都市圏への人口流出は止まらず、しかし東京のような大都市では出生率が抑制されているから、人口減少に歯止めをかけようとするなら大都市圏への人口流出を食い止めるべきだ、と提言している。だが、そこで期待されているのは地方一般ではない。むしろ地方の農村における人口流出は止めるべくもないが、地方中核都市がその受け皿(彼らは「防衛・反転線」と読んでいる)となることで人口減少を食い止めようという、現実的な地方都市重視論なのである。都市と地方という二極構造を想像してしまうと、大都市と地方都市という差異は縮小されてしまうのだが、そこで地方都市の魅力を打ち出せるかどうか、ひとつの挑戦的問題提起である。
彼らの処方箋がそのままに採用され、実現するかどうかはわからないが、少なくとも2014年以降、都市―地方という二極に回収される思考様式は、新しいものに塗り替えられることになると思う。そうして地域のイメージそのものが揺らいでくれば、建築もまた変容せざるをえないのは当然だろう。それらがどんなイメージをとるのか、2014年はさまざまな刺激的な試みが登場することを期待したい。
●A3
上に書いたような流れから言えば、国土強靭化や東京オリンピック計画が旧来的な利権秩序の復活として機能することになれば、いかがなものかという思いはある。防災や祝典が国家レベルで企図されること自体には何の問題もないが(当たり前だ)、現在の日本社会が何をどのようなかたちで必要としているのか、それを問い直し、枠組みを組み直すことは何よりも必要だったはずである(東京オリンピックをどう捉えるべきかについては「10+1 web site」誌上に書かせていただいた。「都市と祝祭──あるいは来るべき不完全なオリンピックへの賛歌」)。すでに復活してしまったものを換骨奪胎というわけにはいかないけれど、自分の意識まで利権秩序に慣らされてしまわないように気をつけなければ。
●A2
2013年の年末に御厨貴教授の『権力の館を歩く』が文庫化(ちくま文庫)された。この本、自分も参加していた御厨教授の「建築と政治」プロジェクトの成果物である。この本に対しては(参加者のひとりでありながら)、空間と政治とを接続する枠組みが明確になっていないと、いろんなところで批判した。もちろん、この批判は御厨教授に対してのみのものではない。東京オリンピックを挙げるまでもなく、空間と政治とのあいだに相互連関があるのは誰しもが納得するけれど、その連関の全体像を意識しながら建築を見るというのはなかなかないのだ(都市計画についてはよくあるのだけれど)。
そんな空間と政治についてだが、今年度は「権力の館を歩く」を後継する国際日本文化研究センターの共同研究(「建築と権力の相関性とダイナミズムの研究」)の最終年度にあたり、成果物が発表されることになっている。これまで空間に目を向けることが少なかった少壮の政治学者も多く参画して、建築に宿る政治性の諸相を描き出すものになる予定なので、それがまた刺激となって空間と政治との連関の議論が発展することを期待したい。自分としても、この研究会で報告させてもらった山県有朋の邸宅と庭園に関する研究、国会議事堂の建設過程についての研究を今年中には公にしたいと考えている。海外の研究者にこのことを話すとやたら受けがいいので、国際展開も考えつつ進められれば。
-

- 御厨貴『権力の館を歩く』
さとう・しん
1988年生。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院法学政治学研究科博士後期課程。著書=『鈴木茂三郎』、『60年代のリアル』(単著)、『政権交代を超えて』(共編著)。
沢山遼(美術批評)
●A1昨年末、突如として四谷アート・ステュディウムの閉校問題が勃発した。現在に至るまで、閉校を告知した当の近畿大学から、閉校の理由にかんする一切の説明は行なわれていない。閉校の情報が公になってから数週間後に私のもとに届いた通知には、「現在の研究所運営の見直しを図る必要があり、2014年3月末日をもちましてコミュニティカレッジを閉講する運びとなりました」との官僚的な文言が添えられているばかりであり、そこになんら具体的な説得力をもった理由は明示されていない。
つまるところこの文言は、閉校の理由をひた隠し、なかば強引に、理由のないことを理由として掲げ、この奇蹟的な芸術の学校を閉鎖しようとする、教育機関としての驚くべき不誠実さを露呈するものである。このような態度は、たとえば「閉校するのだから、閉校するのだ」という同語反復的な、内実を欠いた空疎な言辞に着地するほかないだろう。近畿大学は講師や学生たちの前で平然とそのような態度を取りうるという点で、本来であれば、各人の自由な思想をその論理的な公正さにおいて交通させる場であるはずの大学機関がもっとも忌避すべき、論理を欠いた同語反復的な決断=ファシズム的断行を行なおうとしているということである。
今回の近畿大学の決定ばかりではなく、おおよそ、今後の展開において、権力機構は、このような同語反復的断行をあらゆる場において行使しようとすることになるかもしれない。しかし芸術はつねに、「建てるのだから、建てるのだ」という決断のもとに建設される建築、「通すのだから、通すのだ」という決断のもとに採決される法案、つまりはファシズム的断行の遍在という事態に対する、抵抗の拠点であり続けるだろう。
あるいは私たちはそれを「芸術」と限定的に名指す必要もない。昨年度の四谷アート・ステュディウムの理論講座の通年の共通テーマは「芸術と(いわれる)生産過程あるいは「生」活 」とされていた。これまでも四谷で繰り返し語られてきたように、私たちの文化は、生(life)と生活(life)の双方にまたがる多様な技術や事物に内在するさまざまな秩序に規定されている。日々の生活のさまざまな局面においては、誰もがそのような秩序に遭遇しているはずだ。言い換えれば、妥当性をもった物や行為にはかならずその妥当性を裏付ける正当な根拠=理論が内在しているということであり、またそのさらなる形成に際しては、理論がかならず要請されるということだ。そして芸術批評が、対象の妥当性を判断・吟味する力=判断力を感性的な水準で精錬する場であったのであれば、批評もまた、芸術の形成力に作用しうるものとなるだろう。
ゆえに、生活の場=日々の暮らしこそが闘争の拠点となりうるのであり、日々の鍛錬こそが、芸術的であると同時に批評的営為なのである。私たちの日常生活を拘束する、この秩序こそ希望である。そこで、芸術と呼ばれるあらゆる文化・生活は、未来を構想するもっとも有効かつ具体的な手段でありうるだろう。とするなら、「我々には四谷ART STUDIUMが必要である」[http://www.arttrace.org/books/details/atpress/atpress03_wareware.html]と題された松浦寿夫の希有なテキストに倣って繰り返すべきかもしれない。「我々はあらゆる場所に四谷Art Studiumを出現させなければならない。朝の食卓でパンを手に取るときに、コップで飲料を摂取するときに四谷Art Studiumを出現させなければならない」と。つまりは、日常生活のあらゆる局面に、あらゆる時間と空間に、私たちの四谷アート・ステュディウムを出現させることだ。私たちがこの「生活」と呼ばれる生の持続をあらたな生産と思考の拠点へと精製していくことにおいて、それは可能である。
参照サイト
「芸術教育とは何か?─四谷アート・ステュディウム閉校問題から考える─」
http://artstudium-artandeducation.tumblr.com/
岡﨑乾二郎インタヴュー|われ、またアート・ステュディウムに─
http://as-artandeducation-archive.tumblr.com/
また現在、学生や在学経験者たちによる学校存続を求めるサイトも立ち上がっている。
http://artstudium2014.blogspot.jp/
さわやま・りょう
1982年生。美術批評。武蔵野美術大学非常勤講師。最近の仕事に『Jiro Takamatsu Critical Archive vol.1』など。
城一裕(音響学、インタラクションデザイン/情報科学芸術大学院大学[IAMAS]講師)
●A1
スノーデンとインターネットおじさん
両者ともにポスト・インターネットを実感させてくれた存在。円城塔さんではないが★1、エドワード・スノーデンは秘密は暴かれるものだということを端的に示してくれた。一方で、インターネットおじさんは、人間拡声器★2ではなく「リアルRT」、SNSでのつながりではなく「リアルフォロー」、さらには「リアルペイパル」というかたちでインターネットがあたりまえになった後の世界を体を張って具現可している★3。

- インターネットおじさん
★1──円城塔「今こそ政治を話そう 好きな子の名前は秘密」(朝日新聞DIGITAL、2013年11月21日)
URL=http://www.asahi.com/articles/TKY201311200666.html
★2──メガホンの利用が制限されたオキュパイ・ウォール・ストリートで生み出された手法。「ある人物がグループや群衆に向かって話したい場合、ワンフレーズを発すると、それが発言者を取り囲む人々の声によって復唱され、その声は次々に遠くの人によって復唱される」。
括弧内引用出典=「世界に広がる『怒れる者たち』」(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版、2012年6月号、土田修 訳、URL=http://www.diplo.jp/articles12/1206-2(indignes).html)
★3──「リアルRT」=誰かの言ったことをその場で叫んでくれる。「リアルフォロー」=跡をついて歩いてきてくれる。「リアルペイパル」=後述のインターネットヤミ市に参加するために行なわれている銀行振込のこと。詳細は、http://www.internet-dude.com/を参照。
●A2
インターネットヤミ市 in ベルリン
昨年出版された書籍『FABに何が可能か──「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』★4のなかで松井茂さんが、3・11以降のパーソナル・ファブリケーション(個人的なものづくり)の可能性は、キャピタリズムにおけるイノベーションではなく、貨幣の価値に関わらないということをアドバンテージとした芸術活動として、テクノロジーを実践的に意識化することにあると述べている。その意味において、社会構造の変革を目指すFabLabでも、アカデミズムの新たなあり方を試みるニコニコ学会βでもなく、一見なんのことかわからない「インターネット感」を売買の対象としてしまい、貨幣の価値そのものにも疑いを向けているようにすら思えるインターネットヤミ市★5が、ウィキリークスの創設にも関わったカオス・コンピューター・クラブ(CCC)のお膝元、ベルリンの地にて開催されることは感慨深い。
- Back streets of the Internet
★4──松井茂「FABが芸術を変える」(『FABに何が可能か──「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』、フィルムアート社、2013)
★5──100年前から続くインターネット上の秘密結社、IDPWの主催するフリーマーケット。先述のインターネットおじさんによる「リアルRT」を始めとしてインターネットに関するあらゆるものが売り買いされる。三度目となる今回は初めての海外での開催。詳細は出展者募集サイトおよびプロモーションビデオ「Back streets of the Internet」を参照。
●A3
現在、文化庁からの助成を受けて「アート/メディア/身体表現に関わる専門スタッフ育成事業」★6を実施している。この事業では、現代テクノロジーを用いた多岐にわたる芸術表現を支える人材の育成を目指している。前回のロンドンの例を出すまでもなく、オリンピックが総合的な文化イベントとして演出されていくことは明らかであり、それらをも担うであろう人々を育てる場に関わるということに良くも悪くも責任を感じる。
★6──平成25年度文化庁大学を活用した文化芸術推進事業として実施。
URL=http://amp.iamas.ac.jp/
じょう・かずひろ
1977年生まれ。九州芸術工科大学(現九州大学)卒業・修了。日本IBM、東京大学先端研、英国ニューカッスル大学、東京藝術大学芸術情報センターを経て、2012年より現職。専門は音響学、インタラクション・デザイン。共著=『FABに何が可能か──「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』ほか。
須之内元洋(メディア環境学、メディア情報学/札幌市立大学デザイン学部助教)
●A1
Google Glassを始めとした消費者向けウェアラブルデバイスの勃興と環境メディア化。思えばスマホのながら歩きとは、次なるメディアの環境化に対する切実な欲求の現われだったかもしれない。メディアがポケットの中にあるのと、身体にくっついていることの差異はきっと大きい。過去数十年にわたって研究が行なわれてきたウェアラブルデバイスと、それにまつわるキーテクノロジーが、いよいよ実践的なメディアとして実装され始めた。都市の空間概念、人々の生活行動様式がどのように再デザインされる可能性があるのか興味深い★1,2。
★1──世界の主要都市に拠点を持つデザインファーム frog design による、ウェアラブル・テクノロジを活用した八つのデザインコンセプトの提示
URL=http://www.slideshare.net/frogdesign/wearable-technology-22155193
★2──ウェアラブル・デヴァイスと身体とのインタラクションの課題を提示する記事(MIT Technology Review)。スワイプ(スマホ)≒ OK Glass(Google glass)?
URL=http://www.technologyreview.com/view/511641/google-glass-needs-phatic-interaction-stat/
●A2
2014年7月19日(土)より9月28日(日)までの72日間、札幌国際芸術祭2014が開催される★3。昨年11月に行なわれたシンポジウム「札幌国際芸術祭が目指すもの」において★4、芸術祭企画アドバイザーの浅田彰氏が発したメッセージが印象的だ。百数十年前にアメリカ人のウィリアム・クラーク博士が発した「Boys be ambitious」から「We are ambiguous」へ。アメリカ型の開発モデルによってつくられた近代都市の象徴としての札幌で、近代の意味、これからの都市のあり方を問い、今一度「We are ambiguous」という認識に立ち戻れるかを問う芸術祭になる予定だ。北海道出身で晩年は札幌大学学長を務められ、昨年3月10日に亡くなられた山口昌男さんの言葉「Be ambiguous(両義的ないし曖昧であれ)」である。
- シンポジウム 札幌国際芸術祭が目指すもの
★3──札幌国際芸術祭2014
URL=http://www.sapporo-internationalartfestival.jp/
★4──「シンポジウム 札幌国際芸術祭が目指すもの」
URL=http://www.ustream.tv/recorded/40578943
●A3
安倍晋三首相の「原発はコントロール下にある」発言、2020年の東京オリンピック開催が決まったのも束の間、特定秘密保護法の成立に続いて猪瀬直樹前東京都知事の辞任。北海道から一連の流れをみていると、日本の根深い問題は何も解決しておらず、むしろ問題を象徴しているかのような経緯に映る。まずは、東京都知事選の結果を見守りたい。
すのうち・もとひろ
1977年生。メディア環境学、メディア情報学。札幌市立大学デザイン学部助教。
津田和俊(大阪大学助教、FabLab Japan Network)
「何を自分はアチックに見出さんとしつつあるか、人格的に平等にしてしかも職業に、専攻に、性格に相異なった人たちの力が仲良き一群として働く時、その総和が数学的以上の価値を示す喜びを皆で共に味わいたい。チームワークのハーモニアス・デヴェロープメントだ。自分の待望は実にこれであった。」★1
2013年、渋沢敬三の没後50年記念事業として開催された特別展「屋根裏部屋の博物館」(国立民族学博物館、2013年9月19日〜12月3日)の会場内に、木村伊兵衛によるポートレイトと一緒に掲げられていた言葉です。渋沢敬三が青年時代に自宅の屋根裏に私設したアチック・ミューゼアムでは、民衆が日常の暮らしの必要からこしらえた民具を中心に蒐集し、多様な分野からの視点を持ち寄って調査研究を進めていたことが広く知られています。この言葉は現在もなお私たちに「つくること、つながること」の可能性とそのあり方について、礼讃しながら問いかけているように感じました。例えば、ひとつには、同じ時代を生きる人たちがどのようにつながっていくかということ。もうひとつには、時代を超えてどのようにつながっていくかということです。
インターネット以降、私たちは多くの情報や知識を共有し、また多くの人たちと意見交換ができるようになりました。特に同じ意見を持った人たち同士は飛躍的に集まりやすくなったのではないでしょうか。しかし一方で、民主主義に求められる異なる意見を持った人たちのあいだでの同意や合意形成はますます難しくなりつつあるのではと感じます。そのような異なる他者とのコミュニケーションをすすめるひとつの可能性は、物を介在した対話ではないかと考えています。なぜかというと、物を設計して、つくりあげるためには、多様な視点から対象を考察し、それらが調和した落とし所を見つける必要があるからです。
ここでいう物を介在した対話とは、従来の産学官連携のような組織間の協力や村社会での固定された人間関係におけるコミュニケーションではなく、近代的な個人主義を基礎とした個人対個人のコミュニケーションを指します。まずは外に多様な分野の人たちが個人的に集まってつながり、将来の暮らしの原型や苗代をつくりながら探っていく場に可能性があるように思います。そのような場づくりには、分野を縦横無尽に渡り歩く南方熊楠のような存在や、ある分野を背負いながらもそこに固執しない存在の参加に加えて、いつでも入ったり抜けたりできる多様で流動性のある場をつくることが鍵となりそうです。熊楠のいうところの「人の交わりにも季節あり」の受容といってもいいかもしれません。
加えて、限られた資源をいかしながら、いかに将来世代にわたって生きのびていくことができるかといった社会のサステイナビリティを考えたとき、これまで民衆によって暮らしの必要から長い年数をかけてつくられてきた風景やそれを背景に持った物の変遷、さらにそれらを「民具」(渋沢敬三)、「平民工芸」(今和次郎)、「民芸」(柳宗悦)といったさまざまな言葉をつくり再評価しようとした先達の試みから真摯に学び、これからの将来につなげていくことが必要だと感じています。
このようなことを胸に、現在、私はパーソナルファブリケーションの文化をすすめる「Fab Lab(ファブラボ)」のネットワークに参画し、2013年の年明けからは大阪市住之江区にある協働スタジオ・コーポ北加賀屋★2内に、その関西の拠点をつくり、多様な分野の人たちとともにオープンな実践研究をはじめています。開設以来これまで、エンジニア、デザイナー、美術家、建築家、研究者、行政職員などさまざまな職業の人たちがおもに個人的な関心から集まり、「(almost) anything([ほぼ]あらゆるもの)」をつくることを目標に、参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」を考えています。2014年は、コーポ北加賀屋、国内外のファブラボと協働プロジェクトを展開していきたいと思います。
さて、コーポ北加賀屋では、2014年1月18日から、「(almost) starting over((ほぼ)振り出しに戻る)」★3という展覧会がはじまっています。反射や反復を題材とした松井亜希子さんの銅版画と、時間の反復や一回性をテーマとした東畠孝子さんの彫刻。私も設営を少し手伝わせていただきましたが、硬派で腰が据わっていながらも、水の流れのようにしなやかさのある作品展示となっています。あたたかい格好で、ぜひ足をお運びください。

- 松井亜希子《The candle flickered in the wind, and went out》(2013)
作家提供

- 東畠孝子《River on a Wall》(2011)
作家提供
★1──渋沢雅英『父・渋沢敬三』(1966)より、『アチック・マンスリー昭和10年7月20日号』引用。特別展「渋沢敬三記念事業:屋根裏部屋の博物館──Attic Museum」は、2014年3月21日から5月6日まで、埼玉県立歴史と民俗の博物館で巡回展が開催予定。
URL=http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/?page_id=342
★2──アート、オルタナティブ・メディア、アーカイブ、建築、地域研究、サークル、NPOなど、分野にとらわれない人々や組織が集まる「もうひとつの社会を実践するための協働スタジオ」。
URL=http://coop-kitakagaya.blogspot.jp
★3──2014年1月18日から2月23日まで、会期中の金土日のみオープン。
URL=http://www.adanda.jp/event/140118/
つだ・かずとし
1981年岡山県新庄村生まれ。博士(工学)。資源循環、サステナブルデザイン。大阪大学創造工学センター助教、FabLab Japan Network、FabLab Kitakagaya。共著=『FABに何が可能か──「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』ほか。
土屋誠一
●A1現在私が在住している県でもあり、単に一地方の問題として片づけることのできないことなので記しておくが、昨年末のドサクサで行なわれた、仲井眞弘多沖縄県知事の辺野古埋め立て申請に対する承認を、大きなトピックとして挙げておきたい。私としては、沖縄県宜野湾市のど真ん中に居座る普天間基地は、沖縄の過重な基地負担と、そもそもの危険性とを考えれば、即刻撤去+県外への移設をすべきであるという立場をとる。しかし私が危惧するのは、辺野古の埋め立てが承認されたこと自体は勿論のこと、仮に最悪にも辺野古に新基地が建設されることになるとして、果たして本当に普天間基地が返還されるのか、ということだ。「普天間基地の辺野古移設」とはよく言うフレーズではあるものの、いったい普天間がいつ返還されるのかは、どこにも、そして誰もが明確にできていない。辺野古を埋め立てて、新基地を建設すること自体、面積としては相も変らぬ基地負担を沖縄が負い続けることになるとともに、自然環境を破壊することにしかつながらない。かつ、普天間基地までもが返還されないとなるならば、沖縄はさらに大きな負担を強いられることになるだろう。
この問題は、沖縄の都市開発とも大きく関わっている。普天間基地が撤去されることになれば、地理的には沖縄本島全体の心臓部ともなる普天間跡地が、沖縄県内はもとより、近隣諸地域や諸国と接続する、重要なハブとして機能するはずだからだ。しばしば悪意を持って語られる「基地依存」から脱却し、自立した、サステイナブルな経済圏を確保するためには、普天間が大きなキーとなるのは明白であり、このことは単に日本の一島嶼県の問題にとどまらず、日本という国家がいかなる方向へと舵を切っていくのかが問われている。しかし、対米従属の強化、現政権下の自衛力拡大の路線を見るに、沖縄の「基地問題」は、さらなる苦難に追い込まれつつあるように思われる。近隣諸国との外交関係悪化に、さらなる拍車がかかることを強く危惧する。
一方、震災後の、福島の原発の事後処理すらもままならず、原発事故それ自体が忘却の彼方へと(無理矢理?)追いやられているように見える今日、東浩紀氏らを中心に構想されている「福島第一原発観光地化計画」は、それがいかに破天荒に見えようとも、切実に外交の問題を考えているという点において、将来的なヴィジョンがそこには確実にあるように思われる。国土のデザインとは、一国の問題にとどまるわけではなく、外交問題でもあることを確認するための、モデルケースとしても捉えられるだろう。
-

- 『福島第一原発観光地化計画』思想地図β vol.4-2(ゲンロン、2013.11)
●A2
1とも関わるが、現政権に期待ができない以上、ポジティヴな展望は見いだせない。ただ、個人的な関心の範囲で言えば、美術や芸術全般において、特に日本国内で欠けているのは、個別的な作品や作家に対する分析的批評の言説であることを痛感している。大きな見取り図も必要だが、対象に対する微細な言説を欠いては、日本語で書かれる芸術についての言論は先細りになり、貧しくなる一方だ。この不備を是正するために、自主的なメディアを立ち上げることを構想中である。
●A3
そもそも国家イヴェントであるオリンピックに対して、不快感しかないというのが正直なところではあるが、ひとつ言えることは、何もオリンピックに日本の国家としての威信をかける必要はない、ということだ。オリンピックの開催によって派生するであろうさまざまな都市改造や文化イヴェントは、それに携わる人々はグローバルに開かれたものであるべきであって、日本国内の人材相互の利権争いにとどまっては、国際的に恥をかくだけだ。既にオリンピックの開催は決定してしまっているので、オリンピック自体の是非については特に言う言葉を持たないが、「やらないほうがマシだった」という結果になることだけは避けていただきたいものである。
つちや・せいいち
1975年生。美術批評家。沖縄県立芸術大学講師。共著=『現代アート事典』『現代アーティスト事典』ほか。
永井幸輔(弁護士/Creative Commons Japan、Arts and Law、ファッションは更新できるのか?会議)
●A1
2013年は、共同企画者として参加している「ファッションは更新できるのか?会議」のセッションをまとめた報告書(ジン)★1がリリースされたことが個人的に印象深い。以下、ファッションと法を巡る近年の動きについてコメントしたい。

- 『ファッションは更新できるのか?会議 報告書』(2013)
昨今発展しつつある法分野として、「Fashion Law」に対する注目が国際的に高まりつつある。2000年代後半以降、フォーダム大学やニューヨーク大学などの複数のロースクールがFashion Lawのカリキュラムを設け、2010年にはファッションと法律に焦点をあてた学術機関「Fashion Law Institute」★2が設立された。また、アメリカではファッション分野の法律書『Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives and Attorneys』★3もリリースされており、ボランティア法律家の組織「Volunteer Lawyers for the Arts」(VLA)ではこの本をベースにファッション関係者や法律家向けのセミナーを開催している★4。
日本では、Fashion Lawを積極的に取り上げようとする動きはほとんど目立たず、上記『Fashion Law』の類書も見当たらない。従来から、日本におけるファッション分野への専門性の高い法的マネジメントの提供は、十分だったとは言い難いだろう。加えて、インターネットを利用したプロダクトの小規模な資金調達―製造―流通―販売が実現し、若いデザイナーが活躍の場を広げつつあるいま、その活動を持続的に行なうための法的マネジメントの必要性は明らかに増している。
上記「ファッションは更新できるのか?会議」では、主要なトピックのひとつとして「法律」を取り上げた(vol.3「ファッションのリーガル・デザイン──法律家による分析と提案」)。また、同会議では、たんなる法的マネジメントだけでなく、ジョアンナ・ブレイクリーが紹介したような★5、法的な視座がファッション・デザインにもたらす新しいクリエイティビティにも着目した。例えば、THEATRE PRODUCTSの「THEATRE, yours」★6は、通常オープンにされることのない服の「型紙」をCreative Commonsライセンス★7のもと「改変可能」の条件で公開し、ユーザーが自ら服をつくることの楽しさを、またデザイナーの創造性がユーザーのもとでどのように連鎖して広がっていくのかをデザインしている。インターネットやデジタル・ファブリケーションによるファッション・デザインや制作環境の変化を踏まえ、クリエイションに対する理解のもとでデザイナーと協働できるFashion Lawのあり方が今後一層重要になるだろう。
- ジョアンナ・ブレイクリー「ファッション界の自由な文化から学ぶこと」(TED、2010)
★1──『ファッションは更新できるのか?会議報告書』(2013)は、下記のオンラインストアなどで販売中。
URL=http://www.shibuyabooks.net/commerce/store/items/detail.cgi?sid=40862
★2──Fashion Law Institute
URL=http://fashionlawinstitute.com/
★3──Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys, 2nd edition, Fairchild Books, 2014.
同書では、ファッションを巡る以下のようなトピックが取り上げられている。知的財産権(ライセンス、偽造品対策などを含む)/プロダクトの製造/流通/販売・バイイング/不動産/M&A/フランチャイズ/雇用/マーケティング/広告・プロモーション/リテール・リース/輸入・税関。なお、今年3月には第2版も刊行予定。
URL=http://www.fairchildbooks.com/products/category/116/product/204
★4──Fashion Law, VLA
URL=http://vlany.org/fashion_law.html
★5──ジョアンナ・ブレイクリー「ファッション界の自由な文化から学ぶこと」(TED、2010)
URL=http://www.ted.com/talks/lang/ja/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html
★6──THEATRE, yours
URL=http://theatreyours.tumblr.com/
★7──Creative Commonsライセンス
URL=http://creativecommons.jp/licenses/
●A2
Europeana Fashion portal
絵画、映画、写真、文献などのデジタル化した文化遺産の巨大電子図書館「Europeana」★8のファッション版、「Europeana Fashion portal」★9が2013年12月にオープンした。同サイトでは、ドローイングや服、アクセサリー等を含む数十万のデジタル素材が、フリーアクセスやCreative Commonsライセンスのもとで公開されている。営利目的での利用や改変することも可能なライセンスが付けられた素材も少なくなく、豊富なデザイン・ソースとなる可能性を持っている。
国家規模で急進されている欧米と比べ、日本のアーカイヴィング政策は予算規模としても小さく、見劣りすると言わざるをえない。ただ、今年1月には国立国会図書館による「図書館向けデジタル化資料送信サービス」★10がスタートして話題になっており、幸先のよいスタートを切ってもいる。今後は、公によるアーカイヴィングのさらなる推進に期待しつつも、アーカイヴを利用して新たなデザインを生み出すデザイナー側の動きにも着目したい。
★8──Europeana
URL=http://www.europeana.eu/
★9──Europeana Fashion portal
URL=http://www.europeanafashion.eu/portal/home.html
★10──国立国会図書館がデジタル化した絶版本などの資料を公共図書館、大学図書館などに配信し、各図書館で閲覧できるサービス。2014年1月時点では、図書や雑誌を含む約131万点の資料を閲覧可能。
URL=http://dl.ndl.go.jp/ja/about_soshin.html
coromoza
ファッションデザイナー向けのコワーキングスペース「coromoza」★11。ミシンやプロユースのアイロン台はもちろんのこと、デジタル一眼レフを備えた撮影ブースや、3Dプリンターやテキスタイル・プリンタなどのデジタル・ファブリケーションのための機材を備える。また、「ファッションは更新できるのか?会議」「Think of fashion」「ファッション新リーダー論」「装談」などのトーク・セッションや講座、展示会などの多様なイベントも開催されている。
2013年のオープン以来、多様なファッション関係者が集う、情報共有やデザインの実践の場になりつつあり、次代のファッションが生まれる拠点になる予感を感じさせる。
★11──coromoza
URL=http://za.coromo.jp/
●A3
東京オリンピックの開催決定以来、「東京デザイン2020フォーラム」★12や、「Tokyo 2020 オープンセッション U40編」★13など、デザイナーや建築家、エンジニア、アートディレクター、研究者等が、東京という都市のデザインについて公の場で発言する機会が増えたように思う。
他方で、そのような場に法律家が同席することは少ない。都市計画や建築法制に代表されるように、都市の「ソフト」面である法制度は都市の物理的な造形にも、都市に集う人々の行動にも大きく影響を与える。その意味で、都市における法制度のあり方は都市のデザインに不可欠な一部でもある。
例えば、大阪の老舗クラブ「NOON」が摘発された事件で表出した、風営法によるクラブの深夜営業規制の問題などもその一部だろう。現在の風営法の基準を適用すれば、すべてのクラブは深夜1時以降に営業することはできない。2020年、東京オリンピックが開催された夜に、来日した外国人が、ほとんどのクラブのシャッターが下りた街を見たとき、本当に東京を魅力ある都市に感じるだろうか。都市の安全という視点はもちろんだが、どのような都市に住み、どのような都市文化を育てたいのかという視座のもとで、魅力ある都市をデザインするための法として風営法をとらえることもできそうである。関係各者がそのように知恵を寄せ合うことで、より良い風営法のかたちを模索できるのではないか。
2020年の東京オリンピックは、東京という都市のグランド・デザインを再考する重要な機会であり、その機運も高まっているように感じる。新国立競技場のザハ・ハディド案を巡る活発な議論もその現われだろう。このタイミングは、法制度のリビルドを行なう時期としてもうってつけの筈だ。建築家やデザイナー、研究者とともに法律家が議論に参加することで、法制度も含めた新たな都市のデザインが見えてくるかもしれない。ただ、6年という時間は都市のあり方を変える時間としては長くない。改正に時間のかかる法制度についてはなおさらで、あまり余裕はないだろう。
法をデザインの一部と考え、デザイナーやクリエイターとの協働のなかでよりよい状況やコミュニケーション、クリエイティビティを作り出すこと。東京オリンピックに向けて、その実践を重ねて行きたい。
★12──東京デザイン2020フォーラム
URL=http://tokyo-design.p2.weblife.me/
★13──Tokyo 2020 オープンセッション U40編
URL=http://3-2-1-0.org/tokyo2020-1103
ながい・こうすけ
弁護士。骨董通り法律事務所、Creative Commons Japan、Arts and Lawに所属。「ファッションは更新できるのか?会議」共同企画人。クリエイティブな活動を生む環境自体のクリエイティビティに着目し、法とアート・デザインの間で活動している。現代美術・演劇・ファッション・映画・音楽などのアーティスト・デザイナーから、出版・デジタルアーカイブ・美術館など、クリエイティブに関わる人々に幅広く法務アドバイスを提供。共著=『クリエイターの渡世術』、「法は創造性をつぶすのか」(『広告』2013年5月号)、「今さら聞けないクリエイティブコモンズ」(『WEB+DB PRESS』Vol.59)ほか、「デザイナーのための著作権と法律講座」を月刊『MdN』で連載中(共同担当)。監修=マンガ『ひまわりと天秤』。
成相肇(東京ステーションギャラリー学芸員/評論家)
●A1夏にアンスティチュ・フランセで行なわれた中谷芙二子さんの出版記念シンポジウムが印象に残っています。出版された『FOG』は再読三読しています。それを踏まえて、豊田市美術館「反重力」展の中谷氏の体験も濃密なものとなりました。
加えて、年末のことですが、僕も末席を汚したシンポジウム「思想としてのテレビ 今野勉の映像表現とテレビマンユニオンに関する研究」がすこぶる啓示的で面白かった。松井茂さんが進めるテレビ研究にここ数年触れる機会があり、目から鱗の体験が引き続いています。テレビというメディアがこれほどヴィヴィッドに感じられるとは思ってもみなかった。
-

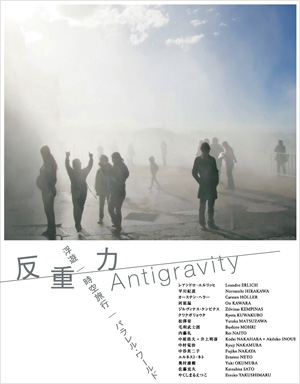
- 反重力展(豊田市美術館、2013年9月14日〜12月24日)
●A2
2014年は職場のある東京駅丸の内駅舎が竣工100周年を迎え、慌ただしくなりそうです。これに関連した企画のために、国鉄(というよりは電通)の一大プロジェクト、ディスカバー・ジャパン・キャンペーンについて調べており、70年代に関心が向いています([1]の回答と大いに関連しています)。どのような現代美術史の概説書でも60年代と80年代の接続が唐突に見える通り、70年代は停滞期としてスルーされてきたようです。主に概念芸術の時代として片づけられてきたのが大勢です。むろん話題に乏しい時代というわけもなく、美術館が扱いづらいコマーシャルな分野が賑やかだったというのが実状のようです。調べてみると特に雑誌の盛り上がりがおもしろく、読み漁っているところです。この頃盛り上がったPR誌の流れもたいへんおもしろい。埼玉県立近代美術館ほかで開催された70年代展が先駆けに位置づけられるでしょうが、より細分化してトピックを拾い上げたいと思っています。今さら○○年代という括りの有効性自体が怪しいところですが、自分の中での自然な成行きとして、ちょうどふさわしい領域が今は70年代にあてはまっているということです。
-

- 開館30周年記念展 日本の70年代 1968-1982(埼玉県立近代美術館、2012年9月15日〜11月11日)
●A3
2020年に開催が決定した「東京オリンピック」について、考えたこと、また現在考えていることについて、お聞かせください。
近くにあるスーパーマーケットの「オリンピック」の方が先に思い浮かぶくらいで2020年のオリンピック自体にはさしあたりまったく関心がありませんが、今後催されるであろう、64年の(第一次)東京オリンピックを回顧・再考する展観などに期待しています。2013年の東京国立近代美術館の「東京オリンピック1964デザインプロジェクト」の資料展示は見応えがありました。これからは直接的・間接的に波及した文化表象がいろいろと出てくることでしょう。思いつくのは横尾忠則による亀倉雄策ポスターのパロディ(これは傑作)とか、今野勉が東京オリンピックをモチーフにしたテレビ番組「土曜と月曜の間」(1964)、村木良彦氏が「東京オリンピック以降の若者たちの解体を横軸に」して演出したという番組「陽のあたる坂道」(1965)など。オリンピックの内容より、その受容過程や波及の方にこそ、僕らが学びうる教えが生きているはずです。
-


- 東京オリンピック1964 デザインプロジェクト(東京国立近代美術館 ギャラリー4、2013年2月13日〜5月26日)
なりあい・はじめ
1979年生。東京ステーションギャラリー学芸員。主な企画展=「石子順造的世界──美術発・マ ンガ経由・キッチュ行」「夏休みこどもびじゅつかん──ミマクル・ミラクル」(いずれも府中市美術館)、「きたときよりも 美しく」(switchpoint)。
成實弘至(京都造形芸術大学准教授/文化社会学・ファッション研究、デザイン研究)
●A12013年は瀬戸内国際芸術祭や愛知トリエンナーレなどの地方発芸術博が例年にもまして話題となり、集客の成果が謳われ、さまざまな地域博覧会がイベントとしてすっかり定着したようだ。こうした芸術博に建築家が「作品」を出すのも見慣れた光景となったが、昨年見たものでいえば、ドット・アーキテクツによる小豆島「馬木キャンプ」が印象に残っている。ローコスト、自力制作による建築を実現するプロジェクトなのだが、面白いのは、建物を建てつつも、その場所をコアとしてメディアイベントを仕掛けて村民と一緒に映画を制作したり、ミニFMを放送したり、家族写真を集めてアーカイブにしたり、動物や野菜を育てたりすることに汗をかく建築家たちの姿であった。住民を巻きこむというより、巻きこまれるというか、右往左往させられて途方に暮れたりしているのが、いわゆる「建築家」のイメージをいい意味で裏切っていて、多様な公共性へのアプローチとして評価したい。
2013年の本としては、多木浩二の『視線とテキスト』『映像の歴史哲学』が編集・出版され、建築、デザイン、メディアの単行本未収録論文が読めるようになったことは喜ばしい。多木の思想の本格的な再評価はこれから進んでいくだろうが、デザインと哲学を深いレベルで結合したその奥行きをきちんと辿らねばならない。
ファッションの分野では、ニューヨーク・ファッション工科大学美術館で開催された「A Queer History of Fashion」(http://www.fitnyc.edu/21048.asp)展をあげておきたい。残念ながら実見していないので内容についてコメントできないが、同性愛とファッションという主題を正面から取りあげた問題作であり、なぜファッションデザイナーに同性愛者が多いのか、同性愛者の服装と流行にはどんな歴史があったのか、ファッション界の長年のアポリアに焦点をあてたものだという。このテーマをどう展覧会に落とし込んだのか、これからの服飾展の方向性を考えるうえでターニングポイントだったかもしれないと思うと、未見なのが惜しい。
-



- 『視線とテクスト』(青土社、2013)/『映像の歴史哲学』(みすず書房、2013)/「A Queer History of Fashion: From the Closet to the Catwalk」カタログ表紙
●A2
昨年台湾でおこなわれたシンポジウムに引き続いて、今年の5月、ロンドンで東アジア・デザイン史会議が開催される(参加予定)。これは1920年代以来の日本、韓国、中国のデザインが近代化のプロセスのなかでどう展開したかを各国のデザイン史研究者が横断的に議論するもの。すでに昨年のシンポジウムでは、日・中・韓のデザイン史が同時代的な問題意識のなかで相互に影響を与えあいながらも独自性をもって発展していることが検証された。東アジアのデザイン・アイデンティティにどんな特質があるのか、さらなる議論の深まりが期待される。
●A3
非東京圏住民としては、正直それほど関心を持っていない(東京圏の人々は日本中が注目していると思っているらしいが、そんなことはないのです)。1964年とは異なり、すでに十分に人も物も金もあふれている発展過剰都市でオリンピックを開催し、さらに都市改造をしようとする意味がよくわからないし、21世紀の新しい都市経済モデルが具体化されればいいが、おそらくそうはならないだろうし。
なるみ・ひろし
1964年生。社会学、文化研究。
西澤徹夫(建築家/西澤徹夫建築事務所)
●A1
3Dフードプリンタ
「宇宙旅行だけでなく人口爆発によって将来起きるとみられる食糧難にも役立つ」とされる、3Dフードプリンタの技術に、NASAが出資しているというニュース★1。いよいよドラえもんの世界が実現するのだと心踊るものがありました。同じような発想と技術がもっと出てくれば、それらはロジスティクスや時間や国境や人的資源の限度といった、いま僕たちの世界を分節しているシステムを一端無効化して、それが引き起こしている諸問題(新しい地球と宇宙の関係、南北の経済格差、戦争や自然災害によるディアスポラ、新たな領土紛争など)を乗り越える契機になるのではないかという気がしました。一方で、銃がプリントアウトできるというLiberatorの発表もありました★2。こちらは直接的には社会にとって悪いほうの影響が大きいのかも知れませんが、それでも先述したようなある種の「乗り越え」には関わってくるような気がします。
エドワード・スノーデンが国家安全保障局(NSA)による個人情報収集を暴露したことによっても、僕たちを取り巻く環境はすでにまったく別のものに入れ替わっていることが明らかになりました。そこでは、個人のプライバシー/共同体としての国家の境界線が知らぬ間に引き直されています。
現行のシステムが分節している世界を、まったく別の空間分布としてとらえ直す必要があるのかも知れません。
★1──「"3Dフードプリンタ"プロジェクトにNASAが出資」(ITmediaニュース、2013年5月22日)
URL=http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1305/22/news080.html
★2──「3Dプリンタで作るプラスティック銃『Liberator』、発砲成功」(ITmediaニュース、2013年5月7日)
URL=http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1305/07/news041.html
原田郁展
CGでつくった仮想の町や建物の風景を描く。これだけでは、建築家にとってはいつもの表現でしかないように聞こえます。しかし窓から見える風景や、風景の側から見た建物を丁寧にマチエールを与えながら執拗に描いていく行為によって、存在しない場所についての仮想の記憶を本当に存在するかも知れない風景へと次第に変えていこうとしているように思えます★3。そして描かれた風景画は、再び仮想の建物の中に飾られ、その様子がまた描かれる。そうやって現実の空間に掛けられた絵画と、仮想の空間に掛けられた絵画が呼応して、見ている者はあっちとこっちを行き来するようになるのです。もうひとつ、ちょっと古いですが、Vincent Van Googleというプロジェクトを見つけたのも2013年でした★4。ビル・ガフィーは、グーグルストリートビューで見つけた世界各地の風景を、それこそゴッホ風に描いているアーティストです。ストリートビューで〈旅〉をしながら〈ロケハン〉し、気に入った場所を描く。ある特定の日時にグーグルによって切り取られた風景をもとに描くことと、実際にその場所に行って風景を切り取って描くことのあいだに、モチーフや場所が時間と空間から切り取られて絵画としてあるということにおいて、本質的な違いはないのかも知れません。
ふたつの例では、日常と身体の延長で風景を描くのではなく、身体を通して知覚したのではないけれど、信じることのできるどこかの風景を描くということは共通しています。少なくとも認識論的なレベルでは、あらゆるものは時間と空間をまたいでこの世界に偏在しています。ここには、これまでにはない空間のとらえ方と表現があると思いました。

- 原田郁(Iku Harada)《HOME-WHITE CUBE #003》キャンバスにアクリル、1,167×1,167mm
★3──原田郁「ひとつの窓と醒める庭」(アートフロントギャラリー、2013年5月2日〜19日)
URL=http://artfrontgallery.com/exhibition/archive/2013_05/1009.html
★4──「Vincent Van Google: Artist uses Street View website to travel the world virtually」(Mail Omlone、2009年9月10日)
URL=http://www.dailymail.co.uk/news/article-1212494/Vincent-Van-Google-Artist-uses-Street-View-website-travel-world-virtually.html
●A2
ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展に期待しています。この100年のあいだに、各国が近代化とグローバリゼーションをどのように受容し変容したか、という社会や制度についてのリサーチを、図面や模型、写真や映像、ワークショップやプレゼンテーション、オーラルヒストリーや数々のドキュメントといったものの網羅性と、それらを俯瞰する観測地点とによってアーカイブすることが、はたして・どのようにして、「今、可能なのか」に興味があります。
●A3
政府が建設現場の外国人雇用拡大を検討しているというニュースがありました★5。東北復興やオリンピックの建設現場では人材不足が深刻だということです。ヨーロッパでは、同じように建設作業要員として受け入れた移民や戦争・経済難民などを多く抱え、社会問題化していると聞きます。日本は、他の先進国に比べればまだ外国籍登録者は少ないようですが、これから多くの外国人の労働力を必要としなければならないことに対して、どのような日本社会にしていくのがいいのか、政治家・国民の関心はそれほど高くないように思います。大量の人間が一度に空間を移動するということには、どういう問題があるのか、どういう解決方法があるのか。スタジアムと周辺の歴史的・文化的な空間の取り合いについてだけでなく、それを支える制度的な空間の変化について、もっと議論が必要であるように思います。当のオリンピックについては、東京ベイゾーンの諸施設をコンペで決めるという話も聞かないし、一連の、さまざまな立場からの発言や議論に対する当局からの回答も聞いていません。オリンピックは6年後の一時の祝祭ですが、政策の一つひとつも一時の勢いでなされることがないように期待したいです。
★5──「外国人労働者、入国緩和 建設人材不足 『単純』解禁も浮上」(産経ニュース、2013年12月31日)
URL=http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131231/biz13123113070005-n1.htm
にしざわ・てつお
1974年生まれ。建築家。西澤徹夫建築事務所主宰。作品=《東京国立近代美術館所蔵品ギャラリーリニューアル》《「建築がうまれるとき:ペーター・メルクリと青木淳」展》《「パウル・クレー|おわらないアトリエ」展》《「今和次郎──採集講義」展》(以上会場構成)、《「津軽」》(舞台美術)ほか。http://tezzo.net/
服部浩之(キュレーター/国際芸術センター青森(ACAC))
●A1
大阪で梅香堂というオルタナティヴ・コマーシャルギャラリーを営んでおられた後々田寿徳さんが2013年12月29日に急逝されました。後々田さんには、都市生活を営むうえで「オルタナティヴ」があるということの重要性や価値を、その静かな活動から教えられました。
僕は青森を拠点としつつ、一年のかなりの日数を異なった複数の都市で過ごすという根無し草な人生を送っています。ただ、一方で自分が暮らす場所を丁寧に楽しみたいという想いもあって、いわゆるオルタナティヴ・スペースを個人的に青森市内で運営しています。複数の道筋や視点を持ち、どんな状況下でも必ず異なった選択肢があるということを意識できることは、いまを生きるうえで非常に重要だと考えています。「オルタナティヴ」とは、誰もが持つ権利としての選択肢であると思います。そのようなオルタナティヴを大阪という都市で約4年間築き続けてきた梅香堂オーナー後々田寿徳さんが急逝されたのは、受け入れがたい出来事でした。「こういう選択肢もあるよ」という道を提示し続けてくれた、僕にとってある意味先生というか人生の先輩であり、芸術に関わる仲間であった後々田さんを失なうことは、都市生活を考えるうえで非常に大きな出来事でした。
少し梅香堂の紹介をします。梅香堂は2009年11月に大阪の此花区にオープンしたオルタナティヴ・コマーシャルギャラリーです。オルタナティヴというのは、後々田さんが指向するアートの方向性が典型的な商業ベースの画廊とは一線を画しているということもありますが、そもそも此花という地区はアート活動などが活発に行なわれているわけではなく、むしろディープな大阪の下町で、そこで商業的にも成立するギャラリー活動を展開すること自体が通常の発想では思い描かれにくいことで、とても特異な存在で、それ自体が極めて特殊な選択肢であると思われるからです。
此花は、後々田さんがギャラリーをはじめたころは、「水都大阪」★1などもあって少しずつアーティストたちが集まる地域になりつつありましたが、現在のような活況が生まれるとは想像できませんでした。此花の紹介をするのが今回の主旨ではないし、それを語るべき方はたくさんいらっしゃると思うので、ここではこれ以上の詳述は控えたいと思います。
後々田さんは縁があってこの土地に辿り着き、ここで暮らしながら梅香堂を細々と、でも非常に丁寧に豊かに続けておられました。青森に住んでいる僕は、そんなに度々来訪できるわけではないけれど、それでも関西に行く際にはほぼ必ず梅香堂に立ち寄っていました。大阪に用事がなくても京都くらいまできたら寄ってみようかなと思える場所なんです。何をするでもなく、そこに後々田さんがいて梅香堂があるから訪れるという存在でした。そういう場が存在する街は非常に羨ましく思います。
梅香堂は不特定多数の人がそのように感じる場所では決してないけれど、少なくとも僕にとっては大阪に行く理由をくれる場所でした。コマーシャルギャラリーと称しているけれど、ギャラリーと聞いて想像されるおしゃれなホワイトキューブとは真逆の、個人の独特な美学や経てきた歴史、その価値観が強烈に香る空間です。建物自体がぼろぼろの川辺の倉庫で、内装はダークグレーのトタン波板で覆われ、2階展示室の中央には90センチ四方の小さな吹き抜けがあり、どう考えても作品展示がし易い空間ではありません。しかし、そこでは驚くほど素晴らしい展覧会がいつも実現されています。もちろん僕は毎回鑑賞することは不可能で、数回の展覧会しか経験できませんでしたが、本当に嫉妬するくらい素敵な展覧会があの場所で起こっていました。どうやったらアーティストをあそこまで本気にさせられるのか、その関係の作り方ひとつとっても完敗だと思わされることがほとんどでした。悔しいのでその原因というか原動力を考え続けたのですが、ひとつだけとてもシンプルな答えがわかりました。それは後々田さんの徹底した愛情があの空間へ、そして作家へと注がれていることです。梅香堂ウェブサイト★2で公開しているカタログのテキスト★3を読むと、作家へのこだわりや愛情がよく伝わってきます。その人がどのような人で、どういうことを考え創作活動を営み、現在に至ったかの背景をつぶさに調べ上げて紡がれた言葉です。アーティスト・イン・レジデンスという作家の制作環境をつくり、その制作に寄り添う現場にいる僕にとっては、本当に見習うべきことの多い優しくて良質なテキストです。
ここで、4年以上前にオープン直前の梅香堂を取材させてもらった際の記事を紹介します★4。また、同じartscapeの企画のなかで、僕が青森で営むMidori Art Center(MAC)にて、後々田さんのお話を伺い対談をさせていただいた際の記録もしっかりとまとめられています★5。
梅香堂というスペースは細部まで後々田さんの手が丁寧に行き届いており、その空間自体が後々田さんそのものと言えます。個人の意思が色濃く反映された空間は、当たり障りのない展覧会の場としては不向きでしょう。しかし、その個人が素晴らしいと信じたアーティストが、まるでその人に見守られているかのような空間で制作に打ち込むことで化学反応が起こって、一歩抜きん出た展覧会が実現するのだと思います。後々田さんは、自分がよいと思ったら、ある距離感を保ちつつ見守りながらも、徹底的に付き合い形にしていきます。自分の意思で考え、選択し、そしてそれに責任をとることの切実な意義を、あまり多くは語らないその姿勢に学びました。
何が言いたかったかというと、結局自分のやりたいこと(やるべきこと)をシンプルに追求し、考え、選択し、どんな場所にいようがそこから自身の生きる環境を築くことで生まれる豊かさを、大阪此花区で梅香堂という比類なきオルタナティヴな場をつくり続けた後々田さんから教えられたということです。いつどこでどんな状況になろうと、そこには選択肢がまだ無数にあるということをずっと忘れないようにします。そして、大多数のためでなくても、王道ではなくても、ほんの少数でもよいのでなんらかの価値を見出してもらえる「オルタナティヴ」をつくっていきたいと思います。

- 梅香堂外観(2009年9月25日撮影)

- 同上(2012年1月22日撮影)

- 下道基行展「AIR / 空」開催中の梅香堂内観(2010年1月4日撮影)

- 下道基行展「torii」開催中の梅香堂内観(2013年11月16日撮影)
すべて筆者撮影
蛇足になるかもしれませんが、一応昨年印象に残った展覧会などあげておきます。東京都現代美術館で開催された「MOTアニュアル2012:風が吹けば桶屋が儲かる」★6は、このような展覧会が公立美術館で開催されるようになったことに対して驚きを覚え感慨深くも思いました。日常生活と地続きの事象に小さなアクションを起こすことで、その風景をささやかに変革する取組み。参加アーティストやその周辺でさまざまな実験的な試みや議論が巻き起こったことも、特筆すべきだと思います。
もうひとつは同館にて2期に分けて開催された「フランシス・アリス」展★7です。ユーモアとウィットに富んだ見事な手法で見えない境界を鮮やかに描出するアリスの態度には、現在の複雑な世界の現状を肯定しつつも批評的に生きるたくさんのヒントが散りばめられていました。
★1──「水都大阪2009」は2009年8月22日(土)〜10月12日(月)に開催された。100名以上のアーティストが参加した同イベントに合わせて、来阪するアーティストの滞在場所となるゲストハウス・モトタバコヤが此花区にて運営された。また、参加アーティストの藤浩志やKOSUGE1-16は此花区にスタジオ兼滞在場所を備えていた。
★2──梅香堂
URL=http://www.baikado.org/
★3──現在開催中の下道基行「torii」のオンラインカタログ。
URL=http://issuu.com/baikado/docs/shitamichi_c/1?e=6604054/5567467
★4──服部浩之「後々田さんの『梅香堂』_baikado」(「artscape BLOG」、大日本印刷、2009)
URL=http://www.artscape.ne.jp/artscape/blogs/blog2/2009/10/_baikado.html
★5──Dialogue Tour 2010 第1回:後々田寿徳×服部浩之「梅香堂のはなしを聞く@Midori Art Center(MAC)」(「artscape」、大日本印刷、2010)
URL(プレゼンテーション)=http://artscape.jp/dialogue-tour2010/1218380_3388.html
URL(ディスカッション)=http://artscape.jp/dialogue-tour2010/1218382_3388.html
★6──「MOTアニュアル2012:風が吹けば桶屋が儲かる(Making Situations, Editing Landscapes)」(東京都現代美術館、2012年10月27日〜2013年2月3日)
URL=http://www.mot-art-museum.jp/exhibition/140/
★7──「フランシス・アリス」展(第1期=MEXICO SURVEY メキシコ編、2013年4月6日〜6月9日/第2期=GIBRALTAR FOCUS ジブラルタル海峡編、2013年6月29日〜9月8日)
URL=http://www.mot-art-museum.jp/alys/
●A2
2013年はアジア各国の同世代の刺激的な人々と、よい議論ができ一緒にプロジェクトを実現できた1年でした。それを日本でアウトプットするひとつの方法として、東南アジア4カ国で開催した展覧会「MEDIA/ART KITCHEN - Reality Distortion Field」★8の日本バージョンを今夏に青森と山口で同時期開催で実施する予定で、こちらも力を入れて展開したいと思います。
2014年は自分が寄って立つ「アジア」とはいかなる場所なのか、どのような境界線上を生きているのか、そしてこの境界を渡り歩くなかでなにができるのかを、もっと意識的に考え、言葉や実践に落とし込んでいきたいと思います。現在「Alternative Lives」というサイトを立ち上げ準備中で、それをアジアという背景を意識しつつ展開したいと考えています。
また、今年は福岡アジア美術館で「第5回福岡アジア美術トリエンナーレ」が開催されると思います。どのようなテーマで展開されるのか興味を持っています。
レム・コールハースがディレクターを務める「第14回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展」にも注目しています。
それから、ヨコハマトリエンナーレへの参加や東京ヘテロトピアを拡充させていくなど、継続的プロジェクトを推進しアジアでの新たな展開も想像されるPortBの活動にも注目しています。

- 「M/AK Bangkok」展示風景。3都市を経て最後の会場となるBangkok Art and Culture Center(BACC)(会期=2013年12月21日〜2014年2月16日)
★8──日本と東南アジアのメディア・アート展「MEDIA/ART KITCHEN - Reality Distortion Field」(国際交流基金、2013-2014)
URL(詳細)=http://www.jpf.go.jp/j/culture/new/1307/07-07.html
URL(公式ウェブサイト)=http://mediaartkitchen.tumblr.com/
●A3
率直に述べるとオリンピックという一過性の祭典にあまり左右されることなく基本的に自分のできることを積み重ねていこうと思います。ただ、オリンピックに向かうことで、地方が必然的に搾取される日本の構造的な問題がより明確になり、さらに拡大していくのではと危惧しています。今後どのような拠点を持つべきか(地盤を築くべきか)、そしてどこにどのように税金を納めるか、意識的に考え選択していきたいと思います。
また、オリンピックの開催自体を悪いこととは思いません。しかし、オリンピックがどのようなスタンスで開催されるのかは重大な問題だと思っています。現状だと、オリンピックという祭典によって、そのすぐ裏側にある現実が覆い隠されたり、忘却されるのではという恐れを抱いています。オリンピックに浮かれるのではなく、現実のリスクと問題を直視する社会を築いていかなければなりません。東日本大震災から10年も経たない2020年にどんな日本の姿を描き出せるのか。それは世界から与えられた大きな課題であり、これから私たちはいかなる選択を重ねていくか、個々人が一手一手を真剣に考えていかなければと思います。そしてその選択の先に、東京以外の都市がより魅力的だと思われるようになり、人口分布が変化し分散していったら日本には少しだけ未来が開ける気がします。
はっとり・ひろゆき
1978年愛知県生まれ。早稲田大学大学院修了(建築学)。青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)学芸員。Midori Art Center(MAC)主宰。2013年は「trans×from─かたちをこえる」(ACAC)、十和田奥入瀬芸術祭「SURVIVE──この惑星の、時間旅行へ」(十和田市現代美術館、奥入瀬エリア)、「MEDIA/ART KITCHEN -Reality Distortion」(東南アジア4都市)などに従事。
平瀬有人(建築家/yHa architects)
●A1
塩塚隆生《Silent House》(2008)、藤本寿徳《田尻の家》(2010)
3月と11月に二つの建築を取材させていただいた(『住宅特集』(2013年5月号、2014年1月号、新建築)。偶然ではあるが、じつはどちらも以前より拝見したいと思っていた建築であり、光栄な機会であった。《Silent House》は、おおよそ私たちが慣習的に建築に必要な要素だと認識しているプロダクトの姿の見えづらい、砦を水平に九十度回転させたモノリスのような塊のような建築。自律的に力強い形態や素材感を持ちながらも、他律的に大地と融合して感じられる、まるで遺跡のようなありようであった。《田尻の家》は、海を巡って繰りひろげられるさまざまな「生活」に対応した機能を持ち、漁港という場所の持つ「イメージ」からつくられた、護岸や堤防がやや肥大化したマッシヴなボリュームの「形態」を持つ、アルド・ロッシの言うような都市の要素の集合体=「都市的創成物」としての建築。サンドブラストによるコンクリート表面のザラザラな肌理のマテリアリティは、護岸や堤防のような解像度の粗い表情を見せ、土木構築物に囲まれた場所との呼応を感じた。

- 塩塚隆生《Silent House》(2008)

- 藤本寿徳《田尻の家》(2010)
松村正恒《日土小学校》(1958)
愛媛県八幡浜市立日土小学校は、市の職員として勤務していた建築家・松村正恒氏によって設計された2階建て木造建築である。戦後モダニズム建築を木構造で実現した極めて稀な事例であり、南面を流れる川に張り出す配置計画やクラスター型教室配置による両面採光などの特徴がある。筆者の学生時代の小学校課題のときにリファレンスとして紹介されて以来かねてから訪れたいと思っていたのが、ようやく昨年実現した。子どもがいきいきと走り回る素晴らしい空間であった。

- 松村正恒《日土小学校》(1958)、喜木川に張り出したテラスのある南東側外観


- 左=同、蹴上が低く踏面が広い階段
右=同、川に面した図書館


- 左=同、階段室
右=同、透明感溢れる主玄関と昇降口
鈴木了二『建築映画 マテリアル・サスペンス』
「10+1 website」の刊行特集(2013年4月号)にも寄稿させていただいたが★1、鈴木了二さんの著書のなかでこの書は異質だ。この書の装いは装丁はもちろんのこと紙質に至るまですべてが秀逸に考えられており、たんなる情報の束なのではなく、手にとったときの物質感や重量感などがレイアウトされた多感覚的なメディア、つまり奥行きや深さをともなう建築的オブジェとなっている。一見この書物は映画評論のようだが、歴然とした日本の現代建築に対する強烈な批評のメッセージを含有した建築書であるように思える。映画を語ることを通じて、「社会性」や「共同体」や「プログラム」といった「意味」を漂白したあとの建築のありようは何かを問う。装いは軽快だが、内容はじつに重い。
いえつく+猪熊純+大西麻貴+木内俊克+田根剛+栃澤麻利+成瀬友梨+平瀬有人+藤原徹平『やわらかい建築の発想──未来の建築家になるための39の答え』
さまざまな質問に若手建築家が答えるかたちで建築的思考のプロセスを紹介する書。ストレートで素朴で単純な質問にそれぞれの立ち位置を明らかにしつつ回答している。筆者も寄稿しており、「建物の中で一番重要な要素は何ですか?」「建築の世界ではどんな人材が求められていますか?」「厳しい建築の条件はどう克服して進行させていますか?」「注目しているマテリアルは何ですか?」「『自然』との付き合い方を教えて下さい。」「『人生』って何ですか?」という問いに答えている。
マテリアライジング展
デジタルファブリケーション技術の発展から、近年ものづくりの現場では「モノを考えること」から「モノを作ること」へのプロセスの変化がみられる。この展覧会はそうした潮流にまつわる研究・作品を集めたものである。2010-11年の10+1アンケートにも挙げているが(「デジタルファブリケーション/ETH-Z CAAD講座」)★2、日本にもそのような試みが流布してきたのは興味深い。個人的にはアートピースやインスタレーションではなく、建築への応用の機会を探りたい。
「計算折紙(コンピューテーショナルオリガミ)のかたち」展
折紙は紙を折ることでさまざまな形をつくる伝統的な遊び、創作活動であるが、その研究は幅広く、数学、情報科学、材料科学、構造工学、建築、デザイン、芸術、教育、歴史など多岐にわたる興味深いテーマである。そのデザインと工学応用の可能性を紹介した展覧会が東京大学で開催された。折紙のなかでおそらく一番有名な折り方は「ミウラ折り」だろう。人工衛星のパネルの展開方法を研究する過程で生み出された地図や飲料缶などに用いられている折りたたみ方だ。2012-13年の10+1アンケートにも挙げているが(「コンピューテーショナル・デザインと立体折紙」)★3、計算折紙という分野は、建築の形態生成においても多くの可能性に満ち溢れている。
アントニオ・ロペス展
スペインを代表する画家アントニオ・ロペス(1936-)の日本初の個展。筆者はかつて画家の藪野健さんの講義中に紹介された映画『マルメロの陽光』(監督=ビクトル・エリセ、1993)★4でロペスを知り、興味を持っていたのだが、ロペス絵画の全貌はほとんど知らなかった。渋谷で一度見たものの脳裏に強く残ったので、長崎へも再度見に立ち寄った。《トイレと窓》(1968-71)、《バスルーム》(1970-73)、《新しい冷蔵庫》(1971-74)などは、とくに印象的な作品であった。日常の生活をモティーフに気の遠くなるほどの時間をかけた描写は、人間、時間、場所という都市のありようを、われわれ人間の営為を、描写することにほかならない。
未来を担う美術家たち 16th DOMANI・明日展
文化庁が1967年度より実施している新進芸術家海外研修制度の成果発表の展覧会である(国立新美術館、2013年12月14日〜2014年1月26日)。今展でははじめて「建築」のジャンルを取り上げ、43名の建築家と8名のアーティストによる表現が一堂に会した。筆者も近年のプロジェクトを出展させていただいた。筆者は6年間の学生時代・6年間の実務経験を経て本研修制度にてスイスに1年間滞在したが、帰国して6年経つ現在、スイスを経ての6年間の成果を発表するとても良い機会であった。






- 『建築映画』/『やわらかい建築の発想』/マテリアライジング展
「計算折紙のかたち」展/アントニオ・ロペス展/DOMANI・明日展


- 「DOMANI・明日展」展示風景
★1──平瀬有人「建築のエモーショナルな感受性へ」(「10+1 website」、LIXIL出版、2013)
URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2013/04/post-69.php
★2──2010-2011年の都市・建築・言葉 アンケート
URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2011/01/issue1.php#465
★3──2012-2013年の都市・建築・言葉 アンケート
URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2013/01/enq-2013.php#2191
★4──マルメロを描くロペス自身の姿を撮ったもの
●A2
『模型で考える──マテリアルとデザインのインテグレーション(仮)』(2014刊行予定)
じつは昨年のアンケートにも挙げさせていただいたのだが、筆者の都合で刊行予定が遅れてしまった。現在鋭意準備中である。日本の建築教育や設計の現場でつくられるモデルはスチレンボードによる白模型がほとんどであるが、こうしたスタディからは抽象的な面の構成以上の発想にはつながらないことが多い。面の構成にあとから素材を貼り付けるといういわばハリボテ建築ではない、マテリアルから展開する建築のありようはないだろうかという視点から書籍の刊行を準備している。本来ならマテリアルとデザインはインテグレートされるべきものであるはずなのだ。石膏、油土、木材、紙、金属、樹脂といった素材をどのように結構(techtonic)、構成(composition)するか。たんなる教科書的な視点を超えた新しい模型論を展開したいと考えている。
『建築グラフィックスの論理と実践(仮)』(2014刊行予定)
建築家・坂牛卓さんと刊行準備中の書籍。建築グラフィックスはたんなる説明ではなく表現であり、現代的視覚におけるヒエラルキーとフラット及び論理と感性のなかでの位置づけを鮮明にすることこそが重要である。コンペのプレゼンボードのみならず、絵画やグラフィックデザインなどの数多くの事例を参照しつつ論理を探り、実践を紹介する。
「韓国交通大学校(韓国)」「タマサート大学(タイ)」との国際ワークショップ
佐賀大学では、2013年夏には韓国交通大学校との、2013年秋にはタマサート大学、北九州市立大学との国際ワークショップを開催した。それぞれ1週間程度現地に滞在し、現地の敷地を題材に共同で建築・都市デザインの提案をまとめるというものである。2014年も開催予定。猫も杓子もグローバルという標語を抱えて大学間交流が進むなか、このワークショップの主眼はなにか。けっしてグローバル・コスモポリタンを育てるということではない。例えばスイスの建築家ギオン・A・カミナダは人口約250人のグラウビュンデン州フリンで地域の伝統構法を用いながら伝統と新しさが統合された建築をつくりつつ、スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH-Z)で教鞭をとり作品集を出版している。グローバルでローカル。そんなグローバルな視野を持つローカリティを育てたい。
《KFG》(2009-)
以前のアンケートにも掲載したが、佐賀県鹿島市に位置する1899年創業の酒蔵の改修計画を進めている。450石にも満たない小さな酒蔵ではあるが、2011年の世界一の受賞を契機に観光客が各地から訪れるようになり、ショールームやギャラリー・オフィスなどの整備が必要となった。1号蔵、旧精米所、麹室は1921年竣工の登録有形文化財であるため、古くから残る建築の祖形を際立たせつつ新しい要素を入れることで所与の空間や古いものがさらに良く見えるような建築的介入(Architectural Interventions)の計画を進めている。2012年には木造の母屋の一部をショールームに改修し(《KFG-os》)、2013年にはオフィスの改修(《KFG-oo》)及び洗米機を収容するための洗米棟を設けた(《KFG-s》)。今後は、2014年に蔵の一部をラウンジに改修(《KFG-l》)、登録有形文化財の旧精米所(1921年竣工)をギャラリーにする改修や(《KFG-g》)、損傷が激しい母屋をオフィスと住宅棟に建替える計画(《KFG-o》)、同じく登録有形文化財の1号蔵をイベントスペースに改修する計画などを予定している。

- 左=《KFG-s》(洗米棟)/右=《KFG-g》(登録有形文化財ギャラリー改修)

- 《KFG-os》(ショールーム改修)

- 《KFG-oo》(オフィス改修)
《KFG》の写真はすべて、(c)Y.Harigane (Techni Staff)
《OHH》(2013-14)、《KNH》(2013-15)、《SIH》(2013-14)、《FHN》(2013-14)
東京、福岡、佐賀で、住宅、集合住宅、保育園などのプロジェクトを進めている。ミリューからマテリアルへ★5。近年考えてきたことが実現しつつあり、楽しみである。
★5──ミリュー(milieu、「社会的・文化的環境」を意味するフランス語
ひらせ・ゆうじん
1976年東京生まれ。2001年早稲田大学大学院修士課程修了後、2004年同大学院博士後期課程単位満了。ナスカ・早稲田大学理工学部建築学科助手・同非常勤講師を経て、yHa architects共同主宰。2007-08年文化庁新進芸術家海外留学制度研修員(在スイス)。2008年より佐賀大学准教授。2010年佐賀大学大学院工学系研究科准教授。
藤村龍至(建築家/東洋大学理工学部建築学科専任講師、藤村龍至建築設計事務所代表)
●A1
五十嵐太郎氏が芸術監督を務めた「あいちトリエンナーレ」での宮本佳明《福島第一さかえ原発》と東浩紀氏らによる『福島第一原発観光地化計画』はともに福島第一原発を対象としており、「絆」「つながり」のキーワードで括られるプロジェクトが多いなかで特に後者は現地住民や東京電力関係者、政治家をはじめとして多くのオピニオンを巻き込み日本の戦後史全体と将来像を俯瞰し、社会に広く問題提起する内容になっており、震災以後の言説やアート、建築プロジェクト全体に対する批評性があると感じました。

- 『福島第一原発観光地化計画』(ゲンロン、2013)
12月末にゲンロンカフェで6日間限定でゲリラ的に行なわれた「『フクシマ』へ門を開く──福島第一原発観光地化計画」展は、文学が音頭をとり、アート、建築、写真、映像、音楽、ファッションなどの分野が連動して作り上げた展示ということでその内容とともに長く記憶に残るユニークな展示になったと思います。
建築ではdot architectsの《Umaki Camp》が印象に残りました。阪神・淡路大震災にルーツを持つ彼らの思想が小豆島の場所で結実し、小豆島町の塩田町長の社会保障のビジョンと共振している点に感銘を受けました。
他方、GAギャラリーの「設計のプロセス」展ではプロセス表現の多様化が、ヒルサイドギャラリーの「SDレビュー」では社会状況との関係が重視されており、ファインアート寄りだった空気が少しずつ政治寄りに戻っていると感じました。
アートといえば東京都現代美術館「うさぎスマッシュ」展が印象に残りました。特にスプツニ子!さんの《ムーンウォークマシン、セレナの一歩》は日本人理系女子というキャラクターが、月面着陸をはたしたニール・アームストロングのマッチョな英雄性と対比されており、自己啓発本を装った新刊『はみだす力』と合わせて、ベタ化して久しい1995年以後の日本の文化的状況に対しなかなか皮肉が利いていて面白かったです。

- スプツニ子!『はみだす力』(宝島社、2013)
●A2
「ART and ARCHITECTURE REVIEW」でもオリンピックに関する特集を組みました(http://aar.art-it.asia/fpage/?OP=backnum&year=2013&month=10)。
新国立競技場の問題のみを考えるというよりは、会場計画全体のあり方、さらには巨大イベントと化した現代オリンピックがグローバルシティに与える影響全般について考える必要があると思います。
晴海の選手村半径8キロの円内に収められたオリンピックの全体計画は、ロンドンのような政治的メッセージは感じられないものの、1970年代以降に新宿、池袋、渋谷へと展開した東京の重心を、都心3区および湾岸に回帰させる明快な意図を感じます。晴海周辺の湾岸がグローバルなビジネスセンターとなり、渋谷や新宿がアジアからの買い物客の目標へと転換するという状況は、丹下健三の「東京計画1960」と槇文彦氏の「見えがくれする都市」、八束はじめ氏に倣えば「ベイエリアン」と「インランダー」の対比と比較可能であると言えます。
他方、東京がグローバルシティとしてさらなる発展を遂げていくのはよいとして、日本における東京の地方都市との格差のますますの拡大が懸念されます。かつて首都機能移転として議論されていたこの問題が、現在は道州制など制度設計を中心にして議論されることになっていますが、2020年以後の東京、および格差解消を念頭に置いた施策をいまから議論していく必要があると思われます。
東洋大学で地元自治体や地元協議会と協働して継続的に取り組んでいる「鶴ヶ島プロジェクト」や「大宮東口プロジェクト」などのソーシャルデザイン・プロジェクトは、こうした「2020年以後」の状況をにらんで仕掛けられていますが、建築界も今後しばらくはアジアとの関係でのグローバルな活動と、国内でストックのマネジメントを行なうドメスティックな活動に二極化するものと思われます。
ふじむら・りゅうじ
1976年東京生まれ。建築家。東洋大学理工学部建築学科専任講師。藤村龍至建築設計事務所代表。作品=《BUILDING K》《東京郊外の家》《倉庫の家》《小屋の家》ほか。編著書=『1995年以後』『アーキテクト2.0』『3・11後の建築と社会デザイン』『コミュニケーションのアーキテクチャを設計する』『リアル・アノニマスデザイン──ネットワーク時代の建築・デザイン・メディア』ほか。http://ryujifujimura.jp/
牧紀男(京都大学防災研究所巨大災害研究センター准教授/防災学)
●A1南海トラフの巨大地震では230兆円(日本の国家予算の2倍以上)の経済被害が出るという想定が3月に、首都直下地震では死者2万3千人、全焼・全壊61万棟、経済被害95兆円という想定が12月に公表された。また、大阪府では大阪市の中心部が水没するという想定も行なわれている。こういった被害想定の見直しは、東日本大震災の反省を踏まえて実施されたものである。実際に被害が発生した東日本大震災ではさまざまな被災地支援が、建築家により行なわれた。
首都直下地震では、火災による被害が甚大であり、密集市街地が問題ということになっている。私たちが「いいな」と思うような路地空間や建物が目の敵にされている。実際の被害が発生する前から、いい都市空間を守りつつ、災害の被害を減らすようなこころみについての取り組みがわれわれに求められている。何かが起きたときだけ、大騒ぎをするのはよくない。
●A2
今年は『復興の防災計画』(鹿島出版会)という本を書きました。『災害の住宅誌』(鹿島出版会)の続編です。東日本大震災の被害を踏まえて、今後発生することが予想される南海トラフ地震にどう備えるのか、という内容です。災害で被害が発生することを前提とした「まち」という考え方を「とりもどす」必要があると思っています。
震災関連のイベントでは、神戸大学の槻橋さんが中心になって実施している「失われた街:模型復元プロジェクト」がすばらしいと思います。震災前の記憶に加えて、災害からの再建のプロセスも記録として残していくような試み(例えば、家を建てたら家の模型を街の模型の上に置きにくるとか)もあればいいな、と思います。
-

- 『復興の防災計画』(鹿島出版会2013.6)
●A3
防災・危機管理業界では、すでに東京オリンピックのBCP(Business Continuity Plan)、BCM(Business Continuity Management)ということが議論されています。BCP、BCMは業務継続計画、業務計画マネジメントと訳され、災害もしくは危機に見舞われた際に、迅速に業務を回復することを可能にするための計画・試みです。
被害が出ないことを前提とするのではなく、東京オリンピックが地震やその他の災害に見舞われることを前提として、災害に見舞われたらどうするのか、ということを考えておくことは重要です。オリンピック開催直前に東京が地震に見舞われたら、また、開催中に地震に見舞われたらどうするのか、といったことが検討されはじめています。
まき・のりお
1968年生。著書に『災害の住宅誌──人々の移動とすまい』『組織の危機管理入門』ほか。
松田達(建築家/東京大学先端科学技術センター助教)
●A12013年、もっとも印象深かった出来事といえば、2013年12月1日に東京大学で行なわれた、槇文彦、磯崎新、原広司をゲストに、隈研吾を司会に開かれたシンポジウム「Architectural Theory Now:これからの建築理論」(http://www.obuchilab.com/dfl/?p=704)である。おそらくこの御三方のうち、2人が同席しているところを見るだけでも珍しい出来事だと思うが、3人が揃い、そして隈氏が司会をつとめるとなれば、これは事件だ★1。それぞれの年齢もこの時、槇文彦85歳、磯崎新82歳、原広司77歳と、平均年齢80歳を超える。にも関わらず、3者のあいだでなされた話は、日本の建築界における最先端の話であったといえよう。単なる昔話では、けっしてない。内容的には、議論というより、3者がそれぞれの立場を語ったともいえる。モダニズムが一艘の船から大海原へと変化したことを語る槇氏、建築史家による「批評」と建築家による「理論」の違いを提示する磯崎氏、空間の統一理論に向けて建築家が遅れてはならないとする原氏。文脈も方向性も、ある意味バラバラである。しかし、それも半ばは予想されたこと。何よりその3人が同居する場が設定されたことが重要だったと思う。そこから見えたのは、むしろ3氏の距離であり、軸が異なることによって、日本の建築理論の広がりを見たような気がした。さらにそこには相互の「絡み」があった。それぞれ独自の道を歩んできた3人の大建築家が、再び互いの距離を測定する瞬間を垣間見た気がして、その一言一言のやりとりが、極めて強く印象に残った。
-

- 「Architectural Theory Now:これからの建築理論」
その他、2013年の出来事を振り返っておきたい。岩波書店から、全8巻となる『磯崎新建築論集』(http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/028601+/top.html)のうち、第7巻までが刊行された。磯崎氏の半世紀に渡る膨大な思考の軌跡は、けっしてすぐには消化されないだろう。しかし、それでよいと思う。特に磯崎新の著作をこれまで読んだことがない世代には、すぐに消化した気にならず、じっくり読んでみてほしいと思う。いかに刺激的な内容であるかが、次第に見えてくるはずだ。特に、冒頭の「反回想」の面白さは際立っている。これが傘寿を超えた人物の書く内容なのかと、各巻ごとにその文章の「若さ」に驚かされる(なお、2月9日には青山ブックセンターにて、第2巻『記号の海に浮かぶ〈しま〉』を手がかりに、磯崎氏と都市工学者羽藤英二氏の対談「都市に未来はあるのか──建築と都市工学の対話」が行なわれるので、こちらにもぜひご注目されたい(http://www.aoyamabc.jp/event/isozaki-review2/)。
2013年はまた、丹下健三の生誕100周年であり、さまざまなイヴェントが催され、刊行物が出版された。その盛り上がりのなかで、ほとんど触れられることのなかった丹下健三の1975年から1990年頃の海外の都市計画を中心としたプロジェクトについて、筆者は隈研吾にインタヴューをさせていただく機会を得た(「知られざる丹下健三──海外プロジェクト・都市計画を中心に」)。先に挙げたシンポジウム「これからの建築理論」とも関連する内容となっているので、興味を持たれた方はぜひご一読されたい(このインタヴューの直後、隈氏から直接に12月に予定されているシンポジウムの話を聞いた)。
9月には、金沢で「歴史的空間再編コンペティション2013 第2回「学生のまち・金沢」設計グランプリ」(http://www.kanazawagakusei-compe.com/)が開催された。一見すると地味に見えるかもしれないテーマであるが、このコンペティションのテーマこそ、2010年代に建築・都市に携わる人が、考えるべき内容であると思う。ゼロから新しく空間をつくるのではなく、すでにある歴史的空間を再編すること。作品をそこに絞っている点が、このコンペを特徴づけている。グランプリを決める最後の瞬間、2案に審査員の立場が分かれ、今後の同コンペティションの方向性にも関わる議論が繰り広げられた。このような議論が継続的に繰り広げられるコンペティションへと育ってほしい。
10月には、建築学会の建築文化週間の一環として、建築夜楽校2013が開催された。テーマは「アーキテクト and / vs アーバニスト」(http://www.kenchiku.co.jp/bunka2013/night/)。筆者はシンポジウムのモデレーターと展覧会のキュレーションを担当させていただいたが、建築分野の論客と都市分野の論客が同じ場で語り合うこのようなシンポジウムを開くことは、長年思い描いていたことだっただけに、感慨が深かった。その内容については、『建築雑誌』2014年2月号に活動レポートを掲載予定であるので、よければそちらをご確認いただきたい。
最後に、年末に著者からご本を恵贈いただいた八束はじめ氏の新刊『ル・コルビュジエ──生政治としてのユルバニスム』(青土社)(http://www.seidosha.co.jp/index.php?9784791767557)についても、ぜひ挙げておきたい。もともと『10+1』誌に「思想史的連関におけるル・コルビュジエ」として連載されていたものである。1930年代のル・コルビュジエをひとつの中心としながらも、むしろそこから内容は広く展開し、フランスの都市計画(ユルバニスム)にまつわる諸事情などさまざまな連鎖(ネクサス)が書き込まれており、連載当時から、その圧倒的な情報量に敬服していた。今回、書籍としてまとめられるとともに、タイトルの「生政治」にもあるようにフーコー的な視点が追加されることで、八束氏の思考がより奥行きのある歴史的パースペクティヴのなかに位置づけられることになるのではないかと思う。
●A2
2013年から2014年にまたがってであるが、2つの展覧会が開催されている。国立新美術館で開催されている「16th DOMANI・明日展〈文化庁芸術家在外研修の成果〉」(1月26日まで)(http://domani-ten.com/)と、NTTインターコミュニケーションセンターで開催されている「磯崎新 都市ソラリス」展(3月2日まで)(http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2013/ISOZAKI_Arata_SOLARIS/index_j.html)であり、奇しくも両者とも同日2013年12月14日から始まっている。筆者もそれぞれ出展者、アドヴァイザーとして関わっている。前者はこれまで美術分野の展覧会であった同展に、今回はじめて建築家が参加した。建築分野は、幅1.5m、奥行き2.7m、高さ3.6mという、おそらく展覧会のスペースとしてはあまり見ないような路地的空間である。43名の建築家がその空間をいかに使いこなすのか、その多様性を一望できるような展示となっていた。後者は会期が大きく3期に分かれ、それぞれの会期で内容が大きく変わるという。会期中は一枚のチケットで何度でも再入場可能であるそうなので、ぜひ何度か足を運んでほしい。いまや伝説的になっている1997年の「海市」展から16年、同じ場所で形を変えて開かれるこの展覧会には、連続的なトークセッションがあり、その最後に統括討議(3月2日)も予定されている。そこまでどのような展示と議論が展開されるのか、ぜひ注目されたい。
3月頃には、例年の恒例であるが、卒業設計関係のイヴェントが多く開催される。筆者も全国合同卒業設計展「卒、」14(3月1日〜3日)(http://sotsuten2014.wix.com/sotsuten14)や、トウキョウ建築コレクション2014(3月4日〜9日)(http://www.tkc-net.org/)にクリティークとして参加させていただく予定であるが、毎年、多くの学生の作品を見ることで考えさせられることも多い。建築や都市を学ぶ学生の皆さんには、提出まであと少し、エールを贈りたい。
同じ3月に、新入生も含む建築学科の学生に向けた本が刊行予定である。建築学科での生活のエッセンスを凝縮したような内容となっており、筆者も含め、多くの建築関係者が執筆している。内容はわかりやすく、どのページもためになるはずだ。学生時代に、まさにこういう本があれば良かったと思えるような本になりそうであるので、無事、予定通り刊行されることを祈っている。
レム・コールハースが総合ディレクターをつとめる第14回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展には、もちろん大きな注目を寄せている。
★1──2014年1月21日に、磯崎新氏に直接聞いてみたところ、やはり3人のうち2人が同席することはあったが、3人が同席したのは初めてのことであったという。
まつだ・たつ
1975年生。建築家。東京大学先端科学技術センター助教。松田達建築設計事務所主宰。共著=『相対性コム デ ギャルソン論』『記号の海に浮かぶ〈しま〉』『窓へ──社会と文化を映しだすもの』など。作品=《JAISTギャラリー》《東京シームレスシティ》など。
松原慈(建築家、美術家/assistant)
●A1
建築に限らないが、空間は、そこでしばらく時間を過ごしてみないと、よくわからない。
時間を過ごしてわかることは、おおげさなことではない。光の細かな動き、色の変化、空気の流れ、身体感覚の鋭さ、土地と建物の持つ強さあるいは脆さ......。
でも、日暮れ頃から夜明けまで、太陽や月の付き添いのもと、その場所で一晩過ごしてみると、連続して自然に感じられる、ときにはぞくっとする変化。
身体と空間の密やかな取り引き。本を読むように知識を手に入れるのとは違い、ひとときとして同じものは交換されない。
2013年に親密な時間を過ごしたいくつかの空間は、空間に対する理解を押し広げ、時間と空間の関係をもっと深く知りたいという衝動を与えてくれた。
パレ・モクリ(Palais Mokri)
モロッコ・フェズ旧市街にタイブ・モクリによって1906年に建てられたフェズを代表する邸宅建築のひとつ。モクリ家の邸宅はフェズ市内にほかにも複数存在するが、なかでも本邸宅は、旅好きで趣味人だったタイブ・モクリがイタリアやイランから輸入したデザインやマテリアルを用いた特別な造りになっている。それぞれ、赤、青、緑のガラスを用いた三つの寝室がとくに美しい。太陽の位置や空の見え方によって、寝室全体は、色が反転するほどに表情を変える。


- 上=パレ・モクリ、外観/下=同、サロン・ルージュ(Salon Rouge=赤い応接間)
ともにフェズ、モロッコ © Megumi Matsubara
Megumi Matsubara & Nástio Mosquito
自身のインスタレーション作品。アフリカ大陸に実在する自身の私的空間を最小限の構造物、光、音で再現したコミュニケーションの場。横浜市芸術文化財団主催で「TICAD V(第5回アフリカ開発会議)」の関連イベントとして開催された「Sound/Art - Tuning in to Africa」のために、日本とアフリカをテーマに、文化や人の出会いの本質を問う作品として構想した。時刻や天候の差とともに、パフォーマンス、トークイベントや音楽ライブなど、さまざまな出来事を招き入れた。


- Megumi Matsubara & Nástio Mosquito インスタレーション、ヨコハマ創造都市センター
©Kenshu Shintsubo
33年目の家
assistant(松原慈+有山宙)設計で2013年に竣工した住宅。奈良市、東大寺に隣接した敷地に建つ。施工中に招聘された国際芸術センター青森(ACAC)でのアーティスト・イン・レジデンスのほか、仙台や東京の複数の場所で、母屋の一部や構成要素のひとつであるパビリオンが制作・展示された。最終的にそれらは奈良に運び、ひとつの住宅として再構成した。家の各部分がもつストーリーと記憶や天候が重なり、ひとつの空間のなかに複数の親密な空間が生まれ、刻々と移り変わるように注意した。


- 33年目の家、奈良
©Tadasu Yamamoto(上)、©Megumi Matsubara(下)
サハラ砂漠の寝室
天井のない砂漠の寝室では、夜の照明は月である。満月の夜は昼間のように明るい。どこまでも平坦な敷地と大きな空しかない風景からは、新月から満月まで、太陽と月の間の光のやり取りがいかに刻々と変わっているかがわかる。これがわたしの身体が感じる光の基本だと実感すると同時に、どの寝室よりも、ここの天井がもっとも美しいということに気づく。その天井は、大きな可能性を夢見させてくれるとともに、ただ存在する空間の前で、つくづく謙虚な気持ちにもさせてくれる。


- ティッサルドゥミン・ヴィレッジ(Tissardmine)、モロッコ
©Megumi Matsubara
まつばら・めぐみ
1977年生まれ。建築家/美術家。2002年より建築スタジオassistantを有山宙と共同主宰。assistantでの活動のほか、個人による作品制作を行ない、建築を土台に、インスタレーション、パフォーマンス、テキストなどの手法を交差させ、存在/不在のバランスを問いかける。近作に《Void/Between》(マラケシュ・ビエンナーレ、2012)、《無名の建築》(国際芸術センター青森、2012)、《33年目の家》(奈良、2013)など。2012年からはモロッコと日本を拠点に活動している。http://megumimatsubara.com
光岡寿郎(メディア研究、芸術文化の社会学/東京経済大学専任講師)
●A1
日常化する国際展
2013年も都市型では「あいちトリエンナーレ」★1、地域型では「瀬戸内国際芸術祭」★2が開催され、それぞれ好評のうちに幕を閉じた。なかなかまとまった休みもとれず、直接訪れることができたのは前者だけだったが、個人的には初回、第2回の横浜トリエンナーレのような熱気を感じ、心地良い疲労感を覚えた。一方で今年は、国際展開催レースから遅れをとっていた北海道(2002年に開催された「デメーテル」★3の扱いは難しいが)や四国でも、それぞれ「札幌国際芸術祭」★4や「道後オンセナート」★5の開催が予定されており、2000年代初頭の国際展の「ハレ」感は確実に薄れつつある。
この状況を鑑みると、今後国際展をめぐっては、国内の諸都市間での差異化と序列化への動きが活発になっていくのではと感じている。2013年10月28日、29日の中日新聞に掲載された「あいちトリエンナーレ」座談会をめぐる一連のやりとりには、そんな側面がかいまみえていた。記者の「新聞/マスメディア」上の批判と、企画者側の「twitter/マイクロメディア」による応答はそれ自体、メディア研究の一事例としても興味深かった。とはいえ、座談会に出席していたある記者(記者E)の「あいちならでは感」の強調はきわめてナイーブな反応ではあったけれども、それゆえに日常化の進んだ国際展が、今後おしなべて行政、ボランティアスタッフ、地域メディアから求められる要件を象徴していたとも思う。そもそも国際展は、先行するグローバルな言説のネットワークのうえに依拠しているという点で★6、ドメスティックな意味でのヴァナキュラーさにはそぐわないアートイベントだ(し、求めれば求めるほど「国際的」な国際展としてはつまらなくなる)と考えていることもあって、今年の、そして2010年代を通して日本で開催される国際展が、どのように変わっていく/変わっていかないのかを淡々と見守っていきたい。
★1──あいちトリエンナーレ
URL=http://aichitriennale.jp/
★2──瀬戸内国際芸術祭
URL=http://setouchi-artfest.jp/
★3──デメーテル
URL=http://www.demeter.jp/j/
★4──札幌国際芸術祭
URL=http://www.sapporo-internationalartfestival.jp/
★5──道後オンセナート
URL=http://www.dogoonsenart.com/
★6──参考=光岡寿郎(2012)「国際展〈論〉のポリティクス」(『芸術と環境』[論創社]所収)


- 街中に散在する展示会場(上=名古屋)、街中に散在する展示会場(下=岡崎)
●A2
KoSAC(Kokubunji Society for Arts and Culture)
手前味噌は承知なのだけれども、東海大学の加島卓さんと一緒に「アート」「デザイン」「社会」を緩やかなテーマとした月例の会を昨秋から始めた。美術大学に通う学生や、研究を続けたい大学院生のすべてが大学に残る必要もないだろうし、社会人として生活するなかであらためて突き詰めて考えていきたいことも生まれるだろうと思う。その受け皿が大学とカルチャーセンターしかない社会はそれなりに息苦しい社会な気がしていて、面白いと感じているテーマを持つ大人が、ともに目一杯面白がれるような場としてKoSACを開きたい。以前このアンケートでも触れた、地域に根ざしたシェルター型のアートスペースに刺激を受けながら出した僕なりの応答になればと考えている。会のコンセプト、および2014年1月29日の第5回KoSACについては以下のURLをご参照いただきたい★7,8。
★7──KoSACのコンセプト
URL=http://toshiromitsuoka.com/blog/2013/08/08/1137/
★8──第5回KoSAC「アート×キャリア×ネットワーキング」
URL=http://toshiromitsuoka.com/blog/2013/12/26/1254/

- KoSACの様子(第3回KoSAC、2013年11月6日。これっきりエンナーレとの共催)
●A3
建築保存の行く末
これは建築や都市計画を専門としない僕は確信が持てないところもあるのだが、2020年の東京オリンピック開催に向けて東京の再開発が進むのだと思う。再開発にともない、一定の建築物の建て替えが想定されるが、この過程でいかなる建築保存についての社会的コンセンサスが形成される/されないのかに関心を持っている。ザハ・ハディド設計による新国立競技場が建設される過程の半ばですでにこれほどメディアを賑わわせていることからも、建築がいかに「面倒臭い」文化財なのかを再認識することができたと思う。建築の保存は、公私の所有権のせめぎあい、保存自体にかかる莫大なコスト、地域住民の合意形成と、文学作品や美術作品といった「モノ」の保存とはまったくレベルの異なる水準の困難を複数抱えており、例えば神奈川県立近代美術館の敷地返還問題のように、この数年折に触れて表面化してきた建築保存の問題が噴出する契機となるのが、オリンピックにともなう都市の再開発なのだろうと漠然と感じている。
みつおか・としろう
1978年生まれ。メディア研究、芸術文化の社会学。日本学術振興会特別研究員、早稲田大学演劇博物館GCOE研究助手を経て2013年より現職。論文=「なぜミュージアムでメディア研究か?」(『マス・コミュニケーション研究』第76号、2010)ほか。共訳=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』。
山内真理(公認会計士、税理士/Yamauchi Accounting Office)
●A1
私は普段表現や創作・文化に携わる個人や組織体の会計・税務などに従事している。そのなかで税制の複雑さとわかりにくさがもたらす諸問題や、文化や社会的価値と経済・産業を巡るジレンマについて、草の根の活動や異業種協働で自分なりにできることを模索してもいる。
国の借金が1千兆円を突破したと報じられた6月、知人の縁でとあるイベントに参加した。税制の仕組みを15分ほどで説明して欲しいというオーダーだった。「税金はどこへ行った?(WHERE DOES MY MONEY GO?)」こう題されたこのプロジェクトは★1、市民や自治体職員有志が公開資料を元に1年間の市税の使い途や金額などをわかりやすく可視化する。元はイギリスが発祥だが、日本では横浜市を皮切りにまたたく間に全国に広がった。
オープンデータ化のプロセスを通じた、このようなボトムアップの取り組みには、硬直化した課題解決手法を柔軟化するために必要な協働や着眼点への示唆が豊富に含まれている。
税制は財政と一体となった究極のアーキテクチャだ。例えば地域発クラウドファンディングのニュースは多様なオルタナティブの選択や試行の可能性と必要性をあらためて問いかける。法律や制度変更には多大なコストを要するが、それらとの付き合い方には創意工夫の余地も多分にある。
★1──「税金はどこへ行った?(WHERE DOES MY MONEY GO?)」
URL=http://spending.jp/
●A2
私は幸いなことに、本業やArts and Lawの活動を通じ、法律家、アーティスト、デザイナー、建築家、漫画家、プログラマー、さまざまな文化経営に携わる方々などとお付き合いがある。2014年はこうした方々とどんな協働ができるのかが楽しみだ。
直近のプロジェクトとしては、新年冒頭漫画家育成事業を手掛ける「トキワ荘プロジェクト」(NPO法人NEWVERY)のもと、プロの漫画家、編集者と協働して、クリエイター向けに消費税増税の留意点を解説するマンガを制作した(山内は原案・監修を担当)。
マンガはネット上で無償公開され、有難いことに一般の多くの方の目にまで触れてもらえる結果となった。
消費税制度は課題もあり、複雑でわかりにくく一般の理解度はけっして高くない制度だ。2014年4月、2015年10月と2段階にわたり実施される予定の税率変更は、消費者にとっても中小事業者にとっても影響が重大であるがゆえに、マンガ作品を通じ、こうした発信ができたことは幸いだった。
●A3
急激な少子高齢化による社会保障費負担やインフラ老朽化、不動産・知財の利活用の問題など、都市や社会を巡る長期的な諸課題と税制の問題はけっして切り離すことができない。
2項対立といった状況を打開し、豊かさの定義を問い直し、多様な選択肢を柔軟な発想で選び取って、持続可能な形で組み立てていくべきだ。
そのために、市民と専門家が同じテーブルで丁寧に議論することや、異種の専門性同志が立場を越えて小さくても可能性のあるプラクティスを集積することが、課題を解決可能なサイズに解きほぐし、人々の前向きなコミットメントをもたらすと信じている。むろん個々の会計・税務の専門家は主体的に試行していくべきと思う。
やまうち・まり
公認会計士、税理士。Yamauchi Accounting Office代表、芸術家を支援するNPO Arts and Law理事。
山岸剛(写真家)
2013年は東北地方太平洋沿岸部の撮影で始まった。瓦礫の撤去が落ち着いたのはもうはるか昔のように感じられ、以後、東北の風景はなにかを待機しているかのごとくほとんど変わらないように見え、それをなぞる私の写真もマンネリズムに陥っているように思え、これを打破すべく10日間の日程を組んで青森から福島まで海岸線を上下した。1月9日から18日までみっちり130枚ほど撮影した。130枚はたいした数に聞こえないだろうが、私はいまだに4×5インチ、通称シノゴの大型フィルムで撮影をしているのでまあそれなりの量になる。ふつう写真家は撮影して、撮影したものから選択して、選択したものを仕上げて、仕上げたものを発表するというのが筋で、私もこれまでそのように仕事をしてきたが、このとき130枚撮って帰ってきたら、なにかの閾を超えたのか、「選ぶ」という行為がバカらしく思えてしまった。お前は何様だ、選ぶなど東北の大地に失礼だ、フィルムに定着したものは等しく価値があるはずだと考えるに至った。そんなわけでこの130枚をもれなく仕上げたらお次は、それまで2011年4月以来撮影してきた400枚強のフィルム、そのなかで「選外」としていたものをあらためて仕上げることになった。そんなふうに2013年の上半期は、ここ二年の過去をひたすら掘り起こして過ごした。

- 2013年1月16日、広田海岸、岩手県陸前高田市広田町

- 2013年1月18日、福島県南相馬市
5月の大型連休前、またあたらしく東北の撮影に出る前に、そのようにして仕上げたこれまで撮影したすべての写真をウェブ上で放流した。当時で総計300カットくらい。「写真家」としての「私」の写真云々はホントどうでもよくて、まずはひとつの記録として、差し迫った現在の、写真によるレポートとして一人でも多くの人に見てもらいたいと考えた。発表の仕方は可能なかぎり即物的で直接的な感じがいい。写真というのは元来、写真術を正確に使いこなせば、ほとんど酷薄なまでに直接に、現実をそのまま「転写」しうるメディウムであり、そのような写真の使い方こそが、切迫した東北の風景と鬱屈とした東京でのリアルな政治の双方に穴を開けうると期待した。
http://takeshiyamagishiphotographs-thk1.tumblr.com
http://takeshiyamagishiphotographs-thk2.tumblr.com
http://takeshiyamagishiphotographs-thk3.tumblr.com
http://takeshiyamagishiphotographs-thk4.tumblr.com
同じく撮影に出る直前の4月21日、東京都大田区西蒲田で、建築家の中川純氏がつくっている自邸を撮影した。「15Aの家」と名づけられた仕事で、放射能の「ホットスポット」となってしまった地域から一家で移り住んで、亡き祖父の家をセルフビルドで改修し、15アンペアの電力で暮らしていくらしい。設計の詳細は私には知る由もないが、その日見た建設現場にとても感銘を受けた。東北でこれまで見てきたものと同じ風景を見ていると直感しすぐさま撮影した。中川氏は私がかつて撮影した《2011年5月1日、岩手県宮古市田老青砂里》という写真にインスパイアされながらこの家をつくっているという。

- 2011年5月1日、岩手県宮古市田老青砂里
建設途中の現場というのはだいたいカッコいいものであるが、私が感銘を受けたのはそれだけの理由ではない。私はかつて二年前のこの欄で上記《2011年5月1日、岩手県宮古市田老青砂里》という自分の写真について、そのとき目にした光景について「建築はかつてないほど健康に見えた」と書いた★1。私はこの日、それと同じ建築の風景を東京で見たのである。ふたつの建築は、もとより「建築」ではなく「建物」、いまなら「建屋」と言われるシロモノかもしれないが、植物が光を求めるように真っ直ぐに、ほとんど快楽的に、光と風と水を享受していた。圧倒的な感覚の驟雨(しゅうう)に自らを開く人工物はとても健康に見える。しかしそのような感覚の驟雨は身体にはとても大きな負荷であり、通常、一時的なものたらざるをえないだろう。氏の仕事は、そんな一時的なハイテンションの感覚の驟雨をどうにか持続の相のもとに、習慣のように、つまり「住む」ことのタフで執拗な反復において我がものにしようとする試みと理解した。そのようなレアな自然の馴致を、彼がこれまで身につけた建築という技術の体系でもって実現しようとする試みと理解した。つまり「建屋」を「建築」にしようとする試みと理解した。
圧倒的な感覚の驟雨は、あまりに人間主義的に閉じた人工性にあっては、ときに必要なものであったのかもしれない。それが「千年に一度」のあの津波だったのかもしれない。そんな災厄によって図らずも開かれてしまった可能性がもしあるとすれば、それをあたらしく自らのものとするのはやはり、これまでに培ってきた知と技術によってでしかないことを私は確認した。

- 2013年4月21日、15Aの家、東京都大田区西蒲田
5月2日から10日まで、前回と同じく青森から福島まで車を走らせた。東北の風景に少しずつ目に見える変化が現われてきた。視野いっぱいを占める広大な荒れ地の端々に小さくダンプカーやらクレーンやらが動きはじめた。水産施設が立地する最沿岸部から一歩入った、かつても人が住んだであろう土地に人々のすまいがぽつぽつ建ちはじめた。それらのすまいはしかし、これが群れをなしたときに、この地の「自然」に拮抗するような「風景」をつくり上げるとは到底思えないように見えた。これまでの長きにわたるスッタモンダの果てに結局このようなものしか建ちえない予想通りの現実に落胆した。一方で想像もしなかった光景にもこのとき出会った。上にも書いたが、あらゆる瓦礫という瓦礫はとうの昔に撤去され、しぶとく残りつづけた建物の基礎も「復興」が進むにつれ姿を消していった。が、最後の最後まで執拗に、大地に固執するように、どうしようもなく残ってしまった遺物がそこかしこにあった。それらは残っていること、ただそれだけでかけがえのない価値をもっているように見えた。自らの正統性を全身で表現するように堂々とそこに建っていた。残ったことは「選ばれた」こととなり、ゆえに彼らは祝福されているように見えた。神々が人類の栄光を謳いあげているかのような光景だった。まさに神話的な光景を前にしているようで、私には筆に尽くしがたい。

- 2013年5月7日、大槌港、岩手県上閉伊郡大槌

- 2013年5月8日、赤崎海岸、宮城県気仙沼市本吉郡下宿

- 2013年5月10日、福島県相馬郡飯館村
10月7日に仙台入りして、海岸線を岩手県は田野畑村まで北上し、いちど内陸の盛岡に寄ってそこから、東北自動車道で一気に福島県の南相馬市まで南下して、12日に仙台から東京に戻った。前回、視界の果てで遠慮がちに動いていた工事用車両は近景から遠景まで、活発に仕事をはじめていた。土木的風景のパノラマがいたるところで展開されはじめた。にわかに騒がしくなった。近くの山々はハゲ山にされ赤い地肌をむき出しにしていた。むき出しにされた順に線が引かれて、高台に宅地らしきが姿を現わした。最後まで残ったものたちのあるものは撤去され、あるものはいまだに残り続けている。この期におよんではじめて私は、ふと、この土地の津波に流される以前の風景を見てみたいと素朴に思った。それを見たことがないことに初めて気づいたかのように。そしていま残っているものはすべて等しく撮影されるべきだと強く思った。それらはいずれも不可能だとしても。そして写真によって「記録」をすることはただそれだけでもう十二分に価値のある仕事だとあらためて思った。

- 2013年10月8日、赤崎海岸、宮城県気仙沼市本吉郡下宿

- 2013年10月9日、大槌港、岩手県上閉伊郡大槌

- 2013年10月12日、福島県双葉郡浪江町
以上、すべて撮影=山岸剛
12月7日から9日までの3日間、首都大学東京の饗庭伸先生からのお誘いで大船渡から車で30分ほどの綾里(りょうり)という集落に滞在し撮影を行なった。先生が手伝いをされている復興計画のおおよそが決定し、さてこれから町が変わっていくという段階で、この土地のアーカイブをつくる一環での写真撮影を依頼された。これまで津々浦々の多くを通過しながら撮影してきたのとはちがって、ひとところに腰を据えて仕事をすることにもなるので、どんな変化を目にできるのか、写真にどんな変化が現われるのか、楽しみである。
2014年で撮影をはじめてから4年目、いろいろな意味で東北の風景も、それをなぞる私の写真も転機を迎えつつある。6月には東北の写真で展示も予定している。少しずつまとめながら、これまでと同じように風景を見据えて、カメラを使って、記録を続けていきたい。
最後に。二川幸夫さんが亡くなった。2010年に日本建築学会の会誌『建築雑誌』で、編集委員のひとりとして建築写真の特集を組んだときに最初で最後★2、じっくりお言葉をいただいて以来折にふれて、二川さんのあり方というか姿勢のようなものが、私の仕事にとってとても大きな意味となって迫ってきた。二川さんのおかげで、私は自分のなかにある大切なものを発見し、それを展開することができた。私が自らの東北での仕事を「写真によるレポート」と呼ぶのは、二川さんが『日本建築の根』のあとがきでご自身の仕事をそっけなく「写真レポート」と呼んでいることをなぞっている。亡くなる少し前に二川さんの『日本の民家』の写真展示を汐留で観たとき、私も東北でおなじものを見ている、と思ったことを二川さんにお伝えしたかったので悔しい。124歳まで生きて写真を撮り続けると豪語されていて、それを人に信じさせるような大きな人物だったので悔しい。私は二川さんのようなあり方を受け継いでいきたいと思う。あのような人にお会いできたことに私はなんと言って感謝しよう。
★1──山岸剛「2011-12年 都市・建築・言葉 アンケート」
URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2012/02/enq-2012.php#1853
★2──『建築雑誌』2010年7月号 特集「建築写真小史」(日本建築学会)
URL=http://jabs.aij.or.jp/backnumber/1606.php
やまぎし・たけし
1976年生まれ。写真家。


