〈建築理論研究 02〉──原広司『空間〈機能から様相へ〉』

- 左から、天内大樹氏、西沢大良氏、南泰裕氏
『空間〈機能から様相へ〉』の出版された時代

- 原広司『空間〈機能から様相へ〉』
(岩波現代文庫、2007)
原広司さんの「均質空間論」(『空間〈機能から様相へ〉』所収)が書かれたのは1975年で、『錯乱のニューヨーク』の原著が刊行されたのは1978年ですので、ほぼ同じ時期だと捉えることが可能です。「均質空間論」では、おおまかに言うと、お互いに関係性の切れたものが寄り集まって、どんな機能をも包含するようなある空間の形式を準備したことが語られる。一方、コールハースは、ロボトミーとしてさまざまな機能や文化や消費といったものがまったく無関係に集積されている状態を語っている。背景はまったく違うにせよ、原さんの「均質空間批判」「機能主義批判」と、コールハースの「スカイスクレイパー」「過密の文化」は同じ問題を対比的に捉えていると見ることができる。つまり、日本のなかで海外とは別の文脈でセンシティヴかつ先鋭的なかたちで理論を組み上げていた原さんが、どのように考えていたのかをフォローしてみると、じつはコールハースと近い時期に近い問題について異なる角度で考察していたのではないかと思うんです。そうしたことから理論のセリー、つながりや継承を考えた際に、『錯乱のニューヨーク』の次に『空間〈機能から様相へ〉』を採り上げてはどうかと考えました。
西沢さんは『空間〈機能から様相へ〉』に対して、どのような思い出がおありですか?

- 西沢大良氏
西沢大良──僕が大学生だったのは1982年から86年までで、ちょうど南さんのおっしゃった理論の絶滅していた時期に当たるんです。当時の学生にとって、それは切実な問題だったんですよね。ほんの5、6年前、自分たちが中学から高校に行っていた70年代半ば頃は、まだいろんな知性や創造性があちこちで生成していたのに、それが完全に途絶えたという実感を持っていました。新しい理論や考察よりも、昔の解説や引用みたいなものが知的活動と見なされるようになったんです。もともと文化全体がそうで、ロックやジャズ、現代音楽や小説なども、中学生の頃からほとんど何も出てこなくなっていました。そのかわりに台頭してきたのが、大企業型の活動というか、量的供給だけを拡大していくというものでした。だから情報量は増えていたのですが、それにあわせて知性や創造性が出てくるようなことは起こらなかった。だから当時の大学生には、とにかく昔の本を読むという習性がありました。最低でも10年くらい前の本、あるいは戦前の本とかです。さもないと、自分の知性がなくなってしまうような恐怖があったんです。
原さんの『空間〈機能から様相へ〉』も出版は80年代でしたけど、収録されている文章は70年代半ばに書かれたものでした。ただ、僕がこの本を読んだ理由は、ちょっと例外的でした。原さんの人柄にあまりに驚いて、本を読んでみようと思ったからです。僕の通っていた東京工業大学には篠原一男がいて、現役の建築家たちを次々に呼んで設計指導をしていただくのですが、そのひとりとして原さんにも2カ月くらい指導していただきました。ちょうど原さんが軽井沢の《田崎美術館》(1986)の設計をはじめられた頃で、それまでの「反射性住居」シリーズのような私的な作品から、公的な施設へ移行しつつあった頃です。実際にお会いしてみると、作品や文章からは予想もつかないような、ものすごく楽天的な方なんですね。なんというか、ありえないくらいに明るいのです。この明るさや楽天性はどこから来るんだろうと思って、著書を読みました。その意味では、原さんの人柄を解き明かすために本を手に取ったようなもので、ちょっと邪道な入り方をしたのかもしれないです。
ちなみに、南さんが冒頭でおっしゃった『錯乱のニューヨーク』も、コールハースの人格どおりに錯乱していたと言えなくもないです(笑)。僕も原さんの本と同じ頃に読みました。
南──当時、西沢さんの周りでは『錯乱のニューヨーク』は読まれていたのですか?
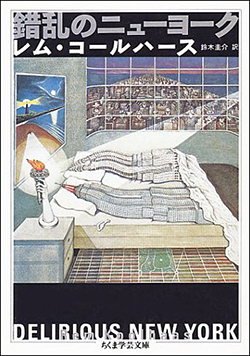
- レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』
(鈴木圭介訳、ちくま学芸文庫、1999)
話を原さんに戻すと、南さんはよくご存じだと思うんですが、原さんの楽天性や明るさは、ただ事ではないと思うのです。あそこまで明るいと、もはや性格の問題を超えているんで、何らかの理論的な検証が必要だという気がします(笑)。僕は今から4年くらい前に、原さんと共同で1─2年くらい設計をご一緒したんですが、原さんは毎日、本当に好きなことしかしていないですよ。設計と料理と数学と将棋しかしていない。自宅にも本当に帰らないし、事務作業とかもぜんぜんしないし、たぶんお金も数えていないと思う。あのような楽天的な人生は、いったいどういう思想に裏打ちされているのか、普通は知りたくなりますよね(笑)。
南──ほんとうにそうですね(笑)。少年のような感じですね。
西沢──それで『空間〈機能から様相へ〉』を読みました。
近代を超克するための近代研究
南──読まれた際にどのような感想をお持ちでしたか?西沢──当時の読者は、今とは違うように建築書を読んでいたと思うんです。これらの文章が書かれた70年代までは、書き手と読み手の間に、ある暗黙の了解があったからです。書き手がモダニズム(近代建築・近代都市)の批判者なのか推進者なのかについて、読み手は完全に理解しながら読んでいたんです。たとえば原さんは、近代都市・近代建築の批判者です。逆に師匠筋の丹下健三さんや高山栄華さんは、もちろん近代都市・近代建築の推進者です。ただし高山さんは近代建築の私的な部分については否定的でした。あるいは、先輩筋の槇文彦さんや磯崎新さんも近代都市・近代建築の推進者でした。ただし磯崎さんは、近世(ルネッサンス)まで含めた人文的な意味での近代の推進者でした。逆に年下の伊東豊雄さんは、近代建築の批判者です。ただし近代都市には無関心です。でも原さんは、近代都市と近代建築のことを、危なっかしいと思っているわけでしょう。もっと言えば、ダメなんじゃないかと思っているかもしれない。そのことが腑に落ちないと、『空間〈機能から様相へ〉』は読めないし、『建築に何が可能か』も読めない気がします。そればかりか、そもそも20世紀の建築理論も読めなくなるし、本当は建築作品も理解できなくなると思います。このことは、どんな本にもリテラルに書かれていないので、いちおう注釈しておきます。

- 原広司『建築に何が可能か』(学芸書林、1967)
僕の記憶では、近代建築・近代都市に対する違和感は、70年代後半から80年代初頭のあたりでなし崩しになったと思います。ちょうどその頃から、原さんの文章や建築は難解だと言われるようになったんです。それは、読み手が近代建築に対する違和感を喪失したために、原さんの仕事の動機がわからなくなり、難解だとしか言えなくなったということだと思うんです。でも原さんの仕事はその後も近代建築・近代都市に対するスタンスを一貫させていますから、僕は難解だと思ったことは一度もないです。
とはいえ、「均質空間論」に限って言うと、難解に見えた理由がもうひとつあるかもしれないです。均質空間として挙げられた事例、つまりミースのオフィス建築から今日のゼネコン建築までを、あたかも擁護しているような記述が出てくるからです。なぜそんな記述があるのかというと、原さんは均質空間の出現したプロセスを、論理的に把握しようとしたからでしょう。そこだけナイーヴに読むと、均質空間で歴史が終わるかのように読めるのかもしれないです。もちろん全体をよく読めばそうではないのですが、もしかすると同時代に読んだ人の何割かは誤解したかもしれないです。
南──たしかにそうかもしれませんね。西沢さんのおっしゃったことはよくわかります。勧善懲悪の物語が前提としてあると、文章はすごく読みやすい。その場合は読者と著者の共犯関係が最初から成立していると言えます。ところが原さんの場合は、デカルトが提出した空間モデルを400年のタイム・スパンを経てミース・ファン・デル・ローエが物象化したその凄みに対して、単純な批判はしない。一筋縄ではいかないものすごいものが目の前にあって、それには畏敬の念をもっているのだけれど、ではどうすればいいのかという論になっている。単純な勧善懲悪ではないので、たしかにわかりにくいかもしれませんね。
西沢──均質空間(ゼネコン建築)なるものが、人類にとって考察に値するものだということを、まず説明しなければならないわけです。その論証はわりと丁寧になされていたと思います。まずミースはオフィス建築を対象化した史上初の建築家だとされて、そのような建築家・建築作品が登場した理由を、主に2つの流れから説明していたと思います。歴史の長期的な流れと、短期的な流れの2つです。長期的には、ルネッサンス以降の数学思想の流れ、つまりデカルトなりライプニッツなりの流れから均質空間には必然性があるとされ、短期的には、20世紀初頭の美学の流れ、つまり未来派なりカンディンスキーなりの流れから別の意味で必然性があるとされる。この長期と短期の波動の交点に、ミースのオフィス建築の出現が位置づけられる。ちなみに、それを世界中に拡散していったのが後のゼネコン建築だとされる。
この論証は、歴史家のものではないですね。発想がちょっと数学的だと思うんです。歴史をほとんどグラフ化するように捉えている。それは原さんの思考の方法を物語っているような気がします。とはいえ、先ほども言ったように、この説明だけを切り取って読むと、ミースで歴史は終わったような誤解が生じてしまう。

- 南泰裕氏
南──ル・コルビュジエが悪しき前例をつくったのかもしれませんが、建築家の理論というのは、つねに話半分で聞かなくてはならないと思ってしまうところがあります。つまり、建築家としてのみずからを宣伝するだけで終わっているのではないかという疑念がつきまとう。そういう側面はメタボリズムにもあるかもしれない。
西沢さん同様に僕も原さんの本に心を打たれました。それがきっかけとなって1991年に原研究室に入ったんです。僕は京都大学の出身なのですが、京都大学の人間は基本的に批判精神旺盛で、話半分にしか聞かないところがあるわけですよ(笑)。ですから原さんが、本に書かれたことを本当に信じているのか、それとも自分の建築の自己宣伝のために言っているのかどうかを確かめたいという思いがあったんです。6年間原研に在籍しさまざまなお話を間近で聞いてきたわけですが、原さんは、ミースを乗り超えなければならないと自分の人生を賭けて考え、そして書き、つくっているのだと感じました。
西沢──そうです。ミースは仮想敵ですからね。今はそういう基本的な事柄が通じなくなっているかもしれないです。でもミースを仮想敵とするかどうかは、好き嫌いの問題ではないんです。認識を持っているかどうかです。先ほども言ったように、長期的なスパンで考えたとき、ミースで歴史が終わるといったことはありえないのです。ミースは人類史にとって経過地点であって、その後も歴史はどうしようもなく続くのです。ではどういう方向に進むのか。歴史の流れを解析するしかないんです。どのような流れにおいてミースの登場に必然性があり、ゆえに今後どのような限界を露呈するのかを、好き嫌いを忘れて把握するしかないです。
さして深く考えずに近代建築を推進している人たちには、均質空間(ミース)がいかに必然的なものかという説明は、できないです。そもそも説明が必要であることに気づかない。でも原さんは、均質空間の出現は人類史的な出来事なのだから、解明に値すると考えているわけでしょう。しかもその解明は、均質空間の次にどのような空間が生じるのかを、推理するためです。
だいたい今日の建築家は、みんなミース(均質空間)の没後に建築をやっているのです。われわれの活動は、後世の人間から見れば、ミースの次のものを目指してなされたものでなければ、理解不能になるでしょう。われわれも、数世紀前の建築の枝葉末節部分について、そのように処理しているわけです。だから今の内輪の好き嫌いだけではダメなんです。長期的で外部的な視点が必要なんです。もちろん長期的・外部的と言ったって、誰も歴史の終点に立てないわけだから、歴史の流れを外からみることはできないです。流れの中から流れの方向を把握するしかないんです。
別の観点から説明してみると、「均質空間論」で標的にされている近代建築というのは、様式ではないわけです。水平連続窓がどうのこうのといった様式(スタイル)にとらわれていると、近代建築の正体を見誤ることになる。近代建築の正体は、その次に出現するものによってはじめて明らかになります。だからこの論文にとっての近代建築は、様式としてではなくて、むしろ文明論的な対象として、あるいは人類史的な対象として、捉えられていると考えたほうがよいです。というのも、もともと原さんは若い頃に生田勉の薫陶を受けていて、学生時代からルイス・マンフォードを読んでいたと思うんです。原さんは昔からライトの初期住宅を褒めるわけですが、あれもマンフォードのライト論から来ているような気がします。マンフォードの近代都市論・近代建築論は、完全に人類史的な文明論でした。もちろん原さんはマンフォードみたいに頑固ではないですが、少なくとも近代建築を様式に還元したりはしていないです。
この論文でも近代建築を生産体制から捉えたり、公害問題から捉えたり、支配階級の様式として捉えたりしています。「均質空間」の必然性を確認するためです。もちろん先ほど言った2つの波動、近世数学思想の流れと、近代美学の流れからも、「均質空間」の必然性を確認しています。むしろ気になるのは、そんなにあらゆる角度で必然性を確認してしまったら、ゼネコン建築を乗り超えられなくなってしまうのではないかと、心配になりますけどね(笑)。
ポストモダン言説と原広司

- 天内大樹氏
天内大樹──原さんは数学や自然科学、哲学などを動員して均質空間という問題を掘り下げていかれたわけですが、原さんの設計される建築物と均質空間とはどのように関連しているのでしょうか。その当時、同時代的な感覚として納得のいくかたちで理論と実践が結びついていたか、またその結びつき方についてはどのようにお考えですか?
西沢──当時の僕は21、22歳の学生にすぎなかったんですが、《田崎美術館》を見に行って面白いと思った記憶があります。ローテクでローコストな建築ですが、トップライトと屋根の架構が複雑で、不思議な光の状態をつくっていました。あれは印象的でした。もちろん「均質空間論」の記述が《田崎美術館》で実現されているというリテラルな対応ではないですが、機能主義からは出てこない空間になりつつあるな、というふうに見ていました。
もうひとつ、「均質空間論」以前の《反射性住居》シリーズの場合、プランとエレベがシンメトリーでしたよね。シンメトリーの建築というのは、ボザール以降ほとんどないです。建築はライトの頃からアシンメトリーになっています。いわば近代建築とは、アシンメトリーな建築のことだと言えるほどです。その意味では《反射性住居》にも、近代建築に対する距離があるんですね。
天内──近代の根本を掘り起こすことで近代批判をし、近代を乗り超えるために使うという姿勢を見せていると、80年代半ばであれば脱構築(デコンストラクション)だと見なされがちだと思うのですが、原さんの作品が脱構築的だと評された形跡はないように思えます。
西沢──それはなかったです。原さんは脱構築というより記号論でした。当時の建築界にとって記号論は、かならずしもソシュールなりヤコブソンなりを論じるという細かいものではなかったけれど、非常に期待されていました。人間の文化活動をトータルに説明できる理論が久しぶりに出てきた、という期待です。「久しぶりに」とは、もちろん「マルクス主義以降、久しぶりに」という意味です。20世紀初頭に近代建築と近代都市を出現させた生みの親のひとりは、明らかにマルクス主義のインパクトだったわけですよね。その生みの親が70年代に退場してしまったので、みんな気にしていたんです。それで70─80年代にかけて、いろんな方が記号論に期待して、建築や都市の分析ツールとして応用していったんですね。
他方、脱構築の方は、もちろんデリダの本のインパクトはもの凄かったです。恐るべき書物という感じでした。ただ、それをどのように建築に適用するのかについて、誰も手も足も出ないという状況でした。日本でもアメリカでもそうでした。
南──原さんは集落の研究をしていましたからレヴィ=ストロースやマリノフスキーなどの文化人類学の文脈のなかで記号論に踏み込んでいくことをされていました。ですから、アプローチの方法としてはデコンストラクションの文脈とは違っていたと思います。

- ジャック・デリダ『グラマトロジーについて』
(足立和浩訳、現代思潮新社、1972)
その後しばらくして、MoMAで「ディコンストラクティヴィスト・アーキテクチャー」展(1988)が開催されたんですが、すでにデリダの脱構築とは関係なくなっていて、たんなる様式論になっていました。あそこに出品した建築家のうち、デリダの本を読んでいたのはたぶん一人だけで、残りの建築家は斜め読みか、読んでいなかったはずです。少なくとも『グラマトロジー』の第1部を読んだのは、ピーター・アイゼンマンだけだったはずです。というのも、アイゼンマンの文章にはある時期から「プレザンス(présence)」という言葉が出てくるんですが、明らかにデリダによる現前性批判の文脈で言われているんですね。それを読むと、こいつも『グラマトロジー』のせいでものを考えられなくなったのね、ということがわかるのです(笑)。でも残りの建築家たちは、もっと無邪気に語っていました。『グラマトロジー』を読んでいないから、無邪気に書けるのです。
そのアイゼンマンも、こと設計になると、脱構築をうまく使えていないという印象でした。「エクリチュール(écriture)」を建築において何に対応させるのかという問題が、最後までハッキリしなかった。だから当時のアイゼンマンの作品は、率直に言って、理論と乖離しているように僕には見えました。当時の僕らの年代は、わりとそう思っていたのではないかと思います。
もともと脱構築は、言語をめぐる理論でしたよね。ザックリ言うと、言葉の意味や価値の現前性を批判して、文字 (écriture) の物質性や先行性を擁護するという、一種の唯物論でした。それは物質感の希薄なジャンルにおいては威力を発揮すると思うんですが、建築というのは物質そのものなんですね。建築の設計とは、物質を操ることなのです。現前性に汚染されていない人もわりといるのです。そういうジャンルで物質性を擁護しようとしても、あまりインパクトは生じないんです。ほとんど空回りになってしまう。
南──原さんは以前、同時代を生きている人間は、そんなに違ったことを考えないということをおっしゃっていていました。実際にそうだと思います。とくにいまはインターネット社会ですから、そんなに違った情報を受け取っていないし、どんなに奇抜なことをしている人物に見えたとしてもじつはあるコモンセンスを共有している。共通の常識に基づいて違う表現を行なっている状況だといえます。

- ジャック・デリダ『エクリチュールと差異』
(若桑毅+阪上脩ほか訳、法政大学出版局、
1977/83)
西沢──脱構築という戦略を建築にもってくると、いわば空中2回ひねりみたいなことになってしまうのです(笑)。まず建築物それ自体よりも、「建築」という大文字の概念こそが重要であるという、1回目のひねりが必要になる。次に、それをプラトンから今日まで、だいたい2400年くらいかけてひねり続けると、ようやく2回目のひねりがインパクトを持つのです(笑)。原さんは、そういう遡及的なひねりを認めていないでしょう。空中2回ひねりどころか、まっすぐ飛んでまっすぐ落ちよ、という態度でしょう。その意味では『空間〈機能から様相へ〉』は、むしろ単純な進歩史観で書かれています。「機能」でできることはここまでで、その先に別のものが出てきます、というパースペクティヴです。未来に対する信頼があるというか、もっと楽天的だと思うんですね。
天内──集落を調査した結果として「様相」というものを示し、自分はそっちへいくんだという決断が言語化されていますね。
南──天内さんの世代ではリアルタイムで読むことはできなかったわけですが、『空間〈機能から様相へ〉』に対してはどのような印象をお持ちですか?

- 原広司『住居に都市を埋蔵する──ことばの発見』
(住まいの図書館出版局、1990)
作品と理論が出会う場所
南──改めて西沢さんにお訊きしたいのは、先ほど天内さんも質問されていましたが、作品と理論との関係です。一般的には、原さんの作品と理論にはある整合性や関連性があると言われています。初期の「有孔体の理論」のときには、《伊藤邸》(1967)や《慶松幼稚園》(1968)のように、ある2次元的な孔を空けるような形態的な作品をつくっている。「反射性住居」に対応するものとして、《粟津潔邸》(1972)や《自邸》(1974)をつくっています。また、「様相」や「意識」という言葉が出てきたときには《田崎美術館》や《ヤマトインターナショナル》(1986)などがつくられています。西沢──そういう対応もあるんですが、こういうこともあると思うんです。「均質空間論」のなかに、ところどころ面白いセンテンスが出てきます。たとえばミースについての要約です。ミースは機能を放棄したことで、機能主義者たちが目指していた空間をあっさり実現した、というようなことが書いてある。面白い認識です。おそらくこれは、設計している最中に出てきた認識ではないかと思います。あるいはこういうセンテンスもある。構成主義についての要約です。構成主義者たちは、建築をプライマリーな形態に還元すると主張したが、やればやるほど形態どうしの組み合わせの手法を開発していった、とある。とても面白い認識です。これも設計中に気づいたことのはずです。
原さんの論文は、そういうセンテンスをところどころに配置して、それらの論証を間に入れたような構成になっています。個々の認識が論文全体のつなぎ材のようになっている。そういう構成は、個々の認識によほどの自信がないとできないと思うのです。ではどうしてそれほど自信があるかといえば、設計している最中に出てきた認識だからでしょう。原さんの場合は、そういうかたちで実作と理論の関係があると思います。
実際、原さんと設計していると、そういう箴言みたいな認識を、日常的にすぱっと言いますね。スタディの節目にそういうことをふっと言う。その意味で原さんという人は、論理的な人ではなくて、直観的な人だと思います。人間の直観はバカにならないと、考えておられる気がします。だから、論文の書き方が演繹的なのです。結論を論理的に帰納しているのではなくて、最初から結論は見えているのです。論理は読み手の理解のためにくっつけただけであって、元にあるのは直観的な認識だと思います。
天内──文章を書きながら設計をやっている場合、予感や想像としてなんとなく文章に書きつけたことが、実作として形になると、形になった時点で結論になってしまう。だとすると、文章には残らないままに、建築が結論に変わってしまうようなプロセスがありうるわけですよね。
西沢──それもあるでしょうね。原さんの文章に、よく「1枚のスケッチ」という言葉が出てきます。どんな論理も1枚のスケッチにはかなわないと言うわけです。論理では想定できないような「1枚のスケッチ」を描けるかどうかが重要だと言うのですね。なんだか居合の達人のようなことをおっしゃっていますが(笑)、それくらい設計に価値を置いているんですね。
原さんの将棋好きも、そのことと関係していると思うんです。「将棋には展開だけがある」と書いているでしょう。棋譜を見ながら分析することはあっても、将棋は過去を見ていない、未来しか見ていない、展開だけしかないんだというわけです。将棋における「次の一手」と建築における「1枚のスケッチ」は、同じことを指していると思います。
原広司の思考方法
天内──原さんの本のなかによく出てきて印象深いのが宮沢賢治です。必ずしも詳しく採り上げられるわけではなく、名前だけが挙げられる場合が多いのですが、宮沢賢治が出てくるパターンは、集落とか農村とかで物語の主人公や村人たちがなんとなくわさわさやっているところに、博士や科学者がやってきてこれはすごいと発見して拾い上げていくというものなんです。たとえば杉の苗を700本植えた「虔十」の死後,アメリカから帰ってきた博士が「虔十の森」の価値を採り上げる(『虔十公園林』)。実際に地球上で行なわれている、土着的な建築実践と自然科学における知の働きあるいは学問や研究との間に、どういう関係がありうるのかを原さんご自身が考えていたときに、宮沢賢治の構造というのは、地球上の実践の構造と科学がすくいとっていく構造とが二重になっている。原さんももしかしたらご自身の実践と地球上の実践とを併せて考えていて、自然科学、典型的なところでは数学のようなものですくいあげる。原さんはそういうことを考えていたのかどうかと思いました。南──僕は修士論文を集落論で書いているのですが、そのときに原先生が宮沢賢治の話をしていたことを思い出しました。いわく宮沢賢治は化学と法華経だとおっしゃるんです。「〈非ず非ず〉と日本の空間的伝統」(『空間〈機能から様相へ〉』所収)やほかの論文なかでも「冷える」という言葉を使われている。僕が共同体論を書きたいと伝えると、熱くなってはだめで冷えた共同体論を書かなければだめだと言われたんです。レヴィ=ストロースの「冷たい社会」と「熱い社会」の対比がよく知られていますが、冷えるということに原さんは関心があったようです。
西沢さんのお話ではないのですが、原さんにはそれこそ宮沢賢治的な、天上の人というか仙人のようなところがあるんですよね。おっとりとして悠長な構えをもった方なのですが、一方で現実世界に対する強い苛立ちというようなものも持っていると思うんです。その苛立ちがかたちを変えて非常に高度な現実社会批判や近代建築批判につながっている。自立とか連帯とか、離れて立つことなどについて、たびたび言及される。例えばべたべたするのは嫌だと言う。自分で立て、頼るな、自分で生きろというスタンスで、研究室の学生にも厳しかった。
西沢さんが最初におっしゃっていましたが、こういう文章を書く方にはまったく見えないんです。にもかかわらず、同時に人物像と書かれたものとのアイデンティティの整合性をものすごく強く感じるのです。
西沢──〈非ず非ず〉について言うと、あれは論理的な話というよりも、倫理的な話だと思うんですよね。Aではなく、Bではなく、Bでなくでもなく、という無限のプロセスは、いわば将棋のごとく展開的であり、また生成的でもあります。ということはつまり、弁証法ではないということです。正反合といった再帰的、完結的なものではなくて、あれでもない、それでもない、これでもないという展開が、どうしようもなく続いていく。これを論理的に受け取ると、外部のなさ、まとまりのなさが非論理性のように思えてくるわけですが、もしも倫理的に受け取ったとすると、実は楽天的な状態を言っているわけですよね(笑)。人生で〈非ず非ず〉を実行できたとしたらかなり楽しいです(笑)。弁証法では生きられないんですよね。弁証法というのは死後の総括として出てくるもので、生きている最中はかならず展開的であり、生成的だと思うんです。原さんはそういうことに大きな価値を置いていると思います。その意味では、原さんの楽天性というのは、倫理的なもののような気がします。
ちょっと話が逸れますが、原さんの倫理については、中南米や北アフリカや中近東に対する態度にもよく現われていると思います。とくに中南米については集落調査で行かれただけでなく、今でも数カ国でセルフビルドを続けています。そもそもシュルレアリズム(ロートレアモン)も中南米から出てきたと、どこかで書いていたと思います。この中南米への態度は正しいと思うんです。中南米というのは近世以来、欧米にめちゃくちゃにされてきた地域で、とくに20世紀はアメリカにめちゃくちゃにされています。原さんが調査されていた頃はどの国も軍事傀儡政権で、一部の富裕層だけが近代都市を謳歌してはいても、大多数の国民は近世と変わらない農奴や貧民なみの扱いでした。原さんの集落調査は、そういう人々の生存拠点を研究しているのです。もちろん原さんは欧米についても興味をお持ちですけれど、自分が知識人としてなにを提出するかという場合は、中南米の貧民たちのような立場からものを考えている。欧米のものをちょっと洗練させてプリッカー賞をもらった先生や先輩たちとは違って、建築界では誰も知的な興味を持たなかった場所、たとえばべネズエラならベネズエラ、パナマならパナマから、未知の認識をつかみ取って提出するという感覚を持っておられると思います。
この態度はとても倫理的で、また教育的でもあります。僕のような80年代に勉強せざるをえなかった人間には、最も必要な情報でした。たとえば、僕は日本の近代化について、欧米と比較するのでなく、中南米と比較すべきだと思っているのですが、そのヒントは原さんの活動から来ています。
南──菊竹清訓さんの「か、かた、かたち」の理論や、あるいはルイス・カーンの「オーダー、フォーム、シェイプ」という考え方があります。この2つの理論には、目指すべきイデアルななにかがあって、そこに一歩でも近づきたいという感じがある。ところが、〈非ず非ず〉では、ああでもない、こうでもないと否定し続けて、それこそ手探りでどこに到達点があるのか、本人にもわからないし、主体すらわからない。いわゆる建築のある理論の方向性のヴェクトルとはぜんぜん違うところに向かっていると感じます。かといって、磯崎新さんのプロセス・プランニング論のように、つくっていってどこかで切断するというわけではない。原さんは、『建築に何が可能か』で、すでに「部分と全体」について考察されており、〈非ず非ず〉の原型になるような思考のかたちは、初期の頃からお持ちで、そのスタンスは崩れていないと思うんです。
原広司と数学
天内──原さんのオーラル・ヒストリーをWebで読むことができるんです(「日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ」http://www.oralarthistory.org/archives/hara_hiroshi/interview_01.php)。原さんは2012年に行なわれたこのインタヴューで、なお建築と数学に貢献したいのだとおっしゃっています。東洋的な、あるいは各集落に内蔵されている論理で、西洋的な近代の根本である数学の論理に貢献したいとお考えになるのだなと、意外な感じがしたんです。
西沢──たしかに原さんはいまも毎晩、数学書を読みふけっていますね。
南──天内さんの言及された集落と数学に関してなのですが、原さんは位相空間論とグラフ理論をずっとやっていて、一点付加問題と固有値の問題をずっと考えていらっしゃいます。比喩的に一言で言うと、集合としてさまざまなグラフの要素があり、そこにひとつの点を付加したときにどのように様相が変わるかということをずっと数学者の方とともに研究されています。例えば、ある状態の都市の群れがあり、そこに新しい都市をつくるとすると、大都市を強化することになってしまう。すなわち結果として中心を強化するように機能してしまう。そうではないモデルを考えるとしたらどうすればいいかを、長いこと研究されています。だから数学への意欲が何十年も続いていることははたしかです。
西沢──単に好きという次元じゃないですよね。
天内──ふつうの集落というと広場は真ん中にありそうなのですが、原さんは、広場が集落の辺境にあるケースをよく取り上げていますね。もしかすると中心を強化してしまうような傾向に対する別の解答として捉えられているのではないかと考えました。
南──もう少し話を拡張すると、建築計画学の射程とはなにかという問題設定があります。原さんは東大では建築計画学の授業をされていました。ビルディング・タイプ論とか、あふれ率、平面分析というような、伝統的な建築計画学の系譜がありますが、原さんの場合はそこにとどまらず、建築計画学として、学問や文化にどのように寄与できるかを意識されていたと思います。そのひとつの流れとして数学的なアプローチによって建築計画学をもう少し一般化することを探られていたのではないかと思います。
天内──いわゆるハウツー的な計画学ではなくて、集落などを観察した結果として計画学のエッセンスを抽出されたのでしょうか。
南──それもあるでしょうね。原さんはスタンダードな計画学はまったく教えなかったんです。大学院の授業でしたが、推理小説について4時間話すとか、別の回は現代音楽について4時間話すとか、量子力学だけについて4時間話すというようなもので、文化全体を広い射程において対象化することが行なわれていました。
西沢──5年くらい前に原さんと食事したときに、グリゴリー・ペレルマンのポアンカレ予想(http://ja.wikipedia.org/wiki/ポアンカレ予想)の解決について話したことがあります。原さんは位相幾何学が好きですよね。60年代、70年代は位相幾何学の隆盛期だったから、その迫力を目の当たりにしていたのではないかと思うんです。ポアンカレ予想についてもアメリカでは位相幾何学でトライされてきたんですけれど、ペレルマンの解決は位相幾何の手法ではなくて、現代代数や解析学の手法だったんですね。僕は幾何と代数の違いにはちょっとこだわりがあったので、「ポアンカレ予想、解かれちゃいましたね。でも幾何学で解かなかったのは事件じゃないですか」と聞いてみた。すると原さんは、「ペレルマンの式のあそこに〈重力〉って出てきただろう」と、具体的な興味を言ったんですね。
もちろんあの証明は、僕らには理解するのが難しいです。原さんも全部は理解していないはずです。アメリカの数学者たちがペレルマンを招待したコンフェレンスでも、彼の証明を誰ひとり理解できなかったそうです。ただ、原さんの興味についてひとつだけわかったのは、ペレルマンの証明のハイブリッドな性質を言ったことです。あれは物理の公式を含めたいろんな解析手法を用いた、ハイブリッドな証明なんですね。それもあってプロの数学者もすぐには理解できなかったようです。
もともと数学の証明には、大まかに言って2つのタイプがあります。ひとつは、見事に簡潔な式の連鎖でできているもので、ほとんど「レス・イズ・モア」と言いたくなるような美しい証明のことです。もうひとつは、いろんな種類の式を横断的していくハイブリッドなものですが、こちらも別の美しさをもった証明になります。これらのうち、原さんの数学に対する関心は、明らかに後者にあるような気がします。いわば数学においても、ミース的なものに抵抗しているのではないかという感じがします。もっと言えば、ミースに対する原さんの違和感には、もともと数学的な根拠があると思います。
天内──とくにトポロジーだけにこだわられていたわけではないのですか?
南──『数学セミナー』(日本評論社)をずっと読んでいらっしゃいましたからね。群論などもひととおりフォローされていました。いまの西沢さんのお話で面白いと思ったのは、1枚のスケッチについて原さんが言っていることともつながる。比喩的に言うと、原さんは1行の式を望んでいるのではないかということです。量子力学の話をされているときに、シュレーディンガーの波動方程式に言及されたことがありました。光の波と粒子の両方の異なった挙動を1行の短い式で記述する方程式です。それと同じように、ロシア・フォルマリズムから、シュルレアリスム、あるいは近代建築など、自分が言及したさまざまなことを非常に美しい短い1行の式としてうまく表現したいという思いがどこかにあるのではないかと思ったんですね。
また、「様相」という言葉についてなのですが、原さんは「aspect」ではなく「modality」の訳として出しているとおっしゃっています。ジョン・ロックやハイデガーなどの著作を読み返して調べていらっしゃったのですが、「様相」という言葉がけっこう出てくるようなんです。実際には様態などと訳されたりしているのですが、歴史を遡った際に、自分が考え出した概念がどこでどう使われているのかを原さんはずっと調べていました。
天内──自分の直観の裏づけを自分でされていたということでしょうか。
南──そうかもしれないですね。
西沢──『空間〈機能から様相へ〉』に、ハイデガーに対する寸評が出てきますよね。ハイデガーは「道具」という概念で人間のあり方を巧妙に説明したけれど、彼の言う道具はまともに作動する機械であって、実際には壊れた機械というものがあるんだと言っていたはずです。ハイデガーは壊れた機械のことがわからない。わからないから巧妙になる、ないし深淵になる。むしろシュルレアリスムやロシア・フォルマリズムのほうが壊れた機械のことを直観的に理解したと。
天内──『空間〈機能から様相へ〉』に、「壊れた道具にかこまれたハイデッガーにとって、それらの断片は、やはり『道具』として現われる」とありますね。ル・コルビュジエの「機械」に対応した議論をシュルレアリスムにつなげていく文脈でハイデッガーを経由しているのですね。
西沢──そうです。あそこで「壊れている」とか「壊れていない」と言われているのは、暗に数学的な「道具」のことを指していると思うんです。ハイデガーは数学に興味がないから、数学という単語は出てこないですが、師匠のフッサールは数学者でした。数学における「道具」、つまりさまざまな定理や数式には、普通の日常的な道具と比べて、ひとつだけ違いがあります。それは用途が決まっていないということです。いわば遊び方の決まっていないオモチャのような存在が数学的な「道具」です。19世紀末から20世紀初頭は、「数学の危機」の時代でもあったわけですけれど、それは数学が自分自身の「道具」によって殺されかけた時期です。この「数学の危機」がなかったら、フッサールの現象学はないし、ということはハイデガーの存在論もない。原さんの好きなヴィトゲンシュタインも「数学の危機」から出てきました。この時期以降、数学における「道具」は、いわば壊れているような壊れていないような、奇妙な存在になったんですね。壊れているかどうかわからないのに、有用だということになったのです。それが数学的な意味での「壊れた道具」です。たぶん原さんは、そういう感覚で今の世の中を見ていると思います。現代数学のもっている粗さと繊細さで、20世紀以降の世界を見ていると思います。
西沢大良の思考と設計
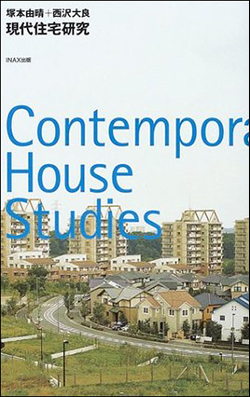
- 塚本由晴+西沢大良
『現代住宅研究』(LIXIL出版、2004)
西沢──理論と実作の関係ということですかね。理論というのは言葉なので、そのまま実作にあてはめると間違うことが多いのです。だから理論に対する警戒心というのが、根本的にあるのです。ですから設計するときには、自分の理論であれ他人のものであれ、頼らないようにしています。もっと言うと、既存の理論をなるべく忘れるようにしています。だとしても、きちんと考えてつくられた新鮮な作品であれば、かならず驚くべき認識や理論を引き出せると思います。逆に新鮮でない作品からは、ろくな認識を引き出せない。そういう意味では、僕は実作中心主義者で、理論に対する本当の意味での尊敬を持っていないのかもしれないです。いずれにしても、理論と実作の関係において、理論に従うような気持ちはゼロです。
『現代住宅研究』の場合も、まずいくつかの印象的な住宅があり、それに対する定まった評価もすでにあったわけです。問題は、その定まった評価が、それらの住宅の新鮮さに匹敵していないことです。だから僕の担当した住宅作品については、そこからこんなに面白い認識が出てくるのだと、証明したいと思って書きました。だから既存の理論的な意味付けを排除しながら書いてある。こういう態度は、自分の設計中の計画案に対する態度と、ほとんど同じなんですね。
天内──それは図面に具体的に線を引いているときにも考えられるのでしょうか。
西沢──考えます。「理論を忘れて」設計するということは「よくある理論を忘れて」設計するという意味で、そのかわり新しい認識や理論が出てくるまで設計を続けることになるんです。だから、ものすごく考えることになる。しかも、デザインというのは、究極的にはAがいいかBがいいかという、判断だけなんです。その瞬間的な判断に対して、批判的な理論を瞬時に考え出して、対抗するわけです。すると、Aでいけば近代建築型になって売れっ子建築家になるだろうけれども、本当に未知のものを目指すならばBだ、ということになったりします。
天内──そういう局面が出てくるんですね。
西沢──出てきますね、細かいところで。しかも事務所全体でそれをするのです。例えば立面のスタディをしているとします。水平連続窓を使うとそれなりにいい商品になるわけですが、今の日本では、ル・コルビュジエの出来損ないみたいな建物にしかならないです。ではどうするかというと、まず所員全員に、「俺たちは水平連続窓は禁止だ」と伝えるのです(笑)。「こんなむちゃくちゃな街で、こんな小さな建物をやっていて、コルビュジエのケツを舐めるようなまねをしてどうする。ここでしかできないものをやろう」と言うわけです。それでいいものができるかどうかはまた別の問題ですが、水平連続窓は禁止とか、白く塗るのは禁止とか、その都度美学的な制約を設けます。もちろん制約を設けないケースというのもあるんですが、既成の手法を使っていくとお手軽に作品ができてしまうので、放っておくとついついそっちに流れてしまうから、それをマネージメントするわけです。もちろん制約の理由を聞かれれば、ちゃんと理論的に説明します。ただ、その結果どういう計画案に到達するのかは、理論では予測できないです。そういう場面になると、理論は無力です。そのつど盲目的に判断していくしかないんです。
最終的な判断基準は、あまり上手い言い方ができないんですけれど、今まで聞いたことのないような新しい認識が湧き上がってくるかどうかです。本当に未知なものに出会うと、僕の場合は認識を言いたくなるからです。そういう計画案は建てる価値があると考えることにしています。逆に、既知の論理に回収可能な計画案は、どんなに完成度が高くても却下します。
南──まさに〈非ず非ず〉ですね(笑)。
西沢──〈非ず非ず〉という言葉は、設計の現場をうまく言い表わしているのです。人間の活動を言い表していると思うんです。つまり人間の歴史はどのように進んでいくのかといえば、弁証法的に進むわけではないんだと。もし弁証法で進むのならば歴史はナポレオンで終わるのかもしれないけれど、実際にはその後も歴史はどうしようもなく続いていく。それは〈非ず非ず〉で続いているということになるんじゃないですかね(笑)。〈非ず非ず〉でいけば歴史は止まらない。ただし、地獄に堕ちることもあるかもしれないけれども(笑)、かくも文明が変転を遂げていくことは、了解可能になりますね。
大学が可能にする建築教育
南──いまの西沢さんのお話はとても面白いですね。理論は思考を拘束するものではない。むしろ危機的なものであり自分でもどこに辿り着くのかわからない。そのわからない先で、なにかの理論が立ち上がるのだと思います。理論に身をゆだねることは気楽なことではなく、むしろ逆で、リスキーなんだと思うんです。西沢──つまり理論の生成ということですね。原さんご自身が大学生のとき、1950年代半ばは、GHQによる占領が終わった直後です。当時の大学では、戦前の学問がよくなかったとされて、新たに学問が生成していった時期です。僕らの学生時代のように、建築史にしても計画学にしても既成の学問としてあったわけではなかった。吉武泰水さんや鈴木成文さんたちが計画学なるものを打ち立てようと研究されていたし、丹下健三さんや高山英華さんも近代都市についてどのようなツールでどう分析したらいいのか、そしてどう実現していくのかを考えていた時期でした。その意味では、日本の50年代はもちろん、欧米の50年代も、わりと知的な活力に溢れていた時代だと思います。そういう現場を目撃されているから、原さんは今でも学問に対する尊敬を保っておられるのではないかと思います。
いつだったか原さんに、「東大の先生って大変じゃないですか」とお訊きしたら、「いやあ、学問の名に値することをしている人はほとんどいないよ」という答えが返ってきました。いままさに生成している学問は極めて少ない、いま起きている説明不可能な現象を解明しようとする知性がほとんどない、とおっしゃっていました。学問というものを尊敬されているんだなと思いました。
南──たしかに80年代というとアーカイヴ化とサンプリングの時代に入っていく時代ですからね。この研究会のテーマでもありますが、現在の環境といえば、過去の組み合わせだけでなんとなくなにかをやっているかのように思えるわけですよね。
さらに、お話をおうかがいしたいと思うのは、教育についてです。原さんは、いま西沢さんからお話があったように、教育者として長く研究室を運営されていました。大学では都市の研究、事務所では建築をやったと原さんはおっしゃっていましたね。もともと大学では都市を研究したいという思いがあったのだと思います。集落調査をはじめとして、活動等高線(Activity Contour)の研究、いわゆる都市活動と呼ばれるさまざまな事象をどう記述するかをテーマにされていました。原研からは、隈研吾さんや小嶋一浩さんなどの建築家を輩出していますが、大学での活動と事務所での活動をはっきりと分けています。
天内──設計の対象の多くはどうしても建築単体でしょうし、一方で都市という大きな対象を研究するには大学という装置を活用することは理に適っていますよね。
南──西沢さんも長く教育の現場に関わられて、現在は芝浦工業大学で教えられています。設計教育なのか、建築学の教育なのかなど、さまざまな切り口があると思うのですが、大学における教育についてどのようにお考えでしょうか。

- 原広司《京都駅》(1997) 撮影=663highland

- 原広司《梅田スカイビル》(1993) 撮影=Suisui
南──『空間〈機能から様相へ〉』や『建築に何が可能か』では、たしかにコミュニティの話がところどころに出てきます。近代建築がコミュニティを復活させようとするのだけれども、結局方向が違っていたということが書かれています。また、コミュニティにはどうしてもうさんくささがつきまとうが、その一方で、コミュニティという概念を抜きにしては語れない現実があり、そうした状況に対してどうやって折り合いをつけていくべきかという話を研究室ではされていました。
また、『GA Japan』No.124(A.D.A.EDITA Tokyo、2013)「特集=歴史観なき現代建築に未来はない」では、原さんと二川由夫さんが対話をされています。ここ何年か、学生の卒業設計に関するさまざまなイヴェントが全国で行なわれていますが、原さんは嫌いらしいんです。ゲストで呼ばれても行かないし、あんなつまらないことはやるべきではないと批判している。つまり、設計のトレーニングをしなくてはならないはずなのにプレゼンテーションのことばかりを考えている。そもそもプレゼンテーションは、設計のトレーニングを積み重ねていけばある程度自然に身につくものなのだから、本末転倒だというわけです。
大学が重要だという話はずっと昔からされていました。原先生の学生時代とは状況がだいぶ変わり、いまでは高校から大学への進学率は50%前後です。西沢さんや僕のころですら30%以下でした。原さんのころは10%前後だった(参考=http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/03090201/003/002.pdf)。大学が大衆化したことで、原さんの学生時代とはかたちは変わってしまっている。とはいえ、大学に信を置く態度は、原さんの場合はずっと変わっていない。大学こそが重要であり、そこからなにかが生まれないといけない。キャピタリズムとは違った文脈のなかで、なにかを産み出し、なにかを守らなければならない。原さんが字義通りの教育者であったかどうかは僕はわからないのですが、大学人であったことはたしかで、大学でしかできないことに対する「信」というのは、ずっとあったんだと思うのです。
西沢──原さんが大学でやった集落調査は、民間の企業やコンサルではできないです。それどころか、民間のNGOやジャーナリストさえ二の足を踏むような、紛争地域や占領地域なども集落調査で訪れていますよね。大学という機関の可能性や存在意義について、原さんはすごく考えていたと思います。
南──西沢さんは今年度から芝浦工大で専任で教えられるようになり、いわゆるプロフェッサー・アーキテクトになられたわけですが、建築教育や大学教育についてはいかがお考えでしょうか。
西沢──まだ着任して半年なので、いまの大学で何ができるのか、まだ手探りの状態なんですけど、建築の実務を大学で行なうつもりはないんです。建築の設計で新しいものをつくるには、ひとつだけ条件があります。十分条件ではなくて必要条件です。それは担当した物件のことだけを、1─2年間かけて、来る日も来る日も延々と考え続けることです。事務所ならばそれができるのですが、大学の研究室では難しいです。事務所で基本設計、実施設計、監理とひとつの物件だけを担当していると、ある時期には連続して壁にぶつかり、別の時期にはそれを放置していられるので、ブレイク・スルーが起こりやすくなります。研究室の学生は授業もあれば研究もあるから、ひとつのことに集中できないので、建築を設計してもブレイク・スルーは起こらない。だから大学の研究室では、事務所ではできないことをやろうかなと思っています。
パースペクティヴを携えた言説
南──原さんの著作について改めて振り返ってみると『建築に何が可能か』が1967年の刊行で、『空間〈機能から様相へ〉』が1987年ですが、「均質空間論」が書かれたのは1975年です。西沢さんや僕が『空間〈機能から様相へ〉』を手にしたときには新しい本だったわけですが、「均質空間論」に関してはすでに38年が経っており、歴史化されていると捉えることが可能です。先ほど西沢さんがお話されていた近代建築批判に関する80年代の状況ですら、いまではすでに昔のことになってしまった。
- 西沢大良「現代都市の9か条──
近代都市の9つの欠陥」
『新建築』2011年10月号(新建築社)
西沢──そうですね。僕の学生時代には、少数ですが、独自のパースペクティヴをもった建築家や批評家がいました。「パースペクティヴ」とはつまり、なぜ歴史がこのようになり、今後はどうなるのかを探りながら、現在の出来事を把握させるような長期的な認識、という意味です。あるいは、現在の価値を外側から測定するような外部的な認識、という意味でもあります。もちろん原さんはそうしたパースペクティヴをお持ちでした。あるいは、歴史家の稲垣栄三さんも強力なパースペクティヴをお持ちでした。さらに言うと、黒沢隆さんも独自のパースペクティヴを持っていたし、八束はじめさんも別のパースペクティヴをもっていました。海外の人もそうです。パノフスキーは強力なパースペクティヴを持っていたし、夭折したロビン・エバンスも鋭いパースペクティヴを持っていました。そういう人たちの文章をよく読みました。もちろん、そんなことだけ考えていたわけではないのですが、自分のパースペクティヴを持たずに一生をごまかすことはできないと思っていました。パースペクティヴである以上、間違うこともあるでしょうし、それは致し方ないと思うんですが、間違えたくないから放棄するというのは、卑怯だと思っていました。建築をつくるなら、これを放棄することはできないと思っていました。
仮に、いまここにパノフスキーが現われたとすると、独自のパースペクティヴを持っていないと話にならないと思うんです。相づちを打つのではなくて、「お前の意見には一理ある」と言わせるには、長期的で外部的な認識が必要だということです。それは知識じゃないのです。パノフスキーの引用や解説をするといった知識は、本人が目の前にいたら意味ないです。意味ないということは、知的な活動ではないということです。あるいは、仮に稲垣栄三が目の前に現われたとき、論破できるのかというようなことです。稲垣さんの調査対象になるような建物を示せるのかということです。長期的で外部的な認識を持っていないと、話もしてもらえないと思うんです。そういうことを考えながら、本を読んでいました。というか、そういうことを自分に考えさせるために、本を使いました。さもないと自堕落になってしまうから。なにしろ80年代だったから。
南──たしかにマイスターであり、父であり、仮想敵であり、導き手でもあるような書き手が存在しました。
西沢──そういう文章が少なくなったんですね。僕が『新建築』に書いた都市論は、かつてそうやって先人の文章を読んでいた学生が、その後25年間に起きたこと、とりわけ90年代以降に世界的に起きていることを重視して、書いたものです。だから、あの都市論も若い人に読んでもらいたいんですよね。そのためにすごく労力を使っている。なるべく認識の連続だけにしたいと思っているんです。認識が良ければ、長い文章でも読めると思うんですよね。
いまの政治や経済をみれば、アベノミクスが典型ですけれど、恥ずかしいくらいに短期的で内部的な利益誘導ばかりです。誰も長期的な問題を考えず、今だけ儲かればいいという風潮です。戦争もしちゃおうかなあとか、遺伝子組み換え食品も売りたいなあとか、原発も続けたいなあとか、スパイ国家にしちゃおうかなあ、という風潮。地獄に向かってみんなで笑顔で進んでいるような状況ですね(笑)。
ただ、それは若い人が支持しているのではなくて、僕らのような40─50代が支持層なわけですよね。資本が本当に切り捨てたいのは僕らです。コストがかかるからです。そして国家が切り捨てたいのは高齢者です。再生産をしないからです。だから切り捨てられないように、息をひそめて昔ながらの体制を支持している。そういう支持層は、近代都市によって生み出されたというのが、僕の意見なんですよね。だから近代都市を部分的にでもつくり変えていかないと、どうにもならないです。近代都市、つまり近代産業や近代エネルギー事業や近代農業といったパッケージを、懲りずに続けようとするからこのザマです。仮にどれほど優れた政治思想や経済政策が出てきても、都市が近代都市のままならば、同じことになると思います。
僕らが学生の頃には、そういうことを考えさせる文章がいくらもありました。近代都市と近代建築はいかがわしいという意見に接する機会がありました。そういう意見が消えたんですね。
南──2020年に東京でオリンピックが開催され、2027年にリニアモーターカーが開業するわけですが、事程左様にいまのキャピタリズムではせいぜい20年ぐらい先のことしか考えられていない。歴史的パースペクティヴと呼ぶにはあまりに短期的です。福島の原発を廃炉にするまでに数十年かかると言うけれど、エネルギーの貯蓄量などのことを含めても、その先のことはまったく考えられていない。どこを見てもそういう状況です。
再び、建築にとって理論とはなにか
天内──80年代に現われたアーカイヴ化とサンプリングはいまや「Delirious」に日常を占めていますが、そうしたなかで前回、レム・コールハースの『錯乱のニューヨーク』ははたして理論書と呼べるのかどうかが議論されましたね。西沢──『錯乱のニューヨーク』は、70─80年代のコールハースの言説のなかで、むしろ良くない部類だったという記憶があります。たしか83年にフランスの『L'Architecture d'Aujourd'hui』誌にOMAの特集が出たんですが、そのときの文章や談話のほうがずっと良かった。あるいは80年のベルリンのInternationale Bauausstellung(IBA)に提出したフリードリッヒ・シュトラーセの分析(http://oma.eu/projects/1980/kochstrasse-friedrichstrasse-housing)もとても良かった。でも『錯乱のニューヨーク』の時点では、認識もそんなに良くなかったし、文章も妙に饒舌でした。それは、真に解明すべき対象を失ったときに生じる饒舌さのように僕には思えました。
もともとあの本は、理論としてというよりも、理論の消滅のために書かれているでしょう。理論が消滅しつつあった70年代末に、いち早くそれを演じてみせたということ。だから、いろいろ分析しているのに、何も解明されない。でも70年代にアメリカにいるのなら、解明すべきことがあったと思うのです。中南米とかめちゃくちゃにされていたわけです。中近東もそうです。ニューヨークの資本主義を言うのなら、そちらを分析の対象にすべきです。その意味では、その後ヨーロッパに帰って実作を作り始めた直後は、取り上げる対象が変化して、認識も良くなった。当時のヨーロッパは凄く不景気で、たとえばイギリスなどは史上最悪の状態で、そこから今に続く新自由主義が始まったわけですが、そういうことを対象化するようになった。
建築家による優れた理論や認識は、かならずその背後に巨大な対象を抱えていると思うんです。建築家以外の理論一般、たとえば哲学なども、わりとそうかもしれないです。哲学にも対象性のあるものとないものがありますよね。例えば、ハンナ・アレントの文章には対象性があって、彼女の考察は必ずナチスを標的にしている。リテラルには「全体主義」と書いてあっても、それはヒットラーを受け入れたかつての同胞たちのことを指している。それは今日の世界も乗り越えていない問題なので、今でも解明するに値すると思います。そういう巨大な対象をもっているから、今でも読めるということがある。これに対して、ほとんど同時代のカッシーラーの書いたものには、あまり対象性を感じない。僕が知らないだけかもしれませんが、何を標的に書いてあるのかわからない。 建築家の書く理論は、明らかに外部に対象をもっているんですね。何らかの実作なり流行なり事件なりを擁護したり敵視したりしながら書かれています。その対象がどこまで巨大かによって、建築理論の水準が決まるのではないかと思うんです。建築家は取り上げる対象を間違えると理論を生み出せないし、対象を消されてしまっても理論を生み出せない、という気がします。
南──一方で、将棋や展開性というキーワードを使って原さんの思考方法を説明されていましたが、理論書のなかには、「書いている自分がどこに行きつくのかわからない」という書き方がされている本があります。文字取り、予定調和ではないかたちで、ベルグソン流の、予期せぬ跳躍を求めて思考を進めるかたちのものですね。建築を設計する際も最終的にどこに行きつくのかわからないからこそクリエイションをしているわけです。つまり、「理論とは何か」を問うた場合に、前回のテーマ『錯乱のニューヨーク』、あるいはコールハースの建築は理論的か否かという水準とは別のテーゼがあると思うんです。
『空間〈機能から様相へ〉』の「序文」に「マルクスはカントをノックアウトしている」という一文がありますが、『グラマトロジーについて』でデリダはなにかを完全にノックアウトした感じを読み取ることができます。
ある完成型として、スタティックで隙のないモデルを構築するというのではなく、自身の思考を終わりのないダイナミズムの渦中にさらしてみる。そしてそこから、偶発的な、予期せぬ思考のかたちを生み出そうとしてみる。そんな運動の軌跡自体を、「理論的」と呼ぶように思うのです。
原さんはよく、ネオ・プラトニズムのことを語っていたのを思い出しますが、それは、ネオ・プラトニズムの思想が、偶発的な介入により、世界を新しく展開させる力を持っていたことに惹かれていたからだと思います。
とは言え、理論の有効性の問題というのはつねにつきまといます。建築の場合は、理論と作品の乖離は必然的に起きてしまう。それを前提としながらも、建築理論を考えること、また理論的な態度自体について考えることは、ひとつの希望だと思うんです。現実世界の不可能性やどうしようもない絶望に対する裏返しとして、わずかばかりの希望から絞り出されてくるものが、理論なのではないかと僕は思います。
[2013年11月5日、LIXIL:GINZAにて]
書誌情報
原広司『空間〈機能から様相へ〉』(岩波現代文庫、2007[初版=岩波書店、1987])
南泰裕(みなみ・やすひろ)
1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。
天内大樹(あまない・だいき)
1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。東京理科大学工学部第二部建築学科ポストドクトラル研究員。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。
西沢大良(にしざわ・たいら)
1964年生まれ。芝浦工業大学教授。1993年、西沢大良建築設計事務所設立。作品=《大田のハウス》(1997)、《諏訪のハウス》(1999)、《駿府教会》(2008)、《今治港再生都市計画》(2009)ほか。著書=『現代住宅研究』(2004)、『西沢大良1994-2004』(2004)、『西沢大良2004-2010 木造作品集』(2011)ほか。



