政治としての建築──隈研吾『対談集 つなぐ建築』
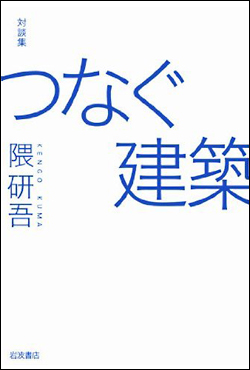
- ◉隈研吾『対談集 つなぐ建築』
(岩波書店、2012)
対談相手は、政治学者、生態心理学者、都市プランナー、演劇作家と、2人以外は他分野の人間である。建築分野の2人は藤森照信と伊東豊雄だが、世代も立ち位置も隈とは異なる。では、本書は座談の名手ぶりが発揮された余興かというと、そうではない。どのページでもいいので開いてみよう。その対話の真ん中には《建築》がある。どんな建築か? 表現としての建築でも、経済としての建築でも、思想としての建築でも、環境としての建築でも無い。「政治としての建築」である。
本書の底に流れているのは「建築空間は政治空間」という率直な信念だろう。それが本書を寄せ集めではなく、一冊の書籍に仕立てている。率直な信念は隈研吾だけが抱いているものではない。対談相手の誰も、建築と無関係のイメージゲームや、大きな時代背景の話でお茶を濁してはいない。今は「政治の季節」なのだ。
「今」と書いてしまったので、先に進む前に書いておかなければならないのだが、正直に申し上げて、東日本大震災を経てこの国に何が起こったのかが、この文章を執筆している私にはまるで見えていない。 何が変わり、何が変わりつつあり、有形・無形に現在何が進行しているのか。その中で、本当に東日本大震災と原発事故が変えたといえるものは何なのか、つかめていないのだ。だから、ここで言う「今」は、震災後に限定した時間ではなく、それを含む連続的な最近といったくらいの意味である。実際、本書は前の5編が2011年3月11日以前の対談で、後の3編が震災後の収録である。今年4月に産経新聞に掲載された書評(執筆者は美術評論家の新川貴詩)では、本書が「半分をすぎたあたりから、対話の内容やムードなどが、唐突に大きく変わる」珍しい対談集であり、「震災で一人の建築家がどう変わったかを記すドキュメントでもある」と紹介されていたが、実際に読んでみると震災の前後でトーンに変化があるようにはまったく感じられない。なので、少なくとも本書を評するうえでの「今」は、断絶のない2010年代といった認識でも構わないと考えて、先に進む。
今は「政治の季節」であり、本書は「建築空間は政治空間」という信念で一貫していると述べた。もう少し書くと、それは「空間」を社会の対立や利害の調整の結果だけで無く、それを実現させる作用として捉えているということである。ここまでの話は本書の中に明記されてはいないが、そうした思想が全編によって構成されている。
例えば、御厨貴が語っているのは「権力の館」の表層のデザインではなく、それをどこにどのように構えるかいう空間配置の効果である。原武史との対談は2編あるが、どちらもマニアックともいえる物そのものへの拘泥から、空間の中での配置が思想と連関する様を論じてスリリングだ。一編は日本の団地がそれとよく似たソ連の集合住宅とは因果関係が逆になって、空間形式から政治形式が生まれたと述べ、もう一編では鉄道を社会や文化の表象であると同時に、それを生み出すものとしてとらえている。
御厨と原は政治学者だから、このように空間を《政治》として把握するのだろうというと、そうでもない。アフォーダンスの研究者として知られる佐々木正人と語り合っているのは、空間が人に働きかける作用の最小で、原初的で、それゆえ暗黙裏に支配的な「肌理」に関してである。「空間」という言葉を使っても、いわゆるモダニズム建築のように明確な輪郭線で切り取られた均質なヴォイドを意味してはいない。これは本書全体における「空間」の定義だ。
演劇作家の岡田利規と驚くほどに話が一致しているのは、人為的に調整した《政治》をどこまで出すか出さないかという決定に関してである。それは常にごりごりと押し出していく旧来型の「政治」ではないにしても、反「人為」や反「政治」などではまったくなく、ともすればそう見られがちだった隈や岡田のこうした発言に、2010年代がはっきりと感じ取れて感慨深い。
感慨深いと言えば、2人の建築関係者も同じだ。もとから社会に杭を打つような個人の決定性に惹かれている藤森照信はともかく、「批評としての建築をつくること〈中略〉を逆転しない限り、建築家はいつまでも社会に組み込まれないだろう」と公言するに至った伊東豊雄の率直さを、本書は収録している。
そして、《建築》と《政治》の関係が最もストレートに説かれているのが、都市プランナー・蓑原敬との対談だろう。本の真ん中に置かれ、他の倍の分量を持ち、対談と掲載との間に東日本大震災が起きた。いわば本書の核だ。開始早々、蓑原は隈に次のように迫る。
「私が心配するのは、あなたはほんとうの意味で負けると言っていないにもかかわらず、『負け』が表に出て、市場原理主義者とか市民参加原理主義者たちに武器を与えているのではないかということです。」
いつもの隈の手管と「市場原理主義者」と「市民参加原理主義者」の三者が、短い言葉で一刀両断だ。なぜそんなことが可能になっているかというと、知性と勇気があるからであって、この言葉自体が知性と勇気無きものに対する投げつけである。そして、蓑原と隈は語り合う。現場を知ること、表層ではなく力学を見ること、個別性の中に次の普遍があること......つまり政治空間についてである。
「政治としての建築」と言っても、建築を政治の道具にするとか、建築は政治を利用すべきといった類の話でないことは、もうお分かりだろう。《建築》は社会の対立や利害を調整する政治であり、それは国土計画から素材のタッチまでを本質的には切り離せない「空間」の布置によってなされる。こうして本書によって、《建築》と《政治》の本来的な類似性が明らかにされていく。

- ◉安冨歩『原発危機と
「東大話法」──傍観者の論理・
欺瞞の言語』(明石書店、2012)
◉東浩紀『一般意志2.0
──ルソー、フロイト、グーグル』
(講談社、2011)
◉與那覇潤『中国化する日本──
日中「文明の衝突」一千年史』
(文藝春秋、2011)
何かずいぶん「当たり前」を書いているようだが、この当たり前のことが、ますます浮上してきたのが「今」ではないだろうか。思いつくままに挙げれば、安冨歩『原発危機と「東大話法」──傍観者の論理・欺瞞の言語』(明石書店、2012)は、わが国になぜ「民主主義」と「個人主義」が根付かないのかという丸山眞男的なてらいのない問いであり、東浩紀『一般意志2.0──ルソー、フロイト、グーグル』(講談社、2011)はその「日本」的ヴァージョンアップを図り、與那覇潤『中国化する日本──日中「文明の衝突」一千年史』(文藝春秋、2011)は同じ問題に「中国」という新たな軸を持ち込んだ。戦後的な問題系が、具体的にこの場所でどうであるかが、東日本大震災以前から捉えられている一例だ。これに高度成長期の建築・都市に対する再考を加えてもよいだろう。すべてを交換可能な情報とみるのでもなければ、「世界」に一足飛びにつながるのでも、現実から抜け出ようとするロマン主義でもなく、《場所》に向き合っていくこと。そうした態度が中核になっていった今、挑発する隈研吾は終わり、実行に歩を進めているのだ。
201206
特集 書物のなかの震災と復興
木造仮設住宅から復興住宅へ──はりゅうウッドスタジオほか『木造仮設住宅群──3.11からはじまったある建築の記録』
線の思考──寸断とネットワーク──原武史『震災と鉄道』
混迷のなかで提示された技法としての倒錯──大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ──3・11後の哲学』
私たちの凄まじく具体的な暮らし──鞍田崇、中沢新一ほか『〈民藝〉のレッスン──つたなさの技法』
「今、音楽に何ができるか」という修辞に答える──震災時代の芸術作品
再び立てられた「問い」──露呈した近代─反近代の限界を超えて──日本建築学会編『3・11後の建築・まち──われわれは明日どこに住むか』
日本という〈身体〉の治癒はいかに可能か── 加藤典洋『3.11──死に神に突き飛ばされる』
逃げない「ヒト」を避難するようにするには── 片田敏孝『人が死なない防災』
政治としての建築──隈研吾『対談集 つなぐ建築』
社会がゲシュタルトクライシスにおちいるとき──篠原雅武『全─生活論──転形期の公共空間』
「拡張現実の時代」におけるプロシューマー論の射程──宇野常寛+濱野智史『希望論──2010年代の文化と社会』


