混迷のなかで提示された技法としての倒錯──大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ──3・11後の哲学』
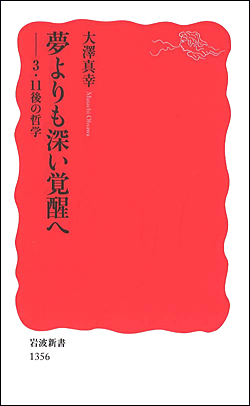
- ◉大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ──
3・11後の哲学』(岩波新書、2012)
実のところ、評者が本書に感じている捉えどころのなさは、上に述べたようなこの書物のできあがりの経緯に由来しているのかもしれない。ひょっとしたら本書は、大澤真幸が、震災と原発事故、それに続いて起こった放射性物質拡散クライシスといった状況に直面して、知識人として、あるいは哲学者として何とかしなくてはいけないという義務感と焦燥のなか、急ぎ足で書き綴った一連の論考を急いでまとめただけのものではないか、とさえいぶかしんでしまう(もしそうであったならば、問題にすべきは編集サイドの態度だろう。自分のような古いタイプの読者にとって、「アド・ホックな編集方針で足早に作られた岩波新書」というものは、もはや矛盾でしかない)。読者が目にするのは、浮き足立った仕草で既存の論理を武器に原発事故と放射能問題に立ち向かう大澤真幸の姿であり、ときにその攻撃が功を奏し問題の核心に触れつつも、別のときには大いに肩すかしをくらっているかのように見えるそのさまは、「敵」の大きさもあいまって、ドン・キホーテ的な情景を想起させずにはいられない。
もちろん、本書で指摘された数々の見解のなかには、注目するに値するものも少なからず見受けられる。とりわけ「未来の他者」に向けられた一連の考察、すなわちロールズの「無知のヴェール」批判から始まってフェリーニの『サテリコン』やパリの二月革命を題材に展開された論考(主として第III部)は、著者の意図と歴史的・文化的分析から引き出される理論的帰結が見事に交点をなし、現代の正義論の欠陥を突いた読み応えのある明晰なくだりとなっている。未来の他者をどのように発見すべきなのかという問いに対して、それはすでにわたしたちのうちにある、未来の他者の姿はわたしたち自身の内に先駆的に見いだされるべきであると答える大澤の議論は、ニーチェの時間論やマルクスの歴史認識を思い起こさせる明解なものだ。だが同時に、この反=時間的な(アナクロニックな)身振りによっても想起されることだが、提起される倒錯の質によっては、本書の議論がきわめてあやういバランスの上にあるということも、指摘せずに済ますことはできない。というのも、これらのあらゆる「倒錯」は、「3・11」以降大澤ら知識人が抱え込んできた複雑な立場と不可分なものに思われるからだ。さらに言えばそれは、「3・11」以降、言論に関わるすべての人々に突きつけられた問いかけなのだろう。わたしたちは「ただちに」役に立つ処方としての言説や思考を提出すべきなのか、それを求めるべきなのか、それを知識人や学者に対して求めるべきなのか?......

- ◉同『文明の内なる衝突──
9.11、そして3.11へ』
(河出文庫、2011)
◉『サンガジャパン』6号
(サンガ、2011)
◉同『THINKING「O」』10号
(左右社、2011)
中核をなすこのロジックを明らかにするために、ひとつめの箇所についてもう少し説明を加えてみよう。原子力が神のように信仰されていたことを証明するために大澤が中心的に提示したのは、原子力平和利用の情勢を受けて財を成し、当時「ウラン爺」と言われた東善作という人物の例である。大澤は、こうした例が多数あると言いながら、そこからの帰結として、「二〇世紀の中盤には、原子力や放射能が、富や健康などのあらゆる幸福をもたらす救世主のようなものになりうると感じられていた、という事実」(80頁)があったと述べる。だが、これは本当に「事実」なのだろうか? ここで問題とすべき点があるならば、それはむしろ、「富や健康などのあらゆる幸福をもたらす」新しい物質的な発展が人々に待望されていたという状況だったのではないか? 人々はようやく訪れつつある物質的な幸福に群がり始めていただけのことであって、その状況はけっして「救世主」待望や信仰などといった宗教的な言動とイコールではないように思われる。大澤の犯した誤りを端的に言うならば(いや、これこそが大澤一流の「倒錯」かもしれない)、パワー・ポリティクスとエコノミクスに基づいた現実的な権勢の強大さのことを、神に匹敵する超越的な審級と見なしてしまっていることだ。だが、仮に現実的な権力がどれほど強大にそびえ立っているとしても、それはあくまでも人から発し、人に属している。大澤自身も忘れてしまっているかもしれないが、大澤もわたしたちも、人なのだ。原発事故にまつわる現状から苦しみがもたらされているとしても、それはわたしたち人が作り出したものによって苦しめられているに過ぎない。大澤はそれを「神」と呼んでしまう。そのとき人が神になる。そしてこのレトリックが、原子力発電所に由来する数々の「人災」を「天災」へと読み替えることを許してしまう。致命的な倒錯がここにはある。実際、本書におけるすべてのアナロジーは、次元の異なるものを力業で共約するこの種の倒錯に由来している。そこには事象の現実的な詳細を見据えた精密な吟味が──決定的な仕方で──欠けているように思えてならない。
この書をドン・キホーテになぞらえたのも、それほど間違いではないようだ。やせた駄馬を名馬と思い込み、風車を巨人とみなして戦いを挑んでいくラ・マンチャの男の言動は、すべて、現実にあるものを騎士道物語の存在と見誤るドン・キホーテの倒錯に基づいていた。もちろん、倒錯によってのみ可能になる効果的なアナロジーも存在するかもしれない。自分だけの物語を世界のストーリーと重ねあわせるような「姫」に出会えるその日まで、倒錯者の遍歴は続くのかもしれない。いずれにせよ、フーコーの『言葉と物』に従うならば、セルバンテスの『ドン・キホーテ』は、ルネサンスのアナロジー的なエピステーメが古典主義時代の認識論へと変化する閾に位置したディスクールであった。万が一大澤が仮にドン・キホーテであったとしても、本書に書かれた彼の言葉は、言説の体制が、ある時代──ポストモダン──から、別の時代──その名前を何と言うか、わたしたちはまだ知らない──への変換点にあったということを、将来告げ知らせてくれることだろう。 最後に、大澤が抱いている一番大きなアナロジーを指摘しておこう。それは「オウム」と「9・11」と「3・11」とが重ねあわせ可能な反復事象である、という見解だ。このリストに「60年代闘争の終わり」を数え入れてもよい。「理想の時代(1945-1970)」から始まって、「虚構の時代(1970-1995)」、そして今日の「不可能性の時代(1995以降)」へといたる戦後社会の変化は、どうやらこれら数々の「終わり」によって徴づけられているらしい。だが残念ながら──おそらくは大澤の無意識に反して──そう簡単に、世界は終わりそうにない。もちろん、終わりを巡る言説を氾濫させてきたある種の(ポスト)モダニズム的傾向や、その背面に糊のようにへばりついてきた「終わりなき日常」崇拝のような、本当に終わったほうがよいものもあるだろう。だがとにかく、ある種の知識人にとっての世界が幾度終わろうとも、そんなことは知ったことではない。あらゆる常態に抗して生きる術を発見することこそが、「哲学」の名のもとで指し示されてきた「生き方」ではなかったか。クライシスが「明確な破局」ではなく「数十年単位でしか減退しない濃度」で現われるようになった今日、垂れ流される害悪から逃れ、その毒を薄め悪い影響を繰り延べつつ、生きる道を探すような。
201206
特集 書物のなかの震災と復興
木造仮設住宅から復興住宅へ──はりゅうウッドスタジオほか『木造仮設住宅群──3.11からはじまったある建築の記録』
線の思考──寸断とネットワーク──原武史『震災と鉄道』
混迷のなかで提示された技法としての倒錯──大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ──3・11後の哲学』
私たちの凄まじく具体的な暮らし──鞍田崇、中沢新一ほか『〈民藝〉のレッスン──つたなさの技法』
「今、音楽に何ができるか」という修辞に答える──震災時代の芸術作品
再び立てられた「問い」──露呈した近代─反近代の限界を超えて──日本建築学会編『3・11後の建築・まち──われわれは明日どこに住むか』
日本という〈身体〉の治癒はいかに可能か── 加藤典洋『3.11──死に神に突き飛ばされる』
逃げない「ヒト」を避難するようにするには── 片田敏孝『人が死なない防災』
政治としての建築──隈研吾『対談集 つなぐ建築』
社会がゲシュタルトクライシスにおちいるとき──篠原雅武『全─生活論──転形期の公共空間』
「拡張現実の時代」におけるプロシューマー論の射程──宇野常寛+濱野智史『希望論──2010年代の文化と社会』


