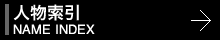ENQUETE
特集:201401 2013-2014年の都市・建築・言葉 アンケート<門林岳史
●A1近頃は毎年のことであるが、2013年も日本各地でさまざまな芸術祭のたぐいが開催されており、私も比較的多くを見てまわった。部分的に参加したものも含めて訪れた順に列挙すると以下となる。「第5回恵比寿映像祭」「堂島リバービエンナーレ2013」「YCAM 10th Anniversary」「あいちトリエンナーレ2013」「おおがきビエンナーレ2013」「十和田奥入瀬芸術祭」「KYOTO EXPERIMENT 2013」「神戸ビエンナーレ2013」「FESTIVAL/TOKYO 13」。すべての芸術祭についてここで適切にコメントすることはできないので、全体を通して印象に残った点として、アートにおける拡張現実性なるものについて書き記しておきたい。
直接的に拡張現実(AR: Augmented Reality)のテクノロジーを利用している作品として、「KYOTO EXPERIMENT 2013」のフリンジ企画「使えるプログラム」に出展していたni_kaによるAR詩劇《キャラクターズ・リブ》と、「FESTIVAL/TOKYO 13」のPort B(高山明)《東京ヘテロトピア》の2作がある。
AR詩劇《キャラクターズ・リブ》は、つい先日サービスを終了したARアプリケーション「セカイカメラ」を利用して、街を歩きながらセカイカメラの画面上に浮かび上がってくる「詩」を鑑賞する、というものである。ni_kaは、2011年2〜3月に開催された「floating view "郊外"からうまれるアート」展(トーキョーワンダーサイト本郷)において、同様の作品を初めて発表しており、今回、京都の出町商店街を舞台に展開した作品はAR詩としては2度目の作品となる。事前に指示されたルートにしたがって商店街付近を歩いていると、セカイカメラの画面上にni_kaが設置した大量の「キティちゃん」のイメージが浮かび上がってくる。それらのキティちゃんのなかにはクリックするとテクストが表示されるものがあり、そのテクストをたどりながら街を歩くことでAR詩を鑑賞できるという作品である。
他方、《東京ヘテロトピア》は、より古いテクノロジーであるラジオを利用した作品である。受付で小型ラジオとガイドマップを手渡され、ガイドマップに従って移動し、指定の場所でラジオの周波数を合わせると、その場所にまつわるテクストの朗読を聞くことができる。東京都内に10カ所あまり散らばっている指定の場所は、記念碑やエスニックレストランなど、それぞれに移民の記憶を携えたトポスであり、鑑賞者はその付近にしばらくたたずんで、ラジオから聞こえてくる移民の声に耳を傾けることになる。ミシェル・フーコーの概念を借用した「ヘテロトピア(異在郷)」というタイトルの通り、都市に偏在している異質な記憶の層を浮かび上がらせる、ある種の観光の提案としては興味深い。ただし、そのからくりがわかってしまうと、一つひとつの朗読を聴く経験はそれほど鮮烈なものではない。
ここにはおそらく、芸術鑑賞の経験における集中と散漫の2つの極が関わっている。ヴァルター・ベンヤミンの有名なテーゼを思い起こすまでもなく、都市を歩く経験は本来的に散漫な経験である。にもかかわらず、ラジオから聞こえてくる朗読は、テクストへのそれなりの集中を要求する。記念碑やエスニックレストランでたたずむ身体は、周りの風景や行き会う人々に気をとられ、この集中への要請に応えることができない。とりわけ、私のように強引に一日で鑑賞を終えようとしている者にとっては、エスニックレストランに立ち寄っても、次の予定を考えるとそこで食事をとるわけにもいかず、なにやら中途半端に一つひとつのミッションをこなしていくことだけに満足感を求め始めてしまう結果となる。それならいっそ、この作品全体の経験がより根底的に散漫なものとして構想されていてもよかったのではないか、という感想を抱いた。
同じことはni_kaのAR詩についても言える。今回京都で展開されていた作品は、少女が父親に宛てた手紙という体裁の12本のテクストを順番に読み進めていくというかたちを取っており、ni_kaが作り出した作品世界に没入し、手紙をすべて拾い集めるというミッションを完了することによってしか、作品の経験に満足感を得ることは許されていない。しかしながら、そうであればこの作品のために拡張現実のテクノロジーを利用する意味はあっただろうか。現実の都市空間と作品世界の境界が曖昧になっていくような経験を与えてこそ、拡張現実のテクノロジーを利用する意義があるはずだが、実際の作品経験は必ずしもそのようなものではない。むしろ、鑑賞者はテクストを探し求めることに必死でセカイカメラの画面に没入し、結果として都市空間はないがしろになってしまった(端的に道を歩いていて危ない)ように思われるのである。
実は、京都でのni_kaの作品を鑑賞したあとになにやらもやもやしたものを感じたので、その後東京に立ち寄ったおりに、上に言及した「floating view」展の際のAR詩の痕跡を体験してきた。結論としては、こちらのほうがはるかに興味深い鑑賞経験であった。まず、京都の作品の場合、ni_kaが設置したものとは関係のない情報をフィルタリングするために、セカイカメラのタグ表示を最近数カ月のものに制限することが求められていた。他方で、東京での作品の場合、2年以上前の作品を追体験することになるので、フィルタリングを無制限にしなければni_kaが設置したタグを追うことはできない。結果として、御茶ノ水駅から会場のトーキョーワンダーサイト本郷まで歩く道程で、セカイカメラの画面には、ni_kaのAR詩に混じって無数の匿名のタグが表示され続けることになる(例えばお茶の水橋上からある方向にセカイカメラを向けると、画面には「肉 肉 肉」というタグが表示される。おそらくその向こうに焼き肉屋があるのだろう)。しかしながら、真に拡張現実的な作品を構想するのであれば、こうした作品外のタグを作品経験にとってのノイズとして排除するのではなく、むしろ、作品に不可欠の構成要素として(パレルゴンとして?)取り込むことこそが望ましいのではないか。
「floating view」展は、その会期中に東日本大震災が起こり、そのことでni_kaの作品も大きく性質を変えることになった。ni_kaは会場付近に設置したAR詩に加えて、会期中に東京各地で被災者を追悼する趣旨のAR詩を展開していったのである。これらのAR詩の記録画像はいまでもni_kaのブログ上で観ることができる。というよりは、ブログ上にはこれらのAR詩が設置されている場所は公開されていないので、東京タワーや六本木ヒルズ展望台のように明らかに場所を特定できるものをのぞいて、これらのAR詩はブログ上でのみ閲覧することが想定されて製作されていると考えてよいだろう。その結果、作品経験はふたたび都市空間から隔離されるのである。
さて、上記2作は明示的に拡張現実のテクノロジーを応用した作品であるが、思い返してみると各芸術祭にはそれ以外にも拡張現実的と呼ぶのがふさわしい作品がいくつかあった。例えば「YCAM 10th Anniversary」で展示されていた瀬田なつきの映像インスタレーション《5 windows》。横浜・黄金町の川辺の風景をスケッチしたオムニバス風の4本の短編と、それらの映像を統合した物語作品の計5本の映画からなる作品である。これまでに横浜、吉祥寺、渋谷などで上映されてきたが、今回のYCAM(山口情報芸術センター)での上映/展示に際しては、山口市内の一の坂川付近が会場に選ばれた。一の坂川に沿って4本の短編をリピート再生するディスプレイが設置され、そこから少し離れたところに位置する山口ふるさと伝承総合センター内の一室で5本目の作品が上映されるという趣向である。その結果得られるのは、横浜の川辺で展開される虚構の物語と、山口の川辺の現実の風景が、映像に媒介されて溶け合うような心地よい経験である。
あるいは「十和田奥入瀬芸術祭」では、芸術祭の一環として『十和田、奥入瀬──水と土地をめぐる旅』(管啓次郎編、青幻舎)という書籍が刊行されていた。芸術祭のカタログに相当する書籍であり、芸術祭出品作に関連するテクストも収録されているが、それだけにはとどまらない。それに加えて短編小説3篇と畠山直哉による撮り下ろしの写真も収録されており、この書籍自体が芸術祭のもうひとつの(ヴァーチュアルな)会場という趣向になっているのである。この書籍のために、小林エリカ、石田千、小野正嗣の3名の作家はそれぞれ、芸術祭の3つの会場である十和田湖、奥入瀬渓流、十和田市街にまつわる物語を書き下ろした。例えば芸術祭を訪れた帰路、記憶も新しいままにこの本のページをめくってみる。そうすると、まだ自分の体に染みついている土地の風景やにおいが、その土地の歴史に根ざして紡がれる虚構の物語と混じりあう不思議な経験をすることになる。その意味ではこの本全体が、書籍という古いメディアを舞台にして現実と虚構、記憶と歴史を折りあわせるある種の拡張現実的な作品である。
そして最後にもうひとつ、「あいちトリエンナーレ2013」で展示されていた宮本住明《福島第一さかえ原発》を挙げておきたい。(あいちトリエンナーレではインヴィジブル・プレイグラウンド《ささいな出来事の美術館》という明示的に拡張現実的な作品も出品されていたのだが、4人一組で参加する作品のため体験することができなかった)。この作品は、トリエンナーレのメイン会場である愛知芸術文化センター全体を、同じくらいの規模の建造物である福島第一原子力発電所の建屋に見立て、会場の床や壁、天井に原子炉の断面線をテープ状のカッティングシートでなぞったものである。テープがかたちづくるなにやらモダニズムめいた抽象的なフォルムは、トリエンナーレ会場を縁どるお洒落な演出のように見え、会場に入ってしばらくの間は、これが作品であるとは気づかない。しばらく会場内を巡ったあとになって、いままで会場内のいたるところで眼にしてきたテープのラインが、実は原子炉をかたどったものであり、自分は拡張現実的な空間において原子炉とそれを取り囲む建屋の内部を移動し続けていたことを知る。それはある種のコペルニクス的転回と言うにふさわしい経験であり、この作品の存在を知った瞬間に、展示会場全体の見え方が変わってしまうのである。
以上、後半では現実の空間と虚構の空間や経験を溶け合わせることを作品経験の核としている3つの作品を概観してきた。そのいずれもが、いわゆる拡張現実のテクノロジーを応用したメディアアートというわけではないが、優れて拡張現実的な経験を作品の内部に折り込んでいる。それに加えて共通しているのは、芸術祭の会場を歩き回るという本質的に散漫な経験が、作品の成立にとって不可欠な構成要素になっている点である。もちろん極論すれば、あらゆる優れた芸術作品は拡張現実的な虚構の経験を与えるものであると言いうるだろう。しかしながら、これらの集中を要求しない作品が与えている散漫な拡張現実的なるものは、各地に芸術祭が乱立する現在のアートシーンになにかふさわしいものなのかもしれない。