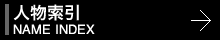ENQUETE
特集:201401 2013-2014年の都市・建築・言葉 アンケート<篠原雅武
●A1今年の夏はとても暑かったが、そのさなか、「エコロジー思考への転回」という文章(『現代思想』10月号に掲載)を書いていた。それでティモシー・モートンの『Ecology without Nature』(Harvard University Press、2007)をあらためて読み返した。この本は、「人間は環境を生きている」ということをめぐってただひたすら考察を進めていくというものだが、重要なのは、モートンが環境を、いわゆる自然環境、人間に対して客体として存在する自然環境ではなく、人間がそこにおいて生きている、「とりまくもの」として捉えようとしている、ということだ。モートンは、「とりまくもの」としての環境を、人工か自然かという図式でとらえるのは適切でないと考えている。現代においては、むしろ人工的な風景が当たり前で、『攻殻機動隊』や『ニューロマンサー』や伊藤計劃の小説や黒沢清の映画といった作品が描き出す、人工化が徹底化された果てに一種の荒廃感をも感じさせるものと化しつつあるというのが実情ではないか。人工化の果てに現われてきた荒みつつある「とりまくもの」をどう考えるかが、現代の課題であると思う。そのためにも、環境といえば自然環境であるという通念を逃れた思考としてエコロジー思考を提示するというモートンの思想の研究は必要だろう。また鈴木了二の『マテリアル・サスペンス』(LIXIL出版、2013)もそうしたことを主題にしているように思われる。
ところでモートンの思想は、object-oriented-ontologyおよび思弁的実在論という思潮の成立と無関係ではない(http://speculations.squarespace.com/storage/Morton_Response%20to%20Peter%20Gratton_v1.pdf)。それは、グレアム・ハーマンやメイヤスーらが中心となって現在進行形で進展している思潮である。その最新の動向については、ハーマンの論考を参照のこと(http://www.speculations-journal.org/storage/Harman_Current%20State%20of%20SR_Speculations_IV.pdf)。これとハーマンのメイヤスー論などを読んでいると、思弁的実在論はそれ自体決して一枚岩ではないこともわかってくるが、なぜこの思潮が現代において重要なのかを考えておく必要はあるだろうし、日本の知的状況に導入をはかるにしても、なんらかの工夫は必要だろう。その点、千葉雅也の『動きすぎてはいけない』(河出書房新社、2013)は、ドゥルーズ論ではありながら、モートンやメイヤスーの思想を射程に入れつつドゥルーズを読むというスタイルで書かれている。思弁的実在論を日本の知的コンテクストにおいてどう導入するかを考えることはこれからの思想研究の課題のひとつになるだろうが、おそらく、建築・都市を考えるうえでも、こうした思潮は大きな示唆を与えるだろうと思われる。それらは、いわゆるポスト・モダン以後の思想であるからだ。千葉さんが『現代思想』で行なっていた連載は、ハーマンとメイヤスーをもっと直接に論じているので、これがどのような形で単行本化されるかが楽しみである。
高嶺格の「ジャパンシンドローム」(関西編、山口編、水戸編)を京都芸術センターで観ることができたが、これも印象的だった。この作品は、2011年3月11日以後の日本社会の雰囲気を捉えたものとなっている。いずれの作品も、演劇仕立てのビデオ作品なのだが、そこで演じられるのが、たとえば喫茶店で店員に、「この食品はどこ産ですか? 放射能対策は大丈夫ですか?」と質問してみたときの実際の反応を再現する、というものだ。あるいは、関西のとある魚市場で、「この鯨、どこを回遊してきたかとか、わかりますか?」と質問したときの反応を再現するとか、和歌山の海辺で魚釣りをしている人に、「海の汚染とか、気になりませんか?」と質問したときの反応を再現するとか、そういうことである。私たちにとって、この問題は、けっこうデリケートだろう。食品に気をつけていることを誰かに対して話すにしても、共感を得られるとはかぎらない。そんなこと、もう大丈夫だろうとか、本気で信じている人も多いと思う。高嶺氏の作品は、そういうことの通じなさを、アートとして捉えようとしている。とくに水戸編に顕著だが、なんとなく放射能のことは気になるが、それでも、日々の暮らしのなかで、それを気にしないでやり過ごそうとしている人の逡巡を、丁寧に再現しようとしている。
宇野重規の『民主主義のつくり方』(筑摩書房、2013年)は、C・S・パース、ウィリアム・ジェームズらのプラグマティズムの現代的意義を問い直そうとする本であるが、藤田省三の「経験論」を再考しようとしていることには、共感を覚えた。というのも、私もここ数年、藤田の論文を熟読していたからで、特に「新品文化」はいろいろとヒントにしてきた。また、『民主主義のつくり方』では、個でもなく共同性でもない紐帯をどう構想するかが重要な課題と述べられているが、それとよく似たことを、塚本由晴さんが私との対談で、「コモナリティ(commonality)」という概念の重要性を説きつつ述べている(「10+1 website」2013年10月号、「空間と個と全体──政治的意図を凌駕する公共空間は可能か──コモナリティのほうへ」(https://www.10plus1.jp/monthly/2013/10/post-85.php))。なお、宇野さんには大阪で公開セミナーをしていただいたが、そこではジェイン・ジェイコブスの重要性を指摘されていた。政治思想と建築というように分野の異なるお二人が関心を共有しているようだが、そのあたりに、現代の重要な思想的・実践的課題があるのではないかと思う。
また、塚本さんとの対談の準備のため、あらためて建築と思想との交錯ということを考えてみたのだが、やはり、多木浩二の業績は重要だと思った。そのとき役に立ったのが『建築と日常』の別冊『多木浩二と建築』であった。これを機に多木浩二再評価が進むことを期待したい。
The Third Gallary Aya(大阪市西区)では、牛腸茂雄の写真展が開催されていたが、これも印象的だった。名前は知っていたが、じっくりと写真をみたことはなかった。配布されていた堀江敏幸の文章もよかった。
あとひとつ、2013年に心に残ったのは、アートエリアB1で12月18日に行なった、岸井大輔とのトークイベント(「『戯曲「東京の条件」』発行記念 劇作家・岸井大輔と考える「都市の公共性」」であった。岸井さんは「東京の条件」というプロジェクト(http://tokyocondition.com)にかかわって、その成果を今年戯曲として発表した。じつは、私はこのイベントに誘われるまで、岸井さんのことを知らなかったのだが、この戯曲を読み、考えているうちに、かなり私と関心の重なることがあるように思った。トークイベントでは、そもそもこの戯曲は何を狙いとしているのかなどと核心にふれる疑問を提起したのだが、岸井さんは一つひとつ丁寧に答えてくれた。劇作家として、都市のなかに人の集まれるおもしろい場(それこそが公共空間であると私は思う)をつくりだそうという試みの紆余曲折をいろいろと伺ったが、彼のやっていることは、建築に関係する人にも多くの示唆をあたえてくれると思われる。
ところで、自宅にはテレビがないために、「あまちゃん」はまったく観なかった。テレビがあったとしても多分観なかっただろう。ただ、なんでこういうドラマがこの年に流行ったかということは、考えてみる価値のあるテーマだとは思う。『ミュージック・マガジン』の特集「ベスト・アルバム2013」の「ロック(日本)」部門では「あまちゃん」のサウンドトラックが一位だったが、私個人の意見では、それよりはむしろ三位にランクインした青葉市子のアルバム(『0』)のほうが、文化の未来を考えるうえでインスピレーションを与えてくれるものだと思う。
-
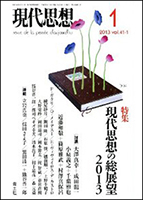
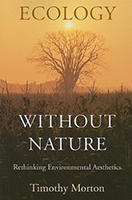




- 『現代思想』2013年10月号/ティモシー・モートン『Ecology without Nature』/鈴木了二『マテリアル・サスペンス』/千葉雅也『動きすぎてはいけない』/宇野重規『民主主義のつくり方』/『多木浩二と建築』
●A2
アトリエ・ワンの広島市現代美術館における展示。塚本由晴さんとの対談が機縁となって、この展示のためのカタログを書くことになった。実際書いてみて思ったのは、アトリエ・ワンは篠原一男から一貫する何かをちゃんと継承しているということであり、また、篠原の対話者であった多木浩二からも何かを継承している、ということだった。その何かが何であるのかをさらに考えてみたいと思ったので、この展示は個人的にも楽しみである。
●A3
2001年9月11日のテロがあったからか、いつしか私は、未来はかならずしも現在の延長上にはなく、唐突に崩壊するということもあると、考えるようになっている。この唐突な崩壊という感覚が、このとき以来ずっと、体のどこかにつきまとうようになって、だから、震災のときも、驚いたといえば驚いたが、9.11のときに呼び覚まされた感覚がまた蘇ったようにも感じた。
2020年に東京でオリンピックが開催されるというのも、確定したこととしては感じられない。つまり、実現されるべき目標として、現在の延長上に確実に行なわれる事業として、実感できない。2020年まで、あと6年。だが、この6年後を、何の破局的事態も起こらぬままに迎えることができると、現在において、確言できるだろうか。ところで磯崎新は、「建築=都市=国家・合体装置」という論考で、日本列島は、25年周期で大変動に見舞われてきたと述べている(『思想』2011年第5号)。1945年、1970年、1995年、というように。そうであるならば、次の区切りは2020年である。ということはつまり、2020年がどのようになっているかは、95年に始まった時代がどのようなものであるかを考えることで想像可能になる、ということだ。2020年にオリンピックが本当に開催されるのだとしたら、そのとき、95年に始まる過程が何であったかがあらわになるかもしれず、そのかぎりでは、興味深い。ただし、本当に開催されるかどうかわからないという、この非現実的な感覚が何であるかを問うことも、必要だろうと思う。さらに、2020年にひとつの過程が終わるとすれば、なにか新しい過程がそこで始まるということでもある。とするなら、私たちは、2020年以後がどのようになるかを想像しなくてはならないだろう。