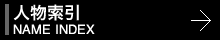ENQUETE
特集:201401 2013-2014年の都市・建築・言葉 アンケート<大山エンリコイサム
表現の空間のために──アブデスメッドからクロックタワーまで
●A1
レーニンの肖像を描いて破壊されたディエゴ・リベラの壁画《十字路の人物(Man at the Crossroads)》(ニューヨーク・ロックフェラーセンター、1933)や、89年に自主撤去を余儀なくされたリチャード・セラの《傾いた弧(Tilted Arc)》(ニューヨーク・フェデラルプラザ、1981)など、美術史上でパブリックアート撤去の先例は散見されるが、2013年はとくに公共彫刻にとっての厄年だったようだ。まずはこれについてざっくばらんに振り返りたい。
サッカー選手・ジダンの有名な頭突きをモチーフにしたアデル・アブデスメッドの《頭突き(Coup de tête)》(ドーハ、10月)、カエルに対する少年の好奇心や恐れを表現したというチャールズ・レイの《蛙を持つ少年(Boy with Frog)》(ヴェネツィア、5月)、サッカーチーム、フラムの本拠地クレイヴン・コテージにサポーターの不満を無視して置かれたマイケル・ジャクソン像(ロンドン、9月)、ルネッサンスの傑作に「下着をはかせてほしい」という苦情で海外からも注目されたミケランジェロのダビデ像レプリカ(島根県奥出雲町、2月)、そして、政府への怒りから市民に引きずり倒されたウラジミール・レーニン像(キエフ、12月)......など、撤去や破壊の憂き目にあった公共彫刻は去年だけでざっとこれだけある。一見それほど共通点がない各事例だが、通して眺めてみると意外に興味深い。
- アデル・アブデスメッドの撤去されるジダン像
引用出典=HUFFINGTONPOST LIVE
たとえば、《Boy with Frog》と奥出雲町のダビデ像は、前者が着色された鉄製の少年、後者が大理石製の屈強な青年と異なるものの、男性の白く古典的な裸体像であるという点で、外見として遠い印象はさほどない。だが、撤去理由はある意味で対称的だ。イタリアの歴史的芸術に囲まれたヴェネツィア住人は裸体像など見慣れているはずだが「(現代アートは)伝統的景観を損なう」ため(観光客には人気があった)《Boy with Frog》の撤去を要求し、そのイタリアが伝統的に誇るルネッサンスの代名詞・ダビデ像は「裸体が不謹慎」と奥出雲町民からクレームを受ける(撤去されたかは不明)★1。
なにが伝統に属し、なにが景観として適切かをめぐる判断は当事者とその慣習に依拠するということだが、その際に当のオブジェクトが与える実際の視覚的印象はさほど問題ではないのかもしれない。なお「裸体に下着を」という発想は、1897(明治30)年の第二回白馬会展に出品された黒田清輝の裸体画《智・感・情》が、当時公開にあたり特別室を設けられ、また下半身を布で覆って展示されたという逸話を想起させる。

- チャールズ・レイ《Boy With Frog》
引用出典=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles-Ray-Boy-with-frog.jpg
★1──島根県奥出雲町のダビデ像については下記を参照のこと。
「Japan town demands pants for Michelangelo's David」(The Straits Times, Asia Report、2013年2月6日)
URL=http://www.stasiareport.com/the-big-story/asia-report/japan/story/japan-town-demands-pants-michelangelos-david-20130206
他方で、ダビデ像と同じ5メートルの背丈となるアブデスメッドのジダン像撤去は当初、ジダン本人の圧力が働いた可能性についてアブデスメッド側が抗議をしていると報じられていた(カタールは2022年のサッカー・ワールド杯のホスト国であるため、国側の政治的配慮があったという指摘もある)。だが本稿執筆にあたり調べ直したところ、現在は「偶像崇拝禁止の教えに背く」という保守派ムスリム教徒たちの反対によって撤去されたという報道に変わっている。
その真偽は置くにしても、たしかにジダンの頭突きは、世界の現状を象徴するモチーフのひとつかもしれない。しばしばスポーツは「ルールを知らないと見方がわからない」ということから現代アートの難解さを説明するメタファとなるが、ワールド杯決勝の大舞台で、その「ルール」を突きやぶって生起してしまったこのスキャンダラスな「逸脱」は、アルジェリア系フランス人のジダンに対する相手選手の差別発言が原因であるという説も示すように、グローバル化する世界において前景化するミクロ/マクロなエスニシティ間の摩擦が、それを制御しようとする国際政治のシステムに抗って噴出する瞬間に準えることもできなくはない。
さらにその決定的瞬間を、同じアルジェリア出身でフランスを拠点にするアブデスメッドが彫刻にし、その作品をアルジェリアと同じイスラム文化圏であるカタールの文化政策事業(Qatar Museum Authority)が購入したという経緯を考えれば、一連の出来事から、複雑化するエスニシティやネーションの問題とそこに並走する今日の文化戦争(スポーツもアートも文化戦争だ)の生々しい姿が透けて見えてくる。
これら重層的なコンテクストをひとつの彫刻に宿したアブデスメッドの手腕は評価すべきだが、完成度の高さも、偶像的な力を危険視された一因ということだろうか。
さて、2011年にオーナーの個人的趣味で設置されたというクレイヴン・コテージのマイケル・ジャクソン像は、同じサッカー関連というよりも、むしろその偶像性でドーハのジダン像に似たところがある。ただし、それはキッチュな偶像だ。パブリックアートではないが、ジェフ・クーンズがかつてマイケルをモチーフにした彫刻作品《マイケル・ジャクソンとバブルス(Michael Jackson and Bubbles)》(1988)を制作したことを思い出そう。消費社会のポップネスとマス・メディアのイメージ再生産によって形成された、時代のアイドル(=偶像)としてのマイケル・ジャクソンである。
だがそのキッチュなアメリカ的偶像は、ロンドンのサッカー・ファンにとって(危険なのではなく)たんに不快なのである。そして不快なものを、彼らにとって神聖な空間であるスタジアムに一方的に設置されれば、怒りを買うのは自然なことである。この心性は、ヴェネツィアや奥出雲町の住人にも重なるが、異なるのは、その過激な熱狂性で知られるブリティッシュ・フーリガンを特徴づけるのは、ときに宗教性を帯びるようなチームへの「信仰心」であり、必ずしも単純に景観や風紀の問題ではないということだ。その意味ではむしろ、規模こそ違うものの、2010年に村上隆がベルサイユ宮殿で展覧会を開催したおり、地元の右翼系団体が抗議のデモをしたケースに近いと言えるかもしれない。

- クレイヴン・コテージのマイケル・ジャクソン像
©Abi Skipp

- ジェフ・クーンズ《Michael Jackson and Bubbles》(1988)
引用出典=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Jackson_et_Bubbles_de_Jeff_Koons_%28Versailles%29_%282973994306%29.jpg
ただ、偶像に対する熱狂がもっとも過激に表出したのは、言うまでもなくキエフでのレーニン像倒壊だろう。もちろん、それは「怒り」の感情が生む熱狂だ。ウクライナがソ連の構成共和国だった1946年に建立されたこの像は、91年の独立時にもその撤去を免れ、清算し切れない過去の遺物であるかのように残存しつづけた。その倒壊はまさに歴史的なインパクトをもっており、ほかの事例とは一線を画す。
一方で印象に残ったのは、この事件については多くのメディア報道が映像をともなっていたことだ。それは本件が、公共彫刻という「静物(の撤去)」についてではなく(それならば静止画で間に合う)、その倒壊、つまり「静物」が「倒れる=動く」瞬間に関するものであるからだと考えたい。ジダン像と比較するならば、アブデスメッドは時間軸のなかに生じた頭突きの一瞬を彫刻へと封じ込め静物化したのに対し、レーニン像は、それが台座から倒れ落ちる数秒をもって映像という時間軸のなかへ放出され、そのイメージは未来派的な運動のつらなりとして残像化していく。ここで公共彫刻は、破壊と同時に映像という別のメディアへと再登録されているのかもしれない。
- 破壊されるキエフのレーニン像
引用出典=「Icon-o-clash: Ukrainian protesters topple statue of Lenin in Kiev」(World News on NBC NEWS.com、2013年12月8日)
この話題についてもうひとつ記しておきたいのは、「撤去」は別の視点からすると「動産化」でもあるということだ。
クレイヴン・コテージから撤去されたマイケル・ジャクソン像はスタジアムの前オーナーに返却され、10月時点の報道によれば、オークションにかけられ売り上げは慈善事業に寄付される予定という。このエピソードは、2013年2月と7月に、ロンドンにあったバンクシーのストリートアートが何者かに壁ごと持ち去られ、その後オークションにて高額で落札されたというニュースを直ちに連想させる。
このバンクシー現象はそれ自体、これからのストリートアートのあり方について示唆に富むものだが、それ以上に、より広いコンテクストにおいてアート全般が直面している市場主義のリスクがそこにあるかもしれない。周知の通り、美術品の動産化は歴史的にもマーケットの論理と密接に結びついている。不動産であるはずのパブリックアートをも飲み込む資本の欲望は、どこに向かおうというのか。
- 持ち去られたあと、オークションに登場したバンクシーのストリートアート
引用出典=Banksy Mural Ripped Off(NowThis News、2013年2月19日)
URL=http://www.nowthisnews.com/news/banksy-mural-ripped-off
●A2
しかしどうやら、資本の欲望に襲われているのは、公共彫刻だけではなさそうだ。つぎに、ストリートアートの話題から広げて触れておきたいのは、ニューヨークで合法グラフィティのメッカとして知られるクイーンズ区ロング・アイランド・シティのファイブ・ポインツ・エアロゾル・アートセンターが、11月19日の早朝、見るも無残に白く塗り潰された件だ。ファイブ・ポインツの取り壊しは以前から噂されていたが、ロング・アイランド・シティでも近年顕著であった地価高騰とジェントリフィケーションの波を受け、建物のオーナーであったジェリー・ウォルコフはいよいよ正式に新しいコンドミニアム(高級分譲マンション)の建設を決めた。ウォルコフ曰く、グラフィティのかいてある壁面をそのまま壊すのは「心が痛む」ので、事前に一度白く塗りつぶしたという。
ここには、公共彫刻の撤去とはまた異なるかたちで、都市空間における芸術のあり方をめぐるクリティカルな状況を見て取ることができる。つまり、ユニークでオルタナティヴな芸術のための自律的な場が、それもとくに貴重なもののうちのいくつかが、2013年に閉鎖に追い込まれたか、あるいは現在その危機に直面しているのだ。
- ファイブ・ポインツ・エアロゾル・アートセンター
筆者撮影
ニューヨークではさらに、歴史的なオルタナティヴ・アートスペースであるクロックタワー・ギャラリーの移転騒動があった。クロックタワーは、ファイブ・ポインツの斜め前にあるMoMA PS1の前身P.S.1 コンテンポラリー・アートセンターの創立者としても著名なアラナ・ハイスによって、1972年にマンハッタン南部トライベッカに開設された世界最初のオルタナティヴ・アートスペースのひとつだが、2013年の11月を最後に、40年以上の歴史を紡いだビルを離れ、ブルックリンのレッドフック地区へ本拠地を移動した。ニューヨーク市の所有物であったビルが、デベロッパーに売却されたためだ。
筆者自身、13年5〜7月に約6週間、クロックタワーのレジデンシープログラムに参加した経験から、この場所が生んださまざまな伝統、人的ネットワーク、そして歴史的手触りとしか言いようのないものを肌身に受け取っていただけに、なにか大きなものの喪失を感じる。やはり「場」に蓄積された膨大な時間は、代替の効かないものだ。ただ、組織としてのクロックタワーは今後も継続され、先述のようにレッドフックの新拠点を中心に新たな展開を目論んでいるとのことなので、いまはその続報を待ちたい。
日本でも、2001年より造形作家の岡崎乾二郎がディレクターを務める四谷アート・ステュディウムの閉校問題が注視されている(本稿執筆時現在)。現場でアクチュアルに活動するアーティストや批評家を多数輩出した本校は、近畿大学国際人文科学研究所というインスティテューショナルな別称にもかかわらず、きわめて個性的で先進的なカリキュラムをもつオルタナティヴな教育施設として、多くの美術関係者がリスペクトしてきた。それを反映するかのように、近畿大学側からの一方的な閉校通知に対し抗議するさまざまなアクションがすでに起こっている(そのひとつが、在学生有志が運営する「四谷アート・ステュディウム存続へ向けて」というウェブサイトだ)。いまだ決着を見ない本件については、引き続き状況を見守っていきたい。
最後に、より個人的な思いからつけ加えたいのは、筆者の学生時代の恩師である東京藝術大学先端芸術表現科教授・木幡和枝氏の退職と、それにともなう木幡研究室の解散である。木幡研究室は、筆者個人にとって重要な成長の場であったのみならず、大学の一研究室でありながら、所属学生に留まらない学内外からの有象無象の表現者・思索者が数多く出入りし、関わり、つねに多くのプロジェクトが活発に行なわれた空間であった。木幡氏が長年にわたり旧P.S.1の客員キュレーターを務め、アラナ・ハイスとともにオルタナタィヴなアートスペースの運動に初期から関わってきたことを踏まえれば、その研究室のアクティヴィティの多産ぶりは驚くに値しないだろう。クロックタワー同様に、大学制度としての研究室がなくなったとしても、そこから生まれたダイナミズムが今後も持続的に発展することを期待している。
ここに挙げたいくつかの「危機」の舞台は、どれも背景や文脈が異なる、それぞれ固有で多様な「場-たち」である。それらを閉鎖や撤退に追いやるのは、しかし、売り上げ重視の大学や、営利目的でデベロッパーと結託するビルオーナーやシティ・ガバメントなど、一元的な経済合理主義と言える。ネグリ+ハートの有名な図式を借りるならば、その関係を「マルチチュード」と「〈帝国〉」と呼んでもよいかもしれない。ふと、以前どこかで聞いた岡崎乾二郎の言葉が頭をよぎる──「絵をかくことには、社会的な力がない。だからこそ、それは抵抗の拠点にもなる」★2。表現者の存在論というものがあるのだとすれば、それはなによりもまず、そのための自律的な時空をみずから生成・確保するということにほかならない。
★2──「絵画TV」(出演=岡崎乾二郎、粟田大輔、田中功起、保坂健次朗、2013年1月27日)における発言。