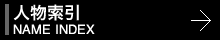ENQUETE
特集:201401 2013-2014年の都市・建築・言葉 アンケート<太下義之
●A1
2013年で印象に残ったものに関しては、「文学」「演劇」「映画」「漫画」「美術」「音楽」「その他」の七つの分野に分けて回答したい。
[1]文学
東日本大震災以降、柳田国男『遠野物語』があらためて脚光を浴びているようである。『遠野物語』は、赤坂憲雄『3.11から考える「この国のかたち」──東北学を再建する』においても引用されているし、畑中章宏『柳田国男と今和次郎──災害に向き合う民俗学』においては主要なテーマとしてとりあげられている。ちなみに、『遠野物語』が発表されたのは明治43(1910)年6月のことであったので、それから100年と9カ月後に東日本大震災が発生したことになる。
そして昨年(2013年)、小説家の京極夏彦が『遠野物語remix』を発表した。同書は京極の新作小説というわけではなく、オリジナルの『遠野物語』に収録されていた119話のエピソードの順序を並び替えて、新しい『遠野物語』をつくりあげたものである。そして、同書を読むと、「改変」および「語り」という二つの創作手法の重要性にあらためて気づかされる。
上述した通り、『遠野物語remix』は物語の順序を並び替えただけで、テキスト自体にはほとんど手を入れていないのだが、本書全体としてはオリジナルとは異なる魅力を有しているように感じられる。ポピュラー音楽の世界でいえば、プロデューサーが収録曲の順番を入れ替えることで、あるCDがまったく別の作品に再創造されることに相通じるものがある。
そして、この京極による「改変」は、オリジナルとされる柳田国男『遠野物語』自体も、もしかしたらこうした「改変」の産物なのではないか、と読者に気付かせる効果も有している。
たとえば、やはり『遠野物語』をオリジナルとする、井上ひさし『新釈遠野物語』(1976)を読んでみよう。こちらは全篇にわたって、いかにも井上ひさし(または東北)らしい艶笑談で構成されているのだが、オリジナルの『遠野物語』にはじつは艶笑談がほとんど収録されていないことに、ふと気づかされる。
柳田国男は当時の農水省の高級官僚であったので(この事実はあまり知られていないようであるが)、独特のセンサーシップをはたらかせ、あえて艶笑談を削除したのではいなか、などと邪推してみたくなってしまう。そして、井上ひさしは、そのように中央政府的な感性で「改変」された『遠野物語』に対するアンチテーゼの意味を込めて、本来の遠野の物語としてこの『新釈遠野物語』を執筆したのではないだろうか。
さて、もうひとつの重要なポイントは「語り」である。「語り」の魅力の素晴らしさ故に、『遠野物語』は100年たっても色褪せることがない。そして、「語り」と言えば、ノーベル文学賞に一番近い作家・村上春樹の新作『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013)も「語り」の魅力に支えられた物語であった。思い返してみると、村上春樹の作品には印象的な「語り」の場面が多々あり、同じ作家の『ねじまき鳥クロニクル』に登場する間宮徳太郎中尉の「語り」も素晴らしかったし、『ノルウェイの森』にも同書の魅力の根幹をなすかのような「語り」の場面があった。さらにいえば、村上春樹をかつてリスペクトしていた小説家・古川日出男の『聖家族』(2008)も「語り」の文学であり、かつ今から振り返ると、3.11を予感させるかのような物語であった。
そして、「語り」は「騙り」でもある。もしも「騙り」の文学を堪能したいのであれば、宗教学者として世界的に有名なミルチャ・エリアーデの小説『ムントゥリャサ通りで』(1968)が一番のおすすめである。
なお、「文学」に関連するテーマとして、2013年は電子書籍の普及がより加速した年でもあった。電子書籍(e-book)に関しては、JapanTimesの記事に私のコメントが掲載されているので、興味のある方はご参照いただきたい。
「Japan's readers slower to make e-book leap」(JapanTimes、2013年11月18日)
URL=http://www.japantimes.co.jp/news/2013/11/18/reference/japans-readers-slower-to-make-e-book-leap/


- 『遠野物語remix』/『新釈遠野物語』
[2]演劇
演劇分野に関しては、2013年に上演された舞台をそれなりの本数見ているので、個人的なベスト5(と番外)をあげさせていただきたい。
マームとジプシー『cocoon』(東京芸術劇場シアターイースト)
漫画家・今日マチ子による、沖縄のひめゆり学徒隊をモチーフとした戦争漫画を原作とした作品。特定のセリフを執拗に反復し、さらにそれらをコラージュしていくという手法はこの劇団の最大の特徴であるが、本作に関してはその手法がたんに表現上の前衛的な手法ということではなく、たとえば前半部分における女子高生たちの会話を通じて立ち上がる、戦時下の女子高生たちの日常生活に象徴されるように、まさにこの舞台のために開発された手法であるかのように、物語にピタリとはまっていたように思う。また、昨今の流行となっている映像と舞台のミクスチャーについても、物語とリンクした極めてインパクトのある映像の投影によって、意味のある形で見事にシンクロしていたと思う。そしてなによりも戦争を題材としながらも"敵"を一人も登場させずに、ただひたすらに死んでいくクラスメイトたちの姿を描くことで、戦争の理不尽さと無意味さを描いている点が素晴らしかった。このような新しい感性に、2020年・東京オリンピックの開幕式の演出を委ねてみたい。そんなことを思わせる舞台であった。
テアトル・ド・コンプリシテ『春琴 Shun-kin』(世田谷パブリックシアター)
2008年に初演された舞台で、今回が四演とのことである。そして、初演時と今回では、役者もスタッフも演出もほとんど変化がないとのことであるが、今回の舞台のほうが初演(これも素晴らしい舞台であった)よりも、作品としてさらに進化してよくなっているように感じられた。たとえば、演出家サイモン・マクバーニーお得意の、シンプルな道具を利用した瞬間的な舞台転換であるとか、主演女優と人形とのエロティックな絡みであるとか、物語の朗読の場面と(物語上の)現実の浮気話との交錯であるとか、初演時にも観ていたはずの仕掛けであるが、今回の舞台はあらためて初見のように感動的であった(もっとも、具体的に何がどう違うのかはうまく説明できないのであるが)。こういう不思議な邂逅がたまにあるから、芝居通いが止められない、そんな作品。
勅使川原三郎『春、一夜にして』(シアターⅩ(カイ))
ポーランドのユダヤ人作家・ブルーノ・シュルツのテキスト「春」をモチーフとした作品。勅使川原三郎とシュルツの組み合わせとなると、これは見逃すわけにはいかない。そして本作は、①シュルツのテキストのナレーション入り、②音楽はなし、③照明による演出効果もなし、④とてもスローな振り付け、⑤群舞もなし、と通常の勅使川原三郎の作品とはまったく異なる作品に仕上げられていた。勅使川原三郎の作品というと、スピード感がある独特の振り付けを期待してしまうが、むしろ本作のように音楽がないなかで異形の踊りを鑑賞するほうが、勅使川原三郎に独特の動きをじっくりと理解することができる。ラストで顔に巻きつけていたテープのようなものをはぎ取っていくという演劇的な演出がとても印象的な作品であった。
クロード・レジ『室内』(静岡県舞台芸術センター)
演出のクロード・レジは御年90歳を超えるフランス演劇界の巨匠。もっとも、来日したご本人の外見はとても若々しく、せいぜい60歳代にしか見えない。そして、本作を見て、いまから30年以上も前、1982年に開催された 第1回世界演劇祭「利賀フェスティバル」のことを思い出した。この演劇祭(特に寺山修司が参加した第1回)は日本と世界から当時の演劇の最前衛が終結した素晴らしいフェスティバルであったが、このなかに、ロバート・ウィルソンの『つんぼの視線』と太田省吾の『小町風伝』があった。そして、『室内』も、そして『つんぼの視線』と『小町風伝』にもみな共通しているのは、超スローな動きが続いていき、そしてある瞬間で突然に動作が早まるという転換が出現する点である。また、本作において、違和感をそのまま観客に投げつけるかのような演者の独特なセリフ術は、かつての転位21を想起させた。とても静謐で緊張感あふれる、素晴らしい舞台。
リミニ・プロトコル『100%トーキョー』(東京芸術劇場)
フェスティバル/トーキョーの常連、リミニ・プロトコルの日本での第四弾。日本初紹介の『ムネモ・パーク』では鉄道模型を舞台とし、続く『資本論』ではあの有名な書籍をテーマに、さらに『Cargo Tokyo-Yokohama』においては東京から横浜に移動する特製トラックでの上演という、常に意外性を追求してきたプロジェクトの新作。本作では、東京23区に住む約900万人の属性(性別、年齢、住所、外国人)の比率を元に抽出された100人の出演者が、次々と繰り出される質問にYesかNoで回答していくという構成となっている。そして、こうした展開が繰り返されていく過程で、われわれ観客はいつしかこの舞台上の100人がわれわれの代表サンプルであるかのように錯覚していくことになる。そして、穏当な質問のなかに、たとえば「憲法九条」「天皇制」「家族を守るために人を殺すことができるか」といった極めてセンシティブな質問が紛れて出されるのである。そして、それらの質問に対する回答のなかには、意外な回答のバランスもあり、そうした回答状況に反応(反発)することによって、観客は自分自身の思想や信条の偏りを再確認することになるのである。一種の社会実験としてじつに興味深い舞台であった。
番外:寺山修司
昨年(2013年)は、寺山修司没後30年という節目の年でもあった。そして、なかでも印象的な舞台であったのが、維新派の松本雄吉が演出した『レミング』(パルコ劇場)と、天井桟敷の遺児・J・A・シーザーが演出した『邪宗門』(座・高円寺)の2件であった。
『レミング』は、一言でいえば維新派の新作のような舞台であり、ヂャンヂャンオペラ風の台詞の繰り返しにより、寺山修司のテキストが(天井桟敷の舞台よりも)リリカルに響いていたことが新鮮な発見であった。もっとも、この『レミング』を寺山演劇を継承する作品として受容できた観客は少なかったのではないだろうか。
もう一方の『邪宗門』は、マッチの炎が燃えている間の一気呵成のセリフ術や、痙攣のように飛び跳ねる演技、シーザー自身による秘教的なロックなど、上述した『レミング』とは対照的に、かつての天井桟敷の演出が伝統芸能のように継承されている点が印象的な舞台であった。
どちらの作品とも見応えがある舞台であったが、見終わっての感想は何かしら不完全燃焼のような気分が残ったことも確かである。そもそも寺山修司の作品とは、そのアウトプット自体に価値があるのではなく、それを体験した観客がまるで疫病にでも感染してしまうかのように、その後の行動や思想を変質させてしまうという、そのような派生的な構造にこそ本質があるのではなかったか。そんなことを考えた寺山没後30年の舞台であった。
-





- マームとジプシー『cocoon』/テアトル・ド・コンプリシテ『春琴 Shun-kin』/勅使川原三郎『春、一夜にして』/『レミング』/『邪宗門』
[3]映画
2013年は映画館で多くの映画を鑑賞したのだが、そのほとんどが旧作であったので、じつは新作はあまり鑑賞していない。そんな数少ないなかではあるが、海外出張のフライト中に鑑賞した怪獣映画『パシフィック・リム』はとても面白かった。本作はメキシコ出身のギレルモ・デル・トロ監督によるものであるが、このデル・トロは、スペイン・カタルーニャ地方を舞台としたダーク・ファンタジーの名作『パンズ・ラビリンス』の監督である。そして、怪獣と怪獣映画を愛するデル・トロ監督は、『パシフィック・リム』において、英語のmonsterではなく、kaiju(怪獣)という日本語をそのまま使用している。さらに、デル・トロ監督は、怪獣を巡る三つの謎に対して自分なりの答えを本作のなかで用意している。その「三つの謎」とは、「怪獣が生物であるとすると、なぜ個体でしか登場とないのか?(同じ形態の生物が多数登場しても良いのではないか?)」「(宇宙または地中から登場するものを除いて)なぜ多くの怪獣は海から出現するのか?」、そして「なぜ怪獣は都市と人間を襲うのか?」である。その謎解きの合理性(および好き嫌い)はともかく、怪獣の骨や臓器の売買でしこたま儲けている怪しいブローカーとその拠点が存在する怪獣の骨で構成された街や、怪獣オタクの研究者が怪獣の脳とシンクロする様子など、怪獣を愛してやまないデル・トロ監督ならではのストーリー展開とキャラクター設定が楽しめる一作である。
なお、その他の映画としては、東京フィルメックスで上映された『ハーモニーレッスン』が素晴らしかった。なお、本作は日本国内ではあまり上映される機会のないカザフスタンの映画であった。
- Pacific Rim - HD Trailer - Official Warner Bros. UK
[4]漫画
本とコミックの情報誌『ダ・ヴィンチ』の2013年「コミックランキング部門」にて№1に見事輝いたのが、諌山創の『進撃の巨人』である。本作については、ヤフー・ニュースにコメントしているので、そちらをご参照いただきたい。
「大人気の『進撃の巨人』 その魅力とは?」(THE PAGE、2013年8月12日)
URL=http://thepage.jp/detail/20130812-00010002-wordleaf
なお、都市と漫画の関係について付言すると、新潟市において「マンガ・アニメを活用したまちづくり構想 検討委員会」(私が委員長を務めました)での提言に基づいて、「新潟市マンガ・アニメ情報館」が2013年5月に開館しており、その入館者数が年間目標(7万人)を超える勢いとなっている。
[5]美術
美術(展覧会)分野に関しても、2013年に開催された展覧会のうち、個人的なベスト5(と番外)をあげさせていただきたい。
瀬戸内国際芸術祭2013
「瀬戸内国際芸術祭2013」においてもっとも主要なサイトのひとつである直島は、《ベネッセハウス・ミュージアム棟》(1992)に始まり、《ベネッセハウス・オーバル》(1995)、《家プロジェクト・南寺》(1999)、《地中美術館》(2004)、《ベネッセハウス・パーク》(2006)、《ベネッセハウス・ピーチ》(2006)、《李禹煥美術館》(2010)、そして極め付きに安藤忠雄自身のミュージアム《ANDO MUSEUM》(2013)と、安藤建築の聖地として進化し続けている姿がじつに印象的であった。
また、アーティスト・内藤礼と建築家・西沢立衛による《豊島美術館》は、前回「瀬戸内国際芸術祭」の閉幕間際に開館したため、タイミングが合わず見逃していたものを今回ようやく初体験できた。美術館と一体となった作品「母型」は、まるで卵の内部のように乳白色に包まれた空間の中で、床の小さな孔から水が湧き出ており、それが緩やかな傾斜に沿って徐々に合流していくという、ただそれだけのアートであるが、これらの動きを見つめていると、これらが生命の営みそのもののように感じられてくる。アーティスト・内藤礼は本物の天才だと実感。この作品と空間を体験するというそのためだけでも、瀬戸内海の豊島に行く価値がある。
十和田奥入瀬芸術祭
この芸術祭で特筆すべきは、《水産保養所》という作品である。廃墟となっていた元宿泊施設「湯治の宿おいらせ」を、梅田哲也、志賀理江子、コンタクトゴンゾという3組のアーティストが、廃墟そのものをひとつの作品として生まれ変わらせた。
ある場所や空間が、そこにアーティストやクリエーターが参加して手を加えることにより、元々とはまったく別の意味を持ちうるのだということをこの「作品」は立証したのだと思う。
「極限芸術──死刑囚の表現」(鞆の浦ミュージアム)
『崖の上のポニョ』(2008)で、宮崎駿監督が構想を練った地として有名な鞆の浦に立地する、アール・ブリュット(障がい者や専門的な美術教育を受けていない人による表現)を紹介するミュージアムで、築150年の蔵をコンバージョンした施設。
この鞆の浦ミュージアムで開催されていたのは、死刑囚たちの作品。たとえば、和歌山毒物カレー事件で死刑が確定した林眞須美死刑囚の作品「国家と殺人」や「四面楚歌」は単純な抽象画であるが、作者の置かれている状況を勘案すると大へん意味深長である。また、埼玉愛犬家連続殺人事件の風間博子死刑囚の作品《無実という希望 潔白の罪》を見ると、この人は本当のところ無実なのではないかと思わせる迫力がある。さらに、大牟田一家4人殺害事件の北村孝紘死刑囚の《自画生首図》は自分が死刑執行される場面を描いているが、ひたすらリアルで不気味である。その他、音音(ねおん、筆名)の《左眼の愁い》は、美術館に展示されているシュールレアリズムの作品と比較しても遜色がない出来栄えである。この大胆な企画に賛辞を送りたい。
ソフィ・カル「最後のとき/最初のとき」(原美術館)
イスタンブールの失明した人々を取材した写真(とテキスト)《最後に見たもの》(2010)と、初めて海を見る人々の表情をとらえた映像作品《海を見る》(2011)の2部構成による展覧会。
このうち《最後に見たもの》は、タイトル通り、失明した人々が最後に見たものや眼が見えていた頃の記憶について語る言葉を、彼らの写真とともに展示するという作品。特に印象的なものは、マフィアの一員に両目を銃で撃たれたタクシー運転手の語る《盲目の人とリボルバー》や、医療ミスによって視力を失ってしまった《盲目の人とマイクロバス》、そして自分の夫がいつまでも(最後に見た)39歳のままのイメージとして残るという《盲目の人と夫》などの作品である。2014年は、記憶とその表現としてのアートについて考えてみるつもりであるが、私にとってその契機となった展覧会。
「つくることが生きること」東日本大震災復興支援プロジェクト展(3331)
2012年に開催された同名の展覧会は、「アートでもとにかく何かをやらないと」という意気込みとそれゆえの表現としての未完成さが同居していたが、震災から2年が経ち、アートによる復興プロジェクトも全体として成熟さと落ち着きを見せ始めているように感じた。
畠山直哉《気仙川》および《陸前高田》にて、写真家によって切り取られた被災地の風景にはもはや震災の生々しさや悲惨さが直接投影されているわけではないのだが、なにか特別な聖痕(スティグマ)の付けられた土地ように感じられ、観客は目を逸らすことができない。
その他、震災のガレキを使って子どもたちとオブジェをつくるという《ワタノハスマイル》や、漁船に企業のロゴを貼り付けるスポンサーシップによって漁業の復興を目指そうという《ADBOAT PROJECT》などが印象的であった。
番外:欧州文化首都。コシツェ(スロバキア)とマルセイユ(フランス)
2013年は、「欧州文化首都」という文化イベントを開催していた、コシツェ(スロバキア)、マルセイユ(フランス)の2都市を自主研究のために訪問した。この「欧州文化首都(European Capital of Culture)」とは、EU加盟国の2都市が協力しつつ(当初は1都市)、一年間を通じてさまざまな芸術文化に関する行事を開催する、という制度である。詳しくは、以下の小文をご参照いただきたい。
太下義之「『東アジア文化都市』と『欧州文化首都』」(2013)
URL=http://www.murc.jp/thinktank/rc/column/search_now/sn130528
「欧州文化首都」は単なる文化イベントではなく、「都市が変化するための触媒」「都市の長期的文化発展戦略」などとも言われている。たとえば、マルセイユの場合、2013年の欧州文化首都に合わせて建設あるいは改修した文化施設は60以上もあり、その投資総額は6億8,100万ユーロにものぼっている。なかでも、フランスの建築家ルディ・リッチオッティ(Rudy Ricciotti)の設計による《欧州地中海文明博物館(MuCEM: Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée)》や隈研吾の設計による《PACA地域圏現代美術基金センター(FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur》は、その代表事例であろう。2014年は前半のうちに、この欧州文化首都についてのレポートをまとめたいと考えている。
-




- 瀬戸内国際芸術祭2013/十和田奥入瀬芸術祭/極限芸術──死刑囚の表現/つくることが生きること
[6]音楽
2013年は、3月には初音ミクの人気曲「千本桜」がミュージカル化、4月には美術展「LOVE展」でミクが展示され、8月にはライブフェス「サマーソニック」にも出演。11月にはミクが主演するオペラ『THE END』が仏パリで遠征公演されるなど、「初音ミク」のメディアミックスが加速した1年だったといえる。
この「初音ミク」については、ヤフー・ニュースにコメントしているので、関心のある方はご参照いただきたい。
「初音ミクの人気の理由と未来」(THE PAGE、2014年1月5日)
URL=http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140105-00000005-wordleaf-cul
[7]その他
その他、2013年で印象に残ったものとして、文化芸術の分野ではないが、異次元的なクリエイティビティという点で、Googleをあげておきたい。Googleの活動は近年さまざまな分野にわたってきているが、そのなかでも特に自動運転車のプロジェクトは、もしかしたら都市や建築というものを根源から再構築する起爆剤となるのかもしれないと考えている。もしも、このようなテーマに関心があるのであれば、私がGoogleについて書いた長めのエッセイをぜひご参照いただきたい。
太下義之「Googleのゴールは何か?──"異次元イノベーション"に関する考察」(『季刊 政策・経営研究』vol.3、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2013)
URL=http://www.murc.jp/thinktank/rc/quarterly/quarterly_detail/201303_01
●A2
2014年で関心のあるアート関連のプロジェクトについては、二つのアート・イベントとひとつの法律の計3点をあげたい。ちなみに「二つのイベント」とは、「ヨコハマトリエンナーレ2014」と「札幌国際芸術祭2014」のことであり、また、「ひとつの法律」とは、「デジタルアーカイブ振興法」(仮称)のことである。
これらの点についても、ヤフー・ニュースの取材にコメントしているので、関心のある方はご参照いただきたい。
「2014年は『東アジア文化』元年? デジタルアーカイブ推進の法整備も」(THE PAGE、2014年1月4日)
URL=http://thepage.jp/detail/20140104-00000003-wordleaf
●A3
2020年の東京オリンピックに関して、じつのところ私は、結果としてリオ・デ・ジャネイロの開催に決定した2016年のオリンピックの招致の時点(概ね2007年ころ)から今回の2020年の招致まで、文化プログラムの面で関わっていた。そこで、このオリンピックに関しては、自分の専門分野である文化政策の視点から、日本ではまだほとんど語られていない三つの点を指摘しておきたい。
第一は、オリンピックはたんにスポーツの祭典だけではなく、文化の祭典でもあるという点である。じつは、オリンピックの提唱者であるクーベルタン男爵の理念(オリンピズム)にのっとって、文化とスポーツ、その両方がオリンピックにおいては非常に大事であるとされている。そこで、国際オリンピック委員会はオリンピックの開催にあたって、オリンピック精神の普及を目指す観点から、スポーツ競技と同時に文化や芸術を通じた国際交流「文化プログラム」を重要なテーマとして開催国に義務付けているのである。
第二点目は、2020年のオリンピックは東京の話だと思っている方が多いかもしれないが、オリンピックの文化プログラムは東京だけではなく、全国で開催されるという点である。実際に2012年に開催されたロンドン・オリンピックでは、全英を12のブロックに分けて、各ブロックのイニシアチブで、イギリス全土でオリンピックムーブメントを盛り上げる文化プログラムが行われた。しかもそれは基本的には公募で、アーティストが主導するアイデアを実現するという「Artist taking the Lead」という、アーティストに主導権を委ねるのだというコンセプトで行なわれた非常に大規模な文化プログラムであった。
もちろん、東京オリンピックはロンドンのまねをする必要はないのであるが、2020年の東京オリンピックの開催にあたっては、東京だけでなく全国で文化的なプログラムが行なわれるということが期待される。
それから三点目が、「そうは言っても,2020年はいまから7年後でずいぶん先の話ですね」というふうに思われるかもしれないが、オリンピックの文化プログラムは2020年だけではなく、2016年から開始されるという点である。オリンピックの文化プログラムは、開催に向けて4年間ずっと続けるものであり、具体的に言うと、2016年に開催されるリオ・デ・ジャネイロのオリンピックの閉幕式Hand over Ceremonyが行なわれた瞬間から、2020年に向けての文化プログラムが開始されるのである。別の言い方をすると、いわゆるスポーツの祭典としてのオリンピックは、4年に1回、世界のどこかで開かれるという性質のものであるが、文化プログラムに関しては、つねに世界のどこかで実施されているのである。
いまから2年後の2016年、リオ・デ・ジャネイロ五輪が終わって直ちに文化プログラムを始めるために、準備期間はじつは余りない。すぐにでも動き出す必要がある。その意味では、2014年は、2020年へ向けての文化政策が本格的に検討され始める元年になるであろう。