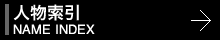ENQUETE
特集:201301 2012-2013年の都市・建築・言葉 アンケート<柴原聡子
夏の家
2012年は、ひとつのプロジェクトにかかりきりで終わった。
東京国立近代美術館の開館60周年記念企画として、建築事務所スタジオ・ムンバイに設計と施工を依頼し、小さなパヴィリオンを美術館の前庭に建てたプロジェクト「夏の家」である。

- 「夏の家」全景
Photo: Masumi Kawamura
スタジオ・ムンバイは、インドのムンバイに拠点を持つ、設計者と大工から成る建築事務所で、2010年のヴェネツィア・ビエンナーレ建築展にて世界の注目を集め、日本では2011年の東京都現代美術館での「建築、アートがつくりだす新しい環境──これからの"感じ"」展、2012年はギャラリー・間で個展を開催し、大勢の観客を集めた。
アジアン・リゾートにありそうな空間をも彷彿とさせる彼らの建築ではあるが、今回のプロジェクトを実施するにあたり、スタジオ・ムンバイに注目した理由は、震災以降の日本において、建築、とりわけ住まいに対する姿勢のひとつとして、彼らの活動が教えてくれるものが多分にあると思ったからだ。
彼らは、設計者と大工が協働して、スケッチを介した設計や、実物大のモックアップづくりを繰り返し、建築をつくっていく。それは、建物をつくることが工業化や機械化された以前の、身体と直結したところにある建築を彷彿とさせる。この、「考えること」と「つくること」の同時進行は、建築が、あらかじめ想定されたものではなく、日々のなかで行ったり来たりを繰り返して、更新され続けていくものであることを伝えてくれる。そのような建築のあり方は、本来、住まうという行為とつながるものだ。スタジオ・ムンバイは建築事務所であり、彼らが設計をした建物に住むわけではないが、しかし、彼らの姿勢は、つくることと住まうことが地続きにあることの重要性を示している。震災という圧倒的な力によって、多くの家がなくなる姿を目の当たりにした私たちに、与えられる器ではなく、自らの手でつくっていくことができるものとしての「家」を、教えてくれるのである。

- スタジオ・ムンバイの職人たち
そのような理由でスタジオ・ムンバイに声を掛け、初めに共有したのが、今和次郎の「震災バラックの回顧」★1である。「考現学」の創始者として知られる今は、1910年代に地方の民家を訪ね歩き、原始的な小屋や、住まい手が止むを得ず処置したさまざまな工夫を発見しては記録した。その調査をした直後、関東大震災が発生、東京は壊滅状態に陥った。今は、焼け野原となった東京で、田舎で見た原始的な小屋に近いバラックが、まるでキノコのようにそこかしこに這い出てくる光景を目の当たりにする。そして、それらバラックを採集して文章とスケッチにまとめた。それが、「震災バラックの回顧」である。採集されたものたちは、せめて寝るところ、雨を避けられる場所が欲しいという思いから、家を失った人々が、焼け残った木々やトタンなどの廃材を使って建てたシェルターや小屋であり、今はそこに人の根源的な住まいづくりの能力を感じたのである。このスケッチと文章からは、人々が自らバラックを建て、そこに住みながら、不便を解消するために都度工夫を凝らしていく様子を伺うことができる。つまり、これらバラックは、いずれも、つくることと住まうことが直結した一番原始的な建築なのである。
この今のスケッチが持つ意味──住まい手によりつくられる家々が示す、生きるための工夫が持つ価値──を、スタジオ・ムンバイの代表ビジョイ・ジェイン氏は即座に理解した。そして、彼らもまた、インド国内で、同じような動機を持って、不法占拠のバラックやありふれた民家を採集していると教えてくれた。彼らがインスピレーションと呼ぶそれらの事例を見ると、建築のつくり手である彼らが、「住まうこと」にどれだけ意識的かということがわかる。そのような、つくることと住まうことが地続きになった状態に価値を見出すことが、彼らの建築づくりの姿勢の根本にあるのではないだろうか。

- スタジオ・ムンバイのインスピレーション。ムンバイ郊外のバラック
このようなコンセプトをもとにつくられた「夏の家」は、小さな三つのパヴィリオンと、彼らがインドでたまたま発見した謎の道具(どうやら、鳥に餌をやるためのものらしい)「バード・ツリー」によって構成されている。スタジオ・ムンバイの魅力のひとつである「つくる」というプロセスを、来場者の方々に身近に感じてもらうため、美術館での施工の様子は一般に公開した。日々、試行錯誤を重ねて、徐々に建物が出来上がり、施工中と竣工後の区切りなく誰でも使用できる場として開放されるという流れそのものも、つくることと住まうこと(このパヴィリオンは住まいではないが、「家」とついたものだ)を地続きにする実践である。

- スタジオ・ムンバイから来日した3人の大工
Photo: Masumi Kawamura

- 「夏の家」バード・ツリー
Photo: Masumi Kawamura
それぞれのパヴィリオンは、彼らの日々のリサーチからインスピレーションを得たもので、民家の軒先であったり、不法占拠者のバラックであったり、あるいは、インドのバス停であったり、といったようなインドの街に溢れるものを連想させる。同時に、どのパヴィリオンも、半屋外空間であり、深い庇や軒を持つ。このような形態は、例えば日本であれば、縁側であったり、玄関先であったり、お寺や公園にあるあずまやであったり、どこか身体的に馴染みのあるものでもある。それは、スタジオ・ムンバイが、インドにありふれているものにインスピレーション・ソースを求めるとき、そこにローカルな特徴を発見しようとしているのではなく、空間をつくるうえでの、普遍的な対処を見出しているからにほかならない。だからこそ、「夏の家」には、雨を流すために窓が傾いてつけられていること、ブランコに乗っていても雨に濡れない大きな庇、ベンチにもなる床の高さなどなど、建物の部分一つひとつがなぜそうあるのか、そして、なぜそのようなかたちになっているのかの理由が、使う人がその空間に馴染み、時間を過ごすことで、自然と見出せるようになっている。それは、つくることと住まうことが切り離されてしまっている現代において、このふたつの行為を緩やかに接続するための、小さなきっかけとなるはずだ。そして、「夏の家」を体験した人が、自らの住まいに戻ったとき、それが与えられた不変のものではなく、自分の手で「つくる」ことのできるものだという意識の芽生えをもたらしてくれるのではないだろうか。

- インドの民家の軒先


- 左=不法占拠のバラック/右=インドによくあるブランコ

- 「夏の家」パヴィリオン・ロング
- Photo: Masumi Kawamura
- Photo: Masumi Kawamura


- 左=「夏の家」パヴィリオン・タワー/右=「夏の家」パヴィリオン・スウィング
- ともにPhoto: Masumi Kawamura
- ともにPhoto: Masumi Kawamura
2013年1月14日までであった「夏の家」は、好評につき、5月26日まで公開されることとなった。また、3月末には、このプロジェクトについての記録集も出版する予定である。プロジェクトの背景となった、さまざまなリサーチから、設計の過程、インドと日本それぞれでの制作、そして、できあがった空間がどのように使われたのかを解説するとともに、「夏の家」を会場に行なわれた関連イベントである、全3回の連続レクチャーの書き起こしも掲載する。特に、レクチャーでは、「家とはなにか?」という普遍的な問いを掲げて、第1回:坂口恭平、中谷礼仁、牧紀男/第2回:後藤治、塚本由晴、藤森照信/第3回:内田祥哉、高橋てい一、戸田穣を迎え、さまざまな角度から議論をした。記録集の詳細は、「夏の家」のブログに3月以降アップする予定である。
★1──今和次郎『民俗と建築──平民工芸論』(磯部甲陽堂、1927)所収。