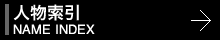ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<沢山遼
震災以降、時折脳裏に浮かぶ一枚の絵がある。萬鉄五郎の《地震の印象》(1924)だ。神奈川県茅ケ崎市在住時の萬が関東大震災の翌年描いたこのキャンバスでは、風景を構成する諸要素が対象相互の「ズレ」によって組み合わされるという方法によって大地の振動が直写的に表象されている。リズミックな筆触と反復的な線模様は、振動する地面の感覚ばかりか、あたり一面に響いたはずの地響きまでをもコミカルに演出するようだ。このとき萬の念頭にあったのは、カンディンスキーをはじめとする構成的絵画であったと思われる。萬は関東大震災が起こる前年の1922年に南画研究のための「鉄人会」を発足し、カンディンスキー的な絵画原理を日本的な風景描写と墨絵の技法へと応用することを試みていた。萬の南画では、画面内の諸要素が断片的に散乱される絵画文法、すなわち「コンポジション」が、南画的な多中心的世界観を成立させる契機として導入されたのだった。《地震の印象》には、南画、あるいはカンディンスキー的絵画文法が、やや戯画化された身体感覚=印象を示すものとして示されている。ゆえに、萬は地震という事象を、いわば「構成」的な運動として見なしていた。絵画が外界を模倣するのではなく、地震が芸術を模倣するという倒錯が、萬に地震を描かせたのである。バラバラに解体された世界の諸断片は、画家によって再び接合-再構成されることが夢見られている。
もとより、このような方法論が美術の歴史においてはじめて意識されたのはおそらく、都市空間を破片と瓦礫の山と化す第一次大戦の経験においてである。ハノーファーのダダイストであったクルト・シュヴィッタースは、爆撃によって破壊された都市の側溝などに吹き溜まった瓦礫や屑から作品素材となるオブジェクトを収集していた。芸術家は、歴史の破局へと向かう無数の破片をつなぎ止める、屑拾いのような存在へと自らの姿を変成していったのかもしれない。
大正期の日本に、カンディンスキーとシュヴィッタース経由の構成主義を持ち込んだのは、ドイツ留学から帰国した村山知義である。西欧の構成主義を「意識的に」超出する自身の方法を村山は「意識的構成主義」と呼び、彼の活動は舞台・演劇活動を行なう前衛芸術集団「MAVO」へと展開された。20年代当時の日本には、MAVO、今和次郎のバラック装飾社、堀口捨巳らの分離派が並びあっていた。萬や岸田劉生らの活動が、これに併走している。
震災以後、村山のMAVOは都内のバラック建築の装飾を請け負ったが、今和次郎のバラック装飾社および考現学の発生もまた、関東大震災を直接的な契機としている。今和次郎らは、震災後数多く建てられたバラック建築をスケッチして歩いた。今はバラック建築を請け負うバラック装飾社を興し、「スケッチ」という手法は、現代風俗のさまざまな事象を採取・記録する「考現学」の主要な方法として採用されることになる。ゆえに、考現学もまた、震災以後の風景を原-光景としていた。分離派の瀧澤眞弓は、今和次郎らのバラック建築について、家屋の表層のみを絵画のキャンバスのように取り繕うその手法が、建築の道義に反する、虚偽のファンタジーを演出するものにほかならないとして批判した。だが、当時、ダダイズムやロシア・アヴァンギャルドさえ参照していた今和次郎は、萬と同じように、震災がもたらす構成的原理に忠実であったということはできないだろうか。バラック装飾は、「バラバラ」であることをその前面性によって誇示し、表層の他からの分離を隠そうとはしない。瀧澤の批判に際し今は、「分離派の人達は、物質神秘を物質構築の仕事に於いて唄おうと言うのだが、私は人生神秘を、物質の表面に於いて唄うことを装飾だと考え、装飾の本系だと考えているのである」(「芸術家の側から分離派の人達へ」)と応答する。今にとって建築の表層に定着する装飾とは、建築使用者の「人生神秘」を記録する。同様に、考現学を「あらゆる行動を分析的に見る」方法と見なしていた今においては、建築もまた物理的な客体ではなく、行為の次元における動態性において理解されている。物ではなく「事」を、建築の存在ではなく、建築の内外で繰り広げられる能動的な行為の主体=エージェントの使用の論理を、彼は「装飾」と呼んだのではないか。
以上はきわめて目の粗いラフ・スケッチに過ぎない。だが、今和次郎の建築観は、不確定的な生の条件と、現在の生々しさにかつてない規模で直面する私たちの「批評」に重要な示唆を与えるものなのではないか、と最近よく考えるようになった。茶碗の欠け方、井の頭公園の自殺場所の分布図、紳士の髭の生やし方に至るまでの生態学的事象をスケッチするその方法は、形を持たず、ゆえに不定形な現在へと向けられている。刻々と移り変わり、けっして客体としての姿を表すことのない現在を捉えること。考現学という名称には、一定の客体的形式に定位し得ない現在=無形(アンフォルム)なものへの眼差しが孕まれている。
日本中にまき散らされた、見ることも、触覚的に感じることも、嗅ぐこともできない、無形の「物質」は、実際には、「物質」であるのだから形があり、場合によっては匂いすら存在するのだという。しかしその「物質」は私たちの貧しい知覚を今後数十年、あるいは数万年単位で批判し続けるだろう。しかし、2011年が、無形なものに眼を開かせたと言いたいのではない。知覚の限界が批評の限界であるなどと言うつもりもない。現在とは、つねに、あるいはすでに、そのようなものとしてあり続けている。その意味で私は、芸術や批評において、2011年に特殊な切断面を見出す殊更な議論自体には懐疑的である。そればかりか、誰もが無関係ではあり得ないこの経験を、芸術・建築・批評の「危機」や「転回」にすり替えることは端的に傲慢であり怠慢ですらあるだろう。私たちの前にはただ、きわめつけの現在が横たわっている。そのことと、2011年を端緒に、市民としての私たちが具体的・現実的に粘り強く「運動」を続けることとはまったく別の話なのである。