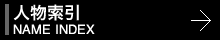ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<土屋誠一
●A1
2011年3月11日、震災の情報は、那覇の自宅で知った。知れば知るほど悪化していく状況を伝える速報に、目を覆いたくなる一方、ニコニコ動画で配信されるリアルタイムの報道を追いつつ、半ば強迫神経症的に、twitterのTLを流れる、有象無象の膨大なつぶやきを、数日間ろくに眠ることもできずに、ほとんど思考停止の状態で見続けていた。被災地、それに福島第1原発から遠く隔たった土地にいて、にもかかわらず強烈に意識させられたのは、普段は意識すらしない「国土」が可視化されてしまったということと、平時ならばむしろ忌避していたはずの「日本」に対する、将来への深い不安だった。このような認識が導いたものは、いくら理念的には左派的な立場を取っているつもりであろうとも、いわば「内なる日本人性」とでも呼ばざるを得ないような意識に、いかに自らが拘束されているのか、ということが顕わになるという、何とも言い難い無力感だった。このような自分語りには意味がないと言われるかもしれないが、いまだ部分像すらはっきりとは見えない3.11以後の状況を語るには、まずはそのような個別的かつ素朴な実感からスタートせざるを得ないように思われる。原発の被害からは相対的に安全(しかし、原発や基地といったリスクの地方への押し付けという点では、フクシマもオキナワも地続きである)な地域に住んでいるものの、しかし、3.11以後、私の生活圏でもしばしば見かけたいわゆる「疎開者」の姿については、那覇という都市の日常のなかに、幾分なりとも非日常的が流入したような風景として、ここに記しておきたい。多くは小さな子供連れで、頼りにできる人のあても少ないのか、所在なさげにしている人たちの姿を、3.11がもたらしてしまったひとつの光景として、きちんと刻んでおきたいと思う。
もう一つ、個人的な記憶としては、美術家の石田尚志と協同した、「石田尚志 in 沖縄」(http://ishidaokinawaproject.ti-da.net/)というプロジェクトに、数人の仲間とともに製作委員会の一員として関わり、原発災害の不安のピークにあった4月初頭、沖縄本島の海岸沿いで、映像作品の制作のための撮影に立ち会ったのも忘れ難い。3.11以後、非日常になってしまった日常のなかで、本来非日常的行為であるはずの芸術が、奇妙に日常のほうへと逆転してしまったような、形容し難い幸福感のなかで行われた作品制作だった。このことを、社会不安からの逃避のために芸術を口実にしているとは思わないでいただきたい。そうではなく、3.11以後、芸術の置かれる位置が、端的に変化してしまったのだ。このプロジェクトの成果は、東京都現代美術館で開かれた「MOTコレクション展:特集展示 石田尚志」(6月11日~10月3日)での出品作品として眼にされた人も多いと思うが、出品された最新の作品には以上のような背景もあったということは、ここに銘記しておきたい。
●A2
2011年の7月から12月まで放映されたアニメ『輪るピングドラム』は、おびただしい隠喩や引用に満ち溢れたスリリングな作品であった一方、都市論としても読める広がりをも持っていた。ここ数年のアニメにおける、現実の風景を参照することで押し進められてきた「聖地巡礼」的な傾向が、参照される地域の風景を拡張し再構成するものであると言える一方、「ピンドラ」は、東京の丸の内線沿線の風景を参照しつつも、1995年の地下鉄サリン事件を力技で召喚するといった点において、「聖地巡礼」とは異なる衝撃を観る者に与えた。そこでは、現代の都市空間を舞台にしながらも、現在時点に過去の歴史の亡霊がふとした隙に召還されるといった事態が描かれていた。非常事態によって日常空間がその脆弱性を顕わにするという点では、「ピンドラ」は明らかに3.11以後の状況を射程に入れた作品であったが、そのメッセージは、「復興」によって過去を忘却するのではなく、現代社会のシステムが生み出してしまう(ヴィリリオ的な)「アクシデント」を常に想起せよ、というものだ。この作品で扱われる「1995年」(地下鉄サリン事件以外にも、あまりにも多くの重大な事件が刻まれた年である)は過去なのではなく、現在に偏在し、未来にも回帰するものである。そのような「アクシデント」を抱えたなかで、いかなる「生存戦略」が構想できるのか、そのことが問われている。機会があれば、都市論的な視点から「ピンドラ」を読むことを考えてみたいと思う。
私自身が関わったプロジェクトだが、美術家の雨宮庸介の呼びかけで開催されたハプニング的催しである「あの、2011年8月28日」(トーキョーワンダーサイト渋谷、2011年8月28日)もまた、3.11以後の状況を反映しての試みだった。青山悟、雨宮、安齊重男、梅田哲也、O JUN、沢山遼、千葉正也、土屋といった面子で行われたこの催しは、会場の開館時間から閉館時間にかけて延々と、通常ならばアトリエで行われる作品制作から、パフォーマンス、批評家によるトークまで、同時多発的かつ並行的に進行し続けるというものであった。呼びかけ人の雨宮は、「震災は従来の価値観をいともたやすくひっくり返し、暗部を明るみに出し、膨大な絶望を投下し、ついでに少しの希望を与える事さえした。語弊はあるが、それ、芸術がやりたかったエフェクトじゃないか? 僕が作品でいつかやりたかったエフェクトじゃないか? 僕は震災以来、どこか震災そのものに嫉妬しつづけている」と、臆面もない震災に対する(ほとんど不謹慎まがいの)リアクションを、この催しのステートメント文の中で語っていたが、アーティストとしては真摯な対応であったと思う。このメッセージは、額面通りに受け取ってはならないだろう。確かに3.11は、銘記すべき特権的な日付である。しかし、このイヴェントの開催日かつ作品タイトルである8.28もまた、その交換不可能な固有性という点において特権的な日付なのであり、そのようなあらゆる日付の固有性とその掛け替えのなさが明らかになったということが、3.11以後の状況なのだ、ということだ。イヴェントの現場に当事者として立ち会った率直な感想で言えば、この試みが優れた作品として成功したとは思わない。けれども、3.11以後、あらゆる日付が常なる危機を抱え込みながら、その固有性を顕わにしたということが、この一日限りの催しにおいて、明確に提示されていたのは間違いない。
「メタボリズムの未来都市」展は、建築の専門家がクリアに取り上げるはずなので、簡単にだけ触れておく。この展覧会で明らかになったのは、丹下健三という建築家が、そのメガロマニアックな想像力において、(その功罪含めて)飛び抜けて優れていたという事実である。「東京計画1960」のような、丹下の提示した都市計画は、国土の脆弱さが顕わになった3.11以後、その耐用年数は確実に切れてしまった。だが、丹下が提示したような未来への「希望」を、今日に至るまでわれわれは提示しえたであろうか。この展覧会が明確にしたものは、好むと好まざるとにかかわらず、常なる参照項としての丹下という存在を無視することはできないということである。
●A3
3.11の影響を被り、まずは延期、最終的には区の財政難を理由に中止に追い込まれた、目黒区美術館の「原爆を観る 1945-1970」展について触れておきたい。重要な展覧会になったはずであることは勿論のこと、展覧会カタログへの寄稿や関連イヴェントへの出演などを予定していた一関係者でもあるので、この展覧会に期待していた少なからぬ人々と同様、私も残念でならない。しかし、開催予定だった昨年の4月の段階で、滞りなく展覧会が開かれていたとして、恐らく展覧会を冷静に鑑賞できる者など、誰一人として存在しなかっただろうし、そもそも展覧会という形式が、多かれ少なかれ祝祭性を持ってしまうことが不可避であることを考慮すれば、原発不安という欠如の埋め合わせとして、消費されるにとどまったと容易に推測される。最終的な中止決定が、区の財政難が原因であったことは、行政の文化に対する軽視という点において批判されるべきであるが、3.11以後の社会状況下であるからこそ開催すべきであるという意見は、明らかに説得力がない。そういった向きには、目黒区からさほど遠くない原爆の図丸木美術館にまずは行ってみて、丸木位里・俊の作品を実見してみることをお薦めする。ともあれ、この展覧会の準備において蓄積された調査研究が失われたわけではないので、どのような形であれ、その蓄積を発表することを、一関係者として諦めているわけではないことは申しておきたい。