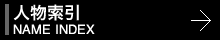ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<松原慈
わたしたちが正しい場所に花はぜったい咲かない
春になっても
わたしたちが正しい場所は
踏みかためられて かたい
内庭みたいに
でも 疑問と愛は
世界を掘りおこす
もぐらのように 鋤のように
そしてささやき声がきこえる
廃墟となった家が かつてたっていた場所に
──イェフダ・アミハイ★1
2011年の世界では、初っ端から騒音がけたたましく鳴り響いていた。
わたしたちは、産声、悲鳴、沈黙を聴いた。
チュニジアで若者が足を踏み鳴らし、その直後、2月11日、東京で静かに雪の降る晩、人々が眠りにつく時間にエジプトで喚声が上がった。アラブの春を整理する間もなく、次に世界に爆発音を轟かせたのは日本だった。5月1日、ロサンゼルスのホテルでテレビをつけると、赤いネクタイを締めたオバマがビン・ラディンの死を告げた。まるで時報のように、機械的に、唐突に。世界でももっとも美しい北欧の夏、わたしたちはノルウェーから恐ろしい銃声を聴き、イギリスで店のウィンドウが次々と割れる音を聴いた。同じ夏、東アフリカを襲った大干ばつで、国境をまたいで難民となった人々の弱々しい叫びを繰り返し聴き、タイの市街を水没させた豪雨の音を聴いた。なににどう因果関係があるのかもわからないスピードで、世界中の都市で音が鳴り止まず、トルコからも、ニューヨークからも、リビアからも鳴動が聴こえた。
こうした音の合間に、日本は常に振動し、街のいたるところで、もっとも不快な不協和音を奏でる地震警報のサイレンが鳴っていた。
わたしには、次第に、騒音と幻聴の区別すらつかなくなっていった。
騒音が聴こえないことは、恐ろしいことである。
3月11日にケニアの首都ナイロビに滞在していたわたしに、日本で起こっていることは大きな音で聴こえてきた。地震が起きてから24時間経たない時点で、市内全土にニュースは触れ渡っていた。
その日わたしはキベラスラムを歩いていた。車、乗り合いバス、バイク、大声、音楽、手押し車、駆け回る子どもたち。ここでは音が止むことがない。すれ違う住民は、目が合うと誰もが"Japanese? I'm very sorry."と十字を切る仕草をし、わたしの手を取った。二日前に大きな火事があり、一角が全焼したという界隈を通ると、真っ黒に焦げた小屋の奥の空き地で、肌の黒い男たちが、真っ黒い粉まみれになり働いていたが、彼らもわたしの顔を見て口々に叫んだ。"I'm sorry. We are praying for you." 男たちは、翌日には再び開店するというキオスクを建設している。
釘を打ち鳴らす音が響く、汗と埃にまみれた工事現場を出ると、通りの向こうから、太鼓と鈴の音が聴こえてきた。音楽を追うと、結婚式に辿り着いた。着飾った女たちが地面に座って手を叩き、老女が太鼓に合わせて踊りながらケタケタ笑っている。体の大きなアンティがわたしを手招きし、女しか立ち入れないという暗い室内に通す。スラムの中でひとり、百合のように美しい若い花嫁が化粧をしている。部屋中に漂う甘い香りが、鼻に残る通りの生ゴミのにおいをしばし忘れさせる。彼女たちは大きな声で歌い、踊り、夜が更ける。
慣れないこのスラムという場所を歩くと、騒音と感じるものと音楽(楽しい音)の差が、すぐに変化することに気がつく。耳を慣らすために、ともに歩くことや話すことや飲み食いすることやただ時間を過ごすことだけが許されていることで、それ以外のことはどうでも良いことに感じられた。

- Kibera, Nairobi, Kenya, Mar 2011
彼らの生活には電気がないが映画館はあり、ヨガ教室はないが太極拳のレッスンは受けられる。映画館の中ではテレビでDVDが上映されるが、停電の場合は暗い中で人々がくつろぐ。教会があり、中古の文房具屋があり、糊のきいた色とりどりのシャツを売る店があり、クリーニング屋もあるが、彼らが気に入りだというバーはときどき屋外にあるのでわかりにくい。花屋は見つけることができなかったが、ヘアサロンなら毎日違う店へ通えるだろう。
見知った言葉の書かれた看板が並ぶ一方で、住む人々が、わたしの知るのと少し違うマナーで生活していることはすぐに理解できる。ここでは白は裕福を意味する。水のない場所での洗濯は一苦労だ。二週間同じ洋服を着続けて新品に取り替える者もいる。ある程度必然をともなったそうした行為も、別の文脈に取り出されればファッションになり、実際スラムのストリートファッションを紹介するメディアもある。市内でもっとも人口密度の高いはずのこの土地は、公式には地図から消されようとしていたが、キベラに住む若者たちが二年前からデジタルマッピングによって地図上に自分たちの生活を刻印し始めた。ここで生きることは厳しく、一度飛び出したら、彼らはこの生活に二度と戻ってこないかもしれないが、巡り巡って海を越えやって来てこの地を歩くのはわたしだけではない。
10,000km離れたところで聴いた爆音。4月、東京に戻ると、震源まで400kmに近づいたはずの東京は、かえってしんと静まり返っていた。静けさに戸惑う一方で、計画停電で街が暗い様子はアフリカ帰りの網膜に優しかった。
紙コップの使い捨てが日常でない青空食堂では、うっかり持ち帰り用にティーを頼むとビニール袋に入れて渡された。石巻で被災した料理屋では、泥をかぶった食器を片付けていると、主人が捨てようというので洗って使いましょうとひたすら泥をはらった。すべての食器に店の名前が印字してあった。津波の後三週間ボランティアを待ちつづけていたという彼らは、その食堂を明日にでもオープンさせたいに違いないのだ。そんな日々を経験した直後、ニューヨークのレストランで、整然と食器が無限に並び、客の着席しているほぼすべてのテーブルで、食事の半分が手をつけられずに下げられるのを見ていると、どうしても食欲が失なわれた。それがあまりにナイーヴな反応だとわかっていても、自分の食欲がもとに戻ったと気づいたときには6カ月が経過していた。食糧不足を憂えてというわけではなく、ニューヨークのような近代都市が立脚している排他性を自身が異化することで自然と起こる反応ではないか。無関心という内面化した都市の魔物は、その存在に気づき目を合わせた瞬間に、見たものを石に変え機能不全にしてしまうのだ。
自分の立つ場所によって、聴こえる音は異なる。なにを騒音と感じるのかも変化し、あるいは聴こえない音の存在を知って、恐怖を感じるようになることもある。わたしたちの耳は、ときに難聴に悩まされている。
この耳をどう治していくのかがわたしの2012年の課題である。
2012年の始まりに辿り着いたこの地、モロッコでは、朝晩どこからともなく礼拝の時を知らせるアザーンが流れ、ある日はその音で目が覚める。ヨーロッパ、アフリカ、中東が混在する北アフリカの砂漠地帯で、わたしの耳は徐々に、どこまで音を拾うことができるようになり、なにを騒音ととらえるようになるのか。
いまはまだ、わたしは、ここでの音をよく聴き分けることができない。

- Guéliz, Marrakech, Morocco, Jan 2012
マラケシュに滞在して4カ月というウクライナ人アーティストの提案で、7kmの道のりをモロッコ人労働者と同じようにロバに乗って移動してみた。7km進むのに90分かかったが、わたしたちの腕が上がれば時間は30分くらいに縮まるのだろう。マラケシュの車道では、車、オートバイ、自転車、電気自転車、ロバ、馬、通行人が同時に進む。車道に七本線が引かれているわけではないので、互いの存在に慣れ、道を譲り合わなければならない。運転免許のないわたしがこの道をひとりで進むなら、アラビア語やベルベル語を聴きながらロバで行くのが一番安全で実りが多そうだ。少なくとも、もう少し耳が慣れるまでは。

- On a donkey on route de l'Ourika, Marrakech, Morocco, Jan 2012
以上、すべて筆者撮影
都市空間は、どの音を遮断し、どの音に窓を開けるように育つべきなのか。
あらゆる振動と騒音の関係について、これからの都市が誠実に回答していくために。
★1──イェフダ・アミハイ『エルサレムの詩』(村田靖子 訳、思潮社、2003)。
*
2011年に日本で関心をもったプロジェクトは多数あったが、下記のような試みは、そのなかで交わされていた対話を含め、対立する複数の視点を同時にもつことが可能かという点で、より深い考察を与えてくれた。
○「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展(21_21 DESIGN SIGHT)
○
UIA2011東京大会第24回世界建築会議 国際建築学生ワークショップ
○彫刻家エル・アナツイの世界
(国立民族学博物館/神奈川県立近代美術館/埼玉県立近代美術館ほかを巡回)
○国民投票プロジェクト(構成・演出:高山明)
○建築雑誌展 2010-2011(建築会館)
これらの企画には、入れ子状に連日シンポジウムが用意され、会期中その意味は重層的に上書きされた。結果、上に挙げた展覧会にメタボリズム展(森美術館)を加えた三つの展覧会は、それぞれ少なくとも三度以上足を運ぶことになった。