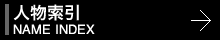ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<榑沼範久
「天災は忘れない頃にやって来る」あるいは、「災禍は忘れることができない」2011年3月11日の巨大地震の経験―自身にとっては「生態学的建築をめざして」(『思想』No. 1045「特集=建築家の思想」2011年5月)を書いている最中に生じた―、そして大きな余震と大量の放射性物質放出が止まらない今年の春の緊張状態は忘れることができない。5月6日に建築家の山本理顕さん、山本理顕設計工場の高橋玄さん、杉浦洋平さん、玉田誠さん、INAX出版の高田知永さん、TBSビジョンの磯原幸道さんと、災禍に遭った石巻や名取の瓦礫のなかを、日が落ちて暗くなるまで歩いた経験も忘れることができない。けれども、「3.11以前/以後」の歴史的切断が自分のなかに生じたとは思っていない。「9.11」も同じだが、こうした「非常事態」を「3.11」と象徴化して、「3.11以後の都市・建築」を考えることが自分にはできない。これらの「非常事態」によって歴史の切断を語ろうとする者、これらの「非常事態」によって「以後」「2.0」を語ろうとする者は、抑圧者の足場に立っていると思うからだ。歴史のエッジ、不定な現在を生きていないと思うからだ。「3.11以後の都市・建築」を善意から語るにしても、それは抑圧者という自分の足場に無自覚であるにすぎない。ヴァルター・ベンヤミン(1882-1941)の言葉が突き刺さるのは、こうしたわれわれの無自覚に対してだ。「抑圧された者たちの伝統は、われわれが生きている『非常事態』は実は通常のものだと教えてくれる。われわれはこれに対応する歴史の概念に到達しなければならない」(「歴史の概念について」『ベンヤミン・アンソロジー』山口裕之編訳、河出文庫、366頁)。ただし、自分は「抑圧された者たちの伝統」を生きているとも思っていない。むしろ、抑圧者たちの伝統のなかに生きていると思っている。「9.11」にしても、「3.11」にしても、そうとしか言いようがない。自分とは違って、「9.11」のような惨劇が「通常」の人々がいる。自分とは違って、「3.11」のような災禍が「通常」の人々や無数の存在がいる。自分など、裂け目に突き放されるだけの不能者でしかない。しかし、だからこそ、「非常事態」を通常のものとする「歴史の概念に到達しなければならない」と自分は思うのだ。地球の気層の底で唾し、不能性にはぎしりゆききしつつも、抑圧者たちの伝統から離れなければいけないと思うのだ。「全能の思考を再建しようなどとはせずに、その不能性から思考方法を生み出さなくてはならない。われわれはむしろ生を信じるために、思考と生の同一性を見いだすために、この不能性を役立てなければならない」(ジル・ドゥルーズ『シネマ2 *時間イメージ』宇野邦一ほか訳、法政大学出版局、237-238頁)。関東大震災後の銀座を歩き回る地球物理学者・寺田寅彦(1878-1935)を襲ったのも、「非常事態」を通常のものとする「歴史の概念」だったはずだ。「銀座というものの『内容』は、つまりただ商品と往来の人とだけであって、ほかには何もなかったということになる。それとも地震前の銀座が、やはり一種のバラック街に過ぎなかったということになるのかもしれない」(『柿の種』岩波文庫、74頁)。寺田寅彦の幻視するこの都市の原光景も、脳裏に焼きついて離れることがない。
-
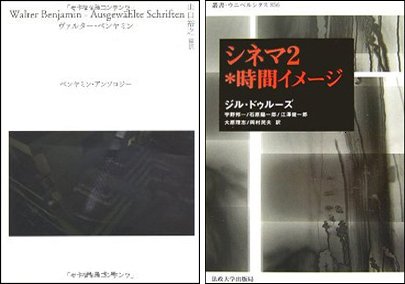
- 『ベンヤミン・アンソロジー』/ジル・ドゥルーズ『シネマ2 *時間イメージ』
寺田寅彦の書いた災害に関する随筆は再編集され、2011年の春から夏にかけて、3冊の文庫本として連続出版された。寺田寅彦『天災と国防』(講談社学術文庫)、『天災と日本人――寺田寅彦随筆選』(山折哲雄編、角川ソフィア文庫)、『地震雑感/津浪と人間――寺田寅彦随筆選集』(千葉俊ニ+細川光洋編、中公文庫)。年末には『寺田寅彦――いまを照らす科学者のことば』(池内了責任編集、河出書房新社)も現われた。寺田の言葉として流通している「天災は忘れた頃にやって来る」のコピーが表紙に躍る。随筆「天災と国防」の言葉で言えば、「畢竟(ひっきょう)そういう天災がきわめて稀にしか起こらないので、ちょうど人間が前車の顚覆(てんぷく)を忘れたころにそろそろ後車を引きだすようになるからであろう」(『天災と国防』16頁)。しかし、こうした格言に反して、自分たちにとっては幸か不幸か、おそらく未来の「天災は忘れない頃にやって来る」。あるいは、「災禍は忘れることができない」。東京帝国大学地震研究所で寺田寅彦も着手した地震研究は、現在、そう遠くはない未来に、日本列島の各所で大地震が発生する確率が高いことを予測している。たしかに寺田寅彦も強調するように、「統計的」現象が「決定的」現象と本質的に区別されるとすれば、「非常事態」の生じる「時間を『精密に』予報する事は六(むつ)かしい、いわんやその場処を予報する事は更に困難である」(「地震雑感」『天災と国防』66頁)。しかしながら、「二十世紀の現代では日本全体が一つの高等な有機体である」とすれば(「天災と国防」『天災と国防』14頁)、地域の「不都合が全国に波及」する(同、15頁)。もし、二十一世紀の現代では世界全体が「一つの高等な有機体である」とすれば、国家・地域の不都合が全世界に波及する。われわれが大きな影響を受ける天災・災禍の周期は、ますます短くならざるをえず、自分たちは「非常事態」を通常のものとして生きざるをえない。寺田の言葉を借りるなら、周期が短くなれば災害は「もう天変でも地異でもなくなるであろう」(「津浪と人間」『天災と国防』141頁)。寺田が綴る天災は、フロイト(1856-1939)の語る「死の欲動」のようなものだ。「地震や津浪は新思想の流行などには委細かまわず、頑固に、保守的に執念深くやって来るのである。紀元前二十世紀にあったことが紀元二十世紀にも全く同じように行われるのである。(...中略...)自然ほど伝統に忠実なものはないのである」(同)。そして、これは寺田の随筆に登場しない災禍だが、原子力発電所の廃炉にかかる年数は、日本列島を襲うとされる大地震の「周期」予想と大差がない。放射性廃棄物の管理に要する年月は、何十年・何百年から数万年に及ぶ。「巨大な失敗だけが、われわれを巨大さに結びつける」(レム・コールハース『S, M, L, XL』The Monacelli Press, p.502)巨大技術は、世界全体を有機化し、破局を全世界に波及させる。したがって、おそらく未来の「天災は忘れない頃にやって来る」。あるいは、「災禍は忘れることができない」。だとすれば、われわれは否応なく、「非常事態」が通常のものである歴史の概念に到達してしまうことになる。
-

- 寺田寅彦『天災と国防』/同『天災と日本人──寺田寅彦随筆選』/同『地震雑感/津浪と人間──寺田寅彦随筆選集』
寺田寅彦は『天災と国防』で文明批判を行なっているように見える。2011年、寺田の震災に関する随筆がひろく読まれたとすれば、理由はそこにあるかもしれない。「災禍を起こさせたもとの起こりは天然に反抗する人間の細工であると言っても不当ではないはずである。災害の運動エネルギーとなるべき位置エネルギーを蓄積させ、いやが上にも災害を大きくするように努力しているものはたれあろう文明人そのものなのである」(「天災と国防」『天災と国防』12-13頁)。もちろん、ここから建築・都市の課題を引き出すことはできる。しかし、ここから自分は、「自然への回帰」「自然との共生」を引き出すわけにはいかない。こうした文明批判でイメージされる「自然」は自然自体ではなく、人間が頭で描いた風景にすぎないからだ。これでは「地球物理学の問題」(「地震雑感」『天災と国防』64頁)に届かない。地球の自然自体は、「まだ形をなしていない不安定な物質や、あらゆる方向の流れに縦横に貫かれ、自由状態の強度や放浪する特異性、狂ったような移行状態の粒子がそこを飛び交っている」一つの「巨大分子」だ(ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラト─・上──資本主義と分裂症』宇野邦一ほか訳、河出文庫、93頁)。自然自体を垣間見たとき、地球物理学者の寺田寅彦は「なんだか非常に恐ろしい事実に逢着(ほうちゃく)したような気がした」と述べている(『柿の種』20頁)。あるいは、「何かしら名状し難い、恐ろしいような物すごいような心持ちに襲われた」と述べている(同、67頁)。なるほど、寺田は関東大震災や暴風被害の跡を歩きながら、「『自然淘汰』という時の試練に堪えた場所に『適者』として『生存』している」旧い建造物を称揚しているように見える(「天災と国防」『天災と国防』16-19頁)。しかし、ここから旧い建造物への回帰を引き出すのも間違っている。なぜなら、こうした建造物は無数の同じような建造物が破壊されたあとに、幸運にも「生存」しているからだ。何が「適者」なのかを事前に設計・計画することは、おそらくできない(建造物の「生存」の原因を探ることは興味深いが、その原因は寺田が探る「地震の源因」と同じく特定はできず、重層的なものになって後退を始める[「地震雑感」『天災と国防』63頁])。ダーウィン(1809-1882)が論じたように、「自然淘汰」において「適者」の「生存」はおそらく事後的に決まる(『種の起源・上』渡辺政隆訳、光文社古典新訳文庫、222-223頁)。われわれは「生存」を事前に設計・計画することは叶わず、生きようと変異の跳躍を反復するのみだ。歴史のエッジ、不定な現在に迷いこみ、そして生きるのみだ。こうした自然自体は、われわれが生きている「非常事態」は実は通常のものだと教えてくれる。われわれはこれに対応する自然史の概念に到達しなければならない。こうした自然自体は、坂口安吾(1906-55)の「文学のふるさと」のように、「モラルを超えたもの」であり、自分たちを「突き放す」(「文学のふるさと」『堕落論・日本文化私観 他二十二篇』岩波文庫、91-100頁)。しかし、これが《建築のふるさと》なのだと思う。坂口安吾を変奏して書くなら、「このふるさとの意識・自覚のないところに建築があろうとは思われない。建築のモラルも、その社会性も、このふるさとのうえに生育したものでなければ、私は決して信用しない。そして、建築の批評も。私はそのように信じています」。2012年1月21日には、建築家の平田晃久さんと藤本壮介さんを横浜・馬車道に招き、Y-GSCスタジオ誕生記念シンポジウム「地球と建築──来るべきアースワークスのすがた、ワンダフルライフのための闘い」を開催する。2012年は、編集協力中の雑誌『SITE ZERO/ ZERO SITE』No.4「特集=地球と建築──来るべきアースワークスのすがた、ワンダフルライフのための闘い(仮)」刊行に向けても進まなければならない。宮澤賢治(1896-1933)の言葉は導き手のひとつだ。「諸君はこの時代に強(し)ひられ率(ひき)ゐられて 奴隷(どれい)のように忍従(にんじゅう)することを欲するか むしろ諸君よ 更(さら)にあらたな正しい時代をつくれ 宙宇は絶えずわれらに依(よ)って変化する 潮汐や風、あらゆる自然の力を尽(つく)すことから一足進んで 諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ」(「詩 ノート」『新編 宮澤賢治詩集』天沢退二郎編、新潮文庫、284-285頁)。
-

- 坂口安吾『堕落論・日本文化私観 他二十二篇』/『新編 宮澤賢治詩集』