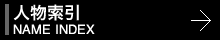ENQUETE
特集:200912 ゼロ年代の都市・建築・言葉 アンケート<濱野智史
建築家・藤村龍至の登場(「批判的工学主義」と「超線形設計プロセス」の提唱)
筆者にとって藤村の出現は事件だった。実に恥ずかしい限りだが、拙著に『アーキテクチャの生態系』という題を付けておきながら、それまで筆者はまともに「建築」に関する書籍を読んだことがなかった。それまで筆者が意識していたのは、主にレッシグ(法学)やクラーク/ボールドウィン(経営学)の文脈であり、いわゆる「建築」とは一切関係がなかった。ゼロ年代の10年間、筆者にとって建築は知的関心の外側にあったのである(いまではそのことを後悔している)。
もちろん、これは単に筆者の知的怠慢でしかない。だが然るべき事情もそこにはあった。ゼロ年代以前、「建築」と「思想」は(磯崎新と浅田彰のタッグに象徴されるように)密接な関係にあったが、ゼロ年代以降は『Any』シリーズも『批評空間』も終刊し、筆者のような門外漢にとって「建築」はアクセスしがたい領域となった。そんな筆者にとって、藤村の存在は強力な「建築へのインターフェイス」であった。
それは一言でいえば、藤村の問題意識の現代的普遍性によるところが大きい。というのも、藤村らの提唱する「批判的工学主義」とは、社会学者のA・ギデンズがかつて提唱した「第三の道」の建築ヴァージョンとみなすことができる。冷戦構造というイデオロギー対立が崩壊し、グローバリゼーションが不可避に進む現代社会においては、単なる市場至上主義路線(ネオリベラル)も福祉国家路線(リベラル)も残されてはおらず、旧来の二項対立を超えた「第三の道」へと、政治も経済も思想も向かわざるをえない。
これに対して「批判的工学主義」とは、アトリエ派と組織派、表層と深層、芸術と工学という《市場的なものと反-市場的なもの》の二項対立を乗り越えようとする、まさに「第三の道」の実践プログラムとして注目に値する。それは(藤村の編纂した書名を借りれば)「1995年以後」の日本の建築界だけに限らない、広く深い射程を持っているのである。
さて、そのうえでさらに「アーキテクチャ論」の観点から注目すべきなのは、藤村の「超線形設計プロセス」という方法論なのだが、これに対する筆者の考えについては『Final Critical Ride』(東浩紀+宇野常寛編、2008)に所収の藤村との対談をあたってほしい★1。
ただ一言付け加えておくならば、筆者が見るに藤村にとっての《建築》とは、(ルーマン風にいえば)ある種の《政治》的な「コミュニケーション・システム」とみなすことができる。建築という巨大な人工物を設計する過程において、そこに関わる主体や変数は多種多様であり、時に相互に背反するような関数的関係を結び合う。建築家はそれらをまとめあげ、いうなれば(アルチュセールの有名な言葉をもじれば)「集合知的決定」として建築という人工物を出力/切断する。藤村の方法論的関心は、この「コミュニケーション・システム」をいかに設計するかに向かっている。
もちろん、こうした建築/建築家像は、建築界の内部から見ればあまりにも当たり前で、日々実践されていることに過ぎないのだろう。しかし、筆者がいま藤村の「コミュニケーション・システム設計論」に大いなる着目を払っているのはなぜかといえば、次のような背景があるからだ。
かつて現代思想は、「内部と外部」(社会システム理論的にいえば「システムと環境」)をめぐって、クリティカルな「脱構築」を繰り広げてきた。しかし筆者の考えでは、情報化によってコミュニケーションの唯物論的基盤(アーキテクチャ)が設計可能となった現在、システムの「内部と外部」の境界線(インターフェイス)は、プラグマティカルな「構築(設計)」の対象となった(その詳細を知りたい読者は、ぜひ「モジュール化」や「エコシステム」をめぐるこの10年あまりの経済学/経営学の議論を追ってほしい)。おそらくいま私達が注目すべきなのは、いうなれば「隠喩としての建築」(柄谷行人)ではなく、「実践としてのアーキテクチャ」であり、それゆえにこそ藤村の活動から目を離すことはできないのである。
★1──2009年6月28日にABC青山本店で行なわれたトークイヴェント「設計/デザインを考える」を収録したもの。
-


- 『1995年以後』/『思想地図』vol.3