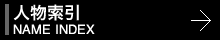ENQUETE
特集:200912 ゼロ年代の都市・建築・言葉 アンケート<池田剛介
無線LANが飛ぶカフェスペースのある店内で、最新の雑誌や書籍を選び、コーヒーを飲みつつブログを更新し雑誌のページをめくる。ゼロ年代中頃、留学先のボストンにてバーンズ&ノーブルやボーダーズといった大型書店でのこうした行為が新鮮だったことを覚えている。同様の光景は、日本でもTSUTAYAとスターバックスの併設店が増えるにつれ、徐々に浸透してきた。くつろいだ店内で、買わずにひたすら読みあさる。当初、これは消費者による資本へのささやかな抵抗ではないかと、冗談っぽくではあれ思えたものだ。むろん、このような環境は今度、多くの監視カメラやRFIDタグといったテクノロジーのさらなる普及とともに進展していくであろうことは想像に難くない。都市空間の自由は、環境管理との共犯関係を結ぶだろう──。酒井隆史『自由論──現在性の系譜学』(青土社、2001)
2001年の7月、つまり9/11のおよそ2カ月前に上梓された酒井隆史による『自由論』は、排除型社会やセキュリティ意識といった、9/11以降いっそう高まってゆくことになる問題群を、理論的なレヴェルで精緻に捉えていた。広く共有されることとなった「規律訓練からコントロール社会へ」というパラダイムの下地にはフーコー『監獄の誕生』での議論がある。古典主義的な法の応報原理──目には目を──から近代型のノルム──精神医学や統計学をつうじて導き出された「標準」としての人間像──へと移行する、刑罰の基準のシフトを丹念に洗い出す。こうした作業を通じて、かつての法原理とも、標準化を目指す規律訓練とも異なる、都市空間におけるコントロール社会のありようが描き出されている。東浩紀+大澤真幸『自由を考える──9・11以降の現代思想』(NHK出版、2003)
東浩紀+北田暁大『東京から考える──格差・郊外・ナショナリズム』(NHK出版、2007)
こうした問題を、より身近なものとして私の意識に立ち上げるきっかけとなるのが東浩紀+大澤真幸『自由を考える』、東浩紀+北田暁大『東京から考える』の2冊だった。前者では、マクドナルドの椅子やAmazon.comでのネット通販といった身近な話題に潜む問題が思想的枠組みと共に示され、後者では人間工学に基づき設計される大規模なショッピングモールやフランチャイズによって郊外が均質化してゆく現状をふまえ、公共性やナショナリズムの問題を考察する。両著ともに、私たちの生に密接した近年の状況の変化に寄り添いながら、そこに潜在する抽象的な次元の問題が鮮やかな手つきで引き出されてゆく。この2冊を通じて都市の情報化と郊外の均質化とがそれぞれに広がりながら相互に織り合わされてゆくゼロ年代の光景を俯瞰できるだろう。-



- 『自由論』/『自由を考える』/『東京から考える』
越後妻有アートトリエンナーレ
取手アートプロジェクト
こうしたゼロ年代特有の都市や郊外の問題を美術の側へと引きつけてみれば、この10年のうちにいつの間にか日本各地で行なわれるようになっていたプロジェクト型アートの存在に目を向けることができる。とりわけ2000年から3年おきに開催されてきた「越後妻有アートトリエンナーレ」や1999年から茨城県取手市にて毎年行なわれている「取手アートプロジェクト」などがその先駆であり、どちらもこの10年を通じて街ぐるみで運営を続け、生き残ってきたことはゼロ年代日本のアートにおけるひとつの達成だといえるはずだ。当初、こうしたプロジェクト型アートのコアには、既存のアートの枠組みを解体し、地域的に、あるいは人々とのコミュニケーションのなかに開いてゆく、といった批評性が宿っていた。しかし、幸か不幸かそうした試み自体が広く認知されてゆくなかで、プロジェクトというかたちそのものが、もはや既成の枠組みとなってしまったように思われる。地方の活性化といった、別の意味でクリティカルな要請もあいまって、各地で行なわれるプロジェクト型アートのパターン化が起こってしまった感は否めない。そもそもweb上でこれだけコミュニケーションが溢れかえっている現在、人は美術に同様の役割を求めるだろうか。いずれにせよ、それ自体としては新鮮みを失いつつあるからこそ、今後こういった試みがサヴァイヴしてゆくためには、何らかの形で問題設定を更新する必要があるだろう。これからさらに進行するであろう郊外化や、テクノロジーの発展によって変化するコミュニケーションのありようなどを通じて、その意義を新たに再考するためのよいチャンスではないだろうか。
ARCHITECT JAPAN 2009──ARCHITECT2.0 WEB世代の建築進化論
ゼロ年代初頭、こうしたプロジェクト型アートとも近い感性を持っているように思われるアトリエ・ワンやみかんぐみなど、ユニット派によるスーパーフラット・バラック建築とでも呼べそうな活動が注目を集めていた。近年ではこうした、グローバル化してゆく都市のなかでニッチ的な抵抗を試みる、といったような議論はやや後退し、むしろ設計の情報化や効率化といった条件を受け入れながら、いかにより良いデザインが可能かを模索する議論が現われ始めている。建築に関して門外漢の私にこういった方向性を印象づけたのは、企画監修を飯田高誉が、キュレーションを藤村龍至/TEAM ROUNDABOUTが担当し、表参道のEYE OF GYREにて開催された展覧会「ARCHITECT JAPAN 2009──ARCHITECT2.0 WEB世代の建築進化論」だった。1945年、1970年、1995年を戦後の切断点ととらえる日本の批評界の議論を受け、戦後建築の展開をこの3つのフェイズに分けて捉える視点を提示。そのうえで、1995年以降、現代の建築における大型化、郊外化、情報環境といった問題を踏まえた視点から、古谷誠章「せんだいメディアテーク案」などに、新たな角度からの光を当てる。展示の締めくくりには、若手エンジニア徳山知永によるCADの図面がさりげなく配されることで、石上純也のような建築家による「アーティスティック」な表現を技術的に支える、もうひとりのアーキテクトの姿が浮かび上がる。このあたりに鋭く批評的な賭けが託されていて、展覧会という形式の可能性を改めて考える点でも、意義深いものとなっていた。
以上、思想、美術、建築といった異なる分野から、都市の情報化や郊外の均質化といった諸問題に触れてきた。今後、こうしてジャンルを超えて重なり合うさまざまな問題を改めて検証してゆく必要があるだろう。ゼロ年代を通じて閉域化を極めた島宇宙内の議論がダイナミックに混じりあい、領域同士の垣根を錯乱させながら、より豊かな創造活動のフィールドが形成されてゆくことを期待せずにはいられない。そういった場所でこそ、ようやく21世紀の新たな創造のパラダイムが開かれるのではないだろうか。